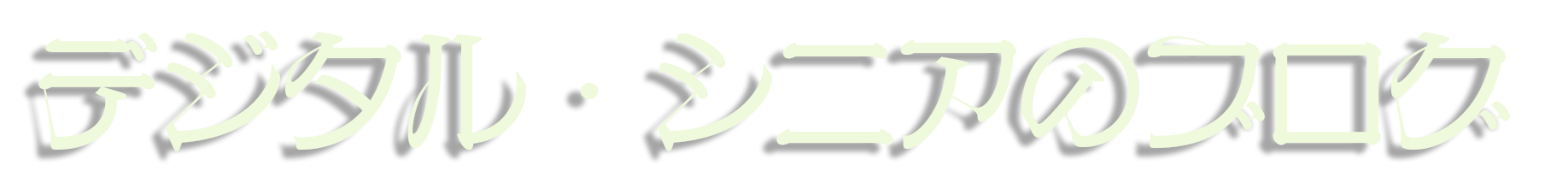![]()
気鋭のマクルーハン研究者である、ポール・レヴィンソンが1999年に出版した、『デジタル・マクルーハン』(NTT出版, 2000)。若干の私見と最新動向を交えながら、そのエッセンスを紹介しておきたい。現代のメディア論を理解する上で、いまでも基本的な文献だと思われる。
レヴィンソン氏は、ニューヨーク大学で「メディア・エコロジー」を学び、博士号を取得している。したがって、メディア・エコロジーの視点から、マクルーハンを解説し、それをデジタル・メディアに応用したのが本書だといってもいいだろう。
本書は15章から構成されているが、各章は、マクルーハンの唱えた有名なキャッチフレーズや法則について、わかりやすく解説するとともに、それをデジタル時代に読み替えたものとなっている。では、第3章以下、章ごとに内容を紹介していきたいと思う。
メディアはメッセージである
いうまでもなく、これはマクルーハンの理論でもっとも有名なキャッチフレーズだ。レヴィンソンによれば、
その基本的な意味は、どのようなコミュニケーション・メディアであれ、そのメディアによって伝達されるコンテンツよりそれを利用する行為自体のほうがはるかに大きな影響力を持ち、例えばテレビを見るという行為はテレビ番組やその内容より重大な影響を私たちの生活に与え、電話で話すという行為はその会話の内容よりも人の暮らしに革命的な変化をもたらすということだ。
これが一部の人々に「コンテンツ」を否定するものと受け取られてしまった。マクルーハンの意図は、われわれの意識をコンテンツからメディア自体に移そうとした点にあった。それは、「コンテンツにばかり気を取られていると、メディアとその周辺すべてのものに対する理解や認識が阻害されてしまうと考えていたからだ」。どのようなメディアも、そのコンテンツは、実は旧来のメディアなのだ、ともマクルーハンは言っている。
いずれのメディアも他ならぬそれ以前に台頭していたメディアをコンテンツとし、その結果古くなったメディアは以前の粗野で目に見えない状態から飼い慣らされ、ようやく全体像を私たちの前に現わすようになる、ということなのだ。
映画のコンテンツは小説であり、テレビのコンテンツは映画やラジオの連続ドラマやクイズなどである。それでは、ウェブのコンテンツとなるメディアは何なのだろうか?それは、「ひとつにとどまらず複数のメディアだ」というのが回答である。なぜなら、「ウェブはそのコンテンツとして、ラブレターから新聞までの書き言葉に加え、電話、ラジオ、テレビの一種とでも言うべき音声つきの動画まで取り入れているからだ」(p。76)。ひとことでいえば、ウェブは「マルチメディア」なのである。なかでも、「書き言葉」という共通要素があることを筆者は強調している。さらに、「ユーザーはインターネットのコンテンツだ」とも主張している。なぜなら、「インターネットのコンテンツとなるのは旧いメディアばかりではなく、利用するごとにオンライン上でコンテンツを創り出す人間のユーザーもそうなのであり、そこが他のマスメディアと違う点とも言えるだろう」(p。77)。実際、マクルーハン自身、テレビについて、「ユーザーはコンテンツである」と語っていたそうである。
これだけでは、「ユーザーがコンテンツ」ということばの意味はわからない。レヴィンソンによれば、ユーザーをコンテンツとするマクルーハンの考え方から、少なくとも三段階の階層構造が浮かび上がってくるという。
(a)人間が眼前に現われるものすべてに対し、込み入った解釈をすることで、すべてのメディアのコンテンツとなる段階、
(b)知覚した人間が、ラジオやテレビなどの一方通行の電子メディアを「通じて」移動し、そこでそのメディアのコンテンツとなる段階、
(c)話し手である人間が電話などの旧いインタラクティブなメディアのすべてのコンテンツを、またインターネットの場合はほとんどのコンテンツを文字通り創造する段階(p。79-80)
さらに、インターネットは、「人間の会話が介在していない時は、テレビの流儀に従って映像を、また印刷の流儀に従って映像を、また印刷の流儀に従って書き言葉を表現するものなので、前記の階層構造の全段階を包括し、人間がコンテンツを決定する過程において、それまでのすべてのコンテンツを完成させたものである」という。
実際、最近のインターネットTVや、ネット上の電子書籍、電子新聞などは、まさに、旧来メディアをすべて包括した完成形という印象を受ける。
それでは、インターネットで電子新聞を読む場合、コンテンツはその新聞なのか、ニュースの言葉なのか、その言葉で表現されたアイディアなのか、、、それともすべてがコンテンツなのだろうか?そのおおもとをたどると、最古のメディアである、「話し言葉」に行き着くだろう。いいかえると、「個々の新しいメディアは旧いメディアをコンテンツとして取り入れていて、そのために最古のメディアである話し言葉は、それ以降に誕生したほとんどすべてのメディアの中に存続しているということが分かってくる」。
例えば、
・表音文字は話し言葉の音を視覚的に表記したものだ、
・印刷機は本や新聞、雑誌などにアルファベットを大量生産したものだ、
・電話、レコード、ラジオはいうまでもなく話し言葉を伝達する、
・サイレント映画は言葉を視覚的におおげさに表現したが、トーキーになって、文字通り話し始めた、
・その映画はテレビのコンテンツになった、
・そして、前記のすべては急速にメディアの中のメディアであるインターネットのコンテンツになりつつある。
最近普及し始めた、「電子新聞」や「電子書籍」は、「メディアはメッセージである」ということばでどう捉えるべきだろうか?朝日新聞や日経新聞は、電子版で「紙面イメージ」を採用し始めたが、これは、インターネットの中に紙の新聞イメージを取り込んだものである。それは、ニュースサイトで読む新聞とは似て非なる体験をユーザーに呼び起こす。つまり、デジタル形式で、紙の新聞を読んでいるような、ある種のノスタルジー的な快感と効用を与えてくれるのだ。つまりは、旧いメディアのフォーマットがインターネットのデジタル情報空間上で再現し、再生したといってもよい。キンドルなどのeインクを使った電子書籍についても、同じような「既視感」を味わうことができる。紙のような肌触り、ページをめくっているような感覚でデジタル書籍を閲覧することができるからだ。これは、「新しい革袋に旧い酒を入れる」ような感覚である。旧いメディアが、デジタル技術によって、新しい棲み場所を得たような気がするのだ。これもまた、「メディアはメッセージだ」という言葉にぴったりと当てはまる現象とはいえないだろうか?
聴覚的空間
マクルーハンは、「聴覚的空間」を強調した。なぜなら、歴史的にみれば、聴覚こそは、視覚に先立って誕生した<始原のメディアだからである。
マクルーハンの「聴覚的空間」という概念は、視覚的空間とアルファベットとの関係に関する彼の立場を非常に明快にする。つまり、聴覚的空間はアルファベト以前に出現したものだということだ。それは文字の出現以前の視点で見た世界であり、境界がなく、情報が固定された場所からではなく、あらゆる場所から生み出される世界だ。それは音楽や神話、全身が包み込まれる世界であり、したがってマクルーハンの考えによると、主にテレビというものはやはり音楽的かつ神話的で、包み込む形態でアルファベットより後に私たちの前に現われ、本や新聞とは異なり、視点や対象物との距離感を持たない世界だ。(p.90)
それでは、インターネットのサイバースペースは、どのような世界なのだろうか?この点について、著者は、サイバースペースはまさしく聴覚的空間だという。アルファベット以前の世界において、「私たちは世界を探索するとき、視覚と聴覚を用い、関わりを持つ時は触覚と味覚を用いる。視覚は私たちが目を向けているものの詳細を正確かつ詳細に伝えてくれるが、聴覚は私たちが世界に耳を傾けようとするかしないかに拘わらず、一日24時間、絶えず私たちと世界の接点を用意している」。深い眠りから目をさまさせてくれるのも、聴覚のおかげである。アルファベットが進化したのも、聴覚のおかげである。印刷の発明後も、出版といえども、声が多くの人の耳に届くことはできなかった。その点では、テレビのもつ聴覚的性質は、「一国のいずれの場所においても、またCNNなどが出現して以来、世界のいずれの場所でも、同じ映像がテレビ画面上で見られるという点にある」。ラジオも同じだ。そして、「アルファベットはインターネットの画面に表示されることで、同じ言葉を、世界的なケーブルテレビの画面よりはるかに容易かつ効率的に世界中に送ることができ、印刷よりはるかに身近で直接的に遠方まで広がりを持つ聴覚的空間のコンテンツになると同時にその媒介にもなったのだ」(p.94)。インターネット上の聴覚的空間は、テレビやラジオよりも拡大したものとなっている。すなわち、その非同期性、非場所性などをもっているからである。また、インタラクティブ性など。「オンラインのアルファベットのコミュニケーションの容易でインタラクティブな性質は、直接に音を聴くことが始まって以来、電話以外ではどのメディアにも欠けていた聴覚的性質の根本的な原動力を回復し増強する」。
ここで、著者は、やや唐突ともいえるが、独自の「メディア進化論」を提示している。
私は「人間の再生-メディア進化論」を皮切りに過去20年間にわたって、コミュニケーションの未来を予言するという困難な仕事のためにメディアの一般n理論を構築してきた。その理論の核心は、メディアはダーウィンの説のように進化し、そこで人間はメディアの発明者であると同時に選択者でもあるということだ。そしてその選択の基準は、(a)私たちは、単なる生物学的な視覚や聴覚の境界を越えてコミュニケーションを拡張するようなメディアを求める、(b)初期の人工的な拡張の過程で失ったかもしれない、生物学的なコミュニケーションの要素を再び取り戻すようなメディアを求めるというものだ。つまり、私たちは自然のコミュニケーションという炉床を求めつつも、私たちを拡張することでそれを凌駕するメディアを求めていく、という二つの点だ。
例えば、電話は、私たちの進化の過程で、一旦は失われた音声という要素を回復する双方向のコつりょミュニケーション・システムの強い進化的な圧力によって、電報に取って代わった。白黒映画からカラー映画での進化、白黒テレビからカラーテレビへの進化も同じ。また、最近のハイビジョン・テレビも、よりリアリティの高い映像や音声への進化を示している。
グローバル・ヴィレッジ
このキャッチフレーズは、「メディアはメッセージである」と同じくらい人口に膾炙されたことばだが、こちらは誤解されることもなく、広く受け入れられた。電子メディアの登場によって、世界は小さな村のようになったということだ。
かつて、小さな村の住人は触れ役の声が全員に行き届くことで、公的な情報にほぼ同じ程度に接触していた。その情報の届く範囲を拡大したのは印刷だった。それは最初の大量の読者、つまり目と耳の届く範囲を超えた反応の速い大衆を初めて創出したが、その結果として本来の聴覚的な村人の同時性が失われてしまった。誰もが同じ朝刊、同じ夕刊を購読しているわけではなく、また同じ新聞を購読しているにしても、同じ瞬間に同じ記事を読んでいることなど考えられないからだ。それからラジオが、そしてテレビが出現し、国中の誰もが居間に腰を下ろして、同時にニュースを読むアナウンサーの声を聴き、同じ顔を見ることが可能になった。80年代にCNをはじめとするグローバルなケーブルテレビの出現によって、村はグローバルとまでは言わないまでも、全国的に再構成され、放送メディアがグローバル・ヴィレッジを実感させるものになっていった。(p.121)
しかし、テレビによって実現したグローバル・ヴィレッジは不完全なメタファーだった。というのは、人々はテレビを通じて双方向のコミュニケーションをすることができなかったからだ。その意味では、インターネットこそが、グローバル・ヴィレッジの正しいメタファーとなりつつあるといえよう。
ラジオからテレビへの変化は、「地球村」の性格を大きく変化させた。著者によると、それは「子供の村」から「のぞき見趣味の村」への変化である。家族内で、子供は重要な問題には両親の意見に逆らうような意見を口にすることは一切許されない。同じように、ラジオという一方通行の音声メディアでは、聴取者はラジオから流れる時の支配者のことばに反論を言うことを許されていなかった。それゆえに、「ラジオ時代は20世紀でもっとも影響力の強い、スターリン、ヒットラー、チャーチル、フランクリン・ルーズヴェルトという4人の政治家を生み出した」(p。123)。日本でいえば、戦時中の政治家や軍部をあげることができるだろう。「聴取者は年齢に関係なく、ラジオという父親の子供になった」のである。ちなみに、マクルーハンは、「テレビがラジオよりも先に登場していたら、そもそもヒットラーなぞは存在しなかったろう」と述べている。
著者によれば、「グローバル・ヴィレッジは、テレビを介することにより聴取者の村から視聴者の村へ、つまり子供からのぞき見趣味の大人へと成長した」という。例えば、1960年当時、ジョン・F・ケネディはその発言よりも、ハンサムなルックスで賞賛を集めていた。それは映画スターとファンのような関係である。また、ケネディの悲劇的な死も、「父親を亡くした子供の心境というより、ティーン・エージャーの子供の自動車事故死による衝撃に近いものだった」という。のぞき見趣味の人たちは、その対象を愛しも恨みもする。その結果、テレビ時代の政治家達は愛憎両方の対象になった。歴代の大統領や日本の最近の首相が頻繁に交代するのも、テレビを通じて視聴者による愛憎の対象とされるからなのかもしれない。
それでは、オンライン時代のグローバル・ヴィレッジはどのようなものになるのだろうか?
実際のところ、政治の世界において、「オンラインのコミュニケーションは、アテネの地方民主政治、もしくは少なくとも国の立場から言えば、直接民主政治を行なう年を地球規模で実現するための道を開き始めている。インターネットは既に、数多くの議論の場と機会を提供している。また、意思統一の実現や評価のためのソフトエアも、投票をし集計するためのソフトウェアも、容易に入手できるようになった」。問題は、私たちがそれを使用したいと思うか、ということだ。
かつて、ウォルター・リップマンは、「国や社会の出来事はあまりにも大きく複雑で、その影響がわかりにくく、個々の市民の理解の範囲を超えているので、間接的な代議制政府が必要だ、と述べ、直接民主主義を全面的に否定した。しかし、インターネットによって、状況は大きく変化した。
今やインターネットでは何百万人もの人々が積極的に話し合い、個々の市民はリップマンの言う「後ろの座席にいる耳の聞こえない観客」ではなく、1927年当時の議員よりずっと簡単にほとんどの事柄に関する情報にアクセスできるようになった。(中略)リップマンは現代でも、オンラインのグローバル・ヴィレッジは原則的に情報の配布をするだけで、誰もが立法府の議員になれるわけではない、と言うかもしれない。しかしグローバル・ヴィレッジはそれにとどまらず、議論、ディベート、世論の確立、投票の手段でもあり、本来統治の手段なのだ」(p.130)
今日のデジタル世界は膨大な情報で溢れかえっている。その中から、どうやって適切な情報、データを引き出せるのか?この点については、検索エンジンが大きな威力を発揮してくれるだろう。そのことは、「確かに、オンライン上での情報入手、論議、投票が可能になった直接民主制の政府がきちんと機能する、あるいは現行の代議制より優れた機能を発揮することを何一つとして保障するものではない。」現代社会は、古代アテネよりはるかに複雑で多くの問題に対処しなければならず、それを統治するには、それなりの能力が必要とされることもたしかだ。したがって、「直接民主制はおそらく、政府の一部の側面でのみその機能を十分に発揮できるのだろう」と著者は述べている。
しかし、現実には2008年のアメリカ大統領選挙では、オバマ候補がインターネットを駆使して、大統領選を勝ち抜くなど、インターネットあるいはソーシャルメディアが草の根の有権者パワーを動員して、政治を大きく変えるなど、ある種の直接民主制が実現しつつある。日本でも、今年の参議院選挙までに、公職選挙法が改正され、インターネットを通じて、国民の意思がより直接的に国政選挙に生かされる道が見えてきたのは、周知の通りである。著者は、「現在の代表民主制の実績とそれに対する人々の満足度が、過去数百年の何らかの目安となるのであれば、インタラクティブなオンライン・グローバル・ヴィレッジで直接民主制が成功する見込みを少し試してみるのもいいかもしれない」と控えめに提案しているが、2010年代の政治は、少なくともアメリカでは、それを着実に実現しているように思われるが、どうだろうか?
オンライン・グローバル・ヴィレッジの進展は、政治だけではなく、ビジネスの世界で、それ以上に進展していることは、周知のとおりである。これについての紹介は、割愛させていただく。
ホットとクール
レヴィンソンによれば、マクルーハンのホットとクールの区別は、新たなメディアの影響を理解するために彼が使った道具の中で、もっとも有名で誤解を受けながらも有益なものだった、という。マクルーハンのホットとクールは、もともと、ジャズの世界のスラングを引用したもので、大音響のビッグバンドの魂を揺り動かし酔わせる「ホット」な音楽と、もっと小さなバンドの心を惑わせ誘い込む「クール」な演奏を比較する言葉だったという(p.183)。マクルーハンの考えによると、「ホットメディアは、飽和しやすい私たちの感覚に近づいて襲いかかる、声高で明るく目立つ情報の発信方法であり、逆にkウール・メディアは、曖昧でソフトで目立たない、静かな夕べにぴったりの、私たちの関与を誘うメディア」である。例えば、「大スクリーンで色鮮やかなホットな映画と小さな画面で見るクールな白黒テレビ、小説や新聞に印刷されたホットな散文とクールな詩や落書き、など。
ただし、小さなブラウン管をもつ白黒テレビが「クール」というのは分かるが、現代のように、40インチ以上の高精細度ハイビジョンの時代に、テレビが依然として「クール」だというのは、やや感覚的にずれているように思われる。もっとも、「クール」と「ホット」は、二分法的に捉えるべきではなく、「温度」と同じように、程度の差をもった、連続的な尺度と考えたほうがよさそうである。現代のテレビは、かつてのちっぽけなアナログ白黒テレビに比べると、はるかにホットなメディアになっているのではないだろうか?
問題は、インターネット時代の「電子化されたテクスト」の性格である。レヴィンソンによれば「電子化されたテクストは必然的にテレビを遙かにしのぐほどクールになり、またその出現は最近のラップ・ミュージックやクエンティン・タランティーノの映画のような、クールなものの成功と時を同じくしている」という。
レヴィンソンによれば、ホットとクールは、文化全般に影響を及ぼし、その文化が今度は適当な温度のメディアを選択することになるという。実際、テレビが登場して以降、文化もまたクールなものになり、その中で、コンピュータやインターネットのような「クール」なメディアが出現したのである。
電話は、音質が比較的悪いため、人間の声のほんのうわべだけしか伝達できず、最初から本質的にクールなメディアだった。また、本質的にインタラクティブな性格をもっており、ベルが鳴るとそれを無視することが非常に難しい。「そうしたインタラクティブな牽引力、つまり電線の向こうにいる生きた人間の引力がとても強いために、電話は音声の強さや明瞭さとは関係なくクールなメディアだった」という。
インターネットは、まさしくテレビ以上にクールなメディアだ。「パソコンは全世界に広がる電話システムに接続すると同時に、テレビと本に変身する。そして特殊な電話となり、強力でクールなインタラクティブな性質を持ち続けるばかりかそれは強まる。それを生み出したのは実際には、電話、テレビだけではなく、本を加えた三つのメディアだ。そして最初の二つがクール・メディアなのだから、オンライン・テキストがクールになるのは至極当然のことなのだ」(p.196)。
最近の例でいえば、電子メールやチャット、ソーシャルメディアなどは、ユーザーの関与度が高く、いかにもクールなメディアと呼ぶのにふさわしいように思われる。また、レヴィンソンによれば、彼自身が実践しているオンライン教育も、きわめてクールなメディアであり、学生の参加度を高めるという意味で、すぐれた教育システムだと考えているようだ。
バックミラー
マクルーハンは、「われわれはまったく新しい状況に直面すると、つねに、もっとも近い過去の事物とか特色に執着しがちである。われわれはバックミラーを通して現代を見ている。われわれは未来に向かって、後ろ向きに進んでゆく」と述べている。これは、メディアの進化に関してどのような意味をもっているのだろうか?メディアの歴史をたどってみれば、その例はいくつでも見つけることができる。例えば、
電話は最初「話す電報」と呼ばれていた。自動車は「馬無し馬車」、ラジオは「無線機」という具合だ。どの場合においても、バックミラーの直接的な影響は、新たなメディアの最も重要かつ革命的な機能を部分的に不鮮明にするものだった。・・・マクルーハンは、旧いメディアは新しいメディアのコンテンツになり、そこで新しいメディアと誤解されるほど顕著にその姿を現わすことになることを指摘した。これはバックミラーの解釈の一つで、私たちの注目を前方から来て目の前を通しすぎたばかりのものへと向け直すものだ。・・・例えば、彼のグローバル・ヴィレッジという概念もまた、もちろんそれ自体がバックミラーだ。つまり、新しい電子メディアの世界を古い村の世界を参考にすることによって理解しようという試みだった。
「ウェブは、新旧のいろいろなことを新しい方法で実証できる場であり、バックミラーの紛れもない宝庫だ」と著者はいう。例えば、インターネットでリアルオーディオを聴くとき、それをラジオと考えることもできる。インターネットで調査するとき、それは図書館を利用しているかのようだ。オンラインのチャットルームは、カフェと同じようなものだと感じる。
しかし、バックミラーというメタファーは、しばしば新しいメディアと過去のメディアの相違点を目隠ししてしまう場合がある。例えば、キンドルのリーダーで本を読んでいるとき、それを落としてしまって、壊してしまったとすると、もはやそれは書籍ではなく、ただのジャンクと化してしまう。紙の本なら、ほんの少し汚れるだけで済むだろう。朝日新聞デジタルをiPadで読んでいるとき、それは紙の新聞のイメージとほとんど変わらないが、やはりメディアとしては別ものである。「紙面ビュー」という発想自体が、「バックミラー」の実現という意味を含んでいる。それは、電子化された「紙面」なのだ。だからといって、それを否定するわけではない。読み慣れた紙面をパソコンの画面やiPadで再現するというのは、旧メディアに慣れ親しんだユーザにとってはありがたいサービスだ。大切なことは、同じ「紙面」といっても、その機能、性質は新旧メディアの間で異なることを認識することだろう。そのメリットとデメリットをしっかりと把握しつつ、新旧メディアを適切に使い分けることが大事なのだ。
どのようなメディアにも欠陥があり、その欠陥を補うように、あるいは克服するようにして、新しいメディアが発明され、普及してきた。これを著者は「治療メディア」の進化と呼んでいる。
メディアの相対的な進化は、まず最初に視聴覚という生物学的な境界線を越えてコミュニケーションを拡張するメディアを発明することで想像力の切なる願いを満たし、次に、最初の拡張で失われた自然の世界の要素を再び取り戻すための試みであると考えることができる。こうした視点からみると、メディアの進化全体が治療だろ考えられる。そしてインターネットは、新聞、本、ラジオ、テレビなどを進化させたものなので、治療メディアの中の治療メディアだといえよう」(p.295)
インターネットそれ自体、現在では、数多くのメディアの複合体となっており、その内部で「治療的」な進化を続けているといえるだろう。マクルーハンのことばでいえば、「内爆発」を起こしているのだ。その内部的な進化の過程は、他の旧メディアを巻き込みながら、次第に大きな「銀河系」を形成しつつあるといえるだろう。そのプロセスは、本書の最後で取り上げられている、「メディアの法則」によってある程度解明できるかもしれない。
メディアの法則
マクルーハンが遺した最後のアイデアは、4つのメディアの法則(あるいは影響)だった。つまり、「拡充」(amplification)、「衰退」(obsolescence)、「回復」(retrieval)、「逆転」(reversal)という「テトラッド」である。
マクルーハンのテトラッドは、いずれのメディアに関しても、次の4つの質問をする。
(1)そのメディアは、社会や人間の生活のどの側面を促進したり拡充するのか。
(2)そのメディアの出現前に支持されていた(あるいは傑出していた)どの側面をかげらしたり衰退させたりするのか。
(3)そのメディアは何を衰退の影から回復させたり再び脚光を当てたりするのか。
(4)そのメディアは自然に消えたり可能性の限界まで開発されたりするときに、何に逆転したりひっくり返ったりするのか。
具体的な例として、著者は、ラジオとテレビをあげて、こう説明している。
ラジオは人間の声を瞬時に拡充して遠距離を超えて大勢の聴衆に届け、重大ニュースの第一報を新聞の「号外」ではなくラジオで聴いたりするように、マスメディアとしての印刷物を衰退させ、印刷物によってほとんど衰退していた町の触れ役を復活させ、聴覚的なラジオは限界に達した時に視聴覚に訴えるテレビへと逆転させる。 テレビは視覚を拡充することによってラジオを衰退させ、印刷物の可視性がラジオによって衰退させられらたのとはまた違った方法で視覚を回復する。テレビの視覚の回復は新しい種類のもので、依然の視覚と現在の電子の特性をまったく異なるかたちで異種交配したものだ。それが限界まで表現されると、テレビ画面はパソコンの画面に逆転する。
それでは、インターネット時代のメディアは、どのようなものへと進化するのだろうか。その進化の方向性を決めるのは、人間のニーズであり、理性的な選択だと著者は考えているようだ。それは「治療メディア」のはたらきであり、それがマクルーハンのメディア決定論を逆転させる。
インターネットと、それによって具体化され実現される現代のデジタル時代は、大きな治療メディアであり、それ以前に生まれたテレビ、本、新聞、教育、労働パターン、そしてほとんどすべてのメディアとその影響の欠点を逆転させたものなのだ。これらの救済の多くは、テレビの儚さを治療したビデオほどには、故意で意図的なものではなかった。しかしこれらが新しい千年紀において集中したことや、以前のメディアが持つ多種多様な問題を連携良く支援していることは決して偶然の一致なのではない。・・・デジタル・コミュニケーションによって強化された理性の働きの下では、すべてのメディアはいつでも手軽に治療できるようになる。(p.331)
ある種、楽観的なメディア進化論のように見えるが、もちろん、危険な側面もあることは、著者も指摘する通りである。これ以上の内容については、本書を実際に手にとってお読みいただければと思う。
なお、著者のPaul Levinson氏の経歴については、Wikipediaに詳しい。Connected Educationは、Wikipediaによると、1985年から1997年まで存続していたが、その後の経緯は明らかではない。若い頃は、ソングライターやレコードプロデュサーなどをしていたり、現在では大学教授などの傍らSF小説を書いたりと、多彩な活動を展開している方のようだ。