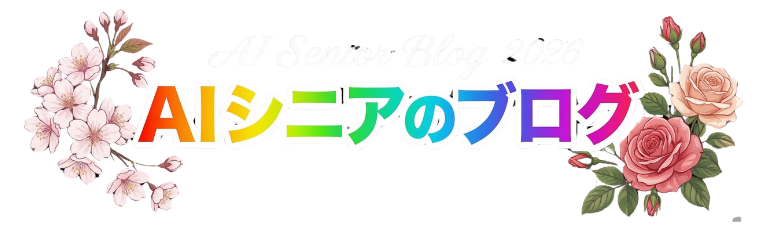![]()
- はじめに
- 第1章 「余震情報パニック」から始まった筆者らのメディア効果研究
- 第2章 「火星からの侵入」事件の調査と再評価
- 第3章 マートン「大衆説得」
- 第4章 「24時間テレビ」の効果分析(三上, 1987)
- 第5章 限定効果論を代表する3つの研究
- 第6章 「利用と満足」研究の展開:能動的オーディエンス像の検証
- 第7章 マスメディアの現実構成機能
- 第8章 培養理論
- 第9章 マスメディアの議題設定機能
- 第10章 沈黙の螺旋理論
- 第11章 選択的接触仮説
- 第12章 フレーミング効果
はじめに
本論文の目的は、過去50年にわたる研究生活を振り返り、特にメディア効果論に関わる実証的研究に、私自身がどのような問題意識をもって取り組んできたかという視点から回顧的に総括することにある。私自身は特定のメディア効果論だけを専門的に研究してきたわけではなく、複数のメディア効果論の研究に積極的に関わり、日本におけるメディア効果論の発展に一定の貢献をすることができたのではないかと考えている。
以下の総括的議論は、実証的コミュニケーション研究としての「メディア効果論」の包括的なレビューを試みたものである。欧米での研究を中心としつつも、これまで1箇所にまとめて論じられることのなかった日本での実証的メディア効果論をできるだけ幅広く紹介することに努めた。足りないところ、記述の間違いなどご指摘をいただければ、随時、加筆修正を加えていきたいと思う。
本サイトはいまだ制作途上にあり、完成は2025年6月の予定です。
追加執筆予定のコンテンツ
第3部 続・メディア効果論
- 第10章 沈黙の螺旋理論
- 第11章 選択的接触仮説
- 第12章 フレーミング効果
- 第13章 プライミング効果
- 第14章 精緻化見込み、情報処理モデル
- 第15章 第三者効果
- 第16章 ニュースの流れ研究
- 第17章 流言、フェイクニュースの心理学
- 第18章 普及理論
- 第19章 知識ギャップ仮説
- 第20章 プロパガンダ、大衆文化論
なお、本稿は、2024年12月7日および2025年2月15日に東京大学情報学環大学院関谷直也ゼミで行われた勉強会のために準備したものです。本ページの内容を無断で複製、転載されることは固くお断りいたします。リンクによる引用はご自由にどうぞ。
著者:三上俊治(東洋大学名誉教授)
メディア・コミュニケーション論、社会心理学
第1部 強力効果論 VS 限定効果論
メディア効果論は、その最初から、「認知面の効果」「行動面の効果」という2つの軸で展開していたことに注目する必要がある。その出発点はリップマンの「世論」とキャントリルの「火星からの侵入」に見出される。すなわち、認知面では「擬似環境」(環境イメージの形成、小文字の世論)「ステレオタイプ」、行動面では「大文字の世論」「プロパガンダ」「パニック」という視点から論じられていた。
ただし、リップマンに欠けていた視点が一つあった。それは、オーディエンス(大衆)が本来持つ「情報リテラシー」である。そのことをデューイは同時代にあって鋭く批判していた。また、「火星人襲来パニック」を研究したHerzogが、いち早く「批判能力」の発揮という視点から証明した。現在では、フェイクニュースに対する「情報リテラシー」の必要性という形で、多くの研究者が指摘するところである。「認知バイアス」の検知と克服においても、情報リテラシーが重要な役割を発揮するであろう。
もう一つ大切な視点は、メディア効果論の歴史の中で、それぞれの創始者が「どのような思い」で新しい理論をつくりあげたのか、という背景や経歴を常に考えてみるということである。例えば、リップマンの場合は、ジャーナリストやPR専門家としての活動、経歴、背景を知ること、LazarsfeldやHerzogの場合は、実証的な社会調査の手法を開発、推進したという経歴である。Gerbnerもまた、ジャーナリストという経歴を経て、培養理論を構想したという経歴があった。
メディア効果論の歴史的展開は、それぞれの理論が登場する「時代背景」「メディア環境」「研究者の経歴」という3つの大きな背景から必然的に生まれたことを忘れてはならない。
第1章 「余震情報パニック」から始まった筆者らのメディア効果研究
筆者にとってのメディア効果論研究は、1978年1月18日に起こった「余震情報パニック」事件に始まったと言ってもいいだろう。1月19日の朝、満員の小田急線に乗っていた私は、読売新聞朝刊1面の「余震情報でパニック」という大見出しを見てびっくりし、「これこそ私が今研究すべきテーマだ」と直感した。早速、新聞研の大学院同級生の水野博介さん(現・埼玉大学名誉教授)と連絡をとり、一緒に研究することで合意した。すぐに、地震予知研究会代表の岡部慶三教授の研究室に行き、ぜひ研究会として調査研究したいと申し出たのだった。
一方、水野さんの証言によれば、1月19日の朝、彼もまた「余震情報パニック」の新聞記事を読んで、とっさにこの問題について調査研究すべきだと考え、筆者を誘って岡部先生の元に行ったということである。このあたりの事実関係は、すでに50年近く前のことなので、どちらの記憶が正しかったかを検証することは難しい。おそらく、ほぼ同時に、「余震情報パニック」の現地調査を思いついたというのが正確だろうと思う。ただ、二人の間で研究動機に若干の違いがあった。私が「パニック」の有無について調べたいと思ったのに対し、水野さんは、修士論文で「認知的不協和理論」をテーマとして研究し、その関係で「災害と流言」について詳しく調べたいと考えたのである。静岡県で起こった「余震情報パニック」は、その両方の条件を満たす事例だったのである。
二人の若手研究者の調査提案に対し、岡部教授は全面的に賛同してくださり、「調査費用についてはオレに任せておけ」とおっしゃり、こうして、新聞研究所チームによる余震情報調査プロジェクト(「地震と情報」研究班)がスタートしたのだった。
ちょうど同じ頃、民間シンクタンクの未来工学研究所でも、吉井博明主任研究員をリーダーとして、静岡県協力の下、余震情報調査研究の準備が進められていた。そこで、両者がバッティングすることは好ましくないと言うことで、両者の間で研究の調整が行われ、筆者ら新聞研のチームが未来研の調査員として協力する代わりに、静岡県沼津市、下田市における新聞研の調査研究は東大新聞研チームが独自に実施、発表することになった。このような分業の結果、静岡県の発表した余震情報がどのようなルートを経て「地震予知情報ないし警報」という流言に変容していったのか、という「地震警報流言」調査の全容は未来研が発表し、余震情報に対する住民の反応を中心とする調査結果は、新聞研が独自に発表することになったのである。
メディア効果論に関わる実証研究は、新聞研チームの沼津調査、下田調査において実施されることになり、これが実際にはメディア効果論の領域で大きな成果を生むことになったのである。
当初は、新聞で大きく報道されたこともあり、「余震情報によって住民の間に大きなパニックが起こった」と信じられていた。しかし、我々が行った調査の結果、実際にはパニックはほとんど起こっていなかったことが明らかになった。また、キャントリルが「火星からの侵入」で明らかにした、住民の「批判能力」(情報確認行動)が余震情報パニックでもはっきりと確認された。これは、メディアの「強力効果」という神話を根本から突き崩すものであった。
以下、「余震情報パニック」沼津調査、下田調査で明らかになったことを述べる。
1. 余震情報発表、伝達の経緯
1978年1月14日に伊豆大島近海地震(M7.0)が発生したが、その4日後の1月18日に、静岡県災害対策本部より、最悪の場合、M6程度の余震が起きる可能性があるという「余震情報」が発表された。この余震情報は、同日1時30分に、災害対策本部より防災行政無線を通じて、県下市町村に伝えられた。また、午後1時40分には災害対策本部長の山本県知事が記者会見して余震情報を発表し、静岡放送(SBS)では午後2時17分に、テレビとラジオでニュース速報を流した。さらに、午後2時頃に、静岡県災害対策本部より県消防防災課を経由して、プロパンガス協会など民間事業者団体の電話連絡網を通じて、余震情報が県の全域に伝えられた。このうち、事業者団体のルートから伝えられた余震情報は、伝達過程で「2〜4時間以内に震度6の大地震が起きる」などの「地震予知情報」ないし「地震警報」の流言となって、わずか数時間のうちに一般住民の間に広がることになった。
2. 「余震情報パニック」報道の実態
翌1月19日、主要全国紙と地元静岡県の新聞は、いっせいに「余震情報でパニックが生じた」と報じた。例えば、読売新聞は朝刊の1面トップで「余震情報」でパニック / テレビ速報→デマ走る / 住民が避難騒ぎ、という見出しで次のように伝えた。

(1978年1月19日『読売新聞』朝刊1面)

(1978年1月19日『朝日新聞』朝刊社会面)
読売新聞は、朝刊の1面トップで次のような記事を掲載した。
「余震情報」が地元民間放送のテレビのテロップや関係市町村の広報車、有線放送で流されたため、住民の不安心理が増幅され、「2時間以内に大地震が起きる」というデマ津波となって広がり、県や各市町村の災害対策本部や警察に問い合わせの電話が殺到、被災地の河津町などでは住民が一斉に外へ飛び出して避難するというパニック状態となった。騒ぎは夕方には収まったが、「余震情報」でパニックが起きたのは、初めてである。
また23面には、次のような関連記事を掲載した。
18日午後、静岡県災害対策本部が流した「余震情報」は、地震におびえていた地元の伊豆半島中南部ばかりか、県内の他市町村の住民まで騒ぎに巻き込んだ。県の災害対策本部、県警本部、国鉄静岡鉄道管理局は、すさまじい問い合わせの電話ラッシュ。被災地の河津町では家財道具を持ってどっと避難するなど、初の余震情報が不安と誤解をからませて、巨大なパニックに膨れ上がった。
河津町谷津、峰地区などでは、住民が家財道具を自動車に積んで広場やたんぼに避難、下田信用金庫河津支店では、午後2時過ぎ閉店した。町の中央にあるスーパーは、客も店員も避難して、店内はもぬけのカラ。ほとんどの住民が家を飛び出して毛布や食糧を手に右往左往するばかり。
他の新聞も似たり寄ったりで、余震情報が住民の間にパニックを引き起こしたという内容の記事がほとんどだった。こうした報道は、約40年前にアメリカでオーソン・ウェルズ演出によるラジオ・ドラマが「火星人来襲 (Invasion from Mars)」という虚報となって全米をパニック状態に陥れたと報じられた事件を彷彿とさせるものであった。筆者が思い浮かべたのもこの出来事であり、ぜひ調査したいと考えた理由も、その共通性にあったのである。
3. 沼津、下田市民調査の概要
沼津と下田を調査対象地にしたのは、未来工学研究所との間で取り決めた役割分担の結果であり、それ以上の意味はない。
調査方法:
1. 1978年1月に実施した世帯留置調査
| 沼津市 | 下田市 | |
|---|---|---|
| 調査方法 | 調査票個別配布 | 郵送回収 |
| 調査対象 | 香貫地区の200世帯 | 旧市街地区の300世帯 |
| 調査票配布時期 | 1978年1月24日 | 1978年1月23日 |
| 調査票回収数 | 97 | 162 |
| 回収率 | 48.5% | 54.0% |
2. 1978年2月に実施した個人面接調査
| 調査時期 | 1978年2月10日〜19日 |
|---|---|
| 調査対象者 | 沼津市香貫地区の5自治会区に在住する全世帯の主婦またはそれに準ずる者714名 |
| 調査方法 | 個人面接法 |
| 有効回収数 | 520(回収率72.8%) |
4. パニック反応の有無
「余震情報パニック」騒ぎがあった直後に沼津市及び下田市で実施した住民調査の結果は、マスコミ各社の報道とは全く異なるものであった。筆者らの調査チームが事件直後に、静岡県に入って、住民への聞き取り調査を行った結果を見ると、当日、情報を聞いてパニック状態に陥ったことを示す事例はほとんど見つからなかった。また、余震情報や地震予知流言に接触した住民の対応行動についてアンケート調査を実施したところ、「パニック」状態に陥って、適切な対応行動がとれなかったと思われる「混乱(状態)」にあった人は、下田と沼津でそれぞれ1人いたにすぎないことがわかった。多くの人は、「食料や水などを準備した」など避難準備をしたという程度にとどまっていた。実際に避難したという人も、下田で3人いただけだった。このように、行動レベルでパニックやそれに近い極端な行動をとった人はほとんどいなかった。これらは、社会学者N.スメルサーの定義する「ヒステリー的信念に基づく集合的逃走」とは程遠いものだった。
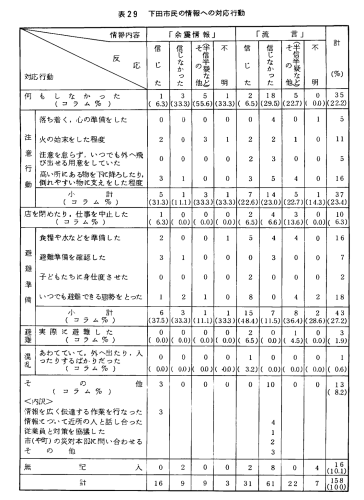
第2章 「火星からの侵入」事件の調査と再評価
1. 事件の概要
「余震情報パニック」報道で想起した40年前の「火星人襲来パニック」は、マスコミの「強大効果」の証拠として、メディア効果論において、しばしば言及されてきた。
1938年10月30日(日)午後8時、アメリカ3大ネットワークの一つ、CBSラジオでは、毎週恒例の「マーキュリー劇場」の放送が始まった。今回は、H.G.Wells原作の『宇宙戦争』(The War of the Worlds)のラジオドラマ脚色版を取り上げることになっていた。 しかし、この脚色は、ハロウィーン前夜にふさわしい、一風変わったストーリーに仕立てられていた。通常の番組にみせかけて、音楽や天気予報を流している間に、「臨時ニュース」を流し、あたかも火星人が地球に来襲し、アメリカ中心部に攻め込んできたかのような、実況中継を繰り返し流すという趣向のドラマだったのである。 主演および演出を務めたのは、当時23歳、売りだし中の若きオーソン・ウェルズ(Orson Welles)であった。
番組の冒頭、ウェルズはおごそかな口調で次のようなセリフから始めた。「20世紀前半の今日、われわれの世界は人類よりも頭脳明晰な生命から監視されているのです」(We know now that in the early years of the twentieth century this world was being watched closely by intelligences greater than man's and yet as mortal as his own.)。続いて、ドラマが始まるのだが、それは通常のラジオ番組のような雰囲気であった。天気予報が読み上げられたあと、アナウンサーが「それではみなさんをニューヨークのダウンタウンにあるホテル・パークプラザのメリディアン・ルームにご案内します。Ramon Raquelloと彼のオーケストラをお楽しみいただきましょう」と語りかけた。 しばらく後、通常の番組とは違った臨時ニュースが挿入された。「みなさん、ここでダンス音楽を中断して、「インターコンチネンタルラジオニュース(Intercontinental Radio News)からの臨時ニュースをお伝えします。8時20分前、イリノイ州シカゴにあるジェニングス山天文台のファレル教授が、火星で高温ガスが連続的に爆発しているとのレポートを発表しました」。このあと、番組はもとのダンス音楽の演奏に戻った。 その後、音楽はしばしば臨時ニュースによって中断されるようになり、火星の異常現象についての最新情報が次々と放送された。ニュースレポートは、プリンストン天文台に移り、「カール・フィリップ記者」が「リチャード・ピアソン教授」と、不可思議な天文学上の異常現象について語り合った。通常番組に戻ってからしばらくして、再び「インターコンチネンタルラジオニュース」が入り、アナウンサーがこう告げた。「みなさん、最新ニュースをお伝えします。午後8時50分、ニュージャージー州トレントンから22キロ離れたグローヴァーズミル(Grover's Mill)近郊の農場に、隕石と思われる巨大な燃える物体が落下しました。・・・」(Ladies and gentlemen, here is the latest bulletin from the Intercontinental Radio News. Toronto, Canada: Professor Morse of Macmillan University reports observing a total of three explosions on the planet Mars, between the hours of 7:45 p.m. and 9:20 p.m., eastern standard time. This confirms earlier reports received from American observatories. Now, nearer home, comes a special announcement from Trenton, New Jersey. It is reported that at 8:50 p.m. a huge, flaming object, believed to be a meteorite, fell on a farm in the neighborhood of Grovers Mill, New Jersey, twenty-two miles from Trenton) 再び通常の音楽が続いたあと、隕石墜落現場からの臨時ニュースが入ってきた。「隕石」と思われた物体は、「金属製の円筒型物体」と分かり、アナウンサーは、この金属物体から巨大な足が伸び、中から火星人と思われる異様な生物が現れ、光線銃から火炎放射を浴びせ始め、これに抵抗する人々を殺戮する様子を、効果音などを使って、緊迫感をもって伝えた。さらに、グローヴァーズミルの現場(ウィルマス農場)付近で、州兵6名を含む少なくとも40名が死亡したと伝え、さらなる惨事を次々に伝え続けた。「臨時ニュース」はますますエスカレートしていった。現場のアナウンサーは、ついに火星人の来襲を告げる。
火星からの侵入者は、次第にニューヨークへと向かい、多数の金属円筒型兵器が地上に落下し、米軍の攻撃を退けて、ニュージャージーだけではなく、バッファローやシカゴ、セントルイスなどにも進攻していることが報告された。火星人と州兵の激しい戦闘状況が、刻々と緊迫感をもって伝えられた。 この頃には、番組をドラマではなく、実際の臨時ニュースと勘違いした少なからぬリスナーが、これに驚き、車で避難したり、なかには自殺をはかった者もいたという。この放送の反響について、のちに詳しい実態調査を行ったキャントリルは、次のように表現している。
この放送が終了するずっと前から、合衆国中の人びとは、狂ったように祈ったり、泣き叫んだり、火星人による死から逃れようと逃げ惑ったりしていた。ある者は愛する者を救おうと駆け出し、ある人びとは電話で別れを告げたり、危険を知らせたりしていた。近所の人びとに知らせたり、新聞社や放送局から情報を得ようとしたり、救急車や警察のクルマを呼んだりしていた人びともあった。少なくとも6百万人がこの報道を聞き、そのなかで少なくとも百万人がおびえたり、不安に陥ったりしていた。(『火星からの侵入』邦訳47ページ)
LONG before the broadcast had ended, people all over the United States were praying, crying, fleeing frantically to escape death from the Mar-tians. Some ran to rescue loved ones. Others telephoned farewells or warnings, hurried to inform neighbors, sought information from newspapers or radio stations, summoned ambulances and police cars. At least six million people heard the broadcast. At least a million of them were frightened or disturbed. (The Invasion from Mars, p.47)
しかし、キャントリルによるこの表現は、かなり誇張したもので、ラジオドラマの及ぼした影響は、後述するように、パニックとはかけ離れたものだった。詳しくは、三上(2017)、佐藤 (2019)などを参考のこと。
-
-
「火星からの侵入:パニックの社会心理学」再考 - AIシニアのブログ
今年も、ハロウィーンが近づいてきました。今から81年前のハロウィーン前夜にアメリカで起こった「パニック」騒ぎについての考察です。この記事は、2014年11月8日に、「メディア・リサーチ」ブログに掲載し
続きを見る
The original ‘fake news’? ‘War of the Worlds’ at 80 USA Today (YouTube)
2. 新聞による「パニック」報道
翌日(10月31日)の新聞各紙は、CBSラジオドラマが引き起こした「パニック」について、センセーショナルに報道した。


たとえば、『ニューヨーク・タイムズ』紙は、翌日の朝刊で、「Radio Listeners in Panic,Taking War Drama as Fact (ラジオ聴取者がパニックに:戦争ドラマを事実と勘違いして)」と題して、1面で大きく伝えた。
「昨夜午後8時15分から9時30分の間に、H.G.WellesのSF小説『宇宙戦争』のドラマ化が放送されたとき、何千人ものラジオ聴取者がマス・ヒステリー状態に陥った。何千人もの人々が、侵略した火星人との宇宙間戦争に巻き込まれ、彼らのまき散らす致死性ガスでニュージャージー州とニューヨークを破壊しつくしていると信じた。 家庭を混乱に陥れ、宗教礼拝を妨げ、交通渋滞を引き起こし、通信障害を招いたこの番組は、オーソン・ウェルズによって制作されたものである。今回の放送によって、少なくとも数十名の成人がショックとヒステリー症状で治療を受けることになった。 ニューアークでは、20以上の家族がウェットハンカチとタオルを顔にかけて家を飛び出し、毒ガス攻撃を受けたと思い込んだ地域から逃亡をはかった。家事道具を持ちだした者もいた。ニューヨーク中で多くの家族が家を後にし、近くの公園に避難した者もいた。数千人が警察や新聞社やラジオ局に電話をかけ、アメリカの他の都市やカナダでも、ガス攻撃への対策にアドバイスを求める人々が相次いだ。」
しかし、アメリカの新聞各社は、主にAP通信の伝える誇張された内容の報道を後追いしたもので、十分な取材をもとに製作してされたものではなかった。アメリカン大学教授のCambellは、全米の新聞36紙を詳細に分析した結果、「放送が大規模なパニックやヒステリーを引き起こしたとする主張は大きく誇張されていたことを発見した。新聞が広範なパニックやヒステリーとして描写していたものが、実際にはごく少数の、恐怖や動揺を感じた人々に関する逸話的なケースに基づいていることが明らかになった。これらの逸話は大規模なものではなく、個人やその家族、隣人の間で見られた興奮や奇妙な行動について述べものにすぎなかった。
Cambellによる分析の結果をまとめると、「パニック報道」の実態は、次のようなものだった(Cambell, 2017)。
- 「パニック」を煽るような新聞報道は、当時新興メディアとして広告の競争相手だったラジオを叩くための絶好の機会だと捉えた新聞業界の対抗策だった。そのために、新聞はラジオドラマが引き起こした「パニック」を誇張して報道したのである。
- ラジオドラマの舞台となったニューヨーク大都市圏やニュージャージー北部では、番組への反応が最も顕著だったため、多くの小規模な記録が新聞に掲載されたが、それらを合わせても、数万人または数十万人のリスナーが恐怖に陥ったりパニック状態になったという主張を裏付けるような記事ではなかった。
- その夜に大規模なパニックやヒステリーがなかったことは、続報が少なかったことによっても示唆されている。もし本当に全国的なパニックやヒステリーが発生していたなら、その後数日、さらには数週間にわたって、この異例な出来事の規模や影響についての詳細な報道が行われたはずである。しかし、ほとんどの新聞では、放送後1日か2日で報道は終息してしまった。ニューヨーク・タイムズ、ワシントン・ポスト、ロサンゼルス・タイムズなどの大新聞も、放送後2日間一面で取り上げただけだった。
- ニューヨークでは、「パニック」が最も詳細に報じられたが、個別的な事例を取り上げたにとどまり、全国的にパニックが広がったという証拠には言及されていなかった。例えば、タイムズの報道では、ブロンクスのルイス・ウィンクラーのような恐怖に陥った人々の個別のエピソードが強調されており、彼は番組を聴きながら「ほとんど心臓発作を起こしかけた」と語っていた。ショックを受けたものの、ウィンクラーは「他の多くの人と共に通りに飛び出し、あらゆる方向に人々が走っているのを見た」と述べた。また、ニューヨークの対岸にあるジャージーシティーの警察に「ガスマスクを分けてもらえないか」と問い合わせた人がいたことも報じられた。さらにタイムズは、マンハッタン北端のワシントンハイツの警察署に「敵の飛行機がハドソン川を越えている」と叫びながら駆け込んできた「恐怖で真っ白になった男」の話も伝えられた。一方で、同じ地域では、通りの角に集まって「空の『戦闘』を見ようと」期待する人々の集まりも報じられ、好奇心がパニックを上回っていた様子も伺えた。ニューヨークの警察署に通報してきた何人かは、「爆弾の煙が街に漂ってくるのを見た」と主張していた。ニューアークのスター・イーグル紙は「戦争の恐怖が全国、特にニュージャージー州の数十万人に襲いかかった」と放送について伝えたが、この大々的な主張を裏付ける証拠として、数人以上が関わった具体的な事例はわずか6件ほどしか挙げていなかった。
- 「宇宙戦争」ドラマがが放送されたのは東部標準時の日曜夜遅くで、ほとんどの新聞社の編集室にはスタッフが少ない時間帯だった。特に締め切りが深夜に設定されている朝刊に間に合うように放送の反応を取材することは、新聞社にとっては大きな問題だった。時間と人員が限られているため、多くの新聞社ではAP通信などの通信社に頼ることが不可欠となった。この依存がAP通信社から配信された広範なパニックの概念を広め、強化する結果となったのである。その夜のAP通信の報道は、基本的に全米各地のAP支局から集めた反応をまとめたものだった。通常、これらのまとめ記事は、詳細や深みよりも、各地からの簡潔で印象的な逸話的な報告に重きを置いていた。これらの逸話は概して簡略で浅薄、そして小規模なものだったものの、その広範な取り上げ方がその夜にパニックが広がっていたかのような印象を与えた。新聞が通信社のまとめ記事に依存していたため、放送が大規模なパニックを引き起こしたという共通認識が生まれたのである。
3. Cantrilらによる調査研究
ラジオドラマの「現場」からほど近くにある、プリンストン大学では、1937年からロックフェラー財団の助成により、Paul Lazarsfeldを主任とし、Frank StantonおよびHadley Cantrilを副主任として「ラジオ研究施設」が設立され、ラジオが聴取者に果たす役割についての調査研究が行われていた。この「ラジオ・パニック」事件は、当時ニューメディアであったラジオの及ぼす影響力を研究するための絶好のテーマと受け取られ、プリンストン・ラジオ・プロジェクトの一環として、キャントリルを中心に研究を進めることが決まった。その裏には、研究の影の推進役となったLazarsfeldの存在があったといわれる。
調査研究は、Cantrilを中心に行われ、1940年に、『火星からの侵入?パニックの心理学に関する研究』(The Invasion from Mars : A Study in the Psychology of Panic)として出版され、大きな反響を呼んだ(Cantril, 。ある意味で、オーソン・ウェルズの『火星からの侵入』ラジオ放送が全米にパニックを引き起こしたとする「通説」は、翌日の新聞でセンセーショナルに伝えられたが、Cantrilらの調査研究によってデータ的な裏付けを与えられ、定着したといえるかもしれない。
4. 世論調査からみたパニックの有無
しかし、このラジオ放送は本当に全米に一大パニックを引き起こしたのだろうか?これについては、『火星からの侵入』で強調されたキャントリルらの知見とは違って、パニックは起きていなかったとする有力なデータがある。
1) どのくらいの人がラジオ放送を聞いていたか?
キャントリル『火星からの侵入』では、放送の6週間後に実施された米国世論調査所(AIPO)の全国調査での「あなたはオーソン・ウェルズの火星からの侵入という番組を聞きましたか?」という質問に対して、「はい」と答えた人が12%いたことから、この数字をもって、番組の聴取率としている。しかし、事件から6週間後というと、アメリカ人のほとんどがパニック騒ぎについて知っていたと推定されるから、実際よりもかなり多くの人が「放送を聞いた」と誤認していたとしても不思議ではない。実際、放送が行われた夜、C.E.フーパーのレーティングサービスが5,000世帯に電話をかけて全国的な視聴率調査を行っているが、「どの番組を聞いていますか?」という質問に対し、「ドラマ」や「オーソン・ウェルズの番組」、またはCBSの番組と答えた人は、わずか2%にすぎなかった。言い換えれば、調査対象の98%は、他の番組を聞いていたか、あるいは何も聞いていなかったのである。このように視聴率がわずか2%と低かったのは不思議ではない。ウェルズの番組は、当時最も人気のあった全国番組の一つ、腹話術師エドガー・バーゲンの「チェイス・アンド・サンボーン・アワー」というコメディバラエティ番組と同じ時間帯に放送されていたからである。(Pooley and Socolow, 2013)。
1930年の国勢調査によると、当時のアメリカの成人人口は約7500万人だったので、視聴率2%というのは、150万人に相当する。
2)どのくらいの人がパニック状態になったか?
それでは、Wellsの放送を聞いた150万人のうち、どれくらいがこれを本当のニュースと勘違いしたのだろうか?同じくAIPOの調査で「あなたが番組を聴いた時、この放送が単なるラジオドラマだと思ったか、それとも実際のニュース放送だと思ったか?」という質問に対しては、28%が「ニュースだと思った」と答えていた。これは数字に直すと、42万人に相当する。キャントリルの著書では、ニュースだと思った人のうち70%(約29万人)が「恐怖に駆られて、狼狽した」と答えたことになっているが、これは、心理的反応の一つであり、逃走行動を伴う「パニック」とは明らかに異なっている。実際にパニック的な逃走反応を示した人は、29万人の中のごく一部に過ぎなかったと推測されるのである。
Cantrilの『火星からの侵入』の第2章「パニックの性質と範囲」では、新聞報道と調査チームの収集した市民の反応を、エピソード的に紹介している。そのほとんどは、パニック状態で逃げ出したり、家族を守ろうとする行動をとった極端なケースであった。次の証言は、その典型的なものである。
ジョスリン夫人は大都市のスラム街に住み、その夫は日雇い労働者だが、次のように語った。「私はとても恐ろしかった。荷物をまとめて、子供を抱き抱えて、友達に声をかけ、自動車に乗り込み、できる限り北に向かおうとしました。でも、私が実際にしたことといえば、窓辺に座って、祈り、神の言葉に耳を傾け、恐怖で身がすくみ、夫ははなをすすり、人々が逃げ出していないか外を眺めていました。するとアナウンサーが『街から避難してください』と言ったので、私は駆け出して、アパートの住民に呼びかけ、子供を抱えて、階段を大慌てで降りて行きました。
このような、ごく少数の極端な証言を多数掲載することによって、Cantrilの『火星からの侵略』は、一般読者に「大規模なパニックが起きた」とする誤ったイメージを植え付けることになってしまったと思われるのである。このことが、メディア効果論の歴史において、「火星人襲来」放送の影響力に対する過大な評価を生み、いわゆる「魔法の弾丸(丸薬)」あるいは「(皮下)注射針」的な強大効果説の代表的研究事例として祭り上げられることになったと推測される。
5. 「火星からの侵略」研究におけるラザースフェルド、ヘルツォーク、ゴーデットの貢献
しかし、PooleyとSocolowが指摘するように、『火星からの侵略』報告書を生み出したプリンストン大学ラジオ研究プロジェクトは、1937年にハードレイ・キャントリルとフランク・スタントンの提案書をもとに、ロックフェラー財団の助成により設立されたラジオ研究施設だった。最初のディレクターは、スタントンがCBS に移籍したため、オーストリア出身の心理学者Paul Lazarsfeldに決まった。
1938年10月30日夜、CBSでウェルズのドラマが放送され、大きな混乱が起こったとき、当時CBSに所属していたStantonは、これがラジオ研究の絶好の機会になると直感した。
Frank Stantonと妻ルースは急いでマディソン・アベニューを走り、52丁目の角にあるCBS本社ビルへ向かった。車内のラジオで「宇宙戦争」のクライマックスを聞いた。『宇宙戦争』ドラマのクライマックスを耳にしたスタントンは、リスナーの間に興奮とパニックが広がり始めていることが、ラジオ史上最も幸運な研究機会であると気づいた。CBSの建物に到着後、スタントンは車を停め、オフィスに向かい、この番組の影響について迅速かつ正確に質問票を作成した。そして、ロックフェラー財団から資金を得ているプリンストン・ラジオ研究プロジェクトの責任者であるポール・ラザースフェルドに電話で相談し、次にジョージア州アトランタのフーパー・ホームズ社に連絡を取りました**。この会社は個別インタビューを専門としており、調査に電話だけでなく対面インタビューも行うことが可能だったのです。
Stantonは経済階層や都市・農村の居住区分といった要素に応じたサンプルの選定を慎重に行い、**翌朝には調査が開始されました**。
スタントンは、その時間の早い段階で、興奮とパニックの報道が流れ始めていることに気づき、これはラジオ史上でも最も幸運な研究機会の一つだと直感しました。CBSビルに到着すると、彼は車を停め、エレベーターでオフィスに向かい、番組の影響に関するアンケートをできる限り迅速かつ正確に作成しました。その後、Lazarsfeldに電話して短時間の相談を行い、次にジョージア州アトランタのフーパー・ホームズ社に電話しました。フーパー・ホームズ社は保険業界向けの個別インタビューを専門とし、特に電話だけに頼らない調査手法を採用していました。Stantonは、経済階層、田舎または都市部といったサンプルを慎重に選び、その他の人口統計的要素を考慮しました。翌朝にはフィールドワークが開始されました。
(Pooley and Socolow, 2017)
このフィールドワークで中心的な役割を担ったのは、Lazarsfeld、Cantril、Herzog、Godetの4人だった。なかでも、女性研究者だったHerzogとGodetは、インタビュー調査の結果を詳しく分析した結果、番組の信憑性をチェックするという「批判能力」(critical ability)がパニックを防止する上で重要な要因であることを突き止めたのだった。これは、もっぱら番組が大規模なパニックを引き起こしたとするCantrilがパニックの原因として「非暗示性」を強調したのとは対照的であった。
プリンストン・ラジオ研究プロジェクトの行った調査には、重大な問題点が含まれていた。それは、番組放送後2ヶ月間にインタビューを行った対象者135人のうち100人が、「ウェルズの放送を聞いて驚愕した」と答えた人から選ばれたということである。つまり、パニック的な反応を示した聴取者に偏ったサンプルが恣意的に選ばれた可能性が高いのである。このことは、135人の回答に基づく報告書の記述が、パニックを誇張するものになったことを裏付けている。
このように、調査サンプルに大きな偏りがあったとはいえ、HerzogやGodetが発見した、リスナーの「批判能力」の存在は、ラジオ番組が大衆にダイレクトに強大な影響力を発揮するという「注射針」あるいは「魔法の弾丸(丸薬)」モデルの代表例を提供しただけではなく、LazarsfeldやE.Katzらによる「限定効果」モデルの先駆的な業績を提示するものだったと言える。
このような再評価の背景には、『火星からの侵入』の出版と調査プロジェクトの主導権をめぐるCantrilとLazarsfeldの葛藤、「火星からの侵入」に関する新聞報道の詳細な分析、Herzogなど研究に精力的に関わった女性コミュニケーション研究者の貢献への注目など、最近のメディア史研究の成果がある(Rowland and Simonson, 2014)。
6. 批判能力とリスナーの反応
Cantrilらは、この番組の聴取者を次の4つに分類し、情報確認行動とパニック反応の関連を明らかにしようと試みた。
- 番組のなかに手がかりを見つけ出して、本当であるはずがないと考えた人びと(内在的チェックに成功したグループ)
- ドラマであることをチェックすることに成功した人びと(外在的チェックに成功したグループ)
- うまくチェックできず、ニュースだと信じつづけた人びと(チェックに失敗したグループ)
- 放送だから本当だと信じて調べようとしなかった人びと(チェックを試みなかったグループ)
この分類は主として135のインタビュー事例のもとづくものであり、一般化することは難しい。ともあれ、それぞれのグループに含まれる人びとは、どのように反応したのだろうか?
内在的チェックに成功した人びとの反応
このグループの約半数は、かれらが入手した情報をもとに、ドラマと見抜くことができた。なかには、ウェルズの『宇宙戦争』を読んでいて、それを思い出した人もいた。「・・・怪物が姿を現したとき、これはオーソン・ウェルズの番組だということが突然頭に浮かびました。そしてそれが『宇宙戦争』という番組であることを思い出したんです」。また、番組の内容自体に含まれる矛盾に気づいて、ドラマであることに気づいた人もいた。「・・・わたしはアナウンサーがニューヨークから放送しており、火星人がタイムズ・スクエアにあっているのを眺めながら、摩天楼と同じくらいの高さだといっているのを聴きました。それで十分でした。・・・ドラマに違いないと思ったんです」。
外在的チェックに成功した人びとの反応
このグループに属する人びとは、新聞のラジオ番組欄を調べたり、他のラジオ局にダイヤルを回したりして、チェックすることによって、ドラマであることを確認していた。また、友人を呼び出したりしてチェックした人もいた。「・・・本物のように聞こえましたが、WOR局にダイヤルをまわして、同じことが放送されているかどうか確かめました。そうでなかったのでつくり話だとわかりました」。
チェックに失敗した人びとの反応
このグループの人びとは、チェックを試みたものの、それがまったく信頼できるものではなかったという特徴をもっていた。もっともよく使われた方法は、窓から外をみるとか家の外に出てみるといったものであった。なかには、警察や新聞社に電話をかけた人もいた。しかし、他のラジオ局にダイヤルをまわしてみるとか、新聞のラジオ欄をみるなどの外在的チェックをとることには失敗していた。「僕らは窓から外を見ました。ワイオミング街は車でまっくろになっていました。みんな急いで逃げようとしているなど思いました」。「私はすぐに警察に電話して、何がおこっているのか聞きました。警察は、<あなたと同じことしか知りません。ラジオを続けて聞いてアナウンサーの忠告に従ってください>ていうんです。当然、電話をかけた後では前よりもいっそう恐ろしくなりました」。
チェックを試みなかった人びとの反応
このグループの半数以上は、驚きのあまりラジオを聞くのをやめて逆上して走り回ったか、麻痺状態におり言ったとしかいいようのない行動をとった。「わたしたちは聞くことに夢中で、他の中継を聞いてみようなどという考えは全く浮かびませんでした。わたしたちはこわくてしかたがなかったんです」。「あたしは天気予報のときにラジオをつけました。小さな息子といっしょでした。主人は映画に行っていましたから。わたしたちはもうだめだと思いました。子どもしっかり抱いて座りながら泣きました。こちらに向かってくると聞いたときは、もうがまんができなくなり、ラジオをとめて廊下へ走りでました。お隣の奥さんもそこで泣き叫んでいました」。 Cantrilらは、第4のグループの記述にいちばん大きなスペースを割いている。これは、なんらのチェックもせずに、パニック反応を示したグループをある意味では、パニック的反応を誇大に記述するという誤りを犯しているように思われる。そもそも、Cantrilがインタビューの対象者として選び出したのは、番組を聞いて「驚いた」という反応を示した人びとだったという点を、ここで思い出しておきたい。
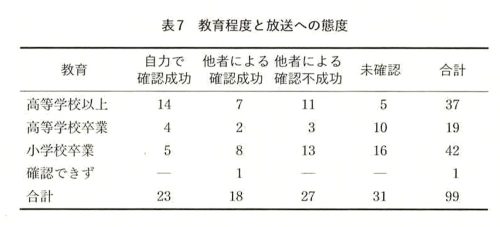
批判能力の発揮
Cantrilらの研究で、その後もっとも有名になったのは、番組を聞いてパニックに陥った人びとが、総じて「批判能力」を欠いた人びとであり、それが「学歴」などのデモグラフィックな指標と結びついていたという指摘であった。その根拠となっよたデータは、主にCBSが行った調査である。データを分析した結果、「より高い教育を受けた人びとはより多くの人がこの番組をドラマであると考えた」ことがわかった、としている。また、番組をチェックしてドラマだとわかった人は、学歴の高い人に多かったという調査結果も明らかにしている。ただし、教育程度の高い人びとのすべてが冷静であったり、チェックに成功したわけではないし、教育程度の低い人びとの中にも番組がドラマであることをすぐに理解した者もいた、と注釈している。 批判能力というのは、個人が生得的にもっている心理的特性ではなく、特定の環境の影響の結果として生じたものである。批判能力を発揮させなかった条件を明らかにしなければならない、として、Cantrilは「個人的感受性」と「聴取状況」という二つの要因をあげている。 感受性とは、放送番組からの影響を受けやすくしているパーソナリティの一般的特性であり、Lazarsfeldに(1)不安定感、(2)恐怖症、(3)悩みの量、(4)自信の欠如、(5)宿命論、(6)信心深さ、(7)教会へ行く回数の7つによって測定されている。放送に対してうまく適応できた者は、暗示に対する感受性が低いという傾向がみられた。 聴取状況は、人びとの番組に対する反応に一定の影響を与えていた。第一に、他人の行動の補強的効果と他人の恐怖の感染が考えられる。親しい者から聞いたり、ラジオをつけるようにいわれた者は、驚く傾向が強くみられた。「姉さんが電話をかけてきて、あたしはすぐにおびえてしまったの。ヒザがガクガクしました」。ある場合には、ビックリした人々を目撃したり、その声をきいたりしたことが、そうでなければ比較的冷静な者の感情的緊張をまし、その結果、批判能力を低下させてしまった。「電話ボックスから出た時には、店の中はだいぶヒステリックになった人たちでいっぱいでした。僕はこわくなっていましたが、そうした人たちをみて、何か起こったのだなと確信しました」。調査データによると、他人からラジオを聞くようにいわれた人びとは、そうでない人々よりも非合理的な行動をとる率が高いという傾向がみられた。また、CBSの全国調査の結果をみると、ニュージャージーのグローバーズミルの「現場」から離れている人ほど、驚きの程、度が低くなっていた。 このように、一般に、「批判能力」だけではパニック状態に陥るのを防ぐことはできず、個人のもつ感受性や異常な聴取状況が批判能力を低下させることがあることも明らかにされている。
第3章 マートン「大衆説得」
Mertonとマス・コミュニケーション研究
Tarcott Parsonsと並んで、構造機能主義社会学の大御所といわれた、Robert Merton。彼は一時期、マス・コミュニケーション研究にも手を染めていたことがある。初期のマスメディア効果論の代表作の一つ『大衆説得』(Mass Persuasion)は、Mertonが主導して行った調査研究であった。その過程では、Paul Lazarsfeldが深くかかわっていた。
Mertonとマス・コミュニケーション研究の関わりは、戦時中の一時期に限られている。そのきっかけは、1941年に彼がコロンビア大学に籍を置くようになり、Lazarsfeldの同僚となったことにあった。彼は、1942年から71年にかけて、Lazarsfeldの創設した応用社会学研究所(Bureau of Applied Social Research)の所長を務め、多くの社会学的な業績を残した。かの有名な「大衆説得」研究は、彼の所長時代に行われたものである。そのきっかけは、Lazarsfeldの着想にあった。Lazarsfeldは、戦時債権の募集キャンペーンのためのマラソン放送が、短時間のうちにきわめて大きな影響を及ぼしたことに注目し、これを類まれな「メディア・イベント」として研究することを提案した。実際の事例研究はMertonをリーダーとして実施され、『大衆説得』(Mass Persuasion)という書物に結実することになった(Merton, 1946)。
ケイト・スミスとマラソン放送
研究対象となったマラソン放送とは、1943年9月にCBSラジオで放送された、18時間連続のキャンペーン番組である。番組のホストを務めたケイト・スミスは、アメリカの生んだ国民的な歌手であり、当代随一の人気を誇るラジオ・タレントであった。
放送当時、彼女は30代で、その人柄から国民から広く親しまれていた。1938年には「God Bless America」を録音し、それはアメリカ賛歌としての地位を確立したのであった。翌年にはホワイトハウスに招かれて、初来米した英国のエリザベス女王の前で歌を披露するという栄誉にあずかったほどである。ルーズウェルト大統領は席上、ケイト・スミスを「これがケイト・スミスです。これがアメリカです」と紹介したという。
第二次大戦中、ケイトは2つのラジオ番組に定期出演し、1000万人もの聴取者の人気を博した。こうした文脈の中で、CBSは戦時債権募集のキャンペーン放送のホスト役として、ケイト・スミスに白羽の矢を立てたのであった。
アメリカの戦時債権は、1945年末までに1850億ドルもの売り上げを記録し、戦争遂行に大きな役割を果たした。アメリカ政府や企業は、各種の広告を通じて債権の販売促進を行ったが、それに加えて、ラジオのキャンペーン放送を通じて、さらに戦時債権の募集を行った。最初のキャンペーン放送は1942年11月に開始され、第3回のキャンペーンは1943年9月に実施された。9月8日にルーズヴェルト大統領の演説が行われたあと、2週間後にCBSラジオはケイト・スミスとともに、聴取者に直接訴えかけるキャンペーン放送を行ったのである。それは、スミスとCBSにとっては3回目のラジオ債権キャンペーンであった。しかし、今回は18時間にわたって、スミスが15分ごとに生出演するという「マラソン放送」であった。彼女の努力によって、多くのリスナーがラジオ局に直接電話をかけたり、手紙を書いたりして、戦時債権を積極的に購入し、4000万ドルもの売り上げを記録したのであった。
「大衆説得」研究の概要
Lazarsfeldはこの放送を一大メディア・イベントとして捉え、ラジオの影響力を示す格好の出来事として、Mertonを説得して、調査研究に取り組むよう進言した。最初はあまり乗り気ではなかった学究肌のMertonではあったが、結局この研究に引き込まれ、フォーカス・グループ調査など先駆的な手法を駆使した独創的な研究を展開することになったのである。この研究は、(1)ケイト・スミスの放送に関する内容分析、(2)放送を聞いた約100名のリスナーに対するインテンシブなフォーカスグループ・インタビュー、(3)約1000名を対象とする世論調査、の3つから成っていた。
内容分析は、放送の客観的な特性を明らかにしてくれた。インタビューは、具体的に説得がどのように行われたかを明らかにするものだった。そして世論調査は、インテンシブなインタビューの結果をクロスチェックする素材を提供してくれた。方法論的にみても、この研究調査は、実証的なマス・コミュニケーション社会学におけるお手本を示すものとなったのである。
このマラソン放送の「時間的な構造」を明らかにすることを通じて、Mertonは、なぜこの番組がかくも多くのリスナーを最後までひきつけ、債権購入に至らせたのかという、巨大なメディア効果を明らかにしたのであった。その中で、ケイト・スミスは、まさにマラソン競争の選手のように、最初から最後までリスナーとともに走り続け、リスナーを番組の虜にしたのであった。
テーマ分析の結果
放送内容を分析した結果、スミスが主に語ったテーマは6つあった。一番多かったのは、「犠牲のテーマ」(The Theme of Sacrifice)(51%)だった。彼女はリスナーに戦争への貢献のために犠牲を払う覚悟を訴えたが、それは3つの方向で行われた。最も強調したのは、戦場で兵士たちが払っている犠牲だった(26%)。
「今、彼らは湿地やジャングルに挑み、病気や怪我、苦痛や死の危険を冒しています。あなたや私が爆撃や空襲の恐怖、あるいは拷問や飢餓といった悲劇に遭わずに済むように、自らの命を賭けているのです。遠く離れた地で私たちの兵士たちが敵の喉元に手をかけているからこそ、私たちは安心してベッドで眠り、空からの突然の攻撃を恐れることなく暮らせるのです。」(Merton, 1946, p.52)。
次に、他の民間人が払っている犠牲にもとづく訴えが行われた(20%)。
「この母親は一人の息子を失いました。そして、もう一人の息子が同じ厳しい任務を果たし、同じ危険を冒していることを知っています。また、末の息子も間もなく彼女のもとを去り、祖国のために戦うことを彼女は知っています。あなたが今していることは、この母親がしていることに比べてどの程度のものでしょうか?攻撃を支えているでしょうか?本当に、心の中で、彼女の息子たちが最高の戦闘装備を持ち、それが十分に供給されるように援助しているでしょうか?贅沢品を買っているのではありませんか?それとも必要のないお金を戦時債券にまわしているでしょうか?」(Merton, 1946, p.52)
このようなアピールによって、リスナーは戦場に大切な息子を送り出して深い喪失の淵にある母親と自分自身を比較することによって、その代償として戦時債券の購入へと導かれる可能性がある。比率は5%と少なく、明確に語られることはなかったが、ケイト・スミス自身がキャンペーン放送で少なからぬ犠牲を払っていることも、繰り返しリスナーに思い出させた。
「皆さん、こんにちは。ケイト・スミスです。またお会いしましたね。…昨日の朝8時からずっとここに座り続けて、CBSラジオの大規模な戦時債券運動に参加するよう、そして今日中に少なくとも1枚の債券を購入してもらうよう、すべてのアメリカ人に呼びかけてきました。…」(Merton, 1946, P.54)
この「犠牲の三角形」(triangulation of sacrifice)、すなわち「兵士たちの犠牲」、「他のリスナーの犠牲」、そして「スミスのマラソン放送による犠牲」は、多くのリスナーに強い自責の念や罪悪感を生じさせた。彼らは自尊心を保つためには何かをしなければいけないと感じたのである。他の三者の犠牲に応えることで、つまり「三角形を四角形にする」ことでしか、その緊張は解消され得なかった。スミスのマラソン放送について、「犠牲の三角形」の全要素に触れたあるインタビュー対象者の言葉を次に引用する。
「彼女が戦場で死にかけている少年について語ったとき、私は心を動かされました。彼女はその少年の生い立ちから話し始め、債券が彼を救えるかもしれないと語っていました。もちろん、私は自分の息子のことを考えました。また、両脚を失った男性の話も美しい犠牲でした。ケイトの訴えや、彼女が自分の時間を犠牲にしていることを知りながら債券を買わないでいたとしたら、私は心が張り裂けていたでしょう。」(Merton, 1946, pp.54-55)。
スミスが2番目に多く語った内容は、「参加のテーマ」(The Participation Theme)だった。この運動の強力な要素の一つは、他者と共通の努力に参加しているという感覚であった。スミスによる戦時債券運動は、具体的で即時的かつドラマチックな活動に参加する機会を提供した。それは、個々に分かれた自己中心的な活動や、戦争があまりにも大きすぎて、個人の努力では到底影響を与えられないという無力感からの解放をもたらした。スミスの訴えは「私たち」「我々の」という言い回しで表現され、リスナーを共同作業者として引き込むものだった。
「私たちは一緒にできます・・・私たちはこの史上最大の戦時債券運動を成功させることができます。」(Merton, 1946, p.55)
債券購入は単なる孤立した購入行為ではなく、継続する共同企画事業の一部であった。それは戦争における単一の利害というだけでなく、スミスが主導する共同事業にとっての利害をも象徴していた。そして多くの場合、一度債券を購入した人々は、その後もラジオ放送を聴き続けた。これにより、同じ事業で他者が行っていることから間接的な満足感を得ることができた。この購入後の継続的な聴取は「強迫的」だったわけではなく、参加している共同努力の成功から生まれる満足感によって維持されていたのである。
スミスのキャンペーンで3番目に多かったのは、「競争のテーマ」(The Competition Theme)だった(12%)。スミスの戦時債券運動において、献身と犠牲の雰囲気と完全に一致するものではなかったが、競争テーマがもたらす追加の推進力を脚本家たちは完全には無視しなかった。競争状況は、目標に到達するための努力を呼び起こし、それを増加させるからである。たとえば、マラソン放送の終盤では、競争がロサンゼルスとニューヨークの間に絞られたのを受けて、次のような呼びかけが行われた。
「さあ、ニューヨーカーの皆さん。カリフォルニアの都市がニューヨークを追い越しているのです…これを変える必要があります。そのためにできることは、6-4343に電話をかけて、すぐに債券を購入することです。(Merton, 1946, p.66)」
スミスとリスナーが協力して過去の記録を超えようとする「協力的な競争」は、聴衆の一部が他の部分と競うのではなく、全員がスミスと協力して新たな目標達成に向かうものであった。
4番目に多かったのは、「簡便さのテーマ」(The Facilitation Theme)だった(7%)。スミスのキャンペーンは、リスナーに対し、どれほど簡単に行動を起こせるかを繰り返し伝えていた。
「私たちは皆さんが今日戦時債券を購入することが世界で一番簡単になるようにしました。コロンビア放送のすべての局、今皆さんが聞いているこの局を含め、特別な戦時債券専用の電話番号を設けています。それだけです。番号を聞き取って、それをメモし、その番号に電話をかけて債券を注文してください。」(Merton, 1946, p.67)
電話による誓約は、リスナーがスミスの説得によって最も動機付けられた瞬間に行動を起こすことを可能にした。行動への刺激とその行動を実現する可能性との間の時間差を最小限に抑えることで、説得は単に態度を変えるだけでなく、実際の行動を引き起こす効果を持ったのである。
スミスのキャンペーンで5番目に多かったのは、「家族のテーマ」(The Familial Theme)だった。現代社会において、感情的な関係の主な拠り所の一つは家族である。このような感情的な関与には変化があるものの、親が子供に対して抱く感情は深く根付いた信頼できる動機の源泉である。スミスのマラソン放送の脚本家たちは、この文化的に強調された親の献身を捉え、それを犠牲、勇気、死、愛国心といった感傷的な要素に結びつけてアピールした。
「こちらはケイト・スミスです。アメリカの少年たちが遠く離れた地で戦っているのを支えるために戦時債券を購入してください。あの少年たちは私たちにとって他人ではありません。彼らは私たちの息子であり…隣人の息子なのです。道を少し行ったところに住んでいる少年たち…食料品店の店員や事務員、ガレージの整備士…一人ひとりが私たちが覚えていて愛している顔であり声なのです。あの少年たちは私たち自身の息子であり、私たちが彼らを支援するのは当然の権利なのです。」(Merton, 1946, p.57)
最後のテーマは、「パーソナルなテーマ」(The Personal Theme)だった。スミスが放送中で主に強調したのは、離れた社会関係ではなく、「あなたと私」という直接的で親密な関係であった。彼女は自らの夢や願望を共有することで、リスナーの心の奥にアプローチする道を開いた。彼女の放送には次のような表現が含まれていた。
「あなたと私で、この運動を大成功させましょう。」
「皆さん、こんにちは…ケイト・スミスです。私の夢を叶える手助けをしていただけませんか?それは素晴らしい夢…壮大な夢…もしかしたら手の届かない夢かもしれません。でも、私たち全員が、自分の役割を果たせば、今日その夢が実現するのを私は知っています。」(Merton, 1946, p.61)。
このようなリスナーの琴線に直接触れるような語りは、訴えをパーソナルなものにし、完全な誠実さを象徴するものであった。スミス自身の感情とリスナーの感情の明確化は、心と心が通じ合う親密な対話そのものであった。一人のリスナーは次のように説明している。
「彼女が自分に語りかけているように感じました。本当に電話を取って債券を注文したのは、彼女が『もう私の話を聞くのに飽きたかもしれませんね。でも私もこれについて話すのに飽きています。それでも止めるわけにはいかないのです』と言ったときでした。その瞬間に購入を決意しました。」(Merton, 1949, p.62)
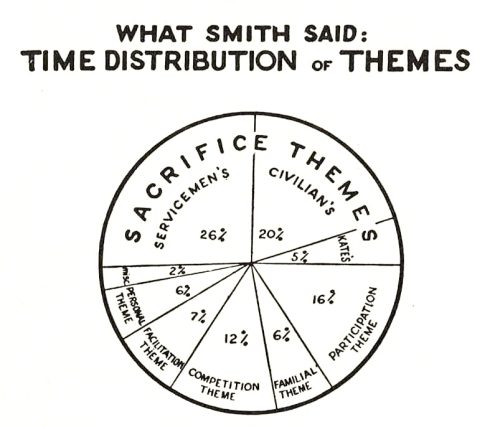
債券購入決定の要因分析
ケイト・スミスによる放送は、すべての聴取者に同じように影響を与えたわけではなかった。一部の人々は興味を増しながら継続的に聴き続けたが、彼女の訴えに全く動じない人々はすぐに別の活動に向かった。債券を購入した者もいれば、そうしなかった者もいた。
マートンは、スミスの説得に対する反応が3つの変数によって引き起こされたと考えた。すなわち、「説得の訴えの内容」「スミスに対する聴取者の態度」「説得の訴えを受けた者の先有傾向」の3つである。ここでは、スミスの債券購入キャンペーンに関連する聴取者の先有傾向の分析結果を紹介する。
マートンは、「戦時債券購入キャンペーン」放送の聴取者がもっていた先有傾向を「一般的態度」(戦時債券に対する好意的な態度)と「特殊な態度」(キャンペーン中に戦時債券を追加購入する意図の有無)という2つの態度からなると考え、この二つの態度の軸を組み合わせることによって、4つのタイプに分類した。
- 先有傾向あり(一般的態度が好意的で、追加の債券を購入する意図がある)
- 感受性あり(一般的態度が好意的で、追加の債券を購入する意図がない)
- 無関心(一般的態度が無関心だが、追加の債券を購入する意図がある)
- 先有傾向なし(一般的態度が無関心で、追加の債券を購入する意図もない)
スミスの戦時債券キャンペーンがすべての購入者に全く同じ影響を与えたと仮定するのではなく、スミスの放送を初めて聞いた時点で債券購入の準備状態が異なる者たちにおける説得の過程を体系的に探ることによって、スミスから戦時債券を購入する決定を促した動機のパターンを明らかにすることが、ここでの目的だった。4つのタイプごとに、説得効果の特徴を探る。
先有傾向のある債券購入者
聴衆の先有傾向が異なれば、説得への抵抗レベルや刺激に対する選択的反応も異なる。スミスの戦時債券キャンペーンにおいても、戦時債券に好意的で、キャンペーン期間中に追加の債券を購入することを決め、そのための資金を確保していた「先有傾向のある聴衆」の抵抗が最も低かったと考えられる。このグループは、平均12回の放送を聞いて購入を決断しており、これは「感受性のある」グループ(好意的な一般指向性を持つが、追加購入の意図がなかった者)が平均16回であったことと比較して明らかである。さらに、他の先有傾向グループの25%が20回以上の放送を聞いたのに対し、先有傾向グループでは15%に過ぎなかった。先有傾向グループは、戦時債券の重要性や追加購入の必要性を訴えるスミスの放送内容にはほとんど注意を払わなかった。彼らにとってそれは「既に決着した問題」であり、関心は「いつ」「どこで」購入するかという未解決の点に集中していたのである。
感受性のある債券購入者
スミスの放送を聞く前、「感受性のある」グループに属する28人の情報提供者は、すでに自分たちの債券購入義務を果たしたと感じていた。しかし、スミスの放送は彼らに対して、自分たちの以前の貢献が十分であったかを再評価させた。彼女は、安定していた自尊心を揺さぶり、自分たちの基準を再検討させる一連のプロセスを促進した。これはどのようにして起こったのだろうか。興味深いのは、先有傾向グループが主に「便利だから」と自分たちの決断を説明していたのに対し、感受性のあるグループは「再び感じた罪悪感」に基づいて動機を語っていた点である。スミスの放送のさまざまな側面が購入すべき債券の適切な量を再定義し、それにより自己非難や不十分さの感覚が生じたと考えられる。
このタイプの購入者は、次のような購入動機を語っていた。
- スミスの努力に感銘を受けた者このタイプは、スミスの「自己犠牲」を繰り返し強調し、彼女の努力の大きさが自分たちの貢献を再評価するきっかけになったと述べている。「彼女が一日中ラジオで頑張っているのに、なぜ私がもう少し努力しないのか」といった思いが強調される。ある者は、「すでに債券を一つ買っていたが、もう少しやるべきだと感じた」と語っている。
- スミスとの感情的関係を重視する者このタイプは、主にスミスへの個人的な献身によって動かされた。「スミスが何かを求めているのなら、私はそれに応えなければならない」といった感情が彼らの行動の根底にある。
- 兵士の犠牲の物語に影響を受けた者このタイプは、戦場での兵士たちの犠牲についての話に触発され、自分たちの行動基準を引き上げた。「彼らがこれほど多くを犠牲にしているのに、なぜ私がもう少し貢献できないのか」と感じたのである。
債券を購入した後、「感受性のある」聴取者の多くは緊張感から解放された。彼らは再び正当な要求を満たしたと感じ、自尊心を取り戻した。「購入後、ようやく眠ることができた。それまでは目を閉じることもできなかった」と語る者もいた。彼らにとって、スミスの言葉ではなく、彼女の行動(献身的な犠牲)が購入を促したのである。
無関心な購入者
スミスから債券を購入した情報提供者の中で、11人は比較的非感情的で、戦時債券に対して無関心な態度を示していた。このうち8人は「無関心層」に属し、キャンペーン期間中に追加の債券を購入する予定があった。
「無関心層」の決断に大きな影響を与えたのは、戦時債券そのものではなく、スミスとの個人的な接触の可能性であった。このカテゴリーの8人のうち5人が、スミスと直接話すことを期待して電話をかけていたのに対し、他の購入者55人のうちその動機で行動したのは12人だけであった。債券購入は、感情的な象徴ではなく、有名人との接触という機会であった。
ある情報提供者は次のように語った。
- 「私は電話をかけたが、スミスと話せないことが分かった。でも、後戻りはできなかった。馬鹿にされるような気がした。まあ、もともと買うつもりだったから、それでもよかった。」
先有傾向なし層
「先有傾向なし層」の説得において主な要因となったのは、スミスへの感情的なつながりであった。債券購入を約束した3人はスミスに好意的な感情を持っていたのに対し、6人の非購入者は彼女に否定的な感情を抱いていた。
購入者はスミスの放送を積極的に聞き続け、説得の機会を得た。一方、非購入者はスミスの放送を避ける傾向があり、影響を受ける機会が少なかった。
- 「私は彼女の放送を聞かないようにした。他の番組を選んだ。」
以上のように、聴取者にとって異なる先有傾向が、スミスの訴えに対して異なる反応を引き起こし、それが債券購入の意思決定に対しても異なる影響を及ぼしたのである。
マートンのマスメディア・キャンペーン効果研究は、先有傾向の分析を通じて、その後の「限定効果説」にも通じる新たな視点を提供する業績として評価することができるだろう。
第4章 「24時間テレビ」の効果分析(三上, 1987)
「24時間テレビー愛は地球を救う」は、日本テレビの開局25周年記念番組として1978年8月25日から26日にかけて、日本テレビ放送網の全国ネットを通じて、24時間半連続で放送されたチャリティ・キャンペーン番組である。そして、一般視聴者や賛助団体、企業から合計11億9011万円余の寄金を集めるという大きな成果を上げた。その後、この番組は毎年8月下旬の土曜から日曜にかけて、恒例のスペシャル番組として放送されるようになり、2024年までに47回の放送を行なっている。1986年までの寄金総額は約80億円にのぼっている(その後の寄金総額は不明)。
(24時間テレビ 2007年 サライ誕生から15年 : YouTubeより)
24時間テレビの企画意図
もともと、このキャンペーン番組の制作意図は、次の4つの点にあったと考えられる。その一つは、福祉問題に関する知識と関心を高めることである。つまり、視聴者に福祉問題についての知識を提供し、また福祉の現状を訴えることにより、福祉に関する人びとの意識を高めようという意図がみられる。第2は、テレビ映像の同時性と参加性をいかしたチャリティ・キャンペーンを展開することにより、視聴者や賛同団体から寄金を集め、その寄付金で巡回お風呂カー、障害者のためのリフト付きバス、電動車椅子を購入し、福祉施設に寄贈することである。つまり、テレビ局自らがチャリティ活動を行い、福祉の向上に貢献しようとするものである。第3には、以上のキャンペーンを通じて日本テレビならびに系列局のイメージアップをはかることである。もともと、この番組の企画は日本テレビ開局25周年記念のイベントとして立てられたものであり、いわば日本テレビの企業イメージを向上させるための広報活動の一環としても位置づけられていた。第4の意図は、視聴者のテレビ離れが進んでいる状況の中で、「テレソン」というイベント性の強いスペシャル番組によって新たな視聴者層を開拓し、視聴率アップをはかることにあったと思われる。
以上4つの制作意図のうち、最初の二つは番組企画者が正面から打ちだしている顕在的な目的である。これに対し、あとの二つは、表にはっきりとは出していないが送り手側に潜在的な意図としてあったと推測されるものである。前者がタテマエとしての制作意図を表わしているとすれば、後者はホンネの部分を表わしていると考えることもできょう。「24時間テレビ」の効果を考える場合には、以上4つの頭在的および潜在的な制作意図を含めて評価することが必要だろう。
調査の概要
本報告のもとになった調査データは、東京大学新聞研究所「放送キャンペーン研究会」(代表:広瀬英彦・東洋大学教授)が「24時間テレビ2」(1979年)、「24時間テレビ3」(1980年)の視聴者を対象として行なったアンケート調査の結果得られたものである。研究会のメンバーは、広瀬英彦、広井脩、川本勝、三上俊治、水野博介、竹下俊郎、波賀稔の7名である。
1.内容分析:
第2回「24時間テレビ」について、24時間30分の放送内容を分析した。マートン(1946)と同様の分類カテゴリーを用いて、テーマ分析を行なった結果、「参加のテーマ」が47.6%と最も多く、以下、「犠牲のテーマ」(21.2%)、「簡便さのテーマ」(10.9%)、「家族のテーマ」(9.7%)、「個人的テーマ」(3.5%)、「競争のテーマ」(1.%)と続いていた(廣井, 1987)。
2. 都民意識調査
1979年の調査(以下「第一次調査」と呼ぶ)は、 東京23区の電話帳から二段階抽出法により744世帯を無作為抽出し、その中で「24時間テレビ2」を見た380人を対象として行なった。回収数は277である。また、1980年の調査(以下「第二次調査」と呼ぶ)は、「24時間テレビ3」の放送時間中に日本テレビに電話で寄金を申し込んだ人の「受付名簿」をサンプリング台帳として、年代別の層化抽出法により選んだ1500人を対象として実施した。回収数は506である。
24時間テレビの視聴者像
ニールセン潤査(関東地区)によれば、「24時間テレビ」の視聴率は、1978年の第1回放送時には、最高28.4%、24時間平均15.7%という高い数字を記録した。第2回放送(1979年)ではやや視聴率は低下したが、それでも、最高25.7%、24時間平均では11.8%であり、これは通常編成時の一日平均視聴率7.5%をかなり上回っている。つまり、数字的に見る限り、「24時間テレビ」制作者たちの潜在的意図の一つである視聴率向上という目標はある程度達成されたといえよう。なお、1986年の同番組視聴率は平均9.7%だった。
都民意識調査のデータを分析したところ、この番組の長時間視聴者が10代に特に多いことがわかった。10代の実に7割までがこの番組を「3時間以上見た」と答えており、また「6時間以上見た」という人も3割に達している。20代以上の人びとの過半数が3時間未満であるのとは対照的な数字である。また、第二次調査の結果をみると、10代の中でも特に12~14歳のローティン層がもっとも長くこの番組を見ていたことがわかる。つまり、「24時間テレビ」を長時間見ることによって、番組全体の視聴率向上にもっとも貢献したのは10代の青少年、とくに14歳以下の小・中学生だったということが、この調査結果から推測されるわけである。
年齢以外の要因について分析してみると、「24時間テレビ」を長時間見ていたのは、テレビが好きな人、NHKよりも民放の方が好きな人、前の年の「24時間テレビ」をみた人、この番組を見ようと前もって決めていた人、などであった。つまり、テレビ特に民放に対してふだんから好意的な態度をもち、番組の始まる以前から視聴経験ないし準備という形で視聴への先有傾向を形成していたことが、「24時間テレビ」を長時間見るための素地となっていたのである。
番組それ自体の構造もまた、長時間視聴を促す大きな要因となっていた。つまり、この番組が、24時間全体を通して一つのまとまった「スペシャル・イベント」あるいは「マラソン放送」としての構造を備えていた、という点を見逃すことはできない。グランド・プロローグショーに始まり、グランド・フィナーレで締めくくる番組構成や、全体を通して「LIVE TOGETHER」などの統一的テーマを掲げ、萩本欽一、徳光和夫、ピンクレディ、タモリなどのタレントたちが「24時間テレビ」のマーク入りのお揃いのTシャツを着て繰り返し登場し、寄金の呼びかけを行ない、電話受付シーン、電光表示板による寄金額の発表などが一定時間をおいて繰り返された、という点などを考えると、この番組は長時間連続の「マラソン放送」という完結したスペシャル番組としての性格を持っていたことは明らかであろう。
このような連続性を持った番組構造が、一部の視聴者、特に小・中学生たちに対して長時間視聴を促すような効果を与えたことは十分に想像できる。たとえば、われわれの行なったグループインタビューの中で、ある回答者は次のような感想を述べていた。「なんだかテレビ局の催眠術にかかったような気になった。もう寝よう、もう寝ようと思っていても、次の場面で何が出てくるか興味があった。途中でつまらないと思ったけれど、その時には目が画面にクギづけになっていた」。これは、マートンの分析した、CBSの「戦時債券購入キャンペーン」のマラソン放送の場合と似ている。CBSのキャンペーン放送も、やはり18時間連続した一つのイベントとしての性格をもっており、それが聴取者に継続的な聴取を半ば強制する働きをしていたのである。
寄金行動に及ぼした効果
次に、寄金行動を引き起こすために、直接的あるいは間接的に何らかの影響を与えたり、その基底的な条件となっていると思われる諸要因を整理、検討してみよう。ここでは、性別、年齢などの「寄金者の属性」、福祉への関心度などの「先有傾向」、寄金の動機づけの焦点としての役割を果たした「24時間テレビ」の番組内容、の三つに整理し、それぞれについて検討を加えることにする。
(1) 基金者の属性
「24時間テレビ」の視聴者を対象とした第一次調査によると、番組放送から約一ヵ月後の時点で、電話をかけて寄金を申し込んだ人が約11%、他の方法で寄金した人が約8%、これから寄金する予定と答えた人が約6%、合わせると約27%だった。これを一応「寄金者」と定義し、残りの約73%を「非寄金者」と呼ぶことにしよう。 寄金者と非寄金者を属性別に比較してみると、年齢では有意差が見出されたが、性別、学歴では有意差はみられなかった。年齢別にみると、寄金者の割合がもっとも高いのは10代であり、視聴者の半数近くが寄金の申し込みをしていた。20代になると、寄金者の割合は大幅に減少し、30代、40代ではやや増えるが、50代になると、寄金者は視聴者の約1割にすぎなくなる。つまり、寄金者は、10代を中心とする比較的若い年齢層に多かったということができる。 年齢層ごとに、数量化II類という多変量解析の手法を使って、寄金者と非寄金者とを判別する要因をべてみると、20代以上の場合には、障害者への同情ないし共感が寄金行動と深い関連をもっているのに対し、10代の場合には、タレントや他の寄金者への評価が寄金行動と比較的強い関連性をもっていることがわかった。つまり、10代の視聴者は福祉問題そのものよりも、むしろそれからは外れた周縁的な要素にひかれて寄金行動をとる、という傾向がみられるのである。
(2)先有傾向
マートンは、「戦時債券購入キャンペーン」放送の聴取者がもっていた先有傾向を「一般的態度」(戦時債券に対する好意的な態度)と「特殊な態度」(事前の債券購入意図の有無)とに分け、この二つの軸を組み合わせることによって、四つのタイプに分類した。24時間テレビでも、先有傾向を4つのタイプに分けて分析した。
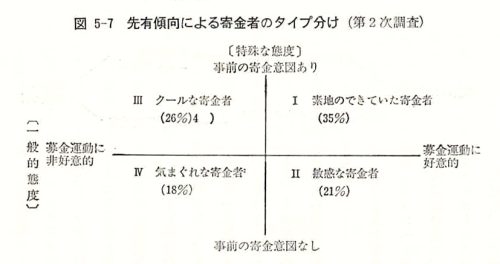
寄金者だけを対象とした第二次調査の結果を用いて、先有傾向によ寄金者のタイプ分けをしてみよう。まず、「福祉をすすめるために一般の人たちから寄付を募ることについての態度」を一般的態度とし、「事前に寄金の意思決定をしていたかどうか」を特殊な態度として質問し、マートンと同じようなタイプ分けをしてみた。各タイプ別に、寄付をしようと決めた理由の分布をみると、タイプI、IIIとタイプII、IVとの間にはっきりした違いがみられる。
テレビで紹介された障害者の姿をみて、寄金への動機づけを生じたのは、タイプIとタイプIIIのグループに比較的多かった。つまり、募金キャンペーンに対する一般的態度のいかんにかかわらず、事前に寄付しようという意図をもっていた人たちは、そうでなかった人に比べて、寄金への動機づけという点で、テレビの福祉関連場面からより大きな影響を受けていたのである。また、「日頃何もしていない」ことに対する罪の意識から、寄金しようという気持になった人の割合も、タイプII、IVに比べると多い。これらの人びとはもともと寄金したいという意図を持っていたのだが、テレビの映像を通して障害者の現状を見たことによって、罪の意識が深まり、あるいは寄金行動への動機づけをいっそう強化された、と考えることができる。これに対して、タイプIIとタイプIVのグループでは、障害者や難民たちのために多くの人びとが献身的に活動しているのを見て、自分も役立ちたいという気持になったり、テレビで大勢の人びとが寄付しているのを見て、自分もという気持になったりした、というように、テレビの中の他者が一種の「行動モデル」になって、「参加」ないし「同調」の欲求を喚起された、という動機づけの傾向が強くみられる。
以上の調査結果は、マートンの分析した戦時債券キャンペーンの場合とはやや異なっている。
マートンの場合には、ケイト・スミスの放送内容にいちばん強く反応したのは、タイプIIのグループであり、タイプIのグループは、すでに戦時債券の購入を前もってきめていたから、スミスによって説得される必要はなかった、としている。そして、タイプの聴取者が、スミスの放送の中でもっとも大きな比重を占めていた「犠牲のテーマ」にもほとんど関心を示さなかったことを、その証拠の一つとしてあげている。さらに、「24時間テレビ」ではタイプI、IIIに比較的多くみられた「罪の意識」は、マートンの事例ではタイプIIにもっとも多くみられた、としている。
このような両者の違いはどこから生じたか、ということは必ずしも明確ではない。戦時債券と福祉キャンペーン募金との間の性格的な相違点もその原因のひとつかもしれない。また聴取者の年代構成の差や、ラジオとテレビというメディアの違いも影響しているかもしれない。さらに、キャンペーンのテーマないしメッセージの違いもあろう。
ただし、ここでは、二つの点を指摘しておきたい。一つは、マートンがタイプIIとして分類したグループというのは、「事前に債券購入意図がなかった」としながらも、実は番組の始まる以前に戦時債券をある程度購入していた人達だった、という点である。つまり、彼らはすでに債券を買っていたので、自分たちの義務は一応果たしており、それ以上買う必要性を感じていなかったのである。ところが、ケイト・スミスの放送を聞いているうちに、自分たちの努力がまだまだ不十分だったことを認識し、新たに生じた「罪の意識」から、債券購入への動機づけを生じることになったわけである。このような人びとは、実際には債券購入の意図を潜在的にはある程度持っていた、と推測することもできる。したがって、マートンの分類したタイプIIのグループとタイプIのグループとの間には、実際にはそれ程の差はなかったのかもしれない。
もう一つは、日本とアメリカにおける「罪悪感」のとらえ方の違いである。周知のように、アメリカではキリスト教的な道徳観念が発達しており、日常的な行動の中で絶えず「罪」の意識が喚起され、それによって行動を律している。これに対して、日本では「罪」の意識は精神の深層部分に沈潜しており、日常的な行動を直接コントロールしているのはむしろ「世間体」とか「恥」などと呼ばれるような意識であることが多い。つまり、番組を見た途端に罪の意識に駆り立てられ、寄金行動へ走るというパターンは日本では考えにくい。むしろ、後述するように、潜在的な罪の意識を持っている人は、「24時間テレビ」を見る以前から寄金をしようという意図を持っていた人に比較的多く、彼らは番組のメッセージからもそれほど直接的な影響は受けていないのである。
(3)番組内容の影響
それでは、「24時間テレビ」の番組そのものは、視聴者の寄金行動を動機づける上でどのような直接的影響を及ぼしたのだろうか。第一次調査のデータをもとに、寄金の有無に影響を与える要因の分析をしてみたところ、番組の内容は、視聴者の属性や先有傾向に劣らず大きな寄与要因となっており、番組内容の中でも、障害者やタレントへの評価がとくに重要なファクターになっていることがわかった。年代別にみると、10代と40代以上では出演タレントへの評価が大きなウェイトを占めているのに対し、20代・30代では障害者への共感が寄金行動と深い関連をもっていることがわかった。つまり、出演タレントに好意的なイメージを抱く一•代や四•代以上の人たちや、放送された障害者の姿に強い共感を抱いた20代・30代の人たちは、それ以外の人たちにくらべて寄金行動をとりやすい、という傾向がみられたのである。
次に、番組のどのような内容が寄金行動を動機づける焦点となったのか、という点をさらに詳しく検討してみよう。第二次調査では、「お金を寄付しようという気持を起こさせたのは番組のどんなことがらでしたか」という質問で、あらかじめ用意しておいた18項目の選択肢の中からいくつでも自由に回答してもらった。回答結果を見ると、障害者や難民の現状紹介、チャリティ・コーナーなど、「24時間テレビ」の主要なキャンペーン・メッセージが大半の寄金者にとっても主たる動機づけの焦点となっていたことがわかる。ただし、これを年齢別に見ると、回答率にはかなりの差が見られる。10代は20歳以上に比べて、「タレントが出演したこと」や「リブ・トゥゲザーの訴えかけが行なわれたこと」が寄金の動機になったという回答率が多くなっている。さらに、「寄金者のメッセージが紹介されたこと」という回答は15~19歳のハイティーン層に比較的多くみられた。つまり、タレントや統一スローガンのような、親しみやすくわかりやすいメッセージは、年齢の低いローティーン層にアピールしやすかったのに対し、福祉の現状紹介などのようにある程度以上の理解能力と知識を必要とするメッセージは、年齢のより高い層を引き付けやすい、ということができよう。また、多くのハイティーンの視聴者たちにとって、他の寄金者たちは、いわばテレビの中の「一般化された他者」、つまり一種の行動モデルとしての役割を果たしたと考えられる。この年代は、キャンペーン・メッセージの意味を一応理解することができるし、またある程度の社会性も備えているが、主体的な決定を下せるような自我が必ずしも十分に確立されていないので、他者への同調志向が他の年代層に比べて生じやすい、といえるのかもしれない。
上記の18項目への回答をもとに、数量化III類という多変量解析の一手法を用いて、寄金への動機づけを与えた番組特性のパターン分類を行なってみたところ、図5-10のような結果が得られた(固有値の一軸と二軸の組合せ)。18項目の散らばり具合と、各項目の特性とを考えあわせると、これらは図に示すように大きく三つのグループに分けることができる。

第一のグループは、福祉の現状や障害者・難民などを紹介した場面が寄金の動機づけの焦点となっていたグループであり、「福祉メッセージ型」と呼ぶことができる。第二のグループには、タレントや局のスタッフ、一般市民などがチャリティを呼びかけたり、メッセージを紹介したり、寄付したりする場面が含まれており、これはテレビの登場人物を通したパーソナル・インフルエンスを受けた人びとからなると考えられるので、「テレバイズド・パーソナル・インフルエンス(略してTPI)型」と名付けることができる。このグループは、図のようにさらに二つに分けることができる。すなわち、一つはタレントや局のスダッフに影響されたタイプ、もう一つは一般市民の行動に影響されたタイプである。第三のグループは、テレビを使った大規模なマラソン放送という「24時間テレビ」の性格、だれでも参加でき、毎年放送されることなど、番組それ自体のもつイベント的ないしお祭り的な性格に引かれて寄金をしたというタイプである。したがって、これは「メディア・イベント型」と呼ぶことができよう。このように、視聴者がこの番組をみて寄金をしようという気持になった動機づけの基本的類型は、「福祉メッセージ型」、「テレバイズド・パーソナル・インフルエンス(TPI)型」、「メディア・イベント型」の三つのタイプに分けて考えることができる。
第二次調査では、寄金の理由を直接たずねる設問を作った。番組内容を動機づけの焦点とする前記の三つのタイプと合わせると、寄金行動への動機づけの主要な類型は、①福祉メッセージ型、②TPI型、③メディア・イベント参加型、④免罪符購入型、の4つにまとめることができる。これら4つの動機類型が受け手のどのような属性や先有傾向と結びついているかを、クロス集計表で検討してみると、次のようなことがわかった。 まず、「福祉メッセージ型」に比較的多く見られる特徴は、10代であること、あらかじめ寄金の意図を持っていたこと、前回のテレソンを見て寄金をしていること、友人とのつきあいが多いこと、「24時間テレビ」を長時間みたこと、などである。次に、「TPI型」、つまりテレビの出演者から直接影響を受けた人に見られる特徴は、10代後半であること、「24時間テレビ」を長時間見ていたこと、「24時間テレビ」を見てテレビ局やタレントと一体感を感じたこと、などの点である。「メディア・イベント参加型」の特徴は、事前の寄金意図がなかった人に比較的多いことだけであり、他の属性や先有傾向などと有意な関連性はみられなかった。また、「免罪符購入型」に比較的多く見られる特徴は、20代以上の大人であること、事前に寄金をしようという意図があったことの二点である。
第5章 限定効果論を代表する3つの研究
メディア効果論では、「強力効果説」から「限定効果説」への転換、その後、再び「強力効果説」の復活、という流れが一般に受容されている。このような捉え方は、必ずしも間違っているとは言えないが、例えば、「火星からの侵入」の事例を詳しく再検討すると、「火星からの侵入」放送のインパクトが、必ずしも「強力効果」を裏付けるものではなかったことは、すでに述べたとおりである。むしろ、ラジオがリスナーの行動に及ぼした影響はごく限定的であり、むしろリスナーの発揮した「批判能力」や「情報確認行動」がメディア効果を抑える役割を果たしたという点では、この研究はメディアの限定効果を浮き彫りにするものだったとも言えるのである。
一方、メディアがオーディエンスの「認知」面(現実構成、擬似環境の形成)に及ぼす効果という視点からメディア効果論の展開を振り返ってみると、1920年代のリップマンによる「擬似環境」や「ステレオタイプ」などオーディエンスの頭の中の映像(環境イメージ、小文字の世論)が、主として新聞などのマスメディアによって造成されたものだとする強力効果論は、1950年代以降の現実構成論、議題設定効果、培養効果、沈黙の螺旋理論においても引き継がれており、メディアの認知的効果において「限定効果」「最小効果」に置き換えられた訳ではなかった。それは、ニューメディア時代のSNSにおいても、「フィルターバブル」「エコチェンバー」「フェイクニュース」などがオーディエンスの現実構成を大きく歪める可能性が指摘されているように、メディアの認知面での効果、影響が大きいことを示すものである。
以下では、いわゆる「魔法の弾丸(丸薬)」または「皮下注射針」モデルから「限定効果」モデルへのパラダイム・シフトを決定づけた3つの代表的な研究として、「ピープルズ・チョイス」「パーソナル・インフルエンス」「クラッパーの一般化」を若干検討してみよう。
ピープルズ・チョイス(Lazarsfeld, Berelson and Gaudet)
本書は、ラザースフェルド、ベレルソン、ゴーデットという、コロンビア大学応用社会調査研究所のメンバーが、1940年5月から11月までの7ヶ月間、オハイオ州エリー郡で実施したパネル調査の報告書である。調査の目的は、大統領選挙のキャンペーンが有権者の投票行動に与えた影響、特にマスメディアの果たした役割を実証的に明らかにすることにあった。本調査研究を通じて、以下に述べるような新しい調査手法の発明、メディア効果論における新しい発見が行われた。
パネル調査の開発
マス・コミュニケーションの効果を実証的に研究する上で大きな役割を果たしたのは、ラザースフェルドが開発した「パネル調査」という調査手法だった。パネル調査とは、同一の人々に対して繰り返し面接調査を実施する調査手法である。具体的には、1940年5月にオハイオ州エリー郡を代表する3000人の住民をサンプルとして選び、この名簿から層化抽出法で4組各600名を選び出し、このうち3つのグループに対し、7月に1グループ、8月に1グループ、10月に1グループと面接調査を1回だけ実施し、これらを統制群として用いた。4番目のグループに対しては、5月から11月にかけて毎月1回の面接調査(パネル調査)を実施した。この6ヶ月間には、パネル調査を通じて民主・共和両党の党大会と投票があり、大統領選キャンペーンの影響を長期にわたって測定することが可能であった。調査では、投票意図、各種メディアへの接触状況、回答者の特性、政治意識、対人関係などを詳しく質問した。
パネル調査が本研究で役に立ったのは、次のような点だった。
(1) キャンペーンの期間中に誰が投票意図を変更したのかを見定め、彼らの特性を研究することが可能になった。
(2) ある面接調査から次の面接調査までのキャンペーン情報への接触状況の変化を調べることができる。
(3) 2回の面接調査の間に回答者が投票意図を変更すれば、彼の意見を変化の過程の中で把握できる。
(4) 繰り返し面接調査を行うことによって、キャンペーンの効果を統計的に追跡することができる。例えば、ある面接調査時点では投票意図が未定だったが、その次の面接調査時点には意見を持つようになった人々を研究できる。
マスメディアの補強効果
パネル調査の結果、6ヶ月間の選挙キャンペーンを通じて、マスメディアは投票行動にはほとんど影響を与えない代わりに、有権者の投票意図を「補強する」という効果を及ぼしたことが明らかになった。5月(党大会前)と10月(投票直前)に投票意図を調査した約600人の回答者のうち半数の人々は、選挙運動への数ヶ月にわたる接触によって、それ以前の投票意図を変えなかったことがわかった。ただし、選挙キャンペーンが人々に何の影響も与えなかったわけではなかった。人々にとって、選挙キャンペーンは、投票行動を変える代わりに、以前の決定をずっと持ち続けるという重要な目的に役立ったのである。つまり、有権者に対して、当初の投票意図を補強する効果があったのである。(Lazarsfeld et.al, 1944, 邦訳p.148)。
先有傾向と選択的接触
一方、パネル調査の結果、人々は先有傾向によって、自分のこれまでの立場を支持する情報源を選択する傾向があることがわかった。例えば、民主党支持者よりも共和党支持者にウィルキー候補(共和党)に耳を傾ける者が多く、共和党支持者よりも民主党支持者にルーズヴェルト候補(民主党)の話に耳を傾ける者 が多かった。党派色の強い人ほど、自分の応援する政党のキャンペーンに接触する傾向が強く見られた。他方、キャンペーンの主唱者が標的としていた投票意図未確定の有権者は、その選挙関心の低さゆえに、マスメディアの政治的な内容にはあまり接触しないことがわかった。パネル調査の結果によると、5月から10月の間に一貫した投票意図を持っていた回答者のうち約3分の2が自分の側を支持するプロパガンダに主に接触し他のに対し、他方のプロパガンダに主に接触したのは4分の1未満だった。このような傾向は、「選択的接触」と呼ばれるもので、Lazarsfeldらのパネル調査で初めて明らかにされたものである。マスメディアが改変効果よりも補強効果を強くもたらした原因の一つは、有権者による選択的接触があったと推測される。
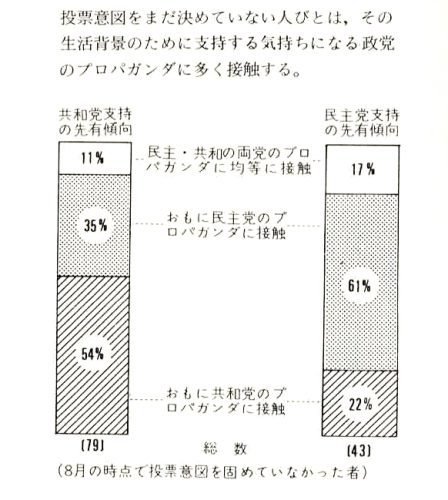
選択的接触(邦訳 p.142)
選択的接触がメディア・キャンペーンの補強効果をもたらすという知見は、これ以降も、いくつかの研究で実証されている。
2段階の流れとオピニオンリーダーの発見
マスメディアの限定効果をさらに明確に示す知見は、投票の意思決定過程における「オピニオン・リーダー」の重要な役割と、「コミュニケーションの2段階の流れ」の発見であり、パーソナルな接触(パーソナル・インフルエンス)は、投票の意思決定において、マスメディアよりも効果的だという発見だった。Lazarsfeldらは、選挙運動の期間中に投票意図を変えた人びとに対し、投票意図を決める上で決定的に影響力を持ったのは何だったかを尋ねたところ、「他の人びと」という回答がいちばん多いという結果を得た。つまり、パーソナルな影響力が一番大きかったのである。このような人びとを、彼らは「オピニオン・リーダー」と呼んだ。しかも、これらのオピニオン・リーダーは、すべての社会階層に広く分散しており、彼らはラジオ、新聞、雑誌などのメディアによく接触していることを発見した。このことから、Lazarsfeldらは、「観念はしばしば、ラジオや印刷物からオピニオン・リーダーに流れ、そしてオピニオン・リーダーからより能動性の低い層に流れる」という仮説を定式化したのであった。この「コミュニケーションの2段階の流れ」仮説は、1955年の『パーソナル・インフルエンス』において、より広い意思決定領域において立証されることになった(Katz & Lazarsfeld, 1955)。
エリー郡調査の問題点
ラザースフェルドらは、投票を一種の消費者の意思決定と捉え、選挙後の調査で、投票行動の決定に影響を与えた情報源や最も重要な情報源について質問した。その結果、3分の2以上が新聞またはラジオを「有益な」情報源として挙げ、半分以下が親戚、仕事の関係者、友人、隣人などの個人的な情報源を挙げた。半数以上がラジオまたは新聞を最も重要な情報源として挙げたが、重要な個人的情報源を挙げたのは4分の1未満だった。このように、メディアの影響を示す証拠が豊富であるにもかかわらず、著者たちは「他人が他人を動かすことが何よりも重要である」と結論づけました。Lazarsfeldらによるこうした結論は、彼らの関心がもっぱら「投票意図」という行動ないし態度のレベルでの影響にあったからだと思われる。実際には、情報取得や認識というではマスメディアは大きな影響を持っていたにかかわらず、Lazarsfeldらはこれを無視し、もっぱら行動面での「限定効果」だけに焦点を当てた可能性がある(Chaffee, and Hochheimer. 1985)。
パーソナル・インフルエンス(Katz & Lazarsfeld)
調査の概要
KatzとLazarsfeldは、「ピープルズチョイス」で発見された「コミュニケーションの2段階の流れ」仮説を検証するために、ごく日常的な意思決定の事例におけるマスメディアの影響とパーソナルの・インフルエンスについて調査研究することにした。ここでのポイントは、意思決定(意見形成)におけるオピニオン・リーダーの析出と、マスメディアの影響力の大きさの調査であった。調査の概要は次のとおりである:
調査地域:アメリカ中西部(イリノイ州)ディケーター
調査対象:各層を代表する800人の女性(16歳以上)
調査方法:面接調査
調査対象領域:買い物、流行、社会的・政治的問題、映画の観覧
質問票の内容:
1. それぞれの領域における意思決定(意見形成)について
2. その決定に際しての影響源の役割について
3. 回答者が考える影響者についての質問
4. 読書、ラジオ聴取習慣について
5. 回答者自身のオピニオン・リーダーシップの測定
6. 回答者の社会的属性(社会的地位、社交性など)
7. 回答者の態度特性
追跡面接:
回答者に対する面接調査の中で質問した「影響源」をもとに、影響者(回答者が何らかの意思決定を行なった際に、彼らが影響を受けた相手)つまりオピニオン・リーダーに対して、追跡面接を実施した。
オピニオン・リーダーの特性、役割
(1) 日用品の買い物行動におけるリーダー
調査の結果、買い物リーダーは、測定した3つの社会地位レベルのすべてにほぼ均等な割合で出現しているということがわかった。追跡面接の結果を見ても、買い物という行動場面での影響の授受が、地位を異にした女性の間で行われることは少なく、影響の方向は上昇的な場合も下降的な場合も同じようにあることがわかった。年齢に関しては、年長層から若年層へという下降的な影響の流れが宇川れる。
(2) 流行に関するリーダー
調査対象者の約3分の2は、化粧品や衣服などの流行に関して変更したことがあると回答した。そして、彼女たちの多くは、流行の変更に際して、オピニオンリーダーからのパーソナルな影響を受けていたことがわかった。流行のリーダーシップは、生活歴のタイプによって異なることがわかった。リーダーシップの大きさは、未婚女性>小世帯主婦>大世帯主婦>年配の夫人という順で減少する傾向が見られた。また、リーダーシップの大きい人ほど、流行に対する関心が高いことも明らかになった。さらに、社交性が高まるほど、流行のリーダーシップも強くなるという関連が見られた。
(3)社会的・政治的問題をめぐるリーダー
本調査における「社会的・政治的問題のリーダー」とは、「現在社会的・政治的領域で起こっている事柄をよく知っており、かつ、他の女性たちからそれについての情報や意見の相談を受けることの多い女性」と定義されている。調査の結果、この領域でのオピニオン・リーダーの数は非常に少ないということが明らかになった。また、社会的・政治的問題に関するリーダーシップは、社会的地位の高い女性ほど多いという結果が得られた。これは、買い物リーダー、流行リーダーとは異なる結果である。
(4) 映画観覧におけるリーダー
最後に、映画観覧におけるオピニオンリーダーの特性を見ると、映画のリーダーシップは未婚女性に集中する傾向が見られた。年齢が若いこと、および未婚であることが、映画館に足を運び、さらには映画のリーダーになるチャンスと結びついている一方、それぞれの年齢層グループ内部において、しばしば映画を見に行く人はあまり行かない人に比べてリーダーになりやすいことがわかった。映画を見に行くという行動は、多くの場合、誰かと一緒に映画を見に行くということである。したがって、この領域における影響の流れの多くは、一緒に映画を見に行く同年齢層の仲間たちの間で生じていると考えられる。
コミュニケーションの2段の流れ
すでに見たように、『ピープルズ・チョイス』の研究において、「コミュニケーションの2段階の流れ」仮説が初めて定式化された。すなわち、「いろいろな観念はラジオや印刷物からオピニオン・リーダーに流れ、さらにオピニオン・リーダーから活動性の比較的少ない人びとに流れることが多い」というものである。しかし、この仮説は選挙運動(政治コミュニケーション)という単一の分野で立証されたに過ぎない。そこで、ディケーター調査では、この仮説が他のさまざまな分野でも成り立つものかどうかを検証することになった。具体的には、(1)「ピープルズ・チョイス」の場合と同様に、オピニオン・リーダーは、ラジオ、新聞、雑誌などのメディアによく接触しているか、(2) オピニオン・リーダーが非リーダーよりもマス・メディアから強く影響を受けているかどうか、(3) オピニオン・リーダーはすべての社会階層に広く分散しており、フォロワーに対して水平的な影響を及ぼしているかどうか、という点をデータによって検証したのである。
まず、雑誌への接触度について見ると、どの分野においても、オピニオン・リーダーは非リーダーよりも多くの雑誌を読んでおり、またよく本を読んでいることがわかった。このような関係は学歴を統制しても変わらなかった。また、オピニオン・リーダーは非リーダーよりも全国雑誌(コスモポリタン的な内容)を読む比率が高いこともわかった。次に、流行を変改した人に、影響源を聞いたところ、オピニオン・リーダーは非リーダーに比べ、マス・メディアから影響を受けたと答える割合が高かった。ただし、買い物、映画観覧、社会的・政治的問題の領域については、このような関連は見られなかった。

パーソナル・インフルエンス(邦訳, p.178)
このように、すべての領域ではないが、「コミュニケーションの2段階の流れ」仮説がある程度立証されたということができる。
クラッパーの一般化(1960年)
1960年に刊行された、J. T. Klapperの著書『マス・コミュニケーションの効果』は、それまでのマスメディア効果論の成果を総合的に検討し、いわゆる「限定効果論」として総括したもので、マス・コミュニケーション効果論の歴史において、重要な業績として評価されるものだった。1920年代に始まる初期のマスメディア効果論を「皮下注射」アプローチとして位置付け、1940年以降の実証的な効果研究を「現象論」的アプローチとして対比させ、限定効果を強調する現象論的アプローチが今後のマス・コミュニケーション研究において主流になると論じた (Klapper, 1960)。
Klapperによれば、これまでの研究を総括すると、説得的マス・コミュニケーションは、受け手を変改させるよりも、補強(reinforcement)の作用因として機能することが多いという。すなわち、受け手に対する支配的な効果として見出されるのは、補強ないし意見の固定性である。第二に、一般的な効果として見られるのは、意見の強化といった小さな変化である。そして、変改という大きな影響は滅多に見られないとしている。このようなマスメディアの補強効果が支配的だとする根拠として、Klapperは、1940年行われたLazarsfeldらのエリー郡での投票研究(Lazsfeld et. al, 1944)と、1948年に行われたBerelsonらのエルミラ郡での投票研究 (Berelson et. al, 1954)を挙げている。例えば、エルミラ郡でのパネル調査では、有権者に対して「補強効果」が最も多く見られたと、次のように述べている。
補強、修正、そして変改は1940年の研究と同じ割合で生じたことが発見された。六月と八月の結果を対比すると、760人の回答者パネルの66%は、六月の政党支持の立場を維持していた。17%はある政党への支持から「中立」、あるいは「中立」からある政党への支持とゆれ動いた。そして実際に変改を示したものはわずか八%にすぎなかった。選挙運動期間の後半にあたる8月と10月のあいだでは、補強の割合はほとんど変らず(68%)、変改の割合は低下した(3%)。さらに、より多く選挙運動に接触したものは、その接触に関して、より選択的であること、そして選挙運動への接触の度合がそれほど高くない人よりも、変改を経験する傾向が少ないことが発見された。ベレルソン、ラザースフェルドおよびマックフィーは、いく分か控え目に、「接触は変改を作り出すよりも結晶と補強の方向に働く」と結論づけた。(Klapper, 1960, 邦訳p.34)
このように、マス・コミュニケーションの影響力が変改ではなく補強の方向に働く原因として、次の5つの媒介的諸要因を指摘した。
(1) 先有傾向 (predispositions)および選択的接触 (selective exposure)、選択的知覚 (selective perception)、選択的記憶 (selective retention)の過程
(2) 個々の受け手が属している集団と集団規範
(3) コミュニケーションの内容の個人相互間の伝播
(4) オピニオン・リーダーシップの行使
(5) 自由企業社会におけるマスメディアの性質
このうち、Klapperの業績として注目される点として、(1)と(2)について説明を加えておきたい。
先有傾向と選択的接触
人々の既存の意見と関心、より一般的には、彼らの先有傾向はマス・コミュニケーションに対する彼らの行動と、このコミュニケーションが彼らに与える効果に対して、非常に大きな影響を与えることが明らかになった。一般に、人々は彼らの既存の態度と関心に一致したマス・コミュニケーションに接触する傾向がある。逆に、既存の態度や関心に沿わないコミュニケーションを、彼らは避ける。また、共鳴しない内容に接触せざるをえない場合には、彼らはしばしばその内容を知覚しないか、あるいは彼らの既存の見解に適合するように内容を作り直し、解釈するか(選択的知覚)、あるいは彼らが共鳴する内容を忘れる度合いよりももっと簡単に忘れる(選択的記憶)。選択的接触は、1940年のLazarsfeldらの投票調査で見られた他、国連のキャンペーンに関するStarとHugの研究においてもはっきりと見られた。この研究によれば、国連に関する情報の増大と国連に対する態度の改善を目的としたメディア・キャンペーンに接触した人々は、もともと国連に関心を持ち、国連を高く評価している人々から主として構成されていたという。
集団と集団規範
KatzとLazarsfeldはによれば、個人の意見や態度と考えられているものは、しばしば彼が属している集団の規範であり、それがマス・コミュニケーションの補強効果の作用因として作用する。人々は自分の意見と適合する意見を持つ集団に所属する傾向があり、集団内討議を通じて、そうした態度や意見は強化される。集団への所属は、補強を促進し、選択的接触を強化することで、変改を阻止する傾向が見られる。集団はまた、対人的な影響力とオピニオン・リーダーシップの行使の舞台を提供することによって、共鳴的なマス・コミュニケーションに潜在する補強力を強化するのに役に立つ。
わら人形としての「魔法の弾丸」「注射針」モデル
このように、Klapperの一般化を通じて、プロパガンダ研究や「火星人襲来パニック」の研究など、マスメディアの及ぼす巨大な影響力に関する研究は、1940年代以降の調査研究で明らかにされた「限定効果」論に対して、「魔法の弾丸(特効薬)」モデルとして、否定されるようになった。
しかし、この「魔法の弾丸」ないし「皮下注射」といった呼称は、メディア効果論において、「限定効果論」の重要性や目新しさを強調するために、袋叩きにするための「標的=わら人形」として捏造されたのではないか、という指摘がその後なされるようになった。例えば、Chaffee and Hochheimer.( 1985)は、「皮下注射針」(hypodermic needle)や「魔法の弾丸(特効薬)」(magic bullet)のイメージは、医療から借用された比喩の誤解であり、後年に限定効果モデルと対比させ、相手の弱点を叩くためにわざと作られた「わら人形」(straw men)に過ぎない、と指摘している。Chaffeeらによると、1920年代後半にペイン基金が後援した若者への映画の影響に関する初期のマスコミ研究は、メディア効果の線形モデルに基づいてはいたものの、その理論の複雑さにおいて非常に洗練されていた。同じ映画でも、子供の年齢、性別、予備的な傾向、知覚、社会環境、過去の経験、親の影響によって子供への影響が異なることが示された。その後の1930年代および1940年代のメディア効果研究者で、メディアの内容が大衆によって直接受け入れられ行動に移されるという単純な直接効果モデルを提案した者は誰もいなかったという。つまり、「魔法の弾丸」モデルとされた1930年代以前の初期の研究においても、マスメディアの直接的な強大効果とは異なる結果が得られていたのである。
Lubken (2008)によれば、「注射器」の比喩を用いて脆弱な聴衆に対するメディアの強力な影響を表現した最も早いマス・コミュニケーション研究者による使用例は、1953年にコロンビア大学の応用社会調査研究所(BASR)のレポートにある。当時、大学院生だったElich Katzがテレビに関する実施委員会のために作成したものである。「誇張すれば、研究が当初持っていたキャンペーンのような説得過程の『モデル』は、巨大な注射器(a giant hypodermic needle)に似ていたと言えるだろう」とカッツは書いている。「非常に最近まで、メディアは全能であり、ほとんどすべての目と耳に影響を与えることができると広く信じられていたのだ。」カッツはそのモデルの構成を次のようにまとめている。「要するに、マス・コミュニケーションのプロセスのモデルはこのようなものだった:一方には強力なマスメディアがあり、メッセージを送り出し、他方には分子化した個人の大衆があり、直接的かつ即座に応答している、間には何も存在しない。」このように、「皮下注射針」モデルという言葉は、1950年代になって、限定効果論の初期の研究者によって作られたものであり、限定効果論の優位性を印象づけるために生み出された「わら人形」であった可能性が高いのである。しかし、「火星人の襲来」パニック研究や、1930年代の主要なマス・コミュニケーション研究に見られるように、初期の研究では、マスメディアの巨大な直接的効果が必ずしも強く主張されたわけではなかったのである。
むしろ、「火星からの侵入」に見られるように、ラジオ聴取者の「批判能力」が情報確認行動を通して、パニック的反応を抑える役割を果たしたという研究結果がしめさえており、これはマスメディアの「限定効果」を明らかにしたものであり、初期のマス・コミュニケーション研究と1940年代以降の研究との間に断絶よりも連続性があった証拠とも考えることができる。
しかしながら、1970年代以降になると、マス・コミュニケーションに関する標準的な教科書において、「魔法の弾丸(特効薬)」や「皮下注射針」という用語が、戦前のマスコミ効果論における「直接的」「巨大」効果の研究を象徴するモデルとして広く紹介されるようになり、アメリカ、日本、その他の国でも既定の事実であるかのように無批判に受け入れられてしまった。これは、後述するように、議題設定機能研究、培養分析、沈黙の螺旋理論、認知バイアス論などが、例えば戦前のLippmannなどの研究をさらに発展させたものであるという事実を隠すことになったと思われる。
第6章 「利用と満足」研究の展開:能動的オーディエンス像の検証
マス・コミュニケーションの実証的な効果研究は、1940年の「ピープルズ・チョイス」から始まったが、同じ頃、問題意識を若干異にする質的な効果研究が、同じ研究グループによって開始された。それが「利用と満足」研究(Uses and Gratification Research:以下、「U&G研究」と略記)と言われるものである。投票行動などキャンペーンの効果研究との違いは次の点にある。つまり、キャンペーン効果研究では、「メディアは人びとの態度や行動をどれだけ変化させることができるか」を問題としていたのに対し、U&G研究では「人びとは生活行動の中でマスメディアをどのように利用し、またマスメディアとの接触によってどのような充足を得ているか」を中心的な主題としている(竹内, 1982)。これは、キャンペーン研究では、マスメディアが主体でオーディエンスはあくまで客体であるのに対し、U&G研究では、オーディエンスが主体として位置付けられ、その能動性に焦点が当てられているという点で決定的な違いが見られるのである。これは効果研究における一種のパラダイム転換だったとも言える。また、オーディエンスの「欲求」「動機」がメディア接触による複合的な「充足」や「機能」と結びつけて研究されることによって、従来の受容理論における「単機能」という前提を超えて、新しい発見がもたらされた点に画期的な意義があった。
1940年代の質的U&G研究
1940年に始まったキャンペーン効果の研究は、世論調査の手法を用いた量的な調査によって行われたのに対し、同じ頃スタートしたU&G研究は、グループインタビューなどの質的調査手法を用いて行われた。その理由について、当時U&G研究を主導したH. Herzogは、「研究対象となる連続ドラマの推定される影響は、ゆっくりと蓄積されて生じるため、これらの影響を社会調査によって特定するのは難しく、継続的な観察と詳細なインタビュー、およびその慎重な解釈を通じて、多様な材料をつなぎ合わせることによって追跡することが可能になる」と述べている(Herzog, 1948)。ここでは、1930年代から1940年代にかけて、Herzogらプリンストン大学ラジオ調査室および後継のコロンビア大学応用社会調査研究所で行われた一連のU&G研究の中から、「プロフェッサークイズ」、「昼間の連続ラジオドラマ」「ストライキ中の新聞利用」に関する事例研究を紹介しておこう。
「プロフェッサークイズ」のU&G研究(Herzog)
(1)調査の概要
実施主体:プリンストン大学ラジオ調査室(およびコロンビア大学応用社会調査研究所)
主たる研究者:Herta Herzog
調査対象:低所得層から選ばれた20歳〜60歳の男女11名
調査方法:クイズ番組のリスナー(男性3名、女性8名)に対する詳細なインタビュー
調査対象ラジオ番組:プロフェッサークイズ。平均聴取率が13%と高く、人気のクイ番組。多くのリスナーから「教育的」だとの評価を得ている番組。
(2)調査の結果
このクイズ番組は、リスナーに対し、4つのアピールを持っていた。
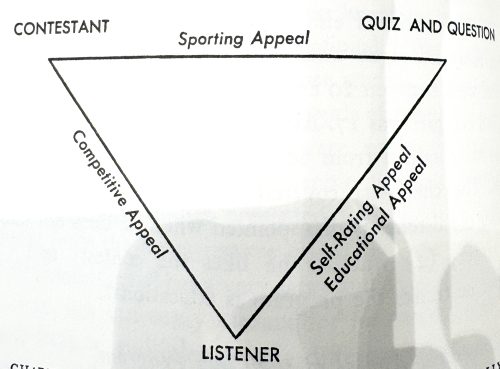
1. 競争のアピール
第1に、番組に出演している回答者とリスナーの間の競争を楽しむという充足があった。第2は、一緒に聞いている共同リスナーとの間で競争を楽しむという充足だった。第3は、一緒に聞いているオーディエンスの前で褒めてもらうことによる自己顕示のアピールである。
2. 教育的アピール
インタビュー対象者のほぼ全員が「教育的要素」の魅力を挙げ、多くの人がそれを最も重要な点として強調した。20人中15人だけが競技そのものが楽しみを増すと答えたが、全員がこの番組を「教育的」と見なしていた。クイズ番組で得られる知識が断片的で多様なものであることを自覚していたが、「クイズ番組から学ぶことは価値がある、知識を増やすことは良いことだ」と感じていた。というのは、クイズ番組を通じて知識の幅を広げることは、日常生活での会話に役立つからだと答えていた。クイズ番組はまた、読書の代替手段としての機能も果たしていることが分かった。
3. 自己評価のアピール
クイズ番組はまた、自分について知る手段として役立っていた。例えば次のような回答があった。「自分がどれだけ愚かなのか分かった」「自分は予想以上に知識があると分かって嬉しくなる」「多くの質問に答えられることに驚くことがよくある」「他の人に勝つことよりも、自分が何を知っているのかを知ることの方が私にとって重要です。自分が思っていた以上に知識があることに気づきます」など。
4. スポーツのアピール
これは、スポーツ番組を見ているときと似た充足タイプである。全体で8人が競技そのものを楽しんでいると答えた。
番組を他人同士の競争として見る場合、主に次の3つの関心が挙げられる。
1)勝ちそうな競技者を選ぶことで、自分が優れた審判であることを示すことができる。
2)勝ちそうな競技者が、自分が勝ってほしいと思う人物像の象徴となる場合がある。
3)競技者が質問に答える際の失敗を楽しむことができる。
「プロフェッサー・クイズ」に関するU&G研究は、一見娯楽的な内容だと思われがちなクイズ番組であっても、リスナーが日常的に引き出している充足は多様であり、なかでも教育的アピールが最も高く、クイズ番組を聴くことがリスナーの知識の幅を広げ、日常の会話場面で役立てられていると同時に、読書の代替手段としての機能も果たしているという意外な知見が得られたという点で、きわめて興味深い結果と言える。
「昼間の連続ラジオドラマ」のU&G研究(Herzog, 1941, 1948)
(1) 調査の概要
実施の主体:コロンビア大学応用社会調査研究所
主たる研究者:Herta Herzog
調査の目的:アメリカで最大の女性聴取者を持つラジオの連続ドラマの影響を詳細に研究すること。
調査方法:ラジオの連続ドラマの内容分析、ドラマのリスナーと非リスナーの比較、リスナーが連続ドラマから得ている充足についての詳細なインタビュー
インタビュー調査:100人の女性リスナーに対する詳細な面接調査
(2)調査の結果
100人の女性リスナーに対する詳細なインタビューの結果、彼らは昼間の連続ドラマから、3種類のタイプの充足を得ていることが分かった。
1. 情緒的解放 (emotional release)
彼らは、ドラマが提供する「泣く機会」を好み、「驚きや、幸せや悲しさ」を楽しんでいた。また、攻撃性を表現する機会も満足感の源になっていた。自分で問題を抱えているリスナーは、「他の人も問題を抱えていることを知って気が楽になる」と述べていた。ドラマの登場人物の悲しみは、リスナー自身の抱える悩みへの補償として受けとめられた。
2. 願望充足としての充足(wishful thinking)
2番目の充足タイプは、リスナーがドラマを通じて代理的な願望充足を得ることだった。あるリスナーは、ドラマの物語に没頭して自分の悩みを忘れるために番組を聴いていた。一方、自分の人生の欠落を補うためや、自身の犯した失敗をドラマでの成功物語によって補償するために聴いている人もいた。例えば、自分の娘が家を出て結婚したり、夫が週5日間家を空けたりする女性は、『ゴールドバーグ一家』や『オニール家』のような幸せな家庭生活を描いたドラマをお気に入りに挙げていた。
3. 生活上の助言と忠告の源泉(日常生活の教科書)としての利用
3番目の充足タイプは、昼間の連続ドラマを日常生活の助言の源として利用するものだった。「これらの番組を聴いていると、自分の人生で何か問題が起こったときにどうすればよいかが分かる」というのが典型的な回答だった。アイオワ州で実施した関連調査によると、教育水準が低い女性ほど、連続ラジオドラマを「役立つ」と考える傾向が強いことが確認された。これは、教育歴の低い女性が「人と親しくなり、影響力を持つ方法」を学ぶ他の手段を持たず、昼間の連続ドラマにより依存している可能性が高いことを裏付けるものだった。具体的に連続ドラマから得られた助言の例を示すと、次のようになる。
・他者とうまく付き合う方法を教えられた
・夫やボーイフレンドを「扱う」方法を教えられた
・子供を「育てる」方法について助けられた
・特定の状況で自分自身をどのように表現すればよいかを学んだ
・自分の老いや戦争に行く息子を受け入れる方法を学んだ
Klapper(1960)は、これまでのマス・コミュニケーションの効果論を集約する中で、Herzogの研究を詳しく紹介しているが、「助言と忠告の源泉としての利用」のことを「日常生活の教科書としての機能」と呼んでいる。的確なネーミングと言える。連続ドラマに関するHerzogのU&G研究の意義は、クイズ番組の研究の場合と同様に、本来は娯楽的、逃避的なコンテンツとして、「情緒的解放」の充足だけがもっぱら注目されていたにもかかわらず、「日常生活の教科書としての機能」という予想外の教育的な充足、機能を発見した点にあったということができる。
「新聞の機能に関するU&G研究」(Berelson, 1949)
(1) 調査の概要
調査の目的:
1945年6月30日土曜日の午後遅く、ニューヨーク市の主要な8つの新聞社の配達員がストライキを開始した。このストライキは2週間以上続き、その期間中、多くのニューヨーカーは通常読んでいる新聞をほとんど読むことができなくなった。彼らは新聞「PM」や一部の小規模で専門的な新聞をニューススタンドで購入したり、いくつかの新聞社の中央オフィスで店頭販売を利用したりすることはできたが、ほとんどの読者が好んで読んでいた新聞は17日間にわたって事実上入手不能だった。このように、新聞を利用できないこと(新聞ロス状態)が、ニューヨーク市民にとってどんな意味を持ち、どのような心理的影響を与えたのか、新聞が果たしている役割、機能を明らかにするために、質的なインタビュー調査を実施した。
主たる研究者:Bernard Berelson
調査方法:
ニューヨーク・マンハッタン地区の市民60名を対象とする詳細なインタビュー調査。新聞ストライキの最初の週の終わりに実施。
(2)調査の結果
インタビューの最初に、新聞がストライキによって読めなくなったことによる喪失感(missing the newspaper)つまり、「新聞ロス」について聞いたところ、多くの回答者は、ストライキによって新聞が読めなくなったことに「喪失感がある」(miss the newspaper)と答えていた。このように、日常生活の中で重要な役割を果たしている新聞について、具体的にどのような役割を果たしているかについて、詳しくインタビューした結果、6つの機能が発見された。
- 公共問題の解釈に役立つ情報入手のため
多くの人が、時事問題に関する解説(社説やコラム)に関心を持っており、それを自分の意見の基準として利用している。
回答例:「現在、詳細な情報が手元にないので、ただ結果だけがわかる状態です。それは、新聞の見出しだけを読んで、記事を追わないのとほとんど同じです。ニュースに至るまでの詳細や説明が懐かしい。背景やニュースに至るまでの展開を知りたい。」 - 日常生活の道具としての利用
一部の人々にとって新聞ストでロス感情を味わった理由は、それが日常生活における直接的な助けとして使われていたためだった。
回答例:多くの人々は、新聞に掲載されているラジオ番組表がないと、ラジオ番組をチェックするのが難しい、あるいは不可能だと感じた。また、映画を見に行こうと思っても、上映作品を調べるために電話したり歩き回ったりするのが面倒だと感じた人もいた。買い物に興味を持つ女性の中には、広告がないことで不便を感じた人もいた。死亡記事を定期的に読んでいた数人の女性は、知り合いが亡くなっても気づかないのではないかと不安を抱いていた。 - 気晴らしとしての利用
新聞は、日常生活の退屈さや単調さからの解放というニーズを満たすのに特に効果的である。その理由は、新聞が「人間味あふれる話題」を豊富に提供する多様性や内容の豊かさを持ち、また手軽に入手できることや低価格だからである。
回答例:「(ストライキ中は)仕事の合間にやることがなくて、ただ編み物をするしかありませんでした。でも、編み物だと新聞を読むことほど気が紛れません。」「どうしていいかわからなくなりました。気が滅入ってしまいました。時間をつぶすために読むものが何もなかったんです。でも、水曜日に新聞を手に入れたら、とても気分が良くなりました。」 - 社会的地位付与の機能
ある回答者たちは、新聞を読むことで社交の場で情報通であるように見せるために利用していた。新聞には会話における交換価値があった。読者は、何が起こったのかを知り、それを仲間に伝えるだけでなく、公共問題に関する議論で使える意見や解釈を新聞に見つけることもできる。このような新聞の利用が、読者の仲間内での地位を高める役割を果たしていたのである。
回答例:「他の人と会話を続けるためには読まなければなりません。ニュースを話題にする場で何も知らないのは恥ずかしいです。」 - 社会的接触のための利用
新聞の人間味あふれる記事、個人向けの相談欄、ゴシップ記事などは、一部の読者にとって単なる日常の悩みやルーティンからの解放以上のものを提供していた。これらは、社会における道徳の指針や他人の私生活への洞察を与えるとともに、それに対する間接的な参加の機会や、有名人との間接的な「個人的接触」機会を提供していた。
回答例:「ドリス・ブレイクのコラム(恋愛相談)を懐かしく思います。彼女のコラムには若い男女の意見が載っていて、それがとてもワクワクします。」「お気に入りのコラムニストを懐かしく思いました。彼らの記事、ニュース、さまざまな人々とのインタビュー、人々との交流が恋しいのです。」 - 「読むこと」自体の効用
Berelsonが発見した、新聞の持つもう一つの機能は、新聞の内容に関係なく、「読むこと」そのものが都市社会においては強く、満足感をもたらす行動になっているということだった。これは、現代ではメディアのもつ「コンサマトリー」な充足として知られる心理的満足のタイプである。これは、Berelsonの調査によって初めて発見された充足タイプであり、その後のU&G研究においても重要なテーマとなっている。こうしたコンサマトリーな充足を得るために、多くの人々は「とにかくなんでも読めればいい」ということで、他の代替手段を利用していた。
回答例:「家にあった古い雑誌を読みました。」「手元にあったもの、雑誌や本を読みました。」「家にある古い雑誌を読み漁りました。」
このように、Berelsonnの新聞ストライキ調査は、「新聞ロス」という思いがけない事態において、新聞が日頃、実に多様な機能を果たしていることを明らかにしたのであった。
テレビ時代の定量的U&G研究
テレビの充足タイポロジー(McQuail, Blumler & Brown, 1972)
1940年代のU&G研究は、主にラジオを中心に行われたが、1950年代に入ると、新たなマスメディアとして、テレビが登場し、1960年代以降のU&G研究はテレビを中心に行われるようになった。テレビ時代のU&G研究についての考察と新しい研究動向については、McQuailらの論文が重要である(McQuail, Blumler & Brown, 1972, 邦訳pp. 20- 57)。
マス・コミュニケーション効果に関する評論的な研究(Klapper, 1960)の中で、Klapperは、テレビの娯楽番組が提供する「現実と一致しない生活と世界の描写」を逃避的内容と認定し、U&G研究の対象を逃避的コンテンツとして考察した。Schramm、Lyle、Parker(1961)の子供とテレビに関する研究でも、子供のテレビ視聴の第一の動機が逃避的なものだと結論づけている:「楽しみを与えられるという受動的な娯楽、それは空想的な世界に住み、スリルに満ちたドラマに代理的に参加し、おもしろい魅力的な人びとと同一化し、現実生活の退屈さから逃避することである」。
しかしながら、テレビ番組が逃避的なコンテンツだけから構成されている訳ではないし、また、逃避的だとみなされているドラマやショー番組でも、それが視聴者(オーディエンス)によって、逃避的な目的や動機だけによって利用されているわけでもない。1940年代に蓄積されたU&G研究は、さまざまなメディアの娯楽的、逃避的コンテンツが、実際には教育的アピール、自己評定的アピールなど、複合的な機能を果たしていることを明らかにした。同じことは、テレビ番組についても言えるのではないか。McQuailらは、このような問題意識に基づいて、実証的、定量的な調査方法によって、視聴者がテレビ番組から得ている充足のタイポロジーを分析したのである。
(1)調査の概要
調査対象のテレビ番組:
連続テレビドラマ「コロネーション・ストリート」、連続ラジオドラマ「デールズ家の人びと」、テレビのクイズ番組、テレビのニュース番組、テレビの連続冒険ドラマ「若者」「セイント」
調査方法:
1. 少数の視聴者に対するグループ・インタビュー
2. インタビューに基づき、番組に対する態度、視聴動機、視聴による充足(視聴者の意見)のリストアップ
3. 視聴者の意見リストを提示して回答してもらう面接調査の実施(70から180人を対象)
4. 調査データのクラスター分析による充足タイプの析出
(2) 調査結果
1. テレビのクイズ番組の充足に関するクラスター分析の結果
視聴者がクイズ番組から得ている充足パターンが2段階の分析によって導出された。第一に、42×42の相関行列によって、すべての意見項目の関連性が説明された。第二に、クラスター分析によって、すべての意見項目は部分集合(クラスター)に再編成された。その結果、4つの主要クラスターが導出されるとともに、2、3の項目による6つの小さなクラスターが分離された。4つの主要クラスター(および命名したラベル)と、それに含まれる主な意見項目は、次のとおりである。
<クラスター1:自己評定のアピール>
・私は自分を専門家と比較することができる
・私は自分が番組に出演してうまく答えているのを想像するのが好きだ
このクラスターに属する視聴者は、クイズの問題に対する自分自身の答えを解答者の答えを比べる異によって、自分の能力を評価する傾向が見られた。また、どのチームが勝者になるかを当てることによって、自分の能力を評価する傾向が見られた。さらに、仮に自分が番組に出演していたらどうするだろうかと想像することによって、自自身を回答者に投影する傾向も見られた。視聴者の属性との関連を見ると、公営住宅に住む労働者階級の人々が、自分自身に関する事柄を学ぶために利用する傾向が見られた。
<クラスター2:社会的相互作用の基礎>
・私は他の人たちとその番組について話し合うのを楽しみにしている
・私は一緒に見ている人たちと競争するのが好きだ
このクラスターは、社会的相互作用に関連しており、クイズ番組が家族で分かち合う関心事を提供するという役割を果たしている。つまり、クイズ番組は、家族全員が回答について一緒に考えることができる。また、視聴者は正しい解答をめぐって競争しあうことができる。さらに、あとでそれを話題にして楽しむこともできる。クイズ番組は、いわば「交換の貨幣」 の機能を果たしているのである。このクラスターにおける高得点グループは、近隣に非常に多くの知人がいると答えた人に多かった。
<クラスター3:興奮のアピール>
・私は接戦に興奮するのが好きだ
・私は自分の心配の種をしばらうの間忘れたい
このクラスターに共通する特徴は、クイズ番組が引き起こす興奮である。クイズ番組は明らかに、だれが勝者になるかを当てたり、自分の予想の結果がどうなるかを判定するという競争そのものがもたらす興奮や、接戦を期待する気持ちを提供していた。これは「プロフェッサークイズ」に関するヘルツォーグのU&G研究で見出された「スポーツのアピール」に相当する。このクラスターで最も得点が高いグループは、社交性の指標が低く、多人数の家族の中で遅く生まれた労働者階級の人たちであった。
<クラスター4:教育的なアピール>
・私は自分が思っていたより多くのことを知っているのに気づく
・私は自分が向上したと感じる
このクラスターでは、クイズ番組の教育的アピールが検出された。クイズは単に思考を刺激するだけではなく、「自己向上」に役立ったり、自分じしんの知的能力への自信を取り戻すためにクイズ番組を利用するという傾向が見られる。これは、ヘルツォーグが「プロフェッサークイズ」から引き出した「教育的アピール」に対応する機能である。このクラスターと最も関連が強い属性は、「教育的背景」(学歴)である。つまり、クイズ番組の教育的アピールは、学校で学んだ経験がごく限られた人々に対して、最も強く作用していたのである。こうした関連は、ヘルツォーグのえた知見とも一致する。
2. 充足タイポロジーの要約から作成された4つのクラスター
上記の結果は、テレビのクイズ番組に関する充足タイポロジーだったが、McQuailらは、他の4つの番組をクラスター分析した結果を含めて、得られた共通の充足タイプ構造を次のようにまとめている。
1. 気晴らし (Diversion)
(a) 日常生活のさまざまな制約からの逃避
(b) 解決しなければならない諸問題の重荷からの逃避
(c) 情緒的な解放
2. 人間関係 (Personal Relationship)
(a) 登場人物への親近感
(b) 社会関係にとっての効用
3 自己確認 (Personal Identity)
(a) 個人についての準拠
(b) 現実への対処法の学習
(c) 価値の強化
4. 環境の監視
これらの充足タイポロジーは、複数のテレビ番組を対象として、事前のグループ・インタビューと、それに基づく面接調査によって得られたデータを多変量解析の手法を用いて分析した結果、統計的に得られたクラスターをもとに析出されたものであるが、そこで得られた充足タイプは、それ以前にラジオや新聞に関して行われたU&G研究の知見と非常によく似ている点は興味深い。本研究をきっかけとして、U&G研究は、テレビを中心とする新たなメディアを対象として、定量的なデータ分析を中心に実施されるようになった。次に紹介する日本の研究も、こうした流れに沿ったものであった。
日本の視聴者参加番組に関するU&G研究(竹内、飽戸、鈴木、田崎、児島、廣井、三上、水野, 1977)
McQuailらによる新たなU&G研究の登場に刺激されて、日本でも、1970年代以降、定量的な手法を使ったU&G研究に対する関心が高まり、テレビ番組の利用と満足に関する本格的な調査研究が行われるようになった。東京大学新聞研究所の竹内郁郎教授を代表とする「マスコミ受容過程研究会」が1974年度放送文化基金の助成を受けて実施したテレビ視聴者参加番組における「利用と満足」の実態に関する調査研究は、その代表的な事例である。研究会の参加メンバーは、竹内郁郎(代表)、飽戸弘、鈴木裕久、田崎篤郎、児島和人、廣井脩、三上俊治、水野博介の8名である。筆者は当時大学院生だったが、本研究会のメンバーとして、初めて実証的メディア効果研究に参加する機会を得た。
本調査研究の目的は、「人びとがテレビ番組を視聴することによっていかなる種類の満足を得ているか、また、日常生活にとってのいかなる効用を見出しているか」を、いくつかの具体的番組について明らかにしようとするものだった。研究のモデルとなったのは、上記のMcQuailらの先行的なU&G研究である。
(1)調査の概要
調査対象のテレビ番組:
1. NHKのど自慢
2. お国自慢にしひがし
3. 家族そろって歌合戦
4. がっちり買いましょう
5. アップダウンクイズ
6. ベルトクイズ Q&Q
7. クイズグランプリ
8. 日本一のおかあさん
9. 新婚さんいらっしゃい
10. 唄子・啓助のおもろい夫婦
調査対象:
静岡県沼津市在住の主婦800名
調査票の構成:
予備的なグループ・インタビュー結果、予想される充足タイプをに関する「充足態様に関するファセット」を作成し、これをもとに調査項目を作成。
調査実施:
1. 主婦6名を対象とするグループ・インタビューを実施
2. 主婦800名を対象とする郵送、訪問回収調査を実施(回収率86.8%)
(2)調査結果
分析の手続き:
各番組ジャンルごとに、、McQuittyの要素連関分析(ELA)、セントロイド法による因子分析、MDS(多次元尺度解析)の代表的手法であるクルスカルの方法とガットマンのSSAを用いて、充足タイポロジーを析出した。
分析結果:
ここでは、クイズ番組(アップダウンクイズ、ベルトクイズ Q&Q、クイズグランプリ)に関する充足タイポロジーだけに絞って、分析結果を紹介する。
まず、要素関連分析(ELA)の結果を見ると、「知識の習得やテスト、頭の訓練などの観点からクイズ番組を受容するクラスター」「クイズ番組によって味わうスリルや緊張感が楽しいという充足タイプ」「日常性からの一時的な逃避を示す項目」「クイズ番組の出場者の勝敗を予想したり、競争のスリルを楽しんだりする充足タイプ」「クイズ番組を視聴しながらそれに回答することが一種の自己確認の機能を果たし、それを通じて満足を味わう充足タイプ」「視聴者がクイズ番組に同一化し、自分もクイズ番組に参加している気分になって楽しむという充足タイプ」といった充足クラスターが検出された。いずれも、従来のU&G研究で得られた充足タイプと重なるところが大きいように思われる。すなわち、「教育的アピール」「日常生活からの逃避(気晴らし)」「競争のアピール」「自己確認」「代理参加」など。
次に、因子分析の結果を見ると、「学習への刺激」(第1因子)、「登場人物との擬似社会的な関係」(第2因子)、「緊張感」(第3因子)、「知的効用」(第4因子)、「競争を通じての自己確認」(第5因子)という5つの因子が析出された。これも、従来のU&G研究の知見と共通する結果と言える。
MDS分析は、異なる因子間の近接性を2次元空間上にマッピングして分析できる多次元尺度解析法である。クイズ番組に関する質問項目と因子間の関係をMDSで解析したところ、学習への刺激(I)が、知的効用(IV)と緊張感(III)とに隣接しており、知的効用は競争を通じての自己確認(V)につながり、緊張感の方は、登場人物との擬似社会的な関係へとつながっていき、最後に、この両者が近接し、I→IV→V →II→III→Iというサイクルをなしているという結果が得られた。このように、因子(充足タイプ)間の相互関係が2次元空間上で納得のいく形で表示されたことは、量的なU&G研究の有効性を示すものといえよう。
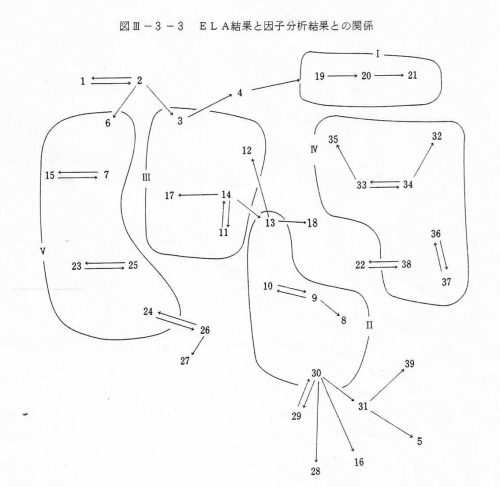
クイズ番組の充足タイプに関するMDS分析の結果(竹内他, 1977, P.127)
インターネット時代のU&G研究
1990年代以降、インターネット、ウェブ、ソーシャルメディアなど、いわゆる「ネット」上のコンテンツが爆発的に増加し、オーディエンスのメディア接触も、マスメディアからネットへとシフトしつつある。それにともなって、マスメディアに関するU&G研究は減少し、ネットメディアに関するU&G研究が増える傾向が見られる。以下では、Webサイト、インターネット、ソーシャルメディアに関する最近のU&G研究の事例を紹介しておきたい。
ウェブサイトの利用と満足(Ferguson and Perse, 2000)
ファーガソンとパース(Ferguson & Perse, 2000)は、インターネットのウェブサイト利用において も、テレビと同じような「利用と満足」の充足パターンがみられるかどうかを検証するために、テレ ビの場合と共通の充足設問を用いた調査を行った。その結果、①娯楽(entertainment)、②暇つぶし (pass time)、③リラクゼーション(relaxation)、④社会的相互作用(social information)に関して、ウェ ブ利用はテレビと同じような機能を果たしていることがわかった。ウェブサイトはとくに 気晴らし的に使われていることがわかった。一方、ウェブ利用は、テレビほどにはリラクゼーション 的な役割を果たしてはいないという結果も得られた。
調査の概要:
1. 調査対象:1997年10月から11月にかけて、アメリカの中西部と東海岸に位置する2つの大学の大学生250名を対象にオンライン調査を実施。
2. 調査方法:調査はHTML形式で作成され、コースのWebページにリンクされた。その後、学生たちはテレビ、ラジオ、印刷メディア、録音音声、ワールド・ワイド・ウェブを含むメディア利用に関する3日間の日記を記録した。日記はコースのWebサイトを通じて課題の一環として提出された。
調査結果:
Webサイトの利用動機に関する27の設問項目を因子分析にかけてみたところ、4つの主要な因子が検出された:
第1因子:娯楽 (Entertainment) : 刺激的な娯楽を求めるためにWWWを利用する
第2因子:暇つぶし(Pass time):空いた時間を埋めるためにWWWを利用する
第3因子:リラックス・逃避(Relaxation - Escape):仕事から離れてリラックスするためにWWWを利用する
第4因子:社会的情報の入手(Social information):学びや会話のきっかけとなる情報を見つけるための利用
本調査は、Webサイトがある程度テレビに対する機能的代替手段として利用されることを示すものと言える。同時に、ウェブの利用動機で「娯楽」が一番多いという知見が得られたが、これはウェブがテレビとある程度類似した利用お次の文章を日本語に訳してください。充足をもたらしていることを示唆している。
PCウェブと携帯ウェブの利用と満足(三上, 2002)
次に紹介するのは、Fergusonnらの調査を踏まえて、日本で行われたU&G研究である。この調査研究は、筆者が日本代表を務める「ワールドインターネットプロジェクト」(WIP)という国際共同研究の一環として実施されたものである。本調査の目的は、PCウェブや携帯ウェブの利用と満足の実態を明らかにすると同時に、テレビの利用 と満足についても同じ設問を用いて調査することによって、在来メディアであるテレビと新しいデジ タルメディアであるインターネットについて、利用と満足の構造がどのように異なるのか、あるいは 共通しているのかを解明することにあった。日本で実施されたインターネットのU&G研究としては最初のものである。
調査の概要:
1. 調査対象:全国の満12 歳以上75 歳以下の男女個人3,500人。
2. 調査期間:2002年10月〜11月
3. 調査方法:調査員による訪問留置訪問回収法
4. 調査項目:
PCウェブ、携帯ウェブ、テレビの3つについて、それぞれ12 項目の充足ないし効用 を設定し、そうした経験が「よくある」から「まったくない」まで4段階で答えてもらった。設定項目は、テレビに関する従来の研究結果やファーガソンとパースの研究などを参考に、「情緒的解放」「気晴らし」「習慣的視聴」「対人関係への効用」「擬似的相互作用(バーチャルリアリティ)」「日常生活か らの逃避」「環境監視(社会情報、趣味情報の入手)」など12 項目を選定した。
調査結果:
PCウェブの充足項目について、回答データを因子分析にかけたところ、次のような結果が得られた。
第1因子:バーチャルな世界での充足
・.情報発信者を親しい友達や相談相手のように感じる
・日常生活上の悩みや問題を解決する助けになる
・日常のわずらわしいことから一時的に逃れることができる
第2因子:娯楽、情緒的解放
・楽しいと感じる
・思わず興奮することがある
・見つけたことを友達と話題にできる
第3因子:社会的情報の入手
・いま世の中で起こっている出来事がわかる
・仕事や勉強に役立つ情報が手に入る
・趣味やレジャーに役立つ情報が手に入る
第4因子:暇つぶし、リラックス
・退屈なときの暇つぶしになる
・つい習慣でアクセスしてしまう
・くつろいだり、リラックスしたりできる
携帯ウェブとテレビについても、それぞれ因子分析した結果、PCウェブとまったく同一の4因子が抽出された。このことは、インターネットのウェブサイト利用に伴う利用と満足の構造が、在来マスメディアであるテレビの場合と共通していることを示すものであり、ウェブサイトの利用行動が、テレビ視聴行動を機能的に代替する可能性を強く示唆するものといえる。また、Fergusonらの調査結果ともかなり共通する因子構造が得られており、文化的な差異を超えたウェブの利用と満足のパターンが見出されたことは興味深い。
ソーシャルメディアのU&G研究 (Whiting and Williams, 2013)
2000年代に入ると、インターネット上でユーザーがコンテンツを作成、共有、交流できるプラットフォームが作られるようになった。これは「ソーシャルメディア」あるいはSNSと呼ばれるようになり、スマートフォンの普及とともに、ウェブと並んで一般個人がもっともよく利用するネットメディアとなった。それに伴い、ソーシャルメディアに関するU&G研究も行われるようになった。次に紹介するのは、そのうちの一つで、2013年に公開された研究である。本研究の目的は、ソーシャルメディアにおける「利用と満足」アプローチの重要性を示すことにあった。
調査の概要:
1. 調査対象:18歳から56歳までの25名(女性52%、男性48%)
2. 調査方法:詳細なインタビューを実施
3. 調査項目:
- なぜソーシャルメディアを利用するのか?
- なぜ友人はソーシャルメディアを利用するのか?
- ソーシャルメディアのどこが楽しいと感じるか?
- ソーシャルメディアをどのくらいの頻度で利用するか?
調査の結果:
得られた質的データについて、U&G研究の先行研究を参考にして、利用と満足のカテゴリーに分類。ディスカッションを重ねて分析した結果、10の利用と満足のテーマが導き出された。数字は、それぞれの充足タイプの回答率を示す。
(1) 社会的交流(Social interaction) 80%
(2) 情報探索(Information seeking) 80%
(3) 暇つぶし(Pass time) 76%
(4) 娯楽(Entertainment) 64%
(5) リラクセーション(Relaxation) 60%
(6) 意見表明(Expression of opinions) 56%
(7) コミュニケーションの効用(Communicatory utility) 56%
(8) 利便性の効用(Convenience utility) 52%
(9) 情報のシェア(Information sharing) 40%
(10) 監視 / 他者についての知識(Surveillance/knowledge about others) 20%
調査の結果は、ソーシャルメディアがユーザーに対して多様な充足を提供していることを示している点で興味深いが、調査の方法が、少数サンプルに対する質的インタビューだけで終わっているので、データとしての信頼性はあまり高くない。今後、ソーシャルメディアをテーマとした定量的なU&G研究が出てくることを期待したい。
「利用と満足」研究 2.0 (Sundar and Limperos, 2013)
これは、Sundar, S. S., & Limperos, A. M.が2013年に発表した論文である。従来のU&G研究では、すべての満足感がユーザー個人のニーズから生まれるという概念に基づいていたが、本研究では、メディア技術の特性(アフォーダンス)がユーザーのニーズを形成し、新しい独特の「満足」を生み出す可能性があると提案している。そして、新しい「満足」の具体例と測定方法についても提案している。
サンダーによれば、伝統的なマスメディアの技術特性と現代のニューメディアの技術特性は大きく変化しており、それはユーザーに多様な行動の可能性を提供している。伝統的なラジオ受信機では操作はダイヤルを回すだけ、テレビではリモコンを使った操作に限られていたが、現代のメディア技術(例: コンピューター)では、ユーザーに多様な行動の可能性を提供している。キーボードは入力を促し、マウスはポイントを示し、ハイパーリンクはクリックを誘発し、ジョイスティックはナビゲーションを可能にし、触覚センサーはスクロールを促す。このような「操作可能な特性」(actionable properties)を、ヒューマン・コンピューター相互作用の研究者ノーマン(Norman, 1999)は「アフォーダンス」(affordances)として概念化しており(Gibson, 1977)、ユーザーとメディアとの相互作用の性質を視覚的に示唆している。これらのアフォーダンスは、インターネット・ユーザーがメディアを新しい方法で体験するだけでなく、ユーザー生成コンテンツ(UGC)を基盤とするインターフェースやアプリケーションの増加により、自らのコンテンツを積極的に生成することも可能にしている。
そこでサンダーは、こうしたメディアをその構成要素であるアフォーダンス(例: インタラクティビティ)に分解し、それぞれから得られる利用と満足感を研究するほうが有益だと主張している。デジタル技術のアフォーダンスは、私たちを個人的な方法でコンテンツと関わるよう誘導することで、単に行動するだけでなく、意味を積極的に構築するよう促すだろう。そこから生まれるユーザーの満足はどのようなもので、どこから由来するものなのだろうか?Katz、Blumler、Gurevitch(1974)によれば、U&G研究の枠組みは次のようなものである。(1) 社会的および心理的起源を持つ (2) ニーズが、(3) 大衆メディアやその他の情報源に対する期待を生み出し、それが (4) メディアの利用パターン(または他の活動への関与)に影響を与え、(5) ニーズの満足感をもたらし、(6) 他の結果を生む。これらの結果の多くは意図されたものではない可能性が高い (P.20)。しかし、充足や満足がユーザーの個人的なニーズだけではなく、利用されるメディア(あるいは情報機器)のアフォーダンス特性からも生じると考えるならば、21世紀の新しいメディアの技術特性とともに大きく変化すると言う予想を立てることが理にかなっていると思われる。その意味では、現代のメディアが提供する数多くのアフォーダンスにより、それらを体系的に分類し、それぞれが特定の満足感にどのように寄与するかを研究する必要性が高まっているといえる。Sundar(2008)のMAINモデルは、デジタルメディアの4つの技術的アフォーダンス(モダリティ、エージェンシー、インタラクティビティ、ナビゲーション性)が心理的に重要な影響を持つことを示しており、これをU&G研究に適用することは有用だろう。
サンダーは、MAINモデルが特定した4つの技術的アフォーダンスに基づいて、新しいメディアの利用者が得る満足感の例を示している。
1. モダリティにもとづく満足
モダリティとは、メディアコンテンツの提示様式(例:音声、画像)のことで、人間の知覚システム(例:聴覚、視覚)の異なる側面に訴求する。インターネットがテキスト、画像、音声、動画といった複数のモダリティでコンテンツを提供できる能力は、それが「マルチメディア」と呼ばれる所以である。これまでの研究によれば、複数のモダリティで情報を提示することは、単なる利便性以上に、知覚的・認知的にも重要であることが示されている。例えば、テキスト情報の処理には多くの認知的労力が必要だが、音声と映像による情報提示は気晴らしになりやすいことが分かっている。
2. エージェンシーにもとづく満足
MAINモデルにおけるエージェンシーのアフォーダンスは、すべての人が情報の発信者または提供者としての役割を担えることを意味する。かつて、ゲートキーピング(情報管理)は特権的な少数者に限定されていたが、今ではインターネット上で誰もがコンテンツのゲートキーパーになれる。たとえば、ブログでは自分のコンテンツを自由に発信したり、他のウェブ上のコンテンツをフィルタリングすることができる。また、YouTubeやFacebookのようなプラットフォームにおけるユーザー生成コンテンツ(UGC)の普及は、送信者と受信者の関係を大きく変えただけでなく、新たな満足感を生み出している。
3. インタラクティビティにもとづく満足
インタラクティビティ(相互作用性)は、メディア内のコンテンツに対してリアルタイムで変更を加えることを可能にするアフォーダンスである。このアフォーダンスは、メディアとの直接的な相互作用を通じて利用者が積極的に関与できるという点で、視聴者の能動性の核心をなすものである。インタラクティブ・メディアの普及に伴い、多くの新たな満足感が生まれる可能性がある。たとえば、ユーザーはより高いレベルの活動性をメディア体験に求め、インターフェースが自分の行動に反応することを期待し、選択肢やコントロールの幅が広がることを望む。また、埋め込まれたハイパーリンクが増え、メディア体験の流れがスムーズになることを期待する。その結果、「活動性」「応答性」「選択」「コントロール」「流れ」といった要素が、インタラクティブメディアにおける次世代の満足感として注目されるだろう。
4. ナビゲーション性にもとづく満足
ナビゲーション性とは、ユーザーがメディア内を移動できるようにするアフォーダンスを指している。インターネットが単なる窓ではなく「空間」として存在しているため、メディアに建築やインテリアデザインの要素が組み込まれ、ナビゲーションがオンラインユーザー体験の重要な側面となっている。インターネット上で1つのサイトから別のサイトへ自由に移動し、さまざまなリンクを「チェックする」という一般的な行動は、「ブラウジング・ヒューリスティック」を引き起こすとされている。こうしたブラウジング行動は重要なプロセス満足感となっており、これが制限されると不満が生じる。つまり、ブラウジングは我々が期待する満足感の1つとなっているのである。
U&G研究の強みは、その柔軟性にある。本論文は、メディアの技術的アフォーダンスが、従来のU&G研究で取り上げられてこなかった21世紀の新しいタイプの「利用と満足」の発見をもたらすと主張するもので、U&G研究の未来に対する一つの明るい展望を示すものとして注目される。
参考文献(第1部)
Berelson, B. (1949).What ‘missing the newspaper’ mean. In P. F. Lazarsfeld & F. N. Stanton (Eds.), Communication research 1948–1949 (pp. 111–129).
New York, NY: Harper.
Campbell, W. Joseph, 2017, Getting it Wrong: Debunking the Greatest Myths in American Journarism. University of California Press.
Chaffee, Steven H., and J. L. Hochheimer. 1985. "The beginnings of political communication research in the United States: Origins of the “limited effects” model. "In The media revolution in America and Western Europe, edited by E. M. Rogers and F. Balle. Norwood, NJ: Ablex Publishing.
Cantril, Hardley, 1940, The Invasion from Mars: A Study in the Psychology of Panic. 邦訳『火星からの侵略:パニックの心理学的研究』高橋祥友訳 金剛出版, 2017
Chaffee, Steven H., and J. L. Hochheimer. 1985. The beginnings of political communication research in the United States: Origins of the “limited effects” model. In The Media Revolution in America and Western Europe, edited by E. M. Rogers and F. Balle. Norwood, NJ: Ablex Publishing
Hayes, Joy Elizabeth, Kathleen Battles, and Wendy Hilton-Morrow (eds.) (2013). War of the Worlds to Social Media: Mediated Communication in Times of Crisis (Mediating American History, 12) New York: Peter Lang.
Herzog, Herta, (1940), Professor Quiz. in Paul F. Lazarsfeld (Ed.), Radio and the Printed Page. Duell, Sloan & Pearce, Inc.
Herzog, Herta. (1941). On borrowed experience: An analysis of listening to daytime sketches. Studies in Philosophy and Social Science, 9 (1), 65–95. (Reprinted in M. Horkheimer (Ed.), Zeitschrift für Sozialforschung/, mit Gesamtregister, München: Deutscher Taschenbuch Verlag, (1980).
Herzog, Herta, 1948, "What Do We Really Know about Day-time Serial Listners?", in Lazarsfeld, Paul F. and Frank N. Stanton (Eds.), Communicaations Research 1948 - 1949. Harper & Brothers: New York.
廣井脩, 1987, 「放送キャンペーンの内容と構造」広瀬英彦編「現代放送キャンペーン論』3章, 学文社
Lazarsfeld, Paul F. , Berelson, Bernard and Gaudet, HazEl, 1944, The Peiple's Choice: How the Voter Makes uo His Mind in a Presidential Campaign. Columbia University Press. 有吉広介他訳, 1967, 『ピープルズ・チョイス ー アメリカ人と大統領選挙』芦書房
Lazarsfeld, Paul F. and Merton, Robert K., 1948, Mass Communication, Popular Taste and Organized Social Action, in Bryson, L. (Ed.), Communication of Ideas, reprinted in Schramm, W. (ed.) , Mass Communications, University of Illinois Press, 1949, 学習院大学社会学研究室訳「マス・コミュニケーション』創元社, 1954.
Katz, Elihu and Lazarsfeld, Paul F. , 1955, Personal Influence. 竹内郁郎訳, 1965『パーソナル・インフルエンス』培風館
Katz, E., Blumler, J.G., and Gurevitch, M., 1974, Ulilization of mass communication by the indiidual. In J.G.Blumler and E. Katz (Eds) , The use of mass communications: Current perspectives on gratification research. Beverly Hills, CA: Sage.
Klapper, Joseph T. , 1960, The Effects of Mass Communication, The Free Press. NHK放送学研究室訳, 1966, NHK放送出版協会
Lubken, Deborah, 2008, Remembering the Strawman: The Travels and Adventures of Hypodermic. in David W. Park & Jefferson Pooley, Eds., The History of Media and Communication Research: Contested Memories. Peter Lang: New York.
McQuail, D., Blumler, J. G., & Brown, J. (1972). The television audience: A revised perspective. In D. McQuail (Ed.), Sociology of mass communication (pp. 135–165). Middlesex: Penguin. 時野谷浩訳, 『マスメディアの受け手分析』
Merton, Robert K. , 1946, Mass Persuasion: The Social Psychology of a War Bond Drive. Greenwood Press. 柳井道夫訳, 桜楓社, 1970
三上俊治, 1987, 「24時間テレビ」の効果分析. 広瀬英彦編『現代放送キャンペーン論』5章, 学文社
三上俊治, 2002, 「インターネットの利用と満足」JWIP編『インターネットの利用動向に関する調査報告 2002』第11章, pp. 112 - 121. (https://jwip.info/report/122/)
三上俊治, 2017, 「火星からの侵入:パニックの社会心理学」再考 (https://itsenior.jp/?p=200)
岡部慶三・三上俊治・水野博介・池田謙一, 1978, 『地震情報の伝達と住民の反応 ーいわゆる「余震情報パニック」(静岡県)に関する事例研究ー』東京大学新聞研究所報告書(http://cidir-db.iii.u-tokyo.ac.jp/hiroi/pdf/report/saigairep/saigairep001.pdf)
Pooley, Jefferson and Michael J. Socorow, 2013, War of the Words: The Invasion from Mars and Its Legacy for Mass Communication Scholarship., in Elizabeth Hayes, Kathleen Battles, and Wendy Hilton-Morrow, (Eds.), War of the Worlds to Social Media. Peter Lang.
Pooley, Jefferson D., and Michael J. Socolow, "Checking Up on The Invasion from Mars:Hadley Cantril, Paul F. Lazarsfeld, and the Makingof a Misremembered Classic." International Journal of Communication 7 (2013), 1920–1948
Quarantelli, E. L., The Nature and Conditions of Panic., American Journal of Sociology 60 (1954), pp. 265-275.
Quarantelli, E. L., 2008, "Conventional Beliefs and Counterintuitive Realities.", University of Delaware Disaster Research Center Article #450.
Rowland, Allison L.. and Peter Simonson, 2014, "The Founding Mother of Communication Research: Toward a History of a Gendered Assemblage", Critical Studies in Communication.
Sundar, S. S., & Limperos, A. M. (2013). Uses and Grats 2.0: New gratifications for new media. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 57(4), 504–525.
佐藤卓己 , 2019, 『流言のメディア史』岩波新書
竹内郁郎, 1976, 「『利用と満足研究』の現況」『現代社会学』3巻1号
竹内郁郎, 1982, 「受容過程の研究」竹内郁郎・児島和人編『現代マス・コミュニケーション論』有斐閣
竹内郁郎・飽戸弘・鈴木裕久・田崎篤郎・児島和人・広井脩・三上俊治・水野博介, 1977, 「テレビ視聴者参加番組における「利用と満足」の実態」『東京大学新聞研究所紀要第25号, pp.92-201.
東京大学新聞研究所編『地震予知と社会的反応』1979
Whiting, Anita and Williams, David, 2013, Why people use social media.
第2部 現実構成論の展開:擬似環境論からフェイクニュースまで
第7章 マスメディアの現実構成機能
リップマンの擬似環境論
「擬似環境」の発見
アメリカの20世紀最高のジャーナリストと言われるウォルター・リップマン (Waltr Lippmann)は、1922年に出版した主著『世論』(Pubic Opinion)の第1章で、擬似環境論を提唱した。 (Lippmann, 1922)。
外界と私たちの頭の中のイメージ
1914年、数人のイギリス人、フランス人、ドイツ人が住んでいた海の中の島がある。その島には電報も届かず、イギリスの郵便船が60日に一度しか来ない。9月にはまだ郵便船は来ておらず、島民たちはガストン・カルメットを銃撃したカイヨー夫人の裁判が近づいているという新聞記事について話していた。9月中旬のある日、コロニー全体がいつも以上に熱心に埠頭に集まり、船長から判決について聞こうとした。そこで彼らは、自分たちがイギリス人やフランス人である者たちが、ドイツ人である者たちと条約の神聖さを守るために戦っていることを、すでに6週間以上も知らずに過ごしていたことを知ったのである。6週間もの奇妙な期間、彼らは友人として振る舞っていたが、実際には敵同士だったのだ。
「しかし、彼らの状況はヨーロッパのほとんどの人々とそう変わらなかった。6週間間違っていたところが、大陸ではその間隔が6日、あるいは6時間だったかもしれない。そこには間隔があった。人々が通常どおり業務を行っていたヨーロッパのイメージは、まもなく自分たちの生活をめちゃくちゃにするヨーロッパとはまったく一致していなかったのだ。誰もがまだ存在しない環境に適応していた時期があった。7月25日まで、世界中で人々は出荷できない商品を作り、輸入できない商品を購入し、キャリアが計画され、事業が検討され、希望が抱かれていた。そのすべてが、既知の世界が実際の世界であるという信念に基づいていたのである。人々はその世界を描写する本を書き、頭の中のイメージを信じていた。そして、その4年後のある木曜日の朝、休戦の知らせが届き、人々は戦争が終わったことに計り知れない安堵を表現した。しかし、実際の休戦が来る5日前には、戦争の終結が祝われたものの、まだ数千人の若者が戦場で命を落としていたのだ。
振り返ってみれば、自分たちが生きている環境を間接的にしか知らないことが見えてくる。その情報が早く届いたり、遅く届いたりすることもあるが、自分たちが正しいと信じるイメージを、それがまるで現実そのものであるかのように扱ってしまうのだ。
現実の環境はあまりにも広大で、あまりにも複雑で、あまりにも一瞬で変わってしまうため、直接知ることは不可能である。我々は、これほどの微妙さ、これほどの多様性、これほど多くの組み合わせや変形に対処する装備を持っていない。しかも、我々はその環境の中で行動しなければならないが、それを扱うためにはより単純なモデルに再構築する必要がある。人びとは、決して見ることも触れることも嗅ぐことも聞くことも記憶することもできない世界の広大な部分を、心で見ることを学んでいる。徐々に、人は手の届かない世界の信頼できるイメージを頭の中に作り上げていくのである。人と環境との間に挿入されているこの環境イメージを『擬似環境』という。その擬似環境に対して人々の行動が反応している。しかし、それが行動である以上、その結果は、行動が刺激を受けた擬似環境の中ではなく、現実の環境の中で作用する。
リップマンは、『世論』より前に出版した「自由とニュース』において、民主主義理論の中核的概念である「万能の市民」像に迫った。それによると、平均的市民は、事実にもとづいて、公共の諸問題に対し理性的判断を下すことができる、とされた。報道機関の仕事は、判断の基準たる事実を客観的に提供することにある (Lippmann, 1917)。しかし、第一次大戦中の自らの宣伝活動の体験を経て、市民に対するこのような楽観的な見方をリップマンは捨て去った。事実なるものがいかに歪曲され抑圧されるかを理解したリップマンは、この歪曲が実は人間の心のなかに本来的に内在しているのだということに気づいた。多くの人びとが外の世界について抱くイメージは、その感情、習性、偏見、ステレオタイプというプリズムを通してつくられているのである。ヴェニスの運河を見て、ある人は虹を見、別の人は水面に浮くごみくずを見る。人びとは見たいものを見、教育や経験によって見るべく訓練されたものを見る。「われわれは、まず見て、そのうえで定義するのではない。まず定義して、それから見るのである」とリップマンは書いている。誰もすべてのことを見ることができない以上、人は自分の経験に見合ったその人なりの現実(擬似環境)を頭の中でつくり出すのである。それによって、さもなければ混沌とした姿としてしかうつらない世界に一定の秩序を発見することができるのである。
「ステレオタイプ」概念の創出
リップマンは、『世論』の中で、擬似環境と並んで、「ステレオタイプ」という言葉を新たに作り出した。人間は現実環境、擬似環境、行動の三角形の中で活動しているが、この三角関係を方向付ける固定観念が、ステレオタイプと呼ばれるものである。ステレオタイプは複雑な現実環境から擬似環境を構成する時に、事実を恣意的に選別するフィルターとして作用する。
われわれは物事の意味を、ただでたらめに決めるのではなく、われわれの文化が命じる「ステレオタイプ」によって決めている。このステレオタイプは認識を限定するが、しかしまた、なくてはならないものである。人間はステレオタイプなしには生きられない。混沌とした世界にあって、これが安心感を与え、また「人間の自己尊厳を保証し、世界に我々自身の価値感覚を投射してくれる」からである。しかし、ステレオタイプによって、いかに見るかばかりでなく、何を見るかが決定されるのであれば、われわれの形づくる意見は、明らかに部分的な真理にしかすぎなくなる。「事実」とされるものは、実は事実ではなく、判断なのだ。この穏やかならざる指摘をリップマンは、次のようにも書き表わしている。「”問題”には常に二つの側面があることは誰しも認める。だが、”事実"とされているものにも二つの側面があるということを、誰も信じようとはしない」(Steel, 1982)
リップマンが発明した「ステレオタイプ」の概念は、現代でも「認知バイアス」の一つとして、学問的にも広く応用されている。その意味では、リップマンは、認知バイアス理論の生みの親といってもいいかもしれない。
リップマンの論考は、実証的・科学的な研究にもとづくものではなかったが、ジャーナリストとしての経験に根差し、深い学識に裏付けられた独創的な理論であり、戦後におけるマスメディアの認知的効果論に大きな影響を与えることになった。
藤竹暁の擬似環境論
リップマンの擬似環境論に独自の解釈を加え、周期性と偏在性を持ったマス・コミュニケーションの働きによる「擬似環境の環境化」という新たな事態について論考を展開したのは、藤竹暁である(藤竹, 1968)。彼は人間の環境を「規定する」力という点に注目してマス・コミュニケーション活動を捉えた。ジャーナリズム活動の成立は、その活動によって提供される擬似環境が、自己転回をとげる過程の成立を意味している。リップマンによって、現実環境と人間との間に介在する「擬似環境」としてとらえられた環境イメージは、ジャーナリズム活動として提示されつづけることによって、(1)消費者にたいしてそれが日々休みなく提示される、という点で、(2)大量の消費者にたいして一様に同じものが提示されるという点で、「擬似」であるという性格を失いはじめ、「擬似環境の環境化」という事態が進行しはじめるとする。ジャーナリズム活動に依存する消費者においては、(1)この活動が周期性をもつことによって、活動の存在それ自体が消費者にとって、習慣化するという事態、(2)消費者は彼が行なうべき環境の確定作業を、ジャーナリズムの活動に全面的に依存するという事態が発生する。このようにして、ジャーナリズム活動は、人間にたいして環境を引きよせる環境把握力を発揮するだけに止まらず、環境を新たに造成するにいたるのである。ジャーナリズム活動が作りあげる擬似環境の環境化は、消費者の側における共有世界の確証の試み(インターパーソナルなコミュニケーション)によって裏付けられて、はじめて社会的な存在が可能となるものである。そしてジャーナリズムの次の活動は、こうして社会的な存在となった擬似環境を環境としてとらえることのなかから生まれる。これが擬似環境の自己転回にほかならない。
人間が外的諸条件との間にある一定の意味をもった関係を作りあげるときに、すなわち環境イメージによって「状況の定義づけ」を下すときに、外的諸条件は人間とある一定の関係を結ぶ(環境となる)ことになるのである。このことは、人間は外的諸条件と関係を結ぶことによって、自らを外的諸条件のなかに「延長」することを意味している。しかし、擬似環境が自己転回の運動を展開し、その結果として、環境の一部として自己を主張するようになるということは、他方では、人間が「現実環境」から疎外されることをも意味している。たしかに、擬似環境の自己転回によって人間は拡大する。しかしながら、人間にとっての環境の一部として、自らを編入することを企てる擬似環境は、その人間が自分の生存との関連においてそれを意味づけたことの結果として、環境化するのではなくて、すでにこの擬似環境は、人間に与えられたときにある一定の意味をもっている存在であることによって、環境化するのである。人間は自分で意味を選ぶ、あるいは意味づけるのではなくて、与えられた意味を学ぶ、あるいは受けとることになる(藤竹, 1968)。
藤竹は、「擬似環境の環境化」の概念を軸に、マス・コミュニケーションやジャーナリズムの活動や効果に関するさまざまな現象や事例を「現実定義」(環境造成、現実構成)の視点から整理し直しており、メディア効果論における重要な業績を次々と生み出すことになった。ただし、藤竹によるジャーナリズムの次の捉え方には、若干問題があるように思われる。
大量生産と大量消費のメカニズムを媒介にして、環境イメージと商品とが「擬似環境」を作りあげ、この「擬似環境」が環境化することによって、もともとの環境を代行するという仕組みが、もっとも組織的かつ日常的に再生産されているのが、ほかならぬジャーナリズムの世界なのである。擬似環境はあらかじめ一義的な意味が確定しているところに特徴がある。環境の主体によって意味が確定されるのでなく、すでに代理的にその意味は確定されているのである。この代理的な意味確定の作業を組織的かつ専門的に行なうのが、ジャーナリズムの活動にほかならない(藤竹, 1968, p.104)
環境の意味づけがジャーナリズムによって一義的に行われるという藤竹の解釈は、能動的なオーディエンスに関する後のメディア効果論では否定されることになった。
「3つの現実」モデル(Adoni & Mane)
マス・メディアの役割について考察したアドーニとメインの論文(Adoni and Mane, 1984)は、シュッツからバーガーとルックマンへと引き継がれた現実構成論をマス・メディアの研究に適用しようとする試みである。彼らは、人びとが社会的相互作用によって構成する現実として、<客観的な社会的現実>(objective social reality)、<シンボリックな社会的現実)(symbolic social reality)、<主観的な社会的現実>(subjective social reality)の3種類を区別している。
まず、「客観的な社会的現実」とは、「厳然たる事実として個人の外部にあって、個人と対立する各観的な世界として経験されるもの」(Adoni and Mane, 1984.p. 325)をいう。これは、疑いをさしはさむ余地のない現実そのものとして受けとめられるもので、シュッツのいう「日常生活の世界」に相当する。
次に、「シンボリックな社会的現実」とは、「芸術、文学、マス・メディアの内容のように、客観的現実についてのシンボリックな表現形態をとるもの」(Adoni and Mane, 1984.p. 326)であり、シンボル体系によって複数のシンボル的な現実が存在する。シュッツのいう超越的現実に近いが、マス・メディアの内容を含めている点で、やや性格を異にしている。さらに、われわれは自分自身のなかに第三の現実、すなわち「主観的現実」を構成している。これは、客観的な現実とそのシンボリックな表現とをインプットとして、個人が意識のなかでつくり上げる独自の世界である。
アドーニらによれば、個人の主観的現実は、<関連性の領域>に沿って組織されており、それは個人の直接的な活動領域であるくいま>とくここ>(日常生活上の直接的経験)からの距離に応じて異なっている。これはもちろん、シュッツのいう<関連性の体系>にほぼ対応する概念である。アドーニらはさらに、バーガーとルックマン(Berger and Luckman, 1966, 邦訳pp.37-38)にならって、関連性の領域を<身近な>(close)領域と<疎遠な>(remote)領域の二つに区分している。個人が対面的な状況で日常的に経験する社会的事象や頻繁に相互作用し合う他者は、身近な>関連性の領域を構成する。一方、<疎遠な>関連性領域は、直接経験することのむずかしい、一般的で抽象度の高い社会的事象から成っている。アドーニらは、疎遠な関連性領域の例として、「世論」や「社会秩序」をあげている。
以上3つの<現実>は、それぞれ<身近な一疎遠な>という軸に沿って構成されるとして、アドーニらはこれを図1のようにモデル化している。
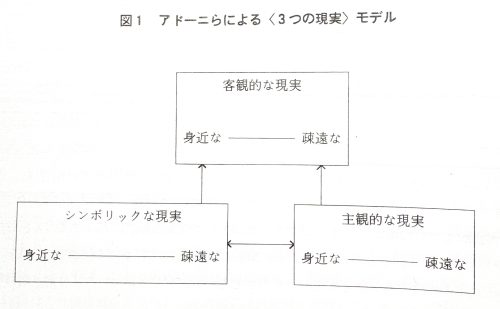
アドーニらは、マス・メディアと社会的現実構成に関する従来の研究を、これら3つの現実の相互関連性という観点から、大きく2つの流れに理している。一つは、シンボリックな現実と他の二つの現実との間の相互作用を別個に分析した研発である。もう一つは、3つの現実の間の相互作用を同時に分析する<全体的アプローチ>(holistic aproach)である。そこで、各々のアプローチについてアドーニらに従って簡単に紹介しておこう。
まず、シンボリックな現実と他の二つの現実との間の相互作用に関する研究であるが、これは(1)シンボリックな現実と客観的な現実の相互作用に関する研発と、(2) シンポリックな現実と主観的現実との間の相互作用に関する研究、の二つに分けられる。前者は、マス・メディアが客観的現実をどのように描写するか、そのような描写が社会の支配的なイデオロギーや価値観や階級構造をどの程度反映し、あるいは強化しているか、といった問題に焦点を当てている。具体的な研究例としてアドーニらがあげているのは、テレビ報道の内容分析を通じて、「マス・メディアが支配的イデオロギーを強化し、現行の社会体制を正当化し、その結果現状維持に貢献している」という結論を導きだす、ネオ・マルクス主義的な研究(Gitlin, 1979;Murdock, 1973;Hall,1977)、テレビのニュースが客観的現実をいかに歪めたものであるかを分析したグラスゴー大学メディア・グループの研究 (Glasgow University Media Group, 1976,1980)、メディアによる現実描写を規定する組織的な条件を追求した研究(Breed, 1955 ; Tunstall, 1971 ;Tuchman, 1978 ;Gans,1980他)、などである。後者は、マス・メディア内容が人びとの現実認知にどの程度影響を与えているか、という問題を扱った研究である。ガーブナーらを中心とする<培養分析>(cultivation analysis)(Gerbner et al., 1976, 1977 b, 1978 1979,1980 a1982,1986)や、<議題設定機能>研究(agenda-setting study)< McCombs and Shaw, 1972 ; Weaver et al., 1981)、<知識ギャップ>仮説(knowledge gap hypothesis)(Tichenor et al, 1970)に関する研究は、いずれもこの系列に属する研究といえよう。
ちなみに、アドーニら自身が提唱する「現実の社会的構成に対する全体的アプローチ」とはどのようなものか、簡単に紹介しておこう。これはひとことでいえば、客観的現実よびシンボリックな現実の分析から主観的な現実の構成までを、体系的かつ一貫した分析枠組にもとづいて実証的に研究しようとするものである。アドーニらによれば、社会過程の中で文化的コミュニケーションの果たす機能を分析したフランクフルト学派の研究は、初期の全体的アプローチの例だという。例えば、アドルノとホルクハイマーによれば、大衆文化の内容は、政治的権力によって支えられた文化産業によって生産されたものであり、その文化産業の役割は、現行の社会を雑持することにある。その結果、これらのシンボル内容において描写された社会的現実は、支配的イデオロギーに沿った歪んだものになりやすい。こうしたシンボル表現の果たす主要な機能は、個人を操作して、社会現象についての<虚偽意識>を醸成することにある、と彼らは指摘している(Adorno and Holkheimer, 1972)。より最近の研究としては、社会システム、メディア組織、個人の社会的現実の受容、の間の相互作用を分析したネオ・マルクス主義的な一連の研究(Gitlin, 1979, 1980 Hall, 1977; Miliband, 1969.Murdock and Golding, 1977:Althusser, 1971)があるが、彼らの分析は歴史的、イデオロギー的な理論構成にもとづいて行われており、思弁的考察に偏っている例が少なくない。一方にうした問題に実証的な方法論でアプローチしたグラスゴー大学メディアグループの研究は、前述したように、客観的現実と記号的現実との間の相互作用を分析するにとどまり、記号環境が個人の主観的現実の構成や行為に及ぼす影響にはほとんど注意を払っていない、とアドーニらは批判している。
客観的現実、シンポリックな現実、主観的現実の間の相互作用について、もっとも精力的に実証的研究を進めてきたのは、何といっても、ガーブナーを中心とする研究グループによる<文化指標>プロジェクト (cultural indicators project)であろう。彼らは、暴力的犯罪に関する統計のような客観的現実に関するデータと、テレビによって構成されたシンポリックな現実とを比較し、さらにこうしたメディア内容が受け手の構成する主観的現実に及ぼす<培養効果>について、実証的調査データに基づいて検証している。ガーブナーらの培養分析は、いくつかの批判すべき点を含んでいるとはいえ、大衆文化に対する全体的アプローチに基づく実証的研究の先駆的事例であるとし、アドーニらはこれを高く評価している。また、ノエル・ノイマンによる<沈黙のらせん的増幅>モデル(Noelle-Neumann, 1974, 1977)は、メディア内容が受け手の<意見の風土>認知に及ぼす長期的影響を実証的に研究しているという点で、ガーブナーらの培養分析に近いということができる。
以上のように、3つの現実の間の相互作用をめぐる従来の諸研究をレビューした上で、アドーニらは、現実の社会的構成におけるマス・メディアの役割をより包括的に理解するためには、ネオ・マルクス主義を基調とするヨーロッパ系統の批判的マスコミ研究とアメリカ系統の実証的メディア効果研究とを統合した<全体的アプローチ>が最も適している、と結論づけている。そして、両者を統合するための理論的基礎として、ドフルールとロキーチの提出した<メディア依存理論>(Ball-Rokeachand DeFleur, 1976)を適用すべきことを提案している。
マッカーサーデーの中継に関する研究(Lang夫妻)
古典的な擬似環境論は、メディアの提示する擬似環境がしばしば現実環境と異なることによって、きまざまな問題を引き起こすことを指摘したが、そうした議論は、リップマンにおけるように、個別的な事例についての記述的な分析をもとに展開されたものであり、科学的な方法論を欠いていた。
1950年代に入ると、客観的現実とメディアの提示する記号的現実との間の違いを実証的に研究する試みがいくつか現われた。その中で、もっとも有名なのは、ラング夫妻による<マッカーサーデー中継>に関する調査研究である(Lang and Lang, 1984,pp: 29-57)。この研究については、論文の日本語訳(Schramm, 1960;邦訳pp.318-338)が出ている他、藤竹(1975)、竹内(1984)などによる詳しい紹介があるので、改めて取り上げることには躊躇を感じないわけにはいかない。しかし、彼らが客観的現実と記号的現実との違いを解明するために用いた方法は、信頼性の面で若干の問題を含んでいたとはいえ、<3つの現実>の間の相互作用を実証的に研究する上で、現在もなお有効性を失っていないと思われるので、ここでは、調査手続きに焦点を当てながら、彼らの研究を紹介しておきたい。
1951年4月11日、アメリカのトルーマン大統領は、朝鮮戦争における政府の方針に従わなかったことを理由に、マッカーサー元帥の米国最高司令官としての地位を解任した。この突然の解任はアメリカ国民を憤激させ、マッカーサー支持の世論がいっせいにわき起こった。4月18日、マッカーサーはサンフランシスコ空港に到着し、続いてワシントンの上下両院合同会議の席上、「老兵は死なず、ただ消え去るのみ(Old soldier fade away・・・)」の一節を含む歴史的な演説を行った。
それから約1週間後の4月26日、シカゴ市の主催で、マッカーサー歓迎の一大イペントが行われた。" Macarthur Day"と呼ばれたこのイベントは、決のような一連のセレモニーから構成されていた。
(1)ミッドウェー空港での歓迎式典
(2)空港から市内までのパレード
(3)パレードの途中、バターン・コレビドール橋での戦没兵士への献花式典
(4) シカゴ目抜通りのパレード
(5)ソルジャー・フィールドでの献迎集会と演説
1951年4月20日「マッカーサー・パレード」のフィルム映像(YouTube)
これら一連のイベントはすべてテレビ中継された。つまり、シカゴ市民は茶の間のテレビで歓迎式典に参加することができたのである。
ちょうどこのイベントが企画されていた頃、シカゴ大学社会学部では、タモツ・シブタニ数授の主催で「群衆行動に関する高等セミナー」が開かれており、ラング夫妻もこのセミナーに参加していた。このイベントに興味をもった夫妻は、マッカーサーデーになにが起こるかについての体系的な調査を提案したところ、参加者の賛同が得られたので、急遽実施ということになったのである。
調査は、バレード現場での参与観察および祝典への参加度を示す統計資料による客観的現実の記録、テレビ中継番組のモニターによる記号的現実の分析、そして、パレード現場で調査員自身および群来の受けた印象とテレビ視職時の印象の記録、という3種類のデータを収集することによって行われた。そのため、31人の学生をイベントの行われる空港やバレードの沿道43ヶ所に派遣し、観察者自身が式典をどう受け取ったか、また他の群来はこの式典をどう受けとめたか、という記録を細かくとらせた。これに加えて、2人の人間が、テレビ中継をモニターし、テレビ式典がどのように放映されたか、また、テレビを通してみた式典が視聴者にどのような印象を与えたかを記録した。これらのデータから、<3つの現実>がマッカーサーデーのイベントにおいてどのように構成されたかをある程度把握することができた、と考えられる。
調査の結果わかったのは、調査員および参加者を通してみた客観的現実と記号的現実との間に著しい食違いがある、ということだった。パレードの現場に集まってきた人びとの多くは、マッカーサーを熱狂的に歓迎する群衆とこれに応えるマッカーサーとの間でドラマチックな一大スペクタルが繰り広げられることを期待していた。しかし、彼らが実際に見たのは、むしろめた雰囲気の群衆であり、これに応えるマッカーサーの姿は、パレードが通過するほんの一解見えるか見えないかの程度であった。
一方、テレビ中継によって再現されたパレードの模様は、人びとがまさに期待していた通りのものだった。そこには、熱狂的に歓迎するシカゴの群衆と、これに笑顔で応えるマッカーサーの姿が生き生きと映し出されていたのである。
それでは、何故このようにパレード現場で調査員が観察した「客観的現実」とテレビに再現された「記号的現実」との間に大きな乖離が生じてしまったのか。この点について、ラング夫妻は、テレビによる中継番組の制作過程における3つの要因を指摘している。
第一は、テレビ制作上の技術的な歪曲である。テレビカメラは、クローズアップの手法を多用して、マッカーサーの表情や歓呼をあげる一部の群衆だけを画面一杯に映し出すことができる。一方、ドラマ的要素に欠ける部分はカットしてしまうことも可能である。このように、たとえ同時中継であっても、現実のごく一部を切り取ったにすぎない画面を組合せることによって、客観的現実とは似て非なる「記号的現実」を構成することができたのである。
第二に、アナウンサーのナレーションによる事件の構成、という要因がある。断片的な映像の組合せに連続性と一貫性を与えるのに、アナウンサーによる解説は重要な役割を果たす。とくに、パレードの治道で実況中継したアナウンサーは、あたかもこの歓迎イベントが全市をあげての歓迎一色の中でドラマチックに展開しているかのように解説してみせたという。例えば、目抜き通りの沿道に立つアナウンサーは、「わが市におけるいまだかつてないもっとも熱狂した群衆です。••・・・・このはりつめた雰囲気を感じていただけると思います。・・・・・群衆のどよめきが聞こえてきます」と解説した。ところが、同じ現場で観察していた調査員の印象はまったく違っていた。「すべての人びとはたしかに緊張していた。しかし、マッカーサーの顔をちらっとでもみた人は少ししかいなかった。彼が通り過ぎてしまってから数秒後、大部分の人たちは肩をすくめ、「これで終わりか」("That's all”)、「こういうことだったのか」(“That was it.”)、「さあ、これからどうしよう」(“What'll we do now?”)といった、きわめてクールな反応を示した」のである。(Lang and Lang, 1984,P.38)。
第三の要因は、「互恵的効果」(reciprocal effect)と彼らが呼んだものである。これは、テレビ制作者と群衆、テレビ制作者と視聴者との相互間で利害と期待が一致した結果、現実を歪める映像がつくられる結果になったという事実をさしている。まず、テレビ制作者は、熱狂的な歓迎のセレモニーを期待する視聴者の意向を敏感に察知し、先程述べた映像技術やナレーションのテクニックを駆使して、群衆が熱狂的にマッカーサーを歓迎したかのような番組を作り上げた。一方、パレードの現場でテレビカメラを向けられた群衆もまた、カメラを意識して自ら熱狂的な歓迎のポーズを演技してみせた。つまり、熱狂的な群菜の映像をとりたいテレビ制作者側と、テレビにカッコよく映りたい群衆との間に、暗黙の共謀関係が成立していたのである。
ラング夫妻はさらに、こうした客観的現実と記号的現実の乖離が受け手のイメージに及ぼす好ましくない影響についても言及している。もし、政治権力者が意図的に自分にとって都合のいい方向に歪んだ記号的現実を構成するならば、メディアによる大家操作の手段としてテレビが悪用される恐れがあることを、彼らは示唆したのである。
ラング夫妻のこの研究は、批判すべきいくつかの問題点を含んでいる。
第一に、バレードの沿道で調査員が観察した記録は、果たして各観的現実を表しているといえるだろうか、という疑問である。31人の調査員がたとえ冷静な目で現場を観察したとしても、彼らの観察し得る範囲はその視野の内に限られている。それを合成したとしても、それは当日の歓迎式典の真の客観的現実像であるとはいえないのではないか。たしかに、視聴者の目はテレビカメラほど現実をゆがめてとらえてはいないだろう。しかし、パレードの全体を見渡せる好位置で観察できるかどうか、という点から見れば、テレビカメラよりもはるかに劣っているに違いない。より正確にいえば、調査員の観察した記録は、沿道の群業と同じ位置とアングルからとらえた現実像だといえる。これをもって客観的現実の指標とすることには問題があろう。もっとも、ラング夫妻は観察記録の妥当性をチェックするために、当日のシカゴ市内の交通量や商店の売上げなどを調べている。その結果、これらの指標はいつもの日とほとんど変化ないことがわかった、という。しかし、これらの指標は、群衆の熱狂度の指標とはいえないから、妥当性を証明したことにはならない。
第二に、主観的現実の測定指標としては、(1)パレードの沿道での調査員の印象、(2)テレビ中継をモニターした記録の受けた印象、が用いられており、これらのデータの比較から、「客観的現実のみから構成された主観的現実」と「記号的現実のみから構成された主観的現実」との間の違いが見出された、としている。しかし、これらのデータはサンプルの代表性という点でかなり問題がある。沿道の群衆にしても、ランダムにサンプルを抽出しているとはいえない。また、主観的現実の測定内容についても、大ざっぱな印象を記録するにとどまり、その内容について体系的な測定は行われていない。
このように、ラング夫妻の調査研究においては、方法論上いくつかの欠陥が含まれてはいたが、同一の対象について構成されたく3つの現実>の間の相互作用を実証的に測定しようと試みた先駆的業績として評価することができよう。
藤竹暁氏は、『テレビメディアの社会力』において、この研究について次のようにコメントしている。
この報告は、オリジナルである「現実」と、テレビによって「再現された現実」とのあいだには、大きな開きのあったことを明らかにしている。テレビが作ったコピーは、最高度の機械技術を駆使したマスメディアによる構成化の産物であった。コピーはオリジナルの忠実な模写なのではなくて、テレビカメラという目を通して、オリジナルに加工をくわえた構成化の所産であった。パレード中継は、テレビ独自の視点で構成化された別の「現実」であった。しかし視聴者は、どうしてそれを「別の」現実として判断することができるであろうか。視聴者が知っている事件は、テレビによって見た事件なのであるから。(中略)現代人は、自分の五感でじかに検証することのできる現実環境において生活しつつ、他方では、こうしたテレビ的現実のなかで生活している。われわれが社会人として感じ、考え、そして行動するとき、テレビ的現実(マスコミ的現実)がたえずその姿をあらわし、影響を与えている。この膨大な象徴的環境の存在を抜きにしては現代人は社会的に生きてゆけないとすれば、現代人にとってはテレビ的現実(さらにはマスコミ的現実)の比重は重くなり、現実環境の比重は逆に軽くなってしまうであろう。現代人は、マスコミによって「構成化された事件」を環境として生きているのである。
社会現象の認知的歪みに及ぼすテレビの影響(TVメディア・バイアス 水野)
本研究は、「コミュニケーション分析研究会」(三上俊治(代表),村松泰子、水野博介、仲田誠、竹下後郎,橋元良明,後藤将之、大畑裕)が、東京大学新聞研究所内研究費の助成を受けて行なった社会的現実の認識に及ぼすテレビの影響に関する実証的調査研究である(三上、水野、橋元 1989)。
調査の概要:
自然な視職状況におけるテレビの短期的効果を測定するのに適した「フィールド実験的調査」の手法を新たに開発し、1987年10月と1988年5月の2回にわたって実施した。具体的には、大学での授業中に、対象者である学生に対し、その週の指定した日時のニュース番組を必ず見るように指示し、翌週の授業時間にアンケート調査を実施するというものである。指定したニュースはVTRで録画し、その内容をもとに、それに関連した社会的現実の認知を測定するための設問を作成した。
調査の結果:
以下では、「テレビは社会現象の認知をどのように歪めるか」 というテーマで研究した水野博介の論文(水野, 1989)を紹介する。
仮説群:
本研究は、情報メディアは、人々がそこから情報を得れば得るほど、人々の知識を増し,社会現象の正確な認識に寄与するだろうという常識に反して、テレビに頼って世の中を知れば知るほど、ある種の歪みをもった現実認識をもってしまうのではないか、という問題意識に立って、一連の仮説を提示し、調査データによって実証を試みたものである。ここでは、メッセージにおけるバイアスのうち、メディアの特性に基づくものを「メディア・バイアス」と呼ぶ。特に、テレビによって現実を知る傾向のある(テレビ依存の強い)人々には、ての世の中が「変化」や「極端な事柄」に満ちたものと見え、また、「表層的」で「ステレオタイプ的」な単純化された構造をもつものと見える傾向がある。これが、ことで言う「TVメディア・バイアスの効果」である。具体的には、8つの仮説を立てている。
(1)「表層現象化(負のアジェンダ・セッティング機能)」仮説
テレビは,言うまでもなく、人々の視覚に訴えるメディアであるから、何らかの現象について伝える場合でも,映像として写しやすい部分をとりあげ、そうでない部分についてはとりあげないというバイアスがどうしても生じる。そして、映像で写しやすい部分というのは、どうしても現象の表面的な部分になりがちである。その結果、テレビを通じてある現象を認知する人々は、その現象について考える際に、表面的な目に見える部分にもとづいて判断する傾向があり、いわば表層的な現象に物事を矮小化する傾きがある。
(2) 「変化バイアス(加速視) 」仮説
テレビは、社会的な「変化」について、最も速く情報を送るメディアである。これは単に情報をリアルタイムで送ることができるという以上に、世の中のいつも変わらぬ様相よりは、変化の最先端(最新情報)を迅速にとらえて写しだす。という意味である。このようなメディアであるテレビに依存している人々は、逆にテレビが伝えてくる情報に対し、そのような特性をもっているととを無意識に期待し、そのような特性をもつ現象だと認知する傾向が強いのではないだろうか。
(3) 「特異現象化(カルガモ効果)」仮説
テレビは、世の中の珍しい事象や現象をとりあげることの多いメディアである。人々にはあまり知られていないが、しかし実際にはそれほど珍しくもない現象でも,一旦テレビがとりあげると、それがいかにも珍しい特異な現象と見えることがある。この数年間、初夏にくり返されてきた「カルガモ騒動」は、まさにその好例である。カルガモにふだん接していない都会の人間にとっては、テレビ(やその他のメディア)を通じて見るその鳥は、まさに珍鳥に近く感じられたであろう。
(「六本木にカルガモ親子」 ANNニュース 2020.7.25)
(4) 「普遍現象化(過大視効果)」仮説
逆に、人々が一応知っている比較的ありふれた現象がテレビで多くとりあげられると、それは社会の窓(縮図)としてのテレビに写しだされているということから、普遍的な現象として、実際以上に多く生じていると見なされることがある。
(5)「中心化(認知的再編Aタイプ)」仮説
これまで、あまりとりあげられなかった事象や人物でも,それが新たに頻繁にとりあげられると、しだいに認知の中心的な位置を占め、その結果、認知構造を再編するだろう。たとえば、新しい首相やタレントについて、このような効果が生じうる。
(6) 「脱中心化(認知的再編Bタイプ)」仮説
逆に、これまで、認知の中心にあったものでも,違う角度からとりあげられた場合に、それが客観化され相対化されて、中心的な位置からはずれるかもしれない。その結果,やはり認知構造の再編が生じるだろう。
(7) 「ステレオタイプ補強」効果
テレビは、大多数の人々にその場で理解される情報を提供するという機能特性から、しばしば「ステレオタイプ」に沿った現実描写を行いやすい。また、受け手もそれに対応して、情報を「ステレオタイプ」に沿って受け取る傾向がある。
(8) 「行動刺激」効果
テレビによる認知は、単に現象を認識させるだけで人々を満足させない。却って、テレビに依存すればするほど、テレビで見た新しい現象(変化の先端)に触れるよう刺激されよう。つまり、認知は認知にとどまらず、行動をも刺教し、喚起すると考えうる。
仮説の検証:
(1) 表層現象化」仮説
テレビ依存が中程度以上の人々で,総裁選出の手続きを問題点として指摘した人は非常に少なかった。仮説は支持された。
(2) 「変化バイアス仮説」
テレビ依存の強い人では、「円高が進む」と答える率が高いととを示していた。つまり、実際に円高になりつつある状況で、テレビ依存をしている人ほど一層その方向への変化を感じていた。仮説は支持された。
(3) 「特異現象化(カルガモ効果)」仮説
「カルガモ」それ自体については、第2回調査で全国での生息数と特性について質問した。その結果、テレビとそれ以外のメディアによって、稀少で「特異」な鳥として認知されていることがわかった。仮説は部分的に支持された。
(4) 「普遍現象化(過大視効果)」仮説
「東京の大学生の性体験者率」の推定についての質問をみると、東京の男子大学生の性体験者率についての推定は、回答者が「テレビ・雑誌の恋愛や性に関する番組・記事への接触」の高いほど、過大に見積もる傾向があったが、有意な相関ではなかった。しかし,女子の回答者による男子大学生の体験者率の推定については、低いが相関があった。仮説はある程度支持された。
(5) 「中心化」効果
仮説は支持されなかった。
(6) 「脱中心化」効果
(該当設問なし)
(7)「ステレオタイプ補強」効果
エイズは、初めて人々にその存在が知られたときから、同性愛とからめて報道されることが多かったが、次第に、より正確な報道がなされるようになり、日本ではアメリカから輸入される血液製剤に頼る血友病患者の間に多くの感染者がいることが、折りにふれ報道されるようになった。その結果,一般に正しい認識がもたれるようになりつつある。しかるに、テレビを多く見る人ほど、一般に以前のステレオタイプ、つまりエイズと同性愛とをからめる認知が多く見られた。仮説は支持された。
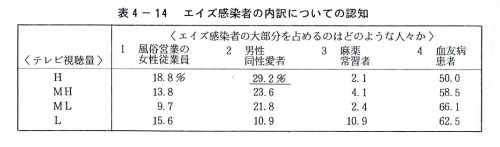
(8) 「行動刺激」効果
現在,評判になっている場所に行きたいかどうかを聞いた5つの質問項目すべてに関して、テレビ依存スケールとの強い相関が見られた。テレビ依存の最も強いグループ(スケール得点3)と最も弱いグループ:(同得点0)とを対比してみると、ブームになっている場所を実際に見たいと回答した者が、前者の方にずっと多い。テレビでの認知が行動を刺激すると考えられる。仮説を支持。
このように、仮説のうちのいくつかについては、それを支持すると考えうる結果が得られた。オーディエンスの現実認知に関して、映像的なインパクトの強いテレビメディアで、このようにメディア依存度の高い人ほどメディア・バイアスの影響を受けやすいことがある程度立証されたわけであり、本研究の意義は大きいといえよう。今後、認知バイアスに関する科学的な研究と連携して研究が発展して行くことを期待したい
擬似イベントからメディア・イベントへ
擬似イベント論 (Booastin, 1962)
ラング夫妻は、テレビ中継やニュース制作に際して生じる現実からの歪曲を、制作者の無意図的バイアスによるものと指摘したが、マス・メディアのニュースをむしろ意図的に合成されたイベントであると論じたのは、ブーアスティンである。ラング夫妻は、マッカーサーデーのテレビ中継が現実を「構成」したことを指摘した。ブーアスティンはこの点をさらに進めて、現代社会のあらゆる領域で擬似イベント(pseudo-event)が製造され続け、現実に変わってイメージが振りまかれていると主張した。ブーアスティンによれば、擬似イベントは、次のような特長を持った出来事である。
- 疑似イベントは自然発生的でなく、誰かがそれを計画し、たくらみ、あるいは扇動したために起こるものである。列車の転覆とか地裏ではなく、インタビューの類であるのを特色とする。
- 疑似イベントは、いつでもそうとは限らないが、本来、報道され、再現されるという直接の目的のために仕組まれたものである。それゆえ、疑似イベントの発生は、報道あるいは再現メディアのつごうのよいように準備される。疑似イベントの成功は、それがどれくらい広く報道されたかということによって測られる。疑似イベントにおける時間関係というものは仮定的、あるいは人工的であるのがふつうである。「何日何時に発表」という但し書のついた記事が事件の発生に先立って配られるし、しかもその発表記事には、事件がすでに起こったように書いてある。「その事件は本当か?」という質問よりも、「その事件にはニュース価値があるか?」という質問のほうが、ずっと重要なのである。
- 疑似イベントの現実に対する関係はあいまいである。しかも疑似イベントに対する興味というものは、主としてこのあいまいさに由来している。疑似イベントに関する限り、「それはどういう意味か?」という質間は新しい重要性をおびてくる。列車の転覆に関するニュース的興味というものは、何が起こったのか、その結果はどうなったのとかいう点にあるのに反し、インタビューに関する興味というものは、ある意味で、インタビューが本当にあったのかどうか、あったとすればその動機はなんであったのだろうかという点にある。ステートメントの場合も、いったいそれが言明しているところのことを本当に意味しているのであろうか。こういった類のあいまいさがない場合には疑似イベントもそれほどおもしろくないのである。
擬似イベントは自己実現の予言としてくわだてられるのが常である。30周年記念祝典は、ホテルがすぐれたものであると宣言することによって、実際にホテルがすぐれたものとなることを可能にしている。
擬似イベントの時代にあっては、われわれを混乱させるのは、経験の人為的単純化ではなく、むしろ経験の人為的複雑化である。擬似イベントが大衆の関心を得ようとして、同じ分野の自然発生的出来事と競争する時には、いつでも擬似イベントのほうに勝ち目がある。テレビの中で起こっている出来事のほうが、テレビの外で起こっている出来事を圧倒してしまう。擬似イベントが自然発生的出来事を圧倒してしまうのはなぜか?ブーアスティンは、その理由となる擬似イベントの特長のいくつかをあげている。
- 疑似イベントのほうがより劇的である。対立候補者によるテレビ討論のほうが、あらかじめ準備されていない立会い演説や、候補者が個々に用意してきた正式の演説の連続よりもはるかに大きなサスペソスを持たせることができる。たとえば、ある質問をあらかじめ用意しておいて、突然それを持ち出すといった方法によってである。
- 疑似イベントは、もともと広く伝達されることを目的として計画されたものであるから報道しやすく、またいきいきとしたニュースにしやすい。登場人物はそのニュース・バリューと劇的性格という観点から選ばれる。
- 疑似イベントは、思いのままにくり返すことができるし、またその印象を後から補強することもできる。
- 疑似イベントは、作り出すのに費用がかかる。したがって、それらを見たり倍じたりする値打ちがあるものとして報道し、拡大し、広告し、賞費することに利害関係を持つ人間が存在する。それゆえ、疑似イベントは投資された金を回収するために、前もって宜伝され、後になっても再演される。
- 疑似イベントは、理解されることを目的として計画されたものであるから理解しやすい。したがって、われわれを安心させる。われわれは候補者の資格や複雑な問題について気のきいた議論をすることができない場合でも、少なくともテレビ出演のできぐあいについては判断を下すことができる。自分たちにも理解できる政治問題があるということは、なんと気持のよいことであろうか!
- 疑似イベントは、社交的で話の種になり、見るのに便利である。疑似イベントの発生はわれわれのつごうに合わせて計画されている。新聞の部厚い日曜版は、われわれがゆっくりとそれを読むことができる日曜日の朝配達される。テレビの番組は、われわれがビールのジョッキを手にしながら見る用意ができた時に始まる。そして朝、人々が事務所に集まった時、話題の中心になるのは、予定されずに突然起こってニュースとなったようなものではなくて、ジャック・パー(群落に以酸番)やその他のスターによって、定期的に放送される深夜番組である。
- 疑似イベントについての知識、すなわち何がどんなぐあいに報道され、何がどんなぐあいに演出されたかについて知っていることが、「ものしり」かどうかの試金石になる。ニュース雑誌には定期的にクイズが現われるが、その質問は、何が起こったかではなくて、誰がニュースに現われたかについてである。すなわち、ニュース雑誌に報道されたことについての質問である。疑似イベントは、いささか時代遅れの私の友人たちが「偉大なる書物」のなかに発見しようと努めた「共通の談話」をわれわれに提供し始めた。
- 最後に、疑似イベントは他の疑似イベントを幾何級数的に発生させる。疑似イベントがわれわれの意識を支配するのは、その数がつねに増大しているからである。
このような「擬似イベント」を作り上げることができるのは、いうまでもなく、テレビ局やそのスポンサー、大企業、広告代理店など、テレビのコンテンツを支配する組織や集団である。テレビ時代には、こうした少数の勢力(権力集団)が、擬似イベントを創造することによって、大衆に対するイメージ操作を独占的に行うことができたのである。
メディア・イベント論(Dayan & Katz)
ダヤーンとカッツ(Dayan & Katz, 1992)は、ブーアスティンの「擬似イベント」よりもやや狭義の概念として、「メディア・イベント」についての実証的研究を行なった。メディア・イベントとは、「テレビがその日常のルーティーン[定期的な番組編成]を破って特別に行う歴史的なイベントの生中継のことである。」(水野, 1998)。メディア・イベントはテレビ放送の一ジャンルであるが、次のような要件を満たすものと定義している。
1. 日常生活を中断して放送されること
2. 生中継(ライブ)であること
3. メディアの「外部」(別な組織や団体およびスタジオ外)で組織・運営されること
4. あらかじめ計画され、予告・宣伝されたイベントであること
5. イベントが行なわれる時間と場所が特定されていること
6. 英雄的なパーソナリティあるいはグループが登場すること
7. 敬虔さと儀式性が賦与されること
8. 何それを見なければならないような社会規範の力が働くこと
9.非常に多数の受け手を感動させ、場合によっては驚かせること。結果的に、社会を統合し,価値や権威への忠誠を新たにさせる機能をもつ
10. 、ジャーナリストの批判性は一時保留され、社会のなかで対立・反目しあっている陣営間で、一時的な和解がなされること
ダヤンとカッツは、メディア・イベントを次の3つの類型に分けている。
(1) 「英雄的使命(heroic mission)」あるいは「征服(conquest)」:宇宙飛行士の月面上陸、サダトのイスラエル訪問、ローマ法王の諸国歴訪などに代表されるもので、常識では不可能と思われた限界にあえて挑戦し、それをのりこえようとする英雄的行為
(2) 「国家的祭典(occasion of state)」あるいは「載冠(Coronation)」:英皇太子の結婚、ケネディ大統領の葬儀、エジプト・イスラエルの平和条約の調印など、ひとつの時代の始まりあるいは終りを象徴するような儀式
(3) 「コンテスト(contest)」:大統領候補者によるテレビ討論、スポーツ世界選手権大会など、スーパー・プレーヤーがルールに従って競い合うもの。
では、メディア・イベントはどのような機能を果たしているのだろうか?この点について、ダヤンとカッツは、イベントに対するテレビのコミットメントという視点から、4つの機能を指摘している。
(1) オーディエンスに対し、セレモニーの現場に居合わせる体験を代償的に提供することによって、儀式における主役 (primary performer)となって、わくわくするような経験を提供する。
(2) テレビの中継は、セレモニーの持っている意味づけを与える機能を果たす(メディア・イベントの現実定義的な側面)。(例)イベントに居合わせた観衆のうち、イベントで称賛されている価値や象徴に同調する人々をクローズアップして見せるなど。
(3) テレビは、イベントが担っている意味の案内役(ガイド)として機能する(解釈的な側面)。この役割は、(アナウンサーのナレーションなどによって)イベントに物語的な統一性を付与し、またそれに物語の筋だてを与えることを通じて遂行される。
(4) イベントは、他のあらゆる番組より絶対的に優先される。すなわち、競合する他の関心事よりも上位に置かれ、「聖なる時」として、いかなる干渉からも保護される(保護的な機能)。例えば、イギリスのロイヤル・ウエディングのセレモニーの間に起きた暴動は、セレモニーが終わるまで報道されることはなかった。
水野(1998)によれば、テレビは、単にイベント自体の定義に忠実でそれを視聴者に目撃させるというだけでなく,視聴者にあたかも現地にいるかのように思わせようとするものである。そのために、テレビは、現地にいる主役たちと観衆との相互作用を描き出す。儀式においては、その焦点は明確に主役たちにある。しかしながら、主役たちと観衆との間に相互作用がなければならない。とりわけ、観衆の反応が不可欠な要素となっている。もし観衆の反応がなければ、儀式は空虚なものとなる。この点で、パレードは典型的だろう。観衆のいないパレードなど考えられもしないからである。
イベントは3次元の現実、観衆は反応する存在であり、テレビはイベントにより近づきうる手段である。現実においては、現場の観衆の間に、ある種の社会階層ができあがる。つまり、招待され儀式の中心近くに位置するか、単に周辺に位置するかによって,自分が社会的にどのような立場にある人間かがわかる。それに対して、テレビというものは、あらゆる視聴者が平等にイベントに接触できるようにするだけでなく、現地の観衆よりももっと多くのものを見させてくれる。それと言うのも,テレビの画面をさえぎるものがないからだけでなく、テレビは、組織者の意図するそのイベントの定義を強調し、さらに解釈を付け加えさえするからである。1993年の皇太子の成婚にあたって、午前中行われた「結婚の儀」には、慣例に従って天皇・皇后は式には出席せず、テレビでそれを見たという。その時点で,テレビ視聴者は天皇・皇后と同じ”特権的な”位置にあったと言える。
テレビはまた、あらゆる人々がイベント全体を見ることを可能にした史上初のメディアでもある。これは、一つには「スペクタクル」ということから生じる。イベントが一大スペクタクルに変換されることにより、かって本物にしかなかった「オーラ」は、今や、むしろメディアイベントの方に付与される。現地の観衆は逆にそのようなオーラの欠けたイベントを体験するのである。
テレビは現地と視聴者の居る場所との物理的な距離を感じさせることはなく、儀式がスペクタクルに変換されていることも意識させまいとする。しかし、テレビは、それがさまざまな距離を消そうとする努力の中で、かえって、その距離を明らかにしてしまうこともある。例えば、テレビによって、かっては普通の人が知りえなかったような、晩餐会における主役のきらびやかなドレスを人々は目にすることができ、それをまねることもできる。しかしながら、決してそのオリジナルを目にしているのではないことが意識させられる。この意味では、テレビによる参加は、それがオリジナルのオーラ(がある場合、それ)を決して侵害しない限りでのものであることが思い知らされるのである。
また、テレビが一旦消してしまった距離というものを,テレビ局のスタッフで現地にいる者とスタジオにいる者との違いを無意図的に浮かび上がらせることによって、テレビはその距離感というものを別な形で再建することもある。例えば、現地にいる者が、そこでしか聞けない「うわさ」を聞き伝えるという形で、イベントにおける物理的な存在感を示すのである。
つまり、テレビは、結局のところは視聴者を現地に運ぶことはできないのである。しかし、この「経験の二次性(secondhandedness)」は、テレビが、これまでに人々が体験できなかったような仕方で補ってくれる。このことについては、すでにブーアスティンの「疑似イベント」論やラング夫妻の実証的な研究においても言われてきた。すなわち、テレビは現実をよりドラマチックに、フィクションとして再構成して視聴者に提示するのである。ダヤーン&カッツは、イギリス皇太子の成婚式中継についての考察をもとに、テレビは日常性からの脱文脈化(de-contextualization)と非日常性への再文脈化(re-contextualization)との二つの過程を通じて、人びとをニュースでもなく娯楽でもない第三の現実に導き入れる、と述べている(竹内, 1984)。脱文脈化は、報道担当の組織面においても、放送時間の編成面においても、平生とはまったくちがった方式をとることによって行なわれる。一方、再文脈化は、めったにない世紀のイベントであることを繰り返し予告し、当日は朝からイベント一色に塗りつぶされた放送を流しつづけることによって、進行してゆく。イギリス皇太子の成婚に際して、「メディア、とりわけテレビは、『水曜日朝のフィーバー』とよばれたほどの集団催眠状態を作りあげた。メディアは人びとを聖域に迎え入れる通過儀礼の司祭として機能した。テレビは人びとを日常世界から連れ出して、この別天地に招き入れた」。こうして、テレビはメディアイベントというものを,神話とシンボルにあふれた儀式から、一編の小説へと翻訳していく機能を果たしているのである。
皇太子結婚パレード中継に関する研究
日本でメディア・イベントについて実証的に研究した事例としては、高橋・岡田・藤竹の研究と、水野・三上の研究がある。時期は異なるが、いずれも皇太子成婚パレードのテレビ中継の事例研究である。前者は、ラング夫妻(Lang & Lang, 1968)のマッカーサーデー研究をモデルとして実施したものであり、後者はLang夫妻(Lang & Lang, 1968)及びDayan & Katz(1992)のメディア・イベント研究をモデルとして実施したものである。
昭和の皇太子結婚テレビ中継に関する調査研究(高橋、岡田、藤竹、由布 1959)
調査の概要:
調査主体:
高橋徹(東大新聞研究所)
藤竹暁(東大大学院)
岡田直之(東大大学院)
由布祥子(東大新聞研究所)
調査時期:1959年4月
調査目的:
皇太子結婚パレードのテレビ報道における「現地」のイメージとテレビで再現された「現地の地図」から得られたイメージの比較によってテレビのメディア特性を明らかにすると同時に、そのいずれが人々の関心を充足するか、またテレビのイベント映像が「天皇制価値感情」にどんな影響を及ぼしたかを明らかにすること。
調査方法:
(1) 視聴者分析
4月10日の馬車行進が行われる二重橋から東宮仮御所までの沿道4区におけるテレビ所有家庭を母集団とし、そのなかから層化無作為抽出法によって選ばれた598世帯をサンプルとして、個人別面接調査を2回にわたって実施した(回収数:第1回411、第2回350)。
(2) メディア分析
4月10日に至るまでのテレビ各局の動きを捉える他、NHK、KRT、NTV三局が4月10日当日行なった「実況放送の内容分析を行うことによって、各局の報道特性を比較した。また、反応分析器(program analyser)を利用して、テレビ視聴者の画面に対する反応と音に対する反応を記録した。
(3) パレードの観察
「現地」と「地図」の相違を明らかにするために、参与観察法の訓練を受けた東大生を主要なテレビカメラの配置地点に位置させ、群衆行動の観察に当たらせるとともに、彼ら自身が直覚的に把握した「お二人」(皇太子、皇太子妃)のイメージを記録させた。それと同時に、パレードの見物人から60名の有意サンプルを選んで、現地に出かけた動機、彼らが「現地」で抱いたイメージとマスメディアから獲得しているイメージとの相違などについて質問紙調査を行なった。
調査の結果:
(1) 現地と地図の選択:
1950年代という、テレビの草創期のメディア・イベントだったにも関わらず、中継当日の1世帯あたりの平均視聴時間は10時間35分にもおよび、当日のテレビ番組に対する視聴者の関心は非常に強いものがあった。特に、当日もっとも深い感銘を受けた番組は「パレードの沿道中継」という回答が47.9%に上った。これは、パレード沿道の住民に対する調査の結果である。これに対し、パレードを見に行った人はわずか17.2%に過ぎなかった。つまり、全サンプルの大半(80.6%)が、彼らに与えられた地理的近接性というチャンスを放棄して、「テレビで再現された現地」(擬似環境)を選択したのだった。その理由を見ても。「沿道では一部しか見られないが、テレビだと全容が見られるから」(38.0%)など<積極型>の回答が多かった。直接経験への参加志向よりも、テレビによる間接的視聴が圧倒的な勝利を収めたのだった。
(2) テレビ中継への充足と現地での失望
当日のテレビ各局の番組への満足度は、89.4%と極めて高かった。特に、「お二人の大写し」が「感動した場面」のトップ(48.0%)に挙げられており、パレード中継でテレビ各局が力を入れたクローズアップ映像が、メディアイベントにおける独自の現実構成力によって視聴者に大きくアピールしたことを示していた。これは、マッカーサー帰還パレード中継においてラング夫妻が見出した知見とも一致する。これとは対照的に、パレードの沿道に集まった人びとの場合、お二人の表情がはっきりと見える範囲を左右50メートルとするならば、わずか15秒のために3時間以上も待ちくたびれた見物人は、相互にほとんどコミュニケーションを欠いていた。ここでは、熱狂する群衆の様子もあらわれなかった。人々は「自分の穴」でお二人に対面したのである(高橋・藤竹・岡田, 1959, p.6)。
1959年4月10日 皇太子ご成婚パレードの映像(中日ニュース)
平成の皇太子結婚テレビ中継に関する調査研究(水野、三上)
メディア・イベントに関して、実証的メディア効果論の視点から取り組んだ日本の研究として、1993年6月9日の「皇太子成婚パレード」のテレビ中継に関する調査研究がある。これは、水野博介(埼玉大学教授:当時)と筆者(三上)が企画・実施したものである。諸般の事情により、筆者は調査結果の報告書作成には加わることができなかったが、水野による報告論文(水野, 1994, 1998)が公刊されているので、以下ではこの論文の要点を紹介することにしたい。
(1) テレビ中継のメディア・イベント特性
本研究でテーマとして取り上げた皇太子成婚パレード中継放送は、Dayan & Katzの研究における「メディアイベント」の定義にほぼ当てはまっていた。
1. この報道は、ルーティーンの放送でないことが明らかである。当日は、国民の祝日となり、ネットワーク・テレビは、通常の番組に代えて、早朝より十数時間に及ぶ特別番組を組んだのだった。
2. これは皇室行事であり、それが国によって費用もまかなわれ、公的な行事となったもので,その運営主体と催された場所の両方の意味で,テレビの「外部」に組織されたものであった。
3. 皇太子の結婚式典は、イデオロギー的な価値及びより普遍的な価値と関わるものであり、今回のイベントの放送は、そのような価値を強化するものと予想された。
4. この特別放送は,あらかじめ予定され,予告され、前宣伝がなされていた。例えば、テレビ番組情報誌は、あらかじめこの日の放送予定を人々に知らせており,テレビ自身も、局の番組CMなどでこれを予告・宣伝していた。
5. この特別放送に敬さと儀式性が付与されていたことは明らかである。むしろ,それらが最も大きな特徴と言えよう。その放送内容において,結婚の当事者やその関係者。あるいは天皇制や皇室についての批判めいた言辞や紹介は全くなく、逆に敬語が連発される。普段聞かれる天皇制や皇室についての批判的な言説は、このイベントの期間中は抑えられていた。
6. 日本社会の中で対立あるいは反目し合う勢力として、政府与党と野党があるが、、野党も,この結婚イベントについては特に言挙げすることはなく,この面では「一時的な和解」に類する雰囲気がかもし出された。
1993年6月9日 皇太子ご成婚パレード(TBS)
(2)調査の概要
1. アンケート調査(以下、「大学生調査」と略記)。もう一つは、やはり6月中旬に、パレードの沿道から幅およそ200メートル以内の範囲にある住
ぞおよび自営のお店に、アンケート調査票を留置き、それを郵送で回収したものである。配布数は780で回収数は345,回収率は44.2%だった(以下,「沿道調査」
と略記)。
2. 6月9日水の特別編成の番組をNHK 及び民放の計6局のすべてについてビデオ録画し内容分析を行なった
3. 現地における参与観察とインタビュー:
結婚パレード当日,3つの研究班(学部学生3人、院生3人を含む計9人による)を構成して、パレードがなされた沿道で観察を行ない,パレードを見るために沿道に集まっていた人々のうち,合計29人を有意抽出してインタビューし、ビデオカメラによる録画と録音も行なった。
(3) 調査の結果
1. 皇太子成婚に関するテレビ視聴とパレードの映像
首都圏では、NHK及び民放の計6局が6月9日(水)には朝から夜まで特別編成の番組を放送したが、この日の放送のメインイベントであった「ご結婚パレード」の中継番組(午後4時30分頃から5時30分頃まで)の視聴については、大学生調査で男女別及びその合計で次のような結果が得られた。
パレードの総世帯視聴率(関東、ビデオリサーチ)は79.9%,ほぼ8割の世帯でパレードを見たことになる。これは、1959年の成婚報道に匹敵する高さである。
しかし、中継されたパレード映像の大部分は、オープンカーに乗ってパレードする皇太子と雅子妃のクローズアップ(それも車の後部左側に座った雅子妃中心)であった。
これは、テレビ放送技術の進歩が、長時間にわたるクローズアップ映像のリレーを可能にした結果であり、1959年のパレード中継においては望めないことであった。しかし、逆にそのために、今回はむしろ映像としては単調であった。今回は、前回の馬車と違って車高の低いオープンカーで、スピードアップされた上に、距離も約半分と短く、また、水も痛らさぬ警備のおかげで、パレードに関してはハプニングもなかったことも、単調さに輪をかけたかもしれない。
2. 現地における参与観察とインタビュー
パレードの一行が出発する二重橋近くで観察した水野と三上は、パレードが始まる約1時間半前の午後3時過ぎに、検問(荷物のチェック)を受け、現地に着いたが、すでに観衆を整理する鉄冊の前列には二重三重の人垣ができ、沿道近くで見ることは不可能だった。。午後4時45分を過ぎ、予定通りパレードが来たらしかったが、筆者らには何も見えなかった。オープンカーが通り過ぎると、人々はあっという間に人垣を解いて、帰路に向かい始めた。帰路の途中で、皇居前広場などで記念写真を撮っていた人々も多くいた。
パレードを待つ群衆の様子を別な観察者はこう述べている。「印象に残ったのは、「これじゃ、見えないわね」『たくさん人が来ているのね』という声の多さである。そして、三宅坂を通過する時刻が近づくにつれて、多くの人が耳を澄まして、まわりの様子を聞いていたことである。『来た?」「いやまだだ」というちょとした会話が聞かれた」。パレードが実際に通過した際には、この観察者の報告では、「日の丸の旗が『バサバサ』と揺れ、それと共に「キャー』『ウォー』『万歳』「雅子さーん」「そこどいて」『見えない』「カメラ邪魔」等々の声が入り乱れ,人びとは前に押し寄せてくるし,ものすごい状態だった。しかし,この状態は、ほんの少しの間だった。あまりにもオープンカーの速度が速かったからだろう、と述べている。年配の人々にとっては、何がしかの感慨を与えるものだったようだが、若年層はただ見ることに熱中しただけの人が多かったようだ。しかし、若者の中でも,皇太子はやはり違うと感じとった人がいたり、皇室にミーハー的ではあるが、たいへん興味を抱いていた人もいたようである。
3. 成熟したテレビ視聴者による新鮮な現場体験
高橋らによる1959年のパレード沿道調査では、家族のうち一人でもパレードに出かけた世帯は、わずか17.1%であった。このときは、家にいて、テレビという最新のメディアで、はっきりと見たいという欲求の方が、現場でちらっと見ることで満足することを上回っていた。それに対して、今回の沿道調査では、留置した調査票の郵送回収率(パレードを見た人が記入して返送)は44.2%であり、おそらく半数かそれ以上の世帯で、誰かがパレードに出かけたと推定される。現在では、ビデオデッキが家庭に普及しており、あとで録画した番組を見ることができるので、とりあえず現場でよく見えなくともいいから、とにかく見に出かけた、というメディア環境の変化を反映した行動とも考えられる。
4. 大学生調査
実際にパレードを見に行った学生は2.7%と少ないが、実際には行かなくても行きたい気持ちがあったとする学生が28.9%と相当数いた。このイベントの一回性が動機づけを生み出す原因であったかもしれない。行きたいという動機の回答結果は次のとおりである。
・「歴史的なイベントに参加したかったから」(58.7%)
・「テレビでしか見たことのない人物を自分の目でみたいから」(51.6%)
・「パレードやお祭りが好きだから」(22.8%)
・「結婚する2人を祝福したかったから」(17.9%)
今回のパレードが一回性しかない希有なイベントであることが大きな動機づけの要素となっていたと思われる。つまり、一回性しかないからこそ、それを体験し実物を見たいとする欲求がかき立てられたのだろう。
5. パレードを見た人々の満足度
1959(昭和34)年の調査では、マスメディアによって肥大した期待を抱いて現地におもむいた人々の多くは失望したと結論づけたが、今回の調査で、実際のパレードが全くあるいはまあ期待通りだったとする回答(選択肢1と選択肢2)は合計64.2%に達しており、仮説通り現地で見たことに大きな価値を認めていることがわかった。
このように、1993年の調査では、ラング夫妻や高橋らの先行研究とは違って、現地(パレードの沿道)で参加した人々の満足度が高かった理由として、水野は、テレビの普及が成熟段階に入り、メディア・イベントの放送が日常化する中で、テレビで見るよりも現地で見ることの価値がかえって高まっているためではないか、と次のように述べている。
2つの先行研究と今回の研究との大きな違いは、先行研究が行われた時代にはテレビはまだ「ニューメディア」そのものであり、その機能や可能性は未知数なところが多かったし、見る側もテレビ視聴体験は浅いかほとんどないようなテレビ普及段階であったのに対し,今回の研究は、テレビが本格的に放送を始めてからすでに40年が経過し、相当に「成熟」したメディアだと考えられる時代に行った、という点である。
先行研究の時代は、テレビを見ること自体がまだ珍しい頃であり、テレビを通して歴史的なイベントや大事件に接し世の中の一面を垣間みるという体験自体が、相当に新鮮で、これまでにない貴重なものと認識されていたと思われる。
それに対して今日では、テレビで歴史的なイベントや大事件を見ることさえ、必ずしもそれほど珍しいことではなくなりつつある。テレビを見る側も「成熟」した視聴者になったのである。それ故、逆説的であるが、テレビで大きなイベントを見ることは、もはやありふれた経験であるため、現地でそれを見ることの方がむしろ高い価値を持つと感じられるのではないかという仮説をたてた。
というのも、テレビの存在が普遍化した今日、逆に、テレビで見るような類のイベントや大事件の現場に物理的に居合わせたり、それらを肉眼で目撃することの方が、稀少であり、ずっと高い価値を持つとする意識が芽生えてもおかしくない。テレビを通じて目撃することは、何万人あるいは何億人の中の1人としての経験でしかないが、現場に居合わせることは、ずっと確率の低い,まれな経験である。また,ダヤーン&カッツが言うところの,テレビが決して克服しえない「距離」を克服できるかもしれない機会でもある。
そうしてみると,先行研究が示しているように、イベントを現場で見ようとして集まった人々が期待はずれに失望し、テレビを見た人々がより満足を感じる,ということも必ずしも言えないかもしれない。むしろ現地では、テレビでは感じえない個々の人物・事物のオーラを感じとることができるかもしれない。
実際,今回のイベントの場合,後で見るデータにもある通り、現場に居た人々は多かれ少なかれ期待通りのものを見,テレビと同じくらいに満足を得たのである。(水野, 1998)
擬似パニックに関する研究(三上)
これまで、災害発生時、警報発令時、生命の危険が迫っている危機的状況においては人々がいっせいに脱出しようとして集合的反応としてパニックが発生しやすいと言われてきたが、実際にはパニックは稀にしか起こらないことが、近年の災害社会学研究において明らかになった。これを「災害神話」の一つとして定式化したのは、アメリカの災害研究所長のE.L.Quaranatelliであった。
Quarantelliは、多数の災害事例の研究や過去のパニック研究をもとに、「パニックが実際に起こった事例は極めて少ない」という実態を明らかにした (Quarantelli, 1954 ; Quarantelli and Dynes, 1972)。そして、パニックが起こったとされている事例の多くは、誤った報道によるもので、ニュース報道はしばしば、パニックを誇張して伝えそれが、歪められた「パニック神話」を構築する大きな要因になっていると述べている。例えば、Quarantelli (2008)によれば、1938年の「火星人襲来」のラジオ放送では、85%以上のリスナーがそれをラジオショーとして受け取っており、実際にパニックを起こした人はごく少数であったという。また、1973年にはスウェーデンで架空の原子力発電所の事故が架空のニュースとして放送され、マスコミはこの放送でパニックが起きたと報じたが、実際にはパニック的逃走は発生しなかったという調査結果もある、と指摘している。筆者の調査した「余震情報パニック」騒ぎも、Quarantelliの指摘する「パニック神話」の一つと考えることができる。
このように、パニック現象は現実世界では滅多に起こらないのに、マスメディアによってしばしば誤って伝えられ、それが一般の人びとの間でも、誤った誇張したイメージとして広がっていることは、防災対策を考える上でも大きな問題となっている。こうした歪んだ「パニック」イメージや、それを醸成するマスメディアの「パニック」報道は、リップマンの擬似環境論に倣って、「擬似パニック」と呼ぶことができるだろう。第1部で紹介した「火星からの侵入」パニックは、大規模な擬似パニックの代表的な事例と言える。しかし、その実態や、なぜパニック報道が作られたのか、という点に関しては、十分な実証研究が行われたとは言えない。そこで、以下では、擬似パニック、擬似パニック報道に関する実証的研究の事例として、スウェーデンと日本で行われた研究を紹介することにしたい。
スウェーデンの「原発事故報道」パニック(Rosengren)
1973年11月13日、スウェーデン・ラジオ局は、当時スウェーデン南部に建設中だった原子力発電所で放射能漏れ事故が発生したという架空のストーリーを、ニュースのスタイルに脚色して放送した。その内容は、放射性物質が風に乗って南方へ運ばれ、海峡を越えてデンマークのコペンハーゲンから15マイルのところまで到達したというものだった。
11分間にわたるこのフィクション番組は,核エネルギーに関連して将来起きるかもしれない危険性をめぐる専門的な問題に一般の人々の目を向けようという意図で作られたものだった。この番組では、救急車のサイレンの音を入れたり、よく知られたアナウンサーの声を入れるなどして、非常にリアリスティックな装いを凝らしていた。ただし、番組の前後には,この番組がすべてフィクションであるという断りのアナウンスが挿入された。
ところが、全く予期しないことに、この番組が視聴者の一部分によって本当のニュースと間違えて受けとられたのである。それから1時間もたたぬうちに、マルメ市のラジオ局が、スウェーデン南部地方で広い範囲にわたってパニックが起きたというニュースを流し、翌日の新聞も大見出しでパニック発生を報じた。その後数週間にわたって、この番組の内容と公衆の反応をめぐってマス・メディアや国会の内外で活発な論争が繰り広げられた。しかし、これらの議論では、広範囲に生じたとされるパニックのメディア・イメージは一度も真剣に検討されることなく,既定の事として受け取られたのである。
しかし、事件直後、Rosengrenらがスウェーデン南部の3都市に住む15-79歳の人を対象にアンケート調査を行なったところ、ラジオ番組聴取者の反応に関してメディアの報道や一般のイメージとはまったく異なる実態が明らかになった(Rosengren eta1., 1975)。つまり,番組によって引き起とされたとされるパニックは、実際にはまったく観察されなかったのである。
調査結果によると,この番組を聞いた人は約19%いたが、そのうち47%が番組を二ュースと誤解していた。誤解した人のうち78%が驚いたり不安になったりした。さらに、驚いた人のうち14%が何らかの対応行動をとっていた。つまり、この地域の成人のうち、番組を誤解したのは約10%であり、びっくりしたのは7~8%、何らかの対応行動をとった人は1%にすぎなかったのである。
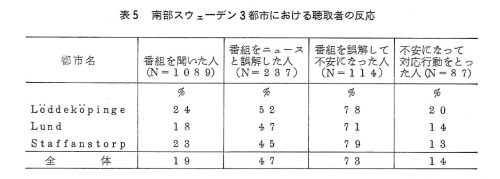
平塚「誤報警戒宣言」パニック(三上、池田、宮田)
これと似たような事件が我が国でも起こった。平塚市での「警戒宣言」誤放送騒ぎである。1981年10月31日(土)午後9時3分でろ,神奈川県平塚市で、市内45箇所に設置された同報無線のスピーカーから、警戒宣言が発令されたことを知らせる市の広報が誤って放送された。これは,市長の声で事前にテープに録音されていたものが、機械の操作ミスから、タイマーと連動して自動的に送出されてしまったための事故とわかった。放送の内容は、内閣総理大臣から警戒宣言が発令されたこと、平塚市が警戒本部を設置して広報活動、デマ対策や交通規制に全力をあげていることを伝えるとともに、市民に対し、情報収集・火の始末・避難準備などの対応行動をとるよう指示するものだった。
翌朝の新聞は、この誤放送によって平塚市でパニックまたはそれに近い騒ぎが起きたととを一斉に報じた。例えば、読売新聞は「東海地震が来る!?/平塚,夜の警報パニック/全市に避難命令放送/実は操作ミス,30分後訂正/問い合わせ電話,パンク寸前」という大見出しで次のように伝えた。

1981年11月1日(日)読売新聞朝刊社会面の記事
「31日夜,神奈川県平塚市で市内全域に配置されているスピーカーから,激しいサイレンが鳴り出し、「地震警戒宣言が発令されました。食糧などを持って避難してください」と避難命令が出された。このため避難袋を抱えて戸外へ飛び出す市民も出るなど、市内はパニック状態に陥り、警察や消防署,市役所などへ市民からの電話が相次いだ。
結局,スイッチの操作ミスから地慶戒報テープが回り出したためと分かり、騒ぎは約1時間でおさまったが、同市は大規模地震対策特別措置法に基づく東海地震の「地震防災対策強化地域」に指定されているだけに、市民の驚きと混乱は大きく、怒りの声が沸き上がっていた。」(11月1日朝刊社会面トップ記事・前文)
また、朝日新聞は、1面のトップでこの事件を取り上げ、「大誤報・・地震警戒宣言(平塚)/広報無線ミス作動/夜間に住民避難騒ぎ」という大見出しで、夜空に不気味に浮び上がる同報無線の拡声装置の写真とともに、次のように報じている。

1981年11月1日(日)朝日新聞朝刊1面記事

1981年11月1日(日)朝日新聞朝刊社会面記事
「東海地震の防災対策強化地域に指定されている神奈川県平塚市で31日夜9時すぎ、市内全域に設置されているスピーカーから突然,「内閣総理大臣から大規模地震の警戒
宣言が発令されました。火を消して身の回りのものを準備して下さい…・・・・」という放送が流れた。約80分後に誤報とわかり、平塚市は大あわてで訂正したが、警察や消防署には市民からの問い合わせ電話が殺到して大混乱。団地住民が戸外に飛び出したり、防災ずきんをかぶって炊き出しの用意をするなど一時はパニック寸前の騒ぎとなった。
訂正放送までの間、市民たちは、実家に話をしたり、子供を起して防災ずきんをかぶせるなど、大騒ぎとなった。大あわてでガスの火を止め、バケツやヤカンを持ち出して飲料水を確保して炊き出しを始めた人や、家中で避難準備をしたり、屋外へ飛び出した人も多かった。」
このうち、読売新聞の記事には、住民の反応以外の事実関係でいくつかの誤りが含まれていた。一つは、「避難命令が出された」という記事である。実際には避難命令が放送されたという事実はなく、これは、「いつでも避難できるように準備しておくように」という「避難準備の呼び掛け」の誤りだった。もう一つは,「激しいサイレンが鳴り出し」という部分で、実際にはそのような事実はなかった。
それでは、住民の反応についてはどうだろうか。新聞が報じたように、警戒宜言発令の誤放送を聞いて多くの平塚市民はパニック状態に陥ったのだろうか。
東京大学新開研究所「災害と情報」研究班が、事件の約2週間後に事件当時平塚市内にいた1.681人を対象として実施した調査によると、実際にこの放送を直接または間接的に聞いた人は、とのうち20%(328人)にすぎなかった。また、警戒宣言放送を聞いた人のうち、これを信じたのは14%、ある程度不安になったのは20%にすぎなかった。
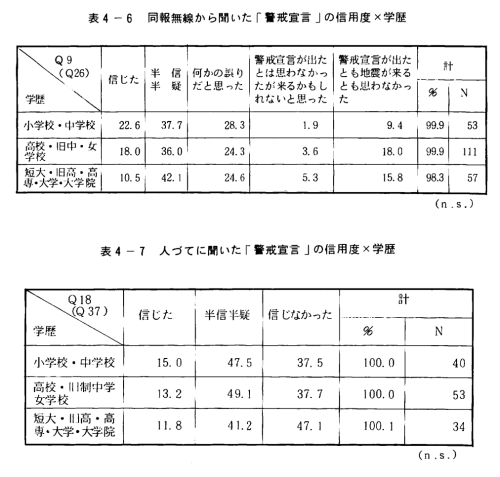
「警戒宣言」を信じたのは、低学歴の人々に比較的多いという傾向が見られた。これは、「火星からの侵入」におけるヘルツォークらの調査結果と一致する。批判能力の高さが誤報の信用度と関連しているということだろう。
対応行動をみると、大半の人は情報を確認したり、火の始末をするなどの冷静な対応行動をとっていたことがわかる。実際に避難したと答えたのは2人だけであり,これは、警戒宣言を聞いた人の0.6%、サンプル全体のわずか0.1%にすぎない。
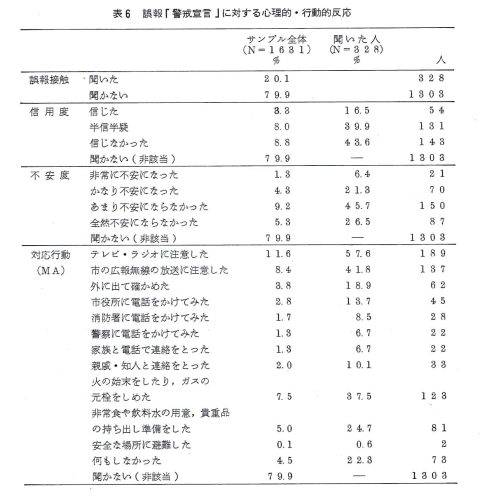
避難をした2人のうち一人に筆者がフォローアップのインタビューをしたところ、この女性(34歳・主婦)は次のように、家族とともに整然とした避難行動をとっていたことがわかった。この日の夜9時でろ、彼女はいつものように自宅で夕食後のひととき、家族そろってテレビを見ていた。同居家族はで主人と子供3人、それにおじいちゃんとおばあちゃんの計7人である。9時3分すぎ、市の同報無線のスピーカーから市長の声で放送が聞とえてきた。それは「警戒官言が出ました。私の言うことをよく聞いてください。デマに惑わされず冷静に行動してください」という内容だと聞き取れた。これを聞いて、彼女は本当に戒宜言が出たと信じ込み,かなり強い不安を感じた。そこで、すぐに寝ていた子供を起して着替えさせ,火の始末をし,非常持ち出し品の準備をして、家族全員で隣の小学校へ避難した。避難する前に,テレビやラジオをつけたり、外へ出て確かめようとしたが、確認できず、ご主人が市役所へ電話をかけたが一向に通じなかったということである。小学校の校庭には他に避難している人もなく,通りかかった人たちが、防災頭巾をかぶって避難している彼女たちの姿を不審そうに見ていた。このような状況に疑問を感じ、ご主人が手び家へ戻って市役所に電話をかけたところ、やっと通じて「誤報」だと確認し、家族は全員家に引き返して、一件落着となった。彼女の家では、ふだんから防災準備をよくやっており、警戒宜言が出たときに家族がどのように連絡を取り合うかとか、どとへ避難するかということを話し合っていた。隣の小学校は市の指定避難場所であり、彼女はとこでの防災訓練にも参加したことがあったのである。このように、実際に避難した人の証言をみても、パニック的な行動とは魅け離れたきわめて環境適応的で整然とした対応行動だったのである。もちろん、このことから直ちに、パニック的な逃走行動を示した人が皆無だったと断定することはできない。しかし、この夜,平塚市民が示した反応は全体的にきわめて冷静であり、集合的パニックは全く起きていなかったと結論づけることができる。
以上,擬似的脅威の集合的認知によって住民の間に一定の心理的・行動的反応が生じ、それがマス・メディアや流言などを通じて「パニック」発生と誤認されて社会成員の間で受容される現象のいくつかを紹介し、実証的研究による実態把握を試みた。そこで、最後に、このような「擬似パニック」がどのようなプロセスを経て形成されるのかという点について検討することにしたい。
擬似パニックは二種類のコミュニケーション過程を通じて形成される。その一つは、流言の作用であり、もう一つは、マス・メディアの取材・報道過程における情報の歪みである。Rosengren らは,サンプル・サーベイのデータを補足するために、局所的にバニックが起きたかどうかについて警察・消防関係者、店員などに対するインテンシヴな聞き取り調査を行なったところ、彼らの中には、パニックがあったというウワサを聞いた人はいたが、実際にパニックの現場を目撃した人はいなかった(Rosengren et al., 1975)。同様の知見は「余震情報パニック」のとき筆者らが沼津市で行なった聞き取り調査においても得られている。事件翌日の日経新聞は、沼津市で非常食の買いだめ騒ぎがあったととを次のように報じた。
ところが、筆者らが事件直後に、同店で店員にインタビューをしたところ、実際には報道されたような「騒ぎ」はまったく起きていなかったことが確かめられた(岡部他、1978)。以下は、店員との一間一答である。
<店員1>(余震情報が出て騒ぎになったが、ここで物が買い占められたとか?).あったらしいが…・・・。(その場にいましたか?)いましたが…・…・・。(お客が殺到して•・・)
殺到するというほどでもない。(乾パンなんか売り切れた?)うわさでしたけど・…・。(現実には?)見なかったから。
<店員2>(18日当日、乾パンとか相当売れたとか聞いたんですが?)乾パンとかかん詰めとか売れました。(ほとんど?)全部というわけではないが、「おかずカン」ですね、マグロッチキン・・・・・そういうもの。(かなりというくらい?)そうですね。
(特に混乱は?)別に混乱はない。(物が買えなくて苦情をいったお客とかは?)
そういう事はない。(3、4年前,トイレットペーパー騒ぎがあったでしょ。そのとき,とちらも買いだめは?)あの時は、なくなる、なくなるでもう・・・・・。(その時に比べたら問題にはならないと・・・・・・)ええ、そうですね。
この他に店の客にインタビューしたり、買いだめがあったというウワサのある他のスーパーでも聞き取りを行なったが、いずれの場合にも、パニック的な買いだめ騒ぎがあったという事実を確認することはできなかった。このように、余震情報騒ぎに関する限り、買いだめパニックはうわさの中で形成された神話にすぎず、現実にはほとんど発生していなかったと結論づけることができる。このような「パニック流言」がどうして拡がるかということの説明は難しいが、人々の潜在的不安を背景に、地震流言の一変種として発生したのではないかと推測される。
「パニック」報道発生原因の解明
ローゼングレンが調査したスウェーデンの事例において、マス・メディアが何故聴取者の反応を誤って「パニック」と報道したのか、その原因を探するために,事件報道の担当責任者に対するインタビュー調査を実施した。その結果,ラジオのニュースで事実が歪められて放送された原因として、次の二つの点があるととがわかった。
第一に,ラジオ局の報道担当者は,最初地方紙の編集記者からバルセベックで原発事故があったという連絡を受けて非常に驚いた。それから間もなく,ラジオ局には一般市民から々に電話がかかってきた。このため,ラジオ局の担当者は、番組を開いた住民の間で何か異常な騒ぎが起とっているという印象を受けることになった。
第二に、ラジオ局では事件の第一報を入手したとき,ニュースの原稿締め切りが1時間足らず後に迫っており、現地へ行って直接確認をとる時間的余裕がなかったため、マルメとランドの察への竜話取材で済ませる他なかった。その頃、察にも興奮した住民からの問い合せ電話が殺到しており、察官はラジオ局の取材に対して、市民から多くの話を受けたことを認めると共に、受けた電話の中で特に変わった内容のものを教えた。その結果,ラジオ局ではパニックが起きたという確信を得るに至ったのである。
こうして、ラジオ・ニュースでは、事件を次のように「原発パニック」として次のように伝えた。
「2つの地域にある普察・消防署・マス・メディアの電話交換機が輻輳した。人々は避難所に列を作っている。バルセベック原発周辺地域の大群集が移動を開始した。マルメの人々は、貴重品を集めて、車で南方へ向かった。」このニュースによって、「パニックが発生した」という状況定義が行なわれ、それ以降のニュースでも「バルセベック原発パニック」という言葉が引き続き使用されることによって既成事実化され、社会的にもそのまま受容されることになったのである。
平塚市の「誤報醬戒言」事件においても,これとほぼ同様のプロセスが進行したことが筆者らの実態調査によってある程度明らかになった(三上, 1984)。この調査では、朝日・読売・神奈川3紙の記者や編集者にインタビューを行ない、事件当夜の取材・報道過程の解明を試みた。ここでは、その中で筆者が担当した読売新聞の事例を紹介しておきたい。事件の取材・報道を主に担当した部局は、東京本社の編集部と整理部、横浜支局,および平塚通信部である。このうち、直接本文および前文の記事の原稿を作成し、送稿したのは、横浜支局および平塚通信部の記者だった。そこで、このふたりの動きを中心として,誤報事件の取材を通じて「パニック」記事が作られていったプロセスを辿ってみよう。
事件の第一報はまず横浜支局に入った。午後9時5分ごろ、平塚市内の読者から「いま広報無線で放送しているが、警戒宣言があったのか」という問い合せがあった。これを開いて、横浜支局の記者は、最初何かの間違いではないかと半半疑だった。というのは、この種のイタズラ電話は以前にも経験していたからである。しかし、とにかく取材を開始することにし,そのとき支局内にいた4人全員に指示して、電話取材に当らせた。
まず、気象台に電話を入れ、警戒宣言が本当に出たのかどうか確認したところ、「そんな警報は出していない」というので、もし実際に出たとすれば誤報であることが確認された。次に、県に電話をしたところ、「そういう話は聞いていない」というので、平塚瞥察に電話して問いあわせた。すると、「そういう話があるので電話が殺到している」という返事だったので、誤報が出たのはどうやら事実らしい,と判断した。そこで、平塚市役所へ電話したが、代表番号は話し中で通じなかった。
A記者と支局デスクは,こうした初動の電話取材を通じて、この事件について、もし誤報が事実だとすればこれは東海地震では初めてのケースであり、ニュースバリューとしてはかなり高く,「全国版の頭を張れるニュースだ」と判断した。以後の取材は、この基本方針に基づいて行なわれることになった。
平塚通信部駐在のB記者との電話連絡は、輻輳のためなかなか取れなかったが、約10分後にやっとつながった。A記者はB記者に対し「大変なことが起きているようだね」と言ったが、B記者はこのとき平塚で何が起きているかをほとんど把握してはいなかった。当日の夜9時ごろ、B記者は平塚市内の自宅で家族とともに、テレビをみたり新聞を読んだりしてくつろいでいた。9時8分すぎ、突然外でスビーカーらしきものから何かワーワーと音がするので、何事かと思い、窓を開けてみたがはっきりせず、妻と一体何だろうと話し合った。最初は広報無線からの放送とは気づかず、廃品回収車の拡声器か何かかと思ったが、その時間にしてはおかしいので、調べてみようという気持になった。
まず、警察署に電話してみたが通じなかったので、次に市役所、消防署の順に電話してみたが、結局どこにもつながらなかった。横浜支局のA記者から電話が入ったのはそのときである。B記者はまだ正確な情報を何一つ得ていなかったが、「大変なことが起きているようだね」という問いかけに対し、突差に「ええそうですね。そちらにはどんな情報が入っていますか?」と受け返し、「誤報が出たという情報が入っている」という返事を得て初めて事件の発生を知ることになった。
この会話で取材の打合せが行なわれた。A記者も支局デスクも「平塚ではパニックが起きている」と思っていたので、恐らく市民が街の中をゾロゾロ歩いているだろうと想像し、「市役所へ行く途中でパニック状態になっている住民の表情がわかるような写真を撮れ」とB記者に指示した。B記者は直ちにカメラを片手に市役所の記者クラブへと急いだ。しかし、市役所へ向かう途中,市民の様子は冷静で「とくに混乱は起きていない」という印象を受けた。A記者に指示されたような絵になる被写体も見つけることはできなかった。その夜一杯、B記者は市役所内の記者クラブにいて、誤報関係者の取材をしたり、8~9人の市民に電話で取材をしたが、市民の反応は冷静だったため、誤報の原因解明に取材のポイントをおくことにし、取材の大半はこれに費やされることになった。
一方、横浜支局では、B記者から市民の反応が予想外に冷静だとの情報を得、またパニックの証拠となるような写真も入手できなかったので、当初の「バニックは起きた」との判断が若干猫らいだ。しかし、支局で平塚市の電話帳をめくって市民に直接電話取材をしたととろ、「防災頭巾をかぶったりして家の中でワーワーやっている」人が何人かいたし、「避難袋を抱えて外に出ている人もいる」と答えた市民もいた。また、B記者からの連絡でも,市役所へ行く途中、外に出ている人を何人か見たということだったので、「完全なパニック」とはいえないまでも、それに近い状態が起きているのではないかと判断し、「パニック状態」と若干ニュアンスを弱めた表現にして記事を書き、東京本社へ送信したのである。
こうして「パニック」記事が作られることになったわけであるが、その主たる原因としては,当初から「パニックが起きた」とA記者が速断していたことの他に、締め切り時間が迫っていた上、現地での取材要員が1名しかおらず、充分な取材が出来なかったこと、および、取材して得た情報が誇張ないし歪曲して解釈されたことをあげることができる。
読売新聞の横浜支局に事件の第一報が入ったのは,31日(土)の午後9時すぎだったが、この時間帯だと首都圏以外向けの早版には間に合わなかった為,神奈川県全域を含む13版と東京・横浜を含む14版(最終版)に載せるととを目標に取材・編集が行なわれた。しかし、13版の締め切りまでには1時間半弱しか時間的余裕はなかった。記事全体の要約ともいえる「前文」をA記者自身が書いたのは午後11時頃であるが、この時点では,パニックが起きたかどうかを最終的に確認することはできず,前述のように「パニック状態」という若干曖味な表現で報道することになった。しかし,この記事が東京本社へ送られ、整理部が「見出し」をつけたときには,この微妙なニュアンスは伝わらず、「夜の警報パニック」というセンセーショナルで断定的な表現にされてしまったのである。
また、現地での取材人員の不足も、短時間で充分な情報を収集できなかった原因の一つに数えられる。当時、平塚通信部に駐在していた読売新開の取材要員はB記者だけであり、B記者は取材,写真撮影,送稿という一連の作業をほとんど一人で行なわなければならなかった。しかも,誤放送の原因解明に手間取ったため,市民の反応について充分な取材をすることができなかった。その結果,横浜支局の「パニック」判断をはっきりと否定するだけの情報を提供するまでには至らなかったのである。
現実を歪めた「パニック」報道が行なわれることになった最後の要因は、取材の過程で知らず知らずのうちに一定方向への誇張ないし歪曲が加えられたことにあったと考えられる。例えば、読売新聞の記事には電話取材で得た市民の証言が2例載っている。筆者を含む調査班が現地で聞き取り調査を実施していた折、そのうちの一人にたまたま行き合せたが、この市民によれば、読売新聞から電話取材を受けたが、同紙はその内容を著しく歪曲して記事にしたということである。この点について、読売新聞側からはこれを肯定する回答は得られなかったが、取材の際に、誘導尋問的な聞き方をしたり、相手の話の内容を記事にする際に、強調点を変えるケースがあることを認める回答が得られた。記者が取材内容を意図的に歪めることは一般に考えられないが、現地から遠く離れた所から「バニックが起きた」という先入見をもって市民への電話取材が行なわれた今回のような事例では、誘導尋問や強調点の移動(すなわちパニックに近い反応部分の誇張)を通じて、無意図的に「バニックが起きた」ことを裏づける方向へと情報が歪められて加工された可能性は否定できない。
以上を要約するならば、「擬似パニック」が形成される要因として、現実的ないし擬似的な脅威の集合的認知とこれを引き起こした社会不安とを背景として、(1)「パニック流言」が伝播すること,(2)マス・メディアの取材・編集担当者が「パニック・イメージ」に基づいて情報の収集と加工を行なうとと、(3)現地通部→支局→本社というタテ系列の情報伝達過程において末端からの情報が正確に上部まで伝わらず、最終的に最もセンセーショナルな「パニック」の見出しが選択されてしまうこと、などを指摘するととができよう。
参考文献(第7章)
Adoni,H.,and S.Mane ( 1984) Media and social construction of reality. Communication
Research, 11 (3): 323 - 340
Adoni,H.,A.A.Cohen,and S.Mane ( 1984) " Social reality and television news:Perceptual
dimensions of social conflicts in selected life area. "Journal of Broadcasting, 28: 33 - 49.
Berger,L.P.,and T.Luckmann ( 1967) The Social Construction of Reality. New York:Anchor Books.
山口節郎訳「日常世界の構成ーアイデンティティと社会の弁証法』新曜社
D.J.ブーアスティン『幻影(イメジ)の時代:マスコミが製造する事実』1964年、東京創元新社
Dayan, Daniel., and Katz, Elihu, 1992, Media events: The Live Broadcasting of History., Harvard University press. 浅見克彦訳, 1996, 『メディア・イベントー歴史をつくるメディア・セレモニー』青弓社
藤竹暁『現代マス・コミュニケーションの理論』1968年、日本放送出版協会
藤竹暁『テレビメディアの社会力』1985年、有斐閣選書
川端美樹, 三上俊治, 2001, How Television News Matters: Television News Viewing and Environmental Awareness in Japan. Keio Communication Review 23(23) 37-52 2001年3月
K. ラング、G.E. ラング「テレビ独自の現実再現とその効果|予備的研究」(W・シュラム編『新版 マス・コミュニケーション』学習院大学社会学研究室訳、東京創元新社、1968年)
G.E.ラング、K. ラング『政治とテレビ』荒木功他訳、1997年
W. リップマン , 1922=1987 , 『世論』, 掛川トミ子訳, 岩波文庫
三上俊治, 橋元良明, 水野博介, 1989, テレビによる社会的現実の認知に関する研究. 東京大学新聞研究所紀要 (38) 73-124 1989年1月
三上 俊治, 1987, 現実構成過程におけるマスメディアの影響力 -擬似環境論から培養分析, 東洋大学社会学部紀要 (24-2) 238-280 1987年3月
三上俊治「世論過程の動態」東洋大学社会学部紀要 (31-1) 123-210 1993年6月
三上俊治, 1993, 1993年7月衆議院選挙におけるマスメディアの役割. 東洋大学社会学部紀要 (31-2) 143-202 1994年3月
三上俊治, 1984, パニックおよび擬似パニックに関する実証的研究. 東洋大学社会学部紀要 (21) 155-202 1984年3月
三上俊治, 水野博介, 1978, 余震情報パニックの実態. 新聞研究 (4月号) 42-55 1978年4月
三上俊治, 竹下俊郎, 川端美樹, 1999, Influence of the Mass Media on the Public Awareness of Global Environmental Issues in Japan. Asian Geographer 18(18) 87-97 1999年7月
Steel, 『現代史の目撃者:リップマンとアメリカの世紀』
水野博介, 1994, 「1993年6月の皇太子成婚報道に関する実証的研究」「埼玉大学紀要 教養学部」第29卷 Pp.49-72
水野博介, 1998, 『メディア・コミュニケーションの理論』学文社
高橋徹・岡田直之・藤竹暁・由布祥子, 1959 「テレビと"孤独な群衆" 皇太子ご結婚報道についての東大・新聞研究所調査報告」『CBCレポート』1959年6月号, 3-13ページ
竹内郁郎「テレビ中継をめぐる功罪論」水原泰介、辻村明編『コミュニケーションの社会心理学』、1984年、東京大学出版会
第8章 培養理論
培養理論とは、1960年代後半に、アメリカのジョージ・ガーブナー(George Gerbner)によって提唱された、マスメディアの現実構成機能に関する実証的効果論である。
文化指標研究
ジョージ・ガーブナーは、1919年、ハンガリーのブダペストで生まれた。1939年、アメリカに渡り、UCLAの学士号を取得後、「サンフランシスコ・クロニクル」紙で新聞記者および編集者として短期間働いた。軍役に従事した後、南カリフォルニア大学で大学院に進学し、1955年にコミュニケーション学の博士号を取得。1964年にはフィラデルフィアにあるペンシルベニア大学のアネンバーグ・スクール・フォー・コミュニケーションの教授および学部長に就任した。1989年に学部長を退任したが、1994年まで同大学で教鞭を執り続けた。1973年、ガーブナーはマスコミュニケーションを理解するための新たなパラダイムを提唱した。このパラダイムは、文化指標研究と呼ばれ、制度過程分析、メッセージシステム(内容)分析、そして培養分析の3つの要素で構成されている。培養分析(または培養理論)は、メディア効果論における重要な理論的視点であり、視聴者の社会的現実に対する認識にテレビがどのように影響を与えるかを解明するものである。これに先立って、1967年、ガーブナーは「テレビ暴力プロファイル」を開発した。このツールは文化指標プロジェクトの一環として作成され、3000以上のテレビ番組と3万5000以上のキャラクターを網羅したデータベースを基に、プライムタイムのネットワーク放送番組における暴力の継続的かつ一貫したモニタリングを可能にした 。
コミュニケーション研究の歴史における他の多くのプロジェクトと同様に、「文化指標」は応用的な文脈で独立した資金を受けて開始された(Gerbner, 1969)。アメリカでは、マーティン・ルーサー・キングやボビー・ケネディの暗殺後の国内混乱の時期である1960年代後半に始まり、社会における暴力(テレビでの暴力も含む)を調査するために「暴力の原因と防止に関する全国委員会」が設立された。「文化指標プロジェクト」として後に知られる研究の初期段階で、ガーブナーらは、テレビでの暴力の程度を明らかにし、その性質を記述し、テレビの世界を長期的に監視するための基準を確立した(Gerbner, 1969)。1969年には、暴力の原因と防止に関する全国委員会の報告が公開される前に、議会が100万ドルを拠出し、「テレビと社会行動に関する外科医総監科学諮問委員会」を設立した。この時期に、「文化指標」を含む23のプロジェクトが資金を受けた。この研究では主に、ゴールデンタイムおよび週末の日中に放送されるネットワークドラマ番組の内容に焦点を当てた。こうして、培養分析に先立って、メッセージシステム分析のプロジェクトがスタートしたのである。
現代の大衆文化において、テレビの娯楽番組が果たす役割はきわめて大きい。日本人は平日に平均して約3時間テレビをみており、その中でも娯楽番組の視聴に費やす時間が圧倒的に多い。娯楽番組の中で、人びとの現実構成にもっとも大きな影響を与えるものがあるとすれば、それはテレビドラマであろう。現代のテレビドラマはリアリズムを基調としてつくられている。テーマは日常の家庭生活から、男女の恋愛、親子の葛藤、ビジネス活動、犯罪、病と死、社会問題に至るまで多種多様であるが、その多くは、われわれの身のまわりでいつ起こるかも知れないような出来事を扱っている。もちろん、視聴者の大半は、ドラマが所詮お話にすぎないということを十分に承知の上で、それを楽しんでいるわけである。ドラマの世界に浸っている間、視聴者はしばしば至高の現実としての<日常生活世界>から限定的意味領域である<ドラマ的現実>の世界に逃避することができるのである。そこでは、視聴者は、日常生活世界でのルールに代わって、ドラマを解釈するための固有の認知様式=解釈フレームを用いて、ドラマ的現実を主観的に再構成しているのである。ドラマの中の釜場人物が殺されたとしても、それを演じた俳優が実際に死んでしまったと思う人はまずないだろう。それはあくまでもお話の世界で起こった出来事にすぎないのである。
しかし、その一方で、われわれはドラマに登場する人物と同じようなタイプの人間が身のまわりにもいることを知っており、またそこで繰り広げられる人間ドラマと同じような出来事が現実世界のどこかで起こっていても不思議ではない、と感じている。また、テレビドラマに没入した一部の視験者が、登場人物の演じるパーソナリティや役柄を現実のそれと混同してしまう、というケースも少なからずみられる。医者を演じた俳優が健康相談を受けたり、悪役を演じた俳優が日常生活でも腹黒い性格をもっているかのような印象をもたれてしまうことは決して珍しいことではない。テレビが茶の間に入り込み日常生活に浸透した<ふだん着>のメディアであり、その映像による表現力がきわめてりアルであるがゆえに、テレビドラマの構成する現実への移行は、シュッツのいうような「ショックによる飛麗」を伴うことなく、ごく自然に行われる。それだけ、ドラマ的現実と各観的現実との間の境界は不明瞭なものになりやすいともいえる。
したがって、視職者の属性、視環境、客観的現実へのアクセス可能性のいかんによっては、視験者がテレビドラマの中で構成される現実を客観的現実と混同する可能性もあるわけである。その意味でも、<ドラマ的現実>と<客観的現実>とを比較してみることは、<主観的現実>椎成への影響を考築する上でも、不可欠の手続きといえよう。ちなみに、後述するように、ガーブナーらの<文化指標アプローチ>においては、培養過程を分析するための前段階のステップとして、メディア内容の分析結果と客観的現実との比較照合が行われているのである。
(1)登場人物の属性
a.性別
もし、テレビドラマが現実を忠実に反映しているならば、登場人物の男女比は全体としては1:1でなければならないはずである。ところが、従来のドラマの内容分析をみると、欧米諸国でも日本でも共通して、女性よりも男性の登場する割合のほうが高い、という結果が得られている(村松、1982.p.183)。例えば、ガーブナーらの内容析によると、テレビドラマの主役の約4分の3は男性であった(Gerbner et al., 1976 ;Gerbner et al., 1986)。グリーンバーグらの分析したテレビドラマにおいても、登場人物の71~73%は男性だった(Greenberg et al., 1980a)。
b.年齢
次に、登場人物の年齢分布をみると、どの内容分析においても共通して、20代から40代までの年齢層に集中している、という結果が得られている(Gerbner et al, 1980 b)。その例として、テレビドラマ(平日のブライム・タイム)の登場人物の年齢分布とアメリカの現実の年齢別人日統計データとを比較したガープナーらの分析結果を図2に示す(Gerbner et al., 1980b)。明らかに、現実の分布とはかなり食い違っていることがわかる。20代から40代というのは、人生でもっとも活動力の盛んな時期であり、恋愛、結婚、出産、就職、成功、不倫、離婚など、ドラマチックな出来事がもっとも起こりやすい時期である。したがってドラマにしやすい、ということが、こうした年齢的な偏りを生む最大の原因であろう。
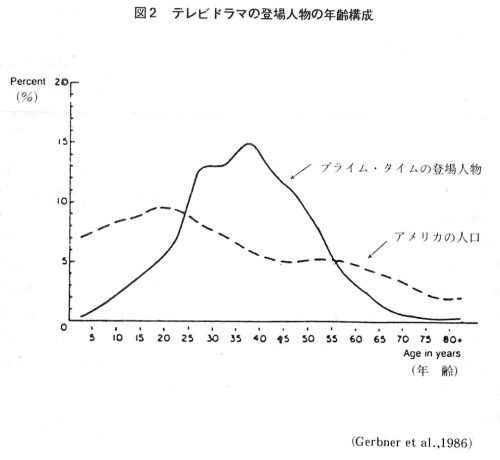
c.職業
登場人物の職業もしくは活動領域をみると、もっとも多いのは専門職であり、サービス業従事者、管理職がこれに続いている。これら3つの職業の比率は、いずれも現実の世界での比率を大幅に上回っている。逆に、事務職や工員などは現実の比率を大幅に下回っていることがわかる。ガーブナーによると、ブルーカラー労働者とサービス業従事者の割合は、アメリカの有職者の67%を占めているにもかかわらず、ドラマの登場人物の中では25%を占めるにすぎないという(Gerbner et al., 1986)。さらに興味深いのは、警察官や弁護士など、犯罪の取締りに関わる職業に就いている人が、現実には有職者人口の1%にすぎないのに、ブルーカラーやサービス業従事者より3倍も多くドラマに登場することである(Gerbner et al., 1977b, 1986)。
d. 社会階層
登場人物の所属する社会階層をみると、10人のうち約7人は、社会階層を5段階に分けたとき「中の中」に相当する人びとである、という分析結果がある(Gerbner et al, 1986)。これは実態とは食い違うものであるが、国民総中流階級という<中流幻想>を反映したものといえるかもしれない。いわば、裕福で社会的に成功した人びとがテレビドラマでは頻繁に登場しているのである(Gerbner et al. 1976;1986)。
(2)登場人物の行為
客観的現実との比較を射程に入れつつ、テレビドラマの登場人物の行為を分析した研究としては、ガープナーらによる「暴力シーン」(violence erisode)の詳細な内容分析がある。これは、登場人物の行為に関する分析としてはもっとも精級なものであり、また後述する指養分析とも深い関わりをつので、ここで少し詳しく紹介しておこう。
まず、(暴力)(violence)という言葉の定義であるが、ガーブナーはこれを「自分自身または他者に対する(武器を用いた、あるいは用いない)物理力の顕在的な行使であり、傷つけられるか殺されるという苦痛を強要したり、実際に傷つけたり殺したりする行為」と定義している(Gerbner et al.1986,1978)。テレビ・ドラマに出てくるく暴力>を量的に測定するために、ガーブナーらは「番組率」(prevalence)、「行為率」(rate)、「役割」(role)という3つの変数を定義している(Gerbner et al..1978)。「番組率」(%P)とは、全サンプルの中で、暴力シーンを少しでも含む番組の割合のことをいう。「行為率」というのは、1番組あたりの暴力シーン数(R/P)、あるいは、1時間あたりの暴力シーン数(R/H)をさしている。また、「役割」は全登場人物の中で暴力行為における加害者または被害者の占める割合のことであり、「加害者」、「被害者」、「暴力関与者」(%V)、「殺人者」、「殺人者」、「殺人の関与者」(%K)の6種類について、それぞれの割合を測定している。
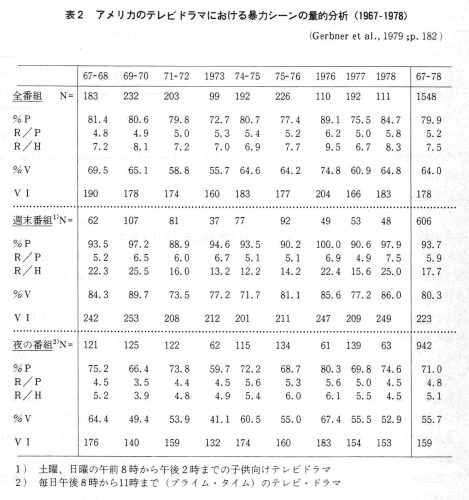
以上の測定データをもとに、ガーブナーらは<暴力指数>(Violence Index;VI)を構成している。これは、「番組スコア」(program score;Ps)と「人物スコア」(character score;CS)とを合計した数値である(VI=PS+CS)。ここで、「番組スコア」と「人物スコア」はそれぞれ次のように定式化されている。
PS=(%P)+2(R/P)+2(R/H)
CS=(%V)+(%K)
ただし、(%V)は「全登場人物の中で、暴力の加害者または被害者の占める割合」を、(%K)は「全登場人物の中で殺人の加害者または被害者の占める割合」を意味している。
12年間を通しての数値でみると、次のようなことがわかる。つまり、全番組の約80%が力シーンを含んでおり、1番組あたりの暴力シーン数は平均5、2回である。また、ドラマの全登場人物の中で暴力に関与する人物の割合は64%に達している。このような傾向は、多少の変動はあるとはいえ、12年間を通してほぼ一定している。また、暴力指数については、1967年から1973年までは減少傾向をみせたが、74年になると再び上昇し、その後もとくに減少している気配はない。さらに、子供向け番組とプライム・タイムの番組とを比較してみると、いずれの指標についても、子供向け番組のほうが暴力的要素を多く含んでいることがわかる。女性は男性よりも被害者になる割合が高い。その中でもとくに、老人の女性、若い女性、未婚の女性、社会階層の低い女性、外国の女性、非白人の女性が被害者になりやすい。また、傷つけられるよりもむしろ殺される率が比較的高いのは、老人の男性、既婚男性、社会階層の低い人、外国人、非白人の男性などである。このようなプロフィールは、長期間にわたって不変であることをガープナーは示している。
このように、アメリカのテレビドラマでは、毎日のように、暴力が氾濫しているわけであるが、ガープナーらは、こうした<ドラマ的現実>は、各観的現実とは著しく食い違ったものであることを指摘している。すなわち、1973年の警察統計によれば、アメリカ国内でも実際の犯罪件数は、人口100人あたり0.41件にすぎず、何らかの犯罪をおかした人のうち、暴力的な犯罪(暴力、傷害、殺人など)をおかした人の割合は10%にとどまっているのである(Gerbner et al., 1977b)。
テレビの培養分析
初期の文化指標の構想では、文化制度の一つとしてのマスメディアが、特定の価値観がコンテンツの制作に影響を与え、さらにそれが個人の影響を及ぼすという視点だったが、次第に対象となるメディアがテレビに絞られるようになった。というのは、テレビからのメッセージが共通のシンボル環境の中心になっているからである。
テレビが登場して以来、われわれをとりまくシンボル環境は激変した。テレビは毎日大量のメッセージを人びとに提供し続けており、アメリカ国民は1日平均3時間以上もテレビを見ている。新聞などと違って、テレビはだれでも容易に近づくことのできるメディアである。そこから流れてくるメッセージは、世の中で何が起こっているか、人びとがどのように生きているのか、大切なことは何か、日常生活でどのように生きるべきかをわれわれに教えてくれる。このようにして、テレビは、かって数会の牧師が定期的な説数を通じて地域社会の人びとに対して果たしていたのと同じような<シンボル機能>を、はるかに広範囲の異質な大衆に対して果たすようになった。いまや、「テレビから反復的に提供される大量のメッセージとイメージは、共通のシンボル環境の主流(mainstream)を形づくっているのである」(Gerbner et al., 1986,p. 18)。
以上のような認識の上に立って、ガーブナーらは、テレビがその圧倒的に高い普及率と視職行動の非選択性・反復性のゆえに、人びとに対して共有された<現実>感覚や価値観を培養している、と主張した(Gerbner et al.,1976)。このような人びとの共通意識は、従来の効果研究が扱ったような特定の態度や意見ではなく、もっと一般的なレベルでの信念や価値観だ、とガープナーらはいう。それは、われわれが社会的現実について認知する際の「前提的観念」(premise)とでも呼べるような基底的意識であり、俗にく文化>と呼ばれるものに近い。それは社会的現実についての共有され、受け継がれたパターンの集合体である。そして、テレビは既存の社会秩序に組み込まれた機関であるがゆえに、現行の秩序や支配的な規範、価値を維持し強化する役割を果たしている、とガーブナーらは述べる (Gerbner et al., 1976)。
こうしたテレビの培養効果を実証的に研究するための方法として、ガーブナーらは<文化指標アプローチ (cultural indicator approach)>を採用したのである。(Gerbner,1969,1973)。ガーブナーによれば、人びとの意見や信念や価値観に及ぼすテレビの影響力を知るためには、まず、テレビから流されるメッセージ・システムについての体系的かつ包括的な分析を長期間にわたって行うことが必要である。これは「メッセージ・システム分析」(message system analysis)と呼ばれる。先に紹介したテレビの「暴力シーン」に関する分析は、その最大の成果といえる。また、そうしたメッセージがどのような制度的過程(権力、役割、社会関係)を通じて選択、形成、伝達されるかを明らかにすることが必要である。これは「制度過程分析」(institutional process analysis)と呼ばれるものである(Gerbner, 1966)。
そして、以上二つの研究にもとづいて、テレビのメッセージが、長期的・反復的・非選択的な視聴を通じて、人びとに共通のイメージや価値観を培養する過程を実証的に研究することが必要になる。これが<培養分析>(cultivation analysis)と呼ばれるものである。ただし、制度過程分析に関する具体的な研究はほとんど行われていないので、ここでは取り上げない。以下では、3番目の「培養分析」について詳しく検討することにしたい。
培養分析の方法と実際
培養分析は具体的にどのような手織きを用いて行われ、また分析の結果、どのような知見が得られているのだろうか。この点について、ガーブナーらの研究を中心にまとめておこう。
前述のように、培養分析は長期的、反復的、非選択的なテレビ視聴が人びとの現実構成に及ぼす影響を実証的に研究することを目的としている。そこからただちに、「テレビをよく見るグループ(高視聴者)とあまり見ないグループ(低視聴者)を比較すると、前者のほうがテレビの提示する現実像を受け入れやすい」という仮説が導き出される。ただし、もしテレビの提示する<記号的現実>が客観的現実の実態に近い場合には、両者の違いを検出することは困難だし、そのこと自体あまり意味はないので、取り上げるべき<現実>は、「暴力シーン」のように、テレビの描写と実態との間に大きな食い違いがあるようなものに限定せざるを得ない。したがって、培養分析を行うためには、まずテレビの内容分析を行い、それと客観的現実との比較照合を行うことが原則的には必要である(Gerbner et al.,1986)。
1968年から77年までのプライム・タイムに放送されたアメリカのテレビ・ドラマの中では、主要登場人物の64%と登場人物の30%が加害者または被害者として暴力シーンに関与している、という分析結果が得られている。ところが、1970年の国勢調査データによれば、暴力的犯罪者の占める比率は100人当たり0.32%にすぎない。つまり、テレビドラマでは現実をはるかに上回る割合で暴力シーンが登場しているわけである。もしこの仮説が正しいとすれば、テレビ高視職者は低視聴者に比べると、テレビに描かれる<暴力>像に近い現実認知をもちやすくなることが予想される。つまり、テレビ高視聴者の方が暴力の比率について過大な認知をしやすいという種向がみられるだろう。
この点を調べるために、視聴者に対して、実生活での暴力の経験について推定してもらい、テレビ的現実に近い数字と実態に近い数字のうち一方を選ばせるという質問を行った。具体的な質問は次のようなものである。「ある1週間にあなたが何らかの暴力に関わるチャンスはどれくらいあると思いますか。それは10日に1回の割合でしょうか、それども100回に1回の割合でしょうか」。「10回に1回の割合」というのはテレビ的現実に近い数字であり、<テレビ寄りの回答>とみなせる。また、「100回に1回」というのは、より実態に近い数字であり、これは<現実寄りの回答>といえる。ガーブナーらは、この他にもテレビの長時間視聴が影響を与えそうな現実認知について、同様の質問をつくり、繰り返し様々なサンプルを対象として調査を実施したり、既存の調査データを分析した。
その結果、高視聴者は低視聴者に比べてテレビ寄りの回答が有意に高いという一貫した傾向が見出された、としている。なお、ガーブナーらは、テレビ寄りの回答率における高視聴者と低視聴者との間の差を<培養格差>(cultivation differential ; CD)と名づけ、これを培養効果の指標として用いている。一般に、CDの値が+で大きくなるにつれて、培養効果も大きくなると解釈することができる。
暴力シーンへの接触と特に強い関連の見出された現実認知としては、①危険の知覚や恐怖感、②対人的な不感や疎外感、の二つがある。それぞれについて、具体的調査データを検討してみよう。
(1)暴力についての危険の知覚と恐怖感
テレビの高視聴者は、テレビ・ドラマの中に氾濫する暴力に繰り返し頻繁に接触することによって、低視聴者に比べると、現実の世界でも暴力がはびこっており、危険に満ち満ちている、というイメージを抱きやすいだろう、という仮説にもとづいて、ガープナーらはこうした危険の認知に関するいくつかの設問を作り、さまざまなサンプルを対象として面接調査を行っている。その結果、いずれの質問についても、高視聴者はそれ以外の人に比べてテレビ寄りの回答をする傾向がみられた。さらに、第3の変数による影響を除去するために、年齢、学歴、新聞関読度、人種、居住地域、所得などでコントロールした上で、テレビ視聴量と現実認知との関連性を調べたところ、大部分の変数とそれぞれのサブ・グループにおいても+のCD値が得られた。
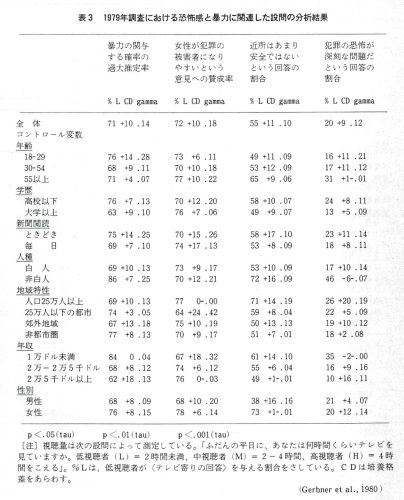
(2)対人不信感と疎外感
このように、テレビの高視聴者は、自分の住む世界を実態以上に暴力と危険に満ちたものとして認知するようになる結果、「大抵の人は信用できない」とか「自分のことしか考えていない人が多い」といった対人的不信感を抱きやすい、という傾向が見出されている(Gerbner et al,1980a)。ガーブナーらはこれを「冷たい世間」症候群("mean world”syndrome)と名づけている。具体的な設問についてみると、例えば、「人びとは大抵自分のことしか考えていない」、あるいは「他の人びととつきあうときには、用心するに越したことはない」と考える人は、テレビを長時間見る人に比較的多い、という講査結果が得られている。性別、学歴、新聞関読度などでコントロールしても、この傾向に変化はみられない。
一方、培養分析を積み重ねるにつれて、培養過程がより複雑に作用することが次第に明らかになってきた。つまり、人びとのおかれた生活状況や集団特性などの要因によって培養効果の程度が異なることが分かってきたのである。ガーブナーらは、こうした培養効果の差を生じる原因の大半が、<主流形成>(mainstreaming)と<共鳴現象>(resonance)という二種類の動的プロセスによって説明できると考えた(Gerbner et al., 1980a)。
まず、<主流形成>というのは、「低視聴者が多様な意見に分かれているような属性集団において、高視聴者の間で共通の意識が形成されること」を意味している(Gerbner et al,,1980a)。例えば、一般に高学歴層や高所得層にはテレビの低視聴者が比較的多いことが知られており、その低視聴者はテレビ的現実を受容する可能性がもっとも低い。しかし、高学歴層、高所得層における高視聴者は、低学歴層、低所得層と同じようにテレビ的現実に偏った共通の意識を抱きやすい、という結果が得られている。(Gerbner et al.,1980a)。
次に、<共鳴現象>というのは、「日常の生活環境がテレビ内容と待合する場合に、培養効果が促進される」という、一種の「相乗効果」作用を意味している。例えば、暴力への不安感がもっとも培養されやすいのは、都市の犯罪多発地域の住民である(Doob and MacDonald. 1979; Gerbner et al., 1980 a ) 。
培養分析の新たな展開
次に、1980年代に入ってからの指養分析の研究動向と今後の課題について、①研究領域の拡大、②研究地域の拡大、③メディア内容の分化と拡大、④効果レベルの拡大、⑤培養効果形成要因の研究、⑥他の関連研究との理論的統合、という5つの側面からまとめておきたい。
(1)研究領域の拡大
70年代の搭養分析は、ガーブナーらの<文化指標アプローチ>にもとづいて、テレビの、暴力シーンが視聴者の現実構成に及ぼす影響に主たる焦点が当てられていたが、最近になって、く社会的現実>の他の領域に培養分析を適用する研究が次々と現われるようになった。そのような<社会的現実>の研究を列挙すると、①政治的志向性、②医者に対する態度、③人種問題に対する意識、④高齢者についての信念、⑤性差別、⑥性役割の認知、⑦生活水準についての知覚、などがある。これらの研究の大半において、一定の培養効果の存在が確認されている。
(2)調査地域の拡大
培養分析は、もともとペンシルバニア大学アネンバーグ・コミュニケーション研究所でガーブナーを中心とするグループが始めたものであり、この理論それ自体、テレビの平均視聴時間の長いアメリカ社会を念頭においてつくられたものである。したがって、当初はアメリカ国内での調査研究に限定されていた。しかし、その後、ヨーロッパ、カナダ、オーストラリアなどでも培養分析を適用した調査研究がいくつか行われるようになった。例えば、ウォーバーは、イギリスのテレビドラマが現実認知に及ぼす悪響を分析しているが、その結果、高視聴者と低視聴者との間で現実認知に有意差は見出されなかった(Wober, 1978)。この点については、ホーキンス(Hawkins and Pingree,1983)が指摘するように、イギリスではテレビドラマに暴力シーンの出てくる比率がアメリカに比べてはるかに低いことや、イギリス人の平均テレビ視職時間がアメリカに比べて著しく短いこと、などの特殊要因を考えれば、当然の結果といえよう。一方、オーストラリアでの暴力番組イメージの認知に及ぼすテレビ視職の影響を調査したピングリーとホーキンスの研究では、培養効果が確認されている(Pingree and Hawkins, 1981)。
(3)メディア内容の分化と拡大
ハーシュは、ガーブナーらの研究に対する批判の中で、指養分析のように、テレビ内容全体を扱うのではなく、特定の番組やジャンルへの接触と現実構成との関連性をもっと重視しなければならない、と指摘している(Hirsch, 1980a)。また、ホーキンスとビングリーも、番組ジャンルによって特養効果の大きさが異なる可能性を調査データによって示唆している(Hawkins and Pingree, 1980)。このように、テレビ番組のタイプによって増養効果の差があることは、すでに指摘したように、テレビの内容自体がく多元的現実)を構成していること、それぞれの<現実>に対する認知様式(解釈フレーム)が異なっていること、等を考えれば、当然の結果といえる。また、ラジオ聴取がテレビ接触と同程度の培養効果をもつというハーシュ(Hirsch,1980)の指摘からも推定されるように、テレビ以外のさまざまなメディアの持つ<培養効果>についても注意を向けることが必要であろう。
(4) レベルの拡大
培養分析においては、メディア内容が現実世界についての知覚に及ぼす影響の研究が中心だが、次第に「信念」「価値観」「態度」などまでも含めて、培養効果を研究するようになってきた。ガーブナーらは、ホーキンスらにならって、これを「第二次の培養分析」(second-order cultivationis)と呼んでいる(Gerbner et al.,1986)。
テレビの継続的な高視聴が態度レベルにまで強い最響を及ぼす可能性のあるグループは、少年など限られた特性の人びとである可能性が強い。一般成人に対しても、態度レベルの培養効果が強力に作用すると考えるのは、非現実的な仮定であろう。さらに、研究の対象は、認知、評価的なレベルまで含めた<現実構成>への影響の有無だけにとどまるべきものではない。問題はむしろ、こうした<現実構成>への影響がさらに、(行動)にまで影響を及ぼすかどうかという点であろう(Hawkins and Pingree, 1983)。今後、この面での研究を進めていくことが大きな課題といえよう。
(5)培養効果形成要因の研究
ガープナーらは、指養効果が形成されるダイナミックなプロセスが<主流形成>と<共鳴現象>という系統的なメカニズムによって生じるとしたが、このようなプロセスそれ自体は、視聴者の置かれている日常生活環境のさまざまな特性や、視聴者のもつさまざまな個人的特性、テレビ視聴行動の特性などによって規定されているものと考えられる。ホーキンスとピングリーは、培養効果が形成される条件として、①情報処理能力、②テレビ・メッセージに対する批判的な態度、③視聴者自身の経験や他のメディアの利用状況、④テレビ視聴における選択性の程度、⑤集団凝集性などの社会構造的要因、などを指摘している。またアドーニらは、日常生活世界の関連性領域における<身近さ一疎遠さ>の位置づけと対応したテレビ・メディアへの依存度を現実構成効果の重要な規定要因と考えている (Adoni et al., 1984) 。以上あげたようなテレビ視聴による培養効果形成の要因は、現実には複雑に絡み合いながら作用しているものと考えられる。こうした諸要因について、今後さらに系統的かつ実証的な分析を深めていくことが必要と思われる。
日本での培養理論研究
培養理論が日本で初めて紹介されたのは、1980年代に入ってからである。村松泰子(1982)、三上俊治(1987、1993)、三上俊治・水野博介・橋元良明(1989)、水野博介(1991)、斉藤慎一・川端美樹(1991)、斉藤慎一(1992、2002、2007)、中村功(1993)などが培養理論について、レビューや実証研究の結果を発表している。なお、"Cultivation Theory"の日本語訳は、当初、「教化理論」「涵養理論」「培養理論」など筆者によってバラバラで統一されていなかったが、村松(1981)、三上(1987)、斉藤(1992)による詳しい紹介論文が出て以降、次第に「培養理論」に統一されるようになった。現在では、ほぼこの訳語で定着するに至っている。
研究レビュー
村松(1982)は、ガーブナーの「文化指標」論と「培養過程」分析をいち早く日本に紹介した論文である。「テレビは、大量に伝達され、人々に共有されるメッセージのシステムである。社会は、このようなメッセージ・システムを通じて、人間存在をめぐる現実や価値について、人々に共有される観念を培養していく。このメッセージ・システムが変化すれば、人々を方向づけている共有されたシンボル環境も遅かれ早かれ変貌を遂げていく。この変貌の性格や速さを捉えるための指標が「文化指標」である」と、文化指標について的確な紹介を行なっている。また、文化指標としてのメッセージ・システムの分析を「メッセージ・システムの分析」「制度的側面の分析」「培養過程の分析」という3つの領域の一つであることも合わせて紹介している。その上で、ガーブナーが1970年に行なった暴力描写の内容分析について詳しく紹介している。
三上(1987)は、現実の社会的構成過程におけるマスメディアの役割について考察したアドーニとメインの論文(Adoni & Mane, 1984)とリップマンの擬似環境論のモデルをもとに、<客観的現実>」<記号的現実><主観的現実>という3つの現実モデルを再構成し、
(1) マスメディアの描く世界(記号的現実)は、現実の世界(客観的現実)とどの程度違っているか、またどのように現実を歪めているか
(2) マスメディアの描く世界(記号的現実)は、受け手の現実構成(主観的現実)にどのような影響を及ぼしているか
について、既存のメディア効果論の文献をレビューしている。そして、テレビにおける<ドラマ的現実>の構成に関する研究として、文化的指標アプローチと培養分析について、詳しい解説を加えている。本論文での培養理論のレビューは、日本語での最初の本格的な解説となっている。
水野(1991)は、文化指標研究と涵養効果分析(培養分析のこと)を単独に取り上げて考察した最初の日本語論文である。本論文では、ガーブナーが1960年代に文化指標研究を立ち上げた経緯を歴史的背景に沿って解説するとともに、テレビが安定したスタイルを持った生活と環境の中で非選択的に接触される結果、家庭や学校、教会に代わって社会化の機能を果たし、人々の現実認識を涵養しているという「涵養効果分析」の基本的考え方を紹介している。そして、暴力プロフィール、涵養効果格差などの基本的研究成果を紹介し、最近の涵養効果研究の成果についても広く解説している。最後に、文化指標研究において蓄積されてきたデータをもとに、長期的な内容の変化を分析することによって、テレビの文化的機能について解明する道が開けるとの展望を示している。
斉藤(1992)は、培養理論の概要を紹介するとともに、培養理論の問題点を整理し、培養理論はいくつかの点で修正が必要であり、今後の課題として因果関係の特定、培養理論の枠組みの中での視聴者のメッセージ解釈の問題、心理学的メカニズムの解明の必要性があることを明らかにした。因果関係については、「テレビ視聴が現実認識に影響する」という考え方と「社会的現実の認識のあり方がテレビ視聴行動を規定する」という考え方があり、前者を主として想定していた従来の培養理論に対しては批判的な研究が相次いでいると指摘している。視聴者のメッセージ解釈については、培養理論では内容分析により明らかにされたテレビの世界を、そのまま視聴者のテレビメッセージ解釈の仕方と考えていた。しかし、実際には視聴者はメッセージ内容の知覚や解釈を能動的に行なっており、メッセージ解釈における多義性を考慮すべきだ、という批判があると指摘している。また、培養理論の基本的前提である「テレビ視聴の非選択性」についても、多くの批判がなされていることを指摘し、特定タイプの番組視聴量と現実認識との関係を調べる方が論理的だとしている。最後に、培養効果過程における心理学的なメカニズムの解明が残されていると述べている。
斉藤 (2002)は、前掲論文以降の培養理論の展開をレビューし、培養理論をめぐる論争点を整理し直している。まず、テレビ視聴量と現実認識との間に見られる関連が擬似相関ではないかという問題については、多くの研究で擬似相関ではないという結果が得られている。因果関係の有無については、パネル調査を用いて因果関係を示する研究がある。また、培養効果が生じる際の心理的メカニズムを解明する研究も進んでおり、テレビ視聴が現実認識に一定の影響を及ぼしていることが示されている。次に、培養効果の独立変数として、「テレビ全体の視聴量」を用いるか、「特定ジャンル(番組)の視聴量」を用いるかで論争が行われてきたが、斉藤は、最近の培養理論の研究動向をもとに、特定ジャンルの視聴量を独立変数として用いた研究も培養理論とみなすべきだと指摘している。最後に、今後の検討課題として、メディア環境の問題を取り上げ「今後仮に、多チャンネル化に伴って番組内容も質的に多様化し、視聴者の細分化や分極化も進んでいくとするなら、培養理論もテレビ全体に共通するメッセージだけを扱うものだとは言っていられなくなるのではないか」としている。
次に、日本でこれまでに行われた文化指標及び培養効果に関する実証的研究の事例をいくつか紹介しよう。
テレビによる社会的現実の認知に関する研究(三上他, 1989)
調査の概要:
大学生235名に対し、特定のテレビニュースを視聴してもらい、1週間後にアンケート調査を実施。主な調査項目は、テレビニュースの視聴有無、普段のマスメディア接触、犯罪、「自殺、エイズに関する認知、短期的効果測定のための項目。
調査結果:
本研究は、培養効果を日本では初めて調査データによって実証的に検証したものである。アメリカでは、テレビドラマの内容分析によって、暴力がテレビドラマに氾濫しているという知見があり、ガーブナーらは、こうした内容上のバイアスが受け手の累積的・反復的視聴を通じて、暴力的な犯罪に対する過大な認知を培養しているという仮説を立て、調査データで検証した。具体的には、ある1週間に実生活で暴力に巻き込まれる確率を推定してもらい、テレビよりの回答(10回に1回)と実態に近い回答(100回に1回)のうち1つだけを選んでもらった。その結果、テレビ高接触群は低接触群に比べてテレビよりの回答が多い、つまり暴力に関わるチャンスを過大に評価するという傾向が見出された。日本でも、岩男ら(1981)の研究によって、アメリカと同様に暴力がテレビに氾濫しているという結果が得られている。
三上らは、培養効果を検証するために、今後1年以内に暴力的事件に巻き込まれる可能性に対する設問の回答とテレビニュース視聴度との関連を調べたところ、ガーブナーらの研究とは反対に、テレビニュースへの接触度の高いグループでは、むしろ犯罪に巻き込まれる可能性を低く評価しやすいという傾向が見られた。また、これとは別の設問で、最近1年間の日米の殺人犯罪件数を別々に推定したもらい、これをテレビニュース視聴量別に分析した。その結果、アメリカの犯罪件数については、培養効果仮説で予想されるように、テレビニュース接触度が高くなるにつれて、殺人発生の推定件数は多くなっていた。これにたいし、日本での殺人件数については、逆にテレビ接触度の高い人ほど件数を少なめに推定するという傾向が見られた。このように、日本では培養効果仮説は必ずしも支持されなかった。ただし、本研究で用いた設問はガーブナーらの調査とは若干異なっていること、データの分析方法がオリジナルの培養効果の分析と異なっていることなど、若干の問題も含んでいる。

培養仮説の日本における実証的検討(斉藤・川端, 1991)
調査の概要:
首都圏の大学生、短大生458人に対して質問紙調査を実施(男性37.3%、女性62.7%)。主な質問項目は、ガーブナーらが培養分析で用いた質問項目、東京で暴力的な犯罪に巻き込まれる人の割合、アメリカの大都市の状況の認識。現在の日本の社会状況に関する質問項目、テレビの視聴時間、テレビ以外のメディアへの接触など。
調査結果:
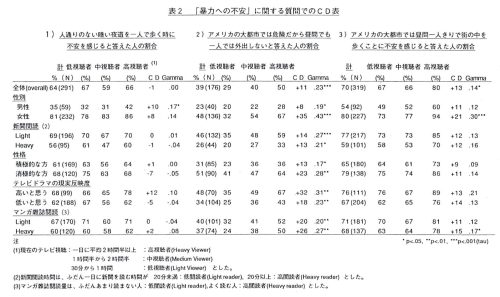
培養効果に関して、4つの仮説を立てた。1.テレビに長時間接触してきた人は、そうでない人より現実の社会をより危険だと知覚し、培養効果が見られる、2. テレビドラマが現実を反映していると思っている人は、そうでない人よリモ、より大きな培養効果が起こる、3. 性格が消極的な人は積極的な人と比べて、より大きな培養効果を示す。調査データについて、暴力に関する11の設問項目の因子分析を行い、因子別に培養効果の有無を測定した。第1因子は「暴力への不安」、第2因子は「暴力の犠牲者数の推測、第3因子は「対人不信感」の因子と名付けられた。第1因子に因子負荷量の高かった3つの質問項目に対する培養格差及びガンマを用いた分析の結果、「夜道を一人で歩くことに不安を感じるかどうか」という質問については、全体として培養効果は見られなかったが、性別で分けてみると、男女ともに弱いながら培養効果が見られた。他の2つの質問項目に関しては、両項目ともに全体・各属性集団ごとを問わずある程度の培養効果が見られた。さらに、男女別で比較すると、性別で共鳴現象がみられた。また、暴力への不安スケールとテレビ視聴量の偏相関分析の結果を見ると。性別・性格・新聞閲読量などを同時にコントロールした偏相関係数は、やや弱いながら有意な値を示した。第2因子の2項目について、培養格差及びガンマを用いた分析を行った結果、両項目とも、テレビドラマの「高信頼グループ」にはある程度の培養効果が見られたが、「低信頼グループ」にはほとんど培養効果は見られなかった。最後に、第3因子(ガーブナーのいう「冷たい世間指標」)の3項目についての分析結果をみると、全体的には弱い培養効果が見られたが、属性ごとの違いはあまり見られなかった。以上の結果をまとめると、第1因子「暴力への不安」に関しては、仮説1のみが支持され、第2因子「暴力の犠牲者数の推測」では、仮説1(部分的)、仮説2、仮説4が支持され、第3因子「対人不信感」では、仮説1(部分的)と仮説4が支持された。
以上の結果、本研究においては、暴力・犯罪の現実にんちに関しては、培養効果は部分的にしか支持されないという結果が得られた。これは、培養効果のパターンは決して単純なものではなく、属性集団の違いによって培養効果は異なって現れることを示している。
文化指標の日米比較研究(Mikami, 1993)
調査の概要:
国際文化指標プロジェクト(International Cultural Indicator Project)の一環として、ガーブナー、シニョリエリなどと行った共同研究。参加者は、George Gerbner(代表)、N. Signorielli、三上俊治、水野博介、竹下俊郎の5名。暴力的なシーンや行動だけでなく、番組内容のさまざまな特徴、主要および副次的登場人物の特徴、テレビドラマに登場する家族のプロフィールを分析した。共通のコードブックとコーディング手法を使用することで、内容分析データを国際的に比較し、2つの国の間の類似点と相違点を検証した。日本の分析対象番組は、1990年6月4日〜10日のNHK、日本テレビ(NTV)、TBS、フジテレビ、テレビ朝日で放送されたすべてのドラマ番組。7月16日から7月19日にかけて、研究チームの5名がペンシルバニア大学アネンバーグ・スクール・オブ・コミュニケーションズに集まり、研究所の他の3名のスタッフとともにコーディング計画に関する共同ワークショップを開催。16カ国が参加する文化指標プロジェクトで使用されたコードブックに基づき、いくつかのコーディングカテゴリを共同で修正し、最終的なコードブックを完成させた。コードブックには、-番組の特徴(96項目)、主要登場人物の特徴(139項目)、副次的登場人物の特徴(28項目)、暴力シーンの特徴(14項目)などが含まれている。
調査結果:
1. 番組のテーマ
日本とアメリカのテレビドラマの最も顕著なテーマは「家族」であり、両国の約70%のドラマが家族を主要なテーマとして含んでいた。また、「犯罪」も両国で頻繁に登場するテーマだった。一方、アメリカでのみ頻繁に登場したテーマには、「ビジネスと産業」「健康と医療」「法執行」「子ども」「青春期」「経済的成功」「マスメディア」だった。対照的に、日本でのみ頻繁に登場したテーマは「個人の監視」と「人為的災害(事故)」だった。これらの結果は、番組のジャンル構成や文化的背景の違いを反映している。2.
2. 登場人物の目標と価値観
日本の女性登場人物が最も頻繁に追求していた目標は「家族の幸福」と「他者の幸福」だった。一方、日本の男性登場人物は「他者の幸福」と「他者の安全・安心」を主な目標としていた。これに対し、アメリカでは、男女ともに「親密な関係」と「個人の幸福」が主要な目標または価値観として描かれていた。この結果は、日本とアメリカの文化的価値観の違いを反映していると解釈できる。しかし、両国ともに、女性は男性よりも「個人の幸福」「家族の幸福」「親密な関係」を追求する傾向が強く描かれ、一方で男性は女性よりも「地位」や「正義」を追求する傾向があった。「親密な関係」「地位」「達成」「富」は、アメリカの登場人物が日本の登場人物よりも追求する傾向が高いことがわかった。
3. 暴力の描写
アメリカのドラマでは59.4%の番組が暴力を題材として含んでいたのに対し、日本のドラマではほぼすべての番組(97.1%)が暴力を題材として含んでいた。この結果は、日本のドラマがアメリカよりもはるかに多くの暴力を描写していることを示すものである。
4. 暴力の行為者と被害者
日本では主要人物の56%が暴力を振るう者として描かれていたのに対し、アメリカでは29%だった。また、日本では主要人物の殺人者の割合もアメリカより高い結果となった。被害者については、日本では主要人物の61%、副登場人物の24%が被害者として描写されており、アメリカでは主要人物の30%、副登場人物の16%が被害者だった。殺人やその他の暴力行為の被害者として描写された人物の割合はアメリカより日本の方が高かった。日本とアメリカの両国で、男性は女性よりも殺人者として描写される傾向が強くあった。

5. 暴力行為の測定(暴力指数)
サンプル内での暴力行為の総数は、アメリカで266件、日本で296件だった。暴力行為を含む日本のドラマの約85%が「犯罪/アクション・アドベンチャー」と分類され、一方アメリカでは58%だった。
暴力行為の平均持続時間は、日本が14.1秒、アメリカが13.6秒だった。暴力に直接関与する参加者の平均人数は、日本が3.1人、アメリカが2.5人だった。暴力行為に用いられた手段としては、アメリカのドラマでは銃の使用頻度が日本より高く(アメリカ23.7%、日本13.5%)、一方で日本のドラマでは体や手足がより頻繁に使用されていた(日本64.2%、アメリカ59.4%)。
1時間あたりの暴力行為の発生率(R/H)はアメリカが4.7、日本が6.9だった。暴力行為を行う者、被害者、またはその両方を含む割合(%V)は、アメリカが40.2%、日本が75.3%だった。殺人を行う者または殺人の被害者を含む割合(%K)は、アメリカが10.9%、日本が22.1%だった。これらの数値から、Gerbnerらが提唱した「暴力指数(Violent Index, VI)」を以下の式で計算した(Gerbner and Signorielli, 1990)。
VI = %P + 2(R/P) + 2(R/H) + %V + %K
その結果、VIはアメリカが126.3、日本が225.7だった。

以上の結果から、日本のテレビドラマではアメリカよりも暴力行為がはるかに多く描写されていることが明らかになった。以上の研究知見は、綿密な国際共同研究の結果明らかになった日米間のテレビドラマ描写の違いであり、文化指標研究における貴重な研究成果といえよう。
テレビにおける暴力ーその実態と培養効果(中村, 1999)
調査の概要:
1. テレビの殺人関連情報の内容分析
1997年9月16日から212日までに松山市で放送された地上波の全番組のうち、殺人関連情報を含む番組数、放送時間、シーンの数などを計測した。対象とした番組はニュース、ワイドショー、ドラマ、時代劇など殺人事件が頻繁に出てくると思われる5つのジャンルである。
2. 調査データの培養分析
1997年9月23日から10月6日の2週間、松山市で20歳から69歳までの1,000人を対象として留置式調査を実施した。有効回収は656票。主な設問項目は、テレビ接触量と現実認識(暴力犯罪の推定、殺人被害者数の推定)である。
調査結果:
1. 内容分析の結果
殺人を含む番組数や殺人項目数では、ニュースが最も多かった。殺人関連情報の放送時間では、ニュースが4604秒、ワイドショーが14164秒、刑事ドラマが538秒、時代劇が1446秒であり、ワイドショーの放送時間が圧倒的に長かった。テレビの暴力描写において、ワイドショーが極めて重要なジャンルになっていることがわかった。
2. テレビ視聴の培養効果
一般代表サンプルに対する調査をもとに、テレビの総視聴時間と現実認識との関係を調べたところ、テレビ視聴時間が3時間以内の低視聴者でテレビ的回答をした人が52.8%であったのに対し、4時間以上の高視聴者であh63.5%にも達した(カイ2乗検定1%水準で有意)。つまり、ガーブナーらの仮説通り、テレビをよくみる人は現実世界でも暴力があふれていると考える人が多かったのである。
次に、テレビ番組のジャンル別の視聴頻度と現実認識との関連を分析した。擬似相関を排除するために、学歴や年齢などの変数をコントロールした上で、ロ現実認知を従属変数に、テレビ視聴状況を独立変数にしてロジスティック回帰分析を行ったところ、次のようなことがわかった。「テレビの総視聴時間をテレビ視聴状況を表わす変数として計算した場合、総視聴時間が長い人ほどテレビ的回答をする傾向が見られた。その影響の信頼性を示すp値は5%以下で、それほどはっきりしたものではないが、各変数をコントロールした上でも総視聴時間の影響が検出された。総視聴時間に関しては弱いながらもガーブナーらの仮説が今回立証されたことになる。一方テレビ視聴状況として、ワイドショー、刑事サスペンスドラマ、バラエティー番組の視聴類度をそれぞれ投入した場合は、よりはっきりと影響が確認された。すなわち1%以下の有意水準で、ワイドショーや刑事・サスペンスドラマやバラエティー番組をよく見る人ほど、現実も暴力があふれていると認識していることがわかったのである。」このように、各ジャンルで培養効果の表われ方が異なっているという結果は、従来の培養効果研究を再検討を迫るものと言えるかもしれない。
21世紀の培養理論
培養理論は、1960年代にガーブナーによって創始されたメディア効果論であり、主にテレビという大衆向けの視聴覚メディア、主流的なマスメディアの認知的影響を説明するための理論だった。21世紀に入り、テレビの支配力が翳りを見せ、双方向的なニューメディア、ユーザー主導型メディアが次々に登場してメディア環境が大きく変わろうとしている現在でも、培養理論はメディア効果論として有効性を保ち得るのだろうか?
培養理論の創始者であるガーブナーは、惜しくも2005年に亡くなっており、彼自身の考えを聞くことは叶わないが、ガーブナーとともに長年にわたって培養理論の研究を続けてきた3人の専門家(モーガン、シャナハン、シニョリエーリ)が2014年に「21世紀の培養理論」(Cultivation Theory in the Twenty-First Century)と題する論文を発表している。この論文の要旨を紹介することによって、培養理論の今後を占うための参考資料としたいと思う(Morgan, Shanahan & Signorielli, 2014)。
依然として大きな比重を占め続けるテレビ
私たちの生活には多くの種類の画面が存在するにもかかわらず、依然として最も多くの時間を費やしているのはテレビ画面である。家族や居間の大画面テレビ、キッチンの小型テレビ、コンピューター、iPad、スマートフォン、などデバイスは多様化しているが、多くの人は毎日テレビのコンテンツに多くの時間を費やしている。このような状況下で、いかなる場所においても、テレビは依然として国家および世界の物語の語り手であり、ほとんどの時間、ほとんどの人々に対して物語を提供し続けている。現代の子供たちは、親、友達、学校、教会ではなく、商業機関によって語られる物語が大半を占める家庭に生まれ育っている。テレビは人生について教え、誰が勝者で、誰が敗者で、誰が権力者で、誰が弱者であるのか、さらに誰が幸福で、誰が悲しんでいるのかを教えてくれる。テレビは、異質な集団に共通の社会化と日常的な情報(通常、娯楽の形で覆い隠された形)を提供する主要な情報源である。それは世界を定義し、特定の社会秩序を正当化する物語の絶え間ない流れを提供しているのである。確かに、テレビは世界を説明する多くのメディアの一つにすぎなくなっている。実際、現代の子供たちはマルチメディアでマルチタスクする環境で成長しており、メディアに費やす総時間は1日あたり11時間を超えている。しかし、その大部分はテレビと関わりを持っている。多様なデジタルメディアや新しいメディア技術が利用可能であるにもかかわらず、今日でもテレビは依然として最も多くの視聴者と広告収益を集めているのである。
したがって、数多くの専門化した新しいチャンネルや、ますます小規模な視聴者を対象としたさまざまなプログラムが登場しているにもかかわらず、制度としてのテレビは引き続き社会のほぼ全員に共通のイメージを提供している。そして、暴力、ジェンダー、人種、階級、権力、消費、その他の基本的なイデオロギー的側面に関する重要なメッセージや教訓は、異なるプログラムやチャンネルを超えて一貫している。
培養理論の発展
2010年の時点で、500本以上の培養理論関連の研究が発表されており、その3分の2は、ガーブナーや彼のオリジナル研究チームと無関係の独立した研究者による拡張、追試、レビュー、批評である。最初の培養研究は、テレビ視聴が暴力や被害の信念と認識にどのように寄与するかを調査したが、その後、ジェンダー役割、少数派や年齢役割のステレオタイプ、健康、科学、家族、教育の達成や志望、政治、宗教、環境など、多くの社会的・生活的側面に研究の対象が拡大した。これらのテーマの多くは、文化間比較の文脈でも検討されている。実際、これまでにアルゼンチン、オーストラリア、ベルギー、ブラジル、中国、イギリス、ドイツ、ハンガリー、イスラエル、日本、メキシコ、ロシア、韓国、スウェーデン、タイなどで培養研究が行われている。培養理論は、議題設定理論や「利用と満足」理論と並び、1956年から2000年の間に発表された主要な学術誌において最も多く引用された3つの理論の1つである。さらに、1993年から2005年に発表された16の学術誌の記事962本を分析した結果、培養理論が最も多く引用された理論であった。このように、培養理論の研究は、21世紀に入った現在も大きく発展し続けている。
メディア効果論における培養理論の独自性
ガーブナーは文化を「社会的関係を規制し、再生産するメッセージとイメージのシステム」と見なした。言い換えれば、文化とは大量生産された物語のシステムであり、それが存在とその意識の間を仲介し、両者に寄与するのである。その結果、私たちを取り巻く媒介されたメッセージやイメージは、世界についての私たちの考え方を反映し、再生産する。培養は「変化」を研究する多くのメディア効果モデルとは異なり、単純な線形的「刺激ー反応」モデルやメディアメッセージに対する短期的な即時反応を意味するものではない。むしろ、テレビの反復的で安定したメッセージへの長期的な累積的接触に焦点を当てている。それは、多くの視聴者に利用可能なチャンネル数が増加したにもかかわらず、依然として持続している。培養とは、テレビ視聴が人々の社会的現実の認識に独自の影響を与えることを意味している。ガーブナーにとって、培養とは、テレビ番組に見られるような社会的および制度的な力学を示す象徴的な環境に住むことであり、それが集団的意識を創り出すということであった。
認知プロセスと現実感の認識
ガーブナーは、培養の認知プロセスを理解することは特に重要ではないと考えていた。彼は、培養に関与するプロセスは、人々が世界や環境について物事を学ぶ一般的なプロセスにすぎないと仮定していた。しかしながら、Shrumの研究は一貫して、ヒューリスティック処理(心理的短絡処理の使用)が社会的現実について学ぶ際の中心的な役割を果たしていることを示している。私たちは通常、情報源(例:テレビ)を特に問われない限り考慮せず、情報源を考慮した場合には、培養効果が見られないことが多い。このメディアメッセージの認知処理に関する研究は、培養理論に対して大きな外的妥当性を提供している。
同様に、「現実感」、特に「現実感の認識」が培養を理解するうえで重要な要素として検討されている。多くの研究者は、「現実的」と認識される番組だけが世界に関する信念に影響を与えると考えていたが、最近の研究はその答えがそれほど単純ではないことを示している。例えば、BusselleとBilandzicは、現実感の認識は「デフォルト」の状態であると提案している。つまり、特段の理由がない限り、私たちはコンテンツが現実的であると仮定してしまう傾向がある。ほとんどのコンテンツは、それがファンタジーと認識されているものであっても、ある程度の現実感の認識を持っており、視聴者はテレビから得た印象を実世界の理解に持ち込むのである。BilandzicとBusselleは、物語への「没入」(批判的な思考を弱める、または物語に完全に「引き込まれる」)が培養における重要な要素だと言う提案を行なっている。彼らの研究結果は、「没入しやすさ」が培養を増加させる特性である可能性を示唆している。
番組ジャンルと培養効果
これまで、多くの研究者が培養現象やその関連効果を理解するうえで、特定のメディアメッセージのジャンルへの露出が重要な要素であるべきかどうかを問いかけてきた。ガーブナーの当初の理論では、テレビ視聴は特定の番組やジャンルではなく、全体の視聴時間によって測定されると考えられた。ShanahanとMorgan(1999)は、「番組ジャンルや視聴形式を超えて共通する設定、配役、社会的類型、行動、関連する結果のパターンがテレビの世界を定義している」(p.30)と指摘している。このため、重視聴者は日々こうしたイメージやメッセージに繰り返し触れることで、社会的現実に対する見解が影響を受けると予測される。
一方で、培養研究は特定のジャンルの番組に焦点を当てるべきだと考える者もいる。これらの研究者は、異なる番組タイプが世界に対して多様な見解を提示し、社会的現実に対する独自の認識を培養すると仮定している。CohenとWeimann(2000)は、異なるジャンルは通常フォーマライズされた構造に基づいているが、それでも視聴者に多様な世界観を提供していると述べている。例えば、ニュース、犯罪、アクション番組や時事問題を探る番組は、社会秩序に焦点を当て、公共の生活を家庭生活とは区別し、正と誤を明確にする傾向がある。一方、シチュエーション・コメディや家庭ドラマ、ソープオペラは、家庭問題、家族関係、友情に焦点を当てている。
特に、一部の研究者は、視聴者の恐怖や暴力に対する認識が、特定ジャンル、特に犯罪関連の番組視聴に起因すると仮定している。犯罪番組が社会における犯罪の統計を歪めていることが知られているにもかかわらず、多くの研究が犯罪に関する認識と犯罪番組視聴との間に関係があることを示している。例えば、Holbert, Shah, and Kwak(2004)は、全国規模のサンプルを用いて、テレビニュースや警察のリアリティ番組の視聴が犯罪に対する恐怖心に関連していることを発見したが、犯罪ドラマの視聴はそうではなかった。また、この分析では、ノンフィクション番組(警察のリアリティ番組など)の視聴が、フィクションの犯罪ドラマ視聴よりも社会的現実に対する認識に強く関連している傾向があることが示された。この違いは、警察のリアリティ番組の現実感の高さによるものと解釈された。
ニューメディアと培養理論
この40年間でメディア環境の多くの側面が大きく変化してきた。1950年代から1980年代にかけて、テレビはABC、CBS、NBCの3つの主要ネットワークが視聴者の大部分を占めており、各市場には独立局が数局しか存在しなかった。映画は劇場で上映されるか、劇場公開終了から数年後にテレビで放映されるのが一般的であり、書籍や雑誌、新聞は書店やスーパーマーケット、薬局、ニューススタンドで購入する物理的な媒体であった。
しかし現在では、ケーブルや衛星放送システムが数百のチャンネルを提供し、オンデマンドで数千の番組や映画を視聴可能である。インターネットは、ほぼすべての映画やテレビ番組への即時アクセスを可能にしている(合法・違法を問わず)。多くの映画は依然として劇場公開されるものの、上映期間が短縮され、ケーブル映画パッケージ、DVD、あるいはダウンロードやストリーミングといった、より収益性の高い市場に迅速に移行する傾向が強まっている。中には、家庭用ビデオ市場専用に制作される映画もある。また、新聞や雑誌、書籍の物理的なコピーを購入することも可能だが、多くの人々がこれらを電子的に消費するようになっている。
こうした状況下で培養は、コンテンツの基盤的要素と視聴者がこれらのメッセージとどのように相互作用するかに焦点を当ててきた。ShanahanとMorgan(1999)は、「メッセージの内容は、それを届ける技術よりも本質的に重要である」と指摘している(p.201)。この点から、新しい技術はメディアが視聴者に与える影響を説明する重要な方法としての培養理論を無効にするものではない。新しい技術により、視聴者は自分の見たいものを、見たいときに、見たい場所で視聴することが容易になったが、同時に視聴量自体も増加している。視聴チャンネルが増えたにもかかわらず、これらのイメージに浸透する共通のメッセージや教訓を探ることが、ますます重要になっている。インターネットでのテレビ番組の視聴は、本質的には「テレビを視聴している」ことに変わりはない。
MorganとShanahan(2010)は、「テレビはまだしばらくの間、私たちの主要な文化的ストーリーテラーであり続けるだろう」(p.351)と述べている。したがって、培養理論に基づく研究は、インターネットの一般的なコンテンツを評価し、コンピュータを主要な娯楽媒体として使用する人々が、受け取るメッセージによって世界をどのように認識するかを明らかにする必要がある。同時に、これらのメッセージがテレビ番組で一貫して見られる価値観や要素と同じかどうかを検証することが重要である。コンピュータ技術に結びついた娯楽を利用する人々が、従来のメッセージを受け取る可能性は高いと推測される。このことから、培養の証拠は基本的に同じままであると考えられる。
結論
全体として、テレビは以前よりも断片化し、多様なスクリーンで視聴されるようになっているが、それでもなお、テレビは多くの物語を多くの人々に、ほとんどの時間語り続ける「物語の語り手」であり続けている。したがって、21世紀においても、目にするもの、語られる物語、そして人々が世界を見る方法との関係は、これまでと同様に重要であり続けている。ガーブナーの培養という広範なアイデアは、1970年代初頭と同様に、現代においてもなお有効性を持ち続けている。
(筆者のコメント)
本論文の著者はいずれもガーブナーの共同研究者や後継者であるせいか、多チャンネル化やインターネットの時代になっても、テレビからのメッセージが支配的な影響力を持つ時代は続くとして、従来の培養理論を擁護する文章で終わっている。しかし、2024年のアメリカ大統領選挙や兵庫県知事選挙にみられるように、今やYouTubeやSNS上のコンテンツが有権者の現実認識に大きな影響を及ぼし、それが選挙の結果をも左右するような時代に入りつつあることも事実である、培養理論も、こうしたメディア環境の変化に合わせて、理論の再検討を行う時期に来ているのではないだろうか。
参考文献(第8章)
Adoni,H.,and S.Mane ( 1984) Media and social construction of reality. Communication
Research, 11 (3): 323 - 340
Adoni,H.,A.A.Cohen,and S.Mane ( 1984) " Social reality and television news:Perceptual
dimensions of social conflicts in selected life area. "Journal of Broadcasting, 28: 33 - 49.
Berger,L.P.,and T.Luckmann ( 1967) The Social Construction of Reality. New York:Anchor Books.
山口節郎訳「日常世界の構成ーアイデンティティと社会の弁証法』新曜社
Doob,A.,and G.MacDonald ( 1979) " Television viewing and fear of victimization:Is the relationship causal?" Journal of Personality and Social Psychology, 37: 170 - 179
Gerbner,G. (1969) Toward 'cultural indicators': the analysis of mass mediated public message systems. " Audio Visual Communication Review, 17 (2): 137 - 148
Gerbner ( 1973) Cultural Indicators:The Third Voice" In Gerbner et al. (eds. ) Communication
Technology and Social Policy. N.Y.: Wiley.
Gerbner,G.,and L.Gross ( 1976) " Living with television: the violence profile. " Journal of Communication, 26: 172 - 199
Gerbner,G.,L.Gross,M.Jackson-Breeck,S.Jeffries-Fox,and N.Signorielli (1977 b) " TV violence profile no.8. " Journal of Communication, 28: 171 - 180
Gerbner,G.,L.Gross,M.Jackson-Breeck,Jeffries-Fox,and N.Signorielli ( 1978) " Cultural indicators:violence profile no.9. "Journal of Communication, 28 (3): 176 - 207 .
Gerbner,G.,M.Morgan, and N.Signorelli ( 1980 a) * The mainstreaming of America: violence profile no. 11. " Journal of Communication, 30 : 10 - 29.
Gerbner,G.,L.Gross.N.Signorielli, and M.Morgan (1980 b) * Aging with television: images on television drama and conceptions of social reality. ~ Journal of Communication, 30 : 37 - 47.
Gerbner,G.,L.Gross,M.Morgan,and N.Signorielli (1981 a) " A curious journey into the scary world of Paul Hirsch. " Communication Research,8 (1): 39 - 72 •
Gerbner,G.,L.Gross,M.Morgan,and N.Signorielli ( 1982) "Charting the mainstream: television's contribution to political orientations. " Journal of Communication, 32: 100 - 127 .
Gerbner,G.,L.Gross,M.Morgan,and N.Signorielli ( 1984) Political correlates of television
viewing. " Public Opinon Quarterly, 48: 283 - 300
Gerbner,G.,L.Gross,M.Morgan,and N.Signorielli ( 1986) " Living with television :the dynamics of the cultivation process. " in J.Bryant and D.Zillmann (eds. ),Perspectives on media
effects (pp. 17 - 40) . Hillsdale,MJ:Lawrence Erlbaum.
Hawkins,R.,and S.Pingree ( 1980) " Some processes in the cultivation effect. " Communication
Research,7: 193 - 226 •
Hawkins,R.and S.Pingree (1983) " Television influence on constructions of social reality. " in I.
Wartella et al. (eds. ),Mass Communication Review Yearbook,Vol.4: 53 - 76.
Hirsch,P.M. (1980) "The 'scary world' of the nonviewer and other anomalies:a reanalysis of Gerbneret al. 's findings on cultivation analysis,part 1. "Communication Research, 7: 403
Holbert, R. L., Shah, D. V., & Kwak, N. (2004). Fear, authority, and justice: Crime-related TV viewing and endorsements of capital punishment and gun ownership. Journalism e Mass Communication
Morgan, M., & Shanahan, J. (2010). The state of cultivation. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 54(2), 337-355.
村松泰子(1982)「マス・コミュニケーションの内容」 竹内・児島編「現代マス・コミュニケーショ
ン論』pp.167-197.有斐閣
Murdock,G. (1973) Political deviance:the press presentation of a militant mass demonstration.
in S.Cohen and J.Young (eds.) The Manufacture of News-Social Problems, Deviance, and the Mass Media. London: Constable.
Murdock,G.,and P.Golding (1977) "Capitalism,communication,and class relations. "in J.Curran et al. (eds.) Mass Communication and Society. London:Open University Press.
三上 俊治, 1987, 現実構成過程におけるマスメディアの影響力 -擬似環境論から培養分析, 東洋大学社会学部紀要 (24-2) pp.238-280
三上俊治, 橋元良明, 水野博介, 1989, テレビによる社会的現実の認知に関する研究. 東京大学新聞研究所紀要 (38) pp.73-124
MIkami, S., 1993, A Cross-National Comparison of the US-Japan TV Drama: International Cultural Indicators. Keio Communication Review, No.15, pp. 29-44.
三上俊治, 竹下俊郎, 川端美樹, 1999, Influence of the Mass Media on the Public Awareness of Global Environmental Issues in Japan. Asian Geographer 18(18) 87-97 1999年7月
川端美樹, 三上俊治, 2001, How Television News Matters: Television News Viewing and Environmental Awareness in Japan. Keio Communication Review 23(23) 37-52 2001年3月
水野博介, 1998, 『メディア・コミュニケーションの理論』学文社
中村功, 1999, 「テレビにおける暴力ーその実態と培養効果」, 『マス・コミュニケーション』55号, pp.186-201
Pingree,S.,and R.Hawkins ( 1981) " Programs on Australian television:the cultivation effect. " Journal of Communication, 31 (1): 97 - 105
斉藤慎一・川端美樹, 1991, 「培養仮説の日本における実証的研究」『慶應義塾大学新聞研究所年報』37号, pp.55-78
斉藤慎一, 1992, 「培養理論再考」『新聞学評論』42号, pp.70-83
斉藤慎一 , 2002, 「テレビと現実認識ー培養理論の新たな展開を目指して」『マス・コミュニケーション研究』, 60号, pp.19-43
Shanahan, J., & Morgan, M. (1999). Television and its viewers: Cultivation theory and research. New York: Cambridge University Press.
竹下俊郎, 1998, メディアの議題設定機能--マスコミ効果研究における理論と実証〔増補版〕学文社
Wober,J.M. (1978) "Televised violence and paranoid perception:the view from Great Britain. " Public Opinion Quarterly, 42: 315 - 321 •
第9章 マスメディアの議題設定機能
議題設定研究登場の背景
議題設定研究は、1968年のアメリカ大統領選挙での調査を通じて生まれたが、そのきっかけとなったのは、ロサンゼルスのホテルでの何気ない会話だった。また、議題設定仮説のヒントになった先行研究は、リップマンの「世論」とコーエンの著作だった。
ホテルでの何気ない会話から始まった
それは1967年のことだった。マクスウェル・マコームズは、カリフォルニア州UCLAのジャーナリズム学部の助教授だった。ロサンゼルスのウィルシャー通りにあるセンチュリープラザホテルで仕事後に一杯飲みながら、マコームズともう一人の若手同僚は、ある特定のニュースイベントがなぜ世論に大きな影響を与えなかったのかを議論した。その日のロサンゼルス・タイムズの一面を見ると、そのニュースイベント(ジョンソン政権における小さなスキャンダル)の記事は、小さな写真と控えめな見出しだけで、ほとんど目立たない扱いだった。一方で、その日の一面には他の二つのニュースが大きく取り上げられていた。しかし、この日に別の新聞、例えばニューヨーク・タイムズを読んでいた人は、そのスキャンダルをもっと重要な問題だと考えたかもしれない。この「メディアによる議題設定」の議論が、マコームズをUCLAの書店に向かわせ、コーエン(1963年)の著作(『新聞と外交政策』)を購入するきっかけとなった。その本には、議題設定についての現在では有名な次のような比喩的表現が含まれていた。
報道は人々に「何を考えるべきか」を伝えるのには必ずしも成功しないが、「何について考えるべきか」を伝える点では驚異的な成功を収めている」
(It may not be successful much of the time in telling people what to think, but it is stunningly successful in telling its readers what to think about. )
その後まもなく、マコームズはノースカロライナ大学でドナルド・ショーと共にチャペルヒル研究を行うことになったのである。
リップマンの「世論」
マコームズらの「議題設定機能」研究の知的ルーツは、リップマンの「世論」における擬似環境論にあった。マコームズの論文「ニュースメディアと我々の頭の中の映像」(The News Media and the Pictures in Our Heads) (McCombs, ) の中で、リップマンの「世論」と議題設定」研究との間の関連について、次のように述べている。
コーエンの論文
コーエンは、「新聞と外交政策」という著書の第1章「設定」の中で、リップマンの「世論」を引用した後に、議題設定研究のヒントになった有名な言葉を残している。関連のある部分を次に引用しておく。
年を追うごとに外交政策はアメリカの公共政策の中心的な課題へと近づいており、国家的価値を守るための困難と費用がますます大きくなっている。問題が国家の存続に関わるものとして明確になるにつれ、我々が行う外交政策の選択の重要性、さらにはその選択肢の範囲を事前に理解することの重要性が、より深く認識されるようになる。ウォルター・リップマンが「頭の中の地図」の重要性について書き、「人々が世界を旅するためには世界の地図を持たねばならない」と述べたのも、まさにこの点に関連している。
国際問題の全体像を直接経験できる者はいないということは自明の理でありながら重要な事実である。我々は、幸運にも重要な出来事に参加したり観察したりする機会があれば、そのごく一部を直接知ることができるかもしれない。しかし、一般的には、外部の世界、すなわち外交政策の世界は、大衆伝達メディア、特に報道を通じて我々に届くものである。
外交政策に関心を持つ大多数の人々にとって、実際に機能する世界の政治的地図、すなわち運用可能な世界地図は、地図製作者ではなく、記者や編集者によって描かれている。例えば、ラテンアメリカは地図製作者の地図では多くの空間を占めるが、アメリカの大多数の新聞が描く政治的地図にはほとんど存在しない。そして、新聞で報道されていない出来事(またはラジオやテレビで報道されない出来事)は、我々にとっては実際には「存在しなかった」も同然である。
つまり、報道は単なる情報や意見の提供者以上の存在である。報道は人々に「何を考えるべきか」を伝えるのには必ずしも成功しないが、「何について考えるべきか」を伝える点では驚異的な成功を収めている。そしてこのことから、個々人の世界観は、個人的な関心だけでなく、彼らが読む新聞の記者、編集者、発行者によって描かれた地図に依存して異なって見えるようになる。
地図という概念は範囲が狭すぎるかもしれない。というのも、報道が伝える政治的現象の全範囲を十分に示唆しているわけではないからである。むしろ、それは場所、人々、状況、出来事のアトラスであり、さらに**報道が人々の問題解決に対する考えを論じる際には、政策の可能性や選択肢のアトラスでもある。編集者は、自分はただ人々が読みたがっているものを掲載しているだけだと考えているかもしれないが、それによって人々の注意を引きつけ、次の波が押し寄せるまで彼らが何を考え、何を話題にするかを強力に決定しているのである。
このように、コーエンの著書でしばしば引用される文章の前後関係を詳しくみると、それはリップマンの「世論」における擬似環境論に強く影響されたものであることがわかるのである。
ラング夫妻の研究
一方、コーエンよりも早く、議題設定機能とよく似た機能に言及したマス・コミュニケーション研究者として、マコームズとショーは、ラング夫妻をあげている。1959年にラング夫妻は「マスメディアは特定の問題に注意を向けさせる。政治家の公的なイメージを構築する。マスメディアは常に、個人が何について考えるべきか、知るべきか、感情を抱くべきかを示唆する対象を提示している(The mass media force attention to certain issues. They build up public images of political figures. They are constantly presenting objects suggesting what individuals in the mass should think about ,know about, have feelings about)」と述べていた(Lang & Lang, 1966; McCombs & Shaw, 1972)。
マスメディアの「議題設定機能」仮説の検証(1968年チャペルヒル調査)
「議題設定機能」仮説とは、「マスメディアが政治的な手点に関する議題を設定し,争点に関する人びとの顕出性(salience:重要度の評価)に影響を与える」という考え方である。議題設定機能仮説を初めて操作的に定式化し,実証的データによって検証したのは、アメリカのマス・コミュニケーション研究者であるマコームズとショー(McCombs & Shaw, 1972)であった。かれらは,1968年のアメリカ大統領選挙キャンペーン期間中、まだ投票態度を決めていない有権者100名を対象として面接調査を行い,議題設定仮説の検証をこころみた。彼らは、調査対象者に,その時点でどんな問題が政策面での重要な争点だと思うかを自由回答方式で答えてもらった。また,調査期間とほぼ同時期に調査対象地域で発行されている新聞,ニュース雑誌、および調査地域で視聴可能なネットワーク・テレビのイブニング・ニュースを内容分析し,主要な6つの手点と選挙キャンペーンに関するニュースの報道量を測定した。分析された争点は、「外交政策」「法と秩序」「財政政策」「公共福祉」「公民権」および「その他」である。そして有権者がどんな争点を重要だと判断しているかという争点顕出性の程度と、マスメディアがそれらの争点を強調する程度(報道量)との間の順位相関係数を算出したところ、主要なニュース報道に関しては+0.967,マイナーな報道に関しては+0.979という非常に高い相関を示した。これは、議題設定機能の仮説をある程度支持するものであった。この選挙では、ニクソンの他にハンフリー、ウォーレスも立候補しており、各候補者のキャンペーンにおいて強調された争点はかなり異なっていたが、有権者による争点顕出性は、それぞれの支持する候補者の争点強調度よりもマスメディアの報道全体における争点強調度との間でより強い相関が見いだされた。このことは、有権者の争点認知が、自分の支持する政党や候補者のキャンペーンよりも、むしろマスメディアが全体として設定する議題によって、より大きな影響を受けていたことを示すものである。
調査の方法:
1. 調査対象
本研究では、チャペルヒルの有権者がキャンペーンの主要な問題として挙げた事項と、キャンペーン中に彼らが利用したマスメディアの実際の内容を比較照合した。調査対象者は、経済的、社会的、人種的にコミュニティを代表する5つのチャペルヒル地区における有権者登録リストから無作為に選出された100名。この100名の回答者を選定するため、フィルター質問が用いられ、まだ投票先を明確に決めていない者だけを選び出した。調査対象をこのように限定したのは、彼らがキャンペーン情報に最もオープンで(特定の候補者にまだ完全にコミットしておらず)影響を受けやすいと推測されたからである。
2. 回答者の「主要な問題」とマスメディアの内容分析
各回答者には、候補者がその時点で何を言っているかに関わらず、自分が重要と考える主要な問題を挙げてもらった。調査者は回答を可能な限り正確に記録した。これと同時に、これらの有権者に情報を提供しているマスメディアを収集し、その内容を分析した。
マスメディアのニュース内容は、「主要」と「副次」の2つのレベルに分けられ、メディアごとの主要項目は次のように定義された。
(1) テレビ:長さが45秒以上、またはトップ3の主要ニュースに該当するストーリー。
(2) 新聞:政治ニュース報道が少なくとも記事全体の3分の1(最低5段落)を占め、かつ一面のトップ記事、または3段組み以上の見出しの下に掲載された記事。
(3) ニュース雑誌:1ページ以上にわたる記事、またはニュースセクションの冒頭に掲載されたリード記事。
(4) 社説ページ:社説ページのトップ左隅に配置されたリード社説、および社説やコラムコメントの3分の1(最低5段落)が政治キャンペーン報道に充てられた項目。
調査結果:
マスメディアは、有権者がキャンペーンの主要問題をどのように判断したかに大きな影響を与えていたことがわかった。調査では、質問項目において「候補者がその時点で何を言っているかに関係なく判断する」よう指示されていたにもかかわらず、有権者が重要な問題として挙げたものと、マスメディアが取り上げた主要項目の重点との間には+0.967の相関があった。同様に、副次項目の重点と有権者の判断との相関は+0.979であった。つまり、このデータは、マスメディアがキャンペーン問題に置いた重点(候補者の重点をある程度反映している)と、有権者の様々なキャンペーントピックの顕出性や重要性に関する判断の間の強い関連性を示唆している。しかし、大統領候補3人がそれぞれ異なる問題に大きく異なる重点を置いたにもかかわらず、有権者の判断はマスメディア報道の全体集約を反映しているように思われる。これは、有権者が特定の支持候補に関係なく、すべての政治ニュースに一定の注意を払っていることを示唆している。
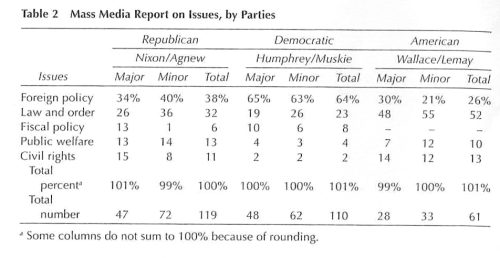
考察:
マスメディアの議題設定機能の存在は、ここで報告された相関関係だけでは証明できないが、マスメディアによる議題設定が起こるために必要な条件と一致する証拠が示された。本研究では、チャペルヒル有権者全体をいくつかのマスメディアの総体的な報道と比較した。このアプローチは議題設定仮説の最初のテストとしては適切であるが、今後の研究では、広い社会的レベルから社会心理学的レベルに移行し、個々の態度を個々のマスメディア利用と対応付ける必要がある。
本研究の証拠をマスメディアの影響を示すものと解釈することは、他の説明よりも説得力がある。有権者とメディアの重点が一致する相関関係が偶然である、すなわち両者が同じ出来事に反応しているだけで相互に影響を及ぼしていないという主張は、有権者が日々の政治情勢の変化を観察するための別の手段を持っていることを前提としている。しかし、この前提は現実的ではない。大統領選挙キャンペーンに直接参加する人は少なく、大統領候補を直接見る人はさらに少ない。対人コミュニケーションで流れる情報も、主にマスメディアのニュース報道に基づき、中継されるものである。マスメディアは国家的な政治情報の主要な一次情報源であり、大多数にとって、マスメディアは絶えず変化する政治現実を簡単に得られる最良かつ唯一の近似情報だからである。
また、高い相関が示しているのは、メディアが単に受け手の関心に合ったメッセージを成功裏に発信した結果であると主張することも可能である。しかし、多くの研究が示しているように、職業的なジャーナリストのニュース価値と視聴者の関心の間には大きな乖離が存在する。このような中で、今回のケースで完璧に近い一致が見られることは驚くべきことである。それよりもむしろ、メディアが主要報道の分野で優位性を持っていると考える方が妥当である。
論文発表の経緯
マコームズとショーの論文(1972)がその後の議題設定研究者に多大な影響を与えたにもかかわらず、この論文が発表されるまでには困難があった。彼らはチャペルヒル研究の論文を当時の主要な学会の一つであったジャーナリズム教育協会 (AEJ) の理論・方法論部門に投稿したが、「型破りすぎる」「サンプルが少なすぎる」「理論的根拠が不十分」といった理由で拒否された(Tankard, 1990, p.281)。彼らは一時論文の発表を諦めようとしたが、最終的にマスコミュニケーション効果を扱う主要な学術誌である Public Opinion Quarterly (P.O.Q) に投稿し、1972年に調査実施から4年後にようやく掲載されることになった。
彼らの論文がP.O.Q.に掲載されて以来、議題設定研究は大きな脚光を浴び、実証的、理論的な多くの議題設定研究が次々と行われるようになった。
議題設定研究の概要
1991年には、それまでの代表的な議題設定に関する研究論文を集めたリーディングスが出版されたが、その中で、これまでに約200もの議題設定に関する実証的研究が行われてきたと述べられている(Protess & McCombs, 1991, p.43).。アメリカ・ジャーナリズム学会(AEJMC)の機関誌 Journalism Quarterly誌 の Vol.69,No.4(1992)は、議題設定研究「生誕20周年記念」の特集を行い。議題設定研究に関する論文9本を一挙に掲載している。その巻頭論文では、議題設定研究の創始者の一人であるマコームズ(McCombs, 1992)が、「探検家たちと測量家たち:議題設定研究の拡大戦略」と題して、過去20年間に議題設定研究がどのような段階を経て発展してきたかを回顧し,今後の研究戦略についての展望を行っている。この論文で,マコームズは議題設定研究の発展段階を、主要な研究業績を基準として4つの時期に区分している。
第1期:1972年にマコームズとショー(McCombs and Shaw, 1972)が、1968年のアメリカ大統領選挙における有権者調査をもとに、議題設定仮説の検証を試みた論文(前述)の発表に始まる。この時期は、いわば研究の黎明期であり、調査そのものはサンプル数が100人程度の小規模なものにとどまり、また調査地域も小さな学園町に限定されていた。
第2期:1972年の大統領選挙期間中に行った大規模な調査をもとに、1977年に出版された初めての単行本『アメリカにおける政治争点の生成(The Emergence of American Political Issues)の刊行によって開始された。この時期には、大規模代表サンプルで議題設定仮説を検証するとともに、「オリエンテーション欲求」「新聞とテレビの議題設定効果の比較」など、いくつかの新しい仮説や研究プログラムを提示することによって,議題設定研究の拡大が図られた。
第3期:1976年大統領選挙期間中の大規模パネル調査をもとに、1981年に刊行された『大統領選挙におけるメディアの議題設定』(邦訳題名『マスコミが世論を決める』(MediaAgenda-Setting in a Presidential Election)の刊行を契機とする。この時期には、候補者のイメージが新たな「属性議題」として追加され、議題設定研究の拡大が行われた。
第4期:1980年代以降現在にまるまでの時期の研究である。この時期にみられる大きな特徴は、「従属変数の転換」にあった、とマコームズは指摘する。すなわち,第1期における議題設定研究の問いかけが「誰が公衆の議題を設定するのか?」(Who sets the public agenda?)というものであったのに対し、第4期になると、「誰がニュース議題を設定するのか?」(Who sets the news agenda?)という問いかけに変わったのである。つまり,それまでの議題設定研究では、もっぱら「公衆の議題」が従属変数として扱われ、ニュース議題が独立変数として扱われていたのに対し,80年代の研究では、「メディアの議題」そのものが新たな従属変数として扱われるようになり,ニュース議題の設定過程に関する実証的研究が精力的に行われるようになったのである。さらに、マコームズは、2005年に公開した論文「議題設定の概観:過去・現在・未来」 (McCombs, 2005)において、1972年以降の議題設定理論の発展を次の5つの段階に分けて整理し直している。これは、それまでにあちこちに分散していた議題設定研究の成果を1箇所にまとめて提示するとともに、この分野における現在および近未来の研究課題を強調する点にあった。
第1段階:基本的な議題設定研究
第2段階:属性型議題設定
第3段階:議題設定効果の心理学
第4段階:メディア議題
第5段階:議題設定効果の帰結
そこで、上の5段階のうち、議題設定の発展において特に重要だと思われる「基本的な議題設定研究」「属性型議題設定」「メディア議題」「議題設定効果の帰結」の4つに絞って、研究の概要をまとめておきたい。
基本的な議題設定研究の発展
(1) 新聞、テレビ、雑誌など異なるメディア
マコームズとショーによるオリジナルの研究では、新聞、テレビ、雑誌を全てひっくるめて議題設定機能を測定していたが、新聞とテレビでは異なる議題設定効果を示すという研究結果がその後いくつか得られた。ただし、新聞とテレビのどちらがより大きな議題設定効果を示すかという点に関しては、必しも一貫した結果は得られていない。パターソンとマクルーの行った調査研究 (MeClure & Patterana ,1976)では、新聞にくらべてテレビの議題設定効果は小さいという知見が得られている。しかし、これとは逆の結果が得られた研究もある(Palmgreen & Clarke, 1977など)。
(2)議題設定効果の時間的変化(最適効果スパン)に関する研究
マスメディアがどのような争点を強調するかということは、時期によって当然異なったものになる。したがって、議題設定研究において、どのくらいの期間のメディア内容を分析するかによって、受け手の争点顕出性との間の因果的関連性も異なったものになるだろう。ここで問題になるのは、いったいメディア報道は、どのくらいのタイムスパン(時間的間隔)をおいて、受け手の争点顕出性に対してもっとも大きな影響を及ぼすのか、という点である。これを「最適効果スパン」の問題という。ストーンとマコームズ(Stone & MoCombs,1981)がニュース週刊誌を用いて行った研究によれば、受け手調査前の2~6ヶ月間のメディア内容がもっとも大きな議題設定効果を示したという。また、ニューヨーグタイムズ紙を用いて行ったウィンターとイエール(Winter & Eyal, 1981)の調査によると、最適効果スパンは受け手調査前の1ヶ月間だった。しかし、最適効果スパンの長さには研究によってさまざまなバリエーションがあり,共通の知見を引き出すことは困難である。最適効果スパンが新聞とテレビでは違うという研究もいくつかある。一般に、新聞のほうがテレビよりも最適効果スパンは長いという研究結果が比較的多く見られるようである(Weaver et al, 1981 ;Shaw & McCombs, 1977など)。つまり、新聞は長時間をかけて受け手の争点顕出性に影響を与えるが、テレビはより速効的に受け手の顕出性に効果を及ぼすといわれる(テレビのスポットライト的効果)。
(3)個人内議題(個人内の争点顕出性),対人議題(対人間の争点顕出性)、知覚された公衆議題(知覚されたコミュニティの争点顕出性)の区分
マクレオドら(MoLeod et al, 1974)は、従来の議題設定研究で受け手の争点顕出性の測定レベルが一意的ではないことを指摘し、これを「個人内の争点顕出性」「対人間の争点顕出性」「知覚されたコミュニティの争点顕出性」に分けて測定すべきことを提案した。これらは後に「個人内議題」(intra-personal agenda)「対人議題」(interpersonal agenda)「知覚された公衆議題」(perceived community agenda)と呼ばれるようになった。個人内議題とは、有権者などの個人ひとりひとりが、政治的な争点に関して抱く重要度の認知ないし評価のことをさしている。マコームズとショー(McCombs and Shaw, 1972)を始めとして、議題設定研究の多くは、「個人内の争点顕出性」に及ぼすメディアの効果を測定したものである。対人議題とは、日常の会話でどんな争点が話題に上るか、というレベルの争点顕出性のことである。また。知覚された公衆議題は、「世間の人びとは、いまどんな問題を重要な政治上の争点だと考えているか」という知覚をさしている。ノエル・ノイマンらが測定した「意見の風土」 (climate of opinion)の知覚がこれにやや類似している。実際の調査では、「あなた自身の関心は別として、世間の人たちはどんな問題を重要だと思っているでしょうか」という設問の仕方をする。マスメディアの議題設定効果は、これら3種類の議題に対して、異なる程度を示すことが予想される。
(4) 「議題設定効果」に関する3つの概念モデル
1) 認知モデル(awareness model)
これは、マスメディアが特定の争点を報道することによって、受け手がその争点の存在を「認知」するか/しないか、という次での議題設定効果である。それぞれの争点がどのくらい重要かという評価は含まれない。いわば、マスメディアの報道が特定の争点を「議論の土に乗せる」機能を果たすと考えるのである。これは、マスメディアの「争点顕在化(公共化)」機能といってもよいだろう。
2) 顕出性モデル(salience model)
これは、マスメディアで特定の争点を強調することによって、受け手の手点顕出性が高まるという効果である。認知モデルよりもレベルの高い効果である。従来行われてきた議題設定研究の大半は、このレベルでの効果を測定したものである(竹下、1984)。
3) 優先順位モデル(priority model)
これは、メディアにおける強調度を基準とする争点の優先順位が、受け手の争点顕出性における優先順位に直接影響を与えるという効果モデルである。これは,顕出性モデルよりもレベルの高い効果といえる。なお、岡田(1992)は,議題設定効果の認知的次元をより体系的に理解するための枠組として、「知覚の焦点化」(注意を比較的限定された争点や話題に焦点化する),「認知の選別的重点化」(争点・話題の重要性や優先度についての評価的認知に影響を与える),「認知の構造化」(主要な争点や話題の全体像を輪郭化する),「認知の方向づけ」(争点や話題に関する思考や論議の枠組みと文脈を設定する),という4つの次元での議題設定効果を指摘している。このうち,とくに「認知の構造化」および「認知の方向づけ」に対する効果は、従来の議題設定効果よりもさらに一歩踏み込んだレベルの認知的効果である。.
(5) 争点の構造
テレビや新聞のニュース報道では、国内外のさまざまな争点に関して、出来事の単なる報道にとどまらず、ときには事件の原因や背景,争点に対する社会各層の反応や意見。問題の解決策などに至るまで、さまざまな角度から取り上げる。これまでの議題設定研究では、こうした争点報道自体のもつ重層的構造が必ずしも明確に認識され、研究デザインに取り入れられることはなかった。その結果、メディアの争点報道のどの部分が受け手の争点認知のどのレベルに影響を及ぼすかを正確に把握することができなかった。しかし、こうした問題点を克服する試みがまったくなかったわけではない。例えば、ベントンとフレイジア(Benton and Frazier, 1976)は、争点を「一般的争点項目」「下位争点」「下位争点に関する特定の情報」の3つのレベルに分け、マスメディアがどのレベルで議題設定効果を持つかを検証した。
(6) 因果関係の検証
初期の議題設定効果に関する研究は、メディア議題と個人内議題との間の単純な相関を計算するだけにとどまっていた。これでは、メディアの議題が受け手の議題に影響を与えたのか、あるいはその逆なのか、といった因果関係を確定することはできなかった。そこで、両者の因果関係を調べるための研究がいくつか試みられてきた。
1) パネル調査データを使った時差相関分析(cross-lagged correlation)
これは、2時点で同じ対象者に対して行ったパネル調査を利用する方法である。もし時点1におけるメディアの争点強調度と時点における公衆の争点顕出性との間の相関Xが、時点Iにおける受け手の手点顕出性と時点におけるメディアの争点強調度との間の相関Yよりも大きければ、メディアの議題設定効果が確証されることになる(McCombs, 1977)。具体的な調査データをみると、例えば、ウィーバーらは、1972年大統領選挙の期間中に行ったパネル調査データと、同時期に地元新聞について行った内容分析の結果をもとにを時差相関分析にかけ、図のような関係を得た。(Weaver et al., 1981など)。
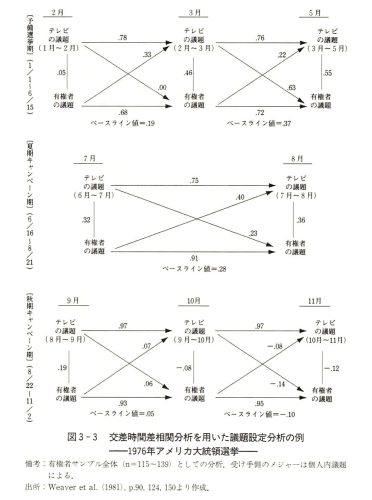
竹下(1998)より
2) 時系列データの分析
ファンクハウザー(Funkhouser, 1973)は,ニュース報道,世論調査,現実世界の指標における時系列データの相関分析を通じて、時間的順序を考慮した議題設定効果の検証を試みている(3)。分析対象期間は、1960年から1970年までの11年間である。14の争点別に、この期間のニュース報道(ニュース雑誌記事)の本数および本数の順位を調べ、また世論調査データをもとに、これらの争点に関する一般公衆の重要度の順位を計算した。その結果,ニュース報道の内容と世論の間には強い相関がみられた(順位相関係数0.78;p<0.001,カイ2乗適合度検定で有意;p<0.001)。一方,各争点に対応する現実世界の指標(統計データ)との関連を調べたところ、メディアの報道内容と現実世界の指標は、必ずしも一致していないことがわかった。しかも,そのような場合には、公衆における争点顕出性の変化は、メディアの報道に追随する傾向がみられた。これは,メディアの報道が公衆の争点顕出性を増大させるという因果関係を示唆する結果といえる。
3) 実験的な研究
アイエンガーとキンダー (lyenger and Kinder,1987)は,フィールド実験の手法を用いて、議題設定効果の厳密な検証を試みた。実験群の被験者に、アメリカの国防の欠陥に関する4本のニュース(計17分間)を4日間にわたって見せ,対照群の被験者には国防問題を含まないニュースを見せた。そして、ニュース視聴の直前と直後に調査を実施して、政治意識の変化を調べた。主な設問項目は、①8つの国家的問題についての重要度評価,②各問題に対する関心度,③政府が対策をとることの必要度、④日常会話で各問題を話題にする頻度,などであった。以上4つの設問への回答は互いに相関が高かったので、合成して問題の重要性に関する尺度をつくった。実験の結果,国防関係のニュースを見た被験者は、実験後、国防問題への関心が高まったのに対し、対照群では変化はみられなかった。この実験の結果、イェンガーらは、議題設定効果が検証されたとしている。
(7) 随伴条件(議題設定効果を規定する媒介的要因)の分析
マスメディアは,つねに、だれに対しても,同じように議題設定果を引き起こすわけではない。個人を取り巻くさまざまの内的。外的な条件が、議題設定効果を促進したり、あるいは反対に抑制したりすることがわかってきた。そうした媒介的要因のことを、議題設定研究では「随伴条件」(contingent conditions)と呼んでいる。これまでに指摘され、ある程度の実証的分析が行われてきた随伴条件には、次のようなものがある。
1) メディア接触量
メディアによく接触する人ほど、議題設定効果を強く受けるという研究結果が、ほぼ共通して得られている。例えば、竹下(19838)は、和歌山市での住民調査と新聞の内容分析をもとに、ニュース報道の争点順位と受け手の争点顕出性の順位相関係数を新聞の政治記事接触度別に計算した結果、「メディアへよく接触する人ほど議題設定の影響を強く受けている」という関連を見い出した。
2) 対人コミュニケーションの役割
他の人と政治的な話題をよくする人ほど、議題設定効果を強く受けやすいという研究がある(Shaw,1977)。ただし、これについては、これまで必ずしも一貫した結果は得られていない。例えば、マクレオドら (Mcleod et al.,1974)は,とくに高年齢層において、キャンペーンの話題に関して対人コミュニケーションの活発な人ほど大きな議題設定効果を受けやすいという傾向を見い出した。また、新間の議題設定効果が低下する選挙キャンペーン後期に対人コミュニケーションが議題設定効果を促進する機能を果たすという知見を得た。またアーブリングら(Erbring et al.,1980)の研究によれば、対人コミュニケーションは、新しく現れた争点に関してはその顕出性を高める働きをするが、長期にわたって継続する争点については効果がないという。これとは反対に、対人コミュニケーションが場合によってはメディアの議題設定効果を抑制する働きをする、という研究もある(Atwater et al.,1985など)。さらに,対人コミュニケーションは議題設定に対してなんらの効果も及ぼさないという結果も報告されている (Lasorsa and Wanta, 1990).ウォンタとウー(Wanta and Wu, 1992)は、争点として,メディアが多く取り上げる「マスメディア議題」と、あまりメディアで取り上げられないが一般公衆の関心の比較的高い「非メディア議題」の両方について、対人コミュニケーションが争点顕出性に及ぼす効果を測定した。その結果、対人コミュニケーションは、マスメディア議題については、議題設定効果を増強する働きをするが、場合によっては、競合的な非メディア議題の顕出性を高めることによって、メディアの議題設定効果を減殺することもある,という知見が得られた。また、ウィーバーら(Weaver et al.,1992)は,楽物乱用問題という争点に対する人びとの知覚を,個人の生活という「個人レベル」での知覚と,州内での問題の深刻化という「社会レベル」での知覚に分け、対人コミュニケーション、個人的経験、マスメディア接触がそれぞれ争点顕出性に及ぼす効果を測定した。その結果,個人的経験やマスメディア接触は、社会レベルの争点顕出性に影響を与えないが、対人コミュニケーションは、薬物問題に関する個人的知覚と社会的知覚をともに増大させるという知見が得られた。ウィーバーらは、この知見をもとに、対人コミュニケーションは、個人の世界を社会の世界と結びつけるという「橋わたし的機能(bridging function) を果たしている、と述べている。
第2レベルの議題設定(属性型議題設定)
(1)第2レベルの議題設定とは
従来の議題設定研究において研究の対象となったのは、ある公共的な争点(問題)だった。けれども、それぞれの争点や問題には、多くの「属性」や「カテゴリー」が含まれており、それが争点項目のイメージや顕出性に影響を与えることがある。こうした属性レベルでの議題設定のことを「第2レベルの議題設定」という。かつて、コーエンは、報道は人々に「何を考えるべきか」を伝えるのには必ずしも成功しないが、「何について考えるべきか」を伝える点では驚異的な成功を収めている、と言ったが、これは基本的な議題設定効果には該当するが、第2レベルの議題設定効果の表現としては不十分である。このレベルにおいては、メディアの報道は人々に「どのように考えるべきか」を伝えている、と考えることができる、とマコームズは言う (McCombs and Estrada, 1997)。
(2)アメリカ大統領選挙における属性型議題設定
1976年のアメリカ大統領選挙に関する2つの研究は、第2レベルの議題設定に関する初期の研究である。ウィーバーらによるパネル調査研究では、シカゴ・トリビューンの属性議題と、イリノイ州有権者による大統領候補ジミー・カーターおよびジェラルド・フォードの描写における属性アジェンダの間には、驚くべき一致が見られた (Weaver et al., 1981)。14の特性で構成されるメディア議題と、それに続く公衆議題との間のクロスラグ相関の中央値は0.70であった。また、1976年の大統領予備選挙に関する別の研究(Becker & McCombs, 1978)でも、ニュースウィークの属性議題と、ニューヨーク州の民主党支持者による党の大統領候補者に関する描写の属性議題との間にかなりの一致が見出された。これらの結果は、ニュースメディアが有権者の心の中で候補者のイメージを定義する属性議題を設定する力を持っていることを示す重要な証拠を提供している。
(3)日本の総選挙に関する議題設定研究
1990年代に入ると、第2レベルの議題設定効果を明確に示す実証的研究が次々と現れた。その最初の研究が、1993年の総選挙について行われた竹下と三上による研究である。彼らは、まず伝統的な議題設定の枠組みをもとに一般的な問題の顕出性を検討している。つまり、メディアが特定の選挙争点を強調することが、有権者によるその争点の重要性(顕出性)の認識に影響を与えたかどうかを分析している。
政治改革の問題がメディア議題を圧倒的に支配していたため、彼らは議題設定の主要な補助仮説を立てて厳密な検証を行った。メディア効果研究の長年の成果に基づき、彼らは、一般大衆における政治改革問題の顕出性は、ニュースメディアへの接触レベルに比例すると言う補助仮説を立てた。この接触レベルの測定は、各回答者の政治関心度の測定を加えることでさらに強化された。このニュース接触と政治関心を組み合わせた測定は、政治ニュースへの注意度を示す指標となる。この指標に基づき、彼らは、政治改革問題の顕著性が政治ニュースへの注意度と正の相関を示す、という仮説を立てた。東京の650人の有権者を対象にした調査データ分析の結果は、この仮説を支持していた。テレビニュースへの注意度については、政治改革の顕出性との相関は0.24であり、新聞については0.27であった。党派的帰属、学歴、年齢、性別を統制した偏相関も有意であった。
ニュースメディアへの接触が公衆議題における政治改革問題の顕著性に影響を与えたという証拠が得られた後、竹下と三上は第二次元へと研究を進めた。政治改革の7つの側面についての回答者の個人的重要度評価を因子分析した結果、2つの明確な因子が明らかになった。一つは「倫理関連因子」(政治家の行動に法的制限を課す提案や、政治家の綱紀粛正を強化する提案を強調するもの)、もう一つは「制度関連因子」(選挙制度の変更や改革を求めるもの)である。テレビニュースと新聞は、制度関連の改革側面を倫理関連の側面よりも2倍頻繁に取り上げていた。このようななメディア議題は、有権者の頭の中にある政治改革のイメージ(属性議題)に影響を与えたのであろうか。議題設定の第2レベルに関するこの問いに答えるためには、竹下と三上が第1レベルの議題設定の分析で用いたものと類似の方法で定式化された2つの仮説を検証する必要がある。第1の仮説は、公衆議題における制度関連の改革の顕出性が、政治ニュースへの注意度と正の相関を示すことを主張する。一方、第2の仮説は、公衆議題における倫理関連の改革側面の顕出性と政治ニュースへの注意度の間に相関がないことを予測する。分析の結果、どちらの仮説も支持された。この研究は、第1レベルと第2レベルの議題設定効果を同時に検討し、我々の頭の中のイメージに対する両レベルの議題設定効果について強力な証拠を示している。
(3) 環境問題の属性議題
経済問題と同じような広がりと複雑さを持った,もうひとつの現代の争点が環境問題である。公共的争点として、環境問題は国際的な関心事からローカルなものまで、あるいは抽象的な関心事からきわめて具体的なものまでを含んでいる。三上・竹下・仲・川端の研究は、地球環境問題に関して、日本の2大日刊紙のニュース報道が東京都民の関心のパターンに影響を及ぼしていることを明らかにした。1992年6月の「環境と開発に関する国際連合会議」に先立つ4ヵ月間、「朝日新聞」「読売新聞」は、地球環境問題の8側面に関する報道を着実に増やした。 こうした報道には酸性雨、野生動植物の保護、人口爆発、地球温暖化など多様な下位争点が含まれていた。 こうしたニュース報道は、東京都民の間で有意な議題設定効果を生み出した。(6月半ばに実施した面接調査の直前から)2月の時点まで遡って報道内容を測定し場合には、新聞の属性議題と公衆の属性議題との相関は+0.68であった。面接直前から4月の初旬までの内容分析期間では、相関は+0.78まで増大し、これが一番高い値で、内容分析期間を面接直前から5月中旬に短縮するまでこの値が続いた。国連会議開催日と重複する日および会議直前週に内容分析期間を絞った場合には、新聞議題との一致度がより低くなってしまった。これは、議題設定の学習過程には時間的ズレが関わっていることを示唆するものである。日本で見出された時間的ズレは、米国で地球環境問題の諸側面に関して発見されたズレと類似していて興味深い (Mikami et al., 1995; McCombs and Estrada, 1997)。
(4) 属性型議題設定とフレーミング効果
第2レベルの議題設定、すなわち属性型議題設定の展開もまた、この理論を同時代の別な主要概念ーフレーミング(framing)一と連結させるものである。属性型議題設定とフレーミングは、メッセージ内で注目された容体それが争点であれ、政治家であれ、他のトビックであれーがどのように提示されるかに焦点を合わせている。属性型議題設定もフレーミングもともに、こうした容体の特定の側面や評細を強調することが、客体に関するわれわれの思考や感情にどの程度影響を及ぼすのかを探究する。画機会の結合に関してこうした一般的な記以上に踏み込むことは難しい。というのも、フレーミングの定義の仕方にはかなりのばらつきが見られるからである。結果として、属性とフレームとが同義的な概念となることもあれば、重複した、ないしは間連した概念とされることもある。ときには、両者はまったく異なる概念と見なされることもある。
両概念を同義的に用いた例から始めると、1996年米大統領選候補者指名で共和党の4人の候補者のキャンペーンをコンピューターを用いた内容分析で調べたある研究は、各陣営のプレスリリースや「ニューヨークタイムズ」「ワシントンポスト」「ロサンゼルスタイムズ」におけるキャンペーン関連ニュースで、28の属性を特定した。議題設定の視点から見ると、この研究の焦点はプレスリリースとニュース報道の属性議題であったが、論文の題名では焦点は「候補者をフレーミングする」と表現された。議題設定研究のデザインとは異なり、発表された論文は、候補者陣営による発表内容とジャーナリストによる描写内容とを比較するものではなかった。議題設定理論にもとづくならば、ごうした追加の比較を行うことで、候補者のプレスリリースがニュース議題に反ほす属性型議題設定効果を発明することができる。テキサス大学で行われた読題設定理論のセミナーで計算したところ、このフレーミングと命名された研究から、属性型議題設定効果に関する実質的な証拠が得られた。候補者のうち3人の相関はそれぞれ+0.74.+0.75.そして+0.78であり、ロバート・ドールに関してはやや低めの、しかしまだ十分に高い+0.62という数値が得られた。ごのドールが最有力候補であり、最終的に共和党の指名候補となった。
フレームと属性との間の重複→理論的連関一に対する独創的な視点を採用したのが、日本経済の第状に対する世論を扱った研究である。この分析は、フレームとは下位の諸属性を集約する装置であるというアイディアにもとづいているが、同時に「問題状況 (problematic situations)」の概念にも依拠している。問題状況概念とは、具体的な社会争点や関心事をより一般的な認知的カテゴリーへと読み換える視点でお客。(200年から201年にかけての)82週間にわたり「毎日新聞」を内容分析し、日本経済の等状に関してニュース報道で取り上げられた12の異なる側面もしくは属性を特定した。日本経済の写状に関するこうした属性を問題状況のコンテクストに位置づけるために、一般公業に対する調査では、こうした12の側面のそれぞれを回答者がどれくらい問題合みだと考えているかがたずねられた。12項目に関する回答を因子分析することで、4つのマクロフレームが析出された。それらは問題状況カテゴリーとしてあらかじめ理論的に仮定されたものとほぼ一致していた。各因子は「制度崩壊」「損失」「不確実さ」「対立」のカテゴリー(フレーム)を表し、12項目はすべていずれかに収まった。
「毎日新聞」による経済報道の属性型議題設定効果は、下位の属性(争点の
12の側面)のレベルと、マクロなフレーム(4つの問題状況カテゴリー)のレベルの両方でテストされた。両レベルとも、ニュースへの接触度が高まるにつれ、新聞の議題と公衆の議題との一致度は増大する傾向が見られた。下位の属性の場合,ニュースへの低・中・高接触グループの相関はそれぞれ+0.54,+0.55., +0.64であった。フレームの場合、同じく接触度別3グループの相関は+1.00,+0.80,+1.00である。相関の値が2つのレベルで異なっているのは明らかにカテゴリー数が異なるからであろう (12対4)。しかし,ミクロ・マクロ属性両方の場合とも議題設定効果が見出された。
メディア議題の設定
ロジャーズとディアリング (Rogers and Dearing, 1988)は,議題設定研究を「社会における影響過程の研究」の一方法として位置づけ、議題設定に関する従来の文献をレビューした結果、これを「メディア議題の設定」「公衆議題の設定」「政策議題の設定」_という 3種類の議題設定に関する研究系譜に整理した。ここで、「議題」(agenda)とは、ロジャーズとディアリングによれば、「ある時点において重要性の階層の中で順序づけられて知覚される争点や事象」と定義されている。これまでの議題設定研究では、上にあげた3つの議題をそれぞれ従属変数として、これらがどんな要因によって影響されるかが研究されてきたという。この論文では、約150にも及ぶ従来の議題設定に関する研究文献を分析し、その問題点を抽出するとともに、将来の議題設定研究に向けての理論的統合を試みている。そのための概念枠組みが、以上3つの議題間の相互依存および規定要因の連関関係として、図のように整理されている。
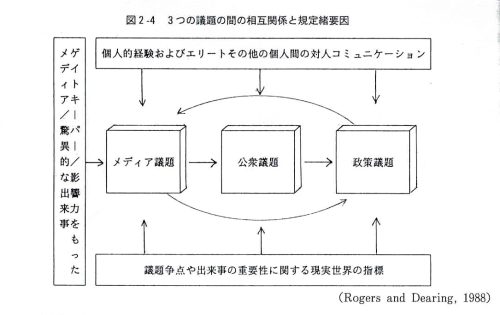
(1) メディア議題の設定
ロジャーズとディアリング(Rogers and Dearing, 1988)によれば、メディア議題(media agenda-setting)の設定に関する研究は、ラザースフェルドとマートン(Lazarsfeld and Merton, 1948)にまで遡ることができるという。ラザースフェルドとマートンは、権力をもった集団、とくに組織された企業が、微妙な社会的コントロールを通じて影響力を行使する結果,メディアの議題が設定される、という認識をもっていた。このような認識は現在の議題設定研究においても基本的に変わっていないが、今日では、メディア議題の設定過程において、単にパワーエリートからの影響力だけでなく、メディア組織内部の権力関係、他メディアとの競争、公衆議題、現実世界の出来事など、多くの影響源が指摘されている。
(2) 公衆議題の設定
すでに見たように、コーエン(Cohen, 1963)は、「プレスは大抵の場合,人びとにどう考えるか(What to think)を教えることには成功しないかもしれないが、何について考えるか(What to think about)という点に関しては大いなる成功を収めている」と述べ,マスメディアの議題設定機能を初めて明確に定式化した。これを「争点顕出性」という概念を用いて操作的に定義し直し、実証的仮説検証に道を開いたのが、マコームズとショー(McCombs and Shaw, 1972)の研究であった。メディア議題の場合と同様に、公衆議題の設定過程に対して影響を与える要因には、マスメディアだけではなく、対人コミュニケーショシ、オリエンテーション欲求などがあり、これらはすでに述べたように「随伴条件」として研究されてきたところである。
(3) 政策議題の設定
政策議題(Policy Agenda)の設定過程に関する研究は、従来から主として政治学の分野で進められできた。そこでの問題は、ある争点が政策決定者の制度的議題に上がるのは、どういったメカニズムによるのか、それを規定する条件は何か、といったことである。最近では、政策議題の設定過程においてマスメディアの果たす役割に注目した研究が、コミュニケーション研究者の側でも活発に行われるようになってきた。これは、実証的な議題設定研究を「議題構築過程」の研究と結びつけることによって、世論過程のダイナミズムをより明確に把握しようとする試みとしても位置づけることができる。ウォーターゲート事件における政策議題の構築過程とマスメディアの役割を詳しく追跡したラング夫妻(Langand Lang, 1983)の研究は、その先駆的な業績といえる。
(4) 3つの議題の間の相互関係
以上述べた3つの議題は,相互に独立したものでないことは、ロジャーズとディアリングの図からも明らかである。また、図の矢印がフィードバック・ループを作っている点にも注意する必要がある。世論形成過程の中で,3つの議題は、相互に複雑な影響を与え合っているというのが実態である。例えば、メディア議題と公衆議題との間の影響関係についても、両者が相互に相手に一定の影響を及ぼしていることが、これまでの研究でも観察されている(Erbring et al, 1980; Weaver et al, 1981など)。ザッカー(Zucker, 1978)によれば、疎遠な争点については、「メディア議題→公衆の顕出増大」という影響が強く作用し、身近な争点の場合には「公衆議題→メディア議題における顕出性増大」という影響がみられたという。ラング夫妻(Lang and Lang, 1983)も,ウォーターゲイト事件が政治争点化していくプロセスにおいて,メディア議題、公衆議題、政策議題の相互間で複雑な形響が作用しあっている様を詳しく記述している。
セメツコら(Semetko et al., 1991)は、マスメディアや政党・候補者が選挙期間中に、どのようにしてキャンペーン議題を形成するかという問題に焦点を当てて、メディア議題の形成過程に関する研究を行った。とくに、メディアの議題形成が社会の政治・文化構造の中で形成されるという点に注目して、アメリカとイギリスという異なる政治・文化構造をもつ2カ国の国際比較研究を行った。この研究は、従来の「メディア効果」という視点から、「メディアー政治組織関係」の視点への転換として位置づけられる。その問題意識は、「もしメディアが議題を設定するとすれば、だれが議題設定者に対して議題を設定するのか? (If the media set the agenda, who sets the agenda for the agenda-setters?)という点にある。研究の焦点は、メディアが選挙キャンペーン中に行う選挙関連ニュース報道は、単に政治家や候補者の提示するメッセージを伝達するだけなのか,それとも,独自の裁量権を発揮して、自ら選挙キャンペーンの争点を提示するのか、という点に当てられた。もちろん。現実にはこの両者は二者択一の関係にあるわけではなく,選挙報道は,つねに政治家とジャーナリストとの間の相互作用の産物である。問題は、その中でメディアの裁量権が現実にどの程度発揮されているか、メディアの裁量権を規定する要因は何か,ということである。
セメッコらは「アメリカの方がイギリスよりもメディアの裁量権は大きい」という仮説を立てた。この仮説を検証するために、彼らはテレビニュースと新聞記事の内容分析、②テレビ局での選挙ニュース制作過程の参与観察、③政党と候補者のキャンペーン資料の内容分析,という3種類の調査データを用いて、英米両国の比較分析を行った。調査の結果、次のような知見が得られた。
1) テレビニュースの議題形成
イギリスのテレビの選挙報道は、アメリカにくらべると、より内容豊かで,多様で,実質的で、政党志向が強く,一方的なコメントに関する自由度が低く、政治家に対して敬意を含んだものになる傾向がみられた。これに対して、アメリカの選挙ニュースは、より簡明で、集中的で、競争レース的で、伝統的なニュース価値によって誘導され,すぐに判断を下しやすく、そうした判断を下す際に、しばしば政治家を見下すような態度をとることがあった。また、イギリスでは、アメリカよりも政治家についてのキャンペーン記事が多く、政治家から直接情報をインプットされる余地があった。イギリスでは、夜のキャンペーンニュースの3分の1以上は政治家の生の声で占められていたが、アメリカのネットワークキャンペーン報道では、わずか9分の1以下であった。ビジュアルな映像を分析した結果,アメリカのテレビ局は、ニュースを選択する際にイギリスより大きな裁量権を行使していることがわかった。
イギリスではアメリカより政党始動型ニュースが多かった。実質的なトピックスとゲーム的なトピックスとをくらべると,イギリスでは実質的な争点が多いのに対し、アメリカでは競馬レースのような勝負により大きな重点が置かれた。その分だけ、アメリカではメディア始動型のニュースが多かった。
以上から、アメリカのテレビ・ニュース制作者は、イギリスにくらべて、キャンペーン議題の設定において、より大きな役割をはたしていることがわかった。イギリスでは、アメリカに比べて、政党の議題とメディアの議題との間により密接な関連がみられた。
2) 新聞議題の形成過程
アメリカではイギリスにくらべて,キャンペーン期間中のメディアの裁量権が大きい,という仮説が支持された。イギリスでは候補者の示す争点順位をそのまま忠実に伝える傾向がみられるが、アメリカの場合には、こうした傾向はあまりみられなかった。
新聞の党派性は、政党の争点議題が報道される仕方に影響を与えている。イギリスの新聞は全体として政党の争点順位をかなり忠実に反映させているが、党派性のとくに強いタブロイド紙は、ときに非常に批判的な報道をしていた。
また,イギリスの新聞はアメリカに比べると、政党始動型のニュースがはるかに多かった。アメリカの新聞は、文達でもビジュアルでも、メディア始動型ニュースがはるかに多いという傾向がみられみリポーターのコメントについても、アメリカのジャーナリストの方がイギリスよりも大きな裁量もっていた。方向性をもったコメント、とくに相手をけなすようなコメントはアメリカのジャートの方が多かった。このように、アメリカではイギリスに比べてテレビでも新聞でも議題形成における裁量権が大きいう知見が得られた。言い換えると,イギリスの場合には、メディアは議題を「設定する」よりは、しろ議題を「増幅する」(agenda amplifying)役割をはたしている。これに対して、アメリカのメテアは、議題を「形成」(agenda shaping)しているということができる。とセメッコらは述べている。
結論として、セメツコらは、今後の研究課題を中心に、次のような点を指摘している。
① 議題設定研究者は、キャンペーン議題の形成過程をもっとくわしく探求すべきである。現実の選挙キャンペーンにおいては、マスメディアの議題をいかにコントロールするかをめぐって、さまざまな政治勢力やジャーナリストの間で激しい駆け引きや争いが展開されているのである。それゆえ、今後の研究においては、「議題設定」を動態的なプロセスとして理解しなければならない。議題形成をメディア議題のコントロールをめぐる戦い(struggle for controling media-agenda)として捉えるならば、このプロセスは政治制度,制度内でのメディアの地位、メディア組織内部特性の相違などによって大きく左右されることに注意すべきである。
② 将来の議題設定研究においては、マスメディアの議題設定行為を所与のものと考えてはいけない。つまり、メディアの議題がジャーナリストとニュース組織だけによって決められると考えてはならない。また,選挙キャンペーン期間中,メディア議題が政党や候補者だけによって一方的に決定されると考えるのも正しくない。
(5) ニュース議題の設定におけるPRの役割
国際レベルから地方レベルまで、政府や企業の活動についてわれわれが知っていることの多くは、広報官や他のPR 実務家が発信源になっている。こうした政府の広報官や企業のPR担当者は、ニュース機関の活動に対して、日々まとまった量の情報を提供することで「情報助成(subsidy)」を行っている。しかも、この種の情報はニュース記事のスタイルを正確に模した「プレスリリース」の形で提供されることが多い。「ニューヨークタイムズ」と「ワシントンポスト」の紙面の 20年間分を調べたところ、記事の約半数はプレスリリースや他の直接的な情報助成に基づくものであった。両紙の記事総数の約17.5%は、少なくとも部分的にはブレスリリースに基づいていた。別の32パーセントは記者会見や背景説明がネタであった(Sigal, 1973)。「ニューヨークタイムズ」や「ワシントンポスト」は、大量のスタッフと多大な資源を有する大新聞社である。これら両紙でさえPR情報源にかなりの程度依存しているという事実は、メディア議題全体が日々形成するうえで情報助成が果たしている役割を浮き彫りにするものである。
ルイジアナ州の主要日刊紙による6つの州政府機関に関するニュース報道もまた、そうした機関の広報官が提供する情報にかなりの程度まで基づいていた。こうした広報官が提供する情報助成(主に文書化されたプレスリリースによるものと、時たま口頭での伝達によるもの)の半数をやや超えるものが、その後に記事化された。トピックの議題は、州の財政から一般経済、また冠婚葬祭から祝賀イベントまでを含む幅広いものであった。具体的に言うと、広報官発の議題とそうした情報を利用したニュース記事の議題との間の8週間の期間での対応度は+0.84であった。州政府機関発の議題とそれら州政府機関に関する全記事との同じ期間での対応は+0.57であった。
(6)メディア間の議題設定
エリート級のニュースメディアは、他のニュースメディアの議題に対してかなりの影響を及ぼすことが多い。米国でメディア間議題設定の主役を演じることが多いのは「ニューヨークタイムス」である。この役割は今やかなり制度化されており、AP通信社はその会員社に対して、タイムズ紙の翌朝刊1面に掲載予定の記事リストを毎日送信するほどである。タイムズ紙の1面に載ることが、あるトピックがニュースバリューを持つ証しと見なされることが多い。
ニューヨーク州西部ラブキャナル運河での深刻な化学物質汚染事件や、ペンシルバニア州やニュージャージー州辺でのラドンガスの脅威といった問題は、地方紙が何ヶ月にもわたって集中的な報道を行っていたにもかかわらず、これらの問題が「ニューヨークタイムズ」の議題に上るまでは全国的な注目を集めることはなかった。1985年後半にタイムズ紙が薬物問題を発見したことが、翌年には米国中の主要紙や全国テレビニュースによる大規模報道をもたらした。その報道のピークは 1986年9月にネットワーク局それぞれが全国放送した特集番組である。ある韓国の研究は、大手ニュース組織によるメディア間のこうした影響が、オンラインニュース環境でも存在することを示している。
議題設定効果の帰結(後続効果)
初期の議題設定研究は、メディアの効果を、受け手の「争点顕出性」という知覚レベルに限定していたが、その後の展開の中で、議題設定効果のレベルを拡大し、受け手の認知構造へ、さらに態度や行動のレベルでの効果にまで研究の射程を広げるようになっている。
ウィーバーら(Weaver et al., 1981)は、アメリカ大統領選挙における調査を通じて、マスメディアが有権者の候補者に対する認知的イメージに影響を与えるだけではなく、候補者への評価にも影響を与えているという結論を下した。これは、マスメディアが受け手の態度を変化させたためだろうか。この点に関しては、ベッカーとマクレオド(Becker and McLeod, 1976)の提案したモデルが参考になる。かれらによれば、公衆の認知変化は、マスメディアの設定した議題による直接的効果であるか、おるいはマスメディアのメッセージ内容から、公衆の態度を通して媒介された、間接的効果であるか、のいずれかだという。これと関連して興味深いのは、イエンガーとキンダー(lyenger and Kinder, 1987)の提唱した「プライミング効果」(priming effect)である。彼らは、内容を統制したテレビ・ニュースを用いたフィールド実験を行った結果,アメリカ大統領に関するニュース報道は、争点についての認知を高めただけでなく、大統領のとっている政策を判断するための基準(standard)を設定するという効果を及ぼしていることを突き止めた(^。このように、政治的評価を下す際の基準が変化することを、イエンガーらは「プライミング」呼んだ。こうした「基準」は、しばしばプラスあるいはマイナスの価値評価を含んでいるので、プライミング効果を通して、争点対象に関する意見形成にも影響を及ぼすことになる。一般に、メディアが争点の特定部分を強調したり、争点対象についての判断基準を与えたり、あるいは特定の文脈の中に位置づけたりすることを、争点対象の「フレーミング」と呼ぶことにすれば、プライミングは、メディアによる「フレーミング」の後続効果と考えることができる。そして、メディアの議題設定効果を「フレーミング効果」にまで拡張することも可能であると思われる。これは、岡田(1992)が指摘した効果の認知的次でいえば、「認知の構造化」および「認知の方向づけ」の効果に相当する。問題は、こうした効果が度変化を必然的に伴うのか、という点であろう(Rogers and Dearing, 1988)。これについては、さきほどのベッカーとマクレオド(Becker and MeLeod, 1976)を参考として考察するならば、次のような仮説が設定できるのではないかと思われる。すなわち、メディお手点をどうフレーミングするかによって、受け手の異なる態度要素が活性化されて、争点と結びっけられ、それが現象的には「意見の変化」を引き起こすことになるのではないか、という仮説である。
例えば、最近再び政治争点として浮上しっつある「憲法9条改正問題」についていえば、マスメディアは以前ならば「憲法改正→自衛隊の軍隊化→過去の戦争への逆行」というフレーミングで報道していたのが、最近では「憲法政正→自衛隊のPKO活動→国際平和の維持」という文脈の中での新たなフレーミングが行われるようになっている。この場合,戦争や平和への態度は不変でも,こうしたフレーミングの変化を受け入れることによって、憲法改正には「賛成」という意見レベルの変化が生じることは大いにありうる。事実,最近の世論調査では、憲法改正に賛成の意見が次第に増えているのである。
マスメディアの議題設定効果が、争点顕出性の増大を通じて、さらに態度や行動にまで影響を及ぼすという「2段階の影響過程」(two-step process)モデルを提唱する研究者もいる。ロバーツ(Roberts,1992) は、1990年のテキサス州知事選挙期間中に、3回にわたるパネル調査を行い,政治広告の議題設定効果を測定した。この選挙は RichardsとWiliams という2人の候補者の間で争われたが、ロバーツは、Richards に投票したグループとWilliamsに投票したグループとの間に争点認知の違いがあるかどうかを,判別分析によって検討した。その結果,争点に対する関心度によって,投票行動の約70%が正しく判別された。さらに、「政党支持」「性別」「メディア情頼度」「勝敗予想への関心」「選挙戦への関心度」を説明変数として追加投入すると、投票行動の判別率は80%以上になった。この結果から、日バーツは,2段階の議題設定効果が生じていることがある程度確かめられたとしている。
それでは、なぜ2段階の影響過程が生じるのだろうか。この点に関しては、ブロシウスとケプリンガー(Brosius and Kepplinger, 1992)の研究が参考になる。ブロシウスらは、メディア議題がドイツの有権者の政党支持に及ぼす効果を解明するために,テレビ・ニュースの内容と有権者の投票意図の関連を調べた。その結果;テレビ・ニュースは、単に有権者の手点顕出性を高めるだけでなく,政党支持にも膨響を与えているという知見が得られた。この知見を説明するための理論仮説として、ブロシウスとケプリンガーは、「手段的実現理論」(The theory of instrumental actualization)を提案した。これは、受け手が一方の対立陣営の見解を支持する出来事に接触すればするほど、彼らはその陣営の見解を支持するようになる」という仮説である。選挙というのは、一種の儀式化された対立抗争である。選挙期間中に,マスメディアが一方の陣営の候補者の得意とする(と一般に知覚されている)争点や出来事を大きく報道するならば、有権者は、そうしたメディアに多く接触すればするほど、その候補者の見解を支持するようになる。このような手段的実現理論は、プライミング効果ときわめて類似しており、またフレーミング効果の一形態とみなすこともできる。
日本における議題設定研究
基本仮説の検証(竹下 1982)
チャペルヒルでマコームズとショーが行った最初の議題設定研究の追試を日本で最初に本格的な形で行ったのは、竹下俊郎(1983)である。データの測定モデルや調査方法はマコームズらに準じている。
調査の概要:
1. 受け手調査
調査地点:和歌山県和歌山市
調査対象:選挙人名簿から無作為抽出された成人男女1,000名。有効回答数は717。
議題設定に関する設問項目:争点顕出性測定のための質問(争点リストの中から最も関心のある争点を選んでもらう)、新聞・テレビ接触、他者との政治会話の頻度、政治への関心度など。
2. 内容分析
対象メディア:新聞(全国紙4紙)、テレビ(NHKおよび民放の夕方のニュース番組)。受け手調査最終日に先立つ6週間分を内容分析。
3. 調査に用いた争点カテゴリー
①外国との貿易摩擦
②防衛問題
③行財政改革
④所得税減税
⑤ロッキード問題
⑥公共事業の談合・不正
⑦校内暴力・青少年非行
調査の結果:
議題設定仮説に従えば、ある争点がメディアにおいて顕出的であればあるほど、受け手の側でもその争点を顕出的(重要)とみなす人が多くなるはずである。この仮説を検証するために、一方ではメディアでの言及量が多い順に争点の順位づけを行い、他方受け手の側でも、最も重要なものとして回答された比率が高い順に争点を順位づけ、両者の争点順位の一致度を順位相関係数を用いて調べた。分析にあたって、メディア議題分析(争点顕出性)の集計期間を変化させることによって、受け手に対する議題設定効果の最適な期間(最適効果スパン)も検討している。
新聞についてみると、新聞の争点顕出性の順位と受け手の順位の相関が最も高かったのは、内容分析の測定期間を面接最終日前2週間ないし3週間とした場合であり、順位相関係数はそれぞれ0.71、0.75であった。議題設定効果を左右する随伴条件として、「メディア接触」「トピックへの関心」などの要因を分析した。メディア接触については、議題設定効果が最も強く現れているのは、新聞の政治記事をよく読むグループだった。トピック(政治)への関心度との関連をみると、タイムスパンが2週間の場合も3週間も場合も、政治への関心が高いグループほど新聞の争点顕出性との一致度が高い、つまり議題設定力が強いことを示す結果が得られた。
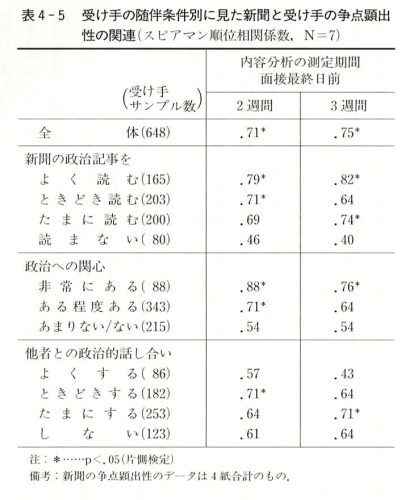
テレビについて同じように分析してみたところ、テレビニュースの議題と受け手議題との間の相関は、最適タイムスパンの如何に関わらず.20以下であり、非常に相関が低いという結果となった。随伴条件との関連についても新聞と同じ分析を行なっている。まず、テレビニュースを「よくみる」と回答したグループでは、他の回答者よりも相対的に高い相関値を示しており、議題設定効果の大きさとメディア接触量とが正の関連にあるという傾向が見られた。政治への関心度との関連をみると、測定期間に関わらず、政治への関心が高いほど、テレビニュースと受け手の関連も強まる傾向が見られた。
パネル調査による検証(竹下 1986)
本研究は、前記の基本仮説調査とは違って、パネル調査による検証を行なっていること、国政選挙の期間中に調査を行なっている点に特徴がある。
調査の概要:
1. 有権者調査:
第1回:1986年6月6日〜8日
第2回:1986年6月21日〜23日
第3回:1986年7月4日、5日
個人内議題をたずねる設問:「今度の選挙で争われる政策上の問題のうち、あなたが最も重要だと考える問題は何でしょうか」
世間議題を尋ねる設問:「では、あなた自身のお考えはさておき、今度の選挙で世間の多くの人々が最も重要だと考えている政策上の問題は何だと思いますか」
(自由回答で答えてもらい、アフターコーディングして分析した)
2. 内容分析:
新聞(朝日、読売)、テレビニュース(夕方の全国向けニュース番組)を分析。
3. コーディングした争点カテゴリー
①税金・税制
②円高・景気・貿易
③物価
④行財政改革
⑤福祉
⑥教育
⑦防衛
⑧首相の政治手法
⑨その他の争点
⑩争点への言及なし
調査の結果:
1. メディア議題
新聞の争点報道を時期別にみると、第1期で最も多く取り上げられた問題は「中曽根首相の政治手法」であり、「円高・景気・貿易」問題がそれに続いていた。第2期になると、「税金・税制」問題が急浮上し、第3期でもそのまま第1位の座を占め続けた。テレビの争点議題も新聞とよく似ていた。第1期の報道で最も突出していた争点は首相の政治手法の問題だった。それが第2期には税金問題がトップに躍り出る。そしてその傾向は第3期まで持続した。
2. 有権者の議題
まず個人内議題をみると、有権者が今回の選挙で最重視した争点は、円高問題や税金問題など経済領域の問題に集中していた。首相の政治手法は有権者の関心を引くことはなかった。特に第2期以降、税金問題に対して有権者の関心が収斂する傾向が強く見られた。一方、世間議題(世間の注目を集めている争点)についても、円高問題や税金問題を挙げる回答者が投票日に近づくにつれて急増する傾向が見られた。
3. 議題設定仮説の検証
パネル調査のデータで見たメディア議題-対-有権者の議題の組み合わせパターンをみると、キャンペーンが進むにつれて、メディア(新聞、テレビ)の議題と有権者の議題(個人内議題、世間議題)との相関(順位相関係数の値)が高まっていく、という傾向が見られた。相関が高まっていった原因は、時期を経るごとにメディアの議題が有権者の議題に歩み寄ったいったためだとわかった。メディアの議題設定効果は有権者の個人内議題のレベルよりも、世間議題のレベルでより明瞭に検出された。すなわち、新聞やテレビニュースの選挙報道は、有権者個人にとっての重要争点を規定するよりも、世間の多くが重視する争点は何かという有権者の認知に対して、より大きな影響を及ぼしていたと考えられる。
i
4. 選挙報道への注目度がきわめて高いレベル(VH)から、比較的高いレベル(日)、中程度(M)、低いレベル(L)までの四グループに分けて分析した結果、VHグループは、各時期・各メディアごとに四通り作成した注目度のタイポロジーのどの場合にも、回答者サンプルの一割前後を占めているにすぎないが、政治への関与度や投票意図の確定度では他のグループより抜きんでていいることがわかった。おそらく、選挙に関して自分なりの判断基準を確立しているがゆえに、メディア報道の高利用者でありながらも、議題設定の影響を受けにくくなっているのだと推測される。(ハードコア層の可能性)
属性型(第2次)議題設定効果の検証(竹下、三上 1995)
本研究は、マコームズのいう議題設定研究の第3期に属するもので、従来の一般的争点を超えて、属性型の争点や下位争点レベルの議題設定効果に注目して仮説検証を試みたものである。新たな段階の議題設定研究を切り開く研究として、国際的にも大きな注目を集めた(例えば、McCombs, 1997など)。
調査の対象となったのは、1993年7月に行われた総選挙である。この総選挙は国政に38年ぶりの政権交代をもたらした画期的な選挙だった。6月19日に政治改革法案をめぐって宮沢内閣不信任案が可決されて、衆議院が解散された。可決後、自民党の一部改革派議員が離党して新党を結成し、野党各党と「非自民連立政権」の樹立で合意するなど、総選挙での政権交代を実現しようという動きが活発化した。選挙の結果、自民党の議席は過半数を大きく割り込み、新生党、日本新党、新党さきがけの保守新党が躍進、与野党間の激しい駆け引きの末に、細川護煕(日本新党代表)を首班とする非自民連立内閣が誕生することになった。
この総選挙では、マスメディア特にテレビの果たす役割が大きな注目を集めた。非自民連立政権を誕生させ、自民党一党支配の55年体制を崩壊に導いた立役者はテレビのニュースや政治討論番組だったのではなかったのか、という議論が自民、非自民いずれの側からも指摘された。いわゆる新党ブームは、マスコミの力を借りて引き起こされたものであることは、誰の目にも明らかだった。特に、テレビ朝日の人気番組「ニュース・ステーション」では、久米宏キャスターや和田解説委員が「政治を変えなければならない」と盛んに強調した。実際、テレビ朝日報道局長(当時)が「政治とテレビ」をテーマにした日本民間放送連盟の会合で、先の総選挙報道について、「非自民連立政権が生まれるよう報道せよ」と指示した、との発言を行ったことが『産経新聞』で報じられるなどテレビで世論操作が行われたのではないかとの疑惑が沸き起こり、国会証人喚問にまで発展した。
調査の概要:
1. 有権者調査(パネル調査)
東洋大学社会学部の社会調査実習の一環として実施した。
第1回調査:
調査期間:1993年7月7日(日)〜11日(日)
調査対象者:練馬区在住の20〜74歳男女650名
標本抽出法:住民基本台帳から確率比例2段階無作為抽出
調査方法:個別訪問面接、留置法を併用
有効回収:342票(52.6%)
第2回調査:
調査期間:1993年7月15日(木)〜17日(土)
調査対象者:第1回調査の回答者342名
調査方法:個別訪問面接、留置法を併用
有効回収:182票(53.2%)
2. 内容分析:
新聞(朝日、読売)、テレビニュース(NHKおよび民放の夜のニュース番組)を内容分析。
3.調査票で取り上げた項目:
a) 一般的な争点レベルの議題
「この中で、最も重要だと思う問題は何ですか?」と尋ねた。
b) 政治改革の下位争点レベルでの議題
「政治改革の問題について、最も重要だと思う点は何ですか?」と尋ねた。
調査の結果:
1. 一般的な争点レベルでの議題設定
内容分析の結果、政治改革が1993年総選挙報道において圧倒的に顕著な争点であったことがわかった。そこで、メディアの強調度と有権者の顕著性の順位を比較する方法を採用せず、仮説検証のために2つの指標を構築した。1つは、最大争点である政治改革問題の一般的な顕出性レベルの測定である。前述の「最も重要な問題」についての質問において、回答者が政治改革問題に全く言及しなかった場合は「低顕出性」とし、それを最も重要な問題の一つとして挙げた場合は「中顕出性」、最重要問題として挙げた場合は「高顕出性」としてコーディングした。全回答者のうち、41.8%が低顕出、33.9%が中顕出、24.3%が高顕出と分類された。2つ目の指標は、テレビや新聞における政治ニュースへの注意度で、テレビニュースや新聞への接触レベルと選挙への関心レベルを組み合わせて構成した。これは、メディア効果に関する測定値として、単なる接触レベルの測定よりも効果的な予測因子であると期待される。
一般的な問題レベルで議題設定効果が発生する場合、テレビや新聞の政治ニュースへの注意度の増加は、政治改革問題の顕出性の増加と関連することが予測される。この予測を検証するため、政治ニュースへの注意度と政治改革問題の顕著性の間の単純および偏相関係数を計算した。分析の結果、テレビや新聞の政治ニュースへの有権者の注意度と政治改革問題の顕著性の間に、統計的に有意な相関が見出された。この相関は、人口統計学的および党派的変数を統制した後でも中程度の強さであった。これにより、一般的な問題レベルで議題設定効果が検証された。
2. 政治改革の下位争点レベルでの議題設定
政治改革に関する下位争点の顕出性は、政治改革の7つの具体的な項目リストを用い、回答者にとって最も重要だと考える項目を選んでもらった。この回答を因子分析した結果、政治改革に対する人々の理解は2つの因子に要約できることが分かった。一つは「倫理関連因子」と呼べるもので、腐敗防止や綱紀粛正を強調するものである。もう一つは「制度関連因子」と呼べるもので、特に選挙制度改革を含む制度の変更や改革を、政治改革全般への最も重要なステップと位置付けるものである。この2つの因子に基づき、政治改革の下位争点顕出性を示す指標を、各回答者の因子スコアを計算することで構築した。
政治改革に関連する報道においてメディアがどのような下位争点を取り上げたかを分析したところ、元の7つのカテゴリーは、回答者の下位争点顕出性測定で使用した2つの因子と同じパターンに統合された。「制度」関連の下位争点に言及する記事の数が「倫理」関連の下位争点に言及する記事の数をほぼ2対1の比率で上回っていることが示された。この結果から、下位争点レベルで議題設定効果が発生する場合、テレビや新聞の政治ニュースへの注意度の増加は、制度関連の下位争点の顕出性の増加と関連し、倫理関連の下位争点の顕出性には関連しないと予測される。調査データを分析すると、政治ニュースへの注意度は、制度関連の下位争点の顕出性とは関連があるが、倫理関連の顕出性とは関連がなかった。このパターンは新聞についても同様だった。つまり、当時、新聞やテレビの選挙報道によく注目した人ほど、政治改革の中でも選挙制度改革を特に重視する傾向が見出され他のである。さらに興味深いのは、このレベルでは新聞がテレビニュースよりも比較的強い影響を持つように見える点である。この理由として考えられるのは、新聞がテレビニュースよりも分析的な記事を多く含み、問題を効果的にフレーミングした可能性があるということである。

竹下(1998)より
竹下と三上による本調査研究は、議題設定効果の属性レベルの第2次議題設定におけるマスメディアの影響を実証的に明らかにした貴重な研究成果として注目を浴び、マコームズも自身の学会や論文で何度も引用している(McCombs, 1997他)。議題設定研究の発展に一定の貢献をすることができたのではないかと考える。竹下(1998)は、この第2次レベル(属性型)の議題設定について、従来の「何について考える」(what to think about)から、ある争点について「それをどのように考えるか」(how to think about it)へと、仮説の適用領域を拡張する試みであ李、結果として、属性型議題設定はフレーミングの概念とlきわめて類似性が高い、と指摘している。
環境問題に関する議題設定研究(三上、竹下、川端、仲田)
次に紹介する研究は、1992年6月にブラジルのリオデジャネイロで開催された「地球サミット」(UNCED)の期間中に、マスメディアの大々的な環境報道が一般市民に及ぼした認知的影響を議題設定研究の手法を用いて分析したものである。環境問題をテーマとして議題設定仮説を検証した数少ない事例と言える。
調査の概要:
1. 一般市民意識調査
調査期間:1993年6月13日〜23日。T大学の社会調査実習の一環として実施。
調査方法:留置回収
有効回収:581件(うち男性50.3%、女性49.7%)
調査項目:マスメディアへの接触状況、テレビや新聞での環境ニュースへの接触状況、環境問題への関心、地域・国内・地球規模における環境問題の顕出性、UNCEDに関するマスメディア報道の評価、環境保全に関連する行動、態度や性格に関する項目、人口統計学的特性。
2. 内容分析
テレビニュース:
NHKの夕方ニュース(「7時のニュース」)、NHKの夜間ニュース(「ニュースセンター9時」)、TBSの夕方ニュース(「ニュースの森」)、TBSの夜間ニュース(「ニュース23」)、フジテレビの夕方ニュース(「スーパータイム」)、テレビ朝日の夜間ニュース(「ニュースステーション」)である。UNCEDの期間(1992年6月1日から6月14日)に、これら6つのニュース番組で報道された環境ニュースをすべて録画し、分析した。
新聞記事:
「朝日新聞」「読売新聞」の2紙について、面接調査の前の20週間(1992年1月27日から6月14日)を対象に分析を行った。調査の質問票に記載された地球環境のサブテーマに該当する記事や社説を「朝日新聞」および「読売新聞」の電子データベースから抽出した。各サブテーマごとに2~5つのキーワードを設定し、それらが見出しやリード文に含まれる記事を選定した。その後、不適切な記事を除外し、適切な記事をコーディングした。
調査の結果:
1. テレビニュース接触度と環境問題顕出性の関連
現代日本が直面する9つの主要な問題をリストアップし、特に重要だと考える問題を複数選択で回答してもらった上で、その中で最も重要だと考える単一の問題を選ぶよう依頼した。回答者の70%以上が環境問題を現代日本の最重要課題の一つとして挙げており、この割合は他のどの項目よりも高かった。UNCED以前に環境問題に関するテレビニュースに接触した頻度と問題の顕出性との間に有意な関連が見られた。テレビニュースを多く視聴するほど、環境問題を重要だと認識する傾向が強かった。
2. 新聞のメディア議題と市民意識の関連性
地球環境問題に関する新聞の議題と、回答者が最も重要だと考える地球環境サブテーマの議題との関連を、全体のサンプルと環境問題全般の顕出性レベルごとに順位相関係数で測定した。分析の結果、最新の2週間の報道量(UNCED期間にほぼ相当)と一般市民の議題との間に比較的弱い相関が見られた。これは、UNCEDがメディアイベントとして一般市民の意識にはあまり影響を与えなかった可能性を示唆している。しかし、メディア議題を過去に遡り、2週間ごとの累積報道量を加味すると相関は増加し、6~10週間の累積期間(タイムスパン)で相関はピークに達した。その後、相関はわずかに減少する。この傾向はSalwen(1988)で見られたものと非常に類似しており、新聞の議題設定効果が長期的かつ累積的であることを示唆している。
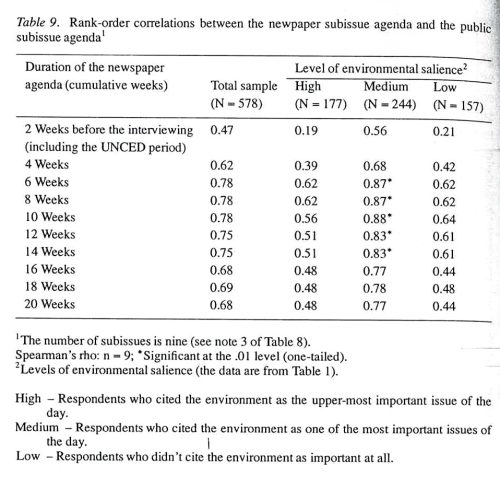
環境問題全般の顕出性レベルを分析に取り入れた場合、中程度の顕出性を持つ回答者が、各累積期間において最も高い相関を示した。この理由として考えられるのは、環境問題に対して高い顕出性を持つ人々は、地球環境問題について固定的なイメージを持っている傾向があり、メディアの議題設定設定の影響を受けにくいということである。
本研究の内容は、議題設定研究を総括したマコームズの単著『アジェンダセッティング』(2017 竹下訳)でも詳しく紹介されており、議題設定研究の国際的な発展において一定の役割を果たしていると評価することができるだろう。
議題設定とフレーミング(竹下)
本研究は、議題設定研究の立場から、メディアのフレーミングが人々の認識に及ぼす効果を、幅広い争点やトピックに適用可能なフレームの枠組みを用いて測定する試みである。ここで、フレーミングとはある問題や出来事に対する解釈枠組みの適用と定義されている。
調査の概要:
1. 調査のテーマ
取り上げた争点は、1990年代初頭の馬ルル崩壊以降、長期にわたって低迷を続けてきた「日本の経済状況」。この複雑で諸説分かれる問題について、一般の人々がどのような視点からどう理解しているのか、またマスメディアの報道は人々の問題理解にどんな影響を及ぼしているかを追求した。
2. 予備調査:フォーカスグループインタビュー
1999年9月から12月にかけて、20歳代から60歳代までの男女28人を対象に、低迷する日本の経済状況のうち、何が一番問題だと思うかを自由に語ってもらった。
3. 意識調査:
2001年5月下旬から6月初めにかけて、東京都在住の20歳以上70歳未満の男女800人を対象に実施。留置法。有効回収数は556(69.5%)。フォーカスインタビューを参考にしながら、12フレーム項目を作成し、それぞれについて、「重大さ」の程度を4段階で評価してもらった。
4. 内容分析:
マスメディアの経済報道における経済問題のフレーミングの仕方を調べるために、内容分析を実施した。「朝日新聞」と「読売新聞」を対象とし、意識調査実施前の1年間を分析対象として、13日分を系統抽出。第1面の「経済関連記事」を分析した。対象記事は「経済の下位争点」と「問題状況フレーム」のカテゴリーで分類した。
調査の結果:
1. 有権者の問題状況認識
日本経済に対する問題状況認識の構造を調べるために、回答選択肢を因子分析した結果、「制度崩壊」「損失」「不確実さ」「対立」という4つの問題状況フレームが抽出された。
2. ミクロ属性次元の議題設定(下位争点レベルでの効果)
新聞の下位争点強調度と有権者の下位争点重要度認知との間の関連を調べると、回答者全体で見た場合、スピアマン順位相関係数は0.59隣、統計的に有意だった。これは、ミクロ属性次元での属性型議題設定効果に一定の支持を与えるものと言える。
3. マクロ属性次元の議題設定(問題状況フレームレベルでの効果)
このレベルでの属性型議題設定効果は、「フレーミング効果」ということができる。意識調査での回答の因子分結果から、4つの問題状況フレームに対応する因子が抽出された。そこで、これらのメジャーと、「経済報道への注意度」尺度との関連を調べたところ、経済報道への注意度と、メディアによる顕出性の最も高かった「制度崩壊」フレームに対する重要度にんちとの間には有意な正の相関(ピアソン相関係数0.31)が見られた。他方、新聞報道で強調されていなかった「損失」と「対立」フレームに関しては、報道への注意度とフレーム重要性認知との間には、有意な関連は見られなかった。以上は、フレーミング効果の存在を支持するデータといえよう。
本研究の意義:
本研究は、メディアによる経済問題のフレーミングが受け手の経済問題の認識の仕方に影響していることを実証的に明らかにしたことに意義がある。新聞の経済報道では、低迷する日本の経済状況を定義する際に、「制度崩壊」を最もよく用いたが、受け手の側でも、経済報道を熟読している人ほど、同じフレーム(制度崩壊)を重視する傾向が見られた。長期的不況の原因・対策については、経済の専門家の間でも「景気循環要因を重視し、マクロの景気対策をとるべきだ」との立場と、「構造的な要因を重視し、構造改革を優先すべきだ」とする立場に分かれている。本調査の結果は、新聞の報道も都民の認識も後者の見方(フレーム)に傾斜していたことを示している。これが、「構造改革なくして景気回復なし」というスローガンを掲げた当時の小泉内閣に国民が少なからぬ支持を与えた理由の一端を示すものと竹下は述べている。
本論文は、「第2レベルの議題設定」の研究に属するもので、「フレーム」という属性のレベルにおける議題設定効果(つまりフレーミング効果)を初めて調査データを用いて詳細に検証したもので、大きな意義を持っていると言える。実際、マコームズも議題設定に関する総論的な著書(McCombs, 2014)の中で、本研究を大きく取り上げているほどである。フレーミング効果研究の分野に対しても、重要な学術的貢献として評価されることだろう。
議題設定研究の将来展望
最後に、議題設定研究50周年を迎えて、創始者のマコームズとショー、それに生成期の共同研究者ウィーバーの3人が、議題設定研究の発展を振り返り、今後の方向性を示した論文を紹介することにしたい。"New Directions in Agenda-Setting Theory and Research" と題して、2014年にMass Communication & Society誌に掲載されたものである。
議題設定研究の7つの側面
議題設定理論は、50周年を迎えるにあたり、過去の研究と現在の成果を踏まえ、さらに発展する可能性を示している。議題設定理論は、チャペルヒルにおけるメディアが公衆の問題意識に与える影響を厳密に検証した研究から始まり、現在では以下の7つの側面を持つ広範な理論へと発展している。
- 基本的議題設定マスメディアの議題が、公衆の議題に対して、問題、政治的な人物、その他注目対象の重要性に与える影響(議題設定の第一段階)。
- 属性議題設定マスメディアの議題が、公衆の議題に対して、それら対象の属性の重要性に与える影響(議題設定の第二段階)。
- ネットワーク議題設定ネットワーク化されたメディアの議題が、ネットワーク化された公衆の議題に対して、対象や属性の重要性に与える影響(議題設定の第三段階)。
- オリエンテーション欲求メディアとの接触における各個人の心理学的要因を詳細に示す概念であり、議題設定効果の強さを理解するための中心的な要素である。最近では、メディア接触と議題設定効果を結びつける二重の心理的経路が詳述されている。
- 議題設定効果の結果議題設定効果が態度、意見、行動に与える影響。
- マスメディアの議題の起源支配的な文化的およびイデオロギー的環境、ニュースソース、メディア間の影響、ジャーナリズムの規範と慣行、ジャーナリスト個人の特性など多岐にわたる。
- 議題融合マスメディアの市民的議題や自分が価値を置くコミュニティの議題を、個人の見解や経験と統合し、満足のいく世界観を形成するプロセスを指す。
上記の7つの側面のうち、本論文では、現代の研究で特に活発な理論的領域である「方向性の必要性」「ネットワーク議題設定」「議題融合」の3つが特に詳述されている。
オリエンテーション欲求と議題設定の心理学
マコームズとウィーバー(1973)は、オリエンテーション欲求を「関連性」と「不確実性」の組み合わせとして定義し、関連性が低い場合にはオリエンテーション欲求も低く、関連性が高く不確実性が低い場合には中程度のオリエンテーション欲求となり、関連性が高く不確実性も高い場合には高いオリエンテーション欲求となるとした。彼らは政治的関連性を、1972年の大統領選挙キャンペーンへの関心やその議論で操作的に定義し、不確実性を投票行動の一貫性、政党への強い帰属意識、大統領候補の選択に対する確信度で測定した。結果として、新聞やテレビを政治情報のために利用する頻度がオリエンテーション欲求のレベルに応じて増加するという仮説が強く支持され、新聞の議題設定効果もオリエンテーション欲求のレベルに応じて直線的に増加することが確認された。
また、2008年の米国大統領選挙に関するカマイとウィーバー(2013)の調査では、オリエンテーション欲求がニュースメディアへの単純な接触頻度よりも政治ニュースへの関心を予測する上で強い指標であることが示され、さらに第2レベルの議題設定効果(候補者属性の重要性)に対しては、メディア接触よりもメディアへの注目度が良い予測因子であることが確認された。
このように、オリエンテーション欲求は議題設定理論において重要な心理学的概念であり、メディア利用や議題設定効果の理解を深めるための鍵となる要素であるといえる。
なぜ議題設定が起こるのか
議題設定効果の心理学を包括的に分析したマコームズとストラウド(2014)は、「なぜ議題設定が起こるのか」という問いに対する答えとして、オリエンテーション欲求が一部を説明するに過ぎないと結論づけている。彼らは、アクセス可能性と適用可能性を含む心理的プロセスを通じて議題設定効果が生じる仕組みを説明する研究をレビューしている。マスメディアを受動的に利用する人々は、積極的に利用する人々に比べてオリエンテーション欲求が低い傾向があることが示されており、「中程度-積極的」オリエンテーション欲求(高い関連性と低い不確実性)を持つ人々は、オリエンテーション欲求が高い人々(高い関連性と高い不確実性)よりも偏向的なメディアを利用する傾向があるとされている。このパターンから、「中程度-積極的」オリエンテーション欲求を持つ人々は方向性の目標に動機づけられ、高いオリエンテーション欲求を持つ人々は正確性の目標に動機づけられると推測される。
オリエンテーション欲求が低い人々や「中程度-受動的」(低い関連性と高い不確実性)のオリエンテーション欲求を持つ人々は、メディア情報を受動的に処理し、ニュースメディアを比較的少なく利用するため、議題設定効果は限定的である。一方、「中程度-積極的」オリエンテーション欲求や高いオリエンテーション欲求を持つ人々は、情報収集を積極的に行い、アクセス可能性バイアス(頭に浮かびやすい情報への偏り)の影響を受けにくい。「中程度-積極的」オリエンテーション欲求を持つ人々は偏向的なメディアを利用する傾向が強く、第2レベルおよび第二レベルの議題設定効果が高い結果を生む。一方、高いオリエンテーション欲求を持つ人々は主流の、偏向の少ないメディアを利用する傾向があり、第1レベル(問題)議題設定効果が強いが、第2レベル(属性)の効果は中程度である。
ソーシャルメディアと議題設定
近年の研究では、ソーシャルメディアの議題設定プロセスが、伝統的なメディアと公衆の関係を超えて広がっていることが示されている。例えば、2012年の米国大統領選挙におけるソーシャルメディアの議題は、伝統的なニュースメディアと比較して非常に多様であり、より包括的な公共の議題設定を観察する手段として機能している。
ただし、ソーシャルメディアの議題設定プロセスは、ニュースメディアと公衆の間の双方向的なフローを含む場合もあり、ニュースメディアが公衆の議題を刺激し、逆に公衆の議題がニュースメディアの議題を刺激するという二段階のプロセスを形成することがある。
ソーシャルメディアのデータを用いた議題設定研究は、世論を連続的に観察する新たな視点を提供するが、依然として世論の限定的な部分を反映している。さらに、ソーシャルメディアデータの単位は主に「メッセージ」であり、個人単位の分析を行う従来の調査との違いがある。このギャップを埋めるためには、ソーシャルメディアデータと伝統的な調査手法を補完的に活用する必要があると考えられる。
ソーシャルメディア議題を含む議題設定プロセスは、ニュースメディアと公衆との関係を超えた拡張を示している。この拡張は、ソーシャルメディア議題の3つの異なるサブセットの起源に基づいて説明される。
ソーシャルメディア議題を構成する一部のメッセージは、市民の特定の問題への長年の、しばしば情熱的な関心から生じる。例えば、妊娠中絶、同性婚、銃規制といったホットボタン問題が挙げられる。時折、ニュースイベントがこれらの問題に関するソーシャルメディア上のメッセージの急増を引き起こすことがあるが、ニュースメディア議題がこれらの問題について市民の対話を刺激する役割は基本的に小さい。まれに、市民が直接的に出来事を観察し、それについてソーシャルメディアでコメントすることもある。これは主にスポーツイベントや政治討論会のような出来事についてのコメントであり、市民ジャーナリズムの一部もここに含まれる。
これら最初の2つのサブセットは、ソーシャルメディア議題を定義するメッセージの小さな部分にすぎないが、ソーシャルメディアから収集した大規模データセットに依存する際に、メディアと公衆の関係を観察する際の「ノイズ」をもたらす。つまり、ソーシャルメディア議題は非常に多様な起源を持つメッセージの混在であり、包括的すぎる。
最初の2つのサブセットは、主に市民によるソーシャルメディア議題への独自の貢献である。3つ目のサブセットは、ニュースメディアの伝統的な議題設定機能の拡張および再定義を示している。このサブセットは、優先問題議題よりもはるかに広範な問題のセットを含むことがある。このソーシャルメディア議題は、ニュースメディアが最初に公衆の議題を刺激し、その後公衆の議題がニュースメディアの議題を刺激するという、2段階の議題設定プロセスの一部となる場合もある。つまり、双方向のフローが存在する。
新たな視点:第3レベルの議題設定
心理学者や哲学者の中には、人々の心的表象が絵画的、図式的、または地図的に機能すると考える者もいる。つまり、観衆は対象と属性をそれらの要素間の相互関係に基づいてネットワークのような絵としてマッピングするのである。この観点から、ニュースメディアは要素群間の関係性の重要性を公共に転移させる。これらの要素群は、メディアや公共の議題における対象や属性、または対象と属性の組み合わせである。メディアと公共の議題の要素間のこれらの関係群が、議題設定の第3レベルである(Guo, 2014)。
ニュースメディアが要素群間の関係性の重要性を公共に転移できる程度を初めて探求した研究は、メディアにおける属性群間の関係性の重要性の転移に焦点を当てた。この研究では、従来の属性議題設定と比較するため、KimとMcCombs(2007)が収集したデータセットにネットワーク分析を適用した。テキサス州知事と米国上院議員の候補者を対象にした研究で、KimとMcCombsは各候補者について、また4人の候補者全体で強い属性議題設定効果を発見した。彼らの分析は、ニュース記事と市民の候補者に関する記述の中で、様々な属性が出現する頻度を比較したものである。ネットワークの視点から再分析を行った結果、ニュース記事と市民の記述における属性の共起を調査し、元の研究の効果の強さと一致する有意なネットワーク議題設定効果を発見した。例えば、KimとMcCombsの分析におけるメディアと公共の属性議題間の相関(0.65)は、メディアと公共のネットワーク議題間の相関(0.67)と一致している(Guo & McCombs, 2011)。
また、対象の重要性の転移を調査した別の研究では、米国ニュースメディアのネットワーク化された問題議題と、2007年から2011年にかけて毎月の全国世論調査で測定された公共のネットワーク化された問題議題を比較した。この5年間の各相関は0.65から0.87の範囲であった。上述の属性議題の分析と同様に、ネットワーク分析と従来の相関分析の統計結果は非常に類似している(Vu, Guo, & McCombs, 2014)。
これらの関係性をメディアが提示する際の冗長性が再び鍵となる可能性が高いが、公共にこれらの効果を生み出すために必要な冗長性のレベルは、研究者たちに新たな問いを提示している。概念的および方法論的に独立したこの新たな広い視点、すなわち議題要素の束ね方に関する第3レベルの議題設定は、「メディアのネットワーク化された問題議題における関係性の重要性が公共のネットワーク化された問題議題に転移できる」という包括的な議題設定仮説を検証するものである。議題の操作的定義は拡大し続けており、研究者にとって豊かな探求領域を提供している。
議題融合と市民共同体の均衡
メディアのメッセージがあっても、それを受け取るオーディエンスが存在しない場合、議題設定は成立しない。1960年代から1970年代にかけて、強力なメディアの影響が再発見されて以降(Gerbner, Gross, Morgan, Signorielli & Shanahan, 1994; Noelle-Newmann, 1993; McCombs & Shaw, 1972)、オーディエンスがメディアの議題を選択する役割についての認識が高まってきた。市場におけるメディアの選択肢は爆発的に増加している。我々の中には、ウェブで新聞を読む者、FacebookやTwitterで同様の興味を持つグループを見つけたり作成したりする者、一日中さまざまなニュースチャンネルを監視する者がいる。一方で、特に高齢者であれば、依然として日刊新聞を読んだり、テレビの夕方ニュースを視聴したりしている。我々には選択肢があり、それを活用して議題メッセージを組み合わせ、自分の個性を満たす議題共同体 (Agenda Community) を形成しているのである。我々は、全ての人に届くネットワーク放送のようなメディアから選択する一方で、個人的な興味や大切な人々の興味に合ったスポーツ雑誌やウェブサイト、ブログといったメディアを利用している。
垂直的なメディア、たとえばネットワークや地方放送局は、大規模な共同体の多様性を取り込み、ピラミッドの頂点から広範な観衆に向かって発信しているように見える。これらのメディアは、通常、社会の基本的な制度や価値観を反映している。一方で、雑誌、ケーブルテレビ、TwitterやFacebookなどは特定の関心や個人的なつながりを持つコミュニティを構築し、ピラミッドの水平面で生きているかのような感覚を生む。現実には、垂直的な制度共同体と、価値ある個人的な共同体の双方に属しながら生きている。我々は受動的な存在ではなく、これら二つの共同体に関する情報を組み合わせ、自分自身の経験や好みに合わせた共同体を見つけ出したり、作り出したりしているのである。
垂直的な市民共同体を構成する情報には、社会全体を代表するものが含まれる一方、水平的なコミュニティは個人的または特殊な関心を反映している。この二つの情報源に加えて、個人の経験や信念が融合の要素として重要である。この三つの要素をどのように組み合わせるかが、議題融合の鍵となる。これを理論的に表現するための仮説が次のものである:
議題共同体の魅力(Agenda Community Attraction, ACA) = 垂直的メディア議題設定の相関(平方)
- 水平的メディア議題設定の相関(平方)
- 個人的選好
たとえば、ある社会システムにおいて垂直的メディアの相関が0.80の場合、その平方は0.64となる。残りの0.36(1.00から0.80を引いたもの)は水平的メディアおよび個人的要素に起因する。このうち水平的メディアが0.20であると仮定すると、その平方は0.04となる。最終的に、残りの0.32が個人的選好に帰属する。この仮説的な例を用いると、以下のように表現される:
ACA = 0.64 + 0.04 + 0.32 = 1.00
この仮説に基づき、議題共同体における水平的コミュニティの寄与を特定し測定することが研究課題となる。心理学的には、個人の選好や経験がメディアの選択やメッセージの受容に影響を与えることは知られている。議題融合の分析を通じて、垂直的および水平的メディア、さらに個人的な影響の役割を総合的に評価することが可能である。
ここで、議題融合(Agendamelding)とは、他者を含む多様な情報源から議題を組み合わせ、自分の経験や好みに合った世界観を形成する社会的プロセスである。このプロセスが非常に個人的で無意識的なため、「議題融合(agendamelding)」という用語が用いられる。
オーディエンスが垂直的議題、水平的議題、そして自身の経験をどのように融合させるかは、グループごとに、また時代ごとに異なると考えられる。垂直的メディア議題の影響が増減すると、それに応じて水平的メディアと個人的な要素も変動する。垂直的メディアとの相関が比較的高いシステムは、安定した社会システムを示唆すると考えられる。しかし、代替的共同体の議題の力が増すにつれ、不安定な移行期間が訪れる。モデルの右端では、代替的共同体を中心とした新たな安定性が再出現する。その後、このプロセスは繰り返され、新たな安定性、または別の代替的共同体への移行が生じる。このモデルは、各国の議題設定データを用いて検証する必要があることは言うまでもない。
(筆者のコメント)
議題設定理論は、1972年に創設されて以来、新しい概念装置や検証方法、適用領域を次々と開発し、目覚ましい発展を遂げてきたが、本論文では、さらに第3レベルの議題設定や議題融合といった、新しい理論装置を加えて、さらに強力な効果論への飛躍しようとしている。また、培養理論とは違って、ソーシャルメディアなどの新しいメディア環境も理論の中にたくみに取り込んで、オーディエンスや市民共同体といった新時代の世論モデルの構築を見据えて理論へと、新たな方向性を示しているように思われる。今後の更なる発展を期待したいと思う。
参考文献(第2部)
Adoni,H.,and S.Mane ( 1984) Media and social construction of reality. Communication
Research, 11 (3): 323 - 340
Adoni,H.,A.A.Cohen,and S.Mane ( 1984) " Social reality and television news:Perceptual
dimensions of social conflicts in selected life area. "Journal of Broadcasting, 28: 33 - 49.
Adorno, T.W.and M.Horkheimer ( 1972) The Dialectics of Enlightenment.New York:Seabury Press.
Althusser,L. (1971) " Ideology and ideological state apparatuses" in Lenin and Philosophy and Other Essays.London:New Left Books.
Ball-Rokeach,S.,and M.DeFleur ( 1976) " A dependency model of mass media effects." Communication Research 3:3 - 21
Becker, L., & McCombs, M. (1978). The role of the press in determining voter reactions to
presidential primaries. Human Communication Research, 4, 301-307.
Berger,L.P.,and T.Luckmann ( 1967) The Social Construction of Reality. New York:Anchor Books.
山口節郎訳「日常世界の構成ーアイデンティティと社会の弁証法』新曜社
Boorstin ( 1962) The Image:or, What Happened to the American Dream. New York: Atheneum. 星野郁美・後藤和彦訳, 『幻影の時代』東京創元社
Breed, W ( 1955) "Social control in the newsroom:a functional analysis" Journalism Quarterly,
33:326-355.
Brosius, H.-B., & Kepplinger, H. M. (1990). The agenda-setting function of television news: Static and dynamic views. Communication Research, 17, 183-211.
Cohen, B. (1963). The press and foreign policy. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Cohen, J., & Weimann, G. (2000). Cultivation revisited: Some genres have some effects on some viewers. Communication Reports, 13(2), 99-114.
Dayan, Daniel., and Katz, Elihu, 1992, Media events: The Live Broadcasting of History., Harvard University press. 浅見克彦訳, 1996, 『メディア・イベントー歴史をつくるメディア・セレモニー』青弓社
Doob,A.,and G.MacDonald ( 1979) " Television viewing and fear of victimization:Is the relationship causal?" Journal of Personality and Social Psychology, 37: 170 - 179
Erbring, L., Goldenberg, E., & Miller, A. (1980). Front page news and real world cues: A new look at agenda-setting. American Journal of Political Science, 24, 16-49.
藤竹暁(1968) 『現代マス・コミュニケーションの理論』日本放送出版協会
藤竹暁『テレビメディアの社会力』1985年、有斐閣選書
Funkhouser, G. R. (1973). The issues of the sixties: An exploratory study in the dynamics
of public opinion. Public Opinion Quarterly, 37, 62-75.
Gans,H.J. (1980 )Deciding What's News.New York:Vintage Books.
Gerbner,G. (1969) Toward 'cultural indicators': the analysis of mass mediated public message systems. " Audio Visual Communication Review, 17 (2): 137 - 148
Gerbner ( 1973) Cultural Indicators:The Third Voice" In Gerbner et al. (eds. ) Communication
Technology and Social Policy. N.Y.: Wiley.
Gerbner,G.,and L.Gross ( 1976) " Living with television: the violence profile. " Journal of Communication, 26: 172 - 199
Gerbner,G.,L.Gross,M.Jackson-Breeck,S.Jeffries-Fox,and N.Signorielli (1977 b) " TV violence profile no.8. " Journal of Communication, 28: 171 - 180
Gerbner,G.,L.Gross,M.Jackson-Breeck,Jeffries-Fox,and N.Signorielli ( 1978) " Cultural indicators:violence profile no.9. "Journal of Communication, 28 (3): 176 - 207 .
Gerbner,G.,M.Morgan, and N.Signorelli ( 1980 a) * The mainstreaming of America: violence profile no. 11. " Journal of Communication, 30 : 10 - 29.
Gerbner,G.,L.Gross.N.Signorielli, and M.Morgan (1980 b) * Aging with television: images on television drama and conceptions of social reality. ~ Journal of Communication, 30 : 37 - 47.
Gerbner,G.,L.Gross,M.Morgan,and N.Signorielli (1981 a) " A curious journey into the scary world of Paul Hirsch. " Communication Research,8 (1): 39 - 72 •
Gerbner,G.,L.Gross,M.Morgan,and N.Signorielli ( 1982) "Charting the mainstream: television's contribution to political orientations. " Journal of Communication, 32: 100 - 127 .
Gerbner,G.,L.Gross,M.Morgan,and N.Signorielli ( 1984) Political correlates of television
viewing. " Public Opinon Quarterly, 48: 283 - 300
Gerbner,G.,L.Gross,M.Morgan,and N.Signorielli ( 1986) " Living with television :the dynamics of the cultivation process. " in J.Bryant and D.Zillmann (eds. ),Perspectives on media
effects (pp. 17 - 40) . Hillsdale,MJ:Lawrence Erlbaum.
Gitlin,T. (1980 )The Whole World is Watching. Berkeley:University of California Press.
Glasgow University Media Group ( 1976) Bad News. London:Routledge & Kegan Paul.
Glasgow University Media Group ( 1980) More Bad News.London: Routledge & Kegan Paul.
Hall,S. (1977) Culture,the media,and the ideological effect. " In J.Curran et al. (eds.) Mass Communication and Society. London:Open University Press.
Hawkins,R.,and S.Pingree ( 1980) " Some processes in the cultivation effect. " Communication
Research,7: 193 - 226 •
Hawkins,R.and S.Pingree (1983) " Television influence on constructions of social reality. " in I.
Wartella et al. (eds. ),Mass Communication Review Yearbook,Vol.4: 53 - 76.
Hirsch,P.M. (1980) "The 'scary world' of the nonviewer and other anomalies:a reanalysis of Gerbneret al. 's findings on cultivation analysis,part 1. "Communication Research, 7: 403
Holbert, R. L., Shah, D. V., & Kwak, N. (2004). Fear, authority, and justice: Crime-related TV viewing and endorsements of capital punishment and gun ownership. Journalism e Mass Communication
Iyengar, S., & Kinder, D. (1987). News that matters: Television and American opinion. Chicago: University of Chicago Press.
Lang, Kurt and Gladys Engel Lang, "The Mass Media and Voting," in Bernard Berelson and Morris Janowitz,eds., Reader in Public Opinion and Communication,2d ed., New York,Free Press,1966
K. ラング、G.E. ラング「テレビ独自の現実再現とその効果|予備的研究」(W・シュラム編『新版 マス・コミュニケーション』学習院大学社会学研究室訳、東京創元新社、1968年)
G.E.ラング、K. ラング『政治とテレビ』荒木功他訳、1997年
Lippmann, Walter (1917), Liberty and the News. New Brunswick, NJ: Transaction,.
Lippmann, Walter, (1922), Public Opinion. 掛川トミ子訳. 1987. 岩波書店
Morgan, M., & Shanahan, J. (2010). The state of cultivation. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 54(2), 337-355.
村松泰子(1982)「マス・コミュニケーションの内容」 竹内・児島編「現代マス・コミュニケーショ
ン論』pp.167-197.有斐閣
McCombs, M., & Shaw, D. (1972). The agenda-setting function of mass media. Public Opinion Quarterly, 36, 176-185.
McCombs, M. E. (1992). Explorers and surveyors: Expanding strategies for agenda-setting research. Journalism Quarterly, 69, 813-824.
McCombs, M., 2005, A Look at Agenda-setting: past, present and future , Journalism Studies, 6(4), 543–557
McCombs, M. and Estrada, G., 1997, The News Media and the Pictures in Our Heads, in Iyengar, S. and Reeves, R., Do Media Govern?. Sage.
Murdock,G. (1973) Political deviance:the press presentation of a militant mass demonstration.
in S.Cohen and J.Young (eds.) The Manufacture of News-Social Problems, Deviance, and the Mass Media. London: Constable.
Murdock,G.,and P.Golding (1977) "Capitalism,communication,and class relations. "in J.Curran et al. (eds.) Mass Communication and Society. London:Open University Press.
三上俊治, 水野博介, 1978, 余震情報パニックの実態. 新聞研究 (4月号) 42-55 1978年4月
三上俊治, 1982, 「災害警報の社会過程」東京大学新聞研究所編『災害と人間行動』東京代が出版会
三上俊治, 1984, パニックおよび擬似パニックに関する実証的研究. 東洋大学社会学部紀要 (21) 155-202 1984年3月
三上 俊治, 1987, 現実構成過程におけるマスメディアの影響力 -擬似環境論から培養分析, 東洋大学社会学部紀要 (24-2) pp.238-280
三上俊治, 橋元良明, 水野博介, 1989, テレビによる社会的現実の認知に関する研究. 東京大学新聞研究所紀要 (38) pp.73-124
MIkami, S., 1993, A Cross-National Comparison of the US-Japan TV Drama: International Cultural Indicators. Keio Communication Review, No.15, pp. 29-44.
三上俊治, 1993, 「世論過程の動態」東洋大学社会学部紀要 (31-1) pp.123-210
三上俊治, 1994, 1993年7月衆議院選挙におけるマスメディアの役割. 東洋大学社会学部紀要 (31-2) pp. 143-202
三上俊治, 竹下俊郎, 川端美樹, 1999, Influence of the Mass Media on the Public Awareness of Global Environmental Issues in Japan. Asian Geographer 18(18) 87-97 1999年7月
川端美樹, 三上俊治, 2001, How Television News Matters: Television News Viewing and Environmental Awareness in Japan. Keio Communication Review 23(23) 37-52 2001年3月
水野博介, 1991, 「文化指標研究と涵養効果分析ーそのアイディア・発展・現状と評価ー」『新聞学評論』, 40号, pp. 274-290
水野博介, 1994, 「1993年6月の皇太子成婚報道に関する実証的研究」「埼玉大学紀要 教養学部」第29卷 Pp.49-72
水野博介, 1998, 『メディア・コミュニケーションの理論』学文社
中村功, 1999, 「テレビにおける暴力ーその実態と培養効果」, 『マス・コミュニケーション』55号, pp.186-201
Noelle-Neumann,E. (1974) " Spiral of Silence. " Journal of Communication, 24, 143 - 159
Noelle-Neumann,E. (1977) " Turbulancee in the climate of opinion: methodological applications
of the spiral of silence theory. " Public Opinion Quarterly, 41 (2): 143 - 159
Okabe, Keizo and Mikami, Shunji, 1985, A Study on the Socio-Psychological Effect of a False Warning of the Tokai Earthquake in Japan. Paper presented at the 10th World Congress of Sociology held in Mexico City.
岡部慶三、廣井脩、広瀬弘忠、松村健生、三上俊治、山本康正、池田謙一、宮田加久子, 1982, 『誤報「警戒宣言」と平塚市民』東京大学新聞研究所報告書 (http://cidir-db.iii.u-tokyo.ac.jp/hiroi/pdf/report/saigairep/saigairep007.pdf)
Pingree,S.,and R.Hawkins ( 1981) " Programs on Australian television:the cultivation effect. " Journal of Communication, 31 (1): 97 - 105
Quarantelli, E.L., 1954, The Nature and Conditions of Panic, The American Journal of Sociology, 60, pp.267-275.
Quarantelli, E. L. and Dynes, R. R., 1972, Images of Disaster Behavior: Myths and Consequences. Columbus, Ohio: Disaster Research Center
Quarantelli, E. L., 2008, Conventional Beliefs and Counter-Intuitive Realities, University of Delaware Disaster Research Center, ARTICLE #450
Rogers, E. M., & Dearing, J. W. (1988). Agenda-setting research: Where has it been? Where is it going? In J. A. Anderson (Ed.), Communication yearbook 11. Newbury Park, CA:
Rosengren. Karl Erik. PeterArvidson. and Dahn Sturesson. (1975) "The Barseback'Panic': A Radio Programme as a Negative Summary Event." Acta Sociologica 18 : 303-321.
斉藤慎一・川端美樹, 1991, 「培養仮説の日本における実証的研究」『慶應義塾大学新聞研究所年報』37号, pp.55-78
斉藤慎一, 1992, 「培養理論再考」『新聞学評論』42号, pp.70-83
斉藤慎一 , 2002, 「テレビと現実認識ー培養理論の新たな展開を目指して」『マス・コミュニケーション研究』, 60号, pp.19-43
Shanahan, J., & Morgan, M. (1999). Television and its viewers: Cultivation theory and research. New York: Cambridge University Press.
Shaw, D., & McCombs, M. (Eds.). (1977). The emergence of American political issues. St. Paul, MN: West.
Steel, Ronald, 1982, 『現代史の目撃者:リップマンとアメリカの世紀』浅野 輔訳. TBSブリタニカ
高橋徹・岡田直之・藤竹暁・由布祥子, 1959 「テレビと"孤独な群衆" 皇太子ご結婚報道についての東大・新聞研究所調査報告」『CBCレポート』1959年6月号, 3-13ページ
竹下俊郎, 1981, 「マスメディアの議題設定機能」新聞学評論 30号
竹下俊郎, 1984, 「議題設定研究の視角」放送学研究 34号
Takeshita, T. and S.Mikami, 1995, How did Mass Media Influence the Voters’ Choice in the 1993 Election in Japan? Keio Communication Review No.17, pp.27-41,
竹下俊郎, 1998, 2008, メディアの議題設定機能--マスコミ効果研究における理論と実証〔増補版〕学文社
Takeshita, T. , 2006, Current critical problems in agenda-setting research. International Journal of Public Opinion Researcch, 18, 275-296.
竹下俊郎, 2007, 「議題設定とフレーミング-属性型議題設定の2つの次元」『三田社会学』第12号, pp.4-18.
竹内郁郎「テレビ中継をめぐる功罪論」水原泰介、辻村明編『コミュニケーションの社会心理学』、1984年、東京大学出版会
Tankard, Jr., J. W.. , 1990, The theorists In W.D. Sloan (ed.) Makers of the media mind : Journalism educators and their ideas. Hillsdale, N.J. : Lawrence Erlbaum Associates.
Tichenor, P.S.,G.A.Donohue,C.N.Olien ( 1970) " Mass media flow and differential growth of knowledge" Public Opinion Quarterly, 34: 159 - 170
Tuchman,G. (1978 )Making News:A Study in the Construction of Reality. New York:Free Press.
Weaver DH.D.A.Graber,M.B.McCombs,and C.H.Byal (1981) Media Agenda-Setting in a Presidential Election. New York: Praeger.
Wober,J.M. (1978) "Televised violence and paranoid perception:the view from Great Britain. " Public Opinion Quarterly, 42: 315 - 321 •
第3部 続・メディア効果論
第10章 沈黙の螺旋理論
「沈黙の螺旋過程」仮説とは
沈黙の螺旋理論(spiral of silence theory)は、1972年にドイツの世論研究者であるノエル・ノイマン女史 (Noelle-Neumann)が初めて提唱した理論仮説である。この仮説はおよそ次のようなものである。
人はふつう、集団や社会の中で孤立したり、村八分にされたりすることを恐れる。こうした恐怖感があるので、周囲の人びとがどんな意見をもっているのか、あるいはどんな行動をとっているのかを絶えずチェックしている。そこから、世の中の意見の分布状況(意見の風土)についての一種の統計的な感覚を身につける。たとえば、ある政治的争点に関して何%くらいの人が賛成しているのか。などといったことに関する判断を下すことができる。こうした判断が、人前で自分の意見を公然と表明するかどうか。という決定に影響を与える。もしある争点に関して自分の意見が、世間の多くの人たちと同じである、つまり、自分の意見が多数派だという認識をもつならば、かれは人前でも堂々と意見を表明するだろう。逆に、自分の意見が少数派だと判断する場合には、その人は自分が孤立したり、あるいは仲間外れにされることを恐れて、沈黙を守るだろう。その結果,自説への信念がきわめて強く孤立を恐れない「ハードコア」と呼ばれるごく一部の人たちを除いては、少数意見は公然と表明されなくなり、多数派と目される意見だけがますます声高で話され、しだいに「世論」として公認されるようになる。このように、孤立への恐怖と意見の風土認知、それに伴う沈黙の螺旋的な増幅という、一種の雪だるま的な循環プロセスを通じて、特定の意見が、次第に優勢な意見つまり「世論」になっていく、という考え方である。
1972年の国際心理学会議
「沈黙の螺旋」仮説がNoelle-Neumannによって初めて公表されたのは、1972年に東京で開催された国際心理学会議である(池田, 1997; 時野谷, 2008)。そして、翌1973年にNHKの英文雑誌Studies of Broadcast誌に沈黙の螺旋仮説に関する最初の論文("Return to the concept of powerful mass media")が掲載された。さらに、1974年にはJournal of Communiication誌に".The spiral of silence: A theory of public opinion"と題する論文が掲載されるに及んで、国際的に大きな反響を呼ぶことになった。
第20回国際心理学会議は、1972年8月13日から19日まで日本の東京プリンスホテルで開催された。33のシンポジウムの一つとして、8月16日に「マス・メディアの影響」というテーマのシンポジウムが行われた。本会議の企画者および主セッションの議長は、ジェームズ・D・ハロラン(イギリス、レスター大学)と池内一(日本、東京大学新聞研究所)であった。発表者として、アレックス・S・エーデルシュタイン(アメリカ、ワシントン大学)、エリフ・カッツ、M・グレヴィッチ、H・ハース(イスラエル、ヘブライ大学)、エリザベート・ノエル=ノイマン(ドイツ連邦共和国、マインツ大学)が参加した。また、藤竹暁(日本、NHK放送文化研究所)が討論者を務めた。残念ながら、ジェームズ・D・ハロランは病気のため来日が叶わなかった。
1973年の論文:Return to the concept of powerful mass media
ノエル・ノイマンが沈黙の螺旋理論を初めて発表したのは、1972年に東京で開催れた「国際心理学会議」のシンポジウムであった (Noelle-Neumann, 1973)。この発表内容は、翌1973年にNHKの英文雑誌 Studies of Broadcasting誌に掲載された。この論文は、「沈黙の螺旋」仮説の最初の定式化の経緯や理論的背景を知る上でも重要である。
多数意見の信念の相互作用としての世論
世論は、個人の態度と「大多数の意見」に対する信念の相互作用によって形成されるプロセスである。マスメディアは、公的な場で機能することにより、大多数の意見が何であるかという評価に影響を与える。本論文では、研究者によってこれまで軽視されてきたマスメディアの遍在性、公衆性の要素、公的な場での機能について検討する。我々のこれまでの意見形成とマスメディアに関するアプローチは、受け手側の個々人が孤立しているかのように扱ってきた。しかし実際には、個人は互いに孤立していない。個人は自身の社会的環境、すなわち他者とその環境に対する認識や見解に大きな関心を示している。特に、支配的な意見や態度に対する彼らの認識は、個人に多大な影響を与える。これらの現象は、17世紀半ばから18世紀半ばにかけて既に「意見の風土」(グランヴィル)、「意見の法則」(ロック)、「世論」(ルソー)として記述されている。これらの概念は、マスメディアの影響を支配する要因を記述するためにも必要である。
沈黙の螺旋
社会の個々の構成員や政府が「世論の圧力」として認識する力の発現は、どのようにして起こるのであろうか。ただ単に人口の大多数が特定の意見を持っているという事実だけでは、その意見が支配的になることを保証しない。重要なのは、大多数という概念が社会の個々の構成員や政治家の心の中で、彼らが周囲の世界を観察する中でどのように形成されるかである。この文脈において、大多数という概念は、強さ、決意、緊急性、または将来の見通しという概念に置き換えられることもある。社会の個々の構成員が観察を通じてそのような強さの印象を得た場合、もしその意見に賛同するならば、彼は自信を持って力強くその意見を支持する。そうでなければ、彼は気落ちし、沈黙を守る方が賢明であると判断する。この態度が社会環境における意見分布の印象に影響を与え、いずれ支配的な地位を確立しつつある側の優勢をさらに強めるという点において、らせんやスパイラルの比喩を用いることができる。
この「沈黙の仮説」によって想定される世論形成のスパイラル的なプロセスは、トクヴィルの『旧制度と革命』に描写されている。トクヴィルは、18世紀フランスにおいて宗教に対する軽蔑が広範かつ支配的な情熱となった経緯を述べている。その主な理由は「フランス教会の沈黙」であったと彼は述べている。「古い信仰に固執していた人々は、自分だけがそうであることを恐れ、孤立を恐れるあまりに誤りを犯すことを恐れず、同調してしまった。その結果、人口の一部だけの意見がすべての人の意見のように見え、それゆえにそれが圧倒的な力を持つように見えた」。
この「沈黙の仮説」に関連して、「公共であること」の重要性が浮かび上がる。もしある観点が意見分布の評価に影響を与えるためには、それらは公共の場で表明されなければならない。実際、「世論」という言葉における形容詞「公共の」の本来の意味と説得力はここにあるのかもしれない。すなわち、制裁(例えば孤立)の恐れなしに公共の場で表明できる意見である。近年では、自分の意見を表明しない多数派の無力さを表すために「沈黙の多数派」という言葉が生まれている。
沈黙の螺旋のフィールドテスト
上述の仮説を検証するために以下の仮説をアレンスバッハ世論調査研究所による調査データを用いて検証した。
- 環境における意見分布に対する個人の認識が世論形成において重要な役割を果たすと仮定されている。このため、人口における多数派意見や少数派意見に関する認識が存在することが前提となる。
- 個人が特定の意見が勢いを増すか失うかと予測することが世論形成の過程に影響を与えると示唆されている。この場合、一般大衆が意見の増減に関する明確な認識を持っていることが期待される。
- 特定の要求や計画が実現する可能性に関する見解が支配的意見の形成に関与すると仮定される場合、多くの人々が将来の展開に関する見解を形成している必要がある。
- 勢いのある、または支配的な意見の支持者は発言し、公的な支持を与える準備ができている一方で、少数派や劣勢にある意見を支持する人々は、公的な場で沈黙を保つ傾向があると仮定される。この結果、意見の実際の分布に関する印象が支配的または成長中の意見に有利に歪められる。
具体的な世論の例として、「死刑に対する賛否」「東ドイツとの条約締結」「体罰を伴わない子育て」「飲酒運転」という4つを取り上げ、意見分布の認識と少数派の沈黙に関する調査を実施した。ここでは、子育ての問題についての実証例を紹介する。
1960年代初頭以来、西ドイツ連邦共和国において、体罰を伴わない子育てを行うべきだという意見が勢いを増していた。支配的になりつつある意見の支持者が、敗北しつつある意見の支持者よりも、自らの意見を公然と主張し議論する準備ができているかどうかという期待が確認されるかどうかを、主婦を対象とした代表的な調査(パネル調査の一部)で検証した。質問は以下のように構成された。まず、主婦たちの態度を確認し、その後、公共的な状況を想像してもらった。この状況として選ばれたのは、数時間の旅をする列車の車両内で複数の人々が話している場面である。この状況は、誰でも参加できるという点で十分に公共的でありながら、参加者の範囲が小さいため、個人が委縮することは少ないと考えられる。異なる意見が表明される状況でのみ、回答者が自らの意見を公然と主張する準備があるかどうかをテストできるため、子どもへの体罰に賛成する女性には、5時間の列車旅の間に反対意見を持つ女性とその問題について話し合いたいかどうかを尋ねた。同様に、子育てにおいて体罰が必要だと考える女性には、体罰は基本的に間違っていると考える女性と話し合いたいかどうかを尋ねた。
回答者の意見は、議論している2人の女性を描いた図を提示することで確認された。一方の女性は「子どもを叩くのは基本的に間違っている。体罰なしで子どもを育てることはできる」と言い、もう一方の女性は「時々の体罰は子どもの教育の一部であり、子どもに害を及ぼすことはない」と言っている。
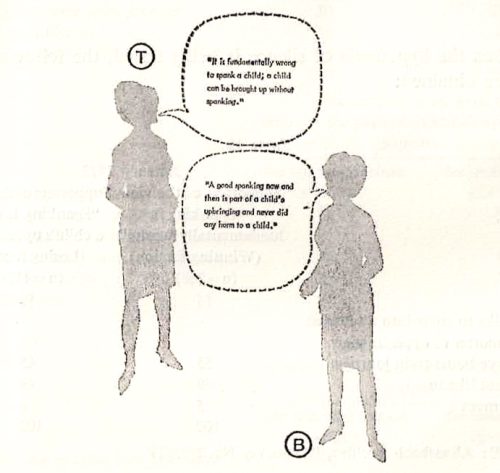
体罰の是非についての、列車での会話(Noelle-Neumann, 1973, p.101)
総合的な結果は以下の表に示されている通りである。2つの異なる教育原則の支持者は数的にはほぼ同等であるが、1960年代初頭以来勢いを失いつつある「体罰は子育ての一部」という意見が、対立する意見よりも依然として多く支持されている。
| 5時間の列車の旅で、反対意見の支持者との議論に | 「体罰は基本的に間違っている」 (支配的になりつつある意見)% |
「体罰は子供の教育の一部だ」 (敗北しつつある意見)% |
| 加わりたい | 55 | 45 |
| 加わりたくない | 45 | 49 |
| 無回答 | 5 | 6 |
| 計 | 100 | 100 |
支配的になりつつある意見(まだ多数派ではない場合でも)を支持する人々が、議論に積極的であるという期待は確認された。現代的な意見は通常、若い女性によって支持されることが多く、若い女性は他人と自分の意見を議論する傾向が強いと主張することもできる。しかし、年齢層別の分析によれば、勢いを増している意見を支持する人々は、年齢に関係なく、公然と自分の意見を表明する傾向が強いことが示されている。
マスメディアの影響
マスメディアが世論形成において最も効果的に影響を及ぼすポイントが明らかになった。それは、共鳴性(意見の一致)、累積性(繰り返しの影響)、そして公然性または普及性が顕著であればあるほど効果的だということである。
1. これらのポイントの一つは、ルーマンの「テーマ化」によって提供される。特定のテーマやトピックに注目を集め、それに重要性や緊急性のオーラを与えることである。このプロセスの一部として、危機を示唆したり、高い地位を持つコメンテーターが特定のメッセージを発信する際に大きな反響を与えたりすることが挙げられる。
2. 問題解決のための要求や提案が世論において優勢を得られるかどうかは、それらが現実的に実現可能であると見なされるかどうかに依存する。マスメディアは、そうした実現可能性に関する判断を高い程度で形成する力を持つ。
3. 個人による社会環境の観察や認識は、マスメディアによって大きく影響を受ける可能性がある。例えば、どの意見が支配的であるのか、どの意見が勢いを増しているのか、または公共の場でどの意見を発表しても孤立する危険がないのかといった点である。これにより、マスメディアは沈黙の仮説で想定されるスパイラル的なプロセスに影響を与えることができる。
ノエル・ノイマンは、報道や編集コメントの共鳴性、メディアでの周期的繰り返しによる累積性によって選択的知覚が制限されるほど、態度はマスメディアによってより影響を受け、形成されやすくな理、個々の意見形成のプロセスは、個人が社会環境を観察することでさらに強化される、と結論づけている。
1974年の論文:The spiral of silence
ノエル・ノイマンが初めて「沈黙の螺旋」(Spiral of Silence)という専門用語を公表したのは、1974年にJournal of Communication誌に掲載した"The spiral of silence: A theory of public opinion."という論文であった(Noelle-Neumann, 1974)1974年の論文「沈黙の螺旋:世論の理論」で、ノエル・ノイマンは「世論」という概念を「制裁を受ける心配をせずに公衆の面前で表明できる意見のことであり、公共の場での行為の基礎となりうるような意見」と定義している(Noelle-Neumann, 1974)。また、「世論は優勢(dominant)な意見であり、それは一定の態度や行動を人びとに強制する。すなわち、これに反抗する個人には孤立化の恐怖感を与え、政治家に対しては有権者の人気が落ちるという脅しを与える」と述べている。
「沈黙の螺旋」仮説とその検証
そして、ノエル・ノイマンは「沈黙の螺旋過程」に関する次の5つの仮説群を提示した。
- 個人は、自身の社会環境における意見の分布とその傾向についてのイメージを形成する。どの意見が力を増しているか、どの意見が衰退しているかを観察する。このことは、個々の意見と環境の想定された意見との相互作用としての世論の存在や発展の前提条件である。環境の観察の強度は、特定の問題に対する関心の度合いだけでなく、個人が特定の話題について公然と自分をさらす必要があるとどの程度予想しているかによっても変わる。
- 自分の意見を公然と表明する意欲は、社会環境における意見の分布とその傾向の個人による評価に応じて変化する。自身の意見が支配的である、または支配的になりつつあると信じる場合には意欲は高まり、自身の意見が劣勢になりつつあると感じる場合には意欲は低下する。意見を公然と表明する意欲の度合いは、公開された意見が世論分布に与える評価に影響を及ぼす。
- 現在の意見分布の評価と実際の分布が明らかに異なる場合、過大評価された意見が公然と表明される頻度が高いことが原因であると推測できる。
- 現在の評価と未来の評価の間には正の相関がある。つまり、ある意見が支配的であると考えられる場合、それは未来においても支配的であると考えられる傾向がある(その逆も同様である)。しかし、この相関の強さには程度の差がある。相関が弱い場合、世論は変化のプロセスにあることを示している。
- 特定の見解について現在と未来の評価が異なる場合、未来の位置づけの期待が、個人が自分を公然とさらす意欲の程度を決定する。このことは、自身の意見が多数派の意見や意見の傾向によって確認されない場合、孤立する恐れや自己肯定感の喪失が原因であるという仮定から導かれる。意見の傾向が自分の意見に向かっていると確信している場合、孤立のリスクはあまり重要ではない。
これらの仮説を検証するために、アレンスバッハ世論研究所が1971年と1972年に実施した調査を使用した。この調査では、代表的な人口層を対象に、1,000~2,000件の構造化インタビューが行われた。調査には以下の4種類の質問が含まれていた。
1. 論争の的となるテーマ(人物や組織、行動パターン、提案)に関する回答者自身の意見についての質問。
2. そのテーマについて「連邦共和国の大多数の人々」がどう考えているかに関する回答者の見解についての質問。
3. 将来の傾向に関する質問。
4. 公的な場での意見表明に関する質問。このため、回答者に長距離列車の旅での乗客同士の会話を想像させ、論争のある話題について会話に加わるかどうか、どのように加わるかを示すよう求めた。
調査では、西ドイツで社会主義の将来について発展すると予測する2つのグループを比較している。この両者は、連邦共和国(西ドイツ)が社会主義に向かっていると考えている点で一致するが、一方はこの発展を歓迎し、もう一方はそれを危険だと見なしているという違いがある。調査結果は、これら2つのグループが自分を公の場で意見を表明する度合いが異なることを示している。発展だとする「敗者グループ」は依然として危険だとする「勝者グループ」より数的にははるかに大きいが、多数派が沈黙を守る傾向は顕著であり、「沈黙する多数派」の印象を与えるものである。
| 社会主義が西ドイツで発展することについて | 発展だ (勝者の側) % |
危険だ (敗者の側) % |
| 議論に参加したい | 53 | 28 |
| 議論に参加したくない | 41 | 61 |
| 無回答 | 6 | 11 |
| 合計 | 100 | 100 |
次に、社会主義の進展を進歩として歓迎するグループが議論に対してより積極的である理由が、より顕著な政治的関心によるものかどうかを検討した。その結果、政治に関心のある者、ない者の両方において、「勝者グループ」の発言傾向と「敗者グループ」の沈黙傾向が明確に見られた。
マスメディアの影響
マスメディアは、個人が環境についての情報を得るために利用するシステムの一部である。個人が自分の直接的な個人的領域外の事柄について考える場合、事実や世論の雰囲気を評価するための情報はほとんど完全にマスメディアに依存している。個人は、公開された(すなわち出版された)意見の圧力に通常通り反応する。研究では、特定のテーマや人物に関する意見の優勢がメディアシステム内でどのように生じるのか、またその促進要因や抑制要因にますます関心を持つ必要がある。これは、ジャーナリストの信念に基づいているのか。それとも、ジャーナリズムの職業的な技術の原則に基づいているのか。あるいは、優勢な意見の支持者がメディアシステムの中で重要なポジションを占め、数的に強い反対者のグループでさえ排除することが可能になっているのか。
マスメディアが世論に与える影響を研究する際には、操作可能な形で世論の生成過程を説明する概念が必要である。そのような概念が「沈黙の螺旋」であり、次のような問いを提起する。どのテーマがマスメディアによって世論として提示されているのか(アジェンダ設定機能)、その中でどのテーマが緊急性を持つと提示されているのか。どの人物や議論が特に、将来を味方につけているという特別な権威を与えられているのか。これらのテーマや緊急性、将来の可能性の提示がどれほど一致しているのか。
長い間、メディアが世論を予測するのか、それとも反映するのか—すなわち、世論の鏡であるのか形成者であるのかについて、科学的な議論が行われてきた。「沈黙の螺旋」と呼ばれる社会心理学的なメカニズムによれば、マスメディアは世論を形成するものとして捉えられるべきである。マスメディアは、人々が迅速に反応したり、同調したり、沈黙したりする環境圧力を提供するのである。
沈黙の螺旋理論の誕生
この理論が生まれるきっかけとなったのは、1965年の西ドイツ連邦議会選挙であった(Noelle-Neumann, 1997, 邦訳1-9)。当時、ノエル・ノイマンはアレンスバッハ世論調査研究所の所長として、選挙調査に携わっていた。世論調査の結果では、選挙の2ヶ月前までは、キリスト教民主同盟(CDU/CSU)と社会民主党(SPD)に対する有権者の支持率はほぼ拮抗しており、大接戦を演じていた。ところが、「選挙ではどちらの政党が勝つと思いますか」という設問に対する回答をみると、「社会民主党が勝つ」と予想する人の割合は一貫して減少し、逆に「キリスト教民主同盟が勝つ」と予想する人の割合が一貫して増大し続けていた。そして、選挙1ヶ月前の世論調査では、キリスト教民主同盟への支持率が急上昇し、社会民主党への支持率が低落した。
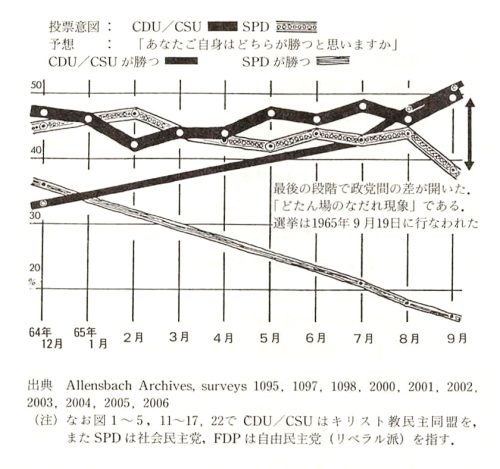
Noelle-Neumann, 1997 邦訳より
最終の選挙では、キリスト教民主同盟が9%のリードで勝利を収めたのだった。
「だれが勝つと思うか」という予想は、いわば政党支持についての「意見の風土の知覚」だといえる。
つまり、世間の多数の人びとがどちらの政党を支持しているかということに関する知覚を測定したものと考えられる。こうした「意見風土の知覚」によって、社会民主党の支持者は、しだいに人前で公然と支持についての意見を表明することをためらうようになり、その結果、選挙戦で次第に不利な立場に立たされ、選挙での敗北を引き起こしたのだ、とノイマンは解釈したのである。
ただし、ノイマン自身は、ある論文の中で、意見風土の認知は同調への圧力を生み、それが態度や行動の変化を引き起こすと考えているようである。ちなみに、彼女は「世論は優勢(dominant)な意見であり、それは一定の態度や行動を人びとに強制する。すなわち、これに反抗する個人には孤立化の恐怖感を与え、政治家に対しては有権者の人気が落ちるという脅しを与える」と述べている(Noelle-Neumann, 1974)。とはいえ、「沈黙」を強いることと,「態度を変化させる」こととの間には矛盾があることも事実である。
こうした「沈黙の螺旋」過程の中で、マスメディアは、「多数派意見」を持続的に受け手の提示することによって、沈黙の螺旋過程を促進する働きをする。
沈黙の螺旋仮説の検証
さて、この沈黙の螺旋仮説は,実際の調査データなどによって,どの程度支持されているのだろうか。
この仮説は、「意見風土の知覚が、公的な場面で自分の意見を自発的に表明するかどうかに影響を与える」というものである。ノエル・ノイマン自身、この仮説検証のために、いくつかの異なる調査方法を用いた。そのうち,もっとも有名なのは、「列車テスト」と呼ばれるものである。公的な場面として「列車の中」を設定し、回答者に次のような設問をする。「あなた自身が列車に乗って5時間の旅をしていると想像してください。あなたのコンパートメントには他の乗客が何人かいて、その乗客があなたに、ある論争的な問題Xについての会話を始めたとします。このとき、あなたはXについての会話に進んで加わりますか?」
例えば、タバコを喫うことに対して脅威的な状況を実験的に作りだした場合、喫煙擁護派の人たちは反対派の人たちにくらべて、「非喫煙者の前でタバコを喫うこと」についての話題に加わりたくないという比率が有意に高いという結果が得られた。これは、沈黙の螺旋仮説を支持するものだとノイマンは主張している(Noelle-Neumann, 1977)。
とくに、列車の同乗者が「非喫煙者の前でタバコを喫うのは控えるべきだ」という意見を述べたと想定した場合には、喫煙者が会話に加わりたくないという比率はさらに低下した。一方、同乗者が喫煙を支持する意見を述べた場合には、会話に加わる比率は上昇するという結果が得られた。喫煙に対する脅威的状況は、心理テストでしばしば用いられる文章完成法を援用した。ここで回答者は文章を完成するよう求められる。このテストを受けた人びとは、喫煙反対派からのプレッシャーを受けると想定された。
列車テスト以外にも,公の場面での意見表明をはかるための選択肢がいくつも工夫された。例えば、次のような項目である。
- キャンペーン用の応援バッジをつけて歩く
- 自分の車に支持政党のステッカーを張る
- 見知らぬ人の家を訪ねて、党の政策を説く
- 自宅の塀や窓に、支援政策のポスターを張る
- 公の場に出かけて支持政党のポスターを掲示する
- 路上での議論に参加し,支持政党を弁護する
- 党大会に出席する
- 党の会合で発言する
- キャンペーン・パンフの配布を手伝う
意見の風土と多元的無知
では、自分の意見が多数派に属するのか、それとも少数派なのか、どうやってチェックすればいいのだろうか?また、こうしたチェックの結果は果たしてどの程正確なものなのだろうか?多元的無知のような認知バイアスはないのだろうか?ノエル・ノイマンは、この点に関して、普通、人々には「準統計感覚」が備わっている、という。つまり、ある争点に関して、賛成の人が何%くらい、反対の人が何%くらいいるか、という意見分布について、人は大雑把な判断をしているのだ、と考えているようである。その手がかりは、マスメディアの報道する「世論調査」を参考にしたり、家族や友人との日頃のコミュニケーションなどを通して得ている、とノイマンは考えているようである。
しかし、人々が周りの意見分布を見積もる際に生じる「認知バイアス」(多元的無知)を考慮した時、果たして人々の「意見分布認知」つまり「準統計感覚」なるものが、果たしてどの程度正確なのか、もしそこに一定の規則的なバイアスが働いているとするならば、「孤立への恐怖」もまた一律に生じることはなく、「沈黙の螺旋」が一律に生じることもないのではないか?つまり、この仮説がどのような条件で生じるのか否かを正確に検討するには、意見分布の認知におけるバイアスや選択的認知、つまりメディア効果論でいうところの「媒介的諸要因」をさらに緻密に検討する必要があるのではないか?
これらの点については、安野(2002)が詳しく検討しているので、その議論を少し引用してみたい。
意見の風土つまり意見分布が誤って認知されている状態は「意見分布の無知」あるいは「多元的無知」(pluralistic ignorance)と呼ばれる(e.g., Katz and Allport, 1931;Prentice and Miller, 1996)。一般に意見分布の無知をもたらすものは、情報の不足と偏りである。そのような場合には、社会規範や身近な人の行動など、既知の分布から意見分布を推測せざるを得ない。その結果、世間の意見が実際以上に保守的に認知されたり、あるいは逆に実際以上にリベラルに認知されたりすることになる。ただし、仮にアグリゲートなレベルでは多数派意見が比較的正確に認知されていたとしても、すべての人が意見分布を正確に認知しているとは限らない。自分と同じ意見や選好を持つ人の割合は一般に、それ以外の意見や選好を持つ人の割合よりも相対的に過大に見積もられる傾向があり、これは「合意性の過大推測(FC)」効果(false consensus effect) として知られている。つまり、少数派のなかにも自らを少数派だと認識していない人がいるということである。
それでは、FC効果はなぜ生じるのであろうか。FC効果が生じるメカニズムとしては、①選択的接触と認知的利用可能性(自分に類似した人の情報は想起しゃすい)、②顕現性と注意の焦点(自分の態度や行動から他者を推測)、③論理的な情報処理(自分の選択は誰にも好まれるという誤った推論)、④動機的要因(自尊心維持、社会的サポートの欲求)、の四つが指摘されている(Marksand Miller , 1987)。
「合意性の過大推測効果」は、今日では、「合意性バイアス」として、認知バイアスの一つとして知られている。これが多元的無知を生じさせることは大いにありうることである。
Jacob Shamir, "Pluralistic Ignorance and the Spiral of Silence Meet Mutual Lessons" in "The Spiral of Silence
New Perspectives on Communication and Public Opinion" Edited ByWolfgang Donsbach, Charles T. Salmon, Yariv Tsfati, 2014
多元的無知という概念は1920年代に初めて提唱されたが、ノエル=ノイマンの沈黙の螺旋に関する論文が英語圏の学術誌に登場した時期とほぼ同じ50年後に、再び関心が高まった。
これら二つの理論は、いずれも世論の認識、すなわち人々が他者の意見や価値観をどのように見ているかに焦点を当てている。多元的無知の伝統的な経験的観察の中心は、人々がしばしば世論の評価を誤るという点にある。言い換えれば、世論の認識は必ずしも実際の世論の分布と一致しないのである。一方、ノエル=ノイマンの理論でも世論の認識は重要な要素であり、人々は常に自分の環境を観察し、どの意見が優勢で勢いを増しているかを確認するとされている(準統計的感覚)。さらに、これらの認識の集積としての「意見の風土」(climate of opinion)はノエル=ノイマンの世論理論の中心であり、個々の意見の分布頻度ではなく、意見の風土の変化に対する反応として沈黙の螺旋が生じるとされる。
多元的無知と沈黙の螺旋理論はいずれも、世論の認識と実際の意見分布の乖離を説明することを目的としている。また、これらの理論は、世論のミクロレベルとマクロレベルを結びつける。多元的無知は心理学的および社会学的観点から研究されており、沈黙の螺旋理論はその変化のメカニズムにおいて両者を統合している(これらの視点に関する初期の優れた議論についてはTaylor, 1982; Scheufele, 2008を参照)。
さらに、これらの理論は動態的な視点が必要である。沈黙の螺旋理論は、明確に動態的な世論理論であり、多元的無知の理解も動態的な視点によって大きく深化している。両理論の動態的要素を結びつけることで、世論に対する視野が広がり、世論の規範的および情報的な要因の役割が際立つのである。
多元的無知
社会心理学者フロイド・オールポートは1920年代に多元的無知という概念を提唱した。彼はこれを心理学的観点から幻覚のようなものと捉え、他者が様々な事柄についてどう感じ、考えているかに関する誤解や不適切で誤った印象とみなした(Allport, 1924; Katz & Allport, 1931)。1970年代以降、この「誤った信念のパターン」に対する関心が再び高まり、人種関係、国際政治、投票傾向、苦境にある人々への傍観者の反応といった多様な研究分野で取り上げられるようになった(O'Gorman, 1986, pp. 335, 345)。
「極端な例では、『多元的無知』の現象は、人々が『誤った』社会的世界、あるいは少なくとも客観的な社会科学者が観察する世界とはかなり異なる社会的世界の中で行動しているように見える状況を反映する」(Fields & Schuman, 1976, p. 427)。
この誤解は、世論研究における多元的無知の伝統において、知覚の正確性という観点から捉えられ(Daschmann, 2008)、多数派の立場を誤って読み取る現象として説明されてきた。特に興味深く、極端な例は、人々がある問題における少数派の立場を多数派と誤認し、逆に多数派を少数派と認識する場合である。多くの実証研究はこのような極端なケースに限定して分析を行ってきた。
多元的無知は、個人レベルの視点と社会的視点とでは異なる形で捉えられる。個人レベルの視点では、「多元的無知」の「無知」という要素が強調されるが、社会的視点ではこの現象の「多元的」な部分が重視される。社会的アプローチでは、「多元的無知は、単なる知らないこととしての無知ではない。それどころか、それは他者についての知識が誤って正しいと考えられている状況である… 社会的に受け入れられているが誤った社会世界に関する命題である」(O'Gorman, 1986, p. 333)。
多元的無知の社会的性質は、「無知」を個人の歪みや無知ではなく、集合的で共有されたものとする。この誤りは必然的に体系的であり、偶然的なものではなく、「無効」であり「信頼できない」ものではない(Fields & Schuman, 1976, p. 427)。社会的視点を採用することで、「本来正確な情報の知覚が歪む状況と、虚偽または誤解を招く情報を正確に知覚する状況の違い」が認識される(O'Gorman, 1986, p. 334)。
O'Gormanによれば、後者の状況が多元的無知であり、本稿のレビューでもこの視点を中心に論じる。これが個人レベルの分析や心理的プロセスが多元的無知の理解において無関係であることを意味するわけではない。しかし、社会的視点こそが、多元的無知と沈黙の螺旋理論の伝統を結びつけるものであり、世論研究において最も重要な関連性を持つものである。
世論の認識と多元的無知の説明
世論の認識、その正確性、多元的無知を理解しようとする試みは、異なる分析レベルやアプローチを交差させるものである。心理学的観点から見ると、多元的無知は、認知的な欠陥や自己利益バイアスのために、人々が完全に適切な情報処理者ではないことに起因する。この説明では、情報処理、帰属、内部的動機に焦点が置かれる。一方、社会的観点では、多元的無知は環境からの誤りやすいメッセージによるものである。不十分な、誤解を招く、または虚偽の情報の手がかりが世論の誤った指標として機能し、多元的無知を生み出す。
多元的無知を共有された現象、あるいは誤情報や虚偽情報を含む現象と見ることは、それが社会的な要因を持つことを意味し、焦点を心理的プロセスから社会的環境へと移す。ここで重要となる概念は「可視性」であり、これは「心理学的理論の観点でいう社会的知覚の社会構造上の対応物」である(Merton, 1968, p. 404)。可視性は社会および社会的文脈における問題の特性であり、メディア環境や対人ネットワーク、公共議題における問題の顕著性、文化的規範や価値観との共鳴、社会的および政治的構造性など、さまざまなコミュニケーション、社会的、政治的要因の関数である(Shamir & Shamir, 2000)。可視性は多元的無知を軽減する。
ノエル=ノイマンの沈黙の螺旋理論は、この視点から二つの洞察を提供する。一つ目は、彼女の著作で明示的に多元的無知と関連付けられてはいないが、沈黙の螺旋理論における必要な要素である「特定の種類の表明された意見」である。少数派であっても、信念を堂々と表明する献身的で熱心な社会的および政治的グループは、沈黙の螺旋を引き起こす可能性がある。「世論の雰囲気は、誰が話し、誰が沈黙するかによる」(Noelle-Neumann, 1993, pp. 4–5)。彼女は選挙キャンペーン戦略の成功例として、党を可視化し、世論の雰囲気に影響を与えることを推奨している(1993)。目立つ活動を行い、強さと勢いを示すグループは、動的な螺旋プロセスを引き起こし、意見表明と意見の認識が相互に影響を与える。その結果、グループや意見の実際の強さに関する誤解を生み出し、多元的無知を生じさせる。
二つ目は、ノエル=ノイマンの理論において、マスメディアが世論の雰囲気の構築や多元的無知の創出において中心的な役割を果たしているという洞察である。彼女は、ジャーナリストの政治的傾向、特にリベラルな傾向がメディアに反映され、社会の実際の意見分布を反映しない雰囲気を形成することがあると考えている。彼女はさらに、「…多元的無知、すなわち人々が他の多くの人々がどう感じているかについて誤った考えを持つ状態は、メディアの影響を追跡するための一種のガイドとして機能するだろう」(1993, p. 169)と述べている。このため、ノエル=ノイマンはマスメディアを多元的無知を引き起こす誤りやすいメッセージの発信源とみなしている。
放送時代の絶頂期に、ノエル=ノイマンは沈黙の螺旋理論を発展させ、「強力なマスメディアの概念への回帰」を提唱した(1973)。しかし、この見解は当時からすでに単純化されすぎていた(Salmon & Kline, 1985)上、現在のポスト放送時代のメディア環境ではさらに適切ではない。ケーブルテレビ、インターネット、携帯電話技術によってもたらされた新しいメディア環境は、情報を求める人々の間で偏向的な選択的接触を強化し、政治的な内容を好む市民と他の内容を好む市民との間にギャップを広げている(Bennett & Iyengar, 2008; Prior, 2007)。
この新しいメディア環境が意見形成、雰囲気の構築、多元的無知に及ぼす影響は、まだ研究が始まったばかりである(例:Debatin, 2008; Tsfati, Chotiner, & Stroud, 2012)。この環境における断片化と選択肢の豊富さは、メディア効果の縮小、分極化、沈黙の螺旋や圧倒的な世論の雰囲気の形成の可能性の低下を示唆している。一方で、新たな学際的パラダイムである「群知能」(Swarm Intelligence)が、多数の個人が集中調整なしに集合して新しい知的存在を形成し、それが意見の集合的表現や世論の雰囲気として現れる可能性を提案している(Garrett, 2006)。
世論の認識、世論の雰囲気、多元的無知は、複数の指標や多様な情報源に基づいて構築されることを忘れてはならない。したがって、放送時代およびポスト放送時代のメディア環境におけるメディアの影響は緩和されるべきであり、理論的および実証的分析では、これらの多様なプロセスや情報源を考慮する必要がある。最後に、ノエル=ノイマンと多元的無知の研究者たちは、顕出性とプライミングが、どの指標が優勢になり多元的無知を生み出し、あるいは打破するかを決定する上で重要な要因であると指摘しており、これらのプロセスは今後の研究に組み込まれるべきである。
多元的無知の通時的視点
多元的無知は、意見分布とその認識の間のギャップに焦点を当てており、この伝統における研究の多くは断面的である。そのため、Glynn、Ostman、およびMcDonald(1995)のレビューでは、多元的無知をプロセスではなく結果として扱っている。しかし、多元的無知に通時的視点を採用することで、その理解が進み、沈黙の螺旋はその一つの動的な経路を提案している。
ノエル=ノイマンの理論は、意見風土の変化が個人の私的態度の変化を伴わずに起こるという、多元的無知の一つのパターンを描いている。大衆メディアや社会的エージェント(熱心な政党活動家や社会運動)が、実際の意見分布とは大きく異なる形で世論の認識に影響を与える。世論の認識は、誰が発言し、誰が沈黙するかに影響を与え、これらの公的表現パターンが世論の認識を再定義し、可視的な人々に有利な方向へ世論の気候をさらに進める螺旋的なプロセスを生み出す。
これとは逆のパターンは、態度が先に変化し、意見風土がそれに遅れるものである。ノエル=ノイマンが巧みに描写するように、世論の意見風土は世論の規範的側面であり、社会のより永続的な規範的および構造的特性に近い。一方、態度は世論の評価的側面を構成し、日々の出来事や政治的、社会経済的、国際的な発展に敏感である。この意見風土と私的態度の理解を踏まえると、この逆パターンの方が一般的であると予測される。
このプロセスは多元的無知の文献で記録され、「保守的バイアス」としてラベル付けされている。このような乖離は、社会的変化の時期、つまり態度が進行中の出来事や発展とともに変化する一方で、社会構造の規範や慣行が気候とともに遅れる時期に最も起こりやすい。この概念は、アメリカの人種関係において提唱され(Fields & Schuman, 1976; Katz & Allport, 1931; O'Gorman, 1975, 1988)、自分自身以外の意見を帰属させる際に、他者を自分よりも保守的と見なす傾向を指している。「保守的」という用語は、イデオロギー的な意味での保守的と、既存の見解、状況、制度を維持しようとする保存的な意味での保守的が絡み合っている。人種平等の文脈では、既存の人種的不平等と分離の社会構造の毎日の表現が、態度が変化した後も長期間にわたって支配的な規範について保守的(リベラルではなく)な方向での強力で誤解を招く情報手がかりを提供していた。
同様の保守的バイアスは、長期的な紛争に巻き込まれた社会でも実証されている。イスラエル人とパレスチナ人の間の世論に関する縦断的データは、世論認識が多元的無知を示す場合、それは「タカ派バイアス」を伴うことを示している。これは、支配的な社会規範、構造、および慣行が紛争に向けられており、公共の言説が民族主義的かつエスノセントリックであり、内集団志向の社会的および政治的行為者やメッセージがより可視的で文化的に共鳴しており、メディアがタカ派の気候を描写する傾向があるためである(Shamir & Shamir, 2011; Shamir & Shikaki, 2010)。
一方で、少数ではあるが、人々の評価におけるイデオロギー的に「リベラル」なバイアスを記録した研究も存在する(例:Glynn, 1987; Taylor, 1982)。ただし、イデオロギー的に保守的なバイアスがリベラルなバイアスを上回る経験的な優勢は、メディアが世論気候に関する誤りの原因であり、メディアがリベラルであるとするノエル=ノイマンの主張と矛盾している。しかし、より根本的には、保存的な意味での保守的バイアス、つまり既存の社会規範、状況、制度に向けられた保守的バイアスは、このような多元的無知に理論的な基盤を提供する。
この観点で理解されると、保守的バイアスは可視性と情報の問題としての多元的無知の概念と一致する。この解釈では、保守的バイアスは世論分布の測定誤差であり、現在は無効な指標の使用に起因する。同じ要因、つまり社会的および政治的制度、共通の社会慣行、広範な文化的規範は、通常は意見分布の有効な指標として機能し、可視性に寄与する。しかし、変化の時期には同期が損なわれ、多元的無知を生み出す可能性がある。
世論のダイナミクス:規範的および情報的な力
多元的無知の現象とその社会構造的かつ動的な視点からの探求は、世論という概念のより完全で深い理解に寄与するものである。「多元的無知の文脈において、世論とは何か」というやや素朴な問いを立てることができる。それは多数派の意見なのか、それとも多数派と認識される意見なのか。
このジレンマに対する私の答えは、世論を多次元的な概念として捉えることである。この概念には、意見の態度や分布の認識だけでなく、将来の展開や意見表明に対する期待といった他の要素も含まれる(Shamir & Shamir, 2000)。世論のこれらの次元は多くの場合同期しているが、間に不一致が生じることもある。多元的無知はそのような不一致の一例であり、実際の多数派意見とその認識の間に、時に大きな乖離を示すものである。この乖離を探求することによって、その原因を明らかにし、世論とは何か、また世論がどのように変化するのかをより深く理解できる。
沈黙の螺旋理論は、明確に動的な世論理論であり、そのエンジンは、規範的な意見から逸脱することによる孤立への恐怖である。しかし、この理論は世論の表明と認識の関係に焦点を当てており、世論の標準的な見方である意見分布を無視している。このため、この理論は「社会的認識の理論」として捉えられることがある(Scheufele & Moy, 2000)。ノエル=ノイマンは、合理的な世論の概念よりも社会的統制としての世論の概念を強調しており(1993, 1995)、その経験的研究では出来事や発展の影響を完全に無視している。
この理論は、世論の規範的な源泉を強調しているが、世論には情報的なエンジンも存在する。態度(および期待)は、政治的・社会的発展や出来事の情報によって影響を受ける(Page & Shapiro, 1992)。これは、多元的無知における保守的バイアスの事例が例証している。
これら二つのアプローチを統合することで、世論の規範的および情報的な源泉の役割に注目が集まる(Deutsch & Gerard, 1955)。集団的な社会的存在としての世論は、一方で社会的統制の規範的な力と、他方で出来事の情報と合理性の強力な影響との間の長年の緊張関係を包含している。世論は情報的および規範的な源泉によって形作られる。
それに対応して、世論のダイナミクスは多様であり、規範的な社会的統制の力、出来事情報、沈黙の螺旋、そして保守的バイアスの関数として機能するものである。
孤立の恐怖と沈黙の螺旋
すでに述べたように、ノエル・ノイマンは、次のような仮説を立てた。
人はふつう、集団や社会の中で孤立したり、村八分にされたりすることを恐れる。こうした恐怖感があるので、周囲の人びとがどんな意見をもっているのか、あるいはどんな行動をとっているのかを絶えずチェックしている。そこから、世の中の意見の分布状況(意見の風土)についての一種の統計的な感覚を身につける。たとえば、ある政治的争点に関して何%くらいの人が賛成しているのか。などといったことに関する判断を下すことができる。こうした判断が、人前で自分の意見を公然と表明するかどうか。という決定に影響を与える。もしある争点に関して自分の意見が、世間の多くの人たちと同じである、つまり、自分の意見が多数派だという認識をもつならば、かれは人前でも堂々と意見を表明するだろう。逆に、自分の意見が少数派だと判断する場合には、その人は自分が孤立したり、あるいは仲間外れにされることを恐れて、沈黙を守るだろう。
つまり、大抵の人は、社会の中で孤立することを恐れる、つまり自分が少数意見の立場にあることを恐れるので、周りの多くの人がどんな意見を持っているかをチェックする。もし自分が多数派だと分かれば、安心して人前で自分の意見を公然と言える。なぜなら、多数派の意見を主張しても、孤立する心配はなく、安心し自分意見を言うことができる。ただし、この「多数派」判断は、現時点での優勢判断だけではなく、「近い将来多数派になりそうか」と言う近未来予測であっても差し支えない。一方、自分の持っている意見が少数派だと分かった場合、あるいは少数派になりそうだと分かった場合には、それを公然と人前で言うと、孤立するばかりか、他者から何らかの制裁(非難される、絶交される、嫌がらせ)を受ける恐れがあるので、沈黙してしまいがちである。
沈黙の螺旋過程で当然だと受け止められている「孤立の恐怖」については、さまざまな疑問が呈されている。孤立の恐怖というのは、確かに存在はするが、それが無条件ですべての人で生じるものか、あるいは生じたとしても、それが意見表明の有無にストレートに結びつくものなのか、という点でも疑問がある。例えば、安野(2002)は、近年の研究レビューを踏まえて、次のように批判している。
孤立への恐怖は、個人差や状況要因の影響を受ける可変的なものだとするとらえ方もある(e.g., Neuwirth, 2000) °また、たとえ孤立への恐怖が普遍的なものであったとしても、「沈黙の螺旋」仮説が扱っているような社会的争点に関して、強い同調圧力が働くことは現実には考えにくい。実験室状況での同調行動をそのまま社会的現実場面に適用することには無理がある。たとえばブースの中で行われる投票や、自宅で回答される世論調査のように匿名が保証され、他者の目にも触れない状況で同調圧力の影響を受けるとは考えにくいからである。
Noelle-Neumann (1993)は、多数派に属する人であっても、メディアの支持が得られなければ沈黙する傾向にあるとして、マスメディアによって認知される意見風土が孤立への脅威をもたらすと論じている。逆にいえば、少数派もメディアの支持があれば積極的に発言することができるということである。しかし、準拠集団の存在を考慮すると、孤立への恐怖がすべての有権者に対して一様に作用するという仮定は非現実的である。見知らぬ他者からの孤立よりも準拠集団内の孤立の方がより恐れられると考える方が妥当であろう。現実に人々の意見や行動と密接に関わるソーシャル・ネットワークについて言及されていない点は、この理論の大きな問題点である。また、意見分布を認知するとき、あるいは意見を表明しようとするときに人々が直接接触する相手には、帰属意識の対象となる家族や友人、同僚といった準拠集団の成員が多く含まれる。そのため相互作用の相手とはもともとの態度が似通っている、つまり自分の意見の支持者が存在する可能性が高い。多くの組織に加入している人の政治参加や意見表明は、加入組織の少ない人よりも意見風土の影響を受けにくいという知見もある。
特に、YouTubeやSNS上で自分と同じ意見がエコチェンバー的に反復されることの多い現在のメディア環境においては、「孤立への恐怖」は以前ほどには生じない可能性が強く、「沈黙の螺旋」過程の存在には疑問符がつくのではないだろうか。
メディアの「公共化」機能
ノエル・ノイマンは、「意見風土の知覚」に影響を与えるものとして、ある意見が優勢だという情報を社会的に「公共化する」マスメディアの機能にも触れている。つまり、社会の中のある意見は,マスメディアの「公共化機能」によって、社会内に分布する顕在的意見を「公共的な意見」すなわち世論に転化するのだ、と述べている。意見が公共化することによって,それは公に認知された多数意見として、同調への圧力を生み、沈黙の螺旋的な展開を引き起こすものとされる。
平林(1987)は、マスメディアを「意味付与を行う機関」(signifying agents)として位置づけることによって、ノエル・ノイマンのいう「公共化機能」を次のように再定式化している。すなわち、「メディアが提示する社会的リアリティは、メディアによる「公共化」を通じて、人びとが共有している(と知覚されている)公共的リアリティになる。公共的リアリティであるからこそ、それは一つの社会的合意の基礎になり、そこから公に逸脱するものには社会的制裁が与えられるのである」(平林,1987)。
沈黙の螺旋過程から外れた人びと(ハードコア)
沈黙の螺旋過程においても,社会的同調への圧力に屈することなく、最後までこれに抵抗を示す人びとがいる。かれらは、新たな社会変動の始発者としての役割を果たす。
ハードコア層(hard core)とは、沈黙の螺旋過程が最終段階を迎え、多数意見が支配的になってもなお、孤立することを恐れず少数意見を固守する少数の人びとのことをいう。ハードコアは、争点に関して非常に強い念をもっているために、孤立の脅威を生じる状況においても、積極的に自分の意見を表明する傾向がみられるという。
ただし、ハードコアの概念規定はかなり暖味であり、研究者によって、その操作的定義は異なっている。例えば,グリンとマクレオド(Glynn & McLeod, 1982)は、「選挙キャンペーン期間中に候補者への選好が決まっており、かつその候補者に投票した人」をハードコアと定義した。しかし、このような人びとは対象者全体の過半数を占めており、根念定義上の問題を含んでいる。
また、沈黙の螺旋過程の初期段階では、ハードコア層を定義することも識別することもできない、という実証上の問題点も指摘されている。さらに、ハードコア層が一般にどのような特性を備えた人々かという点についても明らかにされていない。ロジャーズの普及理論における「遅滞者」(ラガード)と共通する特性を備えているのか、その点についても沈黙の螺旋理論は答えていない。また、安野(2002)いよれば、ノイマンはハードコア層がなぜ最後まで意見を変えないのか、についても説明を与えていないと指摘している。
少数意見の多数意見への転化(スパイラル)
沈黙の蝶施仮説によれば、少数派だと知覚する人たちは沈黙し、多数派が声高に意見を表明するがゆえに、雪だるま式に優勢な世論が形成されるという考え方であるが、これだと、少数意見は,いつまでたっても少数意見のままにとどまってしまうことになり、現実の世論の変化を説明することができない。
この点について、ノエル・ノイマン自身は、「将来優越的になるという見通しを持つ少数者が進んで意見を表明し、逆に将来の見通しに対して悲観的な多数者が沈黙するならば、現在の少数意見は。やがて支配的な意見=世論となる」と述べている(Noelle-Neumann, 1974)。さらに、少数意見を多数意見に変える上で、マスメディアの果たす役割にも注目する必要があるだろう。もし、マスメディアが、それまで少数派だった意見を積極的に提示するならば、それが「知覚された意見の風土」を変え、沈黙の螺旋過程を転換させるきっかけとなるだろう。
沈黙の螺旋理論とナチス時代の遺産
ノエル・ノイマンの「沈黙の螺旋理論」に対しては、マス・コミュニケーション研究史の専門家の間から、深刻な批判が提起されている。それは、第二次大戦の期間中に彼女がナチスのプロパガンダに協力したという過去をめぐる問題である(Bogart, 1991; Simpson, 1998)。こうした批判のイデオロギー的な側面は、母国ドイツの国内問題であるので、ここでは取り上げないが、こうした過去の経歴が沈黙の螺旋理論に含まれる問題点に結びつくものであるならば、問題と得ざるを得ないだろう。それが一般に学説史研究の一つの目的でもあるからである。
ここで紹介するのは、Amerian University助教授のChristopher Simpsonが、コミュニケーション研究の権威ある学会誌 Journal of Communication 46(3)号に発表した、”Elisabeth Noelle-Neumann’s “Spiral of Silence” and the Historical Context of Communication Theory”という論文である。論文作成にあたっては、本人の許可を得てノエル・ノイマンへのインタビューも行っており、内容的には十分信頼できると考えられる。また、本論文の趣旨は、ノエル・ノイマンの戦前におけるナチとの関わりがSpiral of Silenceの著作にどのような影響を与えているかを実証的に解明することにあり、ここでの検討にとって有益だと判断したことをお断りしたい。
アメリカでの世論調査研究
1935年、エリザベートは19歳でドイツ国家社会主義学生連盟(NSDStB)に加入し、同連盟の新聞『ディー・ベヴェーグング』(運動)や、ナチス支持の青年雑誌『ドイチェ・ツクンフト』(ドイツの未来)などに寄稿するようになった。
1937年、ゲッベルスの宣伝省はエリザベートに奨学金を授与し、彼女はミズーリ大学でジャーナリズムと米国で発展していた世論の調査および形成技術を学ぶこととなった。エリザベート・ノエルは、この時期を通じて反ユダヤ的であり、ヒトラー政権を強く支持する公的な姿勢を取っていた。1938年、彼女はミズーリ大学の学生新聞に掲載された記事で、「人種の混合は国家の特性を維持する上で危険であると国家社会主義は考えている。歴史が示すように、偉大な国家の衰退は人種の混合から始まっている」と述べている。
博士論文の執筆
ドイツに帰国後、エリザベート・ノエルは、ベルリン大学で博士論文を完成させた。その論文では、アメリカにおける世論調査技術の研究を総括し、アメリカのメディアがドイツに対するアメリカの世論を結晶化させることに成功したと強調している。彼女は、アメリカ人の多数派は、ドイツやドイツ人に対して好意的な態度を持ち、ユダヤ人、イタリア人、その他の民族グループに対して敵対的な態度を取っていると主張した。その背景には、様々な人種や民族グループとの個人的経験が影響しているとしている。しかしながら、ドイツへの好意的な感情は、敵対的なニュース報道や反ドイツのプロパガンダによって覆い隠され、多くのアメリカ人が自らの親ドイツ的な見解を率直に語ることをためらうようになったと述べている。この議論は後の「沈黙の螺旋(Spiral of Silence)」理論で展開される内容を予見させるものであった。
ゲッベルスが始めたタブロイド週刊誌『ダス・ライヒ』(Das Reich)
1940年初頭、ゲッベルス宣伝省は『ダス・ライヒ』という週刊誌を創刊した。この週刊タブロイド紙は、ナチ党内外の政府、企業、科学、文化の指導者層を含むドイツ知識人を主な対象としていた。ゲッベルスの意図は、『ダス・ライヒ』を知的に尊敬される媒体とすることであった。表向きには独立した出版物とされていたが、『ダス・ライヒ』はゲッベルス省によって企画され、許可され、資金提供されたものであった。ゲッベルス自身がほとんどの号で一面のコラムを執筆し、その文章は彼の週刊ラジオ放送でも使用されることが多かった。
エリザベート・ノエルは、この新しい出版物が創刊された1940年の初期数か月間に寄稿を始めた。『ダス・ライヒ』の女性スタッフライターは非常に少なく、彼女の記事は一面で取り上げられることが多かった唯一の女性であった。彼女の初期の執筆活動には、ホームフロントや職場での女性の士気に関する特集、ベルリンの日常生活を描く軽い記事、ベルリンで学ぶエリート枢軸国兵士を称賛する報告などが含まれていた。刊行から1年も経たないうちに、同誌は彼女の作品を当時の主要な宣伝テーマを反映した二ページ見開きの特集で取り上げるようになった。たとえば、1941年6月8日に掲載された「誰がアメリカに情報提供しているのか」という記事では、アメリカのメディアを痛烈に批判し、アメリカの新聞、ラジオ、映画がユダヤ人に支配され、ドイツに敵対的であると主張した。
アメリカにおける純然たるユダヤ系新聞は、周知の通り、『ニューヨーク・タイムズ』と『ニューヨーク・ポスト』である。しかし、そこでも[ユダヤ系戦争プロパガンダ]はすぐには目立たない…。真に影響力のある評論家たちは、中立的に見える文章を用いて、反ドイツ的な議題を巧妙に隠している。その中で最も学識的なのは、ドイツ系ユダヤ人であるウォルター・リップマンである…。彼はこの中立的な偽装を最も巧みに使いこなし、読者を「アメリカは四方八方から脅かされている」という結論へと賢明に導いている。彼はかつてルーズベルトに反対していたが、現在では無条件で介入を支持する高額金融の代弁者である…。」(『ダス・ライヒ』エリザベート・ノエル、1941年、6-7頁)
ナチスへの幻滅
夫となるヘルベルト・ノイマンは、1939年に『ダス・ライヒ』でノエルと出会い、恋に落ちた著名なドイツ軍の特派員であり、後に『ダス・ライヒ』で東部戦線からの報告を担当した。ノイマンの報告はナチスの方針に沿ったものであったが、スターリングラード後の彼の文章には悲観的なニュアンスが見受けられる。さらに、ノイマンは1937年にナチ党に加入していたが、戦争へのナチ党の関与に幻滅し、会員資格を放棄していたようである。エリザベス・ノエルにとって、この幻滅は一線級のジャーナリズム(ダス・ライヒ)からの離脱という形で表れたようである。
Simpsonは、戦時中におけるエリザベス・ノエルの活動、特に『ダス・ライヒ』での執筆活動を次のように批判している。
彼女の『ダス・ライヒ』における執筆は、無実の人々への迫害を激化させる意図を持つ反ユダヤ的なキャンペーンに寄与していたことが明白である。また、彼女のアメリカのマスメディアに関する記述は、反ドイツ的なアジェンダを持ち、無防備な聴衆を操作しようとする強力で退廃的なリベラル派ユダヤ系メディアとして描写していた。ゲッベルス省は、『ダス・ライヒ』における彼女の作品を、戦争やホロコーストを正当化する試みの中で何度も利用していた。(Simpson, 1996, p.160)
戦後の活躍
戦後、ノエルは新しい夫ヘルベルト・ノイマンと共に、アレンスバッハに「世論調査研究所」を設立した。この研究所の主要顧客は、戦後西ドイツで最も強力な政治組織であるコンラート・アデナウアー首相のキリスト教民主党であった。
彼女はマインツ大学のコミュニケーション学教授であり、ドイツのコミュニケーション研究に実証的手法を初めて導入した人物の一人である。また、経済的に成功し、方法論的に革新的な調査およびマーケティング研究機関「アレンスバッハ世論調査所」の所有者であった。彼女は戦後ドイツ初期からアデナウアー、コール、メルケルに至る歴代首相に対し、ドイツ国民の世論に関する証拠を提供してきた政治顧問でもあった(Donsbach et.al., 2014)。
ノエルは1945年以降、ドイツ保守政治思想の主流に巧みに身を置いてきた。彼女はイスラエルの主要大学から学術的栄誉を受け、またウォルター・リップマンのようなユダヤ人学者を思想の重要な影響源として頻繁に挙げている(Noelle-Neumann, 1984)。
しかしながら、『沈黙の螺旋』やボガート(1991年)の論文による論争へのノエルの対応には、ナチス・ドイツでの青春期に形成された先入観が色濃く反映されている。例えば、ノエルが1937年に述べた「人種混血は国民性の維持にとって危険である」という発言(ニューヨークタイムズ、1991年、p.B-16)は、ナチスの人種理論を明確に表すものである。
反民主主義的な思想
ノエル=ノイマンの議論は、一般的な意味で科学的理論というよりも、むしろ政治的声明と呼ぶにふさわしいものである。『沈黙の螺旋』および関連著作において、ノエル=ノイマン(1984年)は、人類の大多数は「感情的に影響を受けたステレオタイプ」と「社会的孤立への根深い恐怖」に囚われ、無知と無力の中で生きる運命にあると主張している。彼女は、「人々が成熟と寛容をもって行動し、科学者のように観察し、思考し、判断することで客観的に現実を理解しようと努力し、その努力をマスメディアが支える」という古典的な民主主義の理想は「幻想」であると断じている。また、「真に参加型の民主主義」は「合理主義的な自己欺瞞」であり、拒否されるべきものだとも述べている(いずれもp.143からの引用)。
さらに重要なのは、ノエル=ノイマンが、どのような教育、環境、社会構造の変化があっても、特定の集団の大多数がそのような民主主義を実現するために行動を変えることはできないと主張している点である。彼女はこの主張を裏付けるために、ウォルター・リップマンをはじめとするコミュニケーション学の大家たちの文献を引用している。しかし、この主張は根本的には反民主主義的であり、それは「普通の人々」、つまり本格的な参加型民主主義に必要な知的能力を欠いているとされる人々についての彼女のステレオタイプが正しいと前提していることに基づいている。ノエル=ノイマンはこうした人々に同情を示しているものの、彼女自身は決してその一員ではないと考えている(ノエル、1984年、pp.ix-x)。
『沈黙の螺旋』およびその他の近年の著作を通じて、ノエル=ノイマンは、多くの人々が無知で受動的であり、真の自治能力に欠け、単純な社会的儀式を観察する以上の重大な意思決定を担う能力がないと結論づけている(例:ノエル、1984年、pp.143-182)。しかし、まさにこうした大衆こそが強力な体制を支えるか、あるいは崩壊させるコンセンサスを形成する可能性があると彼女は指摘している。これに基づき、ノエルは、文化的および政治的エリート――彼女自身もその一員であると見なしている――が安定性を強制し、低俗な民主主義の波から彼らの価値と伝統を守るべきであると主張する。このようにして、マスメディアの政治的、文化的、イデオロギー的性格を巡る闘争がノエル=ノイマンの研究の中で重要な戦場として浮かび上がる(ノエル、1984年、pp.143-182; ノエル&シュトランペル、1984)。
このように、SImpsonは、ノエル・ノイマンの『沈黙の螺旋理論』には、ナチス時代からの彼女の一貫した反民主主義的、反ユダヤ主義的な偏向思想が貫かれている、と厳しく批判している。この批判がどの程度妥当なものか、資料を詳しく吟味しなければ判断を下すことはできないが、Simpsonの批判は、『沈黙の螺旋理論』の問題点をあぶり出す上では参考になるかもしれない。
ここで、一つだけ注目しておきたいのは、ノエル・ノイマンが一貫して持っていたとされる「大衆蔑視」の思想である。これは戦前の大衆社会論を引き継ぐ考え方であり、『沈黙の螺旋理論』でのマスメディアの役割に対する誤った捉え方につながるものである。ある意味では、沈黙の螺旋理論は、マスメディアの「弾丸理論」に近い強力効果説の系譜に連なるものと言えるが、彼女のナチス時代の思想がその根底にあるとすれば問題だろう。ちなみに、E.Katzは、「沈黙の螺旋」仮説が、かつての大衆社会的前提(一方に社会的紐帯から切り離された原子化した個人を、他方に匿名的で強大な、マスメディアを含む社会統制機関を、各々対置させる社会理論的前提)に立つものであると批判している(Katz, 1981; 平林, 1987)。
エリザベート・ノエル=ノイマンは2010年3月25日に93歳で逝去した。残念ながら、エリザベートは生前、ナチス時代の反ユダヤ主義的、反民主主義的な言説について、反省や謝罪の意を表すことはなかった。
21世紀の沈黙の螺旋理論
The Legacy of Spiral of Silence Theory : An Introduction ,
沈黙の螺旋理論の伝統
by Wolfgang Donsbach, Yariv Tsfati and Charles T. Salmon
エリザベート・ノエル=ノイマンは2010年3月25日に93歳で逝去した。彼女の死は、ドイツ国内のみならず国際的にも広く知られた社会科学者、企業家、政治顧問、ジャーナリストとしての顕著なキャリアの終焉を意味するものであった。彼女はマインツ大学のコミュニケーション学教授であり、ドイツのコミュニケーション研究に実証的手法を初めて導入した人物の一人である。また、経済的に成功し、方法論的に革新的な調査およびマーケティング研究機関「アレンスバッハ世論調査所」の所長であった。彼女は戦後ドイツ初期からアデナウアー、コール、メルケルに至る歴代首相に対し、ドイツ国民の世論に関する実証データを提供してきた政治顧問でもあった。さらに、彼女は第三帝国時代にジャーナリストとしてキャリアを開始し、その後、自ら「世論調査特派員」(demoskopischer Korrespondent)と呼ぶ職務に従事した。
しかし、学術界において彼女の名は主に理論家として、特に「沈黙の螺旋」理論の提唱者として記憶されるであろう。この理論については、出版物、学会、セミナーで多くの論争が繰り広げられてきた。しかし、この理論が過去50年間において、コミュニケーション研究および政治的コミュニケーションの分野で最も影響力のある理論の一つであるという点については、最も厳しい批評家でさえ一致している。「影響力」という言葉が示す意味は多岐にわたるが、理論が影響力を持つとはどういうことか。著者らは、それを評価する基準として、認知、受容、統合、実証データ、そして実践的関連性という五つの観点があると考える。「沈黙の螺旋」理論はこれらの基準においてどのような評価を得ているのか。本論文の目的はこの問いに答えることである。
理論の影響
沈黙の螺旋理論がコミュニケーション研究分野内外でどのような影響を持っているのかを理解するために、Google ScholarでNoelle-Neumann(1974)を引用した500件の文献のサンプルを分析した。Noelle-Neumannを引用した著者の国籍、専門分野、知的背景を分析することで、この理論の影響を議論する際に有用なデータが得られる。この500件の文献には書籍、学位論文、会議論文、他分野の学術誌記事も含まれるが、142件のコミュニケーション学術誌の記事のうち、66件(47%)が実証的な定量研究であり、それ以外は定量データを含まないものであった。さらに、142件中41件(29%)が『Public Opinion Quarterly』『International Journal of Public Opinion Research』『Political Communication』などの政治コミュニケーションや世論研究に特化した学術誌に掲載されていた。多くの論文は、政治的文脈におけるメディア効果を扱っていた。
「行政的理論」(政治・社会的プロセスに影響を与える実践的価値を持つ理論)としての評価を受ける一方で、『Critical Studies in Media Communication』『Media Culture & Society』『Communication Culture & Critique』『Discourse & Society』『Quarterly Journal of Speech』といった批判的・文化的・修辞学的伝統を強調するジャーナルでも引用されている。これらの引用は、サンプル中のコミュニケーション学術誌における引用の11%を占めている。
地理的な広がり
500件の文献を引用した著者・共著者555人の所属国は32か国にわたる。沈黙の螺旋理論を引用した著者の多く(63%)は北米(555人中333人が米国の機関に所属)である。ヨーロッパの研究者は23%、オーストラリア・ニュージーランドが8%、アジアが3%、中東が2%、中南米が1%、アフリカからの引用は2件のみであった。この分布は、主要なコミュニケーション学術誌全体での著者のグローバルな分布と類似している(Lauf, 2005)。いずれにせよ、引用パターンを分析する限り、この理論は単なるドイツの理論を超えている。ドイツの機関に所属する研究者による引用は全体の約3%(17件)のみに過ぎない。
理論の認知をもたらした理由
沈黙の螺旋理論が分野内でこれほど多様な認知を受けた理由は何か。主に以下の四つの理由が挙げられる。Noelle-Neumannの出版戦略、この理論が歴史的なパラダイム変化の中で果たした役割、他の理論との関係性、そしてその挑発的な性格である。
(1) 出版戦略
Noelle-Neumannは、1970年代から80年代当時としては非常に珍しいアプローチを取った。英語を母国語としないドイツや他のヨーロッパの学者として、自国語と英語でほぼ同時に研究を発表するという手法である。これは、自国文化の枠を超えて認知を得るために不可欠な手段であった。
彼女の著書は1980年にドイツ語で初めて出版された。彼女が選んだ出版社であるPiperは、主に学術出版ではなく、幅広い知識層を対象にした非フィクション書籍を提供することで知られていた。その後、シカゴ大学で客員教授を務めた経験から、1984年には英語版がUniversity of Chicago Pressからハードカバーとして出版され、2年後にはペーパーバック版も出版された。後に11言語に翻訳されたものの、この英語版が沈黙の螺旋理論に認知をもたらしたと言える。また、彼女はその後も英語で広く読まれる雑誌に2本の論文を発表し、理論の認知度をさらに高めた(Noelle-Neumann, 1985, 1991)。
Noelle-Neumannが早期から国際的な発信を目指したのは、学術的なプロフェッショナリズムと戦略に基づくものであった。彼女は、WAPOR(世界世論調査研究協会)、AAPOR(アメリカ世論調査協会)、IAMCR(現Media and Communication Research)など、**国際的な学会で活躍し、世界中の研究者と交流していたため、英語で発表することが当然であった。**また、自身の理論の妥当性に対する強い信念から、英語での出版を戦略的に利用して注目と評価を得ようとしたのである。
(2) パラダイム変化との関係
Noelle-Neumannは、当時支配的であったメディア効果最小説のパラダイムに挑戦した。Denis McQuailは彼女の論文『強力なマスメディアの概念への回帰』が「パラダイム変化のスローガンを提供した」と述べている。また、彼女はこの変化を調査するための理論と方法論を提供した。沈黙の螺旋理論、アジェンダセッティング、培養理論などは、それぞれ異なる理論的複雑性を持ちながらも、研究者たちが直感的な仮定に反する結果に悩み、分野全体が社会的な関連性を失いかけていた時期に歓迎された理論であった。
(3) 多領域的な結合
沈黙の螺旋理論が注目された第三の理由は、対人コミュニケーションとマスコミュニケーション、マクロとミクロの分析レベル、コンテンツと受け手、社会学と心理学を結びつけた点にある。この理論は、メディアバイアスに関心を持つジャーナリズム研究者や、メディア効果に興味を持つ心理学者、個人の認知に関心を持つ認知心理学者、集団の同調に興味を持つ社会心理学者にとって有益な洞察を提供する。また、この理論は統計的証拠と実践的な公共世論調査の実施に関する実用性を兼ね備えており、選挙や熟議民主主義を研究する学者にとっても有意義である。
(4) 論争的な経歴
沈黙の螺旋理論が注目された第四の理由は、Noelle-Neumann自身の経歴にまつわる論争である。特に、彼女が1930年代から40年代にアメリカで学び、ベルリン大学で博士論文を完成させ、第二次世界大戦中に新聞『Das Reich』で働いていた時期の著作が問題視された。この論争は、彼女の理論がナチス時代の経験から生まれたものであるとの批判に基づくものであった(Bogart, 1991; Simpson, 1996)。
批判者たちは、彼女がナチスのイデオロギーを支持していたとして学術界にこの理論を無視するよう求めた。さらに、彼女の論争的な著作を公開するウェブアーカイブが設立され、ナチスのプロパガンダ活動への関与が議論の的となった。この批判は主に彼女の科学的功績ではなく、ナチス時代の行動や信念に焦点を当てたものであったが、その結果、彼女の理論に対する注目度が高まる一因となった。
批判
これまでに沈黙の螺旋理論を完全に実証的に検証した研究は一つも存在していない。この理論の構造は、マルチメソッドアプローチと長期的な設計を必要とし、高い感情的影響を持つ政治的問題を扱う必要がある。長期間にわたるパネル調査と内容分析を組み合わせ、多くの変数を統制することは、社会科学者にとって大きな挑戦である。その結果、多くの研究は理論の断片(通常は認識された世論と発言の関係)だけを検証しており、長期的な影響やメディアの役割を無視している(Salmon & Glynn, 2009)。したがって、現在得られている実証的証拠は限られている。
理論的批判は早い段階から現れ、1980年代から90年代に集中した。主に以下の4つの側面が焦点となった。
1. 参照集団と社会的ネットワークの役割
最も頻繁に引用される批判は、参照集団と社会的ネットワークの役割に関するものである。Noelle-Neumannが匿名の公衆に固執したため、社会的認識や発言において、同等かそれ以上に強い参照集団の力を見落としたとされる。この影響を比較的に検証した研究は少なく、その結果も決定的ではない(Glynn & Park, 1997; Oshagan, 1996)。理論の初期の構築において、Noelle-Neumannは公衆と参照集団の競合する役割について明確に扱っていなかった。
2. 擬似統計的感覚
批判者の中には、Noelle-Neumannの「擬似統計的感覚」という概念を疑問視し、人々が社会における意見分布を正確に認識できない理由に関する証拠や説明を提示する者もいた(Shamir、本書第13章)。実証的な「多元的無知」の結果(すなわち、真の意見分布の誤認)は、Noelle-Neumannの仮説に反するように見える(O'Gorman & Garry, 1976)。しかし、沈黙の螺旋理論のメディア効果に関する部分は、ニュースメディアの偏った報道によるこのような認識を含んでいる。Noelle-Neumannの基本仮説は、認識の正確性ではなく、人々が(a)社会環境をスクリーニングし、(b)多数意見を評価し、(c)その変化を認識するという点に重点を置いている。したがって、擬似統計的感覚の概念に関する彼女の説明が不十分であったとしても、基本的な仮定が脅かされるわけではない。
3. 孤立の恐怖
第三の批判は、Noelle-Neumannが社会的状況における人間行動の動機エンジンとして「孤立の恐怖」に集中している点である。この批判の一部は、小集団実験の証拠を公衆での行動に転用したことに基づいている。孤立の恐怖に対抗する動機(例えばコストと利益の計算による個人の利益)や、同調の理由(個人や集団への魅力や同一化)も存在し得るとされる(Salmon & Kline, 1985)。
4. 個人の特性
最後に、個人の特性や特質が孤立の恐怖を容易に上回り、発言するか沈黙するかを決定すると批判する者もいる(Lasorsa, 1991)。
これらの批判の多くは、人間の行動、特に社会的認識や対人コミュニケーションにおける因果関係の複雑な分野を分化させるという意味で、一定の妥当性を持つ。人間の行動を説明する単一の構築物は存在せず、それは沈黙の螺旋理論の仮定であろうと他の理論であろうと変わらない。多くの研究者がNoelle-Neumannの理論に挑戦しようとしたのは、彼女が理論を提示する際に大胆かつステレオタイプ的な方法を取ったことが大きな要因であった。しかし、彼女が自らの文章でしばしば必要な細部や分化を無視した一方で、この「社会的現実の複雑性の削減」(Lippmann, 1922)は、彼女の基本的なアイデアを学術界やそれ以外に広める効果をもたらした。彼女は競合する多くの理論の妥当性をしばしば認めつつも、変数の競争的な説明こそが人間の行動の理解に近づくと主張したのである。
将来の課題
沈黙の螺旋理論に対するもう一つの課題は、変化するメディア環境にある。マスコミュニケーションの環境は、1970年代初頭にNoelle-Neumannが理論を構築した際に想定していたものとは著しく異なってきている。Noelle-Neumannは、調和(すなわち、一貫した意見気候を示す統一されたマスコミュニケーション環境)を前提としていた。また、彼女は、視聴者が同じ意見を持つメディアに選択的に接触することを望まず、またその能力も持たないと仮定していた。この「望まない」という仮定は、擬似統計的感覚が環境全体(イデオロギー的なニッチではなく)をスキャンして意見気候の手がかりを探すよう視聴者を動機づけるためであり、「能力がない」という仮定は、調和したメディア環境においては、視聴者がイデオロギー的に一致した新しいメディアアウトレットを選択的に利用する選択肢を持たないためであった。
しかし、本書第8章のMoyとHussain、および第7章のMutzとSilverが指摘するように、メディア環境の二つの相互に関連する変化がこれらの仮定に挑戦している。一つ目は、保守派またはリベラル派の視聴者を対象とした非常に人気のあるイデオロギー的なテレビニュースチャンネルの発展(主にアメリカで、その他の地域でも一部見られる)であり、同様にイデオロギー的に偏った政治トークラジオやテレビの政治コメディの台頭である。二つ目は、無限の可能性を持つオンラインコミュニケーションの発展であり、主流メディアの情報を回避し、少数派を含む視聴者に「自分たちは孤立していない」という感覚や、同じ意見を持つ具体的な人物についての情報を提供する意見気候の手がかりを提供していることである(Metzger, 2009参照)。さらに、第9章のRösslerとSchulzが指摘するように、インターネットが提供する匿名性は意見表明や社会的孤立への恐怖を軽減し、Noelle-Neumannの予測の一部を時代遅れにする可能性がある。
このような断片化し、極端に分極化した新しい環境において、彼女の理論に基づく予測がどのように評価されるかは、将来の実証研究の課題である。しかし、より重要な問いは、メディア環境の変化やそれに伴う社会的プロセスを考慮して、この理論が将来の研究者世代にとって引き続き関連性を持つかどうかである。Noelle-Neumannの問い、概念、方法論は、異なる分野やサブフィールドからの研究者を引き付け続けるだろうか。
インターネット、Fox News、MSNBC、政治トークラジオが存在して久しい中で、沈黙の螺旋理論の継続的な関連性を探る一つの方法は、過去の引用傾向を検討し、特に過去10年間で引用数が減少したかどうかを調べることである。本書のサンプルによると、沈黙の螺旋理論は1984年から1993年までの間に年間平均10回引用されていた。この数値は1994年から2003年には年間約18回、2004年から2012年には年間約23回に増加している。この期間には、インターネットが広く普及し、Fox Newsが非常に人気を博し、学者が「マスコミュニケーションの終焉」を論じ始めていた時期(Chaffee & Metzger, 2001)である。過去の傾向が必ずしも未来の動向を完璧に予測するわけではないが、サンプルで示された傾向が正しければ、沈黙の螺旋理論を引用する論文の数は将来の数十年間も増加し続けるだろう。
Noelle-Neumannの初期の研究が、彼女が想定していたメディア環境からますます遠ざかっているにもかかわらず、学者たちがその研究にますます言及している事実は注目に値する。人々が他者が何を考えているのかを知りたがり、対人コミュニケーションと媒介されたコミュニケーション(必ずしも「マス」ではないにせよ)を結び付けようとし、現実または認識された少数派と多数派を調査し、人々が意見を持つかどうかだけでなく、それを公に表明する意欲があるかどうかに焦点を当て続ける限り、そして公論、同調性、公共意見が私たちを結び付ける接着剤としての役割を果たし続ける限り、学者たちは沈黙の螺旋理論が提供する概念、方法論、仮説、操作手法の豊富なツールキットを活用し続けるであろう。
“Methodological Conundrums in Spiral Of Silence Research
沈黙の螺旋研究における方法論的課題
Jörg Matthes and Andrew F. Hayes”
エリザベト・ノエル=ノイマンは、マインツ大学で世論調査員およびコミュニケーション教授として活躍しただけでなく、方法論者としても非常に優れた存在であった。彼女は沈黙の螺旋を検証するための具体的な研究方法を提供し、項目の構築や質問紙の設計において直感と確固たる姿勢を持ち、方法論的に不適切だと考えた他の研究に対して遠慮なく批判を行った。ノエル=ノイマンは、数多くの議論を呼び起こし、世論研究や政治コミュニケーションの分野に理論的・方法論的な活力を与えた多くのアイデアを残したことは疑いない。
1974年にJournal of Communicationに発表した論文以来、ノエル=ノイマンは沈黙の螺旋を検証する方法について明確かつ厳格な考えを持っていた。しかし皮肉なことに、彼女自身の研究や世界中で行われた数百もの研究にもかかわらず、沈黙の螺旋理論の全体(すべての側面や前提を含む)を包括的に実証する研究は未だに存在せず、今後も実現しないだろうと考えられる。その代わりに、沈黙の螺旋研究者たちはモデルを分割し、扱いやすい部分や仮定に分けて研究を行う傾向がある。この方法では、他の側面が不変である、または無関係、もしくは無視できると暗黙のうちに前提している。しかし、40年近くにわたる研究の中で、多種多様なデザイン、操作化、測定方法が開発されてきたにもかかわらず、これらの仮定を検証する方法についての統一見解は得られておらず、沈黙の螺旋研究にはいまだに解決困難な方法論的課題が残っている。
本論文では、これらの課題を再検討し、理論の主要な柱を方法論の観点から論じている。本論の背景を設定するために、まず沈黙の螺旋研究における主要な独立変数および従属変数の測定について批判的に検討する。それらは、社会的孤立への恐怖、意見風土の認識、そして自分の意見を表明する意欲である。次に、これまでほとんど無視されながらも未解決のままである二つの方法論的課題、すなわち世論の螺旋を継時的に検証する方法と、多国間で沈黙の螺旋をテストするデザインについて議論する。
沈黙の螺旋研究の方法論的ツールキット
世論理論、一般に「沈黙の螺旋」として知られる理論(ノエル=ノイマン, 1974, 2001)は、人々が現在の社会的および政治的トピックに関して他人の意見をどのように観察し、反応するかを説明する相互に関連した複雑な命題のパターンとして定義される。この理論は、人々が社会的孤立や排斥を恐れる本能を持っており、そのために周囲の意見風土を常に観察しているという前提に基づいている。メディアが伝える世論や日常の会話を通じて得られる情報に基づき、多くの人が共有している立場や、支持が少ない立場についての準統計的感覚を発展させる。
個人が自身の意見が少数派である、または公の意見の中で支持を失いつつあると認識した場合、彼らは自身の意見が大多数に共有されていると感じる人々と比べて、公共の場でその意見を表明する可能性が低くなる。その結果、一部の人々が自分の意見を公共の場で表明ないし沈黙すると、世論の風土は知覚された多数派の方向にさらに移動し、少数派の規模が縮小していく。このプロセスは、最終的には「ハードコア」と呼ばれる少数の人々だけが、少数派であることに関わらず意見を表明し続ける状態に至る。
このような沈黙の螺旋は、少なくとも次の2つの追加的な前提に依存している。第一に、メディア効果理論としての沈黙の螺旋理論は、一貫性のあるメディア報道だけが意見風土を伝えることができると主張している。第二に、ノエル=ノイマン(例: Noelle-Neumann, 2001)は、沈黙の螺旋が発展するためには、問題が論争的であり、道徳や倫理の問題を含んでいる必要があると論じている(議論についてはHayes & Matthes, in pressを参照)。
社会的孤立への恐怖
ノエル=ノイマンは、「ほとんどの人々は孤立することを恐れている」(1977年, p.144)と仮定しており、この仮定は特定の状況(たとえば少数派の意見を持つこと)に限定されないものである。社会的孤立への恐怖(Fear of Social Isolation, FSI)は、個人の一般的な傾向として理解できる(Hayes, Matthes, & Eveland, 2013を参照)。しかし、FSIはほとんどの沈黙の螺旋研究で言及されているものの、事実や既定のものとして扱われることが多く、さらなる実証分析を必要としないものとされてきた。他方、FSIを特定の状況での意見表明を説明する状態と解釈する研究者もいる(例:Neuwirth, Frederick, & Mayo, 2007)。
GlynnとMcLeod(1985)は異なる見解を示し、FSIを社会的な一定値や単なる状態としてではなく、人々が異なる位置に分布する連続体として扱うべきだと提案した。これに沿って、近年の研究では、FSIが人によってより顕著に現れる場合があり、それが意見風土の認識と公共での意見表明の間の先行変数または介在変数として機能する可能性があると主張されている(Petrič & Pinter, 2002; Shoemaker, Breen, & Stamper, 2000)。
しかし、方法論的観点から見ると、これらの多くの操作化は妥当性や信頼性の欠如が批判されている。いくつかの研究では、単一項目のみを用いており、信頼性評価が不可能である(Huang, 2005; Moy, Domke, & Stamm, 2001)。他の尺度(例:Ho & McLeod, 2008; Scheufele, Shanahan, & Lee, 2001)は基準汚染の問題が指摘されており、FSIが予測しようとする基準(すなわち、少数派の意見を公共の場で話すことによる孤立への恐怖)自体を測定している可能性があるという。また、より妥当な項目を使用している研究でも、測定機器の信頼性や妥当性といった心理測定特性を説得力を持って示していない、あるいはその試みすらしていない場合があるとされている(例:Scheufele et al., 2001)。
明らかなように、沈黙の螺旋研究にはFSIを測定する標準化され信頼性があり妥当性を持つ尺度が欠けている。この問題の一因は、FSIがこれらの研究における主要な独立変数ではなかったためである可能性がある。もう一つの理由として、Willnat, Lee, and Detenber(2002)が述べているように、研究がしばしばFSIの明確な概念化および操作的定義を欠いていることが挙げられる。
この問題に対処するために、Hayes et al.(2013)は最近、FSIを測定するための5項目の尺度を提案した(例:「私は所属しているグループに馴染むことが重要だと感じる」)。この研究では、FSIのレベルが異なる人々は、他者が何を考えているかについての情報をメディア環境でどの程度注意を払うかにも違いがあることを示しており、これは沈黙の螺旋理論の基本的だがこれまで未検証だった予測の一つである。Hayesらは、8カ国のデータを用いて、この尺度の心理測定特性に関する強力な証拠を報告しているが、この尺度を完全に検証するにはさらなる実証データが必要である。特に、意見風土と意見表明の関係を調整するなど、FSIが世論進化のダイナミクスにおいて果たす他の役割を探求する際には、さらなる研究が求められる。
意見の風土
理論の第二の重要な側面として、個人には「社会的環境における意見の分布や意見の動向のイメージを形成する」準統計的感覚が備わっていると仮定されている(ノエル=ノイマン, 1974, p.45)。この準統計的感覚は主にマスメディアによって刺激され、とりわけ意見気候に関して一貫したメディア・メッセージが存在する状況下で強く影響を受ける。理論の原初的な概念によれば、この準統計的感覚は意識的な思考には到達しないものである。そのため、ノエル=ノイマン(2001, p.60)は、回答者が自分の意見が多数派の意見と一致しているかどうかを問う調査手法だけでは、一般的に特に価値のある結果を得ることはできないと繰り返し強調している。ここで重要なのは、どの意見が実際に社会の中で支持を得ているか、または失いつつあるのかという点であり、個人がこのプロセスを意識的に認識しているかどうかではない。
しかし、ほとんどの研究では、意見風土に対する人々の主観的な感覚を評価してきた。これは、意見風土の認識が真の意見分布ではなく、人々が意見を表明する意欲を形作るという仮定を反映している。たとえば、Shamir(1993)は、回答者に特定の政治的立場を支持または反対する人々の割合を推定させた。他の研究では、準拠集団の意見を意見表明の予測因子として用いた(Moy et al., 2001)。また、意見風土の認識をマスメディアが伝えるもの(Matera & Salwen, 1992)、広義の「一般大衆」が信じていること(Lasorsa, 1991)、または最近の会話相手の意見(Scheufele et al., 2001)として測定した研究もある。さらに、多くの場合、研究者は複数の準拠集団に関する自己と他者の一致を同時に測定する(例:Moy et al., 2001)。これらの質問への回答は、回答者自身の意見と組み合わされ、多数派または少数派の意見と一致しているかどうかの操作化として使用されることが多い。
しかし、一般大衆がどう考えているかに関する人々の信念を測定するこのような質問は、多数派または少数派への所属を示す方法論的に健全な指標と言えるだろうか。単一項目を使用する場合に信頼性情報が欠如していることに加え、意見風土の認識と自分の意見という2つの単一項目を組み合わせることで、粗い順序変数しか得られないという問題もある。さらに、これらの操作化は、沈黙の螺旋理論の重要な前提、すなわち準統計的感覚がマスメディアによって刺激されるという点を無視する傾向がある。
沈黙の螺旋理論の原初的な概念では、マスメディアは意見風土に関する情報の主な情報源であるとされている。この情報に基づき、人々は、広範かつ一貫したメディアが報じる内容に反する意見を公に表明することにどれだけ快適さを感じるかを判断する。しかし、ニュース・コンテンツへの接触と意見風土に関する準統計的感覚との間に関連があることを示すためのデータを収集した研究は非常に少ない(例:Eveland, McLeod, & Signorielli, 1995)。ノエル=ノイマン自身は、内容分析データを収集したが、それは個人レベルではなく集計レベルであった。他の研究者は意見風土の認識とメディア利用を相関させている(Neuwirth & Frederick, 2004)。これらの研究(主に横断的デザイン)は、被験者が接触したニュースコンテンツと意見風土に関する準統計的感覚の間に関連があることを立証するには不十分である。
意見の表明
人々の意見表明の意欲をどのように操作化するかについては、多くの議論が存在する。ノエル=ノイマンは当初、「列車テスト」として知られる列車内での乗客との会話を用いた。この方法は、列車移動がすべての国や文化で一般的ではないため、バスの車内(Shamir, 1997)、飛行機の機内(Lasorsa, 1991)、社交の場(Moy et al., 2001; Scheufele et al., 2001)、記者とのインタビュー(Shamir, 1997)、医師の待合室(Petrič & Pinter, 2002)、結婚式(Willnat et al., 2002)、または公的な会議(Gonzenbach & Stevenson, 1994)といった、仮定された公共状況に適応されてきた。
これらの方法は直感的で洗練されているが、その仮定的性質について批判がある(Glynn, Hayes, & Shanahan, 1997; Hayes, Uldall, & Glynn, 2010; Scheufele et al., 2001)。沈黙の螺旋理論が、意見風土が社会的孤立の現実的な脅威を介して意見表明に影響を与えると予測する場合、仮定的な会話の場と実際の会話の場では、このプロセスに対する影響の受けやすさが異なる可能性が高い(Scheufele et al., 2001)。現時点の文献では、仮定的な測定が実際の公共状況における人々の行動をどの程度正確に捉えることができるかを示すことがまだ必要とされている。
したがって、理論のこの側面をより厳密に検証するには、実際の会話の場を用いて意見表明の機会を提供し、その際に意見風土を実験的に変化させるか、または事後に測定する必要がある。このような場では、意見表明の「公共性」、被験者の匿名性、聴衆の規模、聴衆が公然と反対を示す能力などを変化させることができる。40年にわたる研究にもかかわらず、このようなデザインは理論を検証するために依然として緊急に必要である(最近の例外としてHayes et al., 2010を参照)。
さらに、これらのさまざまな意見表明の意欲の測定方法について、その信頼性と構成概念妥当性を確立するためのさらなる努力が求められている。
「沈黙の螺旋」における「螺旋」の観察
沈黙の螺旋理論によれば、支配的な陣営は時間の経過とともにより支配的かつ声高になる一方で、敗北しつつある陣営は次第に沈黙していく。この時間的要素は、ScheufeleとMoy(2000, p.11)が「世論の形成、変化、強化のプロセス」と呼び、「時間の経過とともに、意見風土に対する認識の変化が人々の少数派意見を表明する意欲に影響を与える」(p.10)と述べているように、沈黙の螺旋を検証する研究設計において極めて重要である。しかしながら、これまでの研究では、この時間的要素がほとんど無視されてきた。
理論的には、意見風土と意見表明の関係について、以下の4つの明確で相互に関連する予測が立てられる。第一に、意見風土の認識と意見表明は相関があるべきである。すなわち、時点1で自分が少数派だと感じている人は、多数派にいると感じている人と比べて、時点1で意見を表明する可能性が低い。この静的なアイデアは「社会的同調仮説」と呼ばれる。第二に、このプロセスは時間とともに展開するため、意見風土の変化は意見表明の意欲の変化を引き起こすべきである。つまり、時間の経過とともに意見風土がより敵対的になる場合、個人が意見を公に表明する意欲も時間の経過とともに減少する。この仮説は「変化仮説」と呼ばれる。第三に、理論の核心にあるのは、「ある人が意見を表明し、他の人が沈黙する傾向が螺旋的なプロセスを引き起こし、これが次第に一つの意見を支配的なものとして確立する」という考えである(Noelle-Neumann, 1974, p.44)。このプロセスは、世論調査などを通じて意見風土を反映するマスメディアへの継続的な接触や、身近な環境の観察によって引き起こされる。「ある陣営の支持者は自分の意見を表明する意欲があり、これが観察者に実際以上に強い印象を与える。これがさらに他の人々に意見表明を促し、一方で反対派は次第に沈黙していく」(Noelle-Neumann, 1977, p.149)。つまり、一人の意見表明がその後の意見風土を変え、結果として支配的な意見がさらに強化される。この仮説は「強化螺旋仮説」と呼ばれる。第四に、最も挑戦的な仮定として、ノエル=ノイマンは、このプロセスが進行して最終的に行き止まりや麻痺状態に至ると理論化している。この状態では「ハードコア」だけが残り、これ以上の動的な変化は観察されなくなる。この仮説は「麻痺仮説」と呼ばれる。
ノエル=ノイマン(1974, 2001)は、これらのアイデアをトレンド調査データを用いて検証し、意見風土に応じて特定の立場を支持する人々の数が増減することを示した。このような集計デザインは、主要な変数の増減を直感的に理解するための手段を提供する。しかし、生態学的誤謬の問題により、個人レベルでの螺旋的プロセスについて結論を導き出すことはできない。そのため、こうしたデータは理論の動的側面を扱うには不適切である。
さらに深刻な問題として、沈黙の螺旋に関する研究の大多数は横断的調査データを使用しており、このようなデータでは静的な社会的同調仮説を検証することしかできず、他の3つの仮説には対応できない(Neuwirth et al., 2007)。そのため、「恐怖(孤立への)や多数派意見の判断が、議論の変化や同調に基づく隠蔽にどのように影響を与えるかを探るには、パネルデザインが明らかに必要である」(p.466, Gonzenbach & Stephenson, 1994も同様)。
しかしながら、沈黙の螺旋に関する数少ないパネル研究も、理論が提唱する意見動態を十分に検証していない。例えば、McDonald, Glynn, Kim, and Ostman(2001)は、1948年に実施された4波のパネル調査の二次分析を行い、各波ごとに意見風土が候補者の選好に及ぼす影響を推定した。しかし、これはノエル=ノイマンの集計レベルの変化モデルと同様に、風土認知や意見表明の個人レベルの変化については何も示していない。また、この手法は粗雑で不正確な前提に基づいており、誤った結論を導くことが多い。
これらを総合すると、沈黙の螺旋研究で採用されたデザインは、時間をかけた螺旋プロセス(変化、強化螺旋、麻痺仮説)を検証するには不十分である。また、単一項目の使用や測定の時間的不変性(Pitts, West, & Tein, 1996)への対応が不足している。理論的にも方法論的にも魅力的で課題の多い動的側面、特に「強化螺旋仮説」と「麻痺仮説」を検証するには、少なくとも3波のパネルデータが必要である。そのようなデータを用いた潜在成長モデル(例:Selig & Preacher, 2009)は有力な手法である。しかし、時間間隔の選択が意見螺旋の観察可能性に大きな影響を与える点が深刻な問題である。Selig & Preacher(2009)が指摘するように、間隔が短すぎて動的プロセスが始まらない場合や、長すぎて観察可能な効果が消えてしまう場合がある。この問題を解決するためには、異なる時間間隔を設定したサブセットを含む多波設計を用いた研究が有効である。また、多波実験的設定でこれらの動態を検証すれば、個人間および個人内での時間的変動をより詳細に分析できる可能性がある。
理論の普遍性の検証
沈黙の螺旋理論研究におけるもう一つの盲点として、理論の異文化間適用可能性は「ほとんど未解明のままである」(Scheufele & Moy, 2000, p.17; Matthes et al., 2012を参照)。理論の予測を異文化間で一般化しようと試みた少数の研究は、主にアジア諸国と西洋諸国の比較に基づいている。アジアのような集団主義文化が集団の調和を重視し、西洋文化が個人の強さを重視するという仮定に基づき、沈黙の螺旋プロセスは集団主義文化でより顕著であるべきだと一般的に仮定されている。Lee, Detenber, Willnat, Aday, and Graf(2004)は、同じ問題について回答者に尋ねたところ、シンガポールでは沈黙の螺旋効果が見られたが、アメリカでは見られなかった。Huang(2005)の研究でも、異なる問題(アメリカではソマリアへの介入、台湾では大統領選挙の時期)を用いて同様の結果が確認された。
しかし、方法論的観点から見ると、個人主義文化で効果が見られなかったのは、異なる国で異なる問題が使用されたためかもしれない。なぜなら、それらの問題は比較可能ではなく、または一つの国で理論を検証するための要件を満たしていない可能性がある(Matthes et al., 2012)。逆に、同じ問題が使用された場合でも、国ごとに意味や文脈が根本的に異なるため、結果が再現されないこともあり得る。このため、理論を異なる国で検証するには、主要な変数が概念化および操作化の点で合理的に類似している必要がある。しかし、この戦略には「研究のパラドックス」が伴う可能性がある(Matthes et al., 2012)。一方で、国ごとの特異性に対応するために異なる指標を使用することは理にかなっているように思えるが、他方で異なる指標を使用すると、研究間での結果の比較が困難、あるいは不可能になる。また、ある国では道徳的または議論の余地がある問題が、別の国では完全に非論争的である場合もある。
要するに、沈黙の螺旋理論の研究者が文脈依存の測定方法を用いる限り、どのような有意または非有意の結果も、その特定の文脈の特性や適切性に起因する可能性がある。これにより、研究者は研究の結果に応じて事後的に自らの決定を正当化する傾向に陥る可能性がある。
この課題への一つの解決策として、Matthes et al.(2012)は最近、状況非依存の測定方法、たとえばパーソナリティ特性を用いることを提案している。この戦略の主な利点は、特定の国や文化内で文脈を超えて集約できる点にある。パーソナリティ特性は状況に依存しないとされており、個人の一般的傾向も同様である。そのため、特定の問題や状況に依存する特異性が、沈黙の螺旋の背後にある関係に及ぼす影響は小さいと考えられる。Matthesらは、次の2つのパーソナリティ特性が沈黙の螺旋の基本的メカニズムを反映していると主張している:(a) 孤立への恐怖(FSI)。これは螺旋を動かす原動力である(Hayes et al., 2013)、(b) 自己検閲の意欲(WTSC)。これは、少数派の見解を公に表明することへの意欲である(Hayes et al., 2005)。もし、ある人々が一般的に、かつ状況を問わず、他の人々よりも社会的孤立を恐れる傾向があるならば、これらの人々は敵対的な意見環境に直面した際に、一般的に、かつ状況を問わず意見を自己検閲する傾向も強いはずである。
Hayesら(2013)およびMatthesら(2012)は、スペイン語、ロシア語、韓国語、ドイツ語、フランス語、中国語の両測定尺度を開発し、同じサンプリング会社、サンプルサイズ、データ収集手続きで9か国からサンプルを収集した。FSIとWTSCの間に8か国で正の相関が見られたことは、沈黙の螺旋プロセスの基本的な異文化間一般性を示唆している。
もちろん、このような性格的アプローチは、単一の国で沈黙の螺旋理論を完全に検証する理想的かつ本格的な手法とは見なされない。また、理論の動的な側面をモデル化するのにも適していない。しかし、理論の基本要素を異なる国で検証する意味のある方法である。それでもなお、孤立への恐怖と自己検閲の意欲との関係が、文化的、政治的、社会的要因に依存するかどうかを理解するためには、さらなるデータが必要である。
結論
沈黙の螺旋理論における主要な独立変数と従属変数の操作化は、実証研究の数と同じくらい多様であり、理論の中心的な予測を検証する方法や測定手法について合意が欠けていることを反映している。さらに、ノエル=ノイマンの複雑な予測を注意深く検討すると、蓄積された実証的証拠は提唱されたメカニズムと一貫しておらず、せいぜい結論が不確定であることがわかる。また、ノエル=ノイマン自身の研究デザインや測定方法と、彼女の1974年のJournal of Communicationの論文を基に他の研究者が提案した方法との間には方法論的なギャップがあるように見受けられる。
もし理論を文字通り受け取るのであれば、理論の予測に敏感な代替的かつ補完的な方法論が強く求められる。特に、縦断的研究(個人レベルでの内容分析データと組み合わせたもの)や観察的実験は、螺旋プロセスについて重要な洞察を提供し、理論の主要な予測を因果的に検証する機会を提供するであろう。研究者は、測定手法の信頼性と妥当性を確立するためにさらに努力し、特にデータ分析に関して社会科学の最新の方法論に対してもっと受容的になる必要がある。
しかし、理論を文字通り受け取るべきなのか? 本書全体で明らかにされているように、沈黙の螺旋理論は関連する予測と条件のセットで構成されている。それが包括的に証明されたことはなく、恐らく今後も証明されることはないだろう。社会的孤立への恐怖を持つ人が道徳的に議論を呼ぶ問題の意見風土に敏感になり、それが多数派の合図に影響されやすくさせ、結果としてこうした人々が公共の場で意見を抑制する傾向を強め、螺旋プロセスを開始し、将来の意見風土を再び変化させ、このプロセスが少数の「強硬派」だけが残るまで続くという一連の予測がある。しかし、このパズルの1つのピースが無視されたり、誤っていたりすると、全体像が歪む可能性がある。
さらに、メディア報道が一致するかどうか、オンラインおよびオフラインでの多様なニュースソースに人々が触れるかどうか、意見風土が形成されるかどうか、議論の対象が感情的かどうか、そして3波のパネル研究を設計する際にこれらすべてを観察する適切な時点がいつであるかを予測するのは非常に困難である。このように、条件や仮定が多すぎるため、沈黙の螺旋理論を厳密に検証するのはほぼ不可能である。どのような反証的な結果であっても、理論の条件の1つが満たされなかった、設計が適切でなかった、あるいは別の要因が働いたと説明する余地が常に残るためである。このことは、理論を反証不可能なものにしている。
したがって、沈黙の螺旋理論を、ノエル=ノイマンの原初のアイデアに忠実に基づいて研究デザインに適用すべき一連の予測として捉えるべきではないと主張する。むしろ、この理論は、世論の動態における興味深い側面を記述するのに最適な、便利な理論的ツールであると考えられる。理論のいくつかの側面を検証(あるいは探求)することは、世界中で世論研究に新しいアイデアをもたらし、世論研究における方法論的課題への感受性を高め、人々の意見風土に対する意見表明、態度、投票行動への影響を理解する助けとなってきた。
沈黙の螺旋現象を理解し、世論研究を進展させるために、理論の古典的な独立変数および従属変数の単一の操作化や基準デザインを求める必要はない。また、理論のすべての側面や予測を機械的に採用する必要もない。しかし、慎重に設計された複数項目測定手法、内部的および外部的に妥当な実験手続き、そして個人レベルで時間をかけて展開する動態とプロセスに対する感受性が必要である。
オンライン環境における世論表明 : パトリック・レスラー、アンネ・シュルツ
オンラインメディアは、インターネット利用者に対し、他者が何を考え、メディアコンテンツにどのように反応し、自身の身近な環境において何を重要だと考えているかについて、ますます多くの情報を提供している。これらの認識は、伝統的な情報源を補完しつつ、オンライン利用者が世論の雰囲気を評価する際の判断に影響を与える可能性が高いと言える。同時に、利用者自身も、かつてないほど自らの意見を表明する機会を得ており、その意見が読者や視聴者の世論の雰囲気に対する認識に影響を与える場合もある。
しかしながら、オンライン環境はその急速な情報量の増加だけでなく、オフラインのコミュニケーションとは異なる特有の特徴を示している。たとえば、非同期的な相互作用、他者の匿名性、さらには自分自身のアイデンティティを完全に隠す可能性などである。これらの特徴は、個人の行動、すなわち意見を表明する意欲に影響を及ぼし、沈黙の螺旋理論(SoST)の基本的仮定に疑問を投げかける可能性がある。
ノエル=ノイマンが1970年代初頭にその理論を提唱したとき、今日のようなインターネットは想像もつかなかった。しかし、この20年間でのインターネットの驚異的な普及は、世界中の数十億人の人々の日常生活の一部となった。メディア研究者として、これらの発展によりメディアの影響に関する理論を修正すべきか、それとも現在の社会で観察される現象を依然として説明できるのかという問いに直面している(例:Holbert, Garrett, Gleason, 2010; Rössler, 2007, p. 91)。
ユンとパーク(2011)によれば、後者は有意義な試みとなる可能性がある。「実際には、オフラインコミュニケーションがどこで終わり、オンラインコミュニケーションがどこで始まるのかは非常に不明瞭である。伝統的メディアとオンラインメディアの融合は、伝統的なマスコミュニケーション理論が、多くの種類のコンピュータ媒介コミュニケーション(CMC)において依然として有効であることを示唆している」(p. 202)。
これまで、CMCにおける沈黙の螺旋理論の基本仮定を検証した研究者は限られている。たとえば、オンラインチャットルームでの発言意欲を実験的に調査したり(Wanta … Dimitrova, 2000)、対面の議論とCMCでの議論を比較分析した研究(Ho … McLeod, 2008; McDevitt, Kiousis, … Wahl-Jorgensen, 2003)がある。また、オンラインのみの環境で匿名性を実験的に操作した研究も存在する(Yun … Park, 2011)。
これらの実証研究とは対照的に、本論文では理論的観点から議論を展開している。筆者は、特にメディア心理学の最新研究を含む幅広い分野の証拠を用いて、新しいメディア環境の使用における最近の変化を背景に、沈黙の螺旋理論の中心的仮定の堅牢性を論じる。特に、コンピュータ媒介環境に特有の条件(匿名性や非識別性など)が、ノエル=ノイマンの理論と矛盾するのか、それとも支持するのかについて考察する。
沈黙の螺旋理論の理論的枠組みとしての多層的論理
ノエル=ノイマンの沈黙の螺旋理論(SoST)は、個人プロセスと社会的プロセスの双方に関わる理論であるため、多層的な理論として概念化される必要がある。このため、ドイツの社会学者ハルトムート・エッサー(1999年)が提唱した多層的論理に基づいて説明されるべきである。
エッサーの主張に従い、パンとマクロード(1991年)が以前に述べた4種類の影響、すなわち「マクロからマクロ」「マクロからミクロ」「ミクロからミクロ」「ミクロからマクロ」を区別する。筆者は、この枠組みを基に、沈黙の螺旋理論の基本要素をエッサーのアプローチの修正版としてモデル化することを提案している。この適用により、インターネットコミュニケーションによって変化した可能性のある沈黙の螺旋理論内のいくつかのプロセスを、より詳細に検討できる視点が得られる。最も重要な変化として、筆者は、世論の雰囲気に対する人々の認識におけるグループの影響を分析するためのメゾ(中間)レベルの導入を提案する。
エッサー(1999)の社会学的説明モデルに基づく考察
エッサー(1999)の社会学的説明モデルは、「集団現象I」から始まる。この文脈では、大衆メディアのトーンが、社会内の個人が世論の雰囲気をどのように認識するか、さらには個人が属する社会的集団内での認識にも影響を与える(ノエル=ノイマン, 1993)。エッサーが「状況の論理」(1;マクロからミクロ)と呼ぶものは、沈黙の螺旋理論(SoST)の「準統計的感覚」に近いものである。個人は常に、多数派が何を考えているのか、また一方で少数派に支持されている意見が何であるかを評価している。そのために、彼らは大衆メディアのメッセージや自らの社会的環境での個人的なコミュニケーションを観察する(Scheufele, 2008, p. 348)。ノエル=ノイマンは、大衆メディアの報道が一貫性、累積性、遍在性を持つため、この認識プロセスにおいて常に重要な役割を果たしてきたと主張している(インターネット時代におけるSoSTの論理に関するさらなる考察はSchulz & Roessler, 2012を参照)。
個人は自分の意見を社会の多数派の意見と比較し、この比較の結果としての行動は、エッサーの用語では「選択の論理」(2;ミクロからミクロ)で説明される。自分の意見が多数派の意見と一致していると考える人々は行動を起こし、その意見を公に表明する。一方、自分の意見が多数派の意見と不一致であると感じる個人は、自分の意見を公に表明することで社会環境から制裁を受ける可能性に直面する。ノエル=ノイマンによれば、人間は社会的な存在であり、社会からの孤立を恐れる性質を持っている。自分の意見が「間違っている」と見なされることで排除の脅威にさらされる場合、彼らは沈黙を選択する。
時間が経つにつれて、この結果はエッサーのモデルにおける「集計の論理」(3;ミクロからマクロ)によって説明される。仮定された多数派の意見はますます強化され、一方で「沈黙の螺旋」という用語が示すように、対立する意見は公共の場でほとんど見えなくなる可能性がある。このプロセスの結果として、エッサーの「集団現象II」、すなわちノエル=ノイマンの意味での世論、また沈黙の螺旋理論のダイナミクスに従う可能性のある社会集団のメゾ(中間)レベルにおける意見形成プロセスが生じる。
オフラインおよびオンライン環境における制裁の予期
沈黙の螺旋理論(SoST)において、個人の社会環境は、彼らが公共の場で行動することによって形成される。ノエル=ノイマン(1993, p. 19)は、個人の社会生活の重要な部分を構成する家族や友人関係といったプライベートな場面にはあまり関心を示していない。これらは世論形成において大きな影響を持たないからである。彼女の関心は、主に匿名性のある参加者から構成される社会環境に向けられており、公共空間での出会いを通じて形成される。その場では、意見を述べることが他者に影響を及ぼす可能性があり、話者は特定され、その場で他者の反応に直面することになる(p. 81)。
ノエル=ノイマンもその批評家たちも、この匿名性を持つ社会環境が、認識される世論の雰囲気に影響を与える以上に、直接的に個人の孤立の恐怖に影響を及ぼすと提案したことはない。非仮想的な文脈におけるSoSTを見ると、これは妥当な主張である。個人がオフラインの公共空間で非同調的な意見を述べる場合、その場から逃れる機会がないため、制裁を必然的に予期しなければならない。このため、社会環境が個人の制裁予期と孤立の恐怖に及ぼす影響は不変であり、それは個人の認識する世論の雰囲気にのみ依存する。社会環境がどのように構成されているかに関わらず、それは少数派に属するすべての個人に同じ影響を及ぼす。すなわち、制裁を予期しなければならず、実際に制裁が行われなくても、その潜在的な孤立の脅威によって個人は沈黙を余儀なくされる(p. 77)。
しかし、日常のコミュニケーション環境の基本的な変化の中で、サイバースペースでは社会環境がもはや電車の中での偶然の出会いのような匿名の公共空間を構成するものではなくなった。インターネット、とりわけソーシャルメディアは、新たな社会環境の形成を可能にした。これらは個人のプライベートな設定の外部に存在し、通常の友情、対面でのやりとり、共有された物理的空間といったメカニズムが適用されなくても安定して存続する。これにより、オフライン環境では不可避と考えられていた制裁の予期が、これらのオンライン環境では少なくとも部分的に消える可能性があると推測される。
McDevittら(2003, p. 458)による議論に基づき、個人はその社会環境から制裁を受ける可能性を容易に見積もることができると考えられる。第一に、多くの制裁は他者の物理的な存在に依存すると想定される。しかし、Short, Williams, Christie(1976, p. 65)が「社会的存在」の概念で証明したように、物理的存在(例:顔の表情、姿勢など)は媒介された環境では大幅に減少する。第二に、McDevittら(2003)は、規範的影響は非言語的に伝えられることが多く(例:アイコンタクト、ジェスチャーなど)、これらの信号はコンピュータ媒介コミュニケーション(CMC)では適切に伝えられないことを指摘している。第三に、CMCには通常、コミュニケーション相手の地位に関する手がかりが欠如しており(Kiesler, Siegel, McGuire, 1984)、これらの手がかりがない場合、グループの階層は明確でなくなり、社会的影響の源泉としての意味を失う可能性がある(Ho and McLeod, 2008)。
これらの結論が妥当であると仮定すると、SoSTの中心的な前提が疑問視され、理論全体に一定の挑戦が生じることになる。すなわち、社会環境からの制裁を予期しない場合、個人は世間の認識された多数派意見に対応していようといまいと、自由に意見を表明する機会を持つことになる。この場合、個人は抑制のない、あるいは反規範的な行動を示し、ノエル=ノイマンの理論の基本的な仮定に反することになる。このような行動は彼女の理論において病理的な例外と見なされていた。
しかし結論を急ぐ前に、ここで述べた「制裁の予期」という概念をさらに明確にする必要がある。この追加要因は、異なるコミュニケーション状況における制裁の可能性を個人がどのように主観的に見積もるかを説明するものである。ノエル=ノイマン自身は「社会から排除される、または地位を失うという脅威」(1993, p. 179)について述べているに過ぎず、それは個人が自分が少数派であると気づいた際に自動的に経験されるものとされていた。筆者は、個人が制裁を予期するかどうかは、コミュニケーション空間の一般的な特徴や質といった状況的要因に大きく依存すると主張する。
オンライン環境における世論表明の程度に関連する影響として特に重要であると考えられるのは、認識される匿名性である。このアイデアを検証するために、オンラインおよびオフライン環境における匿名性の効果に関する現在の研究成果を利用したい。本章で述べるように、SIDEモデル(脱個人化の社会的アイデンティティモデル)に基づく研究がこの点に関して重要な洞察を提供してきた。YunとPark(2011, p. 216)も、SoSTとSIDEモデルの関連性について言及しており、「…本研究の行動的測定結果(オンラインフォーラムでの投稿行動)はSIDEモデルによって十分に説明される。オンラインフォーラムメッセージの整合性・不整合性の文脈におけるこのモデルのさらなる研究は、世論形成におけるメッセージ投稿行動の心理的プロセスをより深く理解する助けとなるだろう」と述べている。筆者はこの問題をさらに詳細に検討し、オンライン環境の特殊な特徴、すなわち匿名性と識別可能性(SIDE研究における2つの中心的次元)が、個人の制裁予期および意見表明の意欲にどのように影響するかを推論できる理論モデルを提示する。
オフラインおよびオンライン環境における匿名性と識別可能性
以下で詳述するSIDEモデルによれば、個人が他者について知っていること(匿名性)と、個人が自らを他者にどの程度さらしているか(識別可能性)を区別する必要がある(例:Reicher, Spears, Postmes, 1995)。これら二つの概念は、同一の次元の両極ではなく、互いに独立した二つの次元として理解されるべきである。この区別は特にオンライン環境において重要であるが、オフライン環境では次の二つの主張が妥当であると考えられる。
第一に、これらの独立した次元は、ほとんど常に一致すると仮定できる(Mayer-Uellner, 2003, p. 42)。例えば、通りでお互いを知らない二人が出会う場合、匿名性と識別可能性は互いに相殺される。一方の人物が自分をますます識別可能にする一方で、もう一方も自分の匿名性を失う(例:顔や体型の認識を通じて)。
第二に、関連する点として、オフライン環境において完全に匿名または全く識別不能な人物を見つけることはほぼ不可能である。二人の人物が出会うとき、視覚的な特徴が即座にその人物のアイデンティティに関する手がかりを提供する。仮にその人物がマスクを使って顔を隠しても、声や体型などを通じて性別などを識別できる場合がある。
オンライン環境では、これらの主張はもはや適用されない。第一に、ある仮想空間の特徴に応じて、一方の人物が他方よりも識別可能である場合がある。このため、特定の人物が他者に対して識別可能ではない一方で、他者は全く匿名ではない(またはその逆)という状況が生じ得る。このことから、オンライン環境では単一の次元としては扱えない理由が生じる。つまり、一方が識別可能である場合でも、他者も同様に識別可能であるとは限らない。
第二に、オンライン環境では完全な匿名性または完全な識別不可能性が観察される場合もある。したがって、オンライン環境のコミュニケーション空間を以下の四つのタイプに区別することができる。
- 高い匿名性と高い識別可能性(QI)
- 高い匿名性と低い識別可能性(QII)
- 低い匿名性と低い識別可能性(QIII)
- 低い匿名性と高い識別可能性(QIV)
沈黙の螺旋理論(SoST)における匿名性と識別可能性の重要性に関する理論に基づいた仮説を形成するため、オンライン環境でこれらの二つの次元が個人の制裁予期にどのように影響を与えるかに関する社会心理学の研究の知見を参照する。
脱個人化モデルとSIDEモデル
匿名性のあるコミュニケーション環境が集団内外での反規範的行動とどのように関連するかについては、攻撃性に関する研究から多くの証拠が得られている。一方で、Zimbardo(1969)やDiener(1979)によって代表される伝統的および現代的な脱個人化モデルは、匿名性や没入といった要因が「自己意識の喪失を引き起こし、それにより行動の制御を失わせる」と仮定している(Reicher et al., 1995, p. 161)。
Haney, Banks, Zimbardo(1973)が行った古典的なスタンフォード監獄実験では、この仮説が説得力を持って示された。監守には制服が与えられ、囚人には番号が付けられたことで匿名の環境が作り出され、それが脱個人化と攻撃的行動の観察結果を説明する助けとなった。
しかしながら、このスタンフォード監獄実験がいくつかの理由で批判を受けたように、脱個人化研究全般も異論に直面した(例:Reicher et al., 1995, pp. 167–175)。他の研究では、「媒介された相互作用は多くの場合匿名でありながらも、しばしば友好的で非攻撃的な議論を含む」(McDevitt et al., 2003, p. 458)ことが示されている。このため、個人主義的および反集団的なアプローチに反する形で、自己意識の社会的性質と集団行動との関係に明確に焦点を当てた第二の研究路線が発展した(Reicher et al., 1995, p. 176)。
この研究路線の重要な成果の一つが、脱個人化の社会的アイデンティティモデル(SIDEモデル)である。このモデルは基本的に、匿名性が自己意識の喪失やそれに続く攻撃的行動を引き起こすのではなく、むしろ集団規範への行動的な指向性を高めることを提案している。このモデルは1995年にReicherらによって開発され、それ以降、特にコンピュータ媒介環境で検証されてきた(例:Postmes, Spears, Lea, Reicher, 2000; Spears, Postmes, Lea, Watt, 2001)。
このモデルは、社会的アイデンティティ理論(SIT;Tajfel, 1978)および社会的カテゴリー化理論(SCT;Turner, 1987)に基づいており、二つの要素から構成されている。一つは、匿名性の概念に関する認知的次元であり、もう一つは識別可能性の影響に関する戦略的次元である。
SIDEモデルの認知的次元
このモデルは、人間の自己概念が「個人的アイデンティティ」と「社会的アイデンティティ」という二つの主要なサブシステムから構成されているという仮定から始まる。これら両者は、個人が自らを定義するための概念体系を提供する認知的構造である(Gergen, 1971, p. 23)。個人的アイデンティティは、個人固有の特徴や典型的な行動を指し、「能力の感覚、身体的特徴、他者との関係の取り方、心理的特性、知的関心、個人的趣味など」(Turner, 1982, p. 18)を含む。一方、社会的アイデンティティは、個人が自覚しているすべての集団への所属から構成される。
特定の状況下では、個人的アイデンティティが社会的アイデンティティに切り替わるとされている。この現象は特に集団間の文脈で起こりやすいが、この切り替えが実際にどのように機能するかは未だ完全には理解されていない(Turner, 1982, p. 21)。社会的アイデンティティが顕著になると、個人はその特定の状況で自分が所属すると感じる集団の規範に従って行動を取るようになる。典型的な集団メンバーが行動の例となる(Brown, 2001, p. 557)。これにより、個人的アイデンティティが顕著であれば現れないような、通常とは異なる行動を取ることもあれば、通常の行動を控えることもある。
この行動の動機は、社会的アイデンティティ理論によって説明される。「自己カテゴリーは肯定的に評価される傾向があり、その状態を維持するための動機的圧力が存在する」(Turner, 1987, p. 57)。人間はできる限り肯定的な自己概念を達成することを目指し、集団間の肯定的な差異を確立することによってそれを達成する(Tajfel, 1978, p. 83)。この状態は、肯定的な意味合いを持つ集団への所属を目指すことで達成される。集団比較の継続的なプロセスにより、個人はどの集団が肯定的な意味を持ち、どの集団がそうでないかを判断できる。この所属を維持するためには、その集団で有効とされる規範を尊重しなければならない。
沈黙の螺旋理論(SoST)に関して言えば、少数派の一員であると認識される場合に自身の意見を隠す傾向は、SIDEモデルにおける特定の集団の規範を採用する動機に似ている。それは、特定の仲間から排除されることへの恐れである。ノエル=ノイマンの理論では、この仲間は社会全体を指すが、SIDEモデルでは特定の集団の所属を失いたくないという動機が中心となる。SIDEモデルでは、同調は多数派の圧力ではなく、単純な役割の受容によって達成されるが(Price, Nir, Cappella, 2006, p. 51)、結果として社会そのものが特定のタイプの集団と見なされることもある。一方で、顕著な個人的アイデンティティは、ノエル=ノイマンが「ハードコア」や「アヴァンギャルド」(Noelle-Neumann, 1993, pp. 139–142)と呼んだものに関連づけられる可能性がある。また、SITにおける内集団(ingroup)と外集団(outgroup)は、SoSTにおける少数派と多数派と同一視でき、これらの集団を相互に比較するプロセスは、沈黙の螺旋理論で「準統計的感覚」として説明される。
次のステップとして、SIDEモデルの認知的次元は、匿名性が匿名状況に入る以前に顕著であったアイデンティティ(個人的または社会的アイデンティティ)の概念を強化すると仮定する(図9.3参照)。もし社会的アイデンティティが顕著であれば、匿名性は集団規範への指向性を高める。しかし、集団の顕著性が低い場合、匿名性は個人の自身の欲求や望みに対する焦点を高める。このことはReicherら(1995, p. 178)によって説明されている。
SIDEモデルの認知的次元における匿名性の効果
集団レベルのアイデンティティがすでに強調されている場合、匿名性は集団メンバー間の代替可能性を強調し、対人間の差異を曖昧にすることで、社会的アイデンティティの顕著性をさらに高める可能性が高い。しかし、匿名性が明確な集団没入を伴わない場合、その効果は大きく異なると考えられる。集団の顕著性が低く、集団の境界が不明瞭な場合、匿名性は個人化を逆に阻害し、集団からの孤立感を強調したり、集団の境界をさらに曖昧にしたりすることで、社会的アイデンティティの顕著性を低下させる可能性がある。
これらの仮定は、一連の実証研究によって確認されている(例:Spears et al., 2001)。また、これらは沈黙の螺旋理論(SoST)の基本的な仮定と矛盾しない。ノエル=ノイマン自身も、「孤立への恐怖、つまり制裁を受ける恐れとそれに伴う支配的な世論への指向は、非常に大きな匿名の公共圏では著しく高くなる」と述べている(Noelle-Neumann, 1993, p. 215)。
要約すると、SIDEモデルの認知的次元は、個人が社会的アイデンティティまたは個人的アイデンティティのどちらかを顕著に経験する可能性を示している。この二つのアイデンティティのいずれかが常に活性化され、その切り替えは明確な集団間の文脈などの状況的要因によって導かれる。コミュニケーション空間における匿名性は、匿名状況に入る前に顕著であったアイデンティティへの焦点を強化し、それに応じて個人は自分自身の規範(個人的アイデンティティが顕著な場合)または関連する集団規範(社会的アイデンティティが顕著な場合)のいずれかに指向するようになる。
次節では、SIDEモデルの戦略的次元について考察する。
SIDEモデルの戦略的次元
Ng(1982a, 1982b)の研究では、匿名性が個人の社会的アイデンティティへの焦点を高めるのは、対峙する集団が同等もしくはそれ以下の力を持つ場合に限られることが示されている。一方で、対峙する集団が自分の所属する内集団よりも強い場合には、その焦点は高まらない(Reicher et al., 1995, p. 186)。つまり、集団への所属の顕著性は、必ずしも集団行動の表出に十分な条件とはならない。むしろ、内集団の規範への指向は、より強い外集団の存在を認識すると減少する。このような場合、個人は戦略的に、どの範囲の行動を公に表出し、どの行動を控えるべきかを判断することになる。
これらの集団間の力関係は、個人の識別可能性によって調整される。個人が内集団の顕著な規範に基づくすべての行動を示すかどうかは、内集団や外集団のメンバーに対する自身の識別可能性、そして外集団の力の強さの認識に依存する。
Reicherら(1995, p. 187)は次のように述べている:
「内集団メンバーが外集団に対してより識別可能になると、外集団が内集団に対して持つ相対的な力は増加し、内集団メンバーの行動を問責する能力が強化される。一方、内集団メンバーが内集団内でより識別可能になると、外集団に対する内集団の相対的な力は増加し、内集団メンバーが外集団に抵抗する際に互いを支援する能力が高まる。」
- 弱い外集団に対して識別可能な場合SIDEモデルに従うと、個人は内集団の顕著な規範に適合するよう行動を調整する。外部からその行動について問責されることはないためである。
- 強い外集団に対して識別可能な場合個人は内集団に適合する行動を、外集団によって許容される範囲内に制限する。この場合、個人が外集団のすべての規範を採用し、自分の内集団の規範を忘れるわけではない。適応行動のプロセスは、外集団によって制裁される可能性がなくなった時点で停止する。
- 自分の内集団に対してのみ識別可能な場合個人は完全に内集団の規範に従って行動する。強い外集団が存在しないため、外部からの制裁を恐れる必要がない。
- 内集団および強い外集団の両方に対して識別可能な場合この状況はより複雑であるが、SIDEモデルの研究者によって十分に説明されている。通常、個人は外集団に対して不協和的な行動を控えるが、内集団の存在が「社会的支援」を提供する場合がある(Spears, Lea, Postmes, 2000, p. 4)。その結果、強い外集団に対して識別可能であっても、内集団の支援を受けて外集団の規範を超越する行動を取ることができる。
SIDEモデルの戦略的次元と沈黙の螺旋理論(SoST)の融合
SIDEモデルの戦略的次元に基づく仮定を沈黙の螺旋理論(SoST)と融合させる際、ノエル=ノイマンの概念には内集団の社会的支援が含まれていない。人間は常に大きな社会的規範、すなわち世論に向けて行動を調整する。自分の立場を世論と比較し、それに基づいて行動を適応させるのである。自分の見解が多数派と一致していると感じれば発言し、不一致だと仮定すれば沈黙する。
後者の場合、世論はより強い外集団の意見を表し、個人はこれを疑問視しない。ノエル=ノイマン(1993)のアプローチでは、個人が誰に対して識別可能であるかは完全に無関係である。この厳格な考え方は、理論の初期の段階から、意見形成過程における参照集団の役割についての科学的議論を引き起こしてきた(例:Price & Allen, 1990; Salmon & Kline, 1985)。
オンライン環境におけるSIDEモデルとSoSTの統合
SIDEモデルによれば、社会的環境での行動指向の参照点は、個人が識別可能である集団に依存する。しかし、匿名性の条件下では集団規範への指向は弱まる。前述した4つのコミュニケーション状況は、個人が制裁を予期する場合としない場合を評価するためのシナリオとして機能する。次に進むため、まず匿名性の次元のみを検討する。
図9.5に示されるように、特定のコミュニケーション空間で匿名性が高く認識されるほど、規範への順応が強化されると考えられる。この効果は、匿名性の条件下では集団がより均質に認識されるために発生する。このような状況では、集団特有の規範とそれに続く行動がより明確になる(Reicher et al., 1995)。もちろん、非匿名の条件下でも個人は集団規範に従うが、その適応の強度は異なる。
仮想環境では高い匿名性が特徴であるため、これらの環境は、個人が顕著な(集団)規範にオフライン環境よりも強く焦点を当てる空間として認識される可能性がある。この示唆はSoSTにとって有益である。オンライン環境では、規範に従う行動が例外ではなく規則となるように見えるからである。
同時に、SIDEモデルの第二の次元は、個人の識別可能性が高いほど、特定の集団規範への指向が強くなると仮定している。このため、図9.6に示されるように、QIとQIVの象限で表される状況では規範指向が増加することが予測される。
明らかに、ユーザーが識別可能でない状況(たとえば、ディスカッションフォーラムやニュースグループなど)は、SoSTにとって特に興味深いものである。これらの環境では、個人の行動がSoSTの基本的な仮定と矛盾する可能性があるためである。
匿名性と識別可能性が規範指向に与える影響が相互に作用する(互いに打ち消し合うか、あるいは相互に強化し合う可能性がある)と考えられるため、個人が制裁の予期をどの程度強く認識するかについて、詳細な仮定を提案する準備が整っている。結論として、制裁の予期は、おおまかに言えば、特定のオンライン環境において匿名性と識別可能性がどのように相互作用するかに応じて三つの異なるレベルに変化すると考えられる(図9.7参照)。
制裁の予期が高い状況は、他者についての情報が少ない一方で、自身のアイデンティティが他者に認識される場合に生じる。このような状況では、個人は内集団と外集団の両方の規範に直面し、自らの行動を適応させる必要がある(図9.4の文脈d参照)。たとえば、プライベートなブロガーはまさにこの状況に置かれ、常に監視されている状態で行動することになる。外集団のメンバーがいつでも自分の行動を観察する可能性があると想定し、そのため行動は外集団の規範に従ったものでなければならない。
これはまさにSoSTに基づいて、個人が不協和的な世論の雰囲気を認識し、沈黙するか、または認識された多数派意見に応答するべきとされる状況である。
対照的に、個人が自分のアイデンティティを隠すことができ、他者のアイデンティティがよく知られている場合には、制裁を予期する可能性は低く、あるいは全くない。したがって、外集団は指針としての影響力を持たず、内集団の規範が行動を導く。この状況は確かにSoSTの概念と矛盾するが、上述の通り、このような状況はオンラインまたはオフラインのコミュニケーションにおいて限られた特定の状況にしか適用されないため、現実におけるこの結果の重要性を過大評価すべきではない。
全ての参加者が識別不可能、あるいはほとんど識別不可能な場合(図9.7のQII参照)、特に匿名性が高い環境では、行動は一般的に対応する顕著な内集団の規範に従うべきである。この場合、制裁の予期は中程度と考えられる。しかし、匿名性の効果(規範に準拠する行動を促進する)が、識別不可能性の効果(反規範的行動を促進する)を上回るほど強力であるのか、それともこのような状況でも集団規範への指向が比較的低いままであるのかを検討する価値がある。
全ての参加者が互いに識別可能な場合(図9.7のQIV参照)、制裁の予期は平均的なレベルに均されるべきであり、内集団の規範が支配的となる。
これらおよび他の理論的な仮定に基づく主張は、将来的に実証的に検証される必要がある。YunとPark(2011)、HoとMcLeod(2008)、WantaとDimitrova(2000)、およびMcDevittら(2003)による本章冒頭で言及した研究に基づき、実験的なアプローチを追求することを提案する。オンライン環境が利用者にどのように実際に認識されているかを明らかにすることは、沈黙の螺旋研究において大きな進展となるだろう。匿名と定義した空間が、そこに行動する利用者にとって必ずしも匿名に見えるとは限らないからである。
さらに、規範違反的な行動がオンラインディスカッションで本当に一般的な現象であるかについては、逸話的な証拠を超える知識はほとんどない(想定されているほど一般的ではないと考えられる)。その後、異なる設定で規範指向を刺激として操作し、特にオンライン環境においては、時間の経過とともに意見の表明を記録する機会を提供することができる。しかし、倫理的制約により、実験フィールドでの試みは調査状況外で個人に現実的な影響を与える可能性があるため、研究者の選択肢は制限される。そのため、ブログやコメントのアーカイブを活用し、議論参加者への追加インタビューを補完することで、準実験的なデザインが多くの目的に適していると考えられる。
結論
沈黙の螺旋理論(SoST)の仮定とSIDE研究の中心的なアイデアを統合することは、オンライン環境における世論形成に関連する心理的プロセスを説明する上で有効なアプローチであると考えられる。本研究の理論的分析では、SoSTの中心的な仮定、すなわち社会的統制の認識とそれに伴う制裁の予期は、一部のオンライン環境において依然として有効であることを示唆している。
現在のSIDE研究の知見を活用すると、制裁の予期は存在するものの、コミュニケーション環境の特性に応じて変化することが分かる。環境が匿名性を帯びるほど、他者の認識は均質化され、規範に準拠した行動がより重要になる。これは、否定的な印象を与えないようにするためであり、グループ(つまり社会)から排除されるリスクを回避するためである。これに応じて、制裁の予期は高まるべきである。個人がどの規範に従うかは、自身が識別可能である集団に依存する。多くの場合、これらは少なくとも内集団の規範であると考えられるが、強力な外集団が存在する場合には制限されることがある。完全に識別可能な場合、高い制裁の予期が個人の行動を規範準拠に導くと考えられる。
制裁の予期のレベルに応じて、世論の雰囲気(ノエル=ノイマンの理論における基本的な参照点)は、重要性が増減する。制裁の予期が高い場合、個人は世論の雰囲気に従った行動を取るべきであり、不協和的な世論の雰囲気を認識した場合には沈黙する傾向がある。一方、制裁の予期が低い場合、世論の雰囲気の重要性は低下し、個人は不協和を認識しても意見を表明する意欲を持つことが一般的である(不協和は基本的に無視される)。
匿名性と識別可能性が必ずしもオンライン特有の現象ではないことを考慮すると、本研究の知見はオフライン文脈にも適用可能である。しかし、上述の通り、オンラインで見られる高い匿名性の条件はオフライン環境ではほとんど見られない。オンラインでは新しい質の相互作用が見られるため、オフラインでは発生しない、あるいは頻度が著しく低いために世論形成プロセス全体に大きな影響を及ぼさない効果が観察される可能性がある。
その結果、SoSTは、少なくとも一部の問題については実証研究による検証が必要となる。また、オンラインとオフラインの効果はほとんどの場合分離して発生することはなく、個人は通常、同じテーマについて両方のタイプのコミュニケーションに同時に関与していると考えるのが合理的である。理論的分析ではオンラインとオフラインのプロセス間の相互作用を考慮に入れることができなかったが、実証研究においても、それぞれのプロセスを適切に分離するのは困難な課題となる可能性がある。
さらに、この分野の複雑さを高める要因として、現実世界の集団とオンライン集団の間に実質的な重複が存在するという事実が挙げられる。個人の社会的メディアネットワークの中核をなすのは、多くの場合、その個人の身近な環境にいる人々である(例:Boyd, 2008, pp. 16–17)。メディア利用パターンの融合が進む場合、将来的にはSoSTにおいてオンラインとオフラインの区別が不要になる可能性もある。
日本における沈黙の螺旋理論の検証
「沈黙の螺旋」仮説の理論的検討(平林, 1987)
問題設定
平林によると、世論とマス・メディアの関係,問題の所在をより特定化するならば,世論過程においてマス・メディアが果たす役割は、政治学・社会学・その他の関連諸分野に関心をもつ全ての人々にとって、避けて通ることのできない研究課題の一つである。それゆえに、多くの思想家,研究者が、それぞれの方法的立場から,この課題に取組んできた。しかし、本論文のねらいは、先行研究が意識的あるいは無意識的に取り落としてきた問題の諸側面を見直すことにある。まず第一の側面として挙げることができるのは、日常的な社会的事実に即して容易に観察され得る,世論とマス・メディアの結びつきの諸相である。第二の側面は、世論とマス・メディアの関係が、その関係全体として保持している社会的意義あるいは社会的機能である。これは、世論とマス・メディアの関係についての研究を成り立たせる、最も基本的な問題設定であるにも拘らず、正面から論じられ、追究されることがなかった。筆者は、これらの側面を、次のような二つの問題に置き換えて考察する。
第一の問題は、世論過程とマス・メディア効果を理論的に接合し得るような一つの関係モデルを構築する可能性の検討である。この時、求められる関係モデルの構成要件は二つある。一つは世論の概念規定に関わる。世論を一つの動態的過程として、その社会的作用の観点から把握されるべきである。第二の要件は,マス・メディア効果の概念の拡大である。ここでより重要なのは、より長期的な社会レベルでの効果、特に、社会の構成員における状況の定義もしくは世界像の構成という、「社会的リアリティの構成」に関わるイデオロギー的効果なのである。このような視野の広がりをもってはじめて、世論という集合的社会現象ないし社会過程との直接的な連繋が可能になる。
第二の問題は、世論とマス・メディアの関係と「公共性」概念との関わりである。筆者は既に、世論とマス・メディアの関係がもつ社会的意義あるいは社会的機能に注目すべきであると述べた。この社会的意義あるいは機能は、世論(public opinion)を単なる社会内の一意見(an opinion)と峻別する「公共性(being public; publicity)」属性に注目することによって、また、その「公共性」属性とマス・メディアとの関わりに注目することによって、はじめて理解され得る。世論とマス・メディアを理論的に接合し得るキイ概念としての「公共性」は、社会統制(social control),換言すれば、社会構成員に対する社会的同調圧力の源泉として機能する。翻って、世論はそのような同調圧力の社会的装置として、一方マス・メディアは,その装置を支える重要な情報チャンネルとして,位置づけられる。
筆者が本稿で取り上げる Elisabeth Noelle-Neumann の「沈黙の螺旋状過程(the Spiral of Silence)」仮説は、以上の二つの問題を検討する上で最も適切な材料であり、始発点だとしている。筆者は、この仮説の諸論点の整理と理論的検討を通じて,公共性概念を中心に据えた、世論とマス・メディアの関係の基本的構図を明らかにし、同時に、その理論化と検証への具体的な手掛かりを得ることを目指すものである。
「沈黙の螺旋状過程」仮説の問題点
ー「公共性」と「公共化」をめぐって一
ここでの筆者の主要な関心は、「沈黙の螺旋状過程」仮説における二つの問題、すなわち第一に,「公共化」されることによって世論として社会に顕在化した意見が代表する「公共性」の実質は何か、第二に,そのような「公共性」を付与するメディアの「公共化機能」は、現代社会におけるメディアの効果のいかなる特性を示唆するものであるか、という問題にある。具体的には,これらの問題を中心に,「沈黙の螺旋状過程」仮説の四つの主要な論点を検討している。
1「公的状況(public situation)」
Noelle-Neumannは、「世論という文脈での “公的なること”(public)は、世論過程が機能する領域を示している。また,それは匿名的な公の状況(anonymous public situation)を示している。」そのような世論が具現する公共性の機能する領域を、「匿名的な公的状況」と規定している。
彼女は、「調査の回答者が、あたかも公的な場にいる(be in public)かのような状況に直面させられなければならない」として、回答者が5時間の列車旅行の際中で数人の見知らぬ乗客と同じコンパートメントに乗り合わせるという調査デザインを案出した。状況は対面的で、かつ集合の規模は個人の心理的委縮を招来しない程度に小さい。ここで想定されている「公的状況」は,例えば群衆の中の個人というような大衆社会論的イメージを喚起する状況ではなく、むしろ単に相互の社会的背算を知らない他人同志という「匿名性」を含む状況にすぎない。一方,「公的状況」は「世論が機能している場」であるから、そこでは一定環境内の支配的意見である世論が、社会的同調圧力を行使しているはずである。彼女は、世論を「人々の意志」(the public will)ともいうべきものに特徴づけられた、曖味に描かれた匿名的集団が,その意見を通じて(個人に対して)影響を与え、その行動において適切な適応を行うよう」勧告する場としての「判断の法廷(court of judgement)」と位置づけている。この場合,世論は、かくあるべき行動の社会的準拠枠組を積極的に提示するものとして描かれている。そして、「匿名的集団」は、人々の公的行動を統制する社会規範体系の代弁者である。つまり,ここでの「匿名性」は、いわゆる“一般化された他者”がもつ匿名性である。このような匿名性の定義が彼女の真に意図するところであるならば一事実そう意図されているのだが一、この定義が前出の研究デザインにおいて十分に活かされていないことは明白である。偶然に列車に乗りあわせた他の数人の乗客をもって、社会規範体系の代表者として“一般的他者”が行使すると仮定される社会的同調圧カー公共性の圧カーの担い手とみなすことは困難だからである。Noelle-Neumannも指摘しているように,匿名的な同調圧力が行使される場としての「公的状況」は、この仮説の検証作業を精力的に進めているアメリカの研究者たちにさえ、十分に理解されていない。その一つの原因は、「公的状況」の概念規定における曖昧さ、特に「匿名性」の規定の不明瞭さ、加えて、この仮説の理論的前提と実際に援用された検証デザインとの間の不整合にあることを筆者は強調する。
「公的状況」の概念が十分に理解されないもう一つの原因は、世論過程に含まれる様々な社会的相互作用から、全く匿名的な相互作用だけを特に検討対象として取出す理由が仮説の中ではっきり明示されておらず、またそのようなアプローチが、世論研究者にとって、理論的観点からも実際的観点からも馴染みにくい点にある。確かに、世論を直接的・間接的な社会的コミュニケーションの最終的結果と見做す研究者にとって、完全に匿名的な社会関係における相互作用だけが連鎖的に継起することによって成立する世論過程を仮定することは、理論的に見て不合理であり、かつ日常的社会場面の観点から見ても受け入れがたいものに思われるかもしれない。また,「沈黙の螺旋」仮説では、そのような匿名的な対人的コミュニケーションの場は同時に、社会的孤立を恐れる個人が、環境内の優越的意見に同調するよう強要される場でもあることが仮定される。しかし実際には、我々が日常的に体験している対人的コミュニケーションの全てが完全に匿名的であるわけではない。また、必ずしも、対人的コミュニケーションの全ての場面で我々が何らかの価値的基盤へ収斂するよう強要されるわけでもない。我々は日常,全く匿名的な相互作用も営むし、身近で、互いについての知識もある人々との対面的相互作用も営む。しかし、だからといって、この二種類の相互作用が各々、個人の意見形成ひいては世論の形成過程に及ぼしているところの影響力を同一次元で語ることができるだろうか。もし同一次で語るとすれば、「沈黙の螺旋」仮説をめぐる議論の中心が、二つの対立項としてこれらの相互作用の各々が世論過程に占める位置の問題に一世論過程において、また個人の意見形成過程において、これらのどちらがより重要か、という問題に一移行してしまうのは自然なことである。しかし、この二つの相互作用は本当に“対立項”なのか。“一般的他者”と個人の間の相互作用と、具体的で安定的なー定の集団内の相互作用とを同一次元で比較することは可能だろうか。
2 マスメディアと中間集団
実際、「沈黙の螺旋」仮説についての研究では、前述の二つの相互作用を対立項とする前提に立つ議論が多い。そこでは,個人に社会的同調を強要する匿名的相互作用が世論形成過程に占めている位置と、身近な人々との対面的相互作用が同過程に占めている位置とが、マス・メディアと所属集団・準拠集団との対立的構図という文脈で対比的に描かれる。
例えばE.Katz は、「沈黙の螺旋」仮説が、かっての大衆社会的前提一方に社会的細帯から切り離された原子化した個人を、他方に匿名的で強大な、マス・メディアを含む社会統制機関を,各々対置させる社会理論的前提に立つものであると批判した。Katzによれば、この仮説は、「メディアが一つの声で語る程に、また人々がお互いから、中間集団(教会,労働組合,政党,自発的結社など)から、彼ら自身の過去から切り離されていく程に,メディアとメディアの主人たちの支配がより完全になっていく」ことを前提とし、人々がメディアの提示する「意見の風土」によら多く準拠して意見を表明するか沈黙するかを決めるはずであると暗黙の内に仮定している。そこでは,メディアが準拠集団にとって代わる役割を果たすものとして描かれている、とKatzは批評する。また,C.J.Glynn とJ.M. McLeod 39)は、「沈黙の螺旋」仮説には「より広い社会の諸効果を媒介する、コミュニティ組織・準拠集団が果たしている特定の役割」に対する視点が欠落しており、強力な中間集団との関連性が想像される「ハード・コア」の範疇に関してすら,それが所属集団や準拠集団とどのような結びつきをもっているかが明確にされていないと批評している。
この二項対立の図式は、人々が「沈黙の螺旋状過程」にコミットする動機をめぐる議論においても見受けられる。人々は社会的孤立を含む心理的・社会的制裁を恐れるがゆえに、それを回避しようとするのか,それとも,社会の多数派の側につくことによって、何らかの心理的・社会的報酬が得られることを期待するからなのか。いわば、前者の動機は負のサンクションの回避,後者の動機は正のサンクションへの期待である。Noelle-Neumann は、この二つの動機を特に分けて考えているとは思われない。確かに「沈黙の螺旋」仮説においては前者の動機が強調されているが、「人々は人気者になること、賞賛されることを好む」という後者の動機が否定されているわけではない。にも拘らず,動機をめぐる議論では、正のサンクションへの期待を強調するあまり、“正か負か”という二分法的な問題提起がなされる。例えばC.T. Salmon とE.G. Kline(41)は、社会心理学における集団理論の知見を援用して「個人の意見形成や意見の変容に最も大きな影響力を与えるのは、集団のネガティブな制裁の脅威ではなく、その個人にとって集団がもつところのポジティブな魅力である」と主張している。また D.J.Taylorも社会的孤立への恐怖に代わる、ないしそれに加わる、自己表明及び沈黙の動機づけ要因として「特定状況下での政治的表明から生ずるところの刺激および期待された利益」を挙げている。
個人がある集団に対して何らかの魅力を見出す(あるいは見出さない)ためには、既にその集団についての知識や情報が個人によって獲得されていなければならない。しかし、「沈黙の螺旋状過程」で個人が直面することを追られているのは、いわば“匿名的集団”である。所属集団や準拠集団の場合とは異なり、彼はその集団との接触において、あるいは接触に先立って、集団の具体的な特徴や構成メンバーの念や態度を把握しているわけではない。つまり、何をすれば正のサンクションを受け、あるいは負のサンクションを受けるか、彼にとって全く予測できない状態である。共に予測できない時彼はどうするであろうか。恐らくこのように匿名的かつ流動的な集合状況の下では、彼は,期待された態度・行動が何であるかを知ろうとするよりも、ともかくは社会的制裁を回避するよう動機づけられる方が自然であろう。そして Noelle-Neumannは、このような匿名的状況の下で、アウトサイダーやマージナル・マンを除く社会の殆どの構成員を同調に向かわせる共通の動機を社会的孤立という制裁への嫌悪に求めている。ここで示唆されているのは、正のサンクションへの期待と負のサンクションの回避という二項対立ではなく、前者の動機の状況特定性および後者の動機の準普遍性である。
以上見てきたような、匿名的相互作用と親密な対面的相互作用、あるいはメディアと所属集団・準拠集団とを夫々対置させる構図は、「沈黙の螺旋」仮説の分析枠組として妥当なものだろうか。確かに、Noelle-Neumann の一連の論文において、中間集団としての所属・準拠集団に対する言及は、「ハード・コア」をめぐる議論を除けは殆ど見当たらない。この点に関して唯一彼女の考えを窺い知ることができるのは、次のような彼女独自の世論観に基づく主張においてである。
「『意見の風土』一この概念は,世論が伴っている外的影響力を表現するのに特に適しているが、それと同時に、人間に対する内的影響力、および何人も逃れることのできない世論の遍在をも表現するものである。研究者達が、特定の人々あるいは集団の間の相互作用に研究関心の照準を定めて意見形成過程を分析し,「公的なること(public)』,「ほとんどの人々(most people)』,「他者(the others)』の要素を回して通ることを好む時、彼らはこの(時論の遍在という)要素を取込むことを拒んでいるのである。」
この主張から明ちかなように、Noelle-Neumann が世論過程において対置させているのは、個人と“一般的他者”である。換言すれば、個人と、匿名的な人々によって構成されている全体社会である。「何人もそれから逃れることのできない世論の遍在」は、人々が中間集団の枠の中にいようと、あるいはそれから切り離された状況にいようと、彼らが常に“一般的者”の判断を精査するといらことによって成り立つ。つまりここでは、“一般的他者”の判断が人々に及ぼす影響力、すなわち公共性のもたらす圧力の作用が超集団的なものであることが示唆されている。そして、現代社会においては、“一般的他者”の判断を提示する最も有力な機関はマス・メディアである。メディアの効果という観点から見れば、その効果は、メディアによって提示された”一般的他者”の判断に対する人々の知覚を媒介にして成立する。かくして、世識過程におけるメディアと中間集団の対立的構図を立てることは、個人と“一般的他者”,個人と具体的安定的な一定の中間集団という全くレベルの異なる二つの関係を同一地平で論じるという誤まりを犯しているのである。Noelle-Neumann 自身、この点についてのように明言している。
「私は,友人・知人・準拠集団が、意見形成通程において、(メディアとの)二者択一の選択肢(alternatives)であるとは思わない。問題は,メディアかそれとも準拠集団かではない…・・・・せいぜい語ることができるのは、極めて奥味深い,(両者の)相互補強ないし相互減殺(mutual reinforcement orattenuation)に関してである。」
それでは、このように超集団的な“一般的他者”の影響力とは具体的にどのようなものなのか。そして、それはなぜそれ程までに殆ど普遍的な同調強制力をもち得るのか。これが次に検討する課題である。
3 同調圧力の次元と源泉
「 沈黙の螺旋」仮説における重要な検討課題の一つは、世論過程における人々の同調がどのレベルで生起するかという問題である。「沈黙の螺旋」は、人々における真の態度変容を表わしているのか。それとも,夫々の状況に応じた表面的かつ一過性の行動上の同調にすぎないのであって、ただ「逸脱的であると仮定されるような考えの表明が妨げられるにすぎず、より好意的な条件の下では、これらの意見がただちに、予想外に、再び現れてくる。」(傍点原文)のだろうか。例えば,「沈黙の螺旋」に対する類似概念として度々指摘される「多元的無知」をめぐる研究では、ある集団内における同調強制の圧力が、少なくとも人々の逸脱的意見一「意見の風土」と異なるーあるいはそれに反対する意見一の表明を妨げることが指摘される。しかし一方で、人々の私的信念が彼らの内面において潜在的に保持され続けるという可能性も残されている。
この点に関して「沈黙の螺旋」仮説は明らかに、態度と行動の両方のレベルにおける同調を想定している。公の行動はもちろんのこと、行為を成り立たせている態度の次元においても同調が志向されるのは、Noelle-Neu-mannによれば,自分の見解と異なる「意見の風土」を前にした個人は「自らの判断能力への疑い」をもつからである。例えば、ある社会的争点をめぐって互いに異なる立場の間で葛藤的状況が存在し、その葛藤を目撃した個人が、自らどの立場に立つべきかを考えなければならないとする。もし彼の見解が,二つの相反する立場のうち優越的ないし勝ちつつある方の見解に同意するものであるとわかった時、それは「彼の自(self-confidence)を高め,彼は安心して(with an untroubled mind)自己表明できる」のであるが、逆に、彼が自分の見解を力を失いつつある立場に同意するものと見た時、「そう見えれば見える程,増々彼は自分自身について不安で不確実な気持ちになっていく」のである。後者の場合,彼は自らの判断能力を疑い,多数派が標榜する何らかの価値に抗するべき自らの価値的土台を見失なってしまうことになる。
このような発想において、「沈黙の螺旋」仮説は、S.E.Asch等の同調行動研究と明ちかに立場を異にする。例えば、Aschの研究において,統制実験にかけられた被験者が同調したのは、多数者の判断を最善の判断と付じたからではない。彼らの同調は,C.T. Salmon と F.G. Klineの解釈に従うならば、「状況特定的(situation-specifc)」であって、「これらの人々は、自己の内部において同調しているのではなく、自分が実際に見たものに基づいた信念を保持しつつも公には同調した」にすぎない。それゆえに、Asch の実験では、被験者の判断を支持する人間が集団内に一人でもいると、同調の程度が大きく変化するのである。SalmonとKlineは、このAsch実験の知見に基づいて、「沈黙の螺旋」仮説が「状況の如何を問わず,社会的響力が常に大きい」という前提に立ち、同調行動が生起する場番における状況的変数を無視していると批判する。しかし、この批判は妥当ではない。というのは、Aschの研究の知見を世論の過程に適用するにはもともと限界があるからである。同調行動研究においては,「世論の状況と同調への圧力において決定的なもの」に対する配慮が欠落している,と Noelle-Neumann は言う。「決定的なもの」とは、世論の「道徳的次元(moral dimension)」である。ここで強調すべきことは、世論過程における普遍的な同調圧力の源泉が、この世論の「道徳的次元」にあることなのである。彼女は次のように説明している。
「世論から生じるところの同調への圧力は、認知上の判断(cognitive judge-ment)の名において行使されるというよりも、むしろ道徳的ないし審美的諸価値(moral or aesthetic values)の名において行使される。ここでの争点は、『正しいか正しくないか(correct or incorrect)』ではなく、『良いか悪いか(good or bad)』である。世論が道徳的価値を背負ったものであるという事実こそが、同調の強要において世論を力強いものにする。だから、普通の人々にとって、自分と同じ見解をもつ者が一人ないし二人いたとしても,それによって彼らの孤立の恐怖、自分が卑しい存在として他者の目に映る恐怖は少しも減少しない。」
以上見てきたように、「沈黙の螺旋」仮説において、世論のもつ同調圧力すなわち世論が具現している「公共性」の圧力は、人々の価値体系そのものに向けられている。つまり、この仮説が想定している世論のレベルは、社会のかなり基底的な文化のレベル、社会における共通の価値的基盤のレベルである。それは換言すれば社会規範のレベルなのである。「世論がコンセンサスを追い求め、既存の規範を防衛し、あるいは翻って、法的なサンクションを与えるような諸規範を創出する」一方、「孤立を回避しようとする個人は、妥協しようとし、そうすることによって社会に対してある共通の基盤(somecommon ground)を与える」とNoelle-Neumann (54)は説明している。「社会が存在する為の一条件」として社会的統合の達成を可能にする「共通の基盤」は、ある一定の時空間においてのみ妥当性をもつ、いわば世界理解の仕方であり、世界の意味づけであり、道徳すなわち善悪の基準である。この時、世論は「禁止」することによってではなく、孤立をもって人々を脅すことによって彼らを統制下に置こうとする「検閲(censorship)」=匿名的な「目」の役割を果たす。人々が恐れるのは、禁を犯すことによって与えられる物理的制裁ではなく,「共通の基盤」から逸脱しようとする人々に対する匿名の冷ややかな視線であり、それによって仄めかされる社会的孤立である。世論は究極的には、この「共通の基盤」の防衛者として、あるいはそれそのものとして現出する。このように、世論は、個人の側から見れば、匿名的な公共性の同調圧力であり、社会の側から見れば、社会的疑集を生み出す「天の恵み」、個人を道徳や伝統に適応させる一つの「保守的な力」である。
「沈黙の螺旋」過程において想定されている世論のイメージは、社会における道徳的な合意のイメージに近い。そしてその同調強制力は、一時的な社会的争点(例えば選挙や具体的・個別的な社会問題)をめぐる暫定的かつ流動的な合意というよりは、相対的に安定した社会規範をめぐる社会的合意への同調圧力を想起させる。後者のタイプの合意は社会統合の基盤であるから、それから公に逸脱する行動には大きな社会的制裁が伴うことは容易に推察される。しかし前者のタイプについてはどうであろうか。暫定的で流動的な合意からの逸脱に対して与えられる制裁は、殆ど全ての人々を同調させるに足るほど個人にとって深刻な制裁なのだろうか。つまり、制裁への恐怖は、その合意がどのようなレベルの問題領域をめぐって形成されているかによって変化するのではなかろうか。Noelle-Neumann は、世論には二つの位相一流動状態と固定状態ーがあると指摘し、「沈黙の螺旋」仮説においてよう重要な検討対象は流動的位相,すなわち社会において今議論が行なわれている争点をめぐる世論の方であると明言している。事実,この仮説の検証において彼女が提示しているのは、連邦議会選挙における有権者の動向に関するデータをはじめ,一過性の社会的争点をめぐる合意に関するデータが大半を占めている。そのような手点に関しても、彼女が理論的に仮定する深刻な社会的制裁。あるいはそれに対する人々の恐怖を、社会的規範の場合と同じように期待できるだろうか。この疑問は、「沈黙の螺旋」仮説の検証において、少なくとも「争点のタイプ」を随伴条件として考慮に入れる必要があることを示すものである。争点の範疇化は、例えば、「社会規範一一過性の社会問題」というような社会的合意の安定性の次元だけでなく、人々がその争点に対して知覚している心理的距離すなわち争点と個人のパーソナルな利害との知覚された距離ー争点の「身近さ」や「顕出性」一の改元においても試みられるべきであろう。
4 「公共性」と「公共化」
最後の論点として取り上げるのは、社会的同圧力としての世論が具現している「公共性」と,社会環境内のある意見を「公共的」な意見として頭在化させることによって公共的意見すなわち世論を創出するメディアの「公共化機能」である。ここで先に強調した「沈黙の螺旋」仮説の二つの重要な問題一第一に,「公共化」されることによって世論として社会に顕在化した意見が代表している「公共性」の実質,第二に、ある意見の「公共化」の過程に決定的な作用を及ぼしているメディアの「公共化機能」がもっている、メディアの社会的効果としての特性一を,より直接的に検討したいと考える。
3までの議論で明らかなように,「沈黙の螺旋」仮説において中心的に論じられているのは、社会構成員に同調を強要するという世論の「社会統合」機能についてである。しかし Noelle-Neumann 自身が指摘しているように、世論の機能には(a)統合の達成の他に,(b)社会の安定化,【c)優先順位の確定、(d)正当性の付与、がある。ここで重要なのは、(c)すなわち社会に対して何が最も緊急な課題であるかを指示する機能と、(d)すなわち社会的コンセンサスを追求し,社会構成員に同調圧力を行使しつつ既存の規範を防衛し、また法的制裁を与え得る新たな諸規範を創出するという機能の二つである。言うまでもなく,これらの機能は(a)および(b)の機能と相補的関係にある。しかし(c)(d)が,(a)(b)の機能以上により直装的に示唆しているのは、世論過程が社会的同調の強制の過程であると同時に社会的の創出の過程でもあるという事実である。「優先順位の確定」機能は、緊急な課題を選択的に提示するととによって、“緊急ではない”問題を社会の議題から遠ざけ、場合によっては放逐さえする。「正当性の付与」は、社会規範になじまない諸価値をひとまとめにして”逸脱”の格印を押す機能である。
同調の強制と逸脱の創出という世論のこの二つの機能は、世論通の二つの側面を表現している。にも拘らず「沈黙の媒旋」仮説においては、前者の機能ばかりが強調されるあまり、後者の機能に十分な考慮がなされていない。「沈黙の螺旋」が社会に対してもっところの意義は、むしろ後者の機能により注目することによって理解される。そして、世論過程が社会的脱の創出の過程でもあることを最も明瞭に示すのは,メディアの「公共化機能」である。
Noelle-Neumann は、メディアの社会的効果のうちでも、特に人々の認知(cognition)のレベルにおける効果に着目している。例えば彼女は,メディが議題設定を行い,特定の人間や議論に対して特別の威信一特に,将来性があるという威信一を付与し、様々な意見の緊急性ないし成功のチャンスを提示して見せることによって、人々による「意見の風土」の知覚に影響を与える、と指摘する。「螺旋状過程」が展開している時には、メディアは「孤立を回避するためには、何を言い,何をやったらよいか」を人々に教える。しかしその「螺旋状過程」を「圧力の出発点まで遡ると、どんな争点、トピックを考えるべきか、つまり、what to think about に対するマス・メディアの効果の問題に突当たる」ことになる。メディアによって設定された議題、威信を与えられた要素は、メディアが独自に意味を付与した社会的リアリティの一部を構成している。つまり,この場合、メディアが人々の認知に及ぼす効果は、メディアの「社会的リアリティの構成」機能によるものである。
一方,その社会的リアリティの構成において、メディアによって“無意味”と定義づけられた社会的要素一人、集団、ある見解ーは、社会におけるその存在を公には無視されて「効果的に沈黙させられる」と Noelle-Neumannは仮定する。たとえ、ある意見が実質的には多数派意見であったとしても,それを潜在的に支持する人々に対して、それを具体的に支持するための言葉や表現が与えられないとしたら、彼らは沈黙せざるを得ない。このようにして,メディアは、自らの独自な“状況の定義”の外にいるもの、その定義と相容れないものを効果的に社会の議題から抹殺する。しかもそれは、自己と相容れないものに反論を加えることによってではなく、それ自体を表現せず、またそれを擁護しようとする人々に対して手段を与えないことによってである。このようなメディアの機能一表現することによって、ある社会的要素の存在および価値を正当化し、表現しないことによって、それを社会的に抹殺し、沈黙させる機能一を彼女は,メディアの「分節化機能(articulation function)」と呼んでいる。
彼女がここで想定している、メディアによって構成された社会的リアリティは、単なる擬似環境以上のものである。「沈黙の螺旋」仮説において、メディアは、社会の構成要素とその構成のあり方に独自の意味付けを与える機関であると同時に、「公共化」の機菌でもある。「公共化」はそれ自体、一つの意味付与機能を担っている。つまり,メディアが提示する社会的リアリティは、メディアによる「公共化」を通じて、人々が共有している(と知覚されている)公共的リアリティになる。公共的リアリティであるからこそ、それは一つの社会的合意の基礎になり、そこから公に逸脱するものには社会的制裁が与えられるのである。メディアが直接的に制裁を下すわけでは無論ない。メディアはただ,「公共化」を通じて制裁されるものとそうでないものとを区別するだけである。「公共化」によって人々に知覚された社会的合意の、内と外にいるものを区別することによって、メディアは公に"通脱”を創出し、間接的に”逸脱者”を制載しているのである。
S. Hallは、このようなマス・メディアの効果を、社会的な合意形成過程の中でのメディアの役割という文脈において、メディアのイデオロギー的効果として概念化している。Hallによれば、多主義社会一現代の西欧社会はそうであると一般に仮定されているが一においては、「規範についての基本的で広範な合意が全ての人々の間に広がって」おり、また、メディアは「既に達成された合意を広範に反映あるいは表現する」機関であるという理論的前提が存在する。一方,この社会の現実においては、「統合的で有機的な合意」の枠外にいる人間あるいは少数派などの諸集団が、「相互に相容れない構造的・イデオロギー的諸原理をめぐって組織化されているものとは見做されず」に、「合意からの逸脱という形で排他的に定義されている。」そしてそこでは、「合意の外にいるということは、それに代わる別の価値体系の下にあるということではなく、単に無規範つまりアノミーとして規範の外にいる、ということにされた」のである。Hallは、このように仮定されている「合意が、本当に自発的に現出したものなのか、それとも社会の構築と正当化の複合的過程の結果としてあるのか」と問題提起する。Hallは、この後者の見解をとる。すなわち、このような社会は「その既存の構造、それを支持し保証する価値,その存在が続いていくことに対する人々の合意が絶えず生産され続ける」ことを要求するがゆえに、メディアは「既存の構造を支持し正当化する、まさにその状況の定義を再生産する」役割を担う,社会的リアリティの「意味付与を行う機関(signifying agents)」として位置づけられる。この時メディアは、その「社会的リアリティの構成」機能を通じて、規範すなわち社会の既存の諸価値に関する人々の合意の形成に貢献し、そので規範を共有しないものを"逸脱者”として規定するという、優れ一方てイデオロギー的な効果をもっているのである。
以上で明らかなように、「沈黙の螺旋」仮説において、メディアの「公共
化」機能は,社会のイデオロギー的改元に最も明白に作用している。翻って、そのような「公共化」を通じて社会に顕在化する世論の「公共性」は、ある私的意見一社会において実質的に多数派ではない。潜在的に多元化している様々な見解の一つが、メディアの「公共化」とイデオロギー的作用を通じて獲得した社会的認知レベルの属性なのである。
Noelle-Neumann は、「公共性」の三つの位相として、(a)法律的観点から見た「公共性」、(b)政治的観点から見た「公共性」、(C)社会心理的観点から見た「公共性」を挙げている。(a)は「全ての人に開かれている(open to everybody)」,(b)は「社会全体にとって重要な(important to the whole society)」(C)は「個人に対する判断の法廷(a court of judgement to the individual)」を各々意味し、彼女が検討している「公共性」は(C)であると説明された。(a)は「公共性」の影響力が及ぶ範囲を,「私」と対置させて確定し,(b)は社会の諸価値に照らした「公共性」の意味付けを明らかにし、(C)は個人にとっての「公共性」の意味を示している。実は、「沈黙の螺旋」における「公共性」は、(a)(b)(C)の三つの位相のどれか一つではなく、これらの属性を全て含んでいる。しかも、それは三つの属性を単に組み合わせたものではない。むしろ、ある社会的要素あるいは価値を、これらの三つの属性を全て含んだものとして公に措定するイデオロギー的な力が、この仮説における「公共性」の実質であると言うことができよう。
「沈黙の螺旋」仮説における「公共性」および「公共化」は,社会のイデオロギー的次元、社会を支える諸価値の次元と深く関わっている。メディアは、「公共化」機能を通じて、選択的にある状況の定義を社会に向けて提示している。この意味において、「沈黙の螺旋」仮説は、Hallをはじめとするメディア・メッセージのイデオロギー的次元での作用に着目する他の諸研究と,その視座における共通点を有していることは否定できないであろう。例えば、「沈黙」仮説における公共性概念の意味をめぐる議論は、Marina de Camargo Heckによる「特定グループに特別だった意味を社会全体に共通のものにしようと試みる」メディア・メッセージのイデオロギー的次元における「神話」作用の議論と重なって、現代社会におけるメディアの社会的作用のある重要な局面を我々に強く訴えかけるものである。しかし一方で、この“状況の定義づけ”に働く社会的諸力の問題に関して、Noelle-NeumannとHall らは全く異なる立場をとる。「沈黙」仮説では、メディアが提示する「意見の風土」が人々の実質的な「意見の風土」と異なる原因は,メディアの政治的・イデオロギー的偏向に求められる。そこでは、メディアは、“独自な”状況定義を行う社会内の自律的システムとして描かれる。一方Hall ちは、”状況の定義づけ”における最も有力な社会的力の源泉を,社会の既存の構造とそれを支える諸価値を維持することによって最も利益を得る者、すなわち支配階級に見ている。世論過程およびその過程に働くメディアの社会的作用が社会に対してもつところの意味を真に理解するためには、メディアを自律的システムとしてとらえるのではなく、Hall等の立場のように、メディアのシステムに働く社会的諸力を検討することこそ必須の課題であるといえよう。
おわりに
筆者は本稿において、「沈駄の螺旋状過程」仮説における世論過程モデルとマス・メディア効果モデルの連繋の諸相を、公共性および公共化の概念の検討を通じて、明らかにしてきた。世論過程は、一定の社会的諸価値へ我々が収斂することを強要する社会的同調圧力の過程であると同時に、それらの諸価値を共有しないものを逸脱者として排除する社会的圧力の過程であった。
またメディアは、それらの諸価値を社会において公有されたものとして提示することによってーNoelle-Neumann の表現を借りれば、「公共性一形のない、顔のない、手の届かない,不動の公の注目(public attention)を客観化する」”機関として一社会環境の定義づけを行い,それらの諸価値をめぐる実質的な社会的合意の形成に貢献する機関であった。「沈黙の螺旋」仮説の,世論研究およびマス・メディア効果研究に対する最大の貢献は,世論過程もデルとマス・メディア効果モデルとを直接的に連繋し得る仮説の構築の可能性を改めて提示した点にある。緻密な検証作業に耐え得る仮説を組み立てるためには、世論過程,メディア効果、全体社会についてのそデルを一つの統一的全体的視野から構成するのではなく、各々についての個別的モデルを用意する方がよら有効であるという考えは、世論とメディアの関係それ自体がもっている社会的意義の大きさを前にすれば全く説得力を失う。同様に,「沈黙の螺旋」仮説の検証は、先ず、その全体的な理論的構成の見取り図を作成することから始められねばならない。確かにこの仮説には、諸々の点において説明不足のところがあり、それがまた追検証をめざす研究者の誤解を招く原因になっている。しかし、例えばこの仮説で仮定されている「公共性」の意味を理解せずして、どうして世論の同調圧力の検証ができようか。「匿名性」のセッティングを調査デザインにどのように活かすかか、この仮説の検証における重要なポイントであることを、筆者は改めて強調している。
最後に、筆者はこの仮説の今後の発展に向けて、二つの課題を提起している。
第一に、Noelle-Neumann 自身も指摘しているように,「沈黙の螺旋」の国際比較が積極的に進められるべきであろう。例えば、環境内の支配的意見と私的確言の間の個人的葛藤の処理の仕方や、社会的存在としての人間の“脆弱さ”つまり環境圧力への屈服に対して夫々の社会がもっている寛容さ、公の意見表明における積極性、メディア・システムにおける共鳴性の度合、などにはかなりの文化差・社会差が見られるはずである。英語圏にも public eye(世間の目)という表現があるが、日本の場合,「世間」「世間体」「体裁」など、歴名的な社会の同調圧力や,それに対する人々の鋭い感受性を示愛する表現にはこと欠かない。
第二に、世論過程において沈黙を余儀なくされていた人を,集団、あるいは社会的合意からの“逸脱者”という烙印を押されたものたちの、その後の行動は極めて興味深い。彼らは沈黙を守り続けるのか、それとも、何らかの社会的組織化を通じて再び社会の議題に登場してくるのか。少数意見だったものが多数意見へと発展していく過程。逆説者たちが何らかの社会的チャンネルを通じて“敗者復活”してくる過程。それらの「沈黙の螺旋」仮説では語られることのなかった社会のダイナミクスの方にむしろ筆者の今後の関心はある。その変化のダイナミクスこそ,社会がもっている話力と弾性の最も明らかな指標となるからである。
「沈黙の螺旋」仮説の閾値モデル(石井, 1987 ; 古賀, 2012)
石井健一は、グラノヴェッターが集合行動のモデルとして提出した「関値モデル」をベースとして、これを世論過程に適合した形に変形してフォーマライゼーションを試みた。グラノヴェッターの闘値モデル(threshold model)は、世論過程などの集合行動を次のような仮定から出発する。
1. 各個人は、集合行動を採用するかどうかの「閾値」をもち、集団の採用率がこの閾値以上になった時に採用し、それ未満では採用しないとする。
2. この閾値は、集合体全体で、ある確率分布をなしているとする。
3. 個人の閾値は、時間的に一定であるとする。
一方、沈黙の螺旋過程モデルは、次のような5つの仮説から成っている。
1. 個人は、社会的存在として自分の意見が孤立することを恐れる。
2. 個人は、社会的環境を観察し、「準統計的感覚」を用いることで、ある意見が優勢であるかどうかを判断する。
3. 個人は、何が優勢な意見であるかだけではなく、意見の変化の方向についても知覚する。
4. そうした環境の探索は、(1)直接の観察あるいは、(2)メディアを媒介としてなされる。
5. 自分の意見が優勢な意見であるとみなした時、劣勢であるとみなした時に比べて自分の意見をよく表明する。逆に劣勢であると知覚した時は、意見の表明を差し控え「沈黙」する。その結果として、ある意見の「優勢性」に対する人々の社会的知覚が、社会的相互作用の連鎖を通じて螺旋状に自己増殖していく。
この仮説では、個人を世論の全分布を考慮する合理的な存在として仮定している点で、Granovetter の閾値モデルの仮定と共通している。「沈黙の螺旋状通程」の仮説に即して考えると、全集団は、ある争点についての①賛成集団と、②反対集団にわかれ、各集団の成員は自分の意見を外部に表明するかどうかという二つの選択肢をもっている。したがって、集団全体でみると、次の4つの状態があることになる。
1. ある意見に賛成を表明している(顕在的賛成者)
2. ある意見に反対を表明している(顕在的反対者)
3. 本当は賛成であるが、意見を表明していない(潜在的賛成者)
4. 本当は反対であるが、意見を表明していない(潜在的反対者)
このように、個人の状態は4つあるが、「沈黙の螺旋状通程」仮説では、個人の潜在的な意見については不変であると仮定しているから、1と3、2と4の間だけで変化があり、1と2や、3と4の間での変化は存在しないことになる。したがって、ある個人については、表明(1か2)か沈黙(3か4)という2値的な状態をとることになるが、意見表明についての閾値は、賛成意見者(1、3)と反対意見者(24)の間で区別する必要があり、別々の関値分布を考える必要がある。また、「沈黙の螺旋状過程」仮説の場合、賛成意見表明の「関値」は全体の人数に対する賛成意見者(1)の割合ではなく、意見表明者(1+2)に対する賛成意見表明者の割合として定義されなくてはならない。沈黙を守っている人(3+4)は、自分の意見を他人に知らせるという意味での他人への影響力はないから、関値の計算の中では除外されるべきである。
以上のような考え方にそって、モデル化を試みる。まず、潜在・顕在を合わせた贅成者(1+3)の割合をW.(0<W<1)とし、潜在・顕在を合わせた反対者(2+4)の割合をWe(0<We<1)とする。当然、
W1+W2=1
である。そして、関値分布を、
N1(X)=y1
N2(x)=y2
と表現する。ここで、✕は、意見表明者の中の費成者の割合であり、N1、N2はある累積確率分布関数、y1、y2はそれぞれ、賛成者集団、反対者集団について、 値Xを持つ者の割合である。均衡点では、
h(x)=X
が成り立つことになる。以下では、このモデルで、Ni、Neの二つの確率分布を正規分布とした場合の数値シミュレーションの結果の一例を示す。以下の例では、集団全体の人数は1000人であり、Ni、N2の二つの正規分布とも平均500、標準偏差250とした。
1986年の同日選挙(池田, 1988)
池田(1988)は、1986年の同日選挙における有権者の投票行動を調査し、ノエル・ノイマンの沈黙の螺旋仮説の検証を行った。ノエル・ノイマンによれば、世論過程には、自分が少数派意見の持ち主となるのを避けたい。自分が孤立してしまうことは避けたい,という一種の恐怖感が作動しており、それによって世間が支持する動向への同調行動あるいは「勝ち馬」効果が生じ,勝ち馬と目される選択肢に人々の支持が集中する効果が生じうる。もちろん、自分が少数派になりつつあることがわかれば、そして孤立したくはないが意見を変えたくもないというのであれば、公の場では沈黙することになる。しかしこの沈黙は、みかけ上多数派の声がますます大きくなる印象を与えるため、多数派が現実にそうである以上の多数に上るように世間一般が認知する効果を生む、それによって多数派への同調行動はますます促進される結果が生じる。これが、「沈黙の螺旋」と呼ばれる現象である。
以上の仮説を検証するために、池田は「意見変化の方向性の効果」と「候補に関する会話の規定要因」の2点について、データ分析を行った。
意見変化の方向性の効果
この仮説を検討するため、参議院東京地区の小野候補と中山候補についてのみ、第1回から第3回の調査時点で各候補が、「これから支持を増やすと思うかどうか(「自分の予想」と名付けた)」「世間は各候補の支持がこれから増えると思っているかどうか(「世間の予想」と名付けた)」についてそれぞれ尋ねた。すると、図11-1に示すように、小野候補についても中山候補についても、どちらも自分の予想と世間の予想とがパラレルな形で変化していく様子が見られる。

そこで、4つの予想(両候補に対する自分の予想、世間の子想)を独立変数として、これらが当落予想や投票意図に影響するかどうか、パス解析によって検討した。その結果、「支持の増減方向に関する世間の予想」(つまり、ノイマンのいう世論の方向性の認知)が「自分の当落予想」に対してかなりの程度影響しており、また同じ予想でも「支持の増減方向に関する自分の予想」もそれといささかパラレルなかたちで「落予想」に対して影響力を持っていることがわかった。一方,「投票意図」に対しては、「自分」や「世間」の予想の方向が直接影響していることは十分には見い出せなかった。第1回目の「自分の予想」だけが小野候補でも中山候補でも投票意図に影響していた。すなわち、支持を増やすと思う人が投票したいと意図していたが、これは例外的であった。また、「自分」や「世間」の予想が「自分の当落予想」を経て間接的に投票意図に影響するという仮説も,「自分の当落子想」→「投票意図」のパスが別の分析で否定されているために成り立たないことが明らかである。ノエル=ノイマンはこうした「意図」への影響は、選挙の最終段階になって生ずることがあるように論じているが、ここでは彼女のケースと違って最後の段階(第4回)でも影響はなかった。つまり、投票行動それ自体への「世間の方向」の影響に関しては疑問符がつけられるが、ここでも,認知的な面での影響が大きいことは十分認められた。
候補に関する会話の規定要因
ノエル=ノイマンは、こうした認知的な効果が「当該候補について話すかどうか」という対人的な変数に影響し、それがひるがえって「世間の方向」に関する認知(世論の認知)を拡大する(沈黙の螺旋現象)という仮説も述べている。この点を検討するために、「匿名の状況」で有権者がどれだけ「当該候補について話すかどうか」の条件設定を行なった。それは「たまたま街頭演説を聞いたときに隣に居合わせた人と、この候補に関する会話に積極的に加わるかどうか」という設定であった。
その単純集計の結果は図11-2に示す。「積極的に会話に加わる」「たぶん加わる」の回答を足しあげても、匿名の状況で会話に加わる人はいずれの時点でも1割前後であるというのがこの結果の特徴である。日本人の政治行動に関して一般に流布している信念を裏書する結果であった。

この結果を従属変数として、その規定因を探るための重回帰分析を試みた。すなわち、世間の方向の認知が対人的な変数に影響を及ぼすかどうかを検討した。その結果、「当該候補について話すかどうか」への意見変化の方向性変数の認知的な効果は十分でなく、沈黙の螺旋が生じる可能性は小さかったことが示唆された。このように、「匿名の状況」で感じられる世論の方向性という同調圧力は最終段階でも投票行動まで影響しなかった。
このように、検証結果はいずれも否定的なものであった。「世論の変化の方向性」は確かに有権者の落予想には影響を与えるものの、それが投票行動にまで結びつくという保証は得られなかった。また、匿名状況下での会話は、それを行なう人の数の面からみてもこれが活性化されたとは言えず、またその規定要因として「世論の変化の方向性」が影響するという仮説も十分実証されなかった。
昭和天皇の崩御(時野谷, 2008)
時野谷(2008)は、1984年以降20年以上にわたって沈黙の螺旋理論を実証した研究結果をまとめている。沈黙の螺旋理論と下記の変数を考慮して、実際の研究が進められた。
取り上げた変数:
変数1 論争の的となるある争点に関する回答者の意見の分布。
変数2 大多数の人がその争点についてどう考えているかという意見の風土に対する回答者の意見。
変数3 その争点の将来の傾向に関する予想。
変数4 その争点に対する公の場での回答者の発言の意志。
変数1、2、3が独立変数で、変数4が従属変数である。
時野谷の行った研究では、変数1、2、4を主として用いている。研究で用いられた測定尺度は次のとおりである。
変数1 ある争点に関する回答者の意見ー個人的意見。「あなたは、ある争点について、どう思いますか、思いませんか。」
変数2 意見の風土の測定|一般的意見。「あなたを除く日本の国民(世間の大多数の人)は、ある争点について、どう思っていますか、思っていませんか。」
変数3 争点の将来の傾向の予想「あなたは、一年後にある争点がどのようになる(賛成の人が増える、反対の人が増える)と思いますか。」
変数4 発言の意志の測定については、ドンスバッハとスティーブンソンのテレビ・リポーター尺度が用いられた。「テレビカメラとマイクを持ったテレビ局のリポーターが、ある争点について街で人々にインタビューしていたとします。あなたがインタビューを受けたならば、このことについて話したいと思いますか、思いませんか。」
分析方法:
個人的意見、意見の風土、未来の予想における多数派と少数派の分布を見る。次に調査された争点について、多数派、少数派が成り立つものについては発言の意志との関連を検討する。二つの陣営の間に分布の差があるかについて、結果を統計的に証明するためにすべてカイ二乗による独立性の検定をおこない、五%以上の有意差が成り立つかにより沈黙の螺旋を検証した。
以下では、1989年1月7日に発生した昭和天皇崩御を沈黙の螺旋の対象とした研究事例を紹介する。
調査:
調査は天皇崩御の2日後の1月9日から12日にかけて、東京都世田谷区を調査地点としておこなわれた。20歳以上の市民を対象にし、世田谷区五十音順電話帳をもとに調査専門会社が無作為抽出法によって電話調査をし、有効分析サンプル数300を得た。
変数1
「あなたは天皇崩御について、惜しいかたを亡くしたと思いますか、思いませんか。」
変数2
「あなたを除いて日本の国民は、天皇崩御について惜しいかたを亡くしたと思っていますか、思っていませんか。」
変数4
発言の意志の測定については、ドンスバッハとスティーブンソンのテレビ・リポーター尺度が用いられた。
ノエレーノイマンは感情と道徳の結びつきを強調している。彼女は、道徳的または感情的な構成要素がなければ、世論の圧力は発生せず、沈黙の螺旋は起こらないと述べている。これらの尺度は沈黙の螺旋の測定に合致している。
結果:
他人の意見において「惜しいかたを亡くした」と思う人が多数派で、そのなかで「話したい」という発言の意志のある人は44%、一方、「惜しいかたを亡くしたとは思わない」人は少数派で、そのなかで「話したい」という人は28%であった。この結果、カイ二乗検定をおこなうと、多数派と少数派のあいだには意見の分布の知覚と発言の意志に対して明らかに1%水準の有意差があり、沈黙の螺旋理論が成立していた。
一方、個人の意見では「惜しいかたを亡くしたと思う」人が多数派で、「惜しいかたを亡くしたとは思わない」人は少数派である。多数派で話したいと思う人は47%で、少数派では28%である。個人の意見でも、多数派と少数派のあいだには、意見の分布の知覚と発言の意志に対してカイ二乗検定をおこなうと1%水準の有意差があり、明確な沈黙の螺旋理論が成立していた。
この結果について時野谷は、「天皇の崩御は、伝統的な価値観にもとづく古典的な沈黙の螺旋ともみなされがちであるが、現在日本は民主主義国家であり、発言や政治的な自由があり、沈黙を強制されるような状況ではない。 この研究調査は、ノエレーノイマンによる沈黙の螺旋の仮説を日本で初めて明確な形で証明するものであった。」としているが、天皇崩御の式典が、国を挙げて伝統的なしきたりに従って厳粛に執り行われたことを考えると、人々の間にある程度公の場でネガティブな発言をすること自体がタブー視されていた可能性は否定できないだろう。
1993年の総選挙(三上, 1994; 竹下, 1998)
1993年の総選挙は、日本で沈黙の螺旋理論を検証する絶好の機会だと考えられた。この総選挙では、マスメディア特にテレビの果たす役割が大きな注目を集めた。非自民連立政権を誕生させ、自民党一党支配の55年体制を崩壊に導いた立役者はテレビのニュースや政治討論番組だったのではなかったのか、という議論が自民、非自民いずれの側からも指摘された。いわゆる新党ブームは、マスコミの力を借りて引き起こされたものであることは、誰の目にも明らかだった。特に、テレビ朝日の人気番組「ニュース・ステーション」では、久米宏キャスターや和田解説委員が「政治を変えなければならない」と盛んに強調した。実際、テレビ朝日報道局長(当時)が「政治とテレビ」をテーマにした日本民間放送連盟の会合で、先の総選挙報道について、「非自民連立政権が生まれるよう報道せよ」と指示した、との発言を行ったことが『産経新聞』で報じられるなどテレビで世論操作が行われたのではないかとの疑惑が沸き起こり、国会証人喚問にまで発展した。
テレビ朝日の椿・前報道局長は、問題となった放送番組調査会の席上で,「今は自民党政権の存続を絶対に阻止して、なんでもよいから反自民の連立政権を成立させる手助けになるような報道をしようではないか、・・・・それがいま吹いている”政治の風だ”というふうに判断した」と発言している。この場合の”政治の風”とは、椿氏特有の情勢判断にもとづくと思われるが、当時のジャーナリストにはこうした判断がかなり共有されていたのではないだろうか。この「風」は、必ずしも「国民世論」の動向とは一致していなかったことはすでにみた通りである。しかし、「政界」あるいは「財界」だけに限定した狭い意味での「世論」は、当時の各種アンケート調査をみても,確かに非自民連立政権への待望ムードが支配的であった。いわば,政界,財界の「世論」が国民全体の世論を先導する役割を果たしたといってもよいだろう。テレビや新聞などのジャーナリズムは、こうした先導的「世論」と歩調を合わせた報道を展開することによって、国民世論を「非自民連立政権」を支持する方向へと誘導する役割を果たしたということができるかもしれない。これが、当時の世論に吹いていた「風」あるいは、世論の「流れ」 だったと考えられる。こうした「風」や「流れ」に正当性を付与し、かつそれに勢いをつける役割を果たしたのがマスメディアの政治報道だったのである。
ドイツの世界的に著名な世論研究者ノエル・ノイマン(Noelle-Neumann)は、「人びとの孤立への恐怖と意見風土の認知、それに伴う沈黙の螺旋的な増幅が、特定の意見を雪だるま式に膨らませ、それが次第に優勢な世論になってゆく」という「沈黙の螺旋過程」仮説を提唱した。この仮説は、今回の総選挙における「非自民連立政権」成立へと向かう世論の動向とマスメディアの役割を説明する上で、きわめて有効だと考えられる。そこで、三上と竹下は、この仮説について簡単な解説を加え、調査データによって仮説検証を試みた。
1993年の総選挙では、「選挙後の政権のあり方」が大きな政治的争点になり、しかも新聞やテレビの報道では、現実の世論とは裏腹に「非自民の連立政権」への動きが大きく取り上げられ、かつ将来の有力な選択肢として肯定的に報じられた。したがって、多くの有権者は、その時点での世論の分布はともかく、近い将来「非自民の連立政権」をのぞむ声が優勢になるだろうという知覚をもっていたのではないだろうか。つまり、選挙期間中「非自民連立政権」に向けての”追い風”がマスコミ報道などを通じて吹いていたことが、有権者の意見風土知覚にも大きな影響を与えた可能性が少なからずある。
もしこれが事実だとすれば、選挙後の政権のあり方として「非自民の連立政権」をのぞんでいた人は、公共的な場でも進んで自分の意見を表明し、逆に「自民党の単独政権」あるいは「自民・非自民の連立政権」をのぞんでいた人は、人前では意見の表明を控えるという傾向があったのではないかと推測される。その結果,その時点では実際に少数意見であったものが、沈黙の螺旋過程を通じて次第に「優勢な世論」へと転化し、結果的に非自民連立政権を実現させることになったのではないか、との仮説を立てることができる。
自分の意見表明による沈黙の螺旋仮説の検証(三上1994)
「沈黙の螺旋過程」仮説は、「意見風土の知覚が、公的な場面で自分の意見を自発的に表明するかどうかに影響を与える」というものである。調査によって仮説の検証を行う際には、「公的な場面」をどのように設定するかが問題となる。ノイマンが調査で好んで用いた公的場面は、列車の中での会話場面であった。具体的には、対象者に次のような設問をするものである。「あなた自身が列車に乗って5時間の旅をしていると想像してください。あなたのコンパートメントには他の乗客が何人かいて、その乗客があなたに、ある論争的な問題Xについての会話を始めたとします。このとき、あなたはXについての会話に進んで加わりますか?」
この他に、選挙時の調査では、「キャンペーン用の応援バッジをつけて歩くかどうか」「自分のクルマに支持政党のステッカーを貼るかどうか」「自宅の塀や窓に支持政党のポスターを掲示するかどうか」などいろいろな設問が工夫されている。しかし、これらの設問は日本の状況には必ずしもふさわしくないので,そのまま援用することはできない。
わが国では、1986年総選挙時に「たまたま街頭演説を聞いた時に、隣に居合わせた人と、2人の女性候補についての話に加わるかどうか」という場面設定で、公的場面での意見表明を測定した調査研究(池田,1988)があるが、このような設定はいくつかの問題を含んでいる。第一に、ワーディング自体が曖昧さを含んでおり、2人の候補のいずれについての設問なのか、あるいは、当該候補者の演説会を想定しているのかどうかが必ずしも特定できない。第二に、街頭演説に集まる人々は、動員された支持者が大部分を占める場合が多く、「匿名的な公的空間」、とはいいがたい。したがって、このような場面を設定して「沈黙の螺旋過程」仮説の検証を試みることは妥当性に欠けるのではないかと思われる。
そこで,本調査では、わが国の状況にマッチした「匿名的な公的場面」で、かつ現実にふつうの市民が選挙や政治について意見を公に表明する可能性をもったものとして、テレビ局による街頭インタビューを受けるという場面設定を考えた。具体的には、改のようなワーディングで設問を行った。
「いま仮に、あなたが街を歩いているときに、テレビ局の人からインタビューを受け、衆議院選挙後の政権のあり方について意見を求められたとします。あなたは、このインタビューに対して、ご自分の意見をはっきりと述べると思いますか。それとも、自分の意見を述べるのは控えると思いますか。」
回答選択肢は「自分の意見をはっきりと述べる」「自分の意見を述べるのは控える」のいずれかとした。調査の結果は、下図に示すように、ほぼ半々ときれいに分かれた。「意見をはっきりと述べる」という回答が予想以上に多く出たのはやや意外な結果だった。
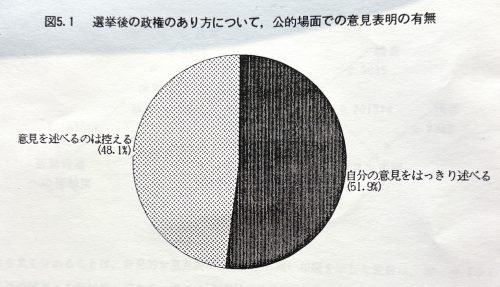
この回答と「選挙後の政権のあり方」についての回答者自身の意見との間の関連性を検討することによって、「沈黙の螺旋過程」仮説を検証してみよう。図5.2は両者の関連を示したものである。これを見ると、自分の意見をすすんで表明する人は、「非自民の連立政権」をのぞんでいる人にもっとも多く、逆に,「自民党の単独政権」をのぞんでいる人にもっとも少ないというリニアな関連がはっきりと示されている。つまり、上記の前提を受け入れるならば、今回の選挙では、「非自民連立政権が優勢な意見になりそうだ」という意見風土のもとで、沈黙の螺旋過程が作用した可能性の高いことがこのデータからは明確に示されている(三上,1994)。
自分の意見と世間の風土の一致パターンによる沈黙の螺旋仮説の検証(竹下, 1998)
1993年の総選挙では、公示前に自民党が分裂したために、仮に自民党候補者が全員当選しても単独政権を維持することが困難な状況になっていた。そこで、選挙後の政権の形態をどうすべきか!自民党を中心とした連立政権が望ましいか、あるいは自民党はいったん下野して、非自民の政党による連立が望ましいかーがひとつの論争点になっていた。回答者自身の意見、社会の多数派意見の知覚(ワーディングでは、社会ではなく世間という語を使った)、自分の意見を公言する意思、をそれぞれ組み合わせ作成したのが表2-1である。ここでは、公の場での意見表明という状況を、街角でテレビのインタビューを受けた場合を想定してもらうことで、シミュレートしようとした。このほかにも、ノエル=ノイマンが考案した「列車テスト」の方法がある。
仮説にしたがえば、表2-1の一行目と四行目のカテゴリーが意見を公言する人の割合が高くなり、二行目、三行目は公言を控える人の割合のほうが高くなるはずである。しかし、予想通りの結果になったのは、二行目と四行目のカテゴリーだけであった。すなわち、結果としては、社会の多数意見をどう知覚しているかにかかわらず、自分の意見として選挙後は非自民の連立政権が望ましいと考える回答者のほうが、自民連立政権を支持する回答者よりも自分の意見をすすんで公言する傾向が見られた。沈黙の螺旋仮説の予想とは必ずしも一致しない。

自らを多数派と自認するにせよ、あるいは自らを少数派と考えるにせよ、総選挙後は非自民の連立政権が望ましいと考える人は、意見を公言してもいいと答える傾向があった。反対に、自民中心の連立政権が望ましいという意見の持ち主は、どちらかといえば意見表明を避けようとする傾向が見られた。各カテゴリーのケース数(カッコ内に示したもの)を比べてみると、サンプル全体としては、自民中心の連立政権を支持する人が多数派であり、非自民の連立
政権を望む人は少数派である。しかし、当時のメディアの論調を見ると、自民党は下野すべきだという主張のほうがかなり強かったのである。非自民の連立政権を支持する人たちはこうしたメディアの論調に力づけられ、意見表明の意欲を持ったと解釈できないだろうか。ともあれ、有声化機能の問題をよりくわしく追究することで、沈黙のらせん仮説と議題設定仮説との接合点を探れるのではないかと竹下は指摘している。ノエル・ノイマンによれば、「メディアは、ある意見や立場を擁護するための言葉や言い回しを提供するのである。だから、自分の意見を言うのに適した表現がメディアによって流布され頻繁に繰り返されることがなければ、その人は沈黙に向かうしかなく、事実上沈黙させられることになる」(Noelle-Neumann, 1993, 邦訳、二〇ーページ)。これをノェル=ノイマンは、メディアの有声化機能と呼んだのである。
日本の常任理事国入り問題(安野, 2002)
安野(2002)は、ノエル・ノイマンの沈黙の螺旋仮説を検討した結果、この仮説に対する支持が少ないことの原因の一つとして、ハードコア層を含めた全体サンプルを分析対象としてことがあると考え、ハイドコア層と非ハードコア層を分けた分析が必要だと考えた。また、デーヴィソンの第三者効果も沈黙の螺旋過程に影響を与えるのではないかと考え、これらの仮定を組み込んだ仮説を立てて、全国パネル調査のデータによる検証を試みた。
仮説:
安野(2002)は、意見強度によって「ハードコア層」と「非ハードコア層」を分けた分析を行うことによって、「沈黙の螺旋」仮説の検証を試みた。ハードコア層の影響を除去し、かつ第三者効果の影響も測定するために、次の2つの仮説を立て、沈黙の螺旋仮説の検証を試みている。
- 世間の中で自分と同じ意見を持つ人の割合を高く見積もるほど、当該争点についてより積極的に意見表明をしようとする傾向があるであろう。つまり、合意性の認知と意見表明の意図との間に関連がみられるであろう。
- ただし、合意性認知と意見表明の意図との関連は、強い意見を持つ層(ハードコア層)では見られないであろう。
調査の概要:
本研究で用いたデータは、1995年2月に「日本人の選挙行動研究会」(JES2:代表蒲島郁夫)の第4波として行われた郵送調査である。JES 2調査は1993年7月から 1996年11月まで7回にわたり、層化二段無作為抽出法により抽出された全国の有権者を対象に行われたパネル調査である。第4回調査(1995年2月20日投~3月14日)は、第3回の送付対象者2682名のうちの,強い拒否を除く 2577名を対象に実施された。1608の回収票(回収率62.4%)のうち有効回答数は1529票(59.3%)であった。
「沈黙の螺旋」仮説を検証する上でとりあげる争点は(最近改めて争点として浮上しているが)当時議論されていた日本の国連安保理常任理事国入りの是非である。なお、ドイツ・インドなども常任理事国入りの対象であった。仮説に該当する質問は次のとおり:
Q1. 日本の国連安保理常任理事国入りについての意見:
「日本が国連の安全保障理事会の常任理事国となることについて、あなたはどのような考えを持っていますか。」
A. 1. 世界の大国の仲間入りができるので常任理事国となることに積極的に賛成。
7. 自衛隊の海外派遣などで戦争に巻き込まれる危険があるので積極的に反対。
(4を中心として、左側に行くほど常任理事国入りに賛成。右側に行くほど反対)
Q2. 世間の中で自分と同じ意見を持つ人の割合についての質問:
「では、世間であなたと同じような意見を持つ人は、何割くらいいると思いますか。」(0から10までの数字で回答)
Q3. 将来予測についての質問:
「将来,大多数の人は、軍事的貢献を含む日本の常任理事国入りに賛成するようになるでしょうか。」
A. 「1. 数年内にそうなる」「2. 10年以内にそうなる」「3. 20年以内にそうなる」「4. 遠い将来そうなるかもしれない」「5. 賛成するようにはならない」
Q4. 意見表明の意図についての質問:
「日本の常任理事国入りの問題に関して、あなたがしても良いと思うことすべてに〇をつけてください」
調査結果:
1) 日本の常任理事国入りに関する意見分布とその認知
自分自身の意見を見ると、賛成が若干多かった。世間の中で自分と同じ意見を持つ人の割合を見ると、わずかながら、常任理事国入りに賛成意見をもつ回答者の方が、より自分と同意見の人の割合を高く見積もる傾向が見られた。
2) 意見表明の意図
.意見分布(合意性)認知あるいは将来子測と意見表明の意図との間に関連が見られれば,沈黙の螺旋が生じているということになる。意見表明の意図の指標としては、「新聞に投書する」「友人や家族に積極的に意見を述べる」「友人や家族に求められれば意見を述べる」「署名運動に協力する」「街頭でインタビューされれば、意見を述べる」の5項目のうち、言及された項目数を足しあわせたものを指標とした。独立変数として投入した変数は以下の通りである。①争点重要性(国連安保理常任理事国入りという争点が自分にとってどの程度重要な問題か」得点が高いほど「重要性が高い」方向に反転),②合意性認知(自分と同じ意見の人は何割くらいいるか),③将来の世論動向(近い将来に賛成者は増えそうか、値が低いほど「近い将来に賛成者が増える」,④自分へのマスメディアの影響(値が高いほど「影響を受けている」に反転),⑤世間の人へのマスメディアの影響(値が高いほど「影響を受けている」に反転)。また、基本的な社会的属性として年齢,性別。学歴を投入した.
①全サンプルを対象とした分析
まず,全サンプルを対象として、意見表明の意図を従属変数とした順序ロジット分析を行った。その結果,争点の重要性が高く、年齢が高いほど、また女性よりも男性の方が常任理事国入り問題についてより発言しやすい(抵抗がない)という結果が得られた。また、自分自身よび世間の人へのマスメディアの影響力認知も意見表明の意図に関連していた。常任理事国入りに関する合意性認知も,弱い効果ながら、意見表明の意図にプラスの効果を持っていた(ただし。サンプル数を考えると、あまり強い意味はない程度のものである)。これに対して、将来の世論動向の予期は意見表明の意図と関連していなかった。
②意見の強度と方向性による4類型ごとの分析
次に、仮説を検証するため、意見の強度と方向性によって回答者を分類した。常任理事国入りの意見として強い賛成から強い反対まで7段階で評定された回答から,「強い反対(1)」「弱い対(2)(3)」「どちらでもない(4)」「弱い賛成(5),(6)」「強い賛成(7)」の5類型を作成した。このうち,「どちらでもない」に該当する回答者(N=337:22%)は「表明する意見がない」と見なせるので分析から除外することにした。ノエルーノイマン定義によれば、「強い反対」あるいは「強い賛成」に該当する回答者がハードコア層に相当すると考えられる。その結果、「弱い賛成」カテゴリに属する回答者は、他のカテゴリの回答者よりも意見表明の意図が弱かった。しかし、合意性の認知の効果は「弱い賛成」サンプルでのみ見られていた(交互作用が有意であった)。この結果は、「弱い贅成意見」を持つ人々の間でのみ合意性認知が意見表明の意図に影響する。すなわち、世間の中で自分と同じ意見を持っ人の割合を高く見積もるほど、日本の常任理事国入りについてより種極的に意見表明をしようとする傾向があることを意味している。これに対して、「沈黙の螺旋」仮説のハードコア層に相当すると考えられる強い賛成意見を持つ層および反対意見を持つ層では合意性認知と意見表明の意図との間に関連は見られなかった。また、「世間の人へのマスメディアの影響力認知」も,意見表明の意図にプラスの効果を持っていた。これは、争点態度や合意性認知その他の変数を統制してもなお、「世間の人は(安保理常任理事国入りに関して)マスメディアの影響を受けている」と考える人ほど、意見を表明する傾向にあることを示している。
要約すると、全サンプルを一括して行った分析では合意性認知あるいは将来予測と意見表明の意図との間に有意な関連が見出されなかったのに対し、争点態度の強度と方向性によって回答者を分割した場合,「弱い賛成」のカテゴリーと合意性認知の交互作用が有意であった、すなわち「弱い賛成者」でのみ合意性認知と意見表明の意図との間に関連が見られたという結果は、「沈黙の螺旋」を一部支持するものであった。この結果は意見の強度や方向性を無視して全サンプルを分析対象とする過去の研究の問題点を明らかにしている。
参考文献(第10章)
Bogart, Leo. (1991, August). "The pollster and the Nazis". Commentary, pp. 47-49. (https://www.commentary.org/articles/leo-bogart/the-pollster-the-nazis/)
Chan, Michael, 2018, Reluctance to Talk About Politics in Face-to-Face and Facebook Settings: Examining the Impact of Fear of Isolation, Willingness to Self-Censor, and Peer Network Characteristi. Mass Communication and Society, 21:1
Donsbach, W. Salmon, C. and Yariv, T., 2014, The Spiral of Silence : New Perspectives on Communication and Public Opinion, Routledge.
Donsbach, W., Yariv, T. and Salmon, C., ”2014, “The Legacy of Spiral of Silence Theory : An Introduction” in The Spiral of Silence : New Perspectives on Communication and Public Opinion, Routledge.
Fox, Josse & Lanier Frush Holt, 2018, Fear of Isolation and Perceived Affordances: The Spiral of Silence on Social Networking Sites Regarding Police Discrimination. Mass Communication and Society, 21:5, 533-554,
Glynn, C. J., Hayes, A. F., & Shanahan, J. (1997). Perceived support for one’s opinions and the willingness to speak out: A meta-analysis of survey studies on the “spiral of silence.” Public Opinion Quarterly, 61, 452–463
Glynn, C. J., & Huge, M. E. (2014). Speaking in spirals: An updated meta-analysis on the spiral of silence. In W. Donsbach, C. T. Salmon, & Y. Tsfati (Eds.), The spiral of silence: New perspectives on communication and public opinion (pp. 65–72). New York, NY: Routledge.
Glynn, C. J., & McLeod, J. M. (1985). Implications of the spiral of silence theory for communication and public opinion research. In K. R. Sanders, L. L. Kaid, & D. Nimmo (Eds.), Political communication yearbook 1984 (pp. 43–65). Carbondale, IL: Southern Illinois University Press.
Glynn, C. J., & Park, E. (1997). Reference groups, opinion intensity, and public opinion expression. International Journal of Public Opinion Research, 9, 213–232.
Hampton, K. N., Rainie, L., Lu, W., Dwyer, M., Shin, I., & Purcell, K. (2014). Social media and the ‘spiral of silence’. Washington, DC: Pew Research Center. (https://www.pewresearch.org/internet/2014/08/26/social-media-and-the-spiral-of-silence/)
Hayes, A. (2007). Exploring the forms of self-censorship: On the spiral of silence and the use of opinion expression avoidance strategies. Journal of Communication, 57, 785–802
Hayes, A. F., Glynn, C. J., & Shanahan, J. (2005a). Validating the willingness to self-censor scale: Individual differences in the effect of the climate of opinion on opinion expression. International Journal of Public Opinion Research, 17, 443–455
Hayes, A. F., & Matthes, J. (2014). Self-censorship, the spiral of silence, and contemporary political communication. In K. H. Jamieson & K. Kenski (Eds.), Oxford handbook on political communication (pp. 763–776). Oxford, UK: Oxford University Press.
平林紀子, 1987, 「沈黙の螺旋状過程」仮説の理論的検討」『放送学研究』, No.37
平林紀子, 1992 「沈黙の螺旋状過程」仮説. 田崎・児島編『マス・コミュニケーション効果研究の展開』北樹出版
Ikeda, Ken'ichi, 1989, "Spiral of Silence" Hypothesis and Voting intention: A Test in the 1986 Japanese National Election. Keio Communication Reiew No.10
池田謙一, 1997, 「訳者解題」ノエル・ノイマン『沈黙の螺旋理論』ブレーン出版
池田謙一, 1998, 「沈黙の螺旋」仮説. 東京大学新聞研究所編『選挙報道と投票行動』
石井健一 (1987)「世論過程の閾値モデル:沈黙の螺旋状過程のフォーマライゼーション」 『理論と方法』Vol.2, No.1 数理社会学会 15-28.
Jeffres, L. W., Neuendorf, K. A., & Atkin, D. (1999). Spirals of silence: Expressing opinions when the climate of opinion is unambiguous. Political Communication, 16, 115–131.
Katz, E., 1981, "Publicity and Pluralistic Ignorance: Notes on 'the Spiral of Silence'" in Bauer, H., Kepplinger, H.M., and Reumann, K. (eds.) Public Opinion and Social Change, Wiesbarder: Westdeutcher Verlag.
古賀豊(2012) 「沈黙の螺旋と閾値分布構造 閾値モデルを用いた沈黙の螺旋現象の分析」『マス・コミュニケーション研究』81号
児島和人、1988,「戦後日本の「マス・コミュニケーションと投票行動に関する研究』の類型と特質」,東京大学新聞研究所編,『選挙報道と投票行動』,PP.9-52.
三上俊治,1993,「世論過程の動態」、「東洋大学社会学部紀要」第31-1号,Pp.123-210
三上俊治, 1994, 「沈黙の螺旋」仮説の検証「1993年7月衆議院選挙におけるマスメディアの役割」. 東洋大学社会学部紀要 (31-2) pp. 143-202
三宅一郎,1989,『投票行動』,東京大学出版会
Neuwirth, K., Frederick, E., & Mayo, C. (2007). The spiral of silence and fear of isolation. Journal of Communication, 57, 450–468
Noelle-Neumann, E., 1973, Return to the concept of powerful mass media., Studies of Broadcasting, 9, 67-112.
Noelle-Neumann, E. (1974). The spiral of silence: A theory of public opinion. Journal of Communication, 24, 43–51.
Noelle-Neumann, E., 1984, The Spiral of Silence: Public Opinion - Our Social Skin. Chicago: University of Chicago Press. 池田謙一・安野智子訳『沈黙の螺旋理論』(改訂版)1997. ブレーン出版
Noelle-Neumann, 1989, Advances in Spiral of Silence Research. Keio Communication Review No.10.
Noelle-Neumann, 1991, The theory of public opinion: the concept of the spiral of silence. In Anderson, J. A. (Ed.) Communication Yearbook 14. Newbury Park, CA: Sage.
Noelle-Neumann (2001). Commentary, International Journal of Public Opinion Research 13, 59–60.”
Salmon, C. T., & Kline, F. G. (1985). The spiral of silence ten years later: An examination and evaluation. In K. R. Sanders, L. L. Kaid, & D. Nimmo (Eds.), Political communication yearbook 1984 (pp. 3–30). Carbondale, IL: Southern Illinois University Press.
Salmon, C. T., & Glynn, C. J. (1996). Spiral of silence: Communication and public opinion as social control. In M. B. Salwen & D. W. Stacks (Eds.), An integrated approach to communication theory and research (pp. 165–180). Mahwah, NJ: Erlbaum.
Scheufele, D. A., & Moy, P. (2000). Twenty-five years of the spiral of silence: A conceptual review and empirical outlook. International Journal of Public Opinion Research, 12, 3–28.
Scheufele, D. A., Shanahan, J., & Lee, E. (2001). Real talk manipulating the dependent variable in spiral of silence research. Communication Research, 28, 304–324.
Schulz, A.,&Roessler, P. (2012). The spiral of silence and the Internet: Selection of online content and the perception of the public opinion climate in computer-mediated communication environments. International Journal of Public Opinion Research, 24, 346–367
Shanahan, J., Glynn, C., & Hayes, A. (2007). The spiral of silence: A meta-analysis and its impact. In R. W. Preiss, B. M. Gayle, N. Burrell, M. Allen, & J. Bryant (Eds.), Mass media effects: Advances through meta-analysis (pp. 415–427). Mahwah, NJ: Erlbaum.
Simpson, C., 1996, Elisabeth Noelle-Neumann's “Spiral of Silence” and the Historical Context of Communication Theory. Journal of Communication, 46-3, 149-171.
Stoycheff, E. (2016). Under surveillance: Examining Facebook’s spiral of silence effects in the wake of NSA Internet monitoring. Journalism & Mass Communication Quarterly, 93, 296–311.
竹下俊郎, 1998, 『メディアの議題設定機能』学文社
時野谷浩, 2008, 『世論と沈黙:沈黙の螺旋理論の研究』. 芦書房
Willnat, L., Lee, W., & Detenber, B. H. (2002). Individual-level predictors of public outspokenness: A test of the spiral of silence theory in Singapore. International Journal of Public Opinion Research, 14, 391–412.
安野智子, 2002, 「沈黙の螺旋理論の展開」『マス・コミュニケーション研究』第60号
安野智子, 2006, 重層的な世論形成過程:メディア・ネットワーク・公共性. 東京大学出版会
Yu QWon Oh, 2019, Who Expresses Opinions in a Hostile Online Forum Environment and When. Mass Communication and Society, 22:423–446,
第11章 選択的接触仮説
J.T.クラッパーによる紹介
メディア効果論の歴史において転換点を画した「限定効果論」は、説得的マス・コミュニケーションの影響力が態度や行動を変改するのではなく、「補強」する方向に働くことを明らかにした。J.T.クラッパー(Klapper, 1960)は、『マス・コミュニケーションの効果』の中で、その作用因として、5つの媒介変数と条件を指摘した。その第1要因として、「先有傾向(predispositions)および選択的接触(selective exposure)、選択的知覚(selectiveperception)、選択的記憶(selective retention)の過程」を指摘した。そして、そうした先有傾向の代表として、選択的接触、選択的知覚、選択的記憶の3つを取り上げ、詳しいレビューを行なっている。
全般的に、人びとは彼らの既存の態度と関心とに一致したマス・コミュニケーションに接触する傾向がある。意識的にあるいは無意識的に、彼らの既存の態度や関心と反対の色合いをもつコミュニケーションを、彼らは避ける。
共鳴しない内容に接触せざるをえないような場合には、彼らはしばしばその内容を知覚しないか、あるいは彼らの既存の見解に適合するように内容を作り直し、解釈するか、あるいは彼らが共鳴する内容を忘れる度合よりももっと簡単に忘れるのである。こうした自己保護的作用に含まれている過程は、選択的接触、選択的知覚、そして選択的記憶として知られている。(Klapper, 1960, 邦訳p.37)
選択的接触に関する初期の研究
エリー郡調査(ピープルズ・チョイス Lazarsfeld et. al, 1944)
クラッパーによると、選択的接触は、1940年のエリー郡の投票者のなかで、ラザースフェルド、ベレルソンおよびゴーデット(1944, 1948)によって発見された。
〔政党による宜伝)への実際の接触は、メディアの利用可能性によってきまるものではない。利用可能性プラス先有傾向が接触を決定する。そして先有傾向は人びとの意見や態度に適合し彼らの現在の立場を支持するコミュニケーションを選択させる。共和党支持者は民主党支持者よりもより多くウィルキーの演説に耳をかたむけ、民主党支持者は共和党支持者よりもより多くルーズベルトに耳をかたむける。キャンペーン・コミュニケーションの世界(政治演説、新聞記事、ニュース放送、論説、コラム、雑誌記事)は実際にはすべての人に開かれていた。しかし接触は一貫して党派的であった。・・・・・....
全般的に、一貫してある党を支持しつづけた人びと(すなわち5月から投票日まで一貫して共和党支持者あるいは民主党支持者であった人びと)の約3分の2は、反対党の宜伝よりも自分が支持する政党の宣伝を、より多く見かつ聞いたのである。
自分の支持する候補者の選挙活動により多くのインタレストをもち、最大の関心をもっている意見の固定者は、インタレストも低く、関心も低い意見の固定者よりも、接触の点でより党派的であった。このような党派的な接触は党派的な既存の態度を補強する方向にのみ作用することができるのである。結局、もっとも党派的な人びとは反対党の議論にほとんど注意を払わないことによって、それに接触することによって生ずる心の動揺から自分を保護するのである。その代りに、彼らは自分の最初の決定の妥当性と聡明さを再確認する宜伝に向かうしそれは彼らの態度の補強に働くのである。
『ピープルズ・チョイス』によると、1940年のアメリカ大統領選挙において、有権者は自分の先有傾向に合うプロパガンダにより多く接触する傾向が見られた。
8月の時点で確実な投票意図をもっていなかった人びとは、政治的先有傾向の指標(IPP)によって二つのグループに分類される。すなわち、民主党に傾くような社会的特性を備える人びとと、共和党支持の先有傾向を示す特性を備える人びとである。これらの人びとは、まだどのように投票するか態度を決めていなかった。次に政治的コミュニケーションへの彼らの接触状況を以前とは違った角度からみてみよう。ここで興味を引くのは、人びとが接触した材料の範囲ではなく、その材料のもつ政治色である。彼らが読んだり聞いたりしたと報告したすべての演説、雑誌記事および新聞記事を、その政治的内容に従って分類した。このようにして、各回答者の接触傾向を主として共和党支持、主として民主党支持、そして中立の三種類に分類することができた。
通常共和党支持者に特有である経済、宗派、および居住地域にかんする属性を備える投票意図の未決定者は、概して、共和党色の濃いプロパガンダの方をどうにかして見聞きしようとした(図29)。経済、宗派、および居住地域にかんする特性が民主党支持の傾向を示す人びとは、共和党系のプロパガンダよりも民主党系のプロパガンダのほうを三倍も多く見聞きした。
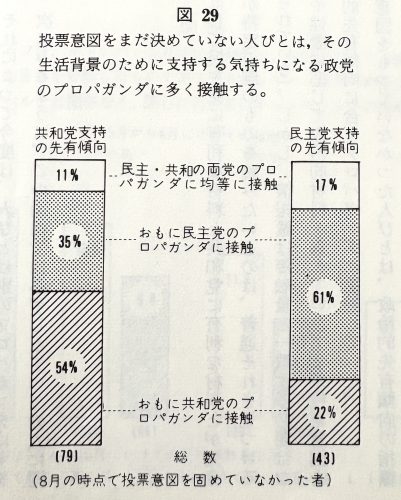
『ピープルズ・チョイス』P.140より
このように、キャンペーンへの選択的接触が既存の態度を補強する方向に作用することが分かったのである。
ハイマンとシーツレイの研究(1947年)
"Some Reasons Why Information Campaigns Fail"
もしすべての人が情報に等しく接触しており、知識の有無がただ単に情報量の違いによって決まるのであれば、同じ個人が一貫して相対的な無知を示す理由は存在しないはずである。しかし現実には、情報の量や性質にかかわらず、こうした無知層はそもそも情報に到達しにくい特性を有している。
情報キャンペーンは事実の提示を伴うものであるが、その内容は、個々人の持つ態度と必ずしも一致するとは限らない。ラザースフェルドは、政治キャンペーンにおけるサンプルパネルの情報接触について、「人々は自らの好みや偏向に一致した政治的資料を選択していた。投票先をまだ決めていない者ですら、無意識のうちに自らの政治的傾向に沿ったプロパガンダに接していた」と述べている。
本論文の筆者が他の情報領域において実施した全国調査の結果もまた、人々が自分の事前の態度と一致する情報には積極的に接し、そうでない情報には接しようとしない傾向、すなわち「選択的接触」の傾向を裏づけている。
まず全国サンプルに対し、ある特定の情報について「聞いたことがあるか」「読んだことがあるか」を尋ねた。その後、すべての回答者に対し、当該情報の要点を1~2文で簡潔に提示した(既知と回答した者には「ご記憶のとおり…」といった前置きを加えた)。続いて、その情報に関連する態度についての質問を行った。
たとえば1946年6月、全国サンプルに対し、パレスチナ問題に関する英米委員会報告を知っているかどうかを尋ねた後、その要点(ユダヤ人10万人の受け入れと、秩序維持へのアメリカの関与)を説明し、「そのような支援に賛成かどうか」を尋ねたところ、事前に情報を知っていた者のほうが支援に対して好意的であった。同様に1946年4月には、英仏米3国によるフランコ政権批判声明を知っていたかを尋ね、その主旨(スペインに民主的政権の登場を望む)を提示したうえで、スペイン政策への態度を問うた結果、情報を既知としていた者のほうがより反フランコ的であった。
これらの顕著な差異は、偶然によるものとは考えにくく、「選択的接触」という現象の存在を強く示唆している。つまり、情報に接したことによって態度が形成されたというよりも、もともとその情報に共鳴しうる態度を持っていた人々こそが、その情報に接していたと考える方が自然である。たとえば、英米報告に接していた人々は、もとからパレスチナへの米国支援に好意的であった可能性が高く、フランコ批判声明を知っていた人々も、もとより反フランコ的であったと推測される。
このように、「人は自身の既存の態度に合致する情報により多く接しやすい」という傾向は、情報キャンペーンを担当する者にとって無視できない要素である。単に「情報の流通量を増やす」だけでは不十分であり、それが結局は「すでに味方である人々」にばかり届いているのであれば、効果は限定的なものにとどまるのである。
シュラムとカーターの研究(1959年)
シュラムとカーター(1959)は共和党支持者で共和党支持のスポンサーが提供する政治キャンペーンのテレビ放送番組をみた人びとは、民主党支持者の約2倍であったことを発見した。
1958年10月31日金曜日午後10時40分から20時間20分にわたって、共和党候補のウィリアム・ノーランドはロサンゼルスでテレビカメラの前に立ち、カリフォルニア州知事選挙における自身の選挙運動を、可能な限り多くの有権者に訴えるためのテレソンを行った。
このテレソンが他に何も成し遂げなかったとしても、少なくとも肉体的持久力における一つの基準を打ち立てたことは確かである。金曜日の朝から土曜日の夜まで、候補者は眠ることなく、電話や遠隔カメラクルーを通じて寄せられた何百もの質問に詳細に答えた。彼はスタジオを行進する様々な国籍の団体や他の代表団を歓迎し、娘の21歳の誕生日をテレビ上で祝った。ゲストと共に選挙問題について議論し、最初の時間から最後の時間まで、彼の選挙戦における二大標的である「労働組合のボスたち」と「カリフォルニアの犯罪」に対し、力強く非難を浴びせ続けた。
この番組は、カリフォルニア州内の複数のテレビ局によって放送された。ノーランド陣営の推定によれば、約7,000件の電話が寄せられ、質問、激励、選挙資金の寄付の申し出があったという。放送中に読み上げられたニクソン副大統領の電報には、彼がこのテレソンについて「輝かしい報告を受けている」と述べ、「この番組が知事選のみならず、カリフォルニア州における共和党候補全体に対しても、何千もの新たな支持者をもたらすであろう」との自信が示されていた。
このテレソンは、選挙戦終盤に差し掛かっていた時期において、ノーランド候補に不利な流れを食い止めるべく挿入された、重大な取り組みであった。では、この試みは何を成し遂げたのであろうか。テレソンという手法は、放送メディアによる説得の他の試みにおいて(例:ケイト・スミスによる戦時国債販売)成功を収めた実績があり、政治キャンペーンへのテレビの貢献としてしばしば検討されるものの、実際にはあまり試みられてこなかった。このため、本手法の効果を問うことは、カリフォルニア州以外にとっても重要な意義を持つ。
このテレソンが放送された主要な都市の一つにおける効果を把握するため、スタンフォード大学コミュニケーション研究所は、番組放送の4日後に、サンフランシスコの電話世帯を対象とした確率標本に基づき、563件の電話インタビューを実施した。この563名のうち、28%(158名)は政党支持を明かさなかった。政党を明示した者のうち、65%(263名)が民主党支持、35%(142名)が共和党支持と回答した。(なお、11月4日の投票において、サンフランシスコは約70対30でノーランドの民主党対立候補に投票した。)我々がインタビューを行った563名のうち、11.5パーセント(65名)がテレソンの一部でも視聴したと答えた。この65名の内訳は、共和党支持者が31名、民主党支持者が27名、政党を明かさなかった者が7名であった。これらを全体サンプルと比較し、割合で比較すると、顕著な差異が見られる。明らかに、共和党支持者は民主党支持者に比べて約2倍の確率で番組を視聴していた。また、「共和党支持の家庭」では、平均1.87人が番組の一部を視聴していたのに対し、「民主党支持の家庭」ではその平均はわずか1.41人であった。
なお、番組を偶然発見した視聴者の割合は、民主党支持者では67パーセントであったのに対し、共和党支持者では48パーセントであり、民主党支持者の方が偶然視聴した割合が高かった。テレソンによって視聴者の投票意図に大規模な変化が生じたとは言い難い。認知の変化はほとんどなく、それに伴って態度変容も少なく、行動の変化も限られていた。視聴者65名のうち2名のみが、「番組によって投票の意思を決めた」と回答した。そのうち1人はノーランドへの投票を決め、もう1人は彼に投票しないことを決めた。また、ある共和党支持者は、当初は民主党候補ブラウンに投票するつもりであったが、番組視聴後に党派意識を強め、ノーランドに投票することに決めたと述べている。
考察:テレソンはどれほど効果的であったか
本調査は、ラザースフェルド、ベレルソン、ガウデットの『ピープルズ・チョイス』における経験的知見、およびフェスティンガーの『認知的不協和理論』に基づく一般化――すなわち、有権者は自らの傾向性を強化し、不協和を減じるためにメディアに接触する傾向があり、相手側の主張を知るためではない――を裏付ける結果となっている。すなわち、共和党支持者は主に共和党の話を聞き、共和党的資料を読み、共和党支持者同士で議論する傾向があり、民主党支持者についても同様の傾向が見られる。本件においても、まさにそのような現象が起こっていた。共和党支持者は、民主党支持者よりも遥かに高い割合で番組を視聴し、事前に番組を知っており、他者に知らせ、番組について語っていた。また、彼らが番組を知らせた相手や議論相手も主に共和党支持者であったようである。
このテレソンの主な効果は、ノーランド上院議員に対する既存の印象と既存の投票意向を再確認・強化することであった。このことは、視聴者の中には番組の技術的巧みさを評価する者や、共和党・民主党双方の視聴者の間でノーランドの耐久力、雄弁さ、人柄や人格の強さに敬意を示す者がいたことを認めたとしても変わらない。番組がサンフランシスコにおいて大規模な票の動きを引き起こしたとは考えにくい。
この結果をもたらした要因として、2つの点が挙げられる。
第一に、少なくともサンフランシスコにおいては、テレソンの事前宣伝が不十分であった。高額な費用が投じられたこの目を引く番組について、視聴者の半数以上が偶然発見したと回答していることは驚きである。電話世帯の確率標本において視聴者が12パーセント未満であったこともまた、注目すべき結果である。この番組に対して行われた広報活動は、例えばケイト・スミスによる戦時国債販売マラソン番組のような、注目を集めた番組と比較する必要がある。
第二に、このノーランドのテレソンは、選挙戦の終盤において実施されたものであり、この時点で政治的説得の手段はすでに出尽くしており、情勢は明らかに共和党に不利に傾いていた。ノーランド上院議員は、まるで押し寄せる波に対抗しようとしていたようなものであった。世論調査および本調査の結果から判断しても、10月末の時点でサンフランシスコの有権者の多くはすでに投票先を決めていた。
まず大多数の人々がすでに心を決めていた。民主党への潮流はすでに確立されていた。宣伝不足により、視聴者数は少なく、かつその多くが共和党支持者に偏っていた。テレソンは期待されたほどの議論を巻き起こさなかったが、それはおそらく選挙戦が終盤に入っており、多くの有権者の判断がすでに固まっていたためである。
番組について語った人々は、主に共和党支持者であり、その語り相手もまた共和党支持者であった。民主党支持者は偶然あるいは好奇心から番組に出会ったが、彼らは共和党候補に対する既存のイメージをそのまま番組内容に重ねて見ていた。共和党支持者は偶然または忠誠心から番組を見て、やはりノーランドに対する印象を再確認していた。
回顧的に見て、民主党支持者にとってこのテレソンは単なる選挙戦の一手段に過ぎなかったと捉えられている。一方、共和党支持者にとっては、それは劇的な悲劇の一幕として記憶された。「彼はあまりに素晴らしい人物であり、こんなことをしてまで認知される必要はなかった」と語り、「私は悲しくなった」と述べた共和党支持者の言葉がそれを象徴している。
選択的接触の原因としての「認知的不協和」
人の心にある「認知的不協和低減」のメカニズムが選択的接触(選択的回避)の原因であることを初めて発見したのは、社会心理学者のL.Festinger(1957)だった(D'Alessio, D., & Allen, M. , 2007)。
個人は自分自身の内部に矛盾がないようにと努力する。人の知識や信念と,かれの行動との間にも同種の無矛盾性が存在する。大学教育はよいものだと信ずる人は、おそらく、自分の子どもが大学へ行くことを奨励するであろう。健康に悪いと知りながら喫煙をつづけている人は、またこんなふうにも感じているであろう。
(a) 自分は喫煙を非常に愉しみにしているので、それだけの価値はあるのだ。
(b)自分の健康をそこなう可能性は、ある人々がいうほど重大ではない。
(c)自分は、起こりうるあらゆる危険な事故を避けることはできないとしてもともかくこうして生きているではないか。
(d)おそらく、たとい煙草をやめても体重が増えるであろうから、健康に悪いという点では同じことである、と。
このように,喫煙をつづけるということは、けっきょく、かれの喫煙に関する考え方と矛盾してはいないのである。 しかしながら、人々はいつも自分自身に対してそのような矛盾をうまくいい抜け,また合理化することに成功するとはかぎらない。なんらかの理由で,無矛盾の状態に到達しようとする試みが失敗するかもしれない。そのときには矛盾はそのまま存続する。このような事情のもとでは一すなわら、矛盾が存在しているばあいには一心理学的にみて不快の状態が存在することになる。
フェスティンガーは、く矛盾>という言葉を,「不協和(dissonance)」という言葉に、<無矛盾>という言葉を「協和(consonance)」という言葉に置き換え、次のような基本的仮説を立てた。
1. 不協和の存在は、心理学的に不快であるから、この不協和を低減し協和を獲得することを試みるように、人を動機づけるであろう。
2. 不協和が存在しているときには、それを低減しようと試みるだけでなく、さらに人は不協和を増大させると思われる状況や情報を、すすんで回避しょうとするであろう。
不協和の存在は、不協和を低減しまたは除去する圧力を生成しめる。不協和を低減する圧力の強さは不協和の天ききの関数である。いいかえれば、不協和は動因、要求または緊張の状態と同じように作用する。不協和の存在は、例えば、飢えの存在が飢えを低減させる行為に導くのとちょうど同じように,不協和を低減させる行為へと導く、また。動因から生ずる行為と同じように,不協和が大であるほど,不協和を低減させる行為の強さは大であり、不協和を増大させるような状況を回避する傾向も大となる。一般に,二つの要素の間に不協和が存在するとき、これらの要素の一方を変化させることによって、その不協和を除去することができる。
行動に関する認知要素を変えること
考察の対象となっている不協和が、環境に関する知識に対応する要素(環境要素)と行動に関する認知要素(行動要素)との間に存在するばあい。不協和は、いうまでもなく、行動に関する認知要素を環境要素と協和するように変化させることによって除去することができる。これを達成するもっとも簡単な、もっとも容易な仕方は、行動要素の中に表現されている当の行為や感情自体を変化させる、ということである、認知がく現実>を反映するものとすれば(このことについてはすでに考察した),生活体の行動が変わるにつれて、その行動に対応する認知要素も同様に変化するであろう。不協和を低減または除去するために,こうした方法が取られる例はきわめて多い。われわれの行動や感情は新しい情報に即応してしばしば変容する。ある人がピクニックに出かけ、雨が降りはじめたことを認めたとすれば、かれはおそらく踵をかえして帰宅するであろう。喫理が自分の健康によくないということを発見したならば,その場で煙草をやめてしまう人々もたくさんいる。
しかしながら、自分の行為や感情を変化させることによって、不協和を除去しまたは実質的にそれを低減させるということが、つねに可能であるとはかぎらない。行動を変えることの困難さがあまりに大きすぎるかもしれないし、また変化によってある不協和が除去されたとしても、多くの新しい不和が別個に創り出されるかもしれない。これらの問いについては以下にもっと詳細に論じよう。
環境に関する認知要素を変えること
行動要素の中に反映されている当の行動自体を変化させることによって、行動に関する認知要素を変化させることが可能であるのとちょうど同じように、環境要素に対応する状況を変化させることによって、環境に関する認知要素を変化させることもしばしば可能である。このことは、もちろん自分の行動を変化させることよりもはるかに困難である。というのは、自分の環境に対して十分高度の統制力を持っていなければならないからである。しかし、そうした例は比較的まれである。
不協和を低減させるために環境それ自体を変化させるということは、物理的環境が問題となっているときよりも、社会的環境が問題となっているときの方がいっそうその可能性が大きい。そこに含まれている事態をややドラマチックに例示するために、幾らかこっけいな架空の例をあげてみよう。自宅の居間の中をあちらこちら歩きまわっている人が、どういう理由かわからないが、床の上の一定の場所までくると、いつもピョンと跳びこえると仮定しよう。この場所を跳びこえるということに対応する認知要素は、この場所の床が平らでしっかりしており、いかなる点でも他の部分と異なっていないといろかれの知識と疑いもなく不協和である。ある晩、妻が外出しているとき,かれが床のちょうどその場所に穴をあけたとすると、かれは不協和を完全に除去したことになるであろう、床に穴があるという認知は、穴のある場所を跳びこえるという知識と全く協和するであろうから。つまり、かれは現実に環境を変えることによって、認知要素を変え、かくして不協和を除去したことになる。
環境に対して十分な統制力を持っているときには、不協和を低減するためにこうした方法が用いられるかもしれない。例えば、他人にいつも非常な敵意を持って対している人は、かれ自身も敵意を挑発するような人たちによって取りまかれることになるであろう。かれが接している人々についての認知は、したがって、敵意のある自分の行動に対応する認知と協和的である。しかしながら、環境を操作する可能性には限度があるから、認知要素を変えようとする努力は大部分は別な方向を取るであろう。
現実を反映する認知要素が,それに対応する現実を変えないでそれ自体変化しなければならないばあいには、現実の状況を無視し、またはそれに反対するためのなんらかの手段を用いなければならない。それは、精神病者のような極端なばあいを除いては、しばしばほとんど不可能である。ある人が雨のなかに立って、みるみるうちに濡れねずみになったとしよう。そのとき、たとい雨が降っているという認知を除去しようとする心理学的圧力がいかに強くても、かれはほとんど確実にその認知を持ちつづけるであろう.ところが、ときには、現実がそのままであっても、認知要素を変えることが比較的容易なばあいもある。例えば,政権担当者の行動や政治情勢が一般に変化しないでも、当の政権担当者についての意見を変えることはできるであろう。通常こうしたことが起こるためには、かれの新しい意見に賛同し,それを支持してくれる他の人々を見出すことができなければならない。一般に、認知を変化させる圧力が存在するとき、他の人々の賛同および支持を得ることによって社会的現実(social reality)を確立するということは、認知を変えるための主要な方法の一つである。容易に理解されることであるが、こうした社会的支持が必要であるとすれば、不協和の結果として認知要素を変えようとする圧力が発生すると、それにともなって種々の社会的過程が起こってくるであろう.この論点は、不協和を低減させる圧力の社会的なあらわれ方を考察する第8,9,10章において、詳細に展開されるであろう。
新しい認知要素を付加すること
明らかなことであるが,不協和を完全に除去するためには、ある認知要素が変化しなければならない。ところが、それがつねに可能であるとは限らないということも明白である。しかし、たとい不協和を除去することが不可能であるとしても,新しい認知要素を付加することによって不協和の総量を低減させることは可能である、かくして、例えば、喫煙の影響に関するある種の認知要素と,喫煙をつづけているという行動に関する認知との間に不協和が存在するとき、喫煙の事実と協和するような新しい認知要素を付加することによって、不協和の総量を低減させることができる。このような不協和が存在するばあいには、したがって、人は不協和の総量を低減させる新しい情報を積極的に捜し求め,それと同時に、既存の不協和を増大させるような新しい情報を回避しようとすることが期待される。かくして、さきの例をつづけると、人は喫煙が健康に有害であるということを証明しようとする研究に対して批判的な資料を捜し求め、熱心にそれをむさぼり読むであろう。それと同時に、かれはこの研究を賞讃する資料を読むことを回避するであろう(もしもかれが後者のタイプの資料に接することを避けられないときには、かれの読み方は全く批判的であろう)。
実際、既存の不協和を低減させるような新しい要素を付加する可能性はいろいろある、例えば、わが喫煙者は自動車事故や自動車による死亡率についてすみずみまで調べあげるかもしれない。喫煙の危険性は、自動車を運転しているときに遭遇する危険性と比較すれば問題にならないという認知を付加することによって、かれの不協和もまたいくらかは低減されるであろう。このはあいには、既存の不協和の重要性を減ずることによって,不協和の総量が低減されるのである.
上述の所論は、ある要素を含む協和関係に対して不協和関係が占める割合を減ずることによって、その要素に関する不協和の総量を低減させる可能性があることを示している。また,不協和な二つの要素をある意味でく和解させる>ような新しい認知要素を付加することも可能である!このことを例証するために、文献のなかから一つの例をひろって考察してみよう。スパイロ(Spito)は文字を持たない社会であるイファルク族(Ialuk)の信念体系のある面について説明している。ここでのわれわれの目的に関連する点はつぎのとおりである。
1. この文化においては、人は善良である、という確固たる念が存在している、この信念は、人は善良でなければならぬというだけでなく、人は現に善良なのである。
2. なんらかの理由によって、この文化に属する幼少の子どもたちは、とくに強い,むきだしの攻撃性,敵意,および、破壊的性癖の一時期を経験する。
人の本性に関するかれらの信念が,この文化の中に住む子どもたちの行動に関する知識と不協和であることは明らかである。こうした不協和を低減させる仕方は幾とおりもあったであろう.かれらは人の本性に関する信念を変えることもできたであろうし、また成人した人だけが完全に善良なのだというように、その信念を変えることもできたであろう。またかれらはく良いもの>く良くないもの>に関する考え方を変え、幼少の子どもたちにおけるむきだしの攻撃性は良いことなのだと考えてもよかったろう。ところが現実には不協和を変える仕方はこれらと異なっていた。<和解>によって有効に不協和を低減させる第三の信念が付加された。はっきりいうと、かれらは、また,人々に乗りうつって悪事を働かせる意地悪な亡霊の存在をも宿しているのである。
この第三の信念によって、子どもたちの攻撃的行動に関する知識は、人は善良である,という信念ともはや不協和ではない。攻撃的な行動をするのは子どもたちではないーそれは意地悪な亡霊である。このような信念が文化の水準において制度化されていることから考えても,心理学的にみて、これは不協和を低減させるための高度に満足な手段であると思われる。不満足な解決ならば、このように広く受け入れられることに成功しなかったであろう。
不協和を低減させる圧力の存在、あるいはそのような低減に向けられる活動でさえも、かならず不協和が低減されるということを保証するものではない.さきへ進むまえに、このことはもう一度強調しておく価値がある。人は認知要素を変化させるために必要な社会的支持を見出すことができないかもしれないし、また不協和の総量を低減させる新しい要素を見出すことができないかもしれない。事実、不協和を低減させようと試みる過程において、不協和がかえって増大することすら考えられる。これは、その人が不協和を低減させようと試みるさいにどんなことに遭遇するか、ということに依存するであろう.いままで強調してきた重要な点は、不協和が存在すると,それを低減させるために数々の試みが見られるということである。不協和を低減させる試みが失敗に終ったばあいには、心理学的不快の数々の徴候が観察されるはずである。もっともこれは、不協和が人目につくほど十分に大きくて、不快が明瞭に外部に表明されると考えたばあいの話であるが•・・・・
不協和の回避
これまでの所論は,不協和を伝減しまたは除去する傾向。および、そのような低減を達成するさいに含まれる数々の問題に焦点をおいてきた。ところが、ある事情のもとでは、不協和の増大または不協和の発生を全面的に回避しょうとする強い重要な傾向が存在することもある。われわれはこのような事情を考察し,そのさい観察されるであろうと期待される回避傾向の現われ方に注意を向けることにしよう。
不協和の増大を回避しようとする傾向は、もちろん不協和が存在する結果として現われてくる。不協和を任減しようと試みる過程において、既存の認知要素のかわりに新しい要素への支持が求められているばあい、または新しい要素が付加されねばならないばあいには、この回避はとくに重要である、このいずれの事情においても、支持を求め、新しい情報を求めるということは、高度に選択的な仕方でなされるはずである。人は新しい認知要素に賛成するだろうと思われる人とはすすんで話し合うであろうが、変化させようと努力している当の要素に賛意を表するかもしれないような人との話し合いは、回避するであろう。かれは、協和を増大させる新要素を付加するであるうと期待されるような情報源には、進んで接触しょうとするであろうが、不協和を増大させるかもしれないような情報源は、きっと回避するであろう。
これまで心理学者たちは決定過程(decision-making process)に多大の注意を払ってきたが,決定が下された後に生じる諸問題は、ごくまれにしか認識されなかった。決定を下すということにひきつづいて生じる主要な現象の一つは不協和の存在ということである。決定の重要性(importance)は決定が下された後の不協和の大きさに影響するであろう。他の条件が等しければ、決定の重要性が大きいほど不協和は強いものとなるであろう。したがって、ある型の自動車をやめて別な型の自動車を買うという決定は、ある商標の石鹸をやめて別な商標の石鹸を買うという決定よりも大きい不協和を生じるであろうし、ある職を捨てて別な職に就くという決定は、音楽会を諦めて映画に行くという決定よりもいっそう大きな不協和を生み出すであろう。これから先の章でも再三この重要性という変数に触れるであろうが、これは不協和の大きさを規定する一般的な決定要因だからである。ところで、決定後の状況に特有な諸問題の考察へと進むことにしよう。 決定後の不協和の大きさを規定するもう一つの主要な決定要因は、選ばれなかった選択肢の持つ相対的魅力(relative attractieness)である。このことは、いうまでもなく、決定後の状況についてのわれわれの分析と、不協和が存在するそもそもの理由とを考えあわせれば、おのずから帰結される。不協和が存在するわけはこうである。すなわち、決定を下してしまった後でも。その本人は、かれの認知のなかに、それだけ単独に考えたばあい、現にかれが採択し,また,従事しているのとは別な行為へと導いたであろうような数数の要素を依然として保持しつづけている、これらの要素は、選ばれなかった選択肢の望ましい諸持性と,選ばれた選択肢の望ましくない諸持とを反映している。したがって、選ばれなかった選択肢が選ばれた選択肢に対して持つ相対的魅力が大きければ大きいほど、決定という行為に対応する認知と不協和な関連要素の割合は大きくなるであろう。
決定後の不協和を低減しようとする圧力の現われ方の一つは、自分の行なった行為と協和する認知を提供してくれそうな情報を探索する、ということであるから、広告の読み方を調べれば,そこから一つのデータが得られるであろう。このことをもう少し詳細に検討してみよう。広告が持っている種々の目的や、広告が人々の注目を引くのに用いるいろいろの巧妙な手口についてはこのさいとりたてて考えないということにすると、そこにはだれもが経験にもとづいて知っているところの。すべての広告に共通な少なくと一つのことがらが残ることになる。つまり,広告というものはいつでもそれが広告しようとしている製品のことをよくいうものだということである。広告にはその製品がなぜよいのかを一般的または特殊的な仕方で述べてあることもあり、その製品が他の有象無象の競争品とくらべてどんなに優れているかをこと細かに述べてあることもある。したがって広告は,明らかに,その広告に出ている特定の製品を購入したことに対して協和的な認知を提供してくれる潜在的な源泉である。それは不協和の解消を求める人々が好んでよりどころを求める源泉であるともいえよう。
最近ある製品を購入した人々は、多分決定の過程を経てその選択を行なったであろう。新しい自動車を購入したばかりの人は、おそらくその前に方々の店をまわり、いろいろな型を検討したあげく、ある特定の車種の車を購入することに決定したにちがいない。背広を買おうとする人も同様にするであろう。かれはしばしば方々の店を十分あさり歩いた上でなければそれを購入しないであろう。食料品店を訪れる家庭の主婦でさえ、陳列してあるいろいろな銘柄の確詰スープを見てまわった上でどれかを選ぶであろう.したがって、なにか新しい買物をした人は,最近決定を下した人だとみなすことができる。これまでの所論から、そういう人は自分の下した決定に対して不協和ななんらかの認知要素を持っていると予想され、また不協和低減への圧力のなんらかの現われが観察されるであろうと思われる。自分の買った製品の広告を読むことは、その買物をしたという認知に対して協和的な情報を与えることになり、結局、不協和を低滅させることになるであろう。競争品の広告を読むということは、おそらく不協和を増大させることになるであろう。
もしこの理論が正しいならば、最近なんらかの買物をした人は,それが重要なものであるばあい、自分が買った製品を作っている会社の広告をよく読み、競争会社の広告を読むことを避けるはずである。
例えば新しい自動車を購入するということは、通常、その人にとってかなり重要な決定である。新車の持ち主には、その車を買った直後からかなりの不協和が存在するはずである。一応考慮はしてみたが実際には買わなかったいろいろな車種の車のあらゆるく長所>と,自分が買った車の<短所>とは、いまや自分がその車の持ち主であるということと不協和である。そこで,かれはさらにこの不協和を低減しようと試みるであろう[Festinger, 1957, p.98].
たしかに,この決定後の不協和を低減させようと試みる仕方は、たくさんあるであろう。しかし,この研究は、それらの可能性のうちの一つ、つまり、自分のとった行為の認知と協和するような認知要素をもっとたくさん獲得し、その行為と不協和な認知要素の獲得を回避することによって不協和を低減するばあいだけを取り扱っている。上の研究者たちのいうところによれば、自動車の広告には、広告しようとしている車種の車だけを礼讃するような材料が含まれているから、つぎのような結果が期待されるであろう。
- 新しい車の持ち主たちは、買ったばかりの車に関する広告を、他の型の車の広告よりも、たくさん読むであろう。
- 新しい車の持ち主たちは、かれらが一度は考慮してみたが実際には買わなかった車に関する広告を読むことを回避しようとするであろう。
- 同じ車でも古い型の持ち主たちは車の広告を読む上で,ほとんど、または全然このような差別をしないであろう。なぜなら、かれらの不協和はすでに大部分除去されているか、あるいは少なくとも安定化しているであろうから、それに,最新型のあらゆる魅力的な特徴を強調している新車の広告では,2年前の古い型の車を持っている人の心にまだ残っている不協和を低減させるわけにはいかないであろう。
ミネアポリス地区に住む成人男子65人に対し,かれらが新しい自動車を買ってから4週間ないし6週間後に面接を行なった。これとは別に、居住地という点では上の新車購入者たちとほぼ対等であるが、3年以上も前の古い型の自動車を持っている成人男子60人に対しても面接を行なった。各回答者にはあらかじめ電話で連絡をとり、面接の時間を打ち合わせた。そのさい。この面接は雑誌や新聞の読に関する調査の一部であるという説明を与えて、回答者がふだんどんな雑誌や新聞を読んでいるかをたずねた。調査員は、回答者の家を訪れるとき、回答者がふだん読んでいるといった雑誌を訪問前の4週間分携えて行った。4週間という時間間隔を選んだのは,新車購入後これだけの期間が経てば、どんな雑誌も新しい号が出るからである。この時間間隔は、いうまでもなく、古い型の車の持ち主たちにたいしても同じように守られた。調査員はまた、回答者が読んでいるミネアポリスの新聞を訪問日の7日前の分まで携行した。
面接時間の大部分は、上に述べた新聞や雑誌に掲載されている自動車の広告を一つ一つ回答者に示し,それが回答者の目についたかどうか、目についたとすればさらにその広告を全部ないし一部読んだかどうかをたずねることに費やされた。面接の終りに、回答者はいまの車を買う前に真剣に考慮してみたことのある車の名をあげるように求められた。調査の結果は、回答者の目についた広告のパーセントの平均値および目についたもののなかで、かれらが読んだ広告のパーセントの平均値という形で第1表に示されている。
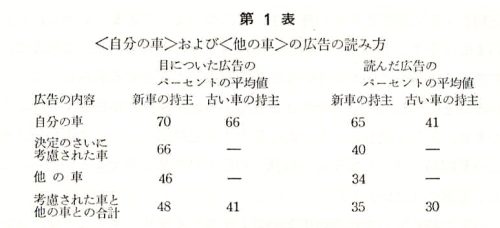
まず新車の持ち主について検討しよう。かれらには自分の買ったばかりの車に関する広告の大部分(70%)が目についていることは明らかである。さらにまた,それらの目についたく自分の車>の広告を並はずれた高い割合で読んでいたことも明らかである。新車の持ち主は自分が買った車に関する広告の平均65%を読んでいる。これに対し、他の車,つまり決定にさいして全然考慮されなかった車に関する広告のうち、かれらの目についたものおよび読んだもののパーセントはそれぞれ46%と34%であった。不協和の理論から導かれた予測はこれまでのところ明確に支持されている。決定にともなって不協和が生じると、新車の持ち主たちは自分たちが買ったばかりの車の広告を読むことによって、その不協和の低減を図ろうとするのである。(Festinger, 1957)。
このように、フェスティンガーは、人々が認知的不協和を低減させるために、広告などの情報に選択的に接触ないし回避する傾向があることを実験によって明らかにしたのである。
選択的接触仮説に関する批判的レビュー ( Freedman & Sears, 1965)
本研究の目的は、まず「選択的接触」の意味を明確化し、それが使用される根拠となる証拠を特徴づけ、最後に支持的情報を非支持的情報より好む心理的傾向が存在するか否かに関する証拠を評価することにあった。
ラザースフェルドらは選択的接触を次のように述べている。「接触は常に選択的である。言い換えれば、人々の意見と彼らが選んで聴いたり読んだりするものとの間には正の関係が存在する」と。リプセットらは「ほとんどの人は、ほとんど常に、自分が最初から同意している種類のプロパガンダに接触する」と述べた。クラッパーはこの点を次のように要約している。「概して、人々は自分の既存の態度に一致するマスコミュニケーションに接触する傾向がある」。チャイルズは次のように結論づけている。「数え切れないほどの研究が、読者が自分が同意し、賛成し、または好むものを読む傾向があることを示している」。これらは単なる記述的な主張であり、コミュニケーションの受け手が通常、発信者の視点を異常な程度に共有していることを主張しているに過ぎない。このような偏向の原因については何も述べられていないため、この形式の選択的接触仮説を「事実上の選択性」(de facto selectivity) と呼ぶことにする。
事実上の選択性の原因は非常に明確である。人々はすでに同意しているコミュニケーションに接触し、同意していないものには接触しない。それは、前者を積極的に求め、後者を積極的に避けるからである。その理由は、おそらく、心理的に互換性のある情報を好む一般的な傾向によるものであろう。本論文は意見や態度に焦点を当てているため、これらの定義のうち最初の一般的なものについては議論しない。したがって、以下では、これら二つの意味における選択的接触の証拠を検討することとする。本稿の残りの部分では、一貫性を保つため、それらをそれぞれ「事実上の選択性」と「選択的接触」と呼ぶこととする。
事実上の選択性
マスコミュニケーションへの任意の聴衆の構成における偏りは、調査研究でしばしば報告されている。このような偏りは、しばしば発信者が強調する意見の次元と一致し、聴衆と発信者との間で異常に高い初期の一致の方向に進む。大規模な集会もまた、偏った聴衆を引きつける傾向がある。長期間にわたるプロパガンダキャンペーンもまた、事実上の選択性を引き起こす傾向がある。古典的な発見として、ラザースフェルドらの研究がある(ピープルズ・チョイス)。また、やや異なる領域ではあるが、エアリッヒらの研究によれば、新車を購入したかどうかに関わらず、人々は自分が購入した車の広告を他の車の広告よりも多く読んでいた。
選択的接触への疑問
選択的接触の代表例としてほぼ必ず引用される、ラザースフェルド、ベレルソン、ゴーデットによる古典的な研究における効果の強さを考察する。この研究では、回答者が主に自分の性向を支持するプロパガンダに接触していたことが確認された。しかし、政党ごとに詳細に分析すると、この結果は共和党の性向を持つ人々にのみ当てはまることが判明する。民主党の性向を持つ人々は、選択的接触どころか、ほぼ均等に分かれており、50.4%が民主党のプロパガンダに主に接触し、49.6%が共和党のプロパガンダに主に接触していた。したがって、実際に選択的だったのは共和党支持者だけであるように見える。しかし、共和党支持派と民主党支持派のプロパガンダの相対的な提供量を考慮すると、この結果はさらに逆説的になる。実際、選挙運動中に利用可能だった党派的プロパガンダの68.8%が共和党寄りであった。そのため、共和党支持の性向を持つ回答者の69.7%が主に共和党寄りの情報に接触し、30.3%が主に民主党寄りの情報に接触していたのは、ほとんど驚くべきことではない。共和党支持者の接触状況は、利用可能な情報の党派的分布とほぼ一致していた。事実、この観点から見ると、民主党支持者こそが選択的接触をしていたと考えられる。というのも、民主党支持者は実際には民主党と共和党のプロパガンダを同量接触していたが、偶然よりもかなり多くの民主党のプロパガンダに接触していたからである。
測定の問題
それにもかかわらず、多くの事実上の選択性に関する報告は、使用された測定方法の性質により、効果の大きさを過大評価している可能性がある。最も明白な問題は、ほとんどの研究で単一のインタビューのみが使用されている点である。このインタビューで、態度と接触が同じ側を支持している場合、その解釈は曖昧になる。整合性は、態度変化を反映している可能性もあれば、事実上の選択性を反映している可能性もある。しかし、例えば特定の広告が現れる前に特定の車を購入したことが知られている場合や、パネル研究のように態度や選好が明確に接触の機会に先行していることが証明されている場合には、曖昧さは生じない。しかし、ほとんどの研究ではこれを許容せず、回答者が正確に記憶していることに期待するか、態度変化の可能性を完全に無視するか、それを否定しようとするしかない。これらのどれも事前測定の代わりにはならず、各方法が事実上の選択性を検出する可能性を最大化する。なぜなら、態度変化は通常、コミュニケーションと回答者の立場の間の不一致を減少させる可能性が高いからである。
第二に、ほとんどの研究が接触に関する遡及的な自己報告に依存しており、接触を直接的かつ即時的に観察していない点も問題である。このような方法がどのような偏りを引き起こすのかを確実に述べることはできないが(選択的記憶や選択的報告などによる)、いずれの研究においても体系的な偏りが生じる可能性が非常に高い。この欠点を克服することは、もちろん非常に困難である。
これまでの研究から、選択的接触に関する一貫した結果は得られていないことが明らかである。以下のように、結果はばらついている。
- 支持的情報への選好を示した研究: エアリッヒら(1957年)、フリードマンとシアーズ(1963年)、アダムズ(1961年)、ミルズら(肯定的な記事、1961年)、ローゼン(肯定的な記事、1961年)
- 特定の選好を示さなかった研究: ミルズら(否定的な記事、1959年)、フェザー(非喫煙者のみ、1962年)、フェザー(1963年)、ミルズとロス(1964年)、ジェッカー(1964年)、シアーズ(1966年)、シアーズとフリードマン(1963年、1965年)
- 非支持的情報への選好を示した研究: ローゼン(選択の逆転記事、1961年)、ブロドベック(1956年)、フェザー(喫煙者のみ、1962年)、シアーズ(1965年)、フリードマン(1965年)
このように、利用可能な証拠は、支持的情報に対する一般的な選好の存在を示すには不十分である。
結論
本論文は、情報への自主的接触における選択性の存在に関する証拠を評価することを主な目的としている。事実上の選択性の存在についてはいくらかの証拠が存在するようであるが、それはしばしば主張されるほど明確ではない。マスコミュニケーションの多くの聴衆は、提唱されている意見にすでに共感している人々が過剰に代表されているようであり、多くの人々が自分の意見を支持するコミュニケーションに不均等に接触しているように見える。
一方で、多くの実験研究では、支持的情報への一般的な心理的選好を示す証拠は見つかっていない。一部の状況では、人々は自分の意見を支持する情報を好むように見えるが、他の状況では、自分の意見と矛盾する情報を好むようにも見える。現在の証拠から、人々が一般的に支持的情報を積極的に求め、非支持的情報を避けると主張することはできない。
これらの二つの結論は矛盾しているように見える。どうして人々は事実上選択的でありながら、支持的情報への一般的な選好を示さないのか。本稿で述べた多様な回答をここで繰り返す必要はない。一般的に、事実上の選択性は、多くの要因によって複雑に決定されるコミュニケーション環境から生じる。これらの要因は情報の支持性とは無関係であることが多い。具体的には、本稿ではこのような要因のうち三つを検討したが、重要な要因はさらに多く存在することは確実である。これらの要因自体が、場合によっては事実上の選択性を生み出すことがある。
一つの一般的な可能性として、これらの要因は自然なコミュニケーション環境において、情報の支持性と無作為には関連していない場合が多いと考えられる。たとえば、特定の種類の情報を最も有用だと感じる人々は、偶然にもその情報が支持する編集方針と一致する傾向がある。金融業界の人々は『ウォール・ストリート・ジャーナル』の財務ニュースを非常に有用だと感じ、同時にその政治的立場にも(おそらく偶然に)同意する傾向がある。大学教授や外交官は『ニューヨーク・タイムズ』の包括的なニュース報道を信頼し、その社説にも同意することが多い。これらは単なる偶然ではなく、必ずしも選択的接触の例でもない。ただし、これらの相関の理由を探ることは本稿の範囲を超えている。
別の可能性として、選択性は短期的よりも長期的において重要であるかもしれない。多くの人々は、特定の機会に非支持的情報に接触することをいとわないかもしれない。しかし、それは疲労や不満を引き起こす可能性があり、特に知的な努力を要する場面でのみ行われる傾向がある。したがって、特定の時点で選好の劇的な選択性は現れないかもしれないが、長期にわたって、人々は自分の環境を事実上の選択性を確保する形で組織する可能性がある。この点に関連するデータは主に友人や配偶者の獲得に関するものであり(情報や接触の選好に関するものではない)、これも本稿の範囲を超えている。しかし、この議論は興味深く、巧妙に収集されたデータが存在する。
最後に、この研究は、人々が矛盾した情報にどのように対処するかについての考え方に変化をもたらす可能性がある。これまで、選択的接触やその他の情報受信を妨げるプロセスが、人々が影響を拒む主要なメカニズムと考えられてきた。しかし、こうしたプロセスが実際にはそれほど重要ではない可能性がある。たとえば、フェザーは、喫煙者が喫煙と肺がんに関する不快な情報を読むことを避けるのではなく、それを慎重に、そして容赦なく批判的に吟味することを報告している。このことから、影響への抵抗は、情報の選択的受信や回避よりも、情報の評価のレベルで最も成功裏に行われることが多いのではないかと思われる。
認知的不協和理論の改訂(Festinger, 1964)
Festinger, L. (1964) Conflict, decision, and dissonance. Stanford, CA: Stanford University Press.
不協和理論の発展、特に「強制的服従」の領域における研究により、不協和が成立するための二つの必要条件が明らかになった。それは、選択(choice)とコミットメント(commitment)である(Brehm & Cohen, 1962 を参照)。これら二つの変数が選択的接触においてどのような役割を果たすかについては、これまで十分な研究がなされていないが、それらが影響力を持つ可能性は高いと考えられる。実験において選択的接触効果が得られなかった理由の一つは、こうした変数を軽視していたことにあると説明できよう。
この点において、フェスティンガー(1964年)による不協和理論の改訂版は、選択的接触の理解にとって一層重要である。
改訂版においてフェスティンガー(1964)は、不協和的な情報は常に回避されるわけではなく、調和的な情報が常に好まれるわけでもないと主張した。彼は、不協和的情報が望まれると想定される以下のような条件を提示した。
1. 不協和的情報が容易に反論可能であると認知されている場合
ある人が、自らの信念と矛盾する情報を容易に反駁または抵抗できると感じているならば、その情報を積極的に求め、不協和の状態を反論によって軽減しようとするであろう。反対に、その情報が容易には反論できないと判断される場合には、それを回避する傾向が強まる。したがって、ここで決定的となるのは、不協和的情報に対する自己の反駁能力に対する自信である。
2. 不協和的情報が将来の意思決定にとって有用である場合
不協和的情報を無視することが、将来において誤った意思決定につながり、結果としてより大きな認知的不協和を引き起こすと信じる場合、人はこの情報を回避せず、むしろ求める可能性がある
3. 明示されてはいないが、暗黙的に仮定されている条件として、
不協和の程度が高く、かつ意思決定が修正可能な場合には、不協和的情報が好まれるという見解がある。フェスティンガー(1964)は、不協和の大きさと情報探索の関係が曲線的(非線形)であることを明示的には強調しなかったが、この点は、不協和が高まると人は最初の決定を見直すことを選択するようになり、その誤りを正すための情報を欲するようになる、という仮定を導入すれば、理論から自然に導き出されるものである。
このようにして、フェスティンガーは改訂理論の中で、認知体系の整合性は、単に情報の回避(回避戦略)によってのみでなく、不協和的情報の受容と反論(接近・回避戦略)によっても維持されると仮定した。両者の戦略はいずれも、情報に対して反論可能であるという前提の上に成り立っている。情報が反論困難であると認識される場合には「回避のみ」戦略が選ばれやすく、情報が容易に反論可能であると認識される場合には「接近・回避」戦略が選ばれやすくなるのである。
まとめると、意思決定後の情報探索における選択性については、以下の二つの基本的立場が存在する。
1. フリードマンとシアーズ(1965)の立場:このような選択性はほとんど(あるいは全く)生じず、仮に生じたとしても、それは不協和理論が想定するメカニズムではなく、他の媒介要因(例:事実上の選択性)によって説明されるとする。
2. フェスティンガーの立場(1957、1964):人は意思決定を下した後に不協和的情報を回避し、調和的情報に接近する傾向があると主張する。ただし、その不協和的情報が将来の決定や意思決定の修正にとって有益である、または当人がそれに反論できる自信があると判断した場合には、その情報を積極的に求める、あるいは少なくとも回避しないとした。
(第4章より)
「人は単純に不協和的情報を避けるとは限らない。第一に、不協和的であるがゆえにむしろ有用と見なされる情報が存在し、そのためにあえて接触することもある。第二に、自己効力感が高い状況においては、人は「不協和的」情報に積極的に接触し、それに反論しようとする。Canonの実験が示したように、特定の条件下においてのみ、人は不協和的情報の回避行動を示すのである。
したがって、より適切な結論は、「新しい情報への選択的接触は、不協和低減の機能において生じるものである」というものである。すなわち、情報の詳細に接触し、対処することによって不協和を効果的に低減できると個人が判断した場合、不協和的情報の回避は起こらない。回避が有効なのは、その情報の詳細に対処できないと感じているときに限られる。そしてもちろん、そのような回避が観察されるのは、有用性や好奇心といった、情報接触を促す他の要因が存在しない場合に限られるのである。」(Festinger, 1964, p. )
Frey (1986) Resent Research on selecive exposure to information
1965年までの選択的接触研究は、不協和理論の支持には乏しく、フリードマンとシアーズ(1965)は、不協和理論はこの現象には適用できないと結論づけた。この結論は当時広く受け入れられ、選択的接触研究への関心を減退させる結果となった(当時の研究の詳細なレビューは、Mills, 1968;Sears, 1968;Sears & Abeles, 1969;McGuire, 1968;Katz, 1968 などを参照)。
しかしながら、フリードマンとシアーズ(1965)の悲観的見解が、選択的接触現象への関心を再燃させることを妨げるべきではない。なぜなら、フェスティンガーが1964年に行った理論の改訂によって、選択的接触に関して新たな予測を導く枠組みが提供されたからである。加えて、方法論的に改善された実験により、不協和理論にとってより支持的な結果も得られつつある。
認知的不協和理論(1957)による説明
不協和理論によれば、人は自身の意思決定(仮説、信念、立場等)を支持する情報を好み、それと矛盾する情報を回避する傾向がある。例えば、ある人物が特定の住宅を購入する決意を固めたとする。その後、その決定に対して支持的な情報もあれば、否定的な情報も得られるような状況に置かれる。例えば、友人の中には「その家は高すぎる」「老朽化している」「見た目が悪い」と言う者もいれば、「美しく快適だ」と評価する者もいるとしよう。このとき、その人物がもはや購入の決定を覆せないとすれば、肯定的情報と否定的情報が同程度に入手可能な状況において、果たしてどちらにより注意を向けるであろうか。少なくとも以下の三つの可能性が考えられる。(1) 購入者が両方の情報に等しく注意を払う、(2) 購入決定を支持する情報を好む(すなわち確認的戦略)、あるいは(3) 逆に、決定に反する情報を重視する(反証的戦略)というものである。第四の可能性として、いずれの情報にも注意を払わないという選択肢もある。認知的不協和理論が正しければ、住宅購入者はその家およびその取引に好意的な情報を探し、逆に「騙されたのではないか」という趣旨の情報を避けようとするであろう。
選択的接触という現象は、しばしば言及されるように、人間の能動的かつ創造的な認知過程を示す好例である(例:Lowin, 1969)。たとえば、ある人物が将来の職業に関する最近の決定について不安や緊張を抱えているとしよう。このとき、「選択を誤った」と告げる情報は、その不安状態の軽減を妨げる。では、その人物はどのような思考に陥るだろうか。不協和理論によれば、当人は意思決定を正当化するように認知を構築し、目標指向的な行動を維持しようとする。すなわち、選択肢に反する情報を拒否するのである。こうした状況は、本稿で後述される実験の多くにおいて観察されている。
フェスティンガー(1957年)によれば、認知的不協和とは、二つの認知が行動に対して相反する含意を持つときに生じる心理的状態である。たとえば、ある人が何らかの意思決定を行った場合、その選ばれた選択肢の否定的側面は、その選択行為と整合しない。また、選ばれなかった選択肢の肯定的側面は、それを見送ったという事実と矛盾する。このようにして不協和が生じる。
不協和は否定的な動因状態とされており、それが生じたときには個人はそれを低減しようと動機づけられる。その動因の強度は、不協和の強さと正の相関関係にある。不協和の強度は、当人の認知体系における不協和的認知と調和的認知の相対的割合、ならびにそれぞれの重要度によって決定される。不協和は、新たな調和的認知を追加するか、不協和的認知を排除するか、あるいはその両方を組み合わせることによって低減される。
意思決定後の認知的不協和を低減する方法としては、その決定と整合する情報を選択的に探し、矛盾する情報を回避することが挙げられる。このような探索は、認知体系の内部(記憶など)で行われることもあれば、外部環境において行われることもある。いずれの場合においても、目的は認知間の不一致を減少させることである。ただし、どのような条件下で人が自らの認知を利用するのか、あるいは外部から新たな情報を得ようとするのかといった戦略選択について、不協和理論は明示的には述べていない。ただし、人は自らの不協和状態を最も確実に軽減できる戦略を選ぶであろうと仮定することはできる。この戦略の選択は、認知体系の内部および外部に存在する情報の量と質に大きく依存すると考えられる。
フリードマンとシアーズ(1965)による否定的評価
フリードマンとシアーズ(1965)による前述の悲観的評価――すなわち、不協和理論が選択的接触現象に適用可能か否かに関する否定的判断――は、彼らが二つの基本的なパラダイムに基づく一連の研究成果を精査したことによるものである。
1. 選択的接触効果が確認されなかった例:
喫煙者と非喫煙者による情報の選択性に関する Feather および Brock の研究プログラム
Feather(1962、1963)および Brock(1965)は、喫煙者が非喫煙者に比して、喫煙と肺がんとの関連性に疑問を投げかける情報をより強く求め、反対にその関連性を裏づける情報をあまり求めないかどうかを調査した。
Feather(1962、1963)の2つの独立した研究においては、喫煙者のほうが非喫煙者よりも、自らの喫煙行動と一致する情報にも一致しない情報にも(望ましさ評価に基づいて)より強い関心を示した。しかし、Feather(1963)は、Feather(1962)が観察したように、喫煙者が「喫煙とがんに関連性はない」と主張する情報を「関連性がある」とする情報より好むという結果を再現できなかった。
Brock(1965)は、Feather(1962、1963)の実験を部分的に再現した。Brockは、従属変数として、被験者に対して「喫煙を支持する情報」と「喫煙に反対する情報」(記事タイトルに基づいて記述された)に対する興味の度合いを順位づけさせた。そのうちの一群には「最も高く評価した記事を必ず読むように」と明示的に指示された(強制接触条件)。もう一群にはそのような指示は与えられなかった(任意接触条件)。後者の条件(これはFeatherの研究でも用いられた)では、喫煙者と非喫煙者との間で、喫煙を支持・反対する情報に対する関心度に有意な差は見られなかった。
これに対し、強制接触条件下では、喫煙者は「喫煙とがんとの関連性を否定する情報」を好む傾向を示した。しかし、どちらの実験においても、「喫煙者が喫煙とがんの関連性を支持する情報を回避する傾向がより強い」と明確に示す結果は得られなかった。なお、これらの実験における「回避傾向」の測定は、望ましさの評価(preference ratings)から間接的に推論されている点に留意すべきである。すなわち、被験者に対して「実際にどの記事を回避するか」が直接的に尋ねられたわけではなく、その点は後続の実験でも同様であった。
2. 調和的情報に対する選択的接触が確認されなかった例:
SearsおよびFreedmanによる研究プログラム
SearsとFreedmanによる一連の研究においては、情報探索行動は、被験者が二つの情報項目(ひとつは調和的、もうひとつは不協和的)から一つを選択するという操作によって測定された。たとえば、Freedman(1965a)の研究では、被験者はある学生の就職面接のインタビューを聴かされた。一部の被験者はその学生について非常に好意的な評価を聞かされ、他の被験者は非常に否定的な評価を聞かされた。その後、すべての被験者は「その学生が職を得たことが正当であったかどうか」を判断させられた。最終的に、被験者は他者によって書かれた二つの評価のうち一つを読む機会を与えられたが、そのうち一つは被験者の判断と一致する内容(調和的情報)、もう一つはそれと矛盾する内容(不協和的情報)であった。
不協和理論の予測に反して、Freedmanは被験者が不協和的情報を選好するという明確な傾向を発見した。
類似の研究において、Sears(1965)は被験者に裁判官の役割を与え、被告人が有罪か無罪かを判断させた。判断後、被験者はその判断を支持する情報または支持しない情報を受け取る機会を与えられたが、結果としては判断を支持しない情報に対する強い選好が示された。
これまでに言及されたすべての研究は、フェスティンガー(1957)による不協和理論のバージョンから導かれる予測の一般妥当性に明確な限界があることを、疑いなく示すものであった。
まずは、選択的接触に関する不協和理論の基本命題を簡潔に紹介し、その初期研究を概観する。続いて、フリードマンとシアーズ(1965)が提起した論争点を述べたのち、第III節では、選択的情報探索に影響を与える諸要因を特定するために筆者らが行った新たな実験研究を紹介する。その際、選択の有無や関与度、論拠の反証可能性、情報量およびその有用性、決定の可逆性、そして不協和の強度といった要因についても論じる。さらに、情報のコスト、矛盾情報の信頼性、パーソナリティの影響といった追加的変数に関する結果も報告する。
フェスティンガー(1964年)による不協和理論の改訂
不協和理論の発展、特に「強制的服従」の領域における研究により、不協和が成立するための二つの必要条件が明らかになった。それは、選択(choice)とコミットメント(commitment)である(Brehm & Cohen, 1962 を参照)。これら二つの変数が選択的接触においてどのような役割を果たすかについては、これまで十分な研究がなされていないが、それらが影響力を持つ可能性は高いと考えられる。実験において選択的接触効果が得られなかった理由の一つは、こうした変数を軽視していたことにあると説明できよう。
この点において、フェスティンガー(1964年)による不協和理論の改訂版は、選択的接触の理解にとって一層重要である。
改訂版においてフェスティンガー(1964)は、不協和的な情報は常に回避されるわけではなく、調和的な情報が常に好まれるわけでもないと主張した。彼は、不協和的情報が望まれると想定される以下のような条件を提示した。
1. 不協和的情報が容易に反論可能であると認知されている場合
ある人が、自らの信念と矛盾する情報を容易に反駁または抵抗できると感じているならば、その情報を積極的に求め、不協和の状態を反論によって軽減しようとするであろう。反対に、その情報が容易には反論できないと判断される場合には、それを回避する傾向が強まる。したがって、ここで決定的となるのは、不協和的情報に対する自己の反駁能力に対する自信である。
2. 不協和的情報が将来の意思決定にとって有用である場合
不協和的情報を無視することが、将来において誤った意思決定につながり、結果としてより大きな認知的不協和を引き起こすと信じる場合、人はこの情報を回避せず、むしろ求める可能性がある。
3. 明示されてはいないが、暗黙的に仮定されている条件として、
不協和の程度が高く、かつ意思決定が修正可能な場合には、不協和的情報が好まれるという見解がある。フェスティンガー(1964)は、不協和の大きさと情報探索の関係が曲線的(非線形)であることを明示的には強調しなかったが、この点は、不協和が高まると人は最初の決定を見直すことを選択するようになり、その誤りを正すための情報を欲するようになる、という仮定を導入すれば、理論から自然に導き出されるものである。
このようにして、フェスティンガーは改訂理論の中で、認知体系の整合性は、単に情報の回避(回避戦略)によってのみでなく、不協和的情報の受容と反論(接近・回避戦略)によっても維持されると仮定した。両者の戦略はいずれも、情報に対して反論可能であるという前提の上に成り立っている情報が反論困難であると認識される場合には「回避のみ」戦略が選ばれやすく、情報が容易に反論可能であると認識される場合には「接近・回避」戦略が選ばれやすくなるのである。
以上をまとめると、意思決定後の情報探索における選択性については、以下の二つの基本的立場が存在する。
1. フリードマンとシアーズ(1965)の立場:このような選択性はほとんど(あるいは全く)生じず、仮に生じたとしても、それは不協和理論が想定するメカニズムではなく、他の媒介要因(例:事実上の選択によって説明されるとする)。
2. フェスティンガーの立場(1957、1964):人は意思決定を下した後に不協和的情報を回避し、調和的情報に接近する傾向があると主張する。ただし、その不協和的情報が将来の決定や意思決定の修正にとって有益である、または当人がそれに反論できる自信があると判断した場合には、その情報を積極的に求める、あるいは少なくとも回避しないとした。
選択的情報探索に影響を与える諸要因の特定
A. 選択の有無が選択的情報探索に与える影響
不協和理論の枠組みにおける評価的変化の研究では一貫して、被験者が自らの信念に反する行動を自由意思で(あるいは比較的自由に)選んだ場合に、不協和低減効果がより顕著に現れることが示されてきた(例:Cohen & Latane, 1962;Cohen, Terry, & Jones, 1959;Frey & Irle, 1972;Frey, Irle, & Hochgürtel, 1979;Linder, Cooper, & Jones, 1967;Sogin & Pallak, 1976;Zanna & Cooper, 1974)。これに対して強制された行動ではそのような効果はあまり見られなかった。
B. コミットメントの効果
BrehmとCohen(1962)、ならびにFestinger(1964)によれば、認知的不協和は対立する認知のいずれかに対して強いコミットメントが存在するときにのみ生じる。したがって、選択的接触の効果は、被験者が特定の決定や立場に対してコミットしているときに最も強くなるはずである。この点を検証するために、被験者のコミットメントを操作し、情報選好における選択性を測定した実験がいくつか存在する。
C. 選択性と論拠の反駁可能性
フェスティンガー(1964)によれば、意思決定を正当化するには二つの方法がある。すなわち、①利用可能な意思決定関連情報に新たな調和的要素を加える方法、②すでに存在している不協和的要素を反駁する方法である。不協和的情報の反駁は、次のような条件下ではより効果的な戦略となる:
1. 不協和的情報が容易に反駁できると予想される場合
2. 情報が信頼性・能力の低い情報源から発信されていると認知されている場合
3. 被験者が意思決定の確信度が高く、かつ支持的情報を多く持っている場合
以下では、これらの条件に関係する研究を順に取り上げる。
D. 選択可能な情報量の影響
すでに述べたように、不協和的情報に対処するには二つの戦略が存在する。すなわち、①その情報を選択し反駁する戦略、②代わりに調和的情報を探す戦略である。理論的には、利用可能な情報の量が、この二つの戦略のいずれを採るかに影響を及ぼすと考えられる。
すなわち、不協和的情報が1件だけであれば、それを選んで反論することによってすべての不協和を排除することが可能である。しかし、複数の不協和的情報が存在する場合、そのうちの1件だけを選んで反論しても、その他の未反駁の不協和的情報が残るため、効果が薄くなる。そのような状況では、調和的情報を探す方が合理的である。
この仮説を検証するために、Frey(1985)は、選択可能な情報の量が選択的接触に与える影響を調べる4つの実験を報告している。被験者はまず、たとえば「架空のマネージャーの契約を更新すべきかどうか」あるいは「特定の企業が発展途上国に投資すべきかどうか」といった意思決定を求められた。
E. 情報の有用性
前述の Frey(1981a) の実験では、高信頼性の情報源からの不協和的情報が、低信頼性の情報源からの調和的情報よりも選好されるという結果が得られた。このような選択的接触の逆転現象は、被験者が学生であり、読んだ情報をもとに将来の意思決定を修正できると予期していたことを考慮すれば理解可能である。
このような状況においては、信頼できる情報源からの情報(その立場が肯定的か否定的かに関係なく)の方が、信頼性の乏しい情報源からの情報よりも有用であると認識されやすい。
この「有用性(usefulness)」という概念は、フェスティンガー(1964)による認知的不協和理論の改訂版において中心的な変数の一つとされており、長期的な認知的不協和の回避という観点からも極めて重要である。不協和を長期的に回避するには、特に将来的に意思決定を修正する可能性がある場合や、今後も同様の決定を下す必要があると予測される場合には、不協和的情報に意図的に接触することが望ましい。
F. 意思決定の可逆性における情報の有用性
前節までの議論から明らかであるように、意思決定の可逆性は、意思決定後の情報探索における選択性(selectivity)にとって重要な決定因である。意思決定が可逆的である場合、被験者は不協和的情報に対してより開かれた態度を取る傾向が強いと考えられる。可逆的な決定においては、**決定の修正自体が不協和低減の一手段となりうるため、不協和的情報は結論を再評価するうえで有用となる。
とはいえ、決定の修正は強い不協和が存在する場合に限って生じるものである。不協和の程度が低い場合には、やはり選択的接触は起きると予測される。
この仮説を検証したのが、Frey(1981b)の研究である。この実験では、Brehm(1956)やGreenwald(1969)の伝統的パラダイムに基づき、被験者に複数の選択肢(書籍)を順位付けさせ、その後、実験者によって指定された2つの選択肢から可逆的または不可逆的な選択をさせた。
G. 認知的不協和の強度
不協和理論は、不協和の強度が高まるにつれて、情報選好の選択性が強まると予測する。ただし、その強度がある閾値を超えて意思決定の見直しが現実的に考慮される段階**に達した場合には、調和的情報の探索は弱まり、代わって反対の立場を支持する情報の探索が始まるとされる。
したがって、不協和の強度全体にわたって考えるならば、不協和と選択的接触との関係は曲線的(逆U字型)であると理論的に仮定される。すなわち、中程度の不協和水準で選択的接触が最大化されるという関係である。ただし、これは意思決定が可逆的であることが前提条件となる。意思決定が不可逆的である場合には、不協和の増加に応じて選択性も直線的に増加すると予測される。
これまでに紹介した実験の多くでは、不協和が強いほど選択的接触が顕著になることが示されてきた。しかしながら、それらの実験のほとんどは、不協和の強度を**2水準以上には操作していないため、曲線的関係の検証には不十分である。このことはFestinger(1957)、Cohen, Brehm, & Latane(1959)、Rhine(1967)を除くほとんどの初期研究にも当てはまる。
これに対し、Frey(1982)は、不協和の量と調和的情報の探索(および不協和的情報の回避)との間の曲線的関係を検証する実験を行った。実験の手続きは、Festinger(1957)およびCohenら(1959)の古典的実験に類似していた。
H . 情報のコスト
意思決定前における情報探索に関する多数の研究において、情報の取得コストが情報探索の量に影響を与えることが示されてきた(Frey, Kumpf, Raffee, Sauter, & Silberer, 1976;Lanzetta, 1963;Lanzetta & Kanareff, 1962;Silberer & Frey, 1980)。しかしながら、情報コストが情報探索の「方向性」に及ぼす影響**については、これまであまり研究されてこなかった。
この点を扱ったのが、すでに言及した Frey(1981c) の実験である。この実験では、自己評価よりも低い数値の知能テスト結果を被験者に提示し、それが情報選好に与える影響を調べた。被験者は、架空の知能テスト結果(自己評価よりも低いスコア)を与えられた後に、次の2種類の情報を含む複数の記事の中から選択する機会を得た:
2. 不協和的情報の妥当性・信頼性の認知が選択的接触に与える影響
不協和的情報が引き起こす不協和の量は、その情報の妥当性または信頼性がどの程度高く認知されているかに依存すると仮定することができる。この仮説は、FreyとStahlberg(1986)によって、前述の「知能テスト・パラダイム」(Frey, 1978b)を用いた2つの実験において検証された。
両実験において、被験者には常に自己評価よりも低いスコアの架空の知能テスト結果が与えられたが、その不協和の程度(深刻さ)は条件によって操作された。
3. 選択的接触とパーソナリティ変数
ある種の性格タイプは、情報探索のパターンにおいて相違を示すのであろうか。すでに述べたように、Canon(1964)は、自信の低い人物は意思決定を支持する情報(調和的情報)を好み、自信の高い人物は意思決定を支持しない情報(不協和的情報)を好む傾向があることを発見した。
なお、Canon(1964)は被験者の自己信頼感を直接測定したわけではなく、課題遂行に関する成功フィードバック(肯定的または否定的)を与えることで、自信感を操作的に誘導したものである。しかしながら、実際に測定された自己信頼感の個人差も、情報選択行動における差異をもたらすと考えられる。
I. 情報回避に関する結果
認知的不協和理論は、人々が調和的情報を選択的に探索するだけでなく、不協和的情報をこれ以上受け取ることを回避しようとするとも仮定している。われわれ自身の研究は、この仮説を明確に支持する証拠を提供している。
すなわち、被験者に「どの情報を見たくないか」を尋ねた実験において、不協和的情報を調和的情報よりも回避しようとする傾向が有意に強く観察された。しかしながら、選択的情報探索と異なり、情報回避の程度は、前述の諸変数によって明確に変化することはなかった。
われわれの実験のうち、唯一、情報回避の程度が不協和の強度に影響されたのは、Frey & Wicklund(1978)によるものであった。この実験では、自由選択(高不協和)条件の被験者が、選択なし(低不協和)条件の被験者よりも不協和的情報をより回避する傾向を示した。しかしながら、不協和の強度を3水準以上で操作した実験(Frey, 1982)では、情報回避行動は誘導された不協和の量に依存していなかった。
V. 結論
選択的接触(Selective Exposure)は、人間の能動的かつ創造的な情報処理プロセスを示す好例である。LewinやFestingerの見解によれば(Wicklund & Frey, 1981参照)、人は目的志向的な行動を促進するために、意思決定を中心とした認知構造を構築し、不協和的な情報を拒否し、調和的な情報を積極的に探索すると考えられる。
近年の実験の多くは、行動傾向と矛盾する認知状態にある人間がいかに活発な情報処理状態にあるかを示している。われわれが要約した研究は、不協和低減過程が能動的かつ動機づけに基づいたものであることを明らかにし、自己知覚理論のような非動機づけ的理論では説明が困難な人間行動の領域であることを強調するものである。
選択的接触効果は、不協和理論における最も強力な動機的側面と見なされてきたが、Festingerの最初の理論発表以降の初期研究では経験的支持は弱かった。このことは、不協和理論の動機概念自体への批判材料としてしばしば引用されてきた。しかしわれわれは、初期研究における実験デザインの不備が、決定的な結果を得られなかった主因であると考える。
1965年以降に行われた選択的接触研究の結果は、Festinger(1957, 1964)の原理的仮定をそのまま保持することはできないことを示している。すなわち、調和的情報が常に不協和的情報よりも選好されるわけではなく、むしろ不協和的情報が好まれる条件も存在する。そのような条件とは:
1. 被験者が不協和的情報に反論可能な場合
2. 不協和的情報が将来的に有用であると認識される場合(例:将来の意思決定、あるいは意思決定の修正が見込まれる場合。特に不協和が極端に大きい状況ではこの傾向が顕著である)
3. 調和的情報にすでに十分に慣れており、新たな意義を見出さない
4. 公正さの規範が存在する場合(たとえば陪審員裁判の実験等。Sears, 1965参照)
このことをより抽象的に言えば、認知体系が安定していて不協和的情報を統合・反論できる状況、あるいは体系が不安定であり、調和的情報の追加では効果的な不協和低減ができない状況では、不協和的情報への選好や選択的接触の傾向が観察されやすいということである。
また、不協和の強度と選択的接触・情報回避の関係**について理論が予測する曲線的関係(逆U字型)は、あくまで「意思決定が可逆的である」と認識されている場合にのみ成立する。不可逆的な意思決定の場合には、選択性は不協和の強度とともに直線的に増加すると示された。
情報回避効果についてもFestingerの原理は修正される必要がある。彼は、不協和的情報の方が調和的情報よりも回避されやすく、その傾向は不協和の増加に応じて曲線的に高まると仮定していたが、実証研究の多くでは、回避行動が不協和の強度に依存しないことが示された。われわれはこの結果を、情報回避は不協和そのものを低減する効果を持たないためであると解釈した。
選択的接触の予測においては、個別の情報だけではなく、被験者の全体的な認知体系を考慮する必要がある。一見すると不協和的な情報でも、将来の意思決定に備えて自己を適切に情報武装したいと望む者にとっては、有意義なものとなりうる。そのような情報を排除すれば、むしろ長期的にはより強い不協和が惹起される可能性すらある**(Mills et al., 1959参照)。
総じて言えば、修正された不協和理論だけでは全ての実験結果を説明しきることはできず、効用性・好奇心・公正の規範といった追加的要因も考慮に入れる必要がある。それでもなお、現在の研究は、人間の情報処理が防衛的性質を有することを明確に示している。
人は、自らの信念や判断、仮説に対して支持的・非支持的のいずれの情報にも開かれている。ただしそれは、それらを修正する可能性があると感じているときに限られる。一方で、外的制約や内的抵抗などの理由で修正の可能性がないと認識されている場合、非支持的情報は無視され、支持的情報への選好が強まる。
著者の見解としては、現在のところ、修正された不協和理論以上に実験結果を正確に説明できる理論的代替案は存在しないと考える。
近年の社会認知理論では、人間を単なる認知的存在として描き、動機・欲求・緊張といった要素を排除しようとする傾向がある。だが、純粋に認知的な説明では、多数の実証的証拠を十分に説明することはできない。本研究は、Lewin的・Festinger的視点から人間を捉え直すという流れをさらに進展させるものである。
選択的接触の国際比較
これまでの党派的選択的接触に関する研究の多くは米国で実施されており、そこでは安定した二大政党制、広く浸透した党派的メディア、そしてエリート層および一般大衆レベルでの政治的分極化といった特性が、党派的選択的接触を促進している。このため、米国において観察された党派的選択的接触の一般化可能性については、国際比較研究によって慎重に検討する必要がある。いくつかの国際比較研究では、米国外における党派的選択的接触が米国内に比べて弱いことが示されているこうした国際的差異は、党派的選択的接触の普遍性およびそのメカニズムに対する疑問を提起する。小林哲郎等は、米国、日本、香港の人々が党派的選択的接触をどの程度示すかを評価・比較することを目的として、参加者が自己の政治的態度と一致または矛盾するニュースのいずれかを模擬ニュースサイト上で選択する行動を観察する研究を行った。また、各国間で観察された違いの要因を検討し、情動的分極化、メディア信頼性の認知、ならびに文化的要素としての弁証的自己観の媒介的役割について分析を行った。
過去の関連文献のレビューに基づいて、本研究では、次のような仮説を立てて検証した。
H1:党派的選択的接触は、日本および香港よりも米国においてより強く観察される。
H2:党派的選択的接触における国際的差異は、情動的分極化によって説明される。
H3:党派的選択的接触における国際的差異は、メディア信頼性の認知によって説明される。
H4:党派的選択的接触における国際的差異は、弁証的自己によって説明される。
仮説H1の検証:
仮説H1を検証するために、米国、日本、香港の各国・地域における閲覧行動を測定するための模擬ニュースサイトを作成した。各模擬サイトには、ニュースの見出し8本と、先頭段落の冒頭部分が表示された(図1左パネルは米国版を示す)。このうち上位4本の見出しは政治ニュースであり、残り4本はエンタメやスポーツなどの非政治的ニュースであった。4本の政治的見出しはいずれも各地域の政治的指導者に関するものであり、米国ではドナルド・トランプ大統領、日本では安倍晋三首相、香港では行政長官キャリー・ラムが対象となった。これらの見出しのうち、2本はその指導者に肯定的な内容、残り2本は否定的な内容であった。回答者は任意でどの見出しを読むかを選択でき、見出しをクリックするとその記事の本文ページに遷移した。記録された閲覧行動および政治指導者への支持・不支持のデータに基づき、参加者が選択した態度一致または態度不一致の見出し数を測定した。態度一致見出しのクリック数から態度不一致見出しのクリック数を差し引いて、選択的接触スコアを算出した。その平均値は、日本0.03(SD = 0.75)、香港0.10(SD = 0.78)、米国0.28(SD = 0.91)であった。見出しクリック数によって測定された選択的接触では、日本および香港のいずれも米国に比べて有意に低い水準であった。しかし、日本と香港の差は統計的に有意ではなかった。記事閲覧時間によって測定した場合も同様の結果が得られ、日本と香港の間に有意差は見られなかった。これらの知見は、仮説H1を明確に支持するものである。
仮説H1では、媒介変数を測定していなかったため、国際的差異の原因を特定することができなかった。そこで、仮説H2〜H4dでは、媒介変数の測定を行い、国際的差異の原因の特定を試みた。
仮説H2の検証:
本研究では、Iyengarら(2012)に従い、政治的内集団および外集団に対する感情温度(feeling thermometer)スコアの差を用いて、情動的分極化を測定し、模擬ニュースサイトを用いた行動データに基づいて、情動的分極化が選択的接触の先行要因であるかどうかを検討した。例えば、米国の場合、「共和党または民主党の支持者に対する感情についてお尋ねします。0〜100(0=非常に好ましくない、100=非常に好ましい)の範囲で、[共和党/民主党]支持者についてどう感じますか?」と尋ね、このスコアの差を100で除して0〜1に正規化して、感情温度の差とした。情動的分極化を独立変数として追加したところ、選択的接触に対して正の影響を持つことが示された。これは、H2(情動的分極化が国際的差異を媒介する)を支持するものである
本研究の結果として、米国、日本、香港における模擬ニュースサイトを用いた比較調査によって、選択的接触に国際的差異があることを実証した。また、情動的分極化の程度の違いが国際的差異を部分的に説明することが示された。
ニューメディア時代のメディア効果論
Bennett, W. L., & Iyengar, S. (2008). A new era of minimal effects? The changing foundations of political communication. Journal of Communication, 58 (4), 707–731.
ニューメディア時代の選択的接触
Selective Exposure in the
Communication Technology Context
by Silvia Knobloch-Westerwick, Axel Westerwick,
and Benjamin K. Johnson
近年の数十年にわたるコミュニケーション技術の多様化の急速な進展は、選択的接触研究に新たな影響を与えてきた。「豊かさへの対処」という問題(Becker & Schoenbach, 1989)は、すでにケーブル技術によってテレビチャンネルの数が激増した時点で聴衆にとって顕在化していたが、さらにデジタルメディアやインターネット、ならびにブロードバンド通信の普及は、メディア利用者が選択可能なメッセージの量を飛躍的に増大させた。無数とも思えるURL、ウェブページ、そして伝統的なメディアを介さずに直接情報発信可能な非メディア機関や個人の登場により、メディア利用における選択性の根本的重要性は一層明白となっている。
このような状況のもとで、新たな問いが生まれている。すなわち、情報源に対する知覚や、どのようなメッセージ特性が選択的接触を引き起こすのかという点である。もちろん、従来から「能動的なオーディエンス」(Webster, 1998)についての一般的な議論は存在していたが、それらは主としてオーディエンスの動機やメディアメッセージの解釈に関するものであった。これに対して、近年の研究は、どのようなコミュニケーション要素が実際に選択されるのか、そしてその選択的接触がいかなる結果をもたらすのかを予測することに、より明確に焦点を当てている。
コミュニケーション技術の変化は、確証バイアスをコミュニケーション研究およびメディア環境の将来に関する議論の中心へと押し上げた。インターネットの登場により情報が爆発的に増加し、それに伴うカスタマイズ可能性やコントロールの容易さが、選択的接触における確証バイアスの機会を拡大させている(Sunstein, 2001)。Sunsteinは、党派的エコーチェンバーによって生じる分極化と過激化に対して懸念を表明し、確証バイアスの広がりとその影響に関する研究と議論を活性化させた。
この議論をさらに発展させて、BennettとIyengar(2008)は、情報技術の発展によってメディア利用者の選択性が高まり、「限定効果の新時代」(Klapper, 1960参照)を迎えたと主張した。すなわち、説得や知識獲得、その他のメディアメッセージ受容の効果はほとんど見られなくなりつつあるという。なぜなら、聴衆はすでに自身の信じていることや知っていることのみを伝えるようなメディアルーティンを形成できるようになっているからである。
しかしながら、態度一致的な選択的接触が広範に見られる一方で、選択的回避の強さは必ずしも同等ではなく、大多数のメディア利用者が定期的に見慣れない、あるいは不快な情報にも接触していることを示す証拠も存在する(Frey, 1982;Garrett, 2009b;Knobloch-Westerwick & Kleinman, 2012)。さらに、選択性が存在するからといって、メディア効果が否定されるわけではなく、態度一致的な接触自体にも効果が存在することが示されている(Holbert, Garrett, & Gleason, 2010;Knobloch-Westerwick & Meng, 2011)。
また、課題の重要性も確証バイアスに影響を与える。すなわち、ある課題に高い重要性を見出すオンラインユーザーは、より強く態度一致的な情報に偏る傾向がある(Knobloch-Westerwick, 2007;Westerwick, Kleinman, & Knobloch-Westerwick, 2013)。さらに、正確な処理を志向するか、防衛的処理を志向するかといった状況的目標も、選択的接触に影響を及ぼしうる(Kim, 2007)。もっとも、反論を予期し、その主張を擁護する必要があると感じていても、被験者はなおも態度一致的な情報を選好する傾向があることが示されている(Westerwick et al., 2013)。
情報源の信頼性 (credibility)
古典的な説得研究(例:Hovland & Weiss, 1951;Wilson & Sherrell, 1993)では、情報源の専門性が聴衆の説得に大きな影響を与えることが示されており、これは情報源の信頼性と密接に関係している。Westerwickら(2013)は、情報源の信頼性および政治的メッセージに対する態度が、オンラインコンテンツの選択に影響するかを検討した。結果は、政治的話題への関与が高い人ほど、情報源の信頼性にかかわらず、自らの態度と一致するコンテンツを有意に多く選択することを示した。これに対し、関与の低い人々は、高い信頼性を持つ情報源からのメッセージをより頻繁に選択した。このことから、情報源の信頼性は選択的接触に影響を及ぼす要因の一つであるが、個人的に重要な態度といった他の要因が関与する場合、その影響力は相対的に小さくなる可能性がある。
Westerwick(2013)の研究は、オンライン情報の利用者がウェブサイトの情報を評価する際に、その情報源の信頼性を考慮している一方で、検索順位もウェブサイトの選択および信頼性の知覚に大きな影響を及ぼしていることを明らかにしている。また、タブ、ナビゲーションバー、検索機能といった技術的な手がかりが、オンライン情報の信頼性を高め、それが選択的接触に影響を与えると示唆されている。
さらに、技術的な手がかりは、ユーザーの知覚および選択的接触に影響を与える可能性がある。たとえば、ウェブページのパーソナライズは、信頼性の知覚およびその後のチャネル閲覧行動に影響を及ぼすことがある(Kalyanaraman & Sundar, 2006)。また、情報信頼性が選択的接触に与える影響を探る新たな領域として、消費者製品の評価も考えられる。オンライン評価の著者は大半が匿名であるが、メッセージの設計、文体、更新時期などに基づくメッセージ信頼性、ならびに製品やメーカーに対する態度が、どの評価をさらに読むか、または意思決定に利用するかを左右する決定要因となる可能性がある。
情報的有用性(Informational Utility)
情報的有用性が選択的接触に及ぼす影響を実証的に検討した研究は、主としてオンラインニュースに焦点を当ててきた。読者は、情報的有用性が高いオンラインニュースを選好し、より多くの時間を費やす傾向がある(Arpan & Tuzunkan, 2011;Kim, 2008;Knobloch, Dillman Carpentier et al., 2003;Knobloch-Westerwick, Hastall et al., 2005)。政治的文脈においては、情報的有用性が、政治的オンラインメッセージに対する選択的接触における確証バイアスを上書きする可能性があると示唆されている(Knobloch-Westerwick & Kleinman, 2012)。
気分管理(Mood Management)
インターネット時代の選択的接触に関して有用なのは、Zillmann(1988)の気分管理理論である。同理論の核心は、メディア利用者が気分を改善するためにコンテンツを選択するというものである。気分状態は覚醒水準(arousal)と快不快(valence)という軸で記述されうる。たとえば退屈を感じているときは、覚醒水準を心地よいレベルにまで高めるために、刺激的なコンテンツが好まれる。一方、ストレスを感じている場合には、気分の快楽的調子を高め、否定的な感情の源から気をそらしてくれるようなコンテンツが選ばれるとされている。これらの考え方は、伝統的メディアに関する多数の研究で支持されており(Knobloch-Westerwick, 2006)、いくつかの研究はこれを新たなコミュニケーション技術の文脈にも拡張している。
例えば、Knobloch(2002)の研究では、実験的に誘導された気分がウェブ閲覧行動に影響を及ぼすことが示された。すなわち、否定的な気分にある被験者は、中立的な気分にある者よりも、肯定的な感情価を持つページに長く滞在する傾向が見られた。また同研究では、否定的な気分の被験者は、肯定的な気分の被験者よりも「娯楽的」と判断されるウェブページへの接触時間が長かった。Mastro, Eastin, および Tamborini(2002)による研究でも、異なる覚醒水準を実験的に誘導し、その後のウェブ利用を観察したところ、退屈していた参加者の方が、ストレスを感じていた参加者よりも多くのページを閲覧していた。
社会的比較と所属(Social Comparisons and Affiliations)
社会生活における基本的な側面として、人はしばしば、自身の能力や意見を、社会環境内の類似した他者と比較することで評価している(Festinger, 1954)。このような自己評価の欲求に加えて、社会的比較は自己高揚のためにも行われる。すなわち、個人が自分に都合のよい比較を行うのである。これには、対照的に自分の優位性を感じさせる「下方比較」(Wills, 1981)や、より高い目標対象に対する同一視・憧れとしての「上方比較」(Lockwood & Kunda, 1997)が含まれる。
オンライン上には、ニュースサイトからSNSに至るまで、他者の多様な描写があふれており、インターネット利用者は自己高揚的な社会的比較を可能にする選択的接触を行う余地を大きく持っている。
他者の描写に関するオンラインコンテンツへの選択的接触に関する研究では、インターネット利用者が社会的比較のために用いるコンテンツの選択に対して明確な選好を示すことが明らかとなっている。たとえば、男女ともに他者の成功や失敗に関するオンラインニュースを読む際、自身の性別役割スキーマに合致するような性別固有の話題について選択的な比較を行う傾向がある(Knobloch-Westerwick & Alter, 2007;Knobloch-Westerwick, Bruck, & Hastall, 2006)。
また、集団所属は、オンラインニュースにおける内集団および外集団の描写への選択的接触にも影響を与える。特にマイノリティにおいてはその傾向が顕著である(Knobloch-Westerwick, Appiah, & Alter, 2008)。社会的比較の観点から、数的多数派と少数派に関する研究では、自尊心が低〜中程度の人々において、マジョリティの参加者は自集団の肯定的描写を回避し、マイノリティの参加者は否定的な描写よりも肯定的な自集団の描写を選好する傾向があった(Knobloch-Westerwick & Westerwick, 2011)。
技術的手がかり(Technology Cues)
インターネット利用者の行動や知覚に対して、技術的手がかりがどのような影響を及ぼすかに関する研究は多岐にわたっている。ウェブサイトのデザイン、インタラクティビティ、情報の新しさなどは、技術が提供する手がかりの一例であり(Sundar, 2008)、これらはインターネットコンテンツへの選択的接触に影響を与えると考えられている。
結果は一様ではないが、特にデザインの手がかりや情報の新しさに関する情報が、ユーザーの知覚および情報の選択に影響を及ぼすという傾向が示されている(Fogg et al., 2001;Shon, Marshall, & Musen, 2000;Sundar, Knobloch-Westerwick, & Hastall, 2007;Wathen & Burkell, 2002)。
今後の研究動向
既存の研究は、新たなコミュニケーション技術の文脈における選択的接触が、確証バイアス、情報的有用性の検討、気分管理の動機、そして社会的比較のプロセスによって影響を受けることを明らかにしてきた。しかしながら、この新たなコミュニケーション技術特有の手がかり(cues)に着目した選択的接触研究は、依然として限られている。今後の研究では、Sundar(2008)の MAIN モデルと Knobloch-Westerwick(2015)の選択的接触パラダイムとを統合することにより、このギャップを埋めることが期待される。
現在の新メディア時代において、選択的接触とその含意に関する理解を深めるための重要な前進はすでになされているが、依然として多くの課題が残されている。接触に影響を及ぼしうる技術的手がかりのリストはほとんど無限に存在するといってよく、今後の研究では、新メディア利用プロセスに関する理解を真に加速するために、理論的枠組みの精緻化と拡張が必要となるであろう。
選択的接触に関する最新の研究論文集
Silvia, S. (Ed.) (2015) Choice and Preference in Media Use : Advances in Selective Exposure Theory and Research
本書は、選択的接触に関する研究を取りまとめた専門書として2冊目となる本である。最初の本は、1985年にZillmannとBryantによる編著"Selective Exposure to Communication"である。本書"Choice and Preference in Media Use : Advances in Selective Exposure Theory and Research"は、政治コミュニケーション、インターネット、娯楽などの分野で、選択的接触に関するその後の理論的、方法論的研究の発展を取りまとめたものである。特に、21世紀に入り、メディアのチャンネルやメッセージが飛躍的に増大することで、選択的接触の影響がますます重要になっている状況における最新の研究動向をレビューしている。
選択的接触パラダイム
Lazarsfeldら(1948)の先行研究
「人々は自分の政治的先有傾向に沿って接触先を選択する[......]人々の意見と、彼らが聴いたり読んだりするものを選択する間には正の関係が存在する」(Lazarsfeldら、1948年、164頁)。
本書での定義:選択的接触とは、「視聴者構成における体系的な偏り」(Sears & Freedman, 1967, p.195)、および、アクセス可能なメッセージの構成から乖離した、選択されたメッセージにおける体系的な偏りを示す。具体的な例を挙げると、100の記事ページからなる雑誌の読者は、各ページを同じ時間見る代わりに、残りの80の記事ページを読み飛ばしながら、20の記事ページだけを読むことに時間の80%を割くかもしれない。いくつかのページの読書時間が不均衡なのは、選択的接触を反映している。
選択的接触を説明する理論
個人が情報や娯楽効果を得るためにメディアへの接触を求める理由を説明する理論には、次にのようなものがある。
(1) 合理的な選択の理論
合理的選択理論では、個人は嗜好に表れた個人的なニーズや目標によって動機づけられていると見なされる。彼らは与えられた制約の中で、現在の状況や利用可能な選択肢に関する通常不完全な情報に基づいて行動する。通常、個人が欲しいものをすべて手に入れることは不可能であるため、目標とその目標を達成するための手段の両方に関して選択を行わなければならない。合理的選択理論では、個人は代替的な行動コースの結果を予測し、どれが自分にとって最善かを計算しなければならないとする。したがって、個人は自分に最大の満足を与えそうな選択肢を選び(Heath, 1976)、この目標に対して最大の期待効用を持つ選択肢を選ぶことで、主観的価値や厚生を最大化することを目指す(Lichtenstein & Slovic, 2006)。
しかし、合理的選択モデルは、さらなる議論のきっかけにはなるものの、選択的接触を研究する学者たちの間ではほとんど注目されておらず、目立たないように観察されるメディア選択の予測に適用されることはほとんどなかった。
(2)不確実性の低減理論
不確実性の低減が情報探索の重要な動機であるという考え方が強まっている(Spink, Wilson, Ford, Foster, & Ellis, 2002など)。個人は、自分を取り巻く世界を構造化し、予 測し、使いこなすために、カテゴリーやルールを開発したがるというのである(deCharms, 1968; Kelly, 1955)。これらの考え方はWhite (1959) の「コンピテンス」の概念、つまり自分の環境を使いこなす動機づけと関連している。コンピテンスとマスタリーの目的のためには、世界についての情報収集が不可欠であり、不確実性は環境に対処するために重要と考えられる情報の欠如を意味する。マスメディアを通じた情報取得は、個人が自分の環境を理解し、知識を通じて課題を予測することを助け、不確実性を低減するという環境監視機能(Lasswell, 1960)を果たす。
(3)認知的不協和理論
認知的不協和の理論はFestinger (1957)によって提唱され、彼は、人は関連する認知の対の間の一貫性または協和を維持するように動機づけられるという仮定を前提にしている。ここでいう認知とは、自己、行動、環境に関する知識や信念のことである。2つの認知が論理的に矛盾している場合、不協和とみなされる。このような不協和は不快であり、不協和を軽減する圧力と、不協和を増大させるような状況や情報を避ける圧力の両方を生み出す。フェスティンガーは、不協和を減少させる圧力の大きさは不協和の大きさの関数であり、ある認知によって生じる不協和の大きさは、その認知と他の関連する認知に与えられた重要性と、関連する認知のうち不協和である認知の割合の両方に依存すると指摘した。不協和は、不協和認知の1つを変更すること、不協和の重要性を減少させること、または不一致認知の1つと一致する新しい情報を追加すること、または何らかの形で2つの不協和要素を調整することによって減少させることができる。例えば、「私はタバコを吸う」と「タバコはガンの原因である」という認知によって生じる不協和を、禁煙することによって、あるいは喫煙とガンを結びつける証拠を否定または誹謗することによって、あるいは喫煙に関連するリスクは、喫煙が対処に役立つかもしれないストレスによって生じるリスクよりも小さいと結論付けることによって、あるいは過激な喫煙者の仲間を求め、非喫煙者を避けることによって減らすことができる。
認知的不協和に関するフェスティンガーの理論は、1950年代から1960年代にかけて莫大な研究活動を引き起こした。しかし、情報探索パターンの予測値には強い疑問が呈された(Sears & Freedman, 1967)。情報への接触に影響する他の関連要因、例えば情報的効用に遭遇したため、関連研究はやがて沈静化した。最近、インターネット時代になって、選択的接触における確証バイアスに関する研究が復活した(Bennett & Iyengar, 2008)。
情報効用モデル
マス・コミュニケーションに関して、Atkin(1973)は情報効用とそれが情報探索に及ぼす影響に関する理論を提唱した。彼の意味での情報探索とは、あるトピックに関する明確な質問に対して、意図的に開始される探索行動であり、情報探索の中の一つの活動を形成している。もう一つの形態は、アトキンが情報受容性と呼んだもので、「日常的なメッセージのスキャニング中にトピックに関連した手がかりに出会うことによって生じる質問形成への開放性」であり、メッセージによって誘発された質問が認知的不確実性を喚起する場合に選択が生じる(アトキン、1973年、238ページ)。不確実性とは、原始的なレベルでは知識の欠如であり、より複雑なレベルでは、態度を形成したり行動を指示したりするのに必要な知識の欠如である。この意味で、追加的な情報は必ずしも不確実性を減らすとは限らない。アトキンは、情報を単に「受け手がまだ知らないこと」と定義している。多種多様な不確実性の中で、特に関心が高いのは、日常的な環境や心理的な問題に関連する不確実性であり、アトキンの用語では外在的不確実性である。この適応的要件は、実際の知識との関係において、確実性の基準レベルを定義する役割を果たす。アトキンはさらに、外在的な不確実性を減らすための情報に対する一般的な必要性を、(a)認知的、(b)情緒的、(c)行動的、および(d)心理的な必要性によって区別した。アトキンは情報ニーズとして、監視、ガイダンス(「物事についてどう感じるか」)、パフォーマンス(「物事をどう行うか」)、強化(「態度を再確認する」)を提案しているのである。Atkin (1973, p. 206)のモデルは、「個人がマスメディアのメッセージを選択するのは、そのメッセージの報酬価値が、そのメッセージに費やす支出を上回ると推定されるときである」と予測している。
認知的不協和と確証バイアス
コミュニケーション研究は、情報選択プロセスに関する理論的・経験的洞察を蓄積してきたと思われる。結局のところ、メディア情報への選択的接触がメディア効果の前提条件であることは広くコンセンサスが得られており(McGuire, 1985)、知識格差、ニュースからの学習、政治的態度の変化、現実世界の認識、問題の重要性の認識などに関する豊富な研究が、メディア情報への接触がもたらす効果を調査してきた(Bryant & Oliver, 2009)。
認知的不協和の理論(Festinger, 1957)が、情報の選択的接触に関する研究の大部分を引き起こした。この理論的観点では、個人は主に、以前の決定や現在抱いている信念と相容れない情報によって生じる不快な認知的不協和を回避しようとする。このパターンは、適合する情報を選好することを伴うが、研究においては、メッセージ回避に重点が置かれていることがほとんどである。
政治学では、確証バイアスの命題である「人は非確証的な議論よりも確証的な議論を求める」(Taber & Lodge, 2006, p.757)という動機づけ認知の視点がルネッサンス期を迎えている。
フェスティンガー(1957, pp.127-129)が3つのシナリ オについて論じ、グラフに示したように、接触行動は直線的ではな い( 図5.2参照):不協和のレベルが非常に低い場合、個人はそれ以上情報を求めようとも避けようともしない。不協和が中程度の場合、個人は協和を高めるような情報を求め、不協和を高めるようなメッセージを避けると言われている。このような状況下では、まだ接触していないメッセージの正確な内容が不明であるため、メッセージへの接触が自分の不協和レベルに対してどのような結果をもたらすかに関する個人の期待が重要となる。しかし、不協和が極めて高く、したがって変化に対する抵抗のレベルに近い場合、個人は自分の信念や行動を変えることによって、その不協和を解消しようとすることさえある。不協和が大きいほど、追加的な情報がその不協和を減少させるという期待は低く、そのような情報を求めることは不協和が大きいほど低くなる。一方、追加的な情報が不協和を増加させるという期待は、不協和が大きいほど大きく、そのような情報を求めることは不協和が大きいほど高くなる。したがって、不協和のレベルが非常に高い人は、自分の信念や行動を変え、不協和を解消する転換点まで不協和を助長するようなメッセージを求めることさえある。
Hartら(2009)は、91の研究を含む67の報告のメタ分析において、情報接触を導く2つの基本的動機-防衛動機(確証バイアスに相当)と正確性動機(情報有用性に相当)を導き出した。確証バイアスに関連する動機は情報接触の分散の13%を説明し、有用性の考慮は7%を説明した。 図5.3に示されているように、確認バイアスの程度を考慮するさらなる構成要素がメタ分析で有意なものとして浮上した。そのうちのいくつかは、数十年前にすでに示唆されていた。例えば、フェスティンガー(1964) とローウィン(1967)はともに、矛盾する情報を回避するか反駁す ることによって信念を維持できると主張した。ローウィン(1967) は接近-回避モデルにおいて、態度に挑戦的なメッセージに接触す るのは、それが容易に否定される場合であると提唱した(Lowin, 1967, 1969)。このように、情報の質はメッセージの反証可能性に関係する。
認知的不協和理論に沿った情報選択は、個人にとって機能不全であるだけでなく、社会の観点からも有害であると考えられる。民主主義における思想市場の理想を認めるならば、十分な情報を得た市民が公共の問題に有意義に参加するためには、対立する議論に接触することが不可欠である。これとは対照的に、認知的不協和理論が予測するように、個人が既存の見解に沿った情報を好むのであれば、このような情報利用パターンは、さらなる意見の発展や政治的寛容を促進することはないだろう。
このような評価的考察はさておき、認知的不協和理論が個人の情報選択に関する研究の大部分を導いてきたことは間違いない。情報探索における確証バイアス(Jonas et al.2001など)という用語がここでは好まれ、第1章で概説した選択的接触という広義の概念との混同を避けるのに役立つが、子音情報に対する一般的な選好という概念は、「選択的接触」や選択性(McGuire, 1968; Milburn, 1979; Ziemke, 1980など)という用語の多くの使用と一致してさえいる。
参考文献(第11章)
Arceneaux, K., Johnson, M., & Murphy, C. (2012). Polarized political communication, oppositional media hostility, and selective exposure. Journal of Politics, 74( 1), 174-186.
Bennett, W. L., & Iyengar, S. (2008). A new era of minimal effects? The changing foundations of political communication. Journal of Communication, 58 (4), 707–731.
Bowman, N. D., Joeckel, S., & Dogruel, L. (2015). "The app market has been candy crushed": Observed and rationalized processes for selecting smartphone games. Entertainment Computing, 8, 1-9. doi: I0.1016/j.entcom.2015.04.001
Bryant, J., & Davies, J. (2006). Selective exposure processes. In J. Bryant & P. Vorderer (Eds.), Psycltology of entertainment. (pp. 19-34). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Cotton, John L., 1985, Cognitive Dissonance in Selective Exposure. in Zillmann D. and Bryant, J. (Eds.), Selective Exposure to Communication. Routledge.
Cummings, J. J., & Ross, T. (20 JO). Optimizing the psychological benefit of choice: Information transparency & heuristic use in game environments. In Proceedings of Meaningful Play 2010. Retrieved March 3, 2016, from http://meaningfulplay.msu.edu/proceedings2010/mp20IO_ paper_ 49.pdf
D'Alessio, D., & Allen, M. (2007). The Selective Exposure Hypothesis and Media Choice Processes. In R. W. Preiss, B. M. Gayle, N. Burrell, M. Allen, & J. Bryant (Eds.), Mass media effects research: Advances through meta-analysis (pp. 103–118). Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
Dylko, I.B., 2016, How Technology Encourages Political Selective Exposure. CommunicationTheory,Volume 26, Issue 4, 1 November 2016, Pages 389–409
Feezell, J.T., 2016, Q"Predicting Online Political Participation: The Importance of Selection Bias and Selective Exposure in the Online Setting", Political Research Quarterly 2016, Vol. 69(3) 495-509
Festinger, L. (1957). A theory of cognitive dissonance. Stanford, CA: Stanford University Press. 末永俊郎監訳 (1965) 『認知的不協和の理論』誠信書房
Festinger, L. (1964) Conflict, decision, and dissonance. Stanford, CA: Stanford University Press.
Fischer ,P and Greitemeyer, T., 2010, "A New Look at Selective-Exposure Effects: An Integrative Model. " Current Directions in Psychological Science*, Vol. 19, No. 6 (DECEMBER 2010), pp.384-389
Klapper, Joseph T. , 1960, The Effects of Mass Communication, The Free Press. NHK放送学研究室訳, 1966, NHK放送出版協会
Knobloch-Westerwick, Silvia (Ed.) (2015) Choice and Preference in Media Use : Advances in Selective Exposure Theory and Research”, Routledge.
Kobayashi, T., Zhifan Zhang, and Ling Liu (2024). Is Partisan Selective Exposure an American Peculiarity? A Comparative Study of News Browsing Behaviors in the United States, Japan, and Hong Kong. Communication Research, Published Online, October 10
Kobayashi, T., Zhifan Zhang, and Ling Liu (2024). 「見たいニュースだけ見る」はアメリカ特有の現象― 日本や香港では選択的接触は弱い ―
(https://www.waseda.jp/inst/research/news/78825)
Lazarsfeld, Paul F. , Berelson, Bernard and Gaudet, Hazel, 1944, The People's Choice: How the Voter Makes uo His Mind in a Presidential Campaign. Columbia University Press. 有吉広介他訳, 1967, 『ピープルズ・チョイス ー アメリカ人と大統領選挙』芦書房
Roberts (Eds.) The process and effects of mass communication (Rev.ed.). Urbana, IL: University of Illinois Press. pp. 209–235.
Scramm, Wilbur and Carter, Richard F. (1959) "Effectiveness of a Political Telethon, "Public Opinion Quarterly, 23, 121-26.
Sears, D.O.,and Freedman, J. L.(1967/1971). Selective exposure to information: a critical review, In W. Schramm and D. F.
Silvia Knobloch-Westerwick, Axel Westerwick,and Benjamin K. Johnson (2015) Selective Exposure in the Communication Technology Contex. in The Handbook of the Psychology of Communication Technology, First Edition. Edied by Shyam Sundar. John Wiley & Sons, Inc. Published 2015 by John Wiley & Sons, Inc.
Stroud, N. J., 2008, "Media Use and Political Predispositions: Revisiting the Concept of Selective Exposure. " Political Behavior , Sep., 2008, Vol. 30, No. 3 (Sep., 2008), pp. 341-366
Zillmann D. and Bryant, J. (Eds.), 1985, Selective Exposure to Communication. Routledge.
第12章 フレーミング効果
Scheufele, D. A., & Iyengar, S. (2017) . The state of framing research: A call for new directions. In K. Kenski & K. H. Jamieson (Eds.), The Oxford handbook of political communication .(フレーミング研究の現状と課題)
フレーミングの定義
フレーミングとは、送り手のレトリックやニュースメディアによる報道の提示様式が、大衆の意見形成に影響を及ぼすという、動的かつ状況に依存したプロセスを指してい(Iyengar, 1991; Scheufele, 1999)。
したがって、フレーミング効果とは、伝達される情報内容そのものの違いによってではなく、情報が公共的な談話の中でどのように提示されるか(どのようにフレーミングされるか)の違いによって生じる行動的または態度的な結果を意味する。
フレーミング研究の2つの系譜
フレーミング研究は、基本的に相互に独立した2つの知的伝統に起源を持つ。第一は、心理学者アモス・トヴェルスキーとダニエル・カーネマンによる研究であり(Kahneman & Tversky, 1979, 1984)、第二は、社会運動研究や一般社会学文献に根ざした多数のフレーミング研究であり、フレーミングを個人レベルではなくマクロまたはメソ・レベルの現象として捉え、広範かつ包括的な定義を採用している。(Ferree ら, 2002;Gamson, 1992;Gamson & Modigliani, 1987, 1989)。
心理学的なフレーミング研究
カーネマンらの研究では、「フレーミング」という語は、選択肢の定義における微妙な差異を記述するために用いられた。彼らの実験では、期待値が同一であるにもかかわらず、「ある金額を得る確率」と「ある金額を失う確率」といった言葉の違いによって、選択肢の提示が異なるように設計された。カーネマンとトヴェルスキーは、選択行動が問題の記述に依存することを実証した。結果が「利益」として定義された場合、人々はリスク回避的傾向を示し、より確実な選択肢を選んだ。しかし同じ結果を「損失」として提示した場合には、リスク志向となり、より不確実な選択肢を好んだ(Kahneman, 2003a )。
このような心理学的アプローチにおいて、フレーミングとは「同一の情報に対する異なる提示様式」を意味する。すなわち、提示される情報の内容はフレーム間で情報的に等価である。この研究系譜は「同等性フレーミング(equivalence framing)」と呼ばれる。
社会学的なフレーミング研究
同等性フレーム研究の生態学的妥当性の欠如に対する懸念は、社会運動研究や一般社会学文献に根ざした多数のフレーミング研究によって補完されている。たとえば Gamson(1992)は、フレーミングを、公共の談話において用いられるアイデアやシンボルと、政治問題に対して人々が構築する意味との関係と定義している。フレームは、報道のルーティンの一部として現れ、情報を迅速に識別・分類し、視聴者に効率よく伝達するための「パッケージ」として機能する(Gitlin, 1980)。最も広く引用されている包括的定義は、Gamson & Modigliani(1987)によるものであり、彼らはフレームを「進行中の出来事の連なりに意味を与える中心的な整理のアイデアまたは物語」として捉えている。「フレームは、論争の焦点、問題の本質を示す」というのである。
大多数のフレーミング研究は、この社会学的伝統に強く依拠し、「ある出来事や問題に対する異なる視点を伝える情報」として、比較的緩やかな定義に収束している。この伝統は「強調フレーミング(emphasis framing)」と呼ばれ、観察されるフレーミング効果は、単なる提示様式の違いに起因するものとは言えないような意見の違いを表している。
フレーミングの定義をめぐる2つの学派の対立
1990年代初頭以降、フレーミング、プライミング、議題設定をめぐる文献は、二つの主要な学派に分岐していった。
McCombsらの学派
第一の学派は、主としてマコームズおよびテキサス大学オースティン校(UT Austin)の伝統に基づく研究者たちで構成されている(McCombs, 2004;McCombs & Shaw, 1972, 1993)。彼らは、三つの理論モデルすべてを、議題設定という中心概念およびその基礎にある顕出性に基づく説明に根差したものと見なしている。この学派によれば、マスメディアは、ある問題の重要性を強調することによって(第一レベルの議題設定)、あるいは問題の属性を強調することによって(第二レベルの議題設定)、受け手の認知に影響を与える。彼らは、この第二レベルの議題設定を、フレーミングと同一視する。
この見解は、プライミングを議題設定の結果と捉えるアイエンガーとキンダー(1987)の概念化と呼応しており、さらにフレーミングを第二レベルの議題設定と同等のものとして包含している。
Scheufeleらの学派
このようなマコームズらのアプローチは、概念的にも実証的にも批判を受けており、多くの研究者が、より限定的で「同等性に基づくフレーミングの定義」へと立ち戻るべきだと主張している(Scheufele, 2000;Scheufele & Tewksbury, 2007;Tewksbury & Scheufele, 2009)。アイエンガー(1991)による政治的メッセージのフレーミングに関する画期的研究を発展させる形で、この第二の学派は、フレーミングを「ある特定の情報内容に対して、提示様式の違いによって引き起こされるメディア効果」のみに限定して定義する。すなわち、異なる事実や問題の異なる側面、あるいは別の議論が提示された結果として生じる効果は、フレーミングとは見なされないという立場である。
この第二の学派に属する研究者たちはまた、フレーミングが依拠する理論的前提と、議題設定およびプライミングが依拠する理論的前提とは、本質的に異なるものだと主張する(Price & Tewksbury, 1997)。そして、それぞれのモデルに固有の理論的前提は、今後の各研究領域の方向性を定める上で極めて重要だとされる(Scheufele, 2000)。
アクセシビリティとアプリカビリティの違い
同等性フレームと強調フレームの混同、ならびにフレーミングと他の認知効果モデル(プライミングや議題設定)との概念的重なりの一因は、研究者たちがそれぞれの概念の歴史的・理論的基盤、すなわち各効果モデルの背後にあるメカニズムを説明する前提条件に十分な注意を払ってこなかったことにある。
アクセシビリティに基づく効果(議題設定)
議題設定およびプライミングは「アクセシビリティ(接近可能性)」に基づく効果である(Iyengar, 1990)。メディア報道は、特定の問題(Funkhouser, 1973a, 1973b)やその属性(Kim, Scheufele, & Shanahan, 2002)に関する顕出性の認知に影響を与える。顕出性が高まることで、受け手の心の中にある関連ノードが活性化され、そこから関連する概念へと活性化が拡散する(Collins & Loftus, 1975)。その結果、これらのノード群はより接近可能となり、候補者や政策について判断を下す際に記憶からより容易に呼び起こされるため、態度や評価に対する影響が強まることになる(Zaller, 1992;Zaller & Feldman, 1992;Iyengar, 1991)。
アプリカビリティに基づく効果(フレーミング)
これに対し、フレーミングは、Price と Tewksbury(1997)が「アプリカビリティ(適用可能性)効果」と呼んだものである。その最初期の理論的基盤は、20世紀前半のゲシュタルト心理学(Wertheimer, 1925)および後の帰属理論(Heider, 1978)に見ることができる。これらの研究領域は、人間が一見無関係な情報断片の中に、既存のスキーマと整合するパターンを見出すことによって意味を構成しようとする傾向に注目していた。
「適用可能性」という概念は、このような知的伝統に依拠しており、特定のフレームの効果は、それが受け手の既存の認知スキーマにどれほど適合するかに応じて強まったり弱まったりすると仮定する。すなわち、ある情報がどのように提示されるか(つまりフレームの形態)は、それが特定のスキーマを用いて処理されるかどうかを大きく左右する。この「適用可能性モデル」は、前述の Bruner と Minturn(1955)による「壊れたB」実験と整合する。すなわち、数字の列の中で提示された場合にはその刺激は数字「13」として処理されやすく、文字の文脈で提示された場合には文字「B」として処理されやすくなる。
フレーミング研究の課題
フレーミング研究の直面する3つの課題
残念ながら、これまでのフレーミング、議題設定、プライミングに関する研究の多くは、こうした「スキーマ非依存型効果」(議題設定・プライミング)と「スキーマ依存型効果」(同等性フレーミング)との区別について、十分な実証的知見を提供していない。この点の曖昧さは、将来的にフレーミング研究が直面する三つの重大な課題を引き起こすことになるだろう。
第一に、それぞれの効果モデルの理論的基盤は、各理論が対象とするメカニズムを明確に区別する手助けとなる。第二次世界大戦以前の「魔法の弾丸」あるいは「皮下注射」モデルが、主に人々に「何を考え、信じるべきか」を伝える説得的コミュニケーションに焦点を当てていたのに対し、議題設定理論はこの直接的な説得の概念を明示的に退け、代わりに「人々に何について考えるべきか」を知らせるというメディアのより間接的な役割に注目した(Cohen, 1963)。これに対し、フレーミングは説得とも議題設定とも異なり、人々が受け取った情報をどのように意味づけ、すなわちどの「心の棚」に分類して記憶するのかというプロセスに関心を持つ。
第二に、スキーマは文化的に共有されるものである。このため、ある特定文化内部でのフレーミング効果の検証では、その「適用可能性効果」は、異文化間比較において観察される効果よりも弱くなる可能性が高い。たとえば、前述の「壊れたB」刺激は、ローマ字やアラビア数字に慣れ親しんだ受け手に対してのみ、フレーミング効果を生じさせる。政治においても、アメリカの「常習犯法(habitual offender legislation)」は実例となる。アメリカの州の約半数では、重大犯罪で三度有罪判決を受けた者に対して、強制的な懲役刑を科すことを義務づける法律が存在する。これらの法律はしばしば「スリー・ストライク法(three strikes laws)」というフレームで語られる。このフレームは、野球のルールに親しんでいる聴衆には強く共鳴するが、ドイツのように野球への理解がほとんどない文化においては意味をなさず、該当する認知スキーマが存在しないため、「three strikes」フレームの影響を受けにくい。
このように、今後の研究では、文化間におけるスキーマの違いがコミュニケーション効果の帰結にどのような影響を与えるかを、より精緻に検討する必要がある。たとえば、アジアとアメリカ合衆国におけるモノカルチャル(単一文化的)およびマルチカルチャル(多文化的)個人の比較研究では、スキーマの体系的差異が将来のフレーミング研究に有益な知見をもたらす可能性があることが示されている(Fung, 2010)。
第三に、そして最も重要な点として、近年の文献における同等性フレームよりも強調フレームへの傾倒が、スキーマ依存型効果を覆い隠してしまっている可能性が高い。すでに述べた通り、現在ではフレームは、メッセージ中の他の情報的または説得的要素との区別を曖昧にしながら、単純な説得効果として検証されることが増えている。このような情報的または説得的効果は、議題設定やプライミングと同様に、受け手にかかわらず普遍的に作用する傾向がある。そのため、これらの効果は、スキーマ依存的なメディア効果としての厳密な「同等性フレーミング」の定義とはほとんど関係がないといえる。
著者による提言
我々は、フレーミング研究を強調フレームから同等性フレームへと再方向づけるべきであると提案する。そのためには、フレーミング操作の対象として用いる刺激の種類を拡張し、より厳密な同等性デザインを追求する必要がある。
現在のフレーミング研究が強調フレームに依存する傾向にある一因は、フレーミング操作を構成する際の容易さにある。すなわち、ある態度対象について異なる観点を提供する3~4段落の文章を用意するのは、相対的にコストがかからない。しかしながら、すでに述べたように、異なる言葉は単なる観点の違い以上の意味を含みうるし、異なる個人が同じ言葉を異なって「読解」する可能性も高い。
このような語義の曖昧さに伴う問題に対する一つの解決策は、非言語的手がかりを用いてフレーミング効果を測定することである。「一枚の写真は千の言葉に値する」と言われるが、フレーミング研究においては、画像操作が精度の高い操作変数として追加的な価値を持つ。すなわち、ある特定の次元においてのみ異なるが、それ以外のすべての観察可能な次元において同一であるような代替画像を作成することが可能であるため、受け手の反応における変化を、操作されたその特定次元に帰属させることができる。
顔の類似性や肌色に関する研究が示唆するように、視覚的フレームは、候補者の特定属性に対する研究者の操作を精密に制御できる点で有効である。候補者は、人種、性別、年齢、その他の身体的属性に基づき、内集団の一員としてフレーミングされ得る。視覚メディアは、フレーミングの精密性と同等性フレーミングの伝統への回帰を可能にするだけでなく、日常的な政治情報の流れにおいて不可欠な構成要素でもある。放送メディアの登場以降、非言語的手がかりは政治的・文化的談話において極めて重要な要素となってきた。視聴者規模においても、放送ニュースの視聴者数は印刷メディアのそれを大きく上回っており、非言語的手がかりはマス世論に対するフレーミング効果の生態学的妥当性のある検証手段とみなされるべきである。
さらに、非言語チャネルは「情動(affect)」の伝達において特に重要であるという点で、研究者にとって大きな利点をもつ。政治的対象に対する態度の多くは情動的な含意を有しているため、非言語的フレームは政治的態度や行動に影響を及ぼす潜在的に強力な手段となる。
そこで著者は、フレーミングおよび関連する認知効果モデルに関して、政治コミュニケーションにおけるより精緻かつ正確な概念的思考を改めて推奨する。特に、フレーミングという概念の内部においてさえ、我々は研究者が将来の実証研究を、メッセージの情報的・説得的内容の操作ではなく、「刺激の提示様式の違い」に基づいて構成することを強く提言している。
参考文献(第12章)
Entman, R. E. (1993). Framing: Toward cclarification of a fractured paradigm. Journal of Communication, 43, 51-58.
Goffman, E. (1974). Frame Analysis: Essya on the organization of experience. Boston, MA: Northeastern University Press.
Johnson-Cartee, Karen S. (2005) News narratives and news framing : constructing political reality /
(Communication, media, and politics)
Gitlin, T. ( 1980). The whole world is watching: Mass media and the making and unmaking of the New Left. Berkeley, CA: University of California Press.
稲増一憲 (2015) 政治を語るフレーム:乖離する有権者、政治家、メディア. 東京大学出版会
Johnston, H., & Noakes, J. A. (Eds.). (2005). Frames of protest:Social movements and the framing perspective. Boulder, CO: Rowman & Littlefield.
Kahneman, D., & Tversky, A. ( 1979). An analysis of decision under risk. Econometrica, 47,263-291.
Levin, I. P., Schneider, S. L., & Gaeth, G. J. ( 1998). All frames are not created equal: A typology and critical analysis of framing effects. Organizational Behavior and Human Decision Processes,76, 149-188.
Matthes, J., & Kohring, M. (2008). The content analysis of media frames: Toward improving reliability and validity. Journal of Communication , 58, 258-279.
Messaris, P., & Abraham, L. (200 I). The role of images in framing news stories. In S. D. Reese, 0. H. Gandy Jr., & A. E. Grant (Eds.), Framing public life:Perspectives on media and our understanding of tire social world (pp. 215-226). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Nelson, T. E., & Willey, E. A. (2001 ). Issue frames that strike a value balance: A political psychology perspective. In S. D. Reese, 0. H. Gandy Jr., & A. E. Grant (Eds.), Framing public life: Perspectives on media and our understanding of the social world (pp. 245-266). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Nisbet, M. C. (2010). Framing science: A new paradigm in public engagement. In L. Kahlor & P.A. Stout (Eds.), Communicating science: New agenda in communication( pp. 41-67). New York, NY: Routledge.
Pan, Z., & Kosicki, G. M. (1993). Framing analysis: An approach to news discourse. Political Commnication, 10, 55-76.
Reese, S. D. (2001). Prologue-Framing publiclife: A bridging model for media research. In S. D. Reese, 0. H. Gandy Jr., & A. E. Grant (Eds.), Framing public life:Perspectives on mediand our
understanding the social world (pp. 7-32). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Scheufele, D. A. (1999). Framing as a theory of media effects. Journal of Communication, 49 (1), 103-122.
Scheufele, D. A., & Iyengar, S. (2017) . The state of framing research: A call for new directions. In K. Kenski & K. H. Jamieson (Eds.), The Oxford handbook of political communication .
New York, NY: Oxford University Press.
Sniderman, P. M., & Theriault, S. M. (2004). The structure of political argument and the logic of issue framing. ln W. E. Saris & P. M. Sniderman (Eds.), Studies in public opinion: Attitudes,
nonattitudes, measurement error, and change. (pp. 133-165). Princeton, NJ: Princeton University Press.
竹下俊郎, 1998, 2008, メディアの議題設定機能--マスコミ効果研究における理論と実証〔増補版〕学文社
竹下俊郎, 2007, 「議題設定とフレーミング-属性型議題設定の2つの次元」『三田社会学』第12号, pp.4-18.
Takeshita, T. , 2006, Current critical problems in agenda-setting research. International Journal of Public Opinion Researcch, 18, 275-296.
Tuchman, G. (1978). Making news : A study in the construction of reality. New York, NY: FreePress.
Vliegenthart, R., & Walgrave, S. (2012). The interdependency of mass media and social movements.In H. A. Semetko & M. Scammell (Eds.), The Sage handboook of political commrmication(pp. 387-397). Los Angeles, CA: Sage.
Zaller, J., & Feldman, S. (1992). A simple theory of survey response: Answering questions versusrevealing preferences. American Journal of Political Science,3 6, 579-616.