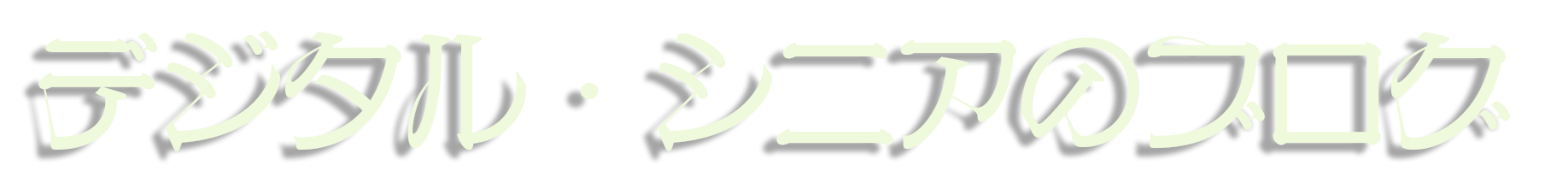![]()
「パニック報道」異聞
マスメディアが「パニツク」をセンセーショナルに報道する傾向は、アメリカに留まるものではない。日本でも過去に「パニック」と報道されながら、実態がそれとは違っていたというケースがいくつかあった。そのなかで、筆者自身が調査に関わった事例を二つ紹介したいと思う。
「余震情報パニック」事件
この事件は、1978年1月18日に起こった。4日前の伊豆大島近海地震のあと、しばしば余震が続いていたが、18日正午、静岡県災害対策本部から「余震情報」が発表された。この中で、今後一カ月程度、最大でマグニチュード6程度の余震が発生する可能性があるので、注意してほしいとの情報が出された。 翌朝、主要全国紙はいつせいに、この余震情報が静岡の全域でパニックを引き起こした、と報じた。


誤報「警戒宣言」パニック報道
1981年10月31日午後9時頃、平塚市で広報無線の拡声機から、東海地震の「警戒宣言」が発令されたとの誤放送が流れた。翌朝の『読売新聞』は、この誤放送が住民の間にパニックを引き起こしたかのような報道を行なった。

読売「パニック」報道の真相
この出来事について、全国紙の『読売新聞』は一面トップで、次のように報じた。
『朝日新聞』も、「パニック寸前の騒ぎ」という表現ながら、やはり1面トップで、同報無線が引き起こした混乱を報じている。 このうち、『読売新聞』の記事には、住民の反応以外の事実関係でいくつかの誤りが含まれていた。一つは、「避難命令が出された」というものである。実際には「いつでも避難できるように準備しておくように」という避難準備の呼びかけにとどまっていた。もう一つは、「激しいサイレンが鳴り出し」という部分で、実際にはそのような事実はなかった。 筆者らの研究グループでは、このような「誤報」ともいえる新聞報道が行われたことの実態を探るために、朝日、読売、神奈川3紙の記者や編集者にインタビューを行い、事件当夜の取材、報道過程の解明を試みた。ここでは、読売新聞の事例を紹介しておきたい。 事件の取材、報道を主に担当した部局は、東京本社の編集部と整理部、横浜支局、および平塚通信局だった。このうち、直接本文および前文の記事の原稿を作成し、送稿していたのは、横浜支局および平塚通信部の記者だった。 事件の第一報はまず横浜支局に入った。午後9時5分ごろ、平塚市内の読者から「いま広報無線で放送しているが、警戒警報があったのか」という問い合わせがあった。これを聞いて、横浜支局のA記者は、最初何かの間違いではないかと半信半疑だった。というのは、この種のイタズラ電話は以前にも経験していたからである。 しかし、とにかく取材を開始することにし、そのとき支局内にいた4人全員に指示して、電話取材に当たらせた。 まず、気象台に電話を入れ、警戒宣言が本当に出たのかどうか確認したところ、「そんな警報は出していない」というので、もし実際に出たとすれば誤報であることが確認された。次に、県警に電話をしたところ、「そういう話は聞いていない」というので、今度は平塚警察に電話して問いあわせた。すると、「そういう話があるので電話が殺到している」という返事だったので、誤報が出たのは事実らしいと判断した。平塚市役所へも電話したが、話し中でつながらなかった。 A記者と支局デスクは、こうした初動の電話取材を通じて、この事件について、もし誤報が事実だとすれば、これは東海地震では初めてのケースであり、ニュースバリューとしてはかなり高く、「全国版の頭を張れるニュースだ」と判断した。以後の取材は、この基本方針に基づいて行われることになった。 平塚通信部駐在のB記者との電話連絡は、輻輳のためなかなか取れなかったが、約10分後にやっとつながった。A記者はB記者に対し「大変なことが起きているようだね」と言ったが、B記者はこのとき当の平塚で何が起きているかをほとんど把握していなかった。 誤放送のあった当日の夜9時ごろ、B記者は平塚市内の自宅で家族とともに、テレビを見たり新聞を読んだりしてくつろいでいた。9時3分すぎ、突然外でスピーカーらしきものから何かワーワー音がするので、何事かと思い、窓を開けてみたがはっきりせず、妻と一体何だろうと話し合った。最初は広報無線からの放送とは気づかず、廃品回収車の拡声器か何かかと思ったが、この時間にしてはおかしいので、調べてみようという気持ちになった。 まず、警察署に電話してみたが通じなかったので、次に市役所、消防署の順に電話してみたが、結局どこにもつながらなかった。横浜支局のA記者から電話が入ったのはそのときである。B記者はまだ正確な情報を何一つ得ていなかったが、「大変なことが起きているようだね」という問いかけに対し、とっさに「ええそうですね。そちらにはどんな情報が入っていますか?」と受け返し、「誤報が出たという情報が入っている」という返事を得て、初めて事件の発生を知ることになったのである。 この電話で取材の打合せが行われた。A記者も支局デスクも「平塚ではパニックが起きている」と思っていたので、おそらく市民が街の中をゾロゾロ歩いているだろうと想像し、「市役所へ行く途中でパニック状態になっている住民の表情がわかるような写真を撮れ」とB記者に指示した。 B記者はただちにカメラを片手に市役所の記者クラブへと急いだ。しかし、市役所へ向かう途中、市民の様子は冷静で「とくに混乱は起きていない」という印象を受けた。結局、A記者に指示されたような「絵になる」被写体を見つけることはできなかった。その夜いっぱい、B記者は市役所内の記者クラブにいて、誤報関係者の取材をしたり、3~4人の市民に電話で取材をしたが、市民の反応は冷静だったため、誤報の原因解明に取材のポイントをおくこととし、、取材の大半はこれに費やされることになった。 一方、横浜支局では、B記者から市民の反応が予想外に冷静だとの情報を得、またパニックの証拠となるような写真も入手できなかったので、当初の「パニックが起きた」との判断が若干揺らいだ。しかし、支局で平塚市の電話張をめくって市民に直接電話取材をしたところ、「防災頭巾をかぶったりして家の中でワーワーやっている」人が何人かいたし、「避難袋を抱えて外に出ている人もいる」と答えた市民もいた。また、B記者からの連絡でも、市役所に行く途中、外に出ている人を何人か見たということだったので、「完全なパニック」とはいえないまでも、それに近い状態が起きているのではないかと判断し、「パニック状態」と若干ニュアンスを弱めた表現にして記事を書き、東京本社へ送稿したのである。 こうして、「パニック」記事が作られることになったわけであるが、その主たる原因としては、当初から「パニックが起きた」とA記者が速断していたこと、原稿の締め切り時間が迫っていたこと、現地での取材要員が一人しかおらず十分な取材ができなかったこと、取材して得た情報が誇張ないし歪曲して解釈されたこと、などをあげることができる。 記事全体の要約ともいえる「前文」をA記者が書き上げたのは午後11時頃だったが、この時点ではまだ、パニックが起きたかどうかを最終的に確認することはできず、前述のように「パニック状態」という若干あいまいな表現で報道することになった。しかし、この記事が東京本社に送られ、整理部が見出しをつけたときには、こうした微妙なニュアンスは伝わらず、「夜の警報パニック」というセンセーショナルで断定的な表現にされてしまったのである。 以上の点から明らかなように、「パニック」報道は、送り手側が日ごろから持っている「パニック神話」にもとづいて、取材の過程で知らず知らずのうちに一定方向への誇張ないし歪曲が加えられた結果つくられたものであった。「メディア・リテラシー」は、情報の受け手側だけではなく、送り手側にも求められるという教訓を残した事件だったということができよう。 1938年の『火星からの侵入』パニック報道にも、同じようなプロセスが働いていた可能性も、あながち否定できないのである。
参考文献:
H.Cantril, 1940, Th Invasion from Mars: A Study in the Psychology of Panic. 齋藤耕二・菊池章夫訳『火星からの侵入?パニックの社会心理学』(1971)
R.Bartholomew and H.Evans, 2004, Panic Attacks: Media Manipulation and Mass Delusion. The War of the Worlds (Wikipedia) The night that panicked America (YouTube)1975
Jefferson Pooley and Michael J. Socolow, 2013, The Myth of the War of the Worlds Panic
東京大学新聞研究所編『地震予知と社会的反応』(東大出版会)(1979)
東京大学新聞研究所編『誤報警戒宣言と平塚市民』(1982)
三上俊治(1984)「パニックおよび擬似パニックに関する実証的研究」『東洋大学社会学部紀要』21号