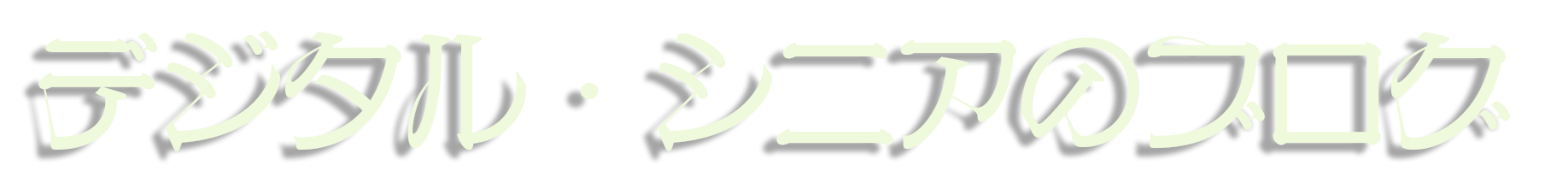![]()
三上俊治 「大衆社会論」の系譜
『新聞学評論』35号 特集 大衆社会論 pp.74-101, 1986
1. 大衆社会論の歴史的展開
大衆社会論は、科学技術の進歩と資本の蓄積とを基盤とする産業革命の進展、および、市民的自由と政治的平等とを基本原理とする民主主義制度の普及を構造的基盤として、十九世紀のヨーロッパで生まれた新しい社会理論である。その基本的な考え方は、政治・経済制度の近代化とともに登場した均質的な「群衆」ないし「大衆」が、その量的膨大さのゆえに、多数の圧力によって大きな社会的影響を及ぼすようになった、という点にある。 そこでまず、大衆社会論の歴史的展開の跡をたどることによって、現在の到達点を確認するという作業を行っておくことにしたい。
大衆社会論の誕生
大衆社会論が登場した当初は、大衆ないし群集が政治的舞台の前面に登場してきたことによる多数者の専制や権力の集中、非合理的・情緒的な群集の支配による社会の混乱、凡庸で愚味な大衆の支配による伝統的文化の危機など、貴族階級の没落と伝統的な自由主義的価値の崩壊が中心的テーマとなっていた。その代表的論客としては、トックヴィル(Tocqueville, 1835, 1840)、J.S. ミル(Mill, 1859)、シュペングラー(Spengler,1925)、ル・ボン(Le Bon, 1895)、タルド(Tarde, 1901)、リップマン(Lippman, 1923)、オルテガ (Ortega, 1930)などがいる。
トックヴィルは、10カ月間にわたるアメリカ視察旅行の経験をもとに、全3巻から成る『アメリカにおけるデモクラシー』を著わした(Tocquevile, 1835,1840)。彼はその中で、「諸階層の平等化」を社会発展の必然的な歴史の趨勢としてとらえ、その政治的本質を「人民の名における多数者の支配」にあると考えた。そして、民主政治が多数者の圧制や権力の集中を招く危険性を指摘すると同時に、これらの弊害を緩和するための方策として、団結の自由、地方自治体の自律性、人民の参加などの制度的保障に加えて、法や習俗などのもつ重要性を強調した。トックヴィルの目に当時のフランスは、「進歩の名において人間を物質化し、正義を顧慮しないで効用のみを求め、信仰と知識とを隔絶し、徳義と幸福とを分離する人々」の進出によって社会秩序が混乱に陥り、デモクラシーが危機に瀕しているように映った。彼の問題意識は、このような危機的大衆社会状況を克服し、真のデモクラシーを実現するための道を探ることにあったといえよう。
ル・ボンもまた、群集の専制と横暴に対して危惧の念を表明した思想家の一人だった。彼は、群衆を暗示と感染にかかりやすい衝動的で移り気な性格をもつものとしてとらえた(Le Bon,1895)。そして、そのような非合理的群衆が政治生活を支配するような現状が続く限り、これまで少数の「貴族的知識人」によって創られてきた文明はやがて破壊されてしまうだろう、と彼は響告したのである。
時期的には二十世紀に入るが、ル・ボンと同様に貴族主義論価値観にもとづいて大衆社会論を展開した思想家にオルテガがいる。彼は当時のヨーロッパにおいて、『大衆』という名の均質性の一形式が勝利をおさめ、完全に社会的権力を掌握するに至った、と考えた(Ortega,1930)。オル・テガにとって大衆とは、歴史性をもたず、自らに厳しい義務を課す高貴な精神や自我意識にも欠け、ただ欲求と権利意識だけを強く持っているような凡俗な人間ないしその集合体のことを意味していた。その大衆が、本来は選ばれた少数のエリートの領域だった政治の分野にまで進出し、法を無視した直接的行動という物質的圧力によって少数者たちを押し退け、彼らにとって代わろうとしている現状に、彼は批判の目を向けた。なぜなら、大衆の支配は確かにマスメディアの登場や産業の発展等による「生の増大」 (空間的・時間的拡大と潜在的可能性の増大)を反映したものであるが、同時にそれは創造的な少数者の圧殺、道徳の退廃、そして遂には国家の没落をもたらす危険性をはらんでいると考えられたからである。オルテガは「大衆」の支配する現状を憂えるとともに、少数の教養あるエリートによるモラルの再興を訴えたのである。
全体主義的状況下の大衆社会論
こうした初期の大衆社会論は、「大社会」状況の出現(Wallas, 1914)という現状認識を共有しながらも、第一次大戦後のヨーロッパにおける全体主義的独裁制の成立という新たな政治的局面の出現に伴って、ファシズム体制を批判するための有力な理論的武器として新たな展開をみせることになった。すなわち、一方では、中間集団の解体と官僚制の進展による近代人の孤立と自己疎外が無力感や不安を生んでいることが指摘されるとともに、他方では、マスメディアを用いた宣伝や暴力などによって、原子化した大衆の操作が行われ、その結果、全体主義的独裁政治を招いたことが批判されたのである。
マンハイムは、初期の大衆社会論者と同様に、産業化と民主化の進展を大衆社会成立の基本的原因と考えたが、その論理的帰結はかなり異なるものであった。
産業化の進展とともに分業化と組織化が進行するにつれて、人間の活動はますます合理的なものになってゆく。官僚制組織はそうした機能的合理性を極限まで追求して得られた社会形態である。しかし、機能的合理性は平均的個人から思考力や責任能力を奪い、それらを少数の指導的エリートに委譲せざるを得なくなる。つまり、大衆の「実質的合理性」は逆に減少し、その結果、エリートと大衆の距離は大きくなり、大衆は無力感と絶望的不安に陥る、とマンハイムは考えたのである(Mann-heim, 1935)°
一方、社会の広範な諸階層が政治に参加するようになるという**「基本的民主化」が進行するにつれて、大衆の非合理的な感情が爆発して政治的混乱を引き起こす危険性も次第に強まっていく**。しかも、相互依存性の大きい近代社会では、こうした非合理的な感情の噴出は全階層、全世界にまで波及する恐れがある、とマンハイムは主張した。独裁制は、こうした大衆民主主義の否定的な活動力を逆に利用することによって成立した政治体制に他ならない。
このように、マンハイムは機能的合理化と基本的民主化の進展が、それぞれ大衆の疎外と非合理的な大衆行動を生み出す危険性を指摘し、大衆社会に内在するディレンマを明らかにしたのである。
**レーデラー、S・ノイマン、H・アレントらは、原子化したアモルフ(無定形)な大衆が近代的独裁政治の基盤となっていると考えた。**すなわち、ファシズム勢力は家族を始めとするあらゆる中間集団を破壊し、言論と表現の自由を奪うことによって、すべての人々をバラバラの大衆人(マス・マン)に解体したうえで、こうして裸になった大衆を宣伝と暴力によって思うままに操作し、そこから熱狂的な支持を引き出すことに成功した (Lederer, 1940; Neumann, 1944; Arendt, 1962)° また、フロムは、ファシズムの存立基盤を近代人の社会的性格に求め、近代的「自由」のもたらす孤独と不安が人々をナチズムの権威主義的性格に引きつける要因となった、と分析している (Fromm, 1941)°
戦後アメリカの大衆社会論
大衆社会論が見いだした第三の舞台は、第二次大戦後のアメリカ社会であった。すなわち、大戦中に蓄積された巨大な資本力、組織の機械化と官僚化、マスメディアの影響力増大などを背景として、アメリカ社会は典型的な大衆社会状況を示すとともに、社会病理的な問題も生じてきた。こうした社会状況を分析し、時代の診断を試みた人々としては、C・W・ミルズ、D・リースマン、W・コーンハウザー、ホワイトなどがいる。
ミルズは、大企業の進出と組織の官僚化などに伴って、農民・中小企業家を中心とする旧中流階級が没落し、それに代わって、管理者・専門職・事務員・販売員などの新中流階級(ホワイト・カラー)の比率が著しく増大している事実に注目した(Mills, 1951)。新中流階級は何らの資産ももたず、ただ官僚組織の一員として、非人格化されたサービスを切り売りするだけの「部品」と化している。高度に合理化された巨大な官僚機構の下で、彼らは無力感と敗北感に陥るが、余暇生活においては、マスメディアの提供する気晴らし的な娯楽に逃避している。
マスメディアはまた、大衆の政治的無関心を助長する原因にもなっている、とミルズは指摘している。さらに『パワー・エリート』において、権力構造の分析を通して、大企業・政府・軍部から成る少数のパワー・エリートがアメリカ社会を支配している一方で、ホワイト・カラーや賃金労働者を中心とする大衆が巨大な底辺を形づくり、権力から疎外された状態に置かれている、と主張した(Mills,1956)。つまり、ミルズにとっての問題意識は、新中流階級の比重が増大したにもかかわらず、彼らが政治的にも経済的にも文化的にも疎外され、無気力な状態に置かれている、という矛盾を解明し、その克服の道を探ることにあったといえよう。
リースマンは、人々の社会への適応様式が人口増加率の変化とともに、「伝統指向型」→「内部指向型」→「外部指向型」という変遷をたどったと考え、現代人の示す典型的な社会的性格が、たえず周囲に気をくばり、自分自身を他者の期待に合わせようとする「外部指向型」である。と指摘している(Riesmanet al,1960)。リースマンにとっての問題意識は、他人指向型の現代人が過剰同調的な傾向に陥り、自律性を喪失することへの危機感にあり、現代社会に適応しながらも、なお自律性を維持するための方策を探ることにあった。
コーンハウザーは、従来の大衆社会論を、エリートが大衆の圧力にさらされ本来のエリート機能を果たし得なくなっていると考える「貴族主義的批判」の系譜と、逆に大衆が疎外・孤立状況の中でエリートのシンボル操作と動員によってたやすく操作されていると考える「民主主義的批判」の系譜とに分けた上で、両者を統合した独自の大衆社会論を展開した。彼は「エリートへの近づきやすさ」と「非エリートの操作されやすさ」とう二つの変数を組み合わせることによって、「共同体的社会」「全体主議社会」「多元的社会」「大衆社会」という四つの社会類型を構成した(Kornhauser, 1959)。そして、大衆社会を「エリートが非エリートの影響を受けやすく、かつ非エリートがエリートに操作されやすい社会制度」として規定した。このような大衆社会の特徴としては、地域社会や自発的組織などの中間的関係の弱体化、個人的関係の孤立化、権力の集中化、文化的画一性と流動性などがあげられる。コーンハウザーにとっての問題意識は、大衆社会が全体主義に転化する危険性の認識と、多元的社会を維持ないし実現するための条件を探ることにあったと思われる。
わが国における「大衆社会論争」
わが国でも第二次大戦後の民主化と産業の発展、マスメディアの普及などを背景として、欧米の大衆社会論が輸入され、やがて「大衆社会論争」を引き起こすに至った。 清水幾太郎氏は、その著『社会心理学』(清水、一九五一)において、現代社会に固有の特性として、「分化」「拡大」「機械化」という三つの側面に注目した。これら三つの傾向は、社会および人間の近代化をもたらしたが、他方では集団の分裂や衝突、人間関係の稀薄化・間接化、マスコミの発達によるコピーの支配と非合理的普遍性の拡大、官僚制機構の下での人間の部品化と無力化とをもたらしている。その結果、タルドが合理的、理性的存在としてとらえた公森は、現実には「大衆」という名の新しい巨大な群集として立ち現れている、と清水氏は考えた。
彼の議論は欧米の大衆社会論を日本に紹介したという点では高く評価できるが、従来の理論を整理し直しただけにとどまり、現実の日本社会に関する実証的分析は十分に行われていない。
そうした欠陥は、一九五六年から六〇年にかけて展開された「大衆社会論争」や、それに触発されて現れた幾多の大衆社会論関係の論文(例えば、高橋・城戸綿・貫、一九五七)においても基本的に克服されることはなかった。
いわゆる「大衆社会論争」の発端となった松下圭一氏の論文「大衆国家の成立とその問題性」(松下、一九五六)は、古典的大衆社会論とマルクス主義的階級社会論の統合をはかろうとしたユニークな試みとして注目された。彼は、大衆社会への形態転化を生み出した原因が資本主義の独占段階への移行にあったと考える。すなわち、資本主義の独占段階への移行は、資本の蓄積・集中およびテクノロジーの発達にもとづいて、生産過程を変化させ、大量生産と大量伝達、労働者階級の量的増大と新中間階級の登場を媒介として、膨大な「大衆」を生み出した。
同時に、それは「組織化」と「原子化」を軸とする社会の形態転化を引き起こし、労働者の商品化・専門化・孤立化、マスメディアの発達に伴う大衆文化の感性的消費化と情緒化とをもたらしている、と彼は主張する。そして、かつての「階級」は膨大な「大衆」として政治過程の前面にあらわれたとはいえ、かえって体制側からの操作対象として受動化され、その政治的自由は内面から空洞化される危険性をはらんでいる、と結論づけている。松下氏の問題意識は、こうしたネガティブな契機をはらむ「大衆」状況を克服するための条件を探ることにあり、階級の論理と結合した市民的自由の再編成と、その出発点としての自主的集団の形成とに解決の道を求めたのである。この松下論文に対しては、正統的なマルクス主義者の側からの反論が加えられ、一連の論争を引き起とすことになった。
例えば、柴田進午氏は、「大衆化」現象の真の原因は国家独占資本主義にあり、新中間階級の増大はそのような矛盾がいっそう深化したことのあらわれだと主張した。また、新中間階級は決して圧倒的多数ではなく、大部分の国民はいまなお生活水準が低く「大量消費」や「大衆文化」の享受者でさえないこと、大衆は決して無力でも無 定形でもないこと、大衆化が進む一方で労働者の団結や闘争の前進がみられること、などをあげ、大探社会論は現象の表面だけをとらえた非科学的理論であるとしている。そして、大来社会論を安易にマルクス主義と折衷するのではなく、マルクス主義自身を内在的に発展させることが必要だ、としている。大衆社会論争は、近代主義的政治学やマルクス主義陣営に対して大きな刺邀になったことは確かであるが、大衆社会論そのものを発展させるまでには至らずに終息した。
大衆社会論の衰退
一九六〇年に入ると、産業社会論、知識社会論、管理社会論、脱工業社会論などの新しい社会理論が次々と論壇を賑わし、大紫社会論は潤落の一途をたどった。大衆社会論衰退の原因としては、次のような事情が考えられる。すなわち、①大衆社会論の有効性・妥当性に対する根本的な批判が提起されたこと、②大衆社会論の提起した諸問題が専門分化した各学問分野の中に吸収されてしまい、大衆社会論そのものは実証的方法論を欠いていたために発展できなかったこと、③大社会論の中で論じるべき問題点がほぼ出尽くしてしまったこと、④大社会状況が常態化したために、新鮮で予測力をもった社会理論としての魅力を失ってしまったこと、⑤他の社会理論が次々と現れ、大衆社会論がある意味では流行運れの「過去の理論」として振り向かれなくなってしまったこと、⑥わが国では、六〇年代に入ると高度経済成長を背景としたバラ色の現実や未来を論じる風潮が強まり、現状批判的性格をもつ大衆社会論は歓迎されなくなったこと、などである。
大衆社会論を真っ向から批判した論稿としては、ダニエル・ベルの『イデオロギーの終焉』(Bell, 1961)が有名である。彼は従来の大衆社会論が、①シルエット以上のイメージを与えてくれず、現実の社会を分析する道具としてはきわめて不十分である、②「大衆」の概念規定にみられるように、大衆社会論の諸説は矛盾を含んでおり、相互連関性が明確ではない、③理論全体を統合する組織原理に穴けている、④「大衆蔑視」「平等への嫌悪と自由の礼識」「大衆社会のマイナス面の強調」など、イデオロギー的偏見を含み公正さを知いている、⑤大衆社会は何世代もかかって成熟するものであり、大衆社会論の主張するような急な大衆化は非現実的である、などとしてきびしく批判した。そして、「大衆社会論はもはや欧米社会の記述として役立つものではなく、現代生活へのロマンティックな抗議のイデオロギーにすぎない」と結論づけている。
また、官僚制組織における機能的合理性と実質的非合理性 (Mannheim, 1935; Mils, 1951)や組織への過剰同調性(Riesman et al, 1960; Whyte, 1956)などの問題は、経営管理論や組織論の発展の中に吸収され、エリートによる大衆操作の問題は、近代政治学やマス・コミュニケーション理論の中で独自の展開を遂げるなど、大衆社会論の提起した多様な論点は、専門分化した個別の学問分野の中に吸収されることになった。
同様に、大衆社会論の取り上げた社会現象が、知識社会論や管理社会論の中で新たな視点から新しい解釈を加えられ、独自の理論として発展させられていった。例えば、科学技術の進歩とそれに伴う産業構造の変化は、知識社会論や脱工業社会論においては、情報を付加価値とする「知識産業」や「情報的職業」の増大として把握され、情報化社会論へと展開していった。
また、少数のエリートによる大衆操作の問題は「管理社会論」において継承されている(庄司、一九七七)。 大衆社会論が実証的な方法論を久いていたことは、大衆社会論が60年代以降急速に後退していったことの重要な原因と考えられる。例えば、「砂粒のようにバラバラの原子化した大衆に対してマスメディアが巨大な影響力を及ぼし、エリートによる大衆操作が容易に行われる」という図式は、第二次大戦後のアメリカにおける実証的マスコミ研究の中でもろくも崩れ去り、むしろ大衆社会論で否定された中間集団の影響力が再評価されるようになったことは周知のとおりである。
「大衆社会論」の復活
しかし、1980年代に入ると、わが国において「大衆社会論」が新たな装いで「復活」してきたかにみえる。「新中間大衆論」、「少衆論」、「分象論」、「高度大衆消費社会論」など、「大衆」の名を部分的に冠した論稿や単行本が次々と現われ、「大衆社会」をめぐる議論が論壇を賑わすようになったからである。 これらの議論は、果して従来の大衆社会論と何らかの関連をもっているのだろうか。それとも、全く別箇の社会論なのだろうか。もし何らかのつながりをもっているとすれば、それはいかなる系譜の下に位置づけることができるのだろうか。
ここでは、新しく登場してきた「大衆社会」をめぐる諸説の中から、代表的なものとして、「新中間大衆論」と「消費文化論」とを取り上げて検討することにしたい。
2. 新中間大衆論
まず、社会の階層的非構造化という視点から大衆社会状況をとらえた「社会構造論」的アプローチの代表として、村上泰亮氏の「新中間大衆」論をとり上げることにしよう。村上氏は『新中間大衆の時代』(村上、一九八四)において、一九七〇年代以降の保守政党支持の復活がどのような要因によって引き起こされたのか、という問題意識にもとづいて、現代日本社会の階層構造を分析し、新中間大衆の登場という決定的な要因を指摘した。その論旨は以下のとおりである。
社会階層は多元的であり、その主要な次元としては、市場で交換可能な財に対する支配力の大小による「経済的階層化」、他人の意思決定に対する影響力の大小、国家的意思決定や組織内部における権限の大小、などによる「政治的階層化」、さまざまな行動様式の優劣評価、情報や知識の程度、価値観の優劣評価、学歴の差、などによる「文化的階層化」の三つが考えられる。社会システム全体の働きの中に、こられ諸次元での階層化を整合する働きが含まれているとき、階層は構造化されているという。戦前の資本主義は、上流・中流・下流の三つの階級から構成され、とくに中流階級はすべての次元にわたって下流階級とは明確に区別され、一次元的な階層尺度でとらえることができた。つまり階層的な構造化がある程度存在していたのである。ところが、現代の日本社会では階層の「非構造化」が進行しつつある。経済的次元では、所得・資産の格差縮小が進行し、文化的次元では、生活様式の均質化、高等教育の普及とマスメディアの発達による知識・教養の格差縮小が進み、手段的価値から即自的価値への転換に伴って、文化的活動における主導権が中流階級から一般大衆へ移行している。政治的次元では、行政的ないし準行政的なエリートの果たす役割が増大して階層化が要因が強まったとはいえ、普通選挙の確立によって、議会政治制度は平等化傾向を強めている。このように、各次元での階層的非構造化が進み、とくに中流階級と下流階級との間の境界が不明確になっている。そればかりでなく、SSM調査の分析結果(今田・原、一九七九)が示すように、異なる次元の間での階層的な非整合化が進んでおり、とくに中間的な階層において非構造化が著しくみられる。その結果として、階層的に構造化されない膨大な「新中間大衆」が歴史の舞台に登場することになった。
新中間大衆の出現は、階級意識を稀薄化させ、階級的イデオロギーにもとづく政治の衰退を招いた。その結果、六〇年代半ばから、自民・社会両党の支持率は低下し始め、「支持なし」層が増大することになった。また、「ゆたかさ」を享受している新中間大衆は、既得権益を守ることによって現在の生活水準を維持しようとする「保身性」をもっており、それが保守政権支持に結びついている。一方、即自的価値を持つ新中間大衆は、産業化やそれを支えてきた手段的合理性、さらにその担い手である行政エリートに対して潜在的不満を抱いており、その限りでの「批判性」を併せ持っている。六〇年代末から七〇年代初めにかけての「新左翼運動」の高揚、最近の「行政改革」に対する国民的支持などは、こうした新中間大衆の批判性のあらわれと考えられる。 以上が「新中間大衆」論の骨子である。村上氏は最近の論文「ゆらぎの中の大衆社会」において、以上の論考をさらに進め、大衆社会についての新たな概念規定を試みている。その論旨を要約すると以下のようになる。
社会を構成する人々の欲望や利害計算の総和は、無定形な「マッス」(mass, 質量)をかたちづくっており、社会がそのような欲望や利害を方向づけるための構造的仕切りを失うと、社会全体の流体化を生じ、大暴走(スタンピード)が起こる。
この場合の「構造的仕切り」というのは、人々の役割を規定する階級ないし階層という「外的構造」と、人々の欲望や利害を規制する中核的価値についての判断パターンとしての「内的構造」とから成っている。大衆社会とは、外的構造と内的構造のうち少なくとも一方が失われた社会をいう。コーンハウザーの提示した大衆社会に関する図式を外的構造化と内的構造化という概念によって再解釈すると、コーンハウザーのいうエリートの自律性(エリートへ近づきにくさ)の軸は、外的構造化の強弱の軸に相当し、非エリートの自律性(大衆の操縦されにくさ)の軸は、中核的価値が人々の判断構造の中にどれだけ内面化されているかの軸に相当すると考えることができる。そうすると、大衆社会とは、「文明の中核的価値を守る構造が内的、外的の両面で衰えている社会」ということになる。外的構造の弱化すなわち階層的非構造化は平等化の必然的帰結であり、これを逆転させることはできないから、大衆社会への退行を避けるためには、中核的価値の内在化を通して内的構造を強化する以外に方法はない。しかし、その中核的価値自体に現在大きな転換のきざしがみられ、場合によっては二一世紀の「X文明」への過渡的段階で大衆社会的状況が現れる可能性もある。
以上が村上氏の展開した「大衆社会論」の要旨である。この議論に対しては、その後さまざまな論評や批判が加えられてきた。ここではそれらを詳しく紹介している余裕はないが、その主なものを列挙するならば、①「中」意識は現実の階層(ないし階級)構造を反映したものではないという批判(岸本、一九 七八、小沢、一九八五、元島、一九八五)、②SSM調査の分析結果をもって階層的非構造化の根拠としていることへの批判(岸本、一九七八、杉山、一九八五)、③中核的価値の性格をめぐる批判(見田、一九八五)、などがあげられる。
村上氏の「新中間大衆」論の系譜をたどると、コーンハウザーからレーデラーを経て、トックヴィルにまでさか上ることができるが、伝統的な大衆社会論との間にはいくつかの基本的な点で断絶がみられる。ここで特に指摘しておきたいのは、レーデラーからS、ノイマン、F・ノイマンらを経てミルズ、松下へと受け継がれる「メディアによる大衆操作」という視点が村上氏の議論ではまったく欠落していることである。第二論文において、同氏はコーンハウザーの設定した二つの次元のうち、「大衆の操作されやすさ」の軸を「中核的価値の内面化」と読み換えているが、これは本来「価値意識」という異なる次元に位置づけられるべきもので置換したことに等しい。その結果、意図的かどうかは不明であるが、「メディアによる大衆操作」あるいはマスメディアの影響力という視点からの分析が抜け落ちることになり、大衆社会状況におけるもっとも重要な側面が十分に考察されずに終わっているのである。
3. 消費文化論
次に、大衆の消費行動にみられる現代的特性という視点から「大衆社会論」もしくは「脱・大衆社会論」を展開した議論のうち、山崎正和氏、藤岡和賀夫氏、博報堂生活総合研究所、小沢雅子氏の最近の著作を取り上げることにしたい。 山崎氏は『柔らかい個人主義の誕生』の中で、消費社会において新しいタイプの自我が生まれつつあるという認識の上に立って、「顔のみえる大衆社会」論を展開した(山崎、一九八四)。その論旨は次の通りである。 一九七〇年代に入ると、国家に対する人々の関心が稀薄化し、地域主義の流行などとも相まって、集団に対する個人の帰属意識はより個別的で、多元的なものになった。また、職場における労働時間の短縮、家庭における主婦の家事労働時間の短縮、高齢化の進展に伴って、現代人はますます多くの時間を「職場や家庭の外のより多元的な帰属関係の中で過ごし、さらには孤独な自分自身に向かい合って生きる」ようになった。
このような個人の個別化は、新しい個人主義の誕生という内面的な条件の変化によっても促進されている。すなわち、六〇年代には「目的志向と競争と硬直した条の個人主義」が優勢だったのが、七〇年代にはいると、「より柔軟な美的趣味と、開かれた自己表現の個人主義」が広がってきたのである。このような傾向は、消費行動の側面ではっきりとみられる。現代人は自己表現ないし自己探求を「消費」という行為を通じて実現している。つまり、現代人は自分の個性や嗜好に合った商品を選択しようとしており、また個人サービスにおいても自分自身をかけがえのない個性的な人格を持った存在として扱われることを要求する。そこでの消費とは、商品との対話を通じた一種の自己探求の行動としてとらえることができる。また、生産行為も実は満費的な性格をもっており、それは自己探求の過程を伴っている。いいかえれば、消費というのは「ものの消費と再生をその仮の目的としながら、じつは充実した時間の消耗こそを真の目的とする行動」のことである。柔らかい個人主義とは、ひたすら物質的欲求をできるだけ早く満足させようとする「原初的な自我」でも、将来のために現在の満足を先送りし目的実現のために効率性を追求しようとする「生産する自我」でもなく、消費する自我、つまり「目的実現の過程そのものを味わうことを目的とし、そのために満足をできるだけ引き延ばす」ことを意味している。消費する自我がこのような性格のものである以上、それは例えば食事やパーティーがそうであるように、消費の場において現実の他人を必要とし、その他人による賛同を求めるようになる。その結果、人々はより柔らかで小規模な単位からなる組織との間に多元的な帰属関係を結ぶようになる。 そこに成立する社会は、もはや匿名的で没人格的な個人の集まりである**「顔の見えない大衆社会」ではなく、開放的で柔らかい自我をもった個人からなる「顔の見える大来社会」である。
多様な論点をもつ山崎氏の大衆社会論を強いてまとめれば、およそ以上のようになろう。山崎氏の主張に対しても、やはり多くの批判が加えられている。例えば、①消費生活における自己表現的な価値を強調することは、業績主義的な価値観に支えられ、個人の自由な自己実現を原理とする現代産業社会の本質をとらえておらず、職業的活動ないし生産活動における過剰同調性や不平等なシステムの存在を無視したものだ、とする批判(広岡、一九八五)、③大衆社会状況の中で生じつつある対立や緊張関係を無視し、現状に対してあまりにも肯定的かつ楽観的な議論である。とする批判(橘川、一九八四、河村、一九八五)、などがある。 藤岡和賀夫氏の唱えた「小衆」論も、山崎氏と同じく、消費行動を通した自己表現に新しい時代の価値観をみる考え方である。『さよなら、大衆。』の中で展開された「少衆」論とは次のようなものである(藤岡、一九八四)。
一九六〇年代までの日本社会では、「大衆」が欲求不満をバネとして共同歩調をとって生活水準の向上に努力してきた。しかし、七〇年代に入ると、人々の基本的な欲求はだいたい充足され、「持つこと」に関しては飽和状態に達してしまった。そこで、今日の清費者が求めているのは、いかにして「自分らしさ」を表現するかということである。「自分らしさ」とは、実は「感性」における個性化なしい差異化をはかることに他ならない。いいかえれば、時代の価値観が「物のゆたかさ」の追求から「感性のゆたかさ」の追求へと転換しつつある、ということである。それに伴って、かつての「中流」という名の「大衆」は、感性という多様で個性的ニーズをもった無数の「少衆」に分解しつつある。つまり、社会はいまや「大衆化時代」から「少衆化時代」へと移行し始めているのである。 この新しい「少衆」は、昭和三〇年以降に生まれた若い世代を中核としている。彼らの価値基準は従来の「よい-悪い」という理性的な判断軸ではなく、「好きーきらい」「おもしろい」「かわいい」「気分に合っている」「かっこいい」「軽い」といった感性的ないし感覚的なものである。そして、彼らは小さな仲間同士のコミュニケーションや消費行動を通じて、表現欲求と感性欲求とを満たしているのである。 彼らは消費面だけではなく、生産の場においても今までとは違った行動パターンを示す。働くことが何より好きな昭和ひとけた生まれ中心の旧世代を「アリ」世代と呼ぶことにすれば、昭和三〇年以降生まれの「少衆」世代は、遊びがこのうえなく好きな「キリギリス」世代である。そして、両者の中間には、仕事も遊びも両方とも器用にこなす昭和二二、二三年生まれの「アリギリス」世代がいる。キリギリス世代は、会社への忠誠心や帰属意識が稀薄で、何でも自分中心にしかみることができない。仕事に対しても「遊び感覚」の基準で選別するから、「おもしろい」仕事だけがキリギリス世代のエネルギーを動員できる。したがって、新世代のニーズにこたえるには、いまや企業自身がゆたかな感性で自己表現することが求められており、また感性欲求を満たすようなハイテク化されたアート感覚にあふれた魅力あるオフィスづくりが求められている。
以上が藤岡氏の主張する「少衆」論の要旨である。藤岡氏の問題意識は、マーケティングの送り手としての立場から、従来の「大衆」概念ではもはやとらえきれない消費者や生活者の新しい価値観やニーズをとらえようとした点にある。博報堂生活総合研究所の「分衆」論も、基本的には同じような問題意識に立ったものである。その論旨はおよそ次のとおりである。
戦後の日本社会は、昭和三〇年代前半の「大衆胎動期」、昭和三〇年代後半から四〇年代前半までの「大安全盛期」、昭和四〇年代後半以降の「大衆崩壊・分衆胎動期」の三つの時期に分けることができる。「大衆」の時代はすでに終わりを告げ、現在は「分衆」の時代を迎えている。大衆の時代は画一性が支配していたが、分衆の時代は感性にもとづく差異化が重要なテーマになる。人々は画一的なモノを買い揃えるだけでは満足できず、感性に根ざす暮しのソフトウェアを求めるようになった。 集団形成の仕方をみても、世代をこえた「ライフスタイル」や「文化」の共有による分衆化が進み、「共通の関心や好み」を軸に展開されるゆるやかでオープンなネットワーク組織が時代の水面に浮上する。分衆時代の生活目標は人それぞれで多様化しており、いままでのように「人並み」をめざしていたものが、脱「人並み」あるいは「自分並み」志向が強まっている。同時に、「大衆」時代とは違って、人々はマスコミの操体を受けにくくなっており、情報の主導権は送り手ではなくむしろ第費者の側で舞るようになっている。
このような新しい価価編と行動様式を持った「分楽」のリーダーとなるのは、国道識では「中流」の幻想を持った人、つまり、貧乏ではないが、住宅ローンの返済や教育費支出の圧温で生活にゆとりの感じられない「ニュープア」選である。
以上のように、「分衆」は「今楽」論とほぼ間じような場旨を展関している。両者の違いといえば、後者の場合、A・トフラー流に「大衆化」時代との対比において「分象」時代をとらえていること、「分衆」の潜在的リーダを「中流」と観定していること、などである。
しかし、果たして「分楽」金のいう「ニューブア」園の満実態はどのようなものなのか。それは本に次の時代の愛リーダーとなりうるのだろうか。この点に関して、最造の酒費市場をめぐる期間を実駐的データにらして分析した小沢舞子氏の「酵」営(小沢、一九人、一九八豆&、一九八五D)も以下で簡単に難約しておこう。 過去約一〇年にわたって、個人酒費は刺予想されたほどの頼びをみせなかった。その理由として「指費和能」が一時有力観された。それは飲のような考え方である。「日本人の生活 水夢が上し、お質化した結果、潤費者の数実は充起されつくしてしまい、もはや買いたい商品がなくなってしまった。それが今日の消費不振の原因である」。しかし、実際に飽和したのは画一的な大衆生産財に対する消費欲求だけであり、他の消費欲求は未充足のままであり、しかも欲求の多様化と高度化が進んでいる。消費行動が実現するためには、①売り手側での品揃えが消費者の欲求を満たすこと、に加えて、②商品の価格が消費者の購買力の範囲内であること、が必要であることを考えるならば、満費欲求だけではなく、購買力の個人差にも注目すべきである。購買力の基礎にある所得格差、賃金格差は近年ほぼ一貫して拡大している。また純金融資産の格差も八〇年以降に入って縮小しているとはいえ、いぜんとして高い水準にある。 とくに、住宅ローンや教育費支出の負担に苦しめられているサラリーマンの購買力は著しく低下している。このように、所得・資産の格差が拡大している中で、消費行動を規定する要因として購買力の占める比重が著しく増大している。事実、全国消費実態調査のデータをもとに因子分析を行ってみると、「金融資産残高」や「財産収入」を高い因子負荷量としてもつ「金融資産」因子が、消費行動について九〇%というきわめて高い説明力を示している。さらに、この「金融資産」軸に関して、購買商品ごとの負荷量の値を比較してみると、金融資産残高の高い家計ほど、高級品・高価格商品の購買率が高くなる傾向がはっきりとみられる。 このように、消費欲求の多様化と購買力格差の拡大という「消費需要の二元的細分化」が進んだ結果、大量生産と大消費の相互循環がもはや十分に機能しなくなっていると考えられる。つまり、これまでの大衆消費時代にかわって、「階層消費」時代が到来したのである。 以上が、小沢氏の主張する「階層消費」論の要約である。 「少衆」論や「分来」論と同様に大衆消費時代の終焉と商品市場の細分化を強調しているが、消費行動にみられる階層性を指摘している点に新しさがある。 「少来」論や「分衆」論に代表されるいわゆる「消費文化論」や「脱・大衆社会論」に対しては、数多くの批判が加えられている。それらを列挙しておくと、①消費文化論は世代差にこだわりすぎている(少論・分菜論は要するに「若者文化論」にすぎない、その若者文化にも画一的な面が多い、逆に中年以上の世代の価値観も実際には多様である)、②消費文化論の賛美する「差異化」は中身のない記号レベルの「差異化ゲーム」にすぎない(小児病的である、伝統や思想を破壊する危険がある、一七〇種類ものデザインを揃えた「缶ビール戦争」などは常軌を逸している、機能や物質レベルでの差異化こそ重要であ る)、(以上、井尻、一九八五、西部、一九八五、広岡、一九八五、飯田、一九八五)◎商品以外の面では、現代の日本はきわめて物質的ないし画一的な大衆社会である(西部、一九八五、 藤竹、一九八五)、@少衆論や分衆論には「大衆」ないし「少 楽」「分」についての明確な概念規定が欠落している(竹、一九八五、石川、一九八五)、⑤きめの細かい実証的分析に欠けている(林、一九八五、石川、一九八五)、⑥「感性」や「感覚」を重視しすぎている(理性を軽視する議論は危険である) (井尻、一九八五、石川、一九八五)、「消費文化論」は、歴史性を背負った人間の複雑な営みの中での消費を論じていない、@消費文化論は六〇年代と七〇年代以降の対比しか行っておらず、それ以前の歴史に対する認識が落している(以上、 井尻、一九八五)、@少染論・分裂論の前提とする「飽和」 説は正しくない(消費者のニーズは決して充足されきってはいない)(小沢、一九八五)、などがある。 「文化論」の系譜をたどると、ボードリヤールからリースマンを経て、ヴェブレンにまでさか上ることができる。これらの古典的消費社会論と最近の一連の消費論とを比較すると、いくつかの共通点と相違点がみられる。共通点としては、いずれにおいても、消費による「差異化」が強調されている、という点をあげることができる。しかし、消費の機能についての解釈はかなり異なっている。ヴェブレン(Veblen,1899)は「街 示的」消費ないし関暇、つまりモノや時間の非生産的消費が、有閑階級の地位表示的機能を持つことを強調したが、山崎氏はこれを「消費する自我」の実現として個人のレベルで肯定的に捉えるのみであり、その社会的逆機能には言及していない。また、リースマン(Riesman et al., 1960)が「自分のパーソナリティに小さな差をつける。その差はほんのちょっとしたものでなければならない」と表現した他人志向的性格における「限界的特殊化」や、ボードリヤール(Baudrillard, 1970)が社会的ヒエラルヒーにおける地位と結びつけてとらえた消費の記号的 差異化作用は、分衆論や少論では、大衆の均質性や階級的イデオロギーとは無縁の個性的な自己表現としてのみとらえられている。つまり、そこでは消費のポジティヴな面だけが強調され、ネガティヴな側面は捨象されているのである。
4. 新「大衆社会論」の提起した問題
トックヴィルに始まりマンハイム、レーデラーらを経てミルズに至る古典的大衆社会論の展開の中で提示された大衆社会状況のメルクマールを、ここでもう一度整理し直してみると、①民主化ないし平等化の進展、◎産業化による大量生産、大量消費の実現、③マスメディアの発達による大量情報、大衆娯楽の提供、@生活水準の全般的上昇、⑤ホワイト・カラーを中心とする新中間層の増大、⑥組織における官僚化の進展、◎中間集団の弱体化ないし解体、という七つの基本的条件をあげることができる。日本社会が高度経済成長の中で⑦以外の条件をすべて満たしてきたことは明らかであろう。前節において紹介した最近の「大衆社会論」においても、こうした条件の存在は決して否定されているわけではない。むしろ、これらの基本的条件が満たされた上で、高度経済成長期以降のわが国で従来の大衆社会状況にはみられない新たな変化が生じつつあり、それが大紫社会状況における人々の意識や行動にも重大な影響を及ぼしている、というのが最近の諸説にみられる論点のように思われる。それでは、何がどう変化したというのだろうか。 従来の大衆社会論では、上述の諸条件の必然的帰結として、 ①大衆の原子化、②人間疎外と無力感、不安感の蔓延、③政治的無関心の増大、④少数のエリートによる大衆操作、⑤生活様式や消費行動の画一化ないし規格化、⑥組織への過剰同調性と他人指向的性格などの病理的社会現象が指摘されていたのであり、それが大衆社会論に「時代の診断」ないし批判理論的な性格を与えていたのである(McQuail, 1983)。ところが、最近の「大衆社会論」においては、これとは正反対の現象の方がむしろ強調されているようにみえる。すなわち、①大来はもはや砂粒のように匿名的な原子の集まりではなく、顔の見える集団の中で自己探求、自己表現を追求する「柔らかい個人主義」をもった自我として成熟しつつある(山崎、一九八四)、②現代人は、消費生活においても、職場においても、感性における個性化ないし差異化をはかることによって、自分らしさを表現しており、疎外や無気力・不安とは無縁である(藤岡、一九八 四)、③新中間大衆は保身性と批判性を併せ持っており、それが最近における保守政党への支持、六〇年代末から七〇年代初めにかけての新左翼運動の高揚、行政改革への国民的支持となって現れている(村上、一九八四)、現代の労働者大衆は決して、政治的に無関心ではない(元島、一九八五)③大衆はメディアの操作を受けにくくなっている(博報堂、一九八四)、テレビの影響力は低下している(藤岡、一九八四)、⑤消費欲求と品揃えの多様化によって、消費の個性化、多様化が進んでいる(費文化論全体)、消費の階層分化が進んでいる(小沢、一九八五)、⑥組織への忠誠心をあまりもたず、余暇の領域での生きがいを重視する新しい世代が育っている(藤岡、一九八 四)、他人指向よりも「自分並み」の価値基準を持つ人が増えている(博報堂、一九八四)、といった主張が展開されているのである。ひとことでいうならば、大衆社会状況の中での人間像が大きく変わろうとしている、とこれらの論者は主張しているように思われる。 以上の諸説を整理してみると、「新しい変化」とその「帰結」は図1のようにまとめることができるだろう。 すなわち、①社会構造の面では階層の非構造化に伴い「新中間大衆」が形成され、②社会意識の面では手段的価値から即自的価値へ、理性的基準から感性的基準へ、仕事志向から遊び志向へ、社会志向から私生活重視へと価値観の転換が進んでおり、③メディアの影響力という面ではエリートによる大衆操作の力は衰えている、という構造変化の認識がみられる!その結果として、①保守政党への支持と@消費文化の多様化ないし個性化という現象が生じている、というのが、新しい「大衆社会論」の主張である。 そこで問題は、このような「構造変化」が現実にどの程度生しているのか、またその変化が、問題となっている保守政権支持や「分衆」「少菜」「階層」的消費行動の直接的要因となっているのか、ということである。 まず、階層的非構造化の点についてみると、村上氏の説に対しては、これまでに実証的データに基づく数多くの批判が加えられている上に、非構造化を支持する論拠それ自体も次第に崩れつつある。村上氏が非構造化の証拠として用いているSSM調査の社会的地位スケールは現実の階層構造を正確に反映したものとはいえない(岸本、一九七九、元島、一九八五)、学歴の格差をベースとする階層構造は現在でもなお厳然として存在し ている(元島、一九八五、秋葉、一九八五、杉山、一九八五)、などの批判は実証的知見に基づいたものであり、説得力がある。 一方、村上氏が「新中間大衆」の主要構成要素と考えている「中の中」意識をもった人々の占める比率は、最近になってやや減少傾向をみせ、中流階級の中での両極分解現象=階層構造化の傾向がみられる。小沢(一九八四、一九八五)によれば、七〇年以降、所得格差は芸大し、資産格差も依然として大きいという。国や③という言葉が流行した背景には、中流階級内部における階層分化の進行という現実があるものと考えられる。 人々の持つ「中」意識それ自体、高度成長の結果、相対的な生活水準の上昇から生じた認知的ラグによる錯覚、つまり「虚偽意識」である場合が少なくないと思われる。 このように、「階層的非構造化」は、村上氏の考えるほど急数には選行していない、というのが現実の姿であろう。問題はむしろ、国民の大多数が「新中間大衆」の一員であるかのような「幻想」を抱いているのは何故なのか、ということであろう。 実証的データには乏しいが、そのような意識を醸成する上で重要な役割を果たしているものはマスメディアのさまざまなメッセージである可能性が強い、という点だけをここでは指摘しておきたい。 次に、価値観の変化についてはどうだろうか。村上氏の引用しているNHKの「日本人の意識」調査や文部省統計数理研究所の「日本人の国民性」調査など、多くの調査データは、高度経済成長期以降のわが国において、「まじめ志向から遊び志向へ」「社会よりも私生活の重視」という変化が起きていることを示している。この変化はとくに若者世代において顕著である。 しかし、こうした価値観の変化がストレートに保守政党への支持や個性的・差異表示的な消費行動を生む原因となっているとは考えにくい。 メディアの影響力については、「少栗論」や「分衆論」において、テレビのパワーダウンが主張されている。事実、若年層を中心として、視聴率や視聴時間の頭打ちないし減少傾向が最近はっきりとみられるし、「ながら視聴」に象徴されるように非没入的視聴の仕方をする人が増えていることが、調査によっても裏づけられている。にもかかわらず、平均的な国民は今もなお一日のうち四時間以上をテレビ、ラジオ、新聞、雑誌などのマスメディアへの接触に費やしており、少なくとも認知的な面ではマスメディアから大きな影響を受けていることも各種の研究によって明らかにされている。また、三らの調査によれば、世論形成に対する影響力という点でも、マスメディアは他のいかなる機関よりも強大なパワーをもつと評価されている(三宅他、一九八五、蒲島、一九八六)。最近とみに強まっているマスメディアに対する国民の批判も、マスメディアの行使する強大な影鬱力に対する不安の表れと考えることができる。
このように、マスメディアの影響力が衰えているという明確な証拠は今のところ得られてはいないのである。
以上のように、最近次々と現れた新しい「大衆社会論」においては、大衆社会状況における構造変動の大きさが過大に評価されており、またそれによって引き起こされる人々の行動や生活様式における変化についても、若者世代を中心とする消費ないし余暇の領域を強調しすぎているように思われる。
にもかかわらず、これらの議論が現代日本の社会構造、社会意識における大きな変化の兆しを先行的に捉えたものであることは否定できない。何よりも、そこには、政治意識やマーケティングの領域において従来の伝統的な大衆社会論では十分にとらえ切れない現象が現れつつあり、これらの現象の原因を構造的に解明しようとする明確な問題意識がみられるのである。
これに関連した問題意識は、実はマスメディアの影響力に重大な疑問が抱かれ始めている今日、マスコミ研究者によっても当然提起されるべきものだったのではないだろうか。研究の歴史がいまだ浅いという事情があるにせよ、われわれは大衆に及ぽすマスメディアの影響力、マスメディアによる大衆操作の実態、マスメディアがパワーエリートに対して及ぼす影響力についてどの程度正確に把握し得ているだろうか、という点には疑問を抱かざるを得ない。また、情報誌や中間的メディアの発達、ニューメディアの登場など情報環境が大きく変貌しようとしている現在、人々の情報ニーズや情報行動はどの程度多様化と専門分化の方向に進みつつあるのだろうか。こういった問題を解明するための理論的枠組として、従来の大衆社会論はきわめて不十分なものであるといわざるを得ない。 成熟した大衆社会状況の中で、いかなる構造的変動が進行しており、それがマスメディアの影響力や人々の情報行動にどのようなインパクトを及ぼしつつあるかを、実証的データにもとづいて検討することは、今後われわれマスコミ研究者に課せられた重要な課題であろう。今日における「大衆社会論」の新たな展開は、批判すべき点を数多く含んでいるとはいえ、こうした問題を解明するための貴重な手がかりをわれわれに与えているように思われる。 (本文中で引用した文献は、本号所収の「大社会論」関連文献目録の中に記載されているので、そちらを参照されたい)
注:
(1) 一九六〇年代以前の大衆社会論に関するより詳しい解説としては、西村(一九五八)、竹内 (一九七二)、Giner(1976) などがある。
(2) 本稿では取り上げなかったが、西部氏によって展開された「大衆社会論」は、オルテガの学説を現代日本の社会状況に適用したものである(西部、一九八三a)。 (3) この大衆社会論争が行われた時期における代表的な論文としては、松下(一九五六、一九五七a、一九五七b)、日高(一九五七b)、高橋他(一九五七)、柴田(一九五七 藤田(一九五七)、北川(一九五六)、新明(一九五七)、田田沼(一九五七)、清水(一九五七)などがある。 (4) 岡田(一九八三)はこれを、「大衆社会論パラダイム」から「行動主義パラダイム」への転換としてとらえた。またフリードソン(Freidson,1953)は、マスメディアの 受け手の反応を研究するのに、匿名的、散在的、非組織的な性格づけを与えられた「大衆」の懸念は有効ではない、と批判している。 (5) 蒲島郁夫氏は、政治システムを説明するために「これまで提唱されてきたモデルは、情報化社会の出現に伴ってメディアの影響力を無視した、不完全なモデルではなかろうか」と批判した上で、大規模なエリート調査の結果をもとに、マスメディアの影響力を中心に据えた多元主義的な政治システムモデルを提案している(蒲島郁夫、マスメディアと政治ーもう一つの多元主義、中央公論、一九八六 年二月号、一一〇|一三〇頁)。 (6)詳しくは本号の竹下論文を参照されたい。 (7) NHKが一九八五年八月に実施した全国世論調査によれば、マスコミ報道の社会的影響力について、「犯罪やスキャンダルの報道に気をとられて、より重要な問題に対する関心がうすくなる」という意見が四二・八%、「人々の意見や考え方が一定の方向に動かされていく」という不安を感じる人が36.5%にも上っている。
「大衆社会論」関連文献目録
ここに収録したのは、一九八六年一月までに雑誌、単行本、報告書等の形で発表された「大衆社会論」関連の文献(主として日本語および英語)である。戦前のものについては代表的なものに限定したが、最近の論文については、出来るかぎり網羅的に収録したつもりである。それでもなお、重要文献で気落しているものが少なからずあると思う。諸者読兄のご教示を賜われば幸いである。
ー、大衆社会論一般
芥川集一(一九五七)マルクス主義と社会学(1)ー大衆社会の問題によせて、理想、十二月号、六十七ー七十八頁
Arendt, H. (1962) The Origins of Totalitalitarianism. Cleveland: World Publishing Co. 大久保和郎他訳(一九七四)全体主義の起源一~三、みすず書房。 Bell, D. (1960) The End of Ideology, New York: Collier. 岡田直之訳(一九六九)イデオロギーの終焉、東京創元社。
Bramson, L. (1970) The Politiaal Context of Sociology. Princeton: Princeton University Press.
De Grazia, S. (1984) The Political Community: a Study of Anomie. 佐藤智雄・池田昭訳、(一九六六)疎外と連帯、勁草書房。
Eliot, T.S. (1961) *Notes toward the Definition of Culture.*London: Faber & Faber.
藤田省三 (一九五七)現代革命思想における若干の問題し ハンガリー問題をめぐる政治学徒と編集者の対話、中央公論、 二月号、二一三ー二二八頁。Fromm, E. (1942) The Escape from Freedom. London: Routledge & Kegan Paul. 日高六郎訳(一九五一)自由からの逃走、東京創元社。
Giner, K. (1976) Mass Society. London: Martin Robertson.
粕谷一希(一九八四)大衆社会論の日本的展開、現代の理論、 三月号、五ー二十三頁。
日高六郎(一九五七a)大衆社会におけるマス・コミュニケーションの問題、東京大学新聞研究所紀要、第六号、一一七 ー一二七頁。
日高六郎(一九五七b)「大衆社会」研究の方向について、講座社会学第七巻・大衆社会、東京大学出版会、二三七ー二 四六頁。
日高六郎(一九六〇)現代イデオロギー、勁草書房。
細谷昂・元島邦夫(一九八二)戦後日本の社会状況ー日本 型「大衆社会」の安定装置、講座・今日の日本資本主義四、 大月善店、三〇七ー三三〇頁。
細谷島(一九八五)大衆社会論と日本型大衆社会、社会学研 究、四十八号、七ー二十五頁。
井上 俊(1九七四)死にがいの喪失、二三四ー二六二頁、筑 摩書房。
伊藤勇(一九八五)日本型大衆社会と「自我」、社会学研究、 四十八号、九十三ー一〇九頁。
加茂利男(一九七三)大衆社会論争ー今日の時点での一考察、現代と思想、九月号、六十一ー八十二頁。
河村 望(一九八五)新「大衆社会」論がふりまく幻想ー村 上泰亮、山崎正和氏の批判的検討、前衛、三月号、一六三ー 一八〇頁。
北川隆吉(一九五六)小集団をめぐる問題、思想、十一月号、 七十七一九十四頁。
北川隆吉(一九五七)大衆社会と小集団の問題、理想、十二 月号、四十二ー五十頁。
橋川忠俊(一九八四)大衆社会論の構図、経済評論、一月号、 六十八ー七十九頁。
小林一穂(一九八五)農村における大衆社会化と農民意識、社会学研究、四十八号、四十七ー六十八頁。
Kornhauser, W. (1959) The Politics of Mass Society. Glencoe: Free Press. 辻村明訳(一九六一)大衆社会の政治、東京創元社。
Le Bon, G. (1895) Psychologie des foules. 桜井成夫訳(1 九四七)群集心理、岡倉書房。
Lederer, E. (1940) State of the Masses: The Threat of the Classless Society. New York:Norton. 青井和夫・岩井完之 訳(一九六一)大衆の国家、東京創元社。
Lippmann, W. (1925) The Phantom Public.
Mannheim,K. (1935) Mensch und Gesellschaft im Zeitalter des Umbaus. Leiden:Sitboff.杉之原寿一訳(一九七六) 変革期における人間と社会、マンハイム全集五、潮出版社。
Mannheim, K. (1943) Diagnosis of Our Times. London: Rovtledge & Kegan Paul. 長谷川善計訳(一九七六)現代の診断、マンハイム全集五、潮出版社。 Mannheim, K. (1965) Freedom, Power, and Democratic Planning. London: Routledge & Kegan Paul. 田野崎昭夫 訳(一九七六)自由・権力・民主的計画、マンハイム全集 六、潮出版社。
Marcuse, H. (1964) One Dimensional Man. London: Rou- tledge & Kegan.Paul 生松・三沢訳、一次元的人間、河 出書房新社°
松下圭一(一九五六)・大衆国家の成立とその問題性、思想、 十一月号、三十一ー五十二頁。 松下 圭一(一九五七a)史的唯物論と大衆社会、思想、五月 号。
松下圭一 (一九五七b)日本における大来社会論の意義1柴田氏その他の批判に答える、中央公論、八月号、八十ー九十 三頁。
松下 圭一(一九六〇a)大衆社会論の今日的位置、思想、十 月号、一ー十五頁。 Mill, John S. (1859) On Liberty・ 塩尻公明・木村健康訳 (一九七一)自由論、岩波文庫。 Mills, C. W. (1956) The Power Elite. New York: Oxford®University Press. 鵜飼信成・綿貫譲治訳(一九六九)パワ ー・エリート(上・下)、東京大学出版会。
見田宗介(一九八五)<大衆社会Vのゆくえ、論壇時評・上、四月二十五日、朝日新聞夕刊七面。
村上泰亮(一九八五)ゆらぎの中の大衆社会、中央公論、五月号、五十二ー六十五頁。
永井 道雄(一九五七)新しい集団の形成、講座社会学第七巻 ・大衆社会、東京大学出版会、一四六ー一六四頁。
中野収(一九八一)大衆社会論の錯誤、経済評論、一月号、 三十九—五十一頁。
Neumann, F. (1944) Behemoth: The Structure and Practice of National Socialism 1933-1944. London: Oxford Univer- sity Press. 岡本友孝・小野英祐・加藤栄一訳(一九六三)ビヒモスーナチズムの構造と実際、みすず書房。
Neumann, S. (1942) Permanent Revolution: Totalitarianism in the Age of International Civil War. New York: Preger. 岩永健吉郎・岡義達・高木誠訳(一九六〇)大衆国家と独 裁、みすず普房。
西部(一九八三a)大衆への反逆、文芸春秋社。
西部 (一九八三b)経済倫理学序説、中央公論社。 西部 (一九八四a)生まじめな戯れ、筑摩書房。
西部(一九八四b)論士歴問!大衆社会をこえていく網 渡り、プレジデント社。
西村勝彦(一九五八)大衆社会論、誠信書房。
岡田直之(一九八三)マス・コミュニケーション研究における三つの知的パラダイム、コミュニケーション紀要、一、成城大学大学院文学研究科。 大橋幸(一九五七)大衆社会における指導体制、講座社会学第七巻・大衆社会、東京大学出版会、一ー三ー一四五頁。
Ortega y Gasset, J. (1930) Le rebelion de las masas. WK$4 一博訳(一九七五)大衆の反道、白水社。
Rosenberg, B., Gerver, I., Howton, F. (1964) Mass Society in Crisis. New York: Macmillan.
作田啓一(一九六六)市民社会と大衆社会、思想、九月号、 三十二ー四十六頁。
佐藤健二(一九八五)社会運動研究における「大衆運動」そ デル再検討の射程、思想、十一月号、七八ー一〇一頁。
佐藤智雄(一九七二)現代社会の社会心理的状況、社会学環 春十六、社会心理学、一〇〇一一三一頁、学文社。
柴田進午(一九五七)「大衆社会」理論への疑問|マルクス主義学徒の立場から、 Shils, E. (1960) "Mase Society and Its Culture", Daedaluo, 89, pр.288-314. Shile, E. (1970) "The Theory of Mase Society", Diogenes, 39.
清水幾太郎(一九五一)社会心理学、岩波書店。
清水幾太郎(一九五七)機械文明、現代思想旧 機械時代、三ー二十六頁、岩波書店。
清水幾太郎(一九六〇)大衆社会論の勝利|安保改定阻止闘争の中で、思想、十月号、二十六一四十三頁。
新明正道(一九五七)大衆社会理論の構造ーその支配的傾 向、理想、十二月号、一ー十頁。
庄司 興吉(一九七〇)「大衆社会」論から「知識社会」論 へ、思想、五月号、九十九ー一一五頁。
庄司興吉(一九七七)現代化と現代社会の理論、東京大学出 版会。
Spengler, O. (1924) Der Untergang des Abendlandes. Munich : Bech.
鈴木幸寿(一九五七)大衆化と大衆社会、講座社会学第七巻 ・大衆社会、東京大学出版会、一ー二十六頁。
高橋徹・城戸浩太郎・綿貫譲治 (一九五七)集団と組織の機 械化、現代思想 皿、八十七ーー七二頁、岩波書店。
高橋徹(一九五七)大衆心理の操作、講座社会学第七巻・大衆社会、東京大学出版会、五十一ー七十三頁。
高根正昭(一九八五)「大衆社会論争」と組織1社会科学 者への提案、思想、五月号、一〇四ー一一五頁。
竹内郁郎(一九七二)大衆社会の社会心理、岡部慶三他編、 社会心理学、二〇六ー二四八頁。
Tarde,G,,(1901), L'Opinion et la Foule.稲葉三千男訳(1 95九六四)、世論と群集、未来社。
Tocqueville, Alexis de (1835, 1840), De Democratie en Amerique. 井伊玄太郎訳(一九七二)、アメリカの民主政治(第一巻、第二巻)、講談社文庫・岩永健吉郎・松本礼二訳(一九七二)、アメリカにおけるデモクラシー(第一巻序、第三巻抜粋)研究社。岩永健吉郎訳(一九七〇)、アメリカにおけるデモクラシーについて(第二巻序、六ー九章、結び)、世界の名著三十三、中央公論社。
辻村明(一九六七)大衆社会と社会主義社会、東京大学出版 会。
辻村明(一九七二)大衆社会論、社会学講座十三、現代社会 論三十一—五十六頁、東京大学出版会。
辻村明(一九八四)大衆現象を解く、講談社現代新書。
上田耕一郎(一九六〇)大来社会論と危機の問題、思想、十月 号、十六ー二十五頁。
Wallas, G. (1914) The Great Society: a Psychological Analysis, 綿貫 譲治(一九五七a)大来社会における社会心理の構造、講座社会学第七巻・大衆社会、東京大学出版会、二十七ー五十頁。
綿貫譲治(一九五七b)大染社会における集団構造、講座社 会学第七巻・大衆社会、東京大学出版会、九十五ー一一二。
山崎正和・西部(一九八三)高度大衆社会と知識人の姿勢、 voice十一月号、一〇二ーーー九真。
矢沢修次郎(一九八五)大衆社会論を越えて1知識人と大衆の弁証法、季刊・思想と現代、第二号、十八ー三十二頁。 二、中流階級(新中間層)をめぐって
秋葉節夫(一九八五)階級構成の変化と日本型「大衆社会」、社会学研究、四十八号、六十九ー九十二頁。
有吉広介・浜口晴彦編(一九八二)日本の新中間層、早稲田大学出版部。
浅沼和典(一九五七)新中間階級と大衆、理想、十二月号、 五十九ー六十六頁。
林知己夫他(一九六四)日本のホワイトカラー、ダイヤモンド 社。 今田高俊・原純輔(一九七九)社会的地位の一貫性と非一貫 性、富永健一編、日本の階層構造、一六ーーー九七百、東京大学出版会。
稲葉三千男(一九七二)階級社会論、社会学講座十三、東京大 学出版会、十一ー三十頁。
石川晃弘他(一九八二)みせかけの中流階級、有斐閣。
石崎 唯雄(一九八三)日本の所得と富の分配、東洋経済新報 社。
経済企画庁(一九八五)国民生活:白善(昭和六十年版)、第I 章中流意識の周辺、大蔵省印刷局。
岸本重陳(一九七八)「中流」の幻想、講談社。
北川隆吉・貝沼海(一九八五)日本のエリート、大月書店。
Mills, C.W. (1951), White Collar: The American Middle Class. New York : Oxford University Press. 杉政孝訳(一九五七)ホワイト・カラー、東京創元社。 元島邦夫(一九八五)企業内人生と日本の大衆、社会学研究、四十八号、二十七ー四十六頁。
村上泰亮他(一九七九)文明としてのイエ社会、中央公論社。
村上泰亮(一九八四)新中間大家の時代(とくに第四章、第五章)、中央公論社。
NHK世論調査所(一九七九)日本人の職業観、日本放送出版協会。
千石保(一九八五)ザ・サラリーマン日米比較、日本経済新 聞社。 庄司興吉(一九八一)現代社会の階級構造ー二つの理論の総合のために、経済評論。一月号、二十四ー三十八頁。
杉山 光信(一九八五)文化の政治装置・ノート、栗原彬編、 文化の中の政治、叢書・社会と社会学二、三ー二ー三三〇頁、 新評論。
多田正仁(一九八五)番/③症候群を撃つー平等主義の逆 説、宣伝会議、三月号、十六ー二十一頁。 高橋王子郎(一九八五)「中流」はどこへ?!すすむ階層二極化のなかで…・・・・・、宣伝会議、二月号、二十八ー三十三百。 高山之(一九八〇)不平等の経済分析、東洋経済新報社。
田沼肇(一九五七)日本における「中間層」問題、中央公論、十二月号、一九五一二〇七頁。 富永健一(一九六五)社会変動の理論=経済社会学的研究、岩波書店。 富永健一編(一九七九)日本の階層構造、東京大学出版会。
土屋 清他(一九六二)ホワイトカラーの意識構造、日本社会構造調査会。
Vogel, E., (1963) Japan's New Middle Class. University of California Press. 佐々木徹郎訳編(一九六八)日本の新 中間階級、誠信書房。
Whyte, W., (1956) The Organization Man.. New York : Simon and Schuster.岡部慶三他訳(一九五九)組織のなかの人間(上・下)、東京創元社。 三、消費社会(消費文化)をめぐって
安部雍子(一九八五)情報環境別=生活カルチャー別ー階層消費社会、宣伝会議、三月号、ニナニー二十五頁。
アクロス編集室(一九八五)いま、超大衆の時代、PARCO 出版。
飽戸弘(一九八五)消費文化論ー新しいライフスタイルからの発想、中央経済社。
Baudrillard, J. (1970) La Societe de Consommation. 4* 仁司・塚原史訳(一九七九)消費社会の神話と構造、紀伊国屋書店。
電通マーケティング戦略研究会(一九八五)感性消費、理性消費、日本経済新聞社。
藤岡和賀夫(一九八四)さよなら、大衆ー感性時代をどう読むか、PHP研究所。
藤岡和賀夫・小沢和一・猪口邦子(一九八五)ヒット商品で社会心理を読むー中流意識の成熟が「自分表現」に必要な商 品を生んだ、voice、八月号、一〇四ー一一九。
藤岡和賀夫(一九八六)ふたたび「さよなら、大衆。』「少 紫化」批判に応える、Voice、一月号、二〇六ー二二九 頁。
福田優二(一九八五)「新消費階級」の成立とニューマーケット、宣伝会議、二月号、三十四ー三十九頁。
Galbraith, K., (1958) The Affluent Society. Boston: Houghton Miffin. 鈴木哲太郎訳(一九七八)ゆたかな社会、 岩波曹店。
博報堂生活総合研究所(一九八五)「分」の誕生、日本経済新聞社。
林知己夫 (一九八五)データにもとづく実証的研究こそ本道、 広告月報、十月号、十四ー十五頁。
広岡守穂(一九八五a)「柔らかい個人主義」は可能かし現代における自己実現と自己表現、世界、七月号、一一八ー 一三〇頁。
広岡守穂(一九八五b)いま「分衆」の時代?i三つの資本主義像をめぐって、世界、十二月号、八十六ー九十八頁。
飯田経夫(一九八五)消費文化論、中庸のすすめー「差異化」推進派と批判派へ、私の自己批判的感想、Voice、 十二月号、一〇二ー一一〇頁。
井尻千男(一九八五)消費文化論批判序説ー饒舌だが「他 者との対話」をいた自閉症的症候群、Voice、八月号、 八十六ー一〇三頁。
石川弘義(一九八五)望まれる理論的なフレームワークの構 築し今、消費者論再考のとき、広告月報、十月号、十五ー 十七頁。
西部(一九八五)差異化という魔語の正体ー商品差異化 に新文明の燭光をみる言説の怠惰を問う、Voice、八月 号、一二〇一一二九百。
小沢雅子(一九八四)幕開ける「階層消費時代」ー「中流 幻想」の崩壊と大衆消費時代の終焉、調査月報、二二二号、日本長期信用銀行。 小沢雅子(一九八五a)「階層消費」の時代ー「格差の時代」の消費、経済評論、一月号、三十二ー四十五頁。
小沢 雅子(一九八五b)新「階層消費」の時代、日本経済新 聞社。
小沢雅子・倉田正昭・竹永茂生・福田純一(一九八五) 見えて きた!!「階染化」社会・この先いったいどうなるの…宣 伝会議、二月号、十六ー二十六頁。 98
Riesman, D., Denny, R., Glazer, N., (1960) The Lonely Crowd. New Haven : Yale University Press. 加藤秀俊 訳(一九六四)孤独な群衆、みすず書房。Veblen, T.B., (1899) The Theory of Leisure Class: An Economic Study in the Evolution of Institutions. New York.小原敬士訳(一九六一)有閑階級の理論、岩波文庫。
渡部修(一九八五)最新、米国ヒット商品事情で占う「階来化社会」のヒット商品考、宣伝会議、三月号、二十六ー三十 三頁。
山崎正和(一九八四)柔らかい個人主義の誕生ージ費社会 の美学、中央公論社。
山崎正和・西部適(一九八五)「差異性」をどう評価するか、 中央公論、一月号、一五四ー一六三頁。 四、大衆文化論
Bell, D., (1976) The Cultural Contradictions of Capitalism. London: Heinemann.平恒次訳(一九七三)今日の資本主義文化、ダイヤモンド社。林雄次郎訳(一九七六)資本主義の文化的矛盾、講談社学術文庫。
江藤 文夫(一九七三)大衆文化の創造、講座・コミュニケーション第四巻、研究社。
藤竹暁(一九六三)大衆文化、今日の社会心理学五、文化と 行動、二二七ー四〇三頁、培風館。
Gurevitch, M.T., B.J. Curran and J. Woollacott, (1982) Culture, Society, and the Media. London, Methuen.
平井正他(一九八三)都市大衆文化の成立ー現代文化の原 型一九二〇年代、有斐閣。 平野秀秋・中野収(一九七五)コピー体験の文化、時事通信 社° 稲葉三千男(一九五七)文化の大衆化、講座社会学第七巻・大 衆社会、東京大学出版会、一六五ー一八〇頁。
Jacobs, N. (Ed.), (1959) Culture for the Millions? Prin- ceton : D. Van Nostrand. NHK放送学研究室訳(一九六 二)千万人の文化、NHK。 ジュリスト増刊号(一九八〇)日本の大衆文化、有斐閣。
加藤 秀俊(一九五七)中間文化論、中央公論、三月号、二五 二ー二六一頁。
加藤 秀俊(一九八〇)大衆文化論、加蕨秀俊著作集四、中央公論社。
栗本慎一郎(一九八四)大衆文化論、白夜書房。
松下圭一(一九六〇D)大衆娯楽と今日の思想状況、思想、 六月号、十九ー五十頁。
丸山圭三郎(一九八四)文化のフェティシズム、動草書房。
McQuail, D. (Ed.), (1972) Sociology of Mass Communica-tion. Penguin Books.時野谷浩抄訳(一九八二)マス・メ ディアの受け手分析、誠信書房。
McQuail, D., (1983) Mass Communication Theory. London:Sage. 内郁郎他訳(一九八五)マス・コミュニケーションの理論、新曜社。
Morin, E.,(1962) L'Esprit du Temps 1. 宇波彰訳(一九七 九)時代精神I、法政大学出版局。
仲村祥一・中野収編(一九八五)大衆の文化、有斐閣。
Rosenberg, B., and White, D., (1957). Mass Culture: The Popular Arts in America. New York: Free Press. HEZE 訳(一九六三)マス・カルチャー、マス・レジャー叢書三、紀伊国屋書店。
佐々木斐夫(一九五七)新しい文化の創造、講座社会学第七巻 ・大衆社会、東京大学出版会、二〇八ー二三五頁。
佐藤智雄(一九五七a)大衆文化とマス・コミュニケーション、講座社会学第七巻・大衆社会、東京大学出版会、一八一 ー二〇七頁。
佐藤智雄(一九五七b)「大衆文化の理論」覚え書、理想、 十二月号、三十四—四十一頁。
佐藤智雄他(一九八四)大衆文化とマス・メディア、テレビ大学講座・マス・コミュニケーション論日、放送教育開発センター。
Swingewood, A., (1977) The Myth of Mass Culture. London:Macmillan.稲増龍夫訳(一九八二)大衆文化の神話、東京創元社。
多田道太郎(一九六二)複製芸術論、勁草書房。
鶴見俊輔(一九六七)限界芸術論、勁草書房。
鶴見俊輔(一九六九)大衆の時代、現代人の思想七、平凡社。
鶴見俊輔(一九八三)大衆文化の戦後史、岩波書店。 辻村 明(一九八一)戦後日本の大衆心理、東京大学出版会。
Wilensky, H., (1964) "Mass Society and Mass Culture : Interdependence or Independence", ", American Sociological Review, 29, pp. 173-197. 五、大衆民主主義(マスデモクラシー)論
Carr, E.H.,(1951) The New Society. 清水幾太郎訳(一九五三)新しい社会、岩波書書店。
飯坂良明他(一九七二)現代の政治学、学陽書房。
京極純一(一九五六)リーダーシップと象徴過程(その1) 1リーダーシップ・グループ内における諸相、思想、十一 月号、一—二十九頁。
京極 純一(一九五八)政治意識の変容と分化、岡義武編、現 代日本の政治過程、岩波書店、四四二ー五〇八頁。 松下圭一(一九五七c)現代政治における自由の条件、理想、 十二月号、 十一—三十三頁。
松下 圭一(一九五七d)マルクス主義理論の二十世紀的転換 1大来ナショナリズムと政治の論理、中央公論、三月号、 一四二ー一五七頁。
三宅一郎・綿貫護治他(一九八五)平等をめぐるエリートと対 抗ェリート、創文社。
三宅一郎他(一九八五)日本政治の座標、有斐関選書。
田口富久治(一九五六)「大社会」の形成と政治理論、思想、十一月号、五十三ー七十六頁。
綿貫譲治(一九五七C)政党と大衆の政治意識、中央公論、 六月号、九十六ー一〇五頁。 六、「大紫」の概念をめぐって
河原宏(一九五七)大衆社会と全体主義的独裁、理想、十二 月号、五十一—五十八頁。
阿閑古(一九五七)大衆化と大衆的人間、理想、十二月号、 十一 二十買。
Blumer, H., (1946) "Collective Behavior", In A.M. Lee (Ed.), Principle of Sociology, New York: Barnes & Noble.
Brown, R.W. (1954) "Mass Phenomena" In G. Lindzey (Ed.), Handbook of Social Psychology, vol. II. **##
Freidson, E., (1953) "Communicaton research and the concept of mass." In W. Schuramm and D.F. Roberts (Eds.), The Process and effects of mass communication. Unive-
夫観(一九五七)大衆、社会心理学講座第七巻、みすず書房。 rsity of Illinois press,福岡仕男駅(一九六九)コミュニケーション海究と「マス」の駆4、Kyowa Ad-Review,第国十六号、四十二ー四十六頁。
藤竹暁(一九七三)大衆社会とマス・コミュニケーション、「情報と生活」(内川芳美他編、講座現代の社会とコミュニケーション五、東京大学出版会。
藤竹暁(一九八五)ますます本格化する大衆の時代、広告月 報、十月号、十ー十三百。
日高六郎(一九五七c)機械時代における人間の問題、現代思想 VI、岩波書店。
池内ー(一九五九)大衆現象の心理学、現代社会心理学四、 中山晝店。
小山陽一(一九五七)大衆の概念規定について、社会学研究、十四号。
Lang, K., and Lang, G., (1961) Collective Dynamics. New York : Crowell.
西部適・富岡多恵子(一九八四)対談・大衆論、草思社。
新明正道(一九五六)大衆と公衆、社会学研究、十二号。
高橋徹(一九五七)大来とは何か、現代思想I、岩波書店。 田崎 篤郎(一九七七)マス・オーディエンス、池内一編、講 座社会心理学三、一五三ー一七八真。 Worth, L. Consensus and Mass Communication. in W. Schramm (ed.)(1949) Mass Communication. 学習院大学 社会学研究室訳(一九五四)マス・コミュニケーション(初 101 版)、三二三ー三五三頁、東京創元社。