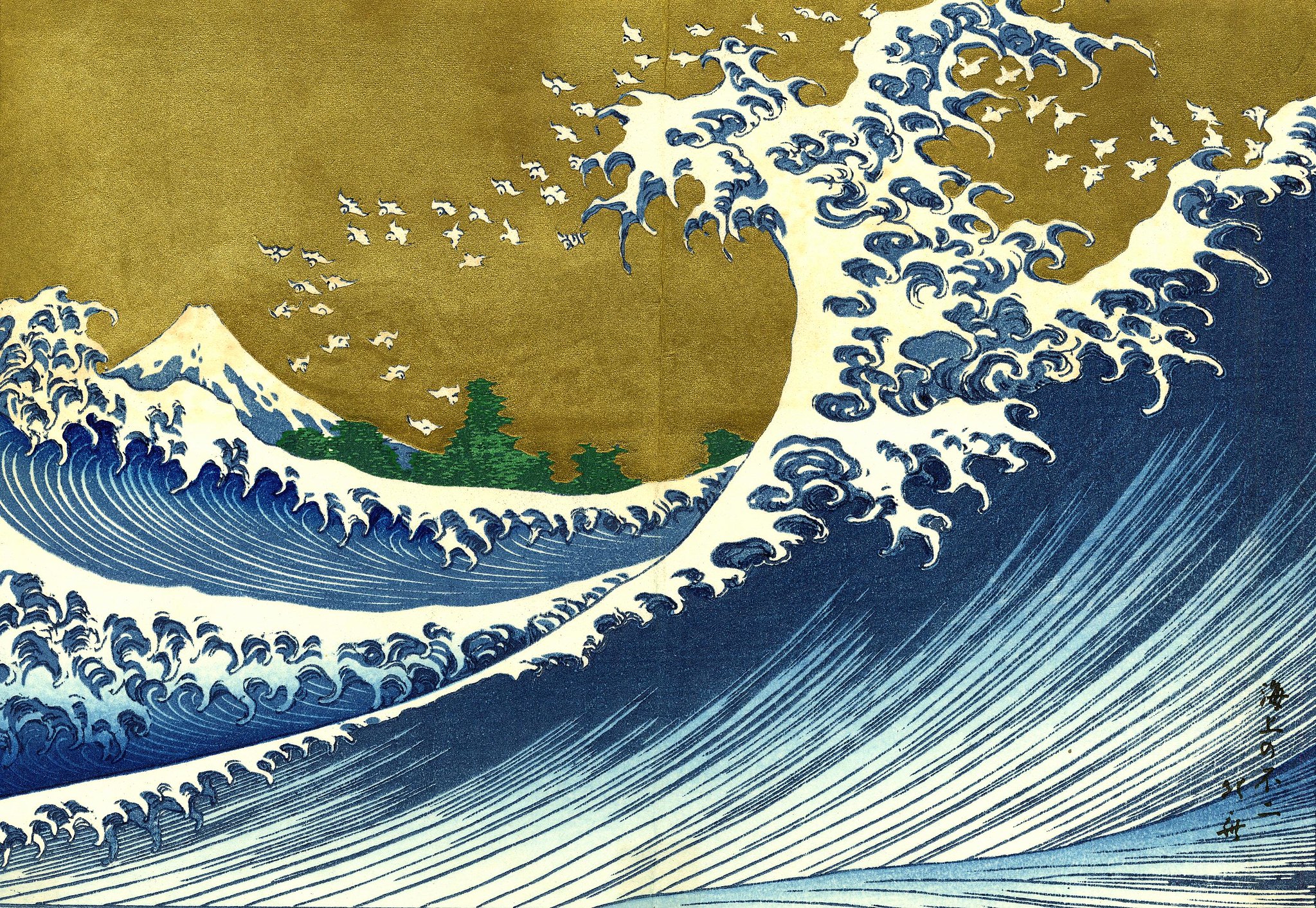![]()
迷走人生のスタート:序奏
高校生の頃、梅棹忠夫の『知的生産の技術』を読んで、大の梅棹ファンになり、自分でも真似して「発見の手帳」をせっせとつけたりもした。その流れで、京大人文研の桑原武夫にも心酔した。いま住んでいる松山は俳句の盛んなところだが、桑原の「第二芸術」という指摘に共感して、俳句の17字に芸術性など込められるわけはない、などとつい思ってしまう。梅棹がヤクザの親分みたいな人かどうかは知らないし、文化人類学者としてどれほどの業績を残したかしらないが、「情報研究の歴史」を語る上では欠かせない人物だ。1960年代前半に「情報産業論」を提唱し、その後の情報社会論の先駆けとなったからだ。
とはいえ、当時は京大に行きたいなどは露とも思わず、マルクスの資本論にあこがれて、東大経済学部に進むという(今思えば)トンチンカンな方向に進んだ私だった。しかも東大紛争を経てからは、主流の経済学ではなく、父(明治大学教授)の専門である「経営学」のゼミに入るなど、まさに支離滅裂の学生時代がスタートした。挙げ句の果て、大学院では経営学でも経済学でもなく、「社会心理学」を専攻することになった。そこで出会ったのが、「社会学」という、高尚だが、どことなく怪しげな学問である。
大学院生の頃
私が進んだのは、東大大学院社会学研究科「社会学Bコース」(新聞学)。「新聞学」がなぜ「社会学」という名のつくコースに含まれていたのか、いまから考えると不思議な話だが、それが私に「社会学」への興味をかき立て、かつ錚々たる社会学の教授や学徒たちと知己を得るきっかけとなったのだから、ありがたい話だった。私はといえば、学部では経済学や経営学を学んだだけで、社会学や社会心理学の基本も知らず、ただ書物だけの独学でしか学んだことのない、チャランポランな学徒だった。それでも、社会学に対する好奇心から、Aコース(本流の社会学)にたまたま非常勤講師で着任していた千葉大学教授の塩原勉先生の担当する社会学理論のゼミに参加した。このゼミには、(私を除いては)その後社会学理論のトップランナーとして、数多くの優れた業績をあげることになる最高の頭脳エリート4名が集結していた。年齢順にあげると、船橋晴俊、梶田孝道、今田高俊の3名である。私はもちろん彼らとは専門も違っており、ゼミの自己紹介でも、「災害情報論」「集合行動論」をしています、とかなんとか言ってごまかしていたような気がする。それは嘘ではないし、塩原先生始めとする4人とつながりがあるといえば「社会運動論」が集合行動論と関連をもっているということくらいだったので、ゼミの中ではごく目立たない存在だったろうと思う。
この1年間のゼミの中で、とくに忘れられないエピソードがある。それは、塩原先生がちょうどライフワークとなる『組織と運動の理論』(新曜社)の執筆を完成した頃で、本のタイトルを何にするか迷っておられ、私たち4人に、タイトルの候補案を示して、どれがいいだろうかと相談されたことである。私たちメンバーが一致して推したのは、メインタイトルが「組織と運動の理論」、サブタイトルが「矛盾媒介過程の社会学」というものだった。塩原先生もこれをタイトルに決めたと記憶する。それが、いまから思えば塩原さんのライフワークの大著になったわけで、感慨深いものがある。今から思うと、メインタイトルとサブタイトルをひっくり返したほうがよかったのかもしれないが、当時はサブタイトルをメインにもってきても一般の読者にはピンと来なかっただろうから、これで正解だったのかもしれない。
私は年のせいでもなく、昔から「エピソード記憶」が弱く、あのとき誰が何を言ったか、自分が何を話したか、といったことを忘れてしまっていることがあまりに多いのだが、塩原ゼミではっきり覚えていて、鮮烈な印象を受けた言葉(新しい理論パラダイム)がある。それは、「対抗的相補性」という概念だ。船橋さんと梶田さんが理論研究と実践活動の中から共同作業を通じて生み出したものらしく、ゼミでの発表に塩原さんも絶賛していたように記憶する。そのせいかどうか、塩原先生は、その後『転換する日本社会:対抗的相補性の視角から』という本を上梓されている。まだ読んでいないので分からないが、お二人の発表に触発、影響されたのかもしれない。
「対抗的相補性」の概念は、塩原先生の造語「矛盾媒介過程」と重なるところが多いように感じる。どちらも「弁証法」に起源を発する概念ではないかと思う。社会運動や社会変動を論じる上ではきわめて有効な概念だろう。彼らから教えられたのは、どんな社会学者も、机上の空論として一般社会を研究することはできず、必ず自分自身コアとなる「フィールド」を持たなければならないということである。船橋さんなら環境汚染問題、梶田さんならエスニシティ、塩原先生なら紀伊半島の新宗教コミュニティ、などなど。そして、「矛盾媒介過程」や「対抗的相補性」などの理論パラダイムは、フィールド研究における問題事象を解明するためのよき道しるべとなることだろう。私には「災害情報」とか「パニック」などの研究対象はあったが、その本質を解明するための理論パラダイムはなかった。理論らしいものといえば、せいぜい、UCLA教授のR.H.Turnerが提唱した「創発的規範(規範創出)」説くらいだった。
「対抗的相補性」生みの親の一人である船橋さんについては、当時だれかからか忘れたが、船橋さんと伴侶の恵子さんの関係は「互いに相手を高め合うという理想的なカップルだ」と言われたような記憶がある。それを聞いたとき、私はこの研究者夫婦を心からうらやましく思ったものだ。いま思えば、こうした関係性は、いい意味での「対抗的相補性」だったのだろう。私と伴侶の関係も「対抗的相補性」といえるのだが、それが「いい意味で」なのかは、言わないでおく。
東大新聞研究所に拾われた私
話は学部時代に遡るが、いまだ自分の進路さえ定まらない優柔不断な私を拾ってくれたのは、まったく畑違いの東大新聞研究所だった。経済学部の3年になったとき、父親の影響と勧めもあって、経営学の宮下藤太郎先生のゼミに入った私だったが、経営学という学問には興味をもつことができなかった。ゼミの同級生がエリートとして大企業や官公庁に就職を決める中、私だけは大学院に進学する道を志したのだった。これも大学教授であった父の影響もあるかもしれないが、それ以上に自分にはサラリーマンとしての会社員人生は似合っていないなあ、という気持ちが強かったのだ。
とはいえ、経営学という学問もまた自分には似合っていないという思いが強く、経済学部の図書館にこもって、人文、社会科学のいろんな本を渉猟する日々が続いた。そんなある日、ふと手にした一冊の本が私の人生を大きく変えることになったのである。それは、エリフ・カッツの『パーソナル・インフルエンス』という翻訳書であった。いまとなると、この本のどこが私をそれほど引きつけたのかは思い出せないのだが、ともかくも、この本を通じて、私には「社会心理学」という学問がバラ色のように光り輝く存在だと感じたことは確かだ。翻訳者は当時、東大新聞研究所の教授だった竹内郁郎先生で、カッツの本の巻末に長い解説を書いておられたので、ぜひ竹内先生のいらっしゃる東大新聞研究所に入り、指導を受けたいと強く思った。これが私の「迷走する研究遍歴」第1楽章の始まりである。
幸い新聞研究所には大学院のコースがあり、その試験日にも間に合ったので、私は社会心理学の勉強もそこそこに、新聞研究所での入試に臨んだであった。語学は英語とドイツ語を選択し、英語の点数は散々だったが、ドイツ語は満点近くをとり、1次試験は無事にパス。専門分野の筆記試験では、「経済学」「法律学」「社会心理学」の選択ができたのだが、私はホームグラウンドのはずの「経済学」ではなく、「社会心理学」をあえて選択し、散々の出来だった。いまから思えば、ごく常識的な知識を問う設問だったのに、当時まだ無知無学の私は、ちんぷんかんで何も答えることができなかった。
続く面接は、もっと散々なできだった。研究所の会議室に通されると、目の前にはそうそうたる教授陣が並んでいる。開口一番、高木教典教授が、「君は経済学部なのに何故経済学ではなく、社会心理学を選んだのかね?と温厚ながら厳しい目つきで問いかけた。わたしがどう答えたかは覚えていない。が、幸いなことに池内一教授が優しい目つきでカバーしてくださった。嗚呼、池内一先生こそは、『レ・ミゼラブル』のミリエル司教のような慈悲深いお方だったのだ。
口述試験、筆記試験の出来は散々だった。筆記試験では、「内容分析」など、新聞学の社会心理学的において基礎的なテーマについて記述するものだったが、新聞学についてはほとんど無知にも等しい私は、とても合格点には達したとは思えない、不十分な回答で終わってしまった。それでも、不思議なことに合格してしまった。いま思えば、これは『レ・ミゼラブル』に喩えれば、まったくの無知蒙昧という原罪を負ったジャン・バルジャンならぬ私が、新聞研究所という司教館に助けを求めて迷い込み、そこの主人(所長)たる池内一先生(ミリエル司教)の深い慈悲のおかげで、この暖かい館に迎えられ、一夜の休息場所を与えられ救われたということだろう。
ヴィクトル・ユーゴーは、ミリエル司教の半生について、詳しく記述しているが、池内先生については、次章で研究者としての活動と私の思い出、私が池内先生から受けた影響、その過去と現在について、やや詳しく論じたいと思う。
※なお、本稿において登場する人物は、すべて実名であるが、私が直接指導を受けた人物には、「先生」の敬称をつけ、それ以外の方については、文献著者の場合は学会の慣例にしたがって「敬称略」、それ以外は「さん」づけで言及することをお許しいただきたい。