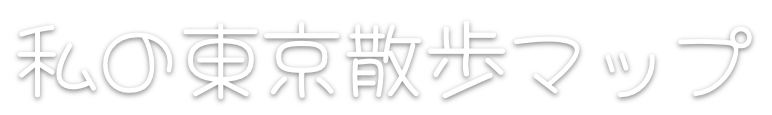5,801 total views, 23 views today
散歩記録
日時:2025年5月23日(金)
天候:曇り
場所:小石川植物園(東京大学大学院理学系研究科附属植物園)
距離:6.51km
歩数: 5,198歩
カロリー:407kcal
所要時間:2時間29分
私の散歩マップ
一昨日は、目黒区の国立自然教育園を散歩したのですが、今日は文京区にあるもう一つの植物園「小石川植物園」を散歩しました。出発地点は、都営地下鉄の「千石」駅です。不忍通りの坂を南西に下り、千石3丁目の交差点を左折して10分ほど歩くと、植物園の入り口に着きます。小石川植物園の正門は南東の角にあります。正門から一番近い駅は、東京メトロ丸の内線茗荷谷駅です。入園料は大人500円です。高齢者割引などはありません。年間パスポートは2,500円と、六義園などに比べて高いので、あまりおすすめとは言えません。
小石川植物園について
この植物園の正式名称は、「東京大学大学院理学系研究科附属植物園」です。植物学の研究・教育を目的とする東京大学の附属施設です。この植物園は日本でもっとも古い植物園であるだけでなく、世界でも有数の歴史を持つ植物園の一つです。
小石川植物園の歴史
小石川植物園の敷地は承応元(1652)年に館林藩下屋敷が設けられたところで、白山御殿と呼ばれ、幼い藩主松平徳松の居邸でした。徳松が5代将軍綱吉となった後、貞享元(1684)年に、現在の南麻布にあった幕府の南薬園が廃止され、白山御殿の敷地の一部が新たに薬園とされて「小石川御薬園」と呼ばれるようになりました。8代将軍吉宗の享保6(1721)年に御薬園が御殿地全体に拡張され、面積約4万5千坪のほぼ現在の植物園の形となりました。明治10年、東京大学が設立された直後に附属植物園となり一般にも公開されてきました。
小石川植物園の概要
小石川植物園の面積は161,588m²(48,880坪)で、台地、傾斜地、低地、泉水地などの地形を利用して様々な植物が配置されています。この植物園は日本の近代植物学発祥の地でもあり、現在も自然誌を中心とした植物学の研究・教育の場となっており、特に東アジアの植物研究の世界的センターとして機能しています。植物園本館には植物標本約80万点(植物標本は、東京大学総合研究博物館と一体に管理されており、全体で約190万点収蔵されています)、植物学関連図書約2万冊があり、国内外の多くの植物研究者に活用されています。園内には長い歴史を物語る数多くの由緒ある植物や遺構が今も残されており、国の史跡および名勝に指定されています。(以上、「小石川植物園」ホームページより引用)
フォト・アルバム
国立自然教育園のような植物園を予想していたのですが、実際に歩いてみると、広大な温室、大量の植物標本に加えて、広大な森林、日本庭園などがあり、世界中の植物を鑑賞して廻ることができます。多様な種類の大樹が鬱蒼と茂る森林の小径を歩いていると、まるで隠れた秘境を彷徨っているかのような錯覚に陥り、都心にいることを忘れてしまいます。私が歩いた順序で撮影した園内の写真と文をお楽しみください。

小石川植物園の案内図(園内で撮影)
植物園の入り口付近

正門から北に続くプロムナード
正門を入り、まっすぐ北に続くプロムナードの緩やかな坂を歩いて行きました。向こうから、外国人の親子が歩いてきました。目黒区の自然教育園と同じように、海外からの観光客も多いようです。わが国が誇る世界有数の植物園であることがわかります。

正門横から日本庭園に至る道
ニュートンのリンゴの木
物理学者のアイザック・ニュートンが、木から落ちるリンゴを見て「万有引力の法則」を発見したというエピソードは有名ですが、小石川植物園にあるこのリンゴの木は、1964年に英国物理学研究所長のサザーランド卿から日本学士院長の柴田雄次博士に贈られた枝を接木したものだそうです。しかし、当初、防疫検査により、この苗木はすでに高接病ウイルスに汚染されていることが発覚し、一時は焼却処分が検討されましたが、学術上貴重なものであること等から、例外的に東京大学理学部附属小石川植物園に隔離され、ウイルス除去の研究対象となりました。その結果、16年後の1980年、ようやくこの木からウイルスに汚染されていない接ぎ穂の切り出しに成功し、翌年の1981年から一般公開されたという経緯があります。これ以降、ニュートンのりんごは国内各地に接木で移植され、今では日本各地でみることができます。
ニュートンがリンゴの落ちるのを見て万有引力を発見したという逸話の出所は、ウィリアム・ステュークリの伝記のようです。Wikipediaから、その部分を引用しておきます。
ニュートンの友人であり、ニュートンの初期の伝記を残したウィリアム・ステュークリは、1726年4月15日にニュートンから直接に聞いた話を回顧録として記録している。ステュークリが1752年に書いた伝記では、1726年4月15日のニュートンとの会話とされる以下のくだりがある。
「 ディナーの後で、暖かい日だったので、庭に出て数本のリンゴの木の木陰でお茶を飲んだ。ニュートンと私だけだった。色々の話の途中で、彼は、「昔、引力についての考えが浮かんできた時と全く同じ状況だ。」と言った。
彼は「なぜリンゴはいつも地面に向かって垂直に落ちるのか?」と自問した。腰を降ろして考えにふけっていたときに、たまたまリンゴが落ちたときだった。「なぜリンゴは横に行ったり上に上がっていかず、いつも地球の中心へ向かうのか?」理由は疑いもなく、地球がリンゴを引き寄せているからだ。物質には引き寄せる力があるに違いない。地球にある物質の引く力の総量は地球の中心にあるのであって、地球の中心以外の所にはないに違いない。
だからこのリンゴは鉛直に、地球中心に向かって落ちるのだ。物質が物質を引き寄せるのであれば、その量は物質の量に比例するに違いない。それゆえ、地球がリンゴを引き寄せるように、リンゴもまた地球を引き寄せるのであると。」
—ウィリアム・ステュークリ(William Stukeley『Memoirs of Sir Isaac Newton's life』Royal Society "Turning the Pages" (オンライン展示)、15頁より)

木から落ちるリンゴを見て万有引力の法則を発見したニュートン (ChatGPT画)

ニュートンのリンゴの木

ニュートンのリンゴ
メンデルのブドウ
ニュートンのリンゴの木に隣裏には、「メンデルのブドウの木」があります。これは、遺伝学の基礎を築いたグレゴール・メンデルが実験に用いた由緒あるブドウの分株育てたブドウ棚だそうです。

メンデルのブドウ
公開温室
そのまま歩いていくと、大きな温室がありました。ここには、珍しい世界の熱帯植物などが栽培され、公開されています。その中から、美しい花をつけた植物を写真でご披露したいと思います。

ヒゴロモコンロンカ(熱帯アフリカ)

ゲンペイクサギ(熱帯アフリカ)


ヒメタニワタリ(小笠原諸島)

エピデンドラム・イバゲンセ

コチョウラン(台湾・フィリピン)

ツルラン

ニムファエア・カエルレア

Carex comosa

ジュンサイ
庭園の花

アメリカシャクナゲ

アメリカシャクナゲ

ムラサキカタバミ

バイカウツギ

バイカウツギ

ウツギ

ミヤマキリシマ

スイカズラ(日本、中国)

ツキヌキニンドウ(北アメリカ)
樹木

クスノキ

鬱蒼たる森の小径


忽然と現れた池

池のほとりを散歩する老夫婦

黄菖蒲とツツジ

池に垂れ下がるツツジ

ウツギ

ウツギ
日本庭園

日本庭園

日本庭園

アメリカキササゲと旧東京医学校本館


アメリカキササゲ

アメリカキササゲ

メタセコイア